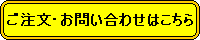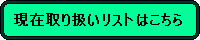過去に売り切れたリクガメです。再入荷が可能な場合も御座います、一度お問い合わせ下さい。
| Top | Blog | Turtles | Tortoises | Snakes | Lizards | Geckos | Others | Books | Foods | Goods | Info |
|
ソリガメ (EUCBベビー) Chersina angulata |





|
|
||||||||
| 何かにつけてハラハラすることもなく純粋に飼育を楽しむにはこのベビーに懸けるしかありません! ワイルドとは丸っきり正反対な最高のコンディションでお届けする貴重なCB、 アンギュラータことソリガメが入荷しました。 南アフリカの先端、沿岸部をなぞるように分布する一属一種の特異な姿を持つ稀少種。 リクガメと呼ばれる仲間は少数ながら世界中の様々な地域に繁栄していますが、 そのどれと比べても本種に似ているというものが一切見当たりません。 表から見ると卵型、 裏から見ると長方形という細長い体型、 開口部の狭まった甲羅にフィットする小振りな頭、 ミズガメのようにバタつき軽快にダッシュすることのできる四肢、 そして何よりも特徴的なのは成長に連れてグイグイと伸びてくる喉下の甲羅でしょう。 学名、英名、和名の全てがその長く伸びる甲羅を由来としており、 その目的はどうやらオス同士が発情期に争うための武器となるようで、 まるでカブトムシのように喧嘩をおっぱじめるのだとか。 エリア的に採集および輸出が難しいということも勿論ですが、 生物的に興味深い部分のみで構成されたと言っても過言ではない、 リクガメとして極めて魅力的なその風貌を目の当たりにしてしまうと、 ペットとして飼育することが少々はばかられるような気もしてきます。 実際に野生個体に対して我々は何度もチャレンジを繰り返してきましたが、 どうにも調子が把握し辛くもちろん全ての方が失敗している訳ではないにしろ、 明解な答えが依然出せないまま後ろめたさだけが増していくような思いです。 しかしここに来て登場したのがまさかの繁殖個体、野生でのデータでは産卵数が1、2個と非常に少ない上に、 下手をすると孵化まで1年近くを要するという信じられないほど生産効率の悪い中、 誰に感謝してよいものか、とにかく有難いことこの上ありません。 元々がシャイなため環境が変わったばかりではさすがに大人しいのですが、 小一時間そっとしておけば知らない内にケージ内を走り回り、 すかさずMazuriリクガメフードを与えてみた所、 ソリガメとは思えないアグレッシブな食事シーンを見せてくれました。 サイズよりも状態で選ぶべきだと思いますのでこの価格帯もお値打ちとしか言いようがありません、 今までの苦い思い出は全て忘れひたすらこのベビーを育て上げることに専念しましょう。 | ||||||||||
|
ソリガメ (ハイカラー・♀) Chersina angulata |





|
|
||||||||
| 春先に産卵を済ませ身軽になった反動か与えた餌を全て完食するアグレッシブモンスター! 背中はもちろんお腹や地肌に至るまで辺り一面が黄金色に発色する鮮やかなカラーリングが目を惹く、 ソリガメ・メスが入荷しました。 このカメが容易に入手できた瞬間などいくら時代を遡ったとしても存在しない、 昔から幾多の愛好家らを弄びそして互いが互いを傷付け合ってきた悲哀のリクガメ。 飼い方が分からなかったとの言い回しは決して正しい表現ではなかったのかもしれず、 最大の原因は来日した時点での初期状態にこそあったのだと考えられ、 それも現地でのストック環境や梱包、輸送方法にエラーが起きていたとも言い切れず、 そもそも健康状態の整った元気なカメがこの世に生存していなかった可能性すらあって、 最初の最初から極めて不利な状況を強いられていたものと思われます。 かつてはナミビアの辺りにも分布していたと言われていますが、 今日では南アフリカ共和国の南部でしかその姿を拝むことが叶わず、 棲息密度は低く産卵数も推定で年間5個程度と決して多くはないことから、 本当の意味での稀少な珍種としてその個体数は減少の一途を辿っています。 最大でも20センチ程度と小振りな体格に感じられますが、 古くは30センチクラスの大型個体も確認されていたと言い、 もしかすると現地のあまりにも厳しい環境により矮小化が進んでしまったのではないかと、 そんな半ば強引な憶測に納得させられてしまうのも無理はありません。 今回やって来たのは良好な状態にて輸入されて以来、 ここ日本で暫く飼い込まれていたフルアダルトのメス。 一目見ただけで視界の全てを覆い尽くす激しい発色に、 思わず体中をグルグルと隅から隅まで見渡してしまいましたが、 背甲の明色部は平均的な色合いと比べ明らかに面積が広く、 腹甲の大部分も熟れた柿のようなべったりとしたオレンジで塗りたくられ、 やはり頬や後頭部、 そして首の奥やその周りの肌にも濃厚な色味を味わうことができます。 ただし本種の選定条件として最も大切なのは、言うまでも無く中身のコンディション。 屋外で日光浴をすれば怯えることなく周辺を爆走し、 見るに見かねてMazuriリクガメフードを差し出そうものならクイックなUターンをかまし、 一心不乱に爆食するため体重は増え続ける一方です。 産卵経験も含めれば見た目も中身も過去最強と謳って差し支えない、 二度と訪れないかもしれない幸運な巡り合わせをお見逃しなく。 | ||||||||||
|
ソリガメ (ヤングサイズ・Pr) Chersina angulata |





|
|
||||||||
| 今では多少なりとも選べる個体数が流通する事がありますが、そんなソリガメは状態で選びましょう。 お客様飼い込みで状態抜群のソリガメ・ペアの入荷です。 本種のイメージと言えば、 頭が出るだけのスペースしかない甲羅の間に顔をじっとうずめ、 餌の時位しか歩かない大人しいカメだと感じている方も多いと思います。しかし立ち上がってしまえば全くの別物、 まるでミズガメの様に地表をバタつき、お腹の写真を撮ろうとしても四肢をバタつかせ頭をブンブン振り回し、元気一杯! そしてオスは何を考えているのか、 目の前に手の平を差し伸べると物凄い勢いで突進してきます。 メスは縁甲板に強烈なイエローが映える美麗個体。 餌食いも抜群で、葉野菜中心にMazuriリクガメフードなども我先にといった感じでバクバク食べています。 飼育下での繁殖例もありますから是非このペアで驚くほど飼い易いベビーを狙って下さい。 価格はASKとしましたが本気で将来的な繁殖をお考えの方にはサービス致しますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ソリガメ (アダルト・Pr) Chersina angulata |





|
|
||||||||
| 有難い事この上ない国内長期飼い込み個体! そして更に嬉しいアダルトサイズの雌雄一組、 ソリガメ・ペアが入荷しました。 南アフリカを原産とし世界的に見ても流通量がとても少ない稀少種。 分布域が狭いとか棲息個体数が少ないというわけではなく、 本種の暮らしている土地の殆どが自然保護区となっているそうで、 今も昔も変わりなく珍しいリクガメとしての地位を保ち続けています。 決して物珍しさだけで脚光を浴びているのではない、ということはその特異な姿形を見れば一目瞭然。 リクガメらしくこんもりと盛り上がった甲羅の先は極限まで細くすぼみ、 頭が飛び出る代わりに腹甲の先がぐぐっと伸びて奇妙なフォルムを作り出しています。 その目的が気になりますが聞く所によると発情期のオス同士が争いに用いるのだとか、まるでカブトムシのようです。 今回やってきたのは輸入後のトリートメントを済ませきっちり飼い込まれたずっしり重たい2匹で、 メスはオスに比べ小型で最大でも20cm前後と言いますから繁殖も可能な大きさでしょうか。 オスは盛るのが早いためこのペアで繁殖を視野に入れることも不可能ではないかもしれません。 飼育のポイントは夏は涼しく乾燥気味に、冬は暖かく湿り気味にと、 日本の気候の反対を意識することで状態良く管理できるでしょう。 輸入直後のワイルド個体では飼い方すらよく分からないと時折言われますが 幸いにも既にコンディションは整っていますので、 ソリガメ特有のクセに慣れながらまずはしっかりと飼い込み、 カメが環境に慣れ飼い主がカメに慣れた辺りからブリードも目指して大切に飼育して下さい。 | ||||||||||
|
ソリガメ (ハイポメラニスティック) Chersina angulata "var" |







|
|
||||||||
|
ビバリウムガイドNo.44にも紹介され、状態が上がってきたので再度ご紹介します。
ヨーロッパより入荷した奇跡のカメ、ソリガメのハイポメラニスティックです。
ここまでド派手なカラーリングの本種を見た事があったでしょうか。
背甲の周囲は真っ白に色抜けし、
特に腹甲はノーマル個体なら黒いはずの部分がほぼ全部ピンクになっており、
甲板はおろか顔や四肢の肌にまでピンクグレープフルーツの様な色彩がベッタリです。
気になる健康状態ですが、持ち上げると四肢をバタつかせ、地面に置いた途端に走り出すその仕草はまるでミズガメの様です。
状態はCB個体で既に大分成長し成長線もかなり出ているので問題ありません。
飼育環境は日本の四季と逆(気温も湿度も低い冬は加温・加湿、夏はその反対)を意識するとうまくいくようで、
実際にそういった管理をしていますが餌食いもよく非常に活発です。ブリーダーに直接お願いし、
その年に初めてとれた3個体のハイポの内の一番綺麗な個体をセレクトした特選個体です。興味のある方は一度お問い合わせ下さい。
寒い時期が続きますが、発送には専用発泡スチロール容器と長時間対応カイロを使いますのでご安心下さい。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (ベビー) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| しばしば”究極のリクガメ”と呼ばれますが近頃では随分身近な存在になってきました。 ワイルドセレクト個体のアルダブラゾウガメが入荷しました。 ゾウガメという名前は爬虫類のことを何も知らない人でも知っている位、 国民に浸透していますがその昔はまさかそんなカメが飼育できるのかという感じでした。 徐々に現地のCBが輸入される様になりましたが当初は欲しい人の順番待ち状態が続いていたので、 渾身の一匹を数年かけて入手したという方も少なくないと思います。 最近では国内CBも加わり選択の幅が大分広がりましたが、 それでも一生付き合う生き物ですから一番納得のいくものをお迎えしたいとお考えではないでしょうか。 今回入荷したのは、ワイルドとして輸入された数いるベビーの中から 甲羅のツルツル具合と 盛り上がり具合を重視して選ばれた個体です。 もちろん甲ズレや爪とび、尾切れなどの欠損もなくかなり綺麗だと思います。 最近では金額的にも大分手に入りやすくなってきましたが、 いざ飼うにあたって少々の価格差はあまり関係ないと思いますので その分は飼育環境をよりよくする為にもメタハラなど高価な器具類の資金に充てて下さい。 終始歩きまわってとても健康的なアルダブラです。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (国内CB・S) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
|
ダッシュ力◎!
コンディション抜群な2匹の国内CBです、お客様委託のアルダブラゾウガメが入荷しました。
ゾウガメの国内繁殖個体、初めて目にした時にはにわかに信じ難いワードでした。
現地からやってくるベビーと同じように流通し、
最近ではむしろ国内需要が国内生産で賄われ始めたような気もします。
一般家庭ではケヅメやヒョウモンなどのメジャーな種類でさえ将来的には1頭を飼うのもやっとですが、
その中でも群を抜いて大型のゾウガメが
商業ベースに乗せられるほどブリードされているという事実には単純に驚かされます。
当然ながらいくら殖えようと飼育面での敷居の高さは変わりませんが、
価格的には昔と比べて随分入手しやすくなりその分は餌や飼育設備に予算を掛けることで、
より良い暮らしを送ることができるゾウガメ自身にとってはメリットではないでしょうか。
今回はベビーから少し育った安心サイズで、2匹ともが超スピードで走るのを目撃した時には、
もしかして中にミズガメが入っているのではと勘ぐる思いでした。
両個体に第5椎甲板の甲分かれがあり、
A個体は腹甲の中央線を見れば分かるように体全体が少し歪に曲がっていて、
B個体は写真では分かり難いですが甲羅の盛り上がり方が左右で異なります。
甲羅の状態はいわゆるB品ですが、体調面ではむしろ群を抜く健康児。
別角度の写真をご希望の場合はお問い合わせ下さい。
個体A: 背甲 ・腹甲 ・第5椎甲板 個体B: 背甲 ・腹甲 ・第5椎甲板 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (S) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| 誰が何と言おうと王座を明け渡すことは無い圧倒的なブランド力を誇るジ・エレファント! 貴方の生涯を見届けてくれる最高の伴侶としてその類稀な実力を如何無く発揮する、 アルダブラゾウガメが入荷しました。 地球上に息衝く数多くの動物の中でこれほど常識を逸脱したものが他にいたでしょうか、 命は何故この世に生まれどのように生きるべきなのか、 私たちにとって一生をかけても導き出せないかもしれないその答えを、 体全体を使い己の生き様として示すことのできる一見カメの形をした神や仏のような存在、 それがこのゾウガメと呼ばれる生き物です。 寿命と言う全てのものが避けることのできない現実を見事に跳ね除け、 まるでそのようなつまらない固定概念にとらわれない暮らしぶりを実現したかのような、 少なくとも我々の視点からはそう見えてもおかしくは無いその姿こそまさに超生命体。 果たして一個人のペットとして扱われることが適切であるか否かはどれだけ考えを巡らしても無駄なことなのでしょうが、 そういったかけがえの無いものとのかけがえの無い時間を共有できる事実に対し、 如何ほどの価値観を見出すことができるかにゾウガメを飼育する意味が込められていると思います。 人生をゾウガメに捧げると言えば随分と格好良い表現に聞こえますが何もそれほど大層な話では無く、 日々の生活を可能な範囲で共有しながらお互いが満足できる一日をできるだけ多く積み重ねていく、 そんな小さな作業の繰り返しが誰も知らない間に誰も見たことが無い大きな喜びを創り出しているのです。 今回やって来たのはあまりにも華奢でふわふわ過ぎる幼年期を難なく通り越し、 安心して彼の暮らしと向き合うことのできる手の平いっぱいのギリギリサイズ。 通常流通するのは鶏の卵よりもややふっくらとしたサイズのベビーが多く、 反対に飼い込み個体となると安定感のあり過ぎる両手で抱えなければならない大きさになってしまい、 一般的なケージの規模で始められかつ安心感も得られる絶妙なお年頃の出物はなかなかありません。 第五椎甲板に筋が入っていますがその他に問題は無く健康そのものです。 最近ではゾウガメやケヅメなどにより適切なローカロリーの新しいリクガメフードも開発されているようで、 当店でも数か月以内には手配できる見込みなので詳細は追ってお伝えしますが、 ますます飼育の幅が広がる嬉しいニュースになると思います。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (セーシェル産・S) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| ハンドボール大に育った安心サイズ! この大きさでもまだまだ幼少期です、 セーシェル産のアルダブラゾウガメが入荷しました。 ゾウガメと聞けば誰もが振り向くほど我々日本人にとってはどこか馴染みのある言葉でしょう。 リクガメの仲間にあって特に大型化する2種類にのみ与えられたその称号は長生きの象徴としても名高く、 野生動物あるいは動物園の展示でしか見ることのできない生き物、というイメージが殆どかと思います。 ガラパゴスは厳重に保護されているためペットとして飼育することはできませんが、 もう一方のアルダブラは一般家庭に家族として迎えることができる唯一のゾウガメです。 ほんの数年前までは想像通り高価でしたがここ最近で国内繁殖も進み、価格は随分と落ち着いてきました。 もちろん誰でも終生飼育ができる種ではありませんので安易な購入は控えるべきですが、 予算を設備投資に多く回せるのでその分カメも幸せに暮らせると思います。 今回やってきたのは現地のワイルドベビーから国内で育てられた1匹で、 葉野菜オンリーでじっくり時間をかけて育成されたというその甲羅は、 ほぼ理想的なフォルムを描いていると言えるでしょう。 しばしば見かけられる腰の落ち込みも無く、 栄養面だけではなく運動量もしっかりと確保されていたことが伝わってきます。 まだ全体的に少し柔らかい甲羅をしていますがベビーほどは成長過程でのボコ付きの影響を受け難く、 良いスタートダッシュを切れています。 勿論甲ズレはありません、日に日に暖かくなりリクガメ飼育スタートにはうってつけの季節です。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (モーリシャス産・WC) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| 中型のワイルド個体をお探しの方、必見です。 見事なスタートダッシュを切った4年飼い込みの安心サイズ、お客様委託のアルダブラゾウガメが入荷しました。 唯一飼育が許されたゾウガメも国産CBや産地付きワイルドと今では少なからず選ぶことができる時代になりました。 しかしながら基本的に流通するのは手の平ベビーサイズであり、幼体時の甲が柔らかい期間が長い本種は いかに甲羅のフォルムを野生の親個体をお手本に仕上げるかが最重要課題となっています。 一言で言えば最初が肝心、 ということになるのですがこの個体の4年間かけて少しずつ刻まれた成長線は全ての箇所がほぼ均等な幅で伸びており、 それ故のこの甲高なシルエットができあがっているのだと実感させられます。 今回スペースなどの事情により手放されるとのことですがゾウガメ好きで現在も何頭か飼われているそうで、 最後までたっぷりと愛情が注がれていたことはあえて言わなくとも伝わってくるでしょう。 最後にこの個体は甲ズレなのですが、 というのもあるはずの項甲板がすっかり見当たりません。 まるであのゾウガメを思わせる面白い特徴だと思います。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (セーシェル産・モーリシャス産) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
|
ピカピカのハイドームで何の問題もなく綺麗に育った黒い王蟲!
ある程度の大きさからの導入を目指すなら温暖になり始めた今が絶好のチャンス、
お客様委託のアルダブラゾウガメが入荷しました。
このゾウガメと呼ばれる生き物がしばしば究極のリクガメと称されるのは何故でしょうか。
単純にリクガメ科の中で最も大きくなるからなのか、
それともゾウガメという名前の響きに価値観を見出してしまうのか、
もちろんそのどちらともが他種には真似できない格別の充足感を味わわせてくれる要因であることに違いありません。
いつかはゾウガメ、との思いを胸に抱く人も少なくないでしょう、
カメ飼育者にとって超巨大なリクガメを自己所有のスペースでのびのびと歩かせるというのは、
誰しもが一度は考えることだと思います。
そしてゾウガメを飼っているというその事実にも、一種のブランド力のようなものが発生してしまうのでしょう。
しかしこのカメが特別なのは何も大きさや名前だけの話ではありません。
ただただ図体のでかいという訳ではなく、
非常に賢い動物であることは少しでもゾウガメを扱っていれば直ぐに気付かされてしまいます。
最も分かりやすいのは狭い環境に置かれた時、もしくは住み慣れた環境から急に場所を移動した時のふたつ。
四方がギリギリに囲まれたような場所に入った途端、
今までドタドタと走り回っていた個体でも急に動きを止めてしまうことがあり、
それは引越し先の新居に入れられた瞬間にも同じような状態に出くわすことがあります。
これにより今自分は何処にいるのかという、
自らが置かれた空間を認識する能力に極めて長けていると考えられます。
それだけに首を伸ばして餌を貰いにこちらへ駆け寄ってくる姿を見た時などは、上手に飼育できている、
飼い主に対して親近感を持っているという最高の幸福に浸ることができるのです。
今回ご紹介するのは2010年生まれのセーシェル産WCと、2008年生まれのモーリシャス産WCの二頭。
一番気になる甲羅の状態については写真を確認すれば一発ですが、
両個体ともハイドームでボコ付きは極限まで軽減され、
陥りやすいとされる第4椎甲板辺りの落ち込みについても
全くと言って良いほど問題は見られません。
外に出して暫くはおどおどしていましたが、次第に慣れたのかマイペースに歩み出したのでほっとしました。
これまで人工飼料の類は一切用いず、野草と野菜のみを与えていたそうで、
特に好きな食べ物はオクラとのこと。同じくネバネバしたモロヘイヤにも目がないというお話でした。
歩かせ放題、紫外線浴びせ放題のこの季節、今後のお付き合いを真剣に考えている方にとっては絶対に見逃せません。
小(セーシェル産): 背甲 ・腹甲 大(モーリシャス産): 背甲 ・腹甲 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (セーシェル産・M) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| 育てた方の手間と愛情が甲高のボディいっぱいに詰まった渾身の力作! 一目見ただけで気合の入り方が違うと分かる極上の逸品です、 お客様委託のアルダブラゾウガメが入荷しました。 遡ること4年前、セーシェル産のワイルドベビーとしてやって来た群れの中から 自身の好みで3匹のベビーを選び抜いたのがことの始まりです。 セレクトの基準はコンディション、左右のバランスなど挙げればいくつも出てきますが、 中でも特に拘ったのが甲羅の高さ。 自分がこれだと思う方法で順調に飼育を続けていたそうですが、 事情で頭数を減らさなければならなくなり最後に残ったのがこの個体で、 この子が最初から一番甲高だったと今でも強く記憶に残っているため直前まで放出を躊躇ったとのことでした。 決して過保護にする訳ではなくあくまでも日本の四季に馴染ませる方向で、 基本的には自宅の庭にて屋外飼育、冬は中に取り込まざるを得ませんが多少寒くとも隙を見ては外気温を測り、 1日1時間でも多く日光浴と運動をさせることを心掛けていたと聞きこちらも熱くなってしまいました。 年中一定温度での管理ををあえて避けたことが功を奏し、 今では少々の冷えにはびくともしない丈夫な体に育っています。 屋内飼育時のライティングにはもちろんメタハラを採用、餌は基本野草で季節柄入手の難しい時は葉野菜、 加えて近所の畑から贈られるバリエーション豊富な野菜と、やはりフード類を避けた低栄養高繊維質がテーマです。 ここまでお話ししたことは今日ではゾウガメ飼育のセオリーとも言うべき内容ですが、 何よりいつもゾウガメのことで頭をいっぱいにして日々それを続けられたこと、 そしてその汗と涙の結晶を物語る甲羅の素晴らしいフォルムを見せられれば、 この4年間で何が行われ何が積み重ねられてきたのか、その答えは第三者の私たちでも容易に分かることだと思います。 最後にこれまで何が一番大変でしたかと伺った所、答えは小さな頃のまめな温浴、 これはつまり代謝を高い状態でキープすることと甲羅表面の湿度を保つことが目的ですが、 それ以上にゾウガメと毎日触れ合いたいといういたってシンプルな願望が自然とそうさせたのかもしれません。 今回は売り切りのためこの高品質にそぐわない年末大特価、迷ったらまずは一度お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (モーリシャス産・L) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| 外観の美しさだけに留まらず知恵と勇気を兼ね備えた高い資質を持つ一級品! この優れたトータルバランスが一生の連れ合いとして迎えるに相応しいと強く思わせる最大の要因です、 モーリシャス産のアルダブラゾウガメが入荷しました。 私たちにとってカメと言えば海の底の竜宮城へと連れて行ってくれるウミガメであり、 また江戸時代より伝わるゼニガメであり、 いずれにしても水との深い繋がりを感じさせる生き物という印象が否応なしに根付いていますから、 リクガメの存在を知った途端に強烈な衝撃を受けることはおよそ避けられないでしょう。 陸上を主な生活圏とするというだけのことと思うかもしれませんが、 既存のイメージを大きく覆す事実が与えるショックとは予想を遥かに超えるものがあり、 知らず知らずの内にそれに対して憧れの念を抱いてしまう人も少なくありません。 その中でもダーウィンの進化論で有名なガラパゴスゾウガメは、 動物好きを自負する者にとって必ず知っておかなければならない重要なキャラクターですが、 あまりの神々しさにとても自分の手元においてどうこうしよう気にはとてもならないと思います。 そこで同じ名前を持ちながら一般に飼育することの許された唯一の存在がこのアルダブラ、 前者同様とても大型に成長するそのポテンシャルは言わずもがな、 何処も彼処も漆黒に染められた貫禄のある配色や、 超重量級の巨体をへっちゃらで支えてしまう図太い体躯など、 一切妥協のない全体のつくりはガラパゴスに勝るとも劣らぬ魅力を備えています。 並の思考では絶対に我が家へおもてなししようなどとは考えない訳ですが、 そういったつまらない常識を打ち破り人々の感覚を麻痺させてしまうのは、 このカメが元来持つ底知れない醍醐味が自ずと導き出した答えなのです。 今回やって来たのは堂々の30センチオーバーという、 いくら大型種とは言ってもそうそうお目にかかれない貴重な一匹。 バランスよく盛り上がった甲羅は各甲板の成長線が均一に刻まれることで成り立ち、 拘る方にとっては絶対に譲れない腰元の落ち込みも全く感じられず、 誕生して以来五年以上にも渡る歳月を適切な環境で過ごしていたことを見事に体現しています。 高度な知能を持つために飼育場所が変わっただけで塞ぎ込んでしまうケースも多々ありますが、 この個体は移動初日から辺りを爆走し、 何気なく放り込んだ葉野菜も一瞬の内に消し去るほどのパワフルさを見せ付けてくれました。 昼間には店先で小一時間散歩させているのですが、 気温が下がり屋内へ収容するとガラス越しに外の風景を眺め続けているので、 その未練がましい素振りに万全な暮らしを提供し切れないこちらの申し訳なさと、 夏場への期待に胸が膨らむときめきとで感情が複雑に入り混じっています。 最後にあえて申し上げたいのは、 綺麗に生え揃った爪と鱗の磨耗し始めた足の裏に全てを感じて頂きたいということ、 そしてそれ以上のことについてはお問い合わせ頂いた際に詳しくお話し致しましょう。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (L) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| この数年で再び入手困難な状況が続く中で久しぶりにお目見えした立派な体格を持つ大型飼い込み個体! 長く暮らした生活環境が変わろうともお構いなく歩き回る屈強なメンタルに救われる安心のラージサイズ、 アルダブラゾウガメが入荷しました。 リクガメと名乗る生き物たちのことをさほど知らない一般社会の人々でさえ、 ゾウガメと名付けられたとてつもなく大きなリクガメがこの地球上で暮らしていることは知っていて、 それはいわゆる絶滅危惧種だとかそんな括りに纏められ即ち稀少な生物なのであるということや、 あまりにも大き過ぎるが故に人を乗せて運ぶことのできる浦島太郎におけるウミガメの陸上版のようであるということ、 そしてそれは普通の人間が通常ペットとして気軽に迎え入れられるような選択肢ではないことや、 この日本中の何処かにはそんな羨ましいものを平然と飼育している人がいそうな気がすることなど、 つまりゾウガメという四文字の単語を前におおよそこれぐらいの話は見当が付くのではないかと思われます。 その程度はさて置き少なからず生き物好きを自負する皆さんにとってもはや一般常識のような存在であるゾウガメは、 ただ単にリクガメの大型種であるという枠組みに囚われない崇高なものとしてキャラクタナイズされ、 神の領域に足を踏み入れたような感動と興奮を生み出し所有欲が猛烈に刺激されるおかしな性質を有しています。 誰もが気付かされる事実として寿命という概念と真剣に向き合うのであれば、 これほど馬鹿げた思考も他に見当たらないような気がしてなりませんが、 カメなる生物に備わるポテンシャルが最大限に引き出されれば全種において桁違いの長寿記録が達成され得るため、 一周回ってどのカメを選ぼうとも長生きすることに変わりはないと割り切ることで、 このような人間の業の極みとも言える行いを僅かな時間でも正当化できたような気にさえなるのです。 今回やって来たのはいよいよ30センチオーバーという大台を軽々飛び越え、 今や40センチに迫らんとする本格的なゾウガメらしいサイズに仕上げられた自慢の長期飼い込み個体。 元を辿ればワイルドのベビーとして輸入されたものを当店にて販売したのち、 およそ十年ほどの歳月を経てこの度私の前に再び姿を現すことと相成りました。 どちらかと言えば繊細で神経質なタイプが多いゾウガメにおいては珍しく、 育ての親から離れてもくよくよせず明朗快活に振る舞う姿に、 傍で見ているこちらもすっかり安心させられる次第です。 最近では数年前に比べ流通量が明らかに減少しており、 もちろんむやみやたらに見かけられる種類でないことは承知の上ですが、 いざ探そうとしてもなかなか巡り合えないのが現実ですからこの好機をお見逃しなく。 | ||||||||||
|
アルダブラゾウガメ (L) Dipsochelys dussumieri |





|
|
||||||||
| 長い四肢を巧みに使い辺り一面を豪快に歩き回るゾウガメらしからぬ強靭なメンタルの持ち主! 環境が変化した直後とは思えないずば抜けた機動力と餌食いに店内が騒然とするほどの、 アルダブラゾウガメが入荷しました。 リクガメと呼ばれる限定的なカテゴリの中だけに留まらず、 もはやペットとして飼育できるカメの最終兵器と言っても過言ではない、 老若男女を問わずカメ愛好家の誰しもが一度は憧れたであろう究極の生命体、それがゾウガメです。 例えばコモドドラゴンがオオトカゲの中でも特別にドラゴンの名を冠されているように、 このゾウガメもまた大半のリクガメとは一味も二味も違うのだということを、 その呼び名によって如実に表されている事実が一番身に染みるエピソードでしょう。 ある見方をすれば気安く触れてはならない神聖な存在として、 またある見方をすれば他の種類では成し得ない最高のペットトータスと成り得る存在として、 そのような全てのリクガメを差し置いてプレミアム極まりないキャラクター性を有しているのは、 何度も申し上げているようにこのゾウガメ以外には考えられません。 単にそのネーミングが持つブランド力が優れているだけではなく、 視力や知能の高さは傍に置き暮らしを共にすることで初めて分かる本当の付加価値であり、 共同生活者として周囲の人間の存在を認めつつも自らのライフスタイルの確立と充実に努めようとする、 類稀なる順応性と生命力には飼い主たったひとりでは堪能し切れないほどの深い味わいが込められているのです。 今回やって来たのは天高く盛り上がったハイドームな甲羅が存在感を倍増しにしてくれる、 まだまだ何とか両手で抱きかかえられるラージサイズの飼い込み個体。 これを本当の健康と言ったら良いのでしょうか、 通常生活空間が変化したばかりの頃は例えば数日、 例えば数週間が過ぎるまで塞ぎ込んでしまいがちな本種において、 入店した翌日に全身をブラシで丸洗いされ野外に放り出された直後から、 縦横無尽に走るだけに飽き足らず冗談で与えた餌を全て平らげてしまう、 ゾウガメらしからぬ屈強なメンタルには心底驚かされました。 多少のボコ付きこそあれど成長線は綺麗に伸び体高もしっかりと稼げていて、 たまたま天候に恵まれ路上での撮影となりましたが、 よほど嬉しかったのか少し笑ったような穏やかな表情を見せてくれました。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイカラー・チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| まとまって輸入される群れの中に時折出現する将来有望と言わざるを得ない絶品のセレクト! 一切の言葉を必要としないほど見た目の訴求力に優れたタイプの異なる美個体を是非、 アカアシガメが入荷しました。 いつかの奇抜なリクガメも今日ではペットトータスの代表種に仲間入りし、 湿潤系が難しそうという謎の先入観を見事に打ち砕いてくれた、 時代を象徴する救世主のような存在のひとり。 赤色というこれまでありそうで無かったチョイスは本種の専売特許として広く認知され、 これは水棲ガメの仲間たちを含めても相当にエキセントリックな配色であるに違いなく、 他では代わりの利かない唯一無二の美しさが人目を惹いて止みません。 黒い瞳のウルウルとした森林棲の種類は総じて愛しさと妖しさを兼ね備え、 いわゆる初心者向けとされる御三家などと比べて陰気で根暗なイメージが付き纏うのも否めませんが、 実際に飼育してみるとその発想が間違いであったことには即座に気付かされ、 むしろアグレッシブさの塊のような性質の持ち主であることは直ぐに分かります。 しばしば気に掛けられる湿度についても常識的な範囲で管理していれば問題無く、 強いて言うのなら床材が湿り気を帯びていた方が体表の艶を維持して育てられますが、 却って意識し過ぎたあまり甲羅や鱗の表面を傷めてしまう可能性もあるため、 結局は他の種類と大差無い環境を提供することが求められるほど。 ここまでの話を纏めると、見たことの無いカラーリングで非常に活発な性格のリクガメが、 さほど変わった飼い方をせずとも飼えてしまうということになり、 この考えが広まることでより一層アカアシガメの需要が高まるのではと考えています。 今回やって来たのは赤味の強さが極まることで人気の高いチェリーヘッドから、 ピックアップにかけた時間は数秒というレベルで激烈に発色していた二匹のベビー。 小さな方は全体に赤黒い印象で、 特に背甲の明色斑までもが濃厚な赤に染め上げられている点は非常にポイント高し。 大きな方は天然ハイポとも言うべき色味の薄さが体中に表れ、 本来黒くあるべき部分でさえもがぼんやりと色抜けを起こし、 頭部も全体的にびっしりと赤く覆われています。 既にMazuriリクガメフードにも餌付けてあり準備万端と言ったご様子、 体表を白化させずにキープするコツもお教えします。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・ベビー) Geochelone carbonaria |




|
|
||||||||
| ハデハデな配色ですがよく見てみるとキュートな顔立ちです。チェリーヘッドのアカアシリクガメ、ベビーサイズの入荷です。 以前はその巨大なサイズから「綺麗だけど最終サイズがちょっと…」と敬遠される事もありましたが、今回入荷のチェリーヘッドは アカアシの中でも小さな個体群らしく、30cm手前で成長が止まるみたいです。 頭部と四肢の赤い斑紋の発色は本種ならでは。多湿な森の茂みに生息しているので、紫外線要求量は他の砂漠系などのリクガメよりは低めですが、 リクガメはリクガメなのでちゃんと紫外線浴びせてあげて下さい。冬季の過乾燥にさえ気をつければ丈夫で飼いやすく、餌も葉野菜から果実まで 幅広く食べるのでバリエーションも楽しめます。写真を撮ろうとケージから出すと、撮影場からトコトコ歩いて何処かに行ってしまう元気さです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイレッド・ベビー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| お腹も背中も当然頭も体中の至る所から赤色の噴出が止まらない極美ハイパーチェリーヘッド! これを逸材と呼ばずしてなんと言えばよいのやら、 誰がどう見ても文句無しに将来有望のアカアシガメが入荷しました。 ブームと言われるほど急加速的なものでは無いにしろ、 昔に比べて明らかに飼育人口が増加し続けていると思われるリクガメの仲間たち。 今日ではカメを飼うと言えばミズガメよりもリクガメの方が連想されるほどで、 結局は多くの人にとって水棲ガメであれば何とか育てられたそんな状況から、 ヘビやトカゲなどその他の爬虫類も普通に飼育されるようになった今日では、 かつて困難とされていたリクガメについても扱い方が確立されつつあり、 ペットとしての選択肢に名乗りを上げるようになったのでしょう。 無論これまで何十年もの間愛され続けてきた歴史あるミズガメのことを否定するつもりは毛頭ありませんが、 やはりコミュニケーションと言う観点に着目した場合には、 水中で暮らすガラスの向こうの存在よりも同じ生活圏で暮らす陸上のカメ、 即ちリクガメの方が親近感が沸き愛情を注ぎ易いのかも知れません。 最近では大型のケージやそれに必要な器材も豊富に取り揃えられるようになり、 暮らしの大部分が屋内で完結したとしてもストレス無く付き合えるようになった、 そんな時代の流れも大きく寄与しているものと思います。 今回やって来たのは茶色や黄色が色彩の主体であった世界に新たな風を巻き起こした、 赤いリクガメと言うインパクトが一際注目を集めているアカアシガメ。 産地により様々なバリエーションを持つことはご存知の通りですが、 いくら色味の良いチェリーヘッドだとしても幼年期にこの発色を目の当たりにさせられるとは誰が想像したでしょうか。 頭部や四肢など鱗部分のカラーリングがえげつないのはもちろんのこと、 腹甲の黒くない部分には全て濃厚な赤色が染み込んでいますし、 背甲に至っては初生甲板の大きな斑紋の周りにもうっすらと赤味が差していて、 もはや全身が真っ赤なカメと言っても過言では無い状態に達しているのです。 成長に連れて色味の増すタイプの本種がこれ以上綺麗にならないはずが無い、 凄まじきクオリティを放つスーパーセレクトな一匹をお見逃し無く。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・S) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 背面の各甲板を彩る蛍光イエローが明瞭に描かれた毒々しくも美しい新感覚チェリーヘッド! 名前ばかりのイメージに惑わされず体の隅々まで拘りを追求していきたい、 アカアシガメが入荷しました。 ブラジリアンドワーフチェリーヘッド、 こうして眺めていると何かの呪文か必殺技かと勘違いしそうな長ったらしい名称は、 いくらかの地域個体群を抱える本種に認められたとあるタイプを指す言葉です。 ブラジルに産する小型で頭部の赤味が顕著なアカアシガメ、 ただ単に和訳しただけに過ぎませんが平常はチェリーヘッドと省略され、 遡ること十年ほど前の話になるのでしょうか、 当時はセンセーショナルで革命的なリクガメとして持て囃されていたのを記憶しています。 つまりかつてのアカアシはひょうたん型で巨大になるものばかりでしたから、 とても家庭内で一般に飼育される風には考えられておらず、 相方のキアシにしても同様に完全なマニアの持ち物としてしか認知されていませんでした。 そこへ彗星のように現れた大きくならないアカアシガメ、 それも従来のタイプとは異なり頭まできっちり赤く染まると言うのですから、 何も否定すべきところが無く大変に気持ち良く受け入れられたのです。 最近では殆どのアカアシがこのチェリーヘッドによって占められている印象ですが、 中に細かなバリエーションもあるためきちんと好みの一匹を選び抜きましょう。 今回やって来たのは頭頂部の赤さは期待通りにベッタリと、 そして背甲の明色斑が激しく黄色いゴージャスな雰囲気のこんな二匹。 赤なら赤だけを追求するのも面白いには違いないのですが、 同種の数を見ていくとカラフルなものへの憧れが強まって来るのも事実で、 一体のカメの中にブラック、レッド、イエローと三色も取り入れられていることが如何に贅沢であるか、 他種と見比べてみればその素晴らしさが実感できると思います。 何となく湿潤系のじめじめしたリクガメの各種には、 下手をすれば不衛生なイメージすら植え付けられているかもしれませんが、 実際にはそこまで過度に湿らせる必要は無くむしろ甲羅を痛めてしまう原因にもなりかねず、 正しい扱い方をすればこんなに明るく陽気で綺麗なカメもそうそう見当たりません。 濡れていても乾いていてもお構いなしに輝きを放ち、 成長線には今にも霜降り模様が浮き出てきそうな予感さえする美個体候補、 本来は黒いはずの腹甲にまで明るい色味が浸食している辺りが全てを物語っています。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (国内CBベビー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| まるでこのカメのフィギュアを写真に収めた様です。 お客様繁殖の国内CB、アカアシガメが入荷しました。 本種の名をアカアシとはよく言ったもので、甲羅からすっと伸びた四肢には綺麗な赤色の乗るリクガメですが、 ちょっとこの個体はやり過ぎでしょう。 大きな鱗のほとんどに見た事のない濃さの赤が惜しみなく発色し、 それは四肢のみならず足の裏やお尻、尾の細部まで至るほど。 頭部は赤いマスクを被った様にこれまた見事な色がついています。 上から見ても背甲の明色部分の面積はとても広く、 腹甲については暗色部はほとんど見られずここだけ見てもクオリティの違いが伝わってきます。 ブリーダーは選別された特別綺麗な個体と称していましたが、 ここまで美しいものを見せられるとパステルの原形かとも思ってしまいます。 甲羅はしっとりと湿り気を帯びた状態で成長しており、 やはりこの手のカメには湿度が必要だという事を物語ります。 一部腹面を乾かせる場所を用意して高湿度を保つのが綺麗に育てるコツでしょう。 餌は現在Mazuriリクガメフードとリザードフードをふやかして与えていますがどちらも好きなようです。 この先どのように成長していくのか非常に興味深い極美個体、貴方の手で立派に育て上げてください。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・ベビー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| その足よりも頭よりも何よりもまず背中にぼわっと描かれた強い赤味に注目して頂きたい美セレクト! いつもとは少々異なる視点で観察することにより個体本来の素質が浮かび上がります、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 ここ数年で全般に人気の高まりが感じられるリクガメの仲間たち、 かつてカメと言えば水棲ガメを飼うのが当たり前だった時代はとうに過ぎ去り、 その頃には高根の花だった数々の種類が次第に庶民的に感じられるようになったことも踏まえ、 ペットとして気軽に選ばれる機会が目に見えて増加しています。 リクガメとはそもそもカメ全体におけるひとつのグループにしか過ぎませんから、 その中に属している種数はどうしても限られてしまうのですが、 その分かり易さや取っ付き易さが次々にファン層を拡大していったようで、 犬や猫ほど手が掛からないという絶妙なポジションでも存在感を発揮しているのだとか。 つまりこれまでのマニアックな雰囲気よりも、 むしろいわゆる爬虫類とは疎遠だった人々が新たな刺激を求めて辿り着くように思われ、 そうした動きが業界全体を後押ししているような気がしてなりません。 俗に初心者向けとされるポピュラーな種類に加え、 近頃では飼育器材や餌事情などの環境整備も整ってきたことからか、 多少なりとも王道を外れたところで失敗の恐れは随分と少なくなり、 そういった部分で自らの個性を発揮しようという向きも強くなっているようなのです。 今回やって来たのはまだまだ変わったリクガメというイメージが強いながらも、 その美しさや飼い易さから年々ファンを増やしつつある当店でも一押しのアカアシガメ。 少し調べてみると様々なタイプが存在することが分かると思いますが、 特にこのチェリーヘッドと呼ばれる個体群が圧倒的に高い支持を集めており、それもそのはず、 やはり元々赤っぽいものがより赤くなると聞けばつい欲しくなってしまうのが人情でしょう。 更に拘ってしまう方なら細部の特徴にも目を配り個体を吟味する訳ですが、 この二匹については将来的な発色の仕上がりに期待すべく、 生まれもって備わるクオリティとその伸びしろに着目してみました。 どちらの個体もとにかく上から見た時の色味が鮮やかで、 ひっくり返して見てもお腹側にまでびっしりと赤が染み出していることが分かります。 一方は全身に万遍なく発色が見られる優等生、 そしてもう一方はアカアシのくせに足がちっとも赤くないという矛盾を孕んだ珍妙かつ興味深い個体です。 少し大きく見えますがハッチサイズを考えるとこれでもまだまだ子ども、 しかしながら持ち前の明るさでケージ内を元気に走り回っています。 初めての方は飼育方法なども併せてご相談頂ければ細かいコツまでお教えします、餌食い良好! | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・ベビー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 文句無しの上質グレードにてお届けする芳醇で濃厚な赤味が炸裂した将来期待の梅干しヘッド! 一体何を考えているのか野生でも目立って仕方ないであろうあまりにもやり過ぎな極彩色、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 同じカメでもリクガメと水棲ガメにおける立場の違いを考えてみると、 前者には何処か平和で親しみ易いイメージを抱きがちで、 また後者にはガラスの向こうの存在とでも言いましょうか、 少なくとも家族だとかそういう感じではなく、 むしろ適度な距離感やそこに生まれるエキゾチシズムを楽しむような感覚が当てはまりそうです。 もちろん全ての種類が総じてこの例に該当する訳ではありませんし、 同じリクガメでも砂漠や草原に暮らすタイプに比して俗に多湿系と呼ばれる森林棲のタイプには、 何となくミズガメ的な趣きがあるのだと昔から言われてきました。 言い換えればちょっと怪しげな雰囲気を醸していると言うような意味合いなのですが、 アカアシガメの昔ながらのキャラクターを一気に覆したのがここにご紹介するチェリーヘッドです。 見た目だけの話をすればややグロテスクな色合いで不気味な印象もあろうかと思います、 しかしこれが育ててみると意外にも明るい性格の持ち主であることが分かり、 そこまで大きくなり過ぎないという事前情報も手伝って年々飼育志願者が増え続けているのです。 今回はそんな人気のチェリーヘッドから、 その名に恥じぬ頭や甲羅の発色が鮮明な二匹をセレクトしました。 人の心情からすればどうせ赤いのならばより赤い方が嬉しいに決まっているでしょう、 と言うことで成長に連れてエグいほどの彩りを楽しめそうな個体は如何でしょうか。 同じさくらんぼでもこの色合いはアメリカンチェリーのように赤黒く、 頭部全体を覆う面積も広いため地色の黒い部分を殆ど浸食してしまう勢いの良さ。 それと同時に四肢の鱗や背甲板の斑紋にまで、 血が滲んだように過激なデザインが見る者を圧倒します。 元々ハッチリングの大きなカメなのでこれでもまだまだ子どもなのですが、 餌食いの活発さと歩くスピードに注目しコンディションに全く問題は見受けられず、 出している糞のサイズも自分の頭かそれ以上のボリュームがありますので、 初めてのリクガメにも安心です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ライトカラー・チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 赤味の強さのみならず全身が淡い栗色に包まれたぼんやりライトカラーの不思議ちゃん! 赤く育つであろうことはもちろん地色の部分がどのように変化するのか目が離せない、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 今やペットの世界では確実に市民権を得られるようになった、 カメはカメでも日本の自然では出会うことのできないリクガメの仲間たち。 その昔、かの著名な千石正一氏がご存命であった頃には、 家庭のペットとして飼育してはならないとまで言われたほどでしたが、 幸か不幸か世界的に野生での個体数が減少しているリクガメはかつての消費的な流通事情も随分とましになり、 その代わり主に現地で養殖された幼体が多く出回るようになったお陰で、 最大のネックであった初期状態が大幅に改善されると共に、 我が国においても飼育下での情報が蓄積されある程度の飼い方なるものが確立され始め、 これまでカメやその他の爬虫類に一切触れて来なかった方でも、 安心して飼育をスタートできるような環境が整えられています。 例えばビギナー向けの看板としてトップクラスの知名度を誇るヘルマンはヨーロッパから、 そしてその一方で育て易さと明るい性格がこの頃評判のアカアシガメは南米から、 それぞれファーミングと呼ばれる環境下で殖やされた可愛らしい幼体が、 輸入業者の努力もあって毎年コンスタントに入手できるようになりました。 安価な種類は比較的飼育が容易であるとの誤った先入観を捨て、 日本にやって来るまでの経緯をきちんと把握しておくことも大切な要因のひとつなのです。 今回ご紹介するのはせっかく地域差や個体差があるのですからお気に入りを選びたい、 一言も二言も余計に喋りたくなるちょっと変わったこんなチェリーヘッド。 頭頂部の赤い面積が広いのはご覧の通り、 甲羅の明色部についても鮮やかな朱色に染まり今後の成長が楽しみなのは言うまでもありませんが、 この個体については本来黒色になるはずのベースカラーがやんわりと淡く、 まるで赤い斑紋の色味が周りへ染み出したような錯覚に陥るほど。 腹甲のメリハリも何だか弱く全体的に色抜けを起こしているようで、 例えば成長線に表れる白い霜降り模様が出易いのではないかなど、 良からぬ期待を抱いてしまうのも無理はないと思います。 この先美しく生まれ変わるのが待ち遠しい特選個体、 店内で暫くストックした安心のコンディションでお届けします。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (コロンビアタイプ・国内CB) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| その名の通りの赤い手足にやや黄色味を帯びた頭の柔らかなカラーリングが可愛らしいコロンビアタイプ! そもそも国内で繁殖された幼体というだけでも有難いところへ細かな産地まで選べるオプション付きの、 アカアシガメが入荷しました。 リクガメにあるまじき奇抜な色彩は賛否両論とまではいかないまでも、 間違ってもこれをスタンダードなどと勘違いされては困る攻めの姿勢で今日の業界を生き抜く、 独自のスタンスを貫いた唯一無二の美麗種がこのアカアシガメ。 大まかにリクガメと言えば茶褐色にまとめられているのがセオリーですから、 こんな見た目では絶対に一癖も二癖もあるおかしなキャラクターだと決め付けられるのが関の山なのかと思いきや、 そのようなつまらない先入観を即座にぶち壊してくれる持ち前の明るさこそが、 本種に備わる外見では分かり得ることのなかった真の魅力なのかもしれません。 その出で立ちは如何にも捻くれもののような印象が強く、 おまけに湿潤系という余計な事前情報のせいで相当に扱い辛そうなイメージが付き纏う中、 実際には竹を割ったような気性という言い回しがぴたりと当てはまるさっぱりとした性格で、 ラテンの空気と江戸っ子のそれとの間にどのような共通点があるのか分かりませんが、 ペットとして付き合ってみると後腐れのない関係性にむしろこちらが救われたような気にさえなるほど。 飼い主と目が合った途端に喜んで駆け寄ってくる純情さの垣間見える立ち振る舞い、 与えた餌は皿を地面に置くか置かないかのうちに食べ始める底なしの食欲、 実は言われているほど高湿度を保つ必要がなかった良い意味での意外性など、 下手にビギナー種として認定された他のリクガメよりもずっとシンプルな暮らしぶりを展開している、 令和の新時代に改めてその潜在能力を見直されたいハイスペックトータスなのです。 今回やって来たのは国内で繁殖されたノーザンフォームに該当するタイプのベビーより、 一方に珍しいコロンビア産の種親を用いた頭の黄色さが目立つ兄弟。 業界内における本種の位置付けを決定付けたチェリーヘッドの登場以来、 頭部も四肢ももれなく赤い派手派手なものが好まれる傾向が強まる中で、 原点回帰とも言うべき足だけ赤いアカアシを望まれる方にはぴったりの出来栄えが期待される血統です。 ノーザンらしく目元は何処までも黒々としたキュートな面立ちが印象的で、 先に述べた黄色と赤色のコントラストも成長に連れてより強まることになっていますから、 大きく育ってこそそのオリジナリティが滲み出てくることでしょう。 言うまでもなく入荷して以来Mazuriリクガメフードをもりもり平らげ、 それのみでも飼育できるよう仕立てられた状態抜群の安心サイズをどうぞ。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (バルバドスフォーム・国内CB) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| チェリーヘッドに次ぐ知名度を誇るノーザンフォームより移入小型個体群とされる稀少バルバドス島産! 近年では明確なロカリティ付きで輸入される機会が殆どないだけにあまりにも嬉し過ぎる国産のベビー、 アカアシガメが入荷しました。 様々な、とはいえ元々の種類が限られているペットトータスの世界においては、 選択肢があるようで実はあまりないという現実的な苦悩が渦巻いているようですが、 そのような状況下でもかなりの奇抜なムードを纏い私たちを楽しませてくれているのが、 南アメリカ大陸の広大な地域に繁栄したアカアシガメと呼ばれる種類です。 リクガメで赤、というのははっきり言って異例中の異例であり、 言い方を間違えればある意味気持ちの悪い配色と捉えることもできますが、 この独自性を武器に数十年に渡って絶妙な存在感を発揮してきた実績を誇ります。 単に美しいともまた見方を変えれば毒々しいとも評されるそのカラーリングは、 水棲ガメの一種であればまだ有り得そうなものの、 穏やかな空気の漂うリクガメにしてはあるまじき手法であり、 やはり地球の裏側に広がる世界最大規模の熱帯雨林では我々の常識など一切通用しないことを思い知らされます。 真面目な話、日照量が決してふんだんではないのであろう森林棲の彼らにとって、 まず黒ベースというのは蓄熱性の関係からとても大切な要素であると考えられ、 大きくて黒々とした瞳もまたそれに関連した形質と思われます。 現地では南北に広がる分布域を有しエリア毎に大きさや色合いが変化するとされ、 そうやって巧みに生命を繋いできたアカアシガメの逞しさが描かれているようです。 今回やって来たのは最も有名な地域個体群であるチェリーヘッドの次に小型であるとされる、 ノーザンフォームの名で知られた棲息域北部に認められるタイプのアカアシより、 そこから更に海を渡って北上したバルバドス島に隔絶された、 通称バルバドスフォームとも呼ばれるノーザンフォームの派生タイプの、 信じられないことに同一ロカリティのペアを用いて繁殖された国内CBのベビーたち。 ついつい説明が長くなるほどのマニアックな掘り出し物に感極まってしまいましたが、 野生生物の世界には島嶼化という孤立した島では巨大化ないしは矮小化するという法則があり、 並のノーザンよりも少々小振りで計算上は前述のチェリーヘッドと同等、 即ちアカアシガメの中でも最小クラスのタイプであるらしいのです。 この二匹が持つ赤味の素晴らしさは個体差によるところも大きいのですが、 同ロットの兄弟でもう少し黄色いものも別で在庫しているのでお問い合わせ下さい。 チェリーヘッドよりも黒目の可愛らしさが際立つ人気のノーザン、 わざわざと言っては誠に失礼かもしれませんが、 バルバドスの付加価値を確信した上でブリーディングに努められる姿勢には脱帽の一言です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| ご好評につき再入荷! 今や湿潤系リクガメの代表種として一角を担うアカアシガメ・チェリーヘッドです。 一昔前まではいざリクガメを飼おうと図鑑を見るや否や飼育対象から外されてしまうカメのひとつだったと思います。 それもそのはず、最大甲長50cmと書かれれば特にビギナーにとってかなり大きなハードルであり、 たとえ容姿が気に入ったとしてもそう簡単に飼い始める事はできませんでした。 しかしいつからかブラジリアンチェリーヘッドという名前のついたものが出回り始め、 それは同時にドワーフチェリーヘッドとも呼ばれていました。 実は棲息範囲の広い本種は地域によって形質に差があり、 特にブラジル産の個体群は四肢のみならず 頭部全体までが鮮やかなレッドトップとなり、 初心者泣かせのサイズも最大で30cm頃と比較的小さくなりました。 それまでは名前の通りせいぜい足に赤がのる程度で頭部は同属のキアシの様に黄色味がかったものが多かったのですが、 ここまで赤みが強く出て更に小ぶりなサイズとなれば言う事なしでしょう。 大きさについては実際に当店でも過去25cm前後のペアで交尾し産卵までを確認しています。 今後ヘルマンやホシガメの様に定番種となっていくであろう注目のリクガメです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・ベビー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 近頃は流通がまばらになりつつも基本キャラクターとして目の前に置いておきたい貴重な赤系リクガメ! 日本に到着しておよそ一か月ほどが経過しMazuriリクガメフードオンリーで育つよう調教された、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 そもそもリクガメというジャンルはカメ全体の中でもほんの一部がそれに含まれているに過ぎず、 よく見るとおおむね黒色と黄色で構成されたデザインを持つものばかりという事実に気付かされます。 何故なら彼らの暮らしぶりや生存戦略が世界中の国や地域においてある程度共通していて、 つまりそれは世界中の何処にいても似たようなことを考え似たような生活を送り、 そしてその結果見た目の雰囲気さえも似通ってくるというのが実態なのでしょう。 気候や風土が変わっても、やりたいことが一緒であれば互いが近付いていくというのは面白いものですが、 その流れの中で赤色を主体としたアカアシガメの容姿というのは極めて異端であり、 何を考えどのような生き方をすればそのような結末を迎えることになるのか、 他の種類では絶対に真似することのできなかった領域に突入しているのが本種です。 こんな風にしてアカアシの赤が如何に珍しいものなのかを熱弁していると、 湿度が要るタイプのリクガメは難しそうだなんて声もちらほら聞こえてきそうですが、 冷静に考えてみれば逆に湿度が要らないリクガメなどほぼ存在しませんし、 こちらアカアシに対して過度な湿度を与えることは却ってリスクになることも踏まえれば、 一周回って他の多くのペットトータスらとなんら変わりないことに気付かされます。 つまり世間が意味もなく敬遠しがちな湿潤系と呼ばれるリクガメの仲間たちには、 まだまだ掘り下げ甲斐のあるお宝が眠っているということです。 今回やって来たのは何だか久々にお目見えするチェリーヘッドのアカアシガメより、 極小のベビーでもなければ無闇に育ってしまったそこそこのサイズでもない、 ちょうど良い頃合いで安心感と育て甲斐をミックスさせたベストな大きさの一匹。 本種が現地で棲息している国や地域によって複数のタイプに分けられ、 そのタイプ毎に最大甲長が異なることは既にご案内の通りですが、 最も小型であるこのチェリーヘッドが仮にサイズ面での魅力がなかったとしても、 この強烈な赤味によっていずれにしても高い人気を誇っていたことは想像に難くありません。 この個体は頭部や前肢の発色が顕著であることは言うまでもなく、 腹甲の大部分にまでその赤が滲み始めてしまっているところも好印象で、 適切な環境で絶品のアカアシを目指しコツコツと仕上げていきたい優良物件です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 近頃のベビーサイズの安定的な供給により、新たな湿潤系リクガメの人気種として台頭してきています。 特に人気なのはこのタイプでしょう、チェリーヘッドのアカアシリクガメが入荷しました。 昔主流だった赤い足に黄色い頭のタイプと違い、 ブラジルなどに棲息する個体群は足だけでなく顔全体にまで赤みが入る事から、 ブラジリアンチェリーヘッドと呼ばれます。 また南米のリクガメ代表のキアシガメと並び大型化する事も知られていましたが、 それも個体群によって違いこのタイプはおよそ30cmに満たない最終サイズという事からドワーフチェリーヘッドとも呼ばれています。 美しくかつ飼い切れるサイズとして人気は急上昇、今やビギナー向けとも言われる程になりました。 他のポピュラー種には無い黒や赤などのカラーが主体で、 また湿潤系と言えば潤みを帯び黒々とした瞳がとても愛らしいです。初期状態の落ち着いたものが多く 今回の個体も早速Mazuriリクガメフードを美味しそうに食べ、 ホットスポットとその反対を行き来しとても活発に動き回っています。 あまりの食欲に撮影用のディスプレイとして置いた観葉植物にまで興味を示す程。 今後の成長が非常に楽しみな2匹です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイカラー・チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 僅かな成長線の隙間から顔を覗かせる白い霜降りに大いなる可能性を秘めた極美候補生! その色合いも然ることながら安心サイズに至るこの段階で早くも理想的な成長過程を見せる、 アカアシガメが入荷しました。 一世代ほど昔の話になるかもしれませんが、 数年前のとある頃にアカアシガメこそ日本国内で飼育されるべきビギナー向けの種類だと、 大きく謳われていた瞬間があったかと思います。 それは何十年も前のゴリゴリとしたサイズが輸入されていた時代では無く、 ブラジリアンドワーフチェリーヘッドと呼ばれた小型個体群が発見され、 同じアカアシでもさほど大きくなり過ぎないことが分かり始めたつい最近の話です。 例えるのならばラグビーボールぐらいでしょうか、 脇に抱えれば何とか片手でも持ち上げられるギリギリ小型種と呼べるぐらいのサイズ感と、 何しろ元々が森林棲のカメですから紫外線要求量の少なさはとにかく有難いばかりで、 なおかつ夏に湿度の高い日本では外へ放り出すだけで快適な暮らしが提供できると言う、 新世代のリクガメとして一挙に注目を浴びた訳がここにあります。 性格も明朗快活な個体が多いため良く動き回って面白いですし、 彩りについてはリクガメでは異例の赤を採用する奇抜さも相まって、 今もなお広く愛される種類のひとつとして認知されています。 今回やって来たのはあまり大きくならないことが特徴のチェリーヘッドから、 その外観にはサイズの件以上にインパクトが感じられる、 同タイプに時折出現する各甲板の隙間と言う隙間に白い斑模様が描かれる美麗個体。 頭部全体および四肢の鱗がベッタリとした赤色に染まるだけでは飽き足らず、 明色斑も眩しい黒色の甲羅に更なる柄をあしらった贅沢な色使いには、 本種特有の毒々しさがより一層高められたような雰囲気が味わえます。 あくまでも成長線に対して表れるものなので幼体時にはその片鱗が見られず、 反対に幼い段階でそれが確認できると言うことは即ち、 フルサイズに到達した時にとてつもなく綺麗に仕上がる可能性が高いと言えるのです。 背甲の酷いボコ付きや体全体のカサつきもほぼ見受けられず、 餌食い良好で甲羅全体のシルエットも申し分無い将来期待の逸品です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ノーザンフォーム・国内CB) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| チェリーヘッドだけじゃない、梅干しのように真っ赤な頭を持つ美血統ノーザンフォーム! 甲羅からはみ出した部分がもれなく蛍光色で彩られたハイクオリティな国内CBです、 アカアシガメが入荷しました。 今後我が国におけるリクガメシーンを盛り立てていく上で、 最も注目されるべき昔ながらの湿潤系代表選手がこのアカアシガメ。 乾燥地帯や草原をトコトコと歩き回る一般のイメージとは少々異なった、 いわゆる森のリクガメとして異彩を放つこの系統は、 その先入観からなのか不思議と陰気臭く飼育の難しいイメージが付き纏っています。 確かに昔はシーズンインするとワイルドの中型から大型の個体がまとまった数でゴロゴロと登場し、 小傷は当たり前なのに加えて妙な風格まで漂う野蛮なオーラに包まれており、 可愛らしさなど何処吹く風といった具合で世間を圧倒させていました。 この辺りが俗に言うリクガメよりもむしろ水棲ガメのファンに好まれる所以なのでしょうが、 そのキャラクターを一通りに決め付けてしまうにはあまりにも勿体ないと思います。 この場でも何度か申し上げていますが、 冷静に考えてみるととにかく赤いリクガメというのは他に例を見ない貴重な存在であり、 代わりの利かない重大な役目を担っているというだけで有難味が感じられるでしょう。 かつては総じて50センチほどに大きくなると信じ込まれていた節があったため、 もしそれが本当ならケヅメクラスの広大な設備を必要とする訳ですが、 蓋を開けてみると国内で飼育されている個体の殆どが20センチから大きくても30センチ前後とリアルな数値で収まっており、 何ならこのボリュームは野外で歩かせて眺めるにはちょうど良いぐらいです。 また意外と気が付かれていないポイントが非常に強健であるということで、 湿度の高い日本の環境にすんなりとマッチしてくれるからなのでしょうか、 些細なマイナートラブルから深刻な病気まで症例の比較的少ない種類であり、 私の経験則で恐縮ですが健康かつ綺麗に育て上げられた個体が多いように感じます。 性格も大変明朗で活気溢れる姿が観察できるのも嬉しい、隠れた銘種と崇めるべき逸材なのです。 今回やって来たのは一部で有名なあの血統、 ではなく新たに発掘してしまったこれが事実上のメジャーデビューとなるニューカマー。 バルバドス島などを由来とするノーザンフォームと呼ばれる個体群を親に持つ、 お腹の広い明色部が特徴的なベビーなのですが、 足以外は黄色くなりがちなこのタイプには珍しく頭までしっかり赤く塗られ、 驚くべきことに腹甲の一部にはその余剰分が染み出しているではありませんか。 これこそリクガメではあまり前例のない、赤みの強い雌雄を掛け合わせた選択交配が生んだ結果であり、 この時点で既に美しい将来像が約束されたと言っても過言ではないでしょう。 毎日甲羅を濡らしながらとことん歩かせ、 もりもり食べさせてすくすくと大きくなる成長記録をお楽しみ下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ベビー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 今日のアカアシはチェリーヘッドではありません! かつて主流であった足だけ赤いオールドタイプ、アカアシガメが入荷しました。 南米大陸を代表するアカアシとキアシ、 どちらも巨大種でそうと納得させるワイルドの大型個体が輸入されていたのは昔の話。 いつしか本種のスタンダードはブラジル産のチェリーヘッドと名づけられたものに移り、 ドワーフとも呼ばれるそのタイプはさほど大型化しないことからアカアシの大衆化へ大きく貢献したことでしょう。 しかし旧産地の個体群を望む声が無くなった訳ではなく、 今回はそんな方々にお勧めしたい懐かしの大型個体群です。 足と頭は同じ暖色系でも赤と黄に色分けされ、 将来的にはよりはっきりと色の違いが見てとれるようになると思います。 そして要注目なのがプレーンな黄一色の腹甲で、 チェリーヘッドではむしろ黒い部分が目立つのに対しこの2匹は完全に異なった色彩を表していて、 残念ながら産地は不明ですが昨年入荷したベネズエラ産によく似ています。 多湿を好むことからか成長した個体には甲羅がかさついたり頭頂部が白くなってしまったものをしばしば見かけますが、 艶に満ちたピカピカのこのサイズから飼い始めれば潤いを保ったまま綺麗に育てることができるでしょう。 初めての方には多湿系の管理ポイントもお教えします。寝る時は寝て歩く時は歩くメリハリの良い元気な2匹です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ベネズエラ産) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 恐らく初入荷の産地だと思われます。ベネズエラ産のアカアシガメ・ベビーの入荷です。 近頃ではブラジリアンチェリーヘッドと呼ばれるブラジル産の頭部が赤く小型の個体群が多く流通し、 その昔はスリナムやガイアナ産の中型から大型の個体群がよく見かけられましたが、 今回は初めてのベネズエラ産の個体群です。南米北部の個体郡と同様、 その名の通り赤いのは足のみで頭部は黄色く染まる特徴が共通しており、 ドワーフと比べるとそれなりに大型化するのかもしれません。リクガメの仲間でもなかなかコアな部類ですが昔ながらの大きなアカアシをお好みの方に。 確証は無いですがペアっぽいので2匹セットの場合はサービスします。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・S) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 背中全体がぼんやりと発光する極上チェリーヘッド! 明色部の広さが著しいとてつもなく高いポテンシャルを秘めたセレクトハイカラー、 アカアシガメが入荷しました。 今やリクガメの一飼育対象として初心者から玄人にまで幅広く愛される、 南米を代表する種類のひとつがこのアカアシガメ。 昔はそれこそ足が赤いだけだとか、全体的に黒っぽいから変わっているだとか、 そこまで深く注視されることもないのと同時にその実態があまり知られていなかったのかもしれません。 定番の人気種と言うのはいつの時代も決まって同じようなものですが、 まだリクガメを飼うという行為が一般的ではなくなおかつ容易でもなかった頃に、 少々マイナーでマニアックなこういった仲間をわざわざ飼ってみようというのは少数派で、 しかも野生個体の大きなものがごろごろと並べられてはどうしても敷居が高くなってしまいます。 それが近頃ではこちらの飼育欲をそそるベビーに近いサイズが主に流通するようになったことや、 美しくしかも大きくならない個体群としてチェリーヘッドというタイプが紹介されるなど、 全てが追い風となりアカアシというカメの存在価値がどんどん高まってきているように感じます。 評判が集まり見かける数も増えてくると人間の欲としてはより良い個体、 自分の納得する個体に何としてでも出会いたいと思うのが心情で、 いくらチェリーヘッドと言えどものべつ綺麗になる訳ではありませんから、 凝れば凝るほど自ずと個体の良し悪しを見比べるようにもなってきます。 今回やって来たのはパッと見た印象で明るい、華やか、 そんな言葉がすらすらと出てくる非常に贅沢な色使いがなされた一匹。 同じチェリーでも大概は初生甲板の黄色味は面積が小さいか、 下手をすると成長に従い徐々に薄れてしまうものもいる中で、 この個体はその色がきちんと各甲版の形そのままで塗られぼやけた様子も今の所殆どなく、 美個体と呼ばれる個体の多くはこの辺りの基礎がしっかりしているというのも共通しています。 頭部や四肢など体全体の発色も申し分ありません、 未来のスターというのはこういった所から誕生していくのでしょうか。 見た目は小さいですが甲羅全体はもうすっかり硬くなった文字通りの安心サイズ、 せっかく育てるのなら最初の選別にも納得のいくまで拘り抜きたいものです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・S) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 鮮やかに灯る初生甲板の黄色い輝きに光る何かを感じて止まない底知れぬ素質を持つ美個体候補! 全身がパステル調の色彩を呈する明らかに一味違うポテンシャルを秘めた有望個体です、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 華々しい再デビューから数年が経ち、 ようやくペットトータスの定番種に名を連ねるまでにのし上がってきた、 今最も注目度の高いリクガメのひとつに数えられるアカアシガメ。 昔は馬鹿が付くほどの巨大な野生個体が文字通りゴロゴロと出回り、 こんなカメを誰が飼うのかと罵られてもおかしくはない完全なるマニア向けの種類だったはずが、 今となってはリクガメのデビュー種に選ばれるほどの市民権を得るまでに大化けし、 その功績たるやよくぞここまでと感心させられるほどです。 南米大陸の北部を中心に広い分布域を持つ本種は、棲息する国や地域によって色合いや大きさ、 形状などに豊富なバリエーションを持つことで知られ、 その特徴が自分の気に入った個体を選びたいと言う愛好家の思いと合致したのでしょう、 近頃では多くの人がより質の高い一匹を求めて探し回ることも珍しくありません。 当店でも過去に様々なタイプのアカアシをご紹介してきましたが、 ホシガメなどと同様に毎回手に取る度に異なる形質を目にしては、 その奥に広がる無限の可能性に自然の驚異を痛感させられるのです。 今回やって来たのは顔中にすっきりとした透明感のある朱色を掲げながら、 背甲の明色斑がかなり強めのイエローに色塗られた変わった雰囲気の個体。 他産地では頭部と四肢の色が異なる場合もありますが、 チェリーヘッドにおいては全体がおおまかに赤なら赤、 オレンジならオレンジと同一色で綺麗にまとめられることはあっても、 地色を除いた部分がここまではっきりと二色刷りに仕上がるケースは殆ど無いため、 成長した暁にはかなり目を惹く美貌に仕上がるのではないかと期待しています。 加えてチェリーヘッド特有の霜降り模様が成長線に現れれば、 相当なグレードのアカアシが出来上がることでしょう。 左第二肋甲板に小さな亀裂がありますが、 成長後には殆ど目立たなくなるであろう軽度のものです。 通常現地から送られて来るベビーよりも一回り育った元気もりもりサイズ、 甲羅や肌が白くカサつかない上手な育て方もお教えします。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・S) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 偶然の産物のように扱われていた霜降りチェリーが目前に迫った将来楽しみなセレクト個体! 成長線の隙間を埋めるように侵食し始めた白いもやもやに背中が覆い尽くされるのを期待しましょう、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 昔からカメを知る方々にとって、 あれほど憧れの的と言われていたリクガメの仲間たちが全般にリーズナブルな価格帯となり、 初心者でも入手し易くなったことについては、 ちょっとしたカルチャーショックに似た感覚を覚えるのではないかと思います。 ふたつの意味でかえない人が仕方なく別の種類で代替えをする、 そんな光景があちこちで見られたあの頃とは打って変わって、 今日では初めて飼育する人が当たり前のようにリクガメを選択する時代になりました。 様々な種類が毎年コンスタントに流通する中で、 かつては野性味バリバリの大型個体だらけであった南米を代表するこのカメも、 可愛らしいベビーから育てることができるようになり人気は上昇する一方。 他種においてはまず考えられない赤と言う要素を全面に押し出した センセーショナルなデザインはいつまでも色褪せることが無く、 今後もビギナー向けの定番種として愛され続けることでしょう。 今回やって来たのは今となっては何処でも見かけられるお馴染みの小型個体群、 ブラジリアンドワーフチェリーヘッド。 その名の通り脚部のみならず頭部にまで赤色が飛び火することで知られていますが、 他の個体群とは異なりしばしば甲板の継ぎ目付近に白斑を生ずることがあり、 この個体はなんと成長の初期段階で既にその兆候が見え始めています。 現地のファーミングで殖やされたようなベビーサイズではほぼ分からないこの特徴、 しかしながらほんの少し大きくなったぐらいでは容易に発現しないことが殆どですから、 これほど若い年齢で発色していると言うことは、 単純に面積だけでも将来的にかなりのクオリティが期待できるはずです。 ご覧の通り日本に到着してから幾分成長しているため、 甲羅を指でグッと押しても硬く餌はリクガメフードを中心にもりもりと食らい、 基本的なコンディションに全く問題はありません。 この先五ミリずつ大きくなる度に楽しみが倍増する素敵な一匹、 甲羅に出た芽が花開くのを心待ちにして綺麗に育てましょう。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・ハイカラー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| さくらんぼが熟し過ぎ遂に火を噴いてしまった燃え上がる顔面のファイアーヘッドアカアシ! 妖しげに発光する背中の黄色斑がとても昼行性の生き物とは思えない美しさを演出します、 アカアシガメが入荷しました。ビギナー向けとされるお馴染みの御三家に待ったをかける、 今リクガメの中でも特に注目が集まる新たな刺客として期待されるのがこのアカアシ。 申し訳無いことに最大サイズがどうしても厳しいと言う方には チチュウカイリクガメの有難味を噛み締めて頂きたいのですが、 反対にもう少しボリュームに対して許容ができる、 それどころか大きさは気にせずむしろある程度の重みが欲しい、 なんて方にとっては新たな選択肢として大いに検討され得る種類かと思います。 湿潤系のタイプは難しそうと言う謎の固定概念は早く捨てて下さい、 日本の環境にはそれがベストマッチするケースすら考えられますし、 上手に育てるコツはいくらでも実践することが可能です。 一番大切にしたいのは視覚的に最も気に入った種を選ぶ極めて単純な志向であり、 こんなに奇抜で特徴的な容姿を持つカメが放って置かれるはずも無く、 少し拘りを持って始めたい初心者の方にも着実に支持されつつあるようです。 今回やって来たのはチェリーヘッドを通り越し、 まるで別種のような衝撃を受けるハイカラーのセレクト個体。 あえて言葉で説明するまでも無いクオリティの高さは頻繁に巡り会えるものでは無く、 赤黒いと表現したくなるほど濃厚具合の甚だしい発色がその存在感を一瞬にして脳裏に焼き付けます。 背甲に規則正しく並んだ斑紋の鮮やかさにも目を見張るものがあり、 誰がどう見ても羨ましがられる逸品に仕上がることは間違いありません。 厳しい目付きを持つその表情はダースモールを思わせる強面ですが、 明朗快活なその性格により餌が貰えると分かれば親しげに近寄って来ますし、 環境に馴染んでしまえば随一の運動量でいくら見ていても飽きません。 普段現地より輸入されるサイズに比して幾分大きなこの個体、 やはりエキセントリックな色彩を持つがために暫しの間勿体ぶってストックされていたのでしょうか。 甲羅の形も全く崩れていない大満足の安心サイズです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ベネズエラ産) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 木苺とパパイヤ、ふたつの味が揃いました! 地域やタイプによって個性があるからこそ気に入った個体を選びましょう、 ベネズエラ産のアカアシガメが入荷しました。 アカアシリクガメとも呼ばれる本種はお隣のキアシと並び昔から馴染み深いリクガメのひとつです。 キアシは近頃現地からの輸入が少なくなり姿を見かける機会が減ってしまいましたが、 一方のアカアシはと言うと時代を重ねるに連れて広い棲息地から様々な地域個体群が紹介され、 次第に多様な形態の違いが知られるようになってきました。 今回はベネズエラからの使者、ですが成長すると具体的にどうなるのでしょうか。 ものの本によるとベネズエランフォームやノーザンフォームと紹介され、 最大甲長はあまり大きくならないとされるチェリーヘッドより気持ち大きくなる程度。 決定的な特徴は腹甲の色、チェリーでは黒地に白い霜降り模様が入りますがこちらはほぼ無地の黄色で、 当店で過去に取り扱った個体の中には少なからずこういった形質を持つものが存在しています。 具体的には産地不明ですが長期飼い込みでも27cmだったメス、そしてガイアナ産のペアなどが当てはまるでしょうか。 そんな分類上の小難しい話はさておき、 この2匹はそれぞれ持ち味が異なりチェリーヘッドにはない独特の美しさが光ります。 1匹は手足と頭部が同系色で、 かつ甲羅のスポットやちょっと恥ずかしいですがお尻の周りまで、 とにかく赤いアカアシが好きという方にはたまらない配色。 そしてもう1匹は一目見ただけで分かりますが赤足だけど頭は黄色という二色刷りで、 金髪でビシッと決め込んだ辺りはなかなかいかしています。 こちらの個体は特に頭部全体の色のりが良く、 長く伸ばしたもみあげはヘッドギアを被ったようで派手さに磨きがかかっています。 甲羅のフォルムなど全く崩れず安心サイズまでしっかりと飼い込まれているため、 あとはカラーリングの好みだけで選んで頂けると思います。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ベネズエラ産) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 欠片ほどの赤みしか見られないロカリティ付き珍個体群! ベビーからの国内飼い込み個体です、ベネズエラ産アカアシガメが入荷しました。 南米に繁栄したリクガメの一グループには本種の他にキアシ、チャコ、そしてガラパゴスゾウガメなどが棲息し、 かつての大所帯リクガメ属から新しくナンベイリクガメ属として独立させる動きが強まっています。 ゾウガメは極端な例にしろ基本的には大型のグループで、 野生下では甲長にして50cmを超えることも少なくありません。 その中で突如現れた異端児として近年シーンを賑わせているのが、 本種のブラジル産個体群通称ブラジリアンチェリーヘッド。 別名ドワーフチェリーとも呼ばれるこのタイプは成熟しても30cm程度にしかならないとされ、 今まで大きくなるからと敬遠され続けてきたアカアシにたちまちスポットが浴びせられることとなりました。 しかしその流行に乗ってかここ数年アカアシとして見かけるのはほぼ全てドワーフタイプで、 昔ながらの赤くないアカアシガメは姿を消してしまいました。 今回は1,2年前にふと輸入されたベネズエラ産のベビーが育ったもので、 成長してより一層その違いがはっきりと見て取れる珍しい1匹。 まず目に入るのはパパイヤの実を模した様な黄色い頭で、 このカメを初めて見るのがこの個体であれば間違いなくアカアシとは呼ばないでしょう。 というのも多くは黄色い頭に赤い足であるのに対し、 この個体は足の赤みが殆ど見られず、 その大胆な色合いは奇妙かつ魅力的。 またドワーフ系とは違い腹甲には暗色部よりむしろ明色部の方が大きく目立ちます。 今日は晴れの舞台なので温浴し体を清めましたが、 普段は食い意地が凄いので体がすぐに餌で汚れてしまう大変元気な個体です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイカラー・チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| もはや霜降りどころの騒ぎでは無く一面が乳白色に覆われそうな究極のメインディッシュ! サシを入れ過ぎたために頭上の赤が霞むほどのインパクトを手に入れた一級品、 チェリーヘッドのアカアシガメが入荷しました。 あまり大きくならないアカアシがいる、 そんなまことしやかな噂が流れたのも早十数年以上前の話ですが、 かつてブラジリアンドワーフチェリーヘッドと言うフレーズが与えた衝撃は、 一体何処へ行ってしまったのでしょうか。 つまり何を申し上げたいのかと言うと、 今日ではアカアシガメイコール足も頭も赤いリクガメとしての印象が根強く、 例えば足だけが赤くて頭は別の色だったとか、 大人が抱えるのも大変なほど巨大になる種類だったとか、 成熟すると甲羅のウエスト部分が綺麗にくびれる面白いカメだったとか、 本種に纏わるエピソードの数々も忘れ去られそうになってしまうほど、 全く別のキャラクターとして新たな道を歩み始めているようなのです。 ですから今となってはチェリーヘッドなる品種名、 正しくは特定の個体群を表す商品名のようなものなのですが、 それ自体が特別な付加価値を持たないようになってしまい、 冷静に考えれば体の何処かに赤色が表れるリクガメなどほぼ存在せず本当に凄い特徴であるはずが、 ただ赤いだけでは驚かれなくなっている現実に胸が痛みます。 そこで新たに注目され始めているのが背甲に描かれる霜降り模様、 これはチェリーヘッドの中でもごく一部の個体だけに許された特権であり、 もちろん程度の差はあるものの目に見えてはっきりと出現するものは稀で、 しかも成熟度が増した頃にようやく確認できる場合が殆どですからたちが悪く、 輸入される個体の多くは幼体であるが故に将来像を見定めることが困難なため、 それが却ってマニア心を擽っているように思います。 今回やって来たのは安心サイズの時点で怪しげな個体をピックアップし、 それを暫く育ててみたら本当に大変なことが起きてしまった絶世の美貌を誇る最高級の霜降りチェリー。 アカアシガメについての大まかなバックボーンを解説すれば、 この一匹が如何にぶっ飛んだ存在であるか、 そしてこの先の成長過程が楽しみで仕方ないことが嫌でもお分かり頂けるでしょう。 個人的にはセレクティブブリードにより甲羅の大部分が白く色抜けしたアカアシなんて面白いのではと考えています。 これまでの育て方も大変お上手で文句の付けようが無い素晴らしさです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・フラワーバック) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| あまりにも熟し過ぎて中身が炸裂してしまった極上の霜降りチェリーヘッド! 手の平に収まるこのサイズにして熟れるという言葉のミスマッチ感が堪りません、 アカアシガメが入荷しました。 リクガメ飼育の黎明期から長きに渡り多くのファンを獲得してきた古参種、 その歴史において特別な流行と言うものは無かったように記憶していますが、 それでも他種には真似することのできないかけがえのない魅力を武器にここまでやって来ました。 その昔アカアシと言えば本当に足だけが赤く、 その他の部分については甲羅が真っ黒で頭は黄色いという、よく言えば画期的な配色であり、 悪く言ってしまえば常識外れの不気味な空気を漂わせていたように思います。 図鑑で見る最大甲長がとても初心者向けとは言えない所も問題視され、 当時は情報が明らかになればなるほどますます変わり者扱いされる始末でしたが、 そんなピンチを一瞬にして救ってくれたのが、皆さんご存知のブラジリアンドワーフチェリーヘッド。 あえて正式名称のような表記をすると実に長いネーミングとなりますが、 要するに数ある地域個体群の中でブラジルを中心に分布する、 同種内でもさほど大きくならないタイプのことを指した言葉で、 その名の通りツートンに分けられていたはずの頭部までもが赤く染まるという、 我々日本人にとっては嬉しい最終サイズが抑えられた上に、 より美しさに磨きがかかるということで絶大な人気を誇りました。 これをブームと言うのであればそうなのかもしれませんが、 森林棲であることが過剰にハードルを上げてしまうらしく、 未だに飼育が難しそう、陰気臭そうと言った誤った認識が流布しているようで、 本当は丈夫な体質と明るい性格の持ち主ですから今後より一層の普及率向上に努めていきたい所です。 チェリーヘッドがすっかり浸透した今、近頃では愛好家の意識もかなり高まっているようで、 ただ単に頭が赤いだけでは当たり前と突っ込まれることもしばしばありますが、 パッと見た全体像から明らかな異変を感じさせるこんな個体は如何でしょうか。 私自身も含め、 これまで出会ってきた数々のアカアシと各々の大きさをよく思い出し比較して頂きたいのですが、 元々のデザインをここまで崩壊させるとんでもない甲羅がかつて存在したでしょうか。 長さで見ればベビーが倍になった程度の現時点で明色部の噴き出し方がえげつなく、 先のことを考えるだけで恐ろしくなるのも決して間違いではないと思います。 顔全体を包み込む赤色にも濁りなきフレッシュさが光り、 トータルクオリティの高さが証明されているようです。 これぞまさしく将来を約束されたサラブレッド、 美の追求に余念がない大満足の逸品を貴方の手で完成させて下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・M) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| じゅくじゅくに熟れすぎてこぼれ落ちそう! ちょっとやり過ぎな赤が目に染みる美個体です、アカアシガメ・チェリーヘッドが入荷しました。 南米大陸に広く分布するアカアシガメは産地によってある程度のまとまりに分けられ、 それらは個体群として異なった特徴を持つとされています。 昔は名前の通り足だけ赤い巨大になるタイプしか見かけませんでしたが、 最近の主流はブラジリアンドワーフという小型で美しいと言われるタイプに変わり、たちまち人気種の一員に加わりました。 今回やってきたこの個体はどう見ても赤が主張し過ぎている感があり、 チェリーヘッドにチェリーノーズ、 チェリーチークとがっつりさくらんぼ尽くし。 他の個体と比べて写真を撮ってみました。 黒地のはずの部分に黒がありません。 顔が赤くて体が黒いその姿は見つめれば見つめるほど、 映画スター・ウォーズに登場するあの悪役にしか思えません。 いわゆる安心サイズからもう少し育った手の平大で甲羅はおおむね綺麗に育っており、 お腹側に少し乾きがありますが上手に飼えば成長に連れて綺麗になるでしょう。 餌にも飲み水にも貪欲な健康児で状態に不安はありません、オススメ! | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・フラワーバック) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| むしゃぶりつきたくなるほどジューシーなこの色使いはチェリーヘッドを超えた未知の領域! 弱冠15cmにして甲羅の霜降り模様が大変なことになっています、 フラワーバックのアカアシガメが入荷しました。 最近になってようやく明らかになってきた、実は豊富なアカアシガメのバリエーション。 南米大陸に広く分布することからエリア毎のグループ分けはもちろん、 同じ個体群同士を比べてもそれぞれ持ち味が少しずつ異なり、 気に入った雰囲気のものを選ぶ楽しみも風潮として広がってきました。 その中で突出して人気の高いタイプがこのチェリーヘッド、 いわゆるドワーフ系列のひとつで大きくなり難いというのは勿論ですが、 何よりその真っ赤に染まる頭がキャッチーで分かりやすいというのが強みです。 登場したばかりの頃は非常にセンセーショナルな存在でしたが、 今ではアカアシの主流というポジションに安定してきたので、 そのブームは随分と落ち着いてきたように思います。 しかし今回、その安穏とした空気を吹き飛ばすビッグウェーブとなりかねない、とんでもない一匹がやって来ました。 一体なんでしょうか、さり気なくも確実に一歩一歩を踏み出している、 それは近い将来間違いなく獲得するであろうずば抜けて美しい姿への道を、 その瞬間に立ち会った私たちが感じる期待と恐怖が入り混じったようなこの不思議な心境は。 頭の赤さ、四肢の赤さ、 そして甲羅の継ぎ目に溢れ出した新たな可能性の芽吹き、 そのどれかが欠けでもすれば今目の前にいるこのリクガメが与えてくれる感動が生まれることはなかったのでしょう。 地肌はしっかりと黒く染まり、その上に塗られたのは赤の度合いをより強めた紅、 特に顔の部分はまるでマスクを被ったようなべったりとした着色が見事で、 基本的なクオリティについては申し分ありません。 更に新しい成長線に表れた白のもやもや、 元飼育者に病気ではないかとまで言わしめた異常な現象はチェリーヘッドにおいて時折見られるプラスアルファの発色で、 全く出ないか出ても20cmを過ぎた辺りで少しだけ楽しめる程度が平均的なので、 こんなに早く出てきてしまっては後が大変になることは目に見えています。 本来は黒がちになりやすいお腹側も、 明色部がかなり広い面積を占有していることは綺麗になることの証かもしれません。 あくまでも完成型ではない、完成まで自らの手で仕上げていくというのもこの個体の醍醐味、 数年後に化けることを思うと期待で胸が膨らみます。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・ハイカラー) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 何もなかったはずの黒地が霜降り始めたこれぞチェリーヘッドの醍醐味! 見つめるだけで口の中にじゅわっと涎が滴るしわしわの赤い頭が素敵です、 アカアシガメが入荷しました。 昔ながらのリクガメとして知られるアカアシガメについて、 皆さんはどのような印象を抱いているのでしょうか。 甲羅は全体的に何処かしっとりとしていて、 潤みを帯びた瞳がはめ込まれたその表情は森のカメであることを伝えてくれます。 木々が鬱蒼と生い茂る熱帯の森林地帯に、 隙間から射し込む木漏れ日を浴びながら暮らす情景を思い浮かべれば、 地球の裏側で繰り広げられている野生動物たちの物語を覗き見たような気分に浸ることができます。 それでも私たちがリクガメに描くイメージとは、 砂漠や草原で燦々と降り注ぐ日光に負けじと歩み続けるあの姿ですから、 この手の湿潤系と呼ばれる仲間はどうしても陰気に見られがちで、 むしろマイナスに捉えられてしまうこともあるかもしれません。 しかしそれはあくまでも人間の都合で作られた虚像であり、 カメそのものと真摯に向き合って得られた回答ではないのです。 少々小難しい説明になってしまいましたが、本当の答えを知るのに最もシンプルでかつ簡単な方法は 、一度でも手元に置いて飼育してみることではないでしょうか。 少なくとも私はアカアシガメが陰鬱とした性格の持ち主であるなどと感じたことは一度たりともありませんし、 同種他種問わず他の個体を押しのけて我先にと餌場へ向かうシーンをもう何度見せられたのか分からないほど、 ペットないしは家族として迎え入れるのに最高の逸材ではないかと考えています。 どれほど色や形が綺麗でもリクガメに求められるのは第一に歩くことですから、 目と目が合うだけでこちらに駆け寄ってくる愛嬌の良さに幾度となく惚れ直してしまうのです。 今回やって来たのは綺麗で小さな個体群としてお馴染みのチェリーヘッド、 本タイプがアカアシガメの人気を根底で支える功労者であることは言うまでもありません。 かつて流通の主体であった足だけが赤いアカアシとは異なり、 頭部はペンキをぶちまけたようなべったりとした赤に覆われ、 もちろん四肢にも同色がタイル状にはめ込まれ毒々しくも美しい容姿をつくり出しています。 そしてお楽しみは成長の中盤から、 てんとう虫のように明かりが灯る初甲板のスポットだけでは飽き足らず、 伸び続ける成長線に次々と白い色抜けが始まっていき、 まさしく特上和牛のように贅沢な模様が次第に甲羅全体へと広がっていくのです。 全体のフォルムに大きな崩れはなく、よくあるトラブルに数えられる頭頂部の鱗がかさついたり、 腹甲がダメージを受けたような形跡も殆ど見られないため、 この調子で適切な環境を維持していけば思い描く通りのチェリーヘッドアカアシができあがっていくでしょう。 腹甲の明色部は面積が広く、背甲のまだらは数が多く、頭部全体の色乗りが良いなど、 随所のクオリティがそれぞれ並以上の美個体なので将来有望として強く推薦します。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイカラー・チェリーヘッド) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| いくら気を付けてもこぼれ落ちそうな多量のまだら模様が食欲をそそる極美チョコレートクランチ! 育ててみなければ分からなかった資質の高さが今まさに花開こうとしています、アカアシガメが入荷しました。 今やリクガメ界を代表する人気種へと成長したアカアシガメ、 その栄光の陰には度重なる苦労があったと言われています。 私たちにはどうやら赤い生き物を珍重する風潮があるようで、 伝統的な金魚や錦鯉を筆頭に観賞魚の世界ではアジアアロワナなどもその例として挙げられ、 本種も唯一の赤いリクガメとして十二分に通用する素質を持っているはずでした。 しかしながら昔から定期的に輸入され人目に触れる機会もそう少なくなかったにもかかわらず、 やれ大きくなるだの湿度管理が難しいだの第一印象から悪くするようなことばかりを言われ続け、 とても不利な立場からのスタートとなってしまいました。 そこで彼らは広大な分布域に根差した豊富な地域個体群という多勢を以ってして勝負に挑む訳ですが、 日本人の感性に響くヒット作を世に打ち出すまでには現実に何年もの月日を要したのです。 その答えのひとつとして揺るぎないのがブラジリアンドワーフチェリーヘッドと呼ばれるこのタイプ。 名前をそのまま呑み込んで頂ければ特徴は全て掴み取れますが、 つまり足だけでなく頭まで赤く染まるさほど大きくならないブラジル周辺の個体群という意味を表しています。 初出時は実にセンセーショナルな衝撃を与えた革命児でしたが、 近頃ではチェリーヘッドであることへの価値観に慣れてしまい、 よりクオリティの高いものを求める動きが強まってきているようです。 今回やって来たのはもはや別亜種ないしは別種として騒がれてもまるで差し支えのない、 斑入りの甲羅が原種の持ち味を限界かそれ以上に引き上げてしまった最高品質の一匹。 今更になって初めて気が付くことになるのですが、 初生甲板の輝きからして並のアカアシでは到底及ばないクオリティを放ち、 それが勢い余って辺り一面に星屑を撒き散らしてしまったがためにこの意匠が完成形へと近付いているのです。 体は鮮やかでも甲羅は暗色にまとめられるはずでした、 しかし遠目から見ても陰気なイメージは全く伝わって来ず、 むしろホシガメやヒョウモンガメと同じ草原の明るい雰囲気に包み込まれているではありませんか。 本当は黒が先行するはずだった腹甲にも明色部が爆発することで、 チェリーヘッドらしからぬ奇抜さを証明しているようです。 顔と体の赤みも質を落とすことは一切なく全体のバランスも良好で、 今現在が一体何分咲きなのか、 そして最終的に如何ほどの実力を発揮してくれるものなのか、 期待に胸を膨らませてもきっと裏切られることはないと思います。 背甲の黒色がやや茶色味がかっているのは何かの変異なのかもしれません、 今すぐにでも知りたいその答えをどなたか解明して頂けないでしょうか。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 見ているだけでお腹いっぱいの完熟さくらんぼ頭! 納得の赤みです、チェリーヘッドのアカアシガメ・オスが入荷しました。 南アメリカに棲息する森林棲のリクガメで、黒地に赤という狂気的な色彩に一目で心奪われた方は多いと思います。 同時に、どんなリクガメを飼おうかと図鑑を眺めていて最大甲長50cmの文字が目に入った途端に、 これは飼えないからとスルーしてしまった経験をお持ちの方もまた多いと思います。 しかしそれはもう過去の話、という訳ではありませんがあながち間違いではないかもしれません。 というのも、ここ数年で流通しているこのカメの殆どに名付けられた ”ドワーフチェリーヘッド”と呼ばれるタイプは最大で30cm程度にしかならないとされ、 これは棲息域が広い本種の一部地域個体群に見られる特徴と言われています。 大型のリクガメは誰もが飼えるわけではなくかつては雰囲気の変わったマニアックな種類と称されることもあったでしょう。 しかし現在では状況一転、 現実的な最終サイズが知られることによりビギナー向けのスタンダードなリクガメに見事イメージチェンジを果たしました。 この個体は典型的ながらいざ探すとなかなか見つからない赤みの強い頭部を持ち、 また甲羅の成長具合もまるでベビーを見ているかのような満足のフォルム。 甲羅の柔らかい時期はとうに越えていますので今後も順調に大きくなってくれることでしょう、 色も形も綺麗なお勧めの良個体です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイカラー・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 何処まで発色すれば気が済むのか将来の美貌を想像するだけで末恐ろしいレッドスペックルチェリー! 甲羅の質感から形状まで首尾良く丁寧に育て上げられたよく盛る未来の種親候補、 アカアシガメ・オスが入荷しました。 ビギナーにお勧めのリクガメとして毎度決まって名前が挙げられるチチュウカイリクガメ、 例えばギリシャやヘルマンなどはもはやこちらから説明するまでも無いほどの定番種ですが、 そんな常勝軍団の地位を脅かすべく新たに名乗りを上げ始めているのがこのアカアシガメ。 その昔本種のイメージとしては南国の大型種という説明がぴったりなほど、 どちらかと言えばある程度カメに通じた人向けのマニアックな存在だったはずが、 さほど大きく育ち過ぎないブラジリアンドワーフチェリーヘッドと呼ばれるタイプが世に知られて以来、 これまでに無かった鮮やかな体色がたちまち脚光を浴び見事人気種の座を掴み取るまでになりました。 最近では現地からの繁殖個体もコンスタントに流通するようになり、 初めてのリクガメに選ばれるケースも多いと聞きます。 何となく陰気臭そうに見える外観とは裏腹に、 よく歩きよく食べよく出す明朗快活な個体が多いのも嬉しいポイントで、 ペット的に見た場合でもたっぷり可愛がられて然るべき有望株です。 今回やって来たのはただのチェリーヘッドには飽き足らない、 一味違った極上の一匹をお探しの方へ強く推薦したいこんな風変わりな個体。 これまで見栄えのする幼体を選ぶとなるとやはり頭部の発色については言うまでも無く、 その他には前肢など鱗の赤く染まる部分ばかりに着目してきたのですが、 こうしてある程度育った段階では甲羅の色柄までもが露わになり、 しかしながら初生甲板以外の箇所にも赤い斑点が出現するなど一体誰が想像したでしょうか。 俗に霜降りと呼ばれる甲板の継ぎ目に白いもやもやが描かれることがあり、 それはチェリーヘッドに特有の現象とされているのですが、 まさかその部分にまで色味を呈したことについては驚きを隠せません。 法則に従えば大きくなるに連れて美しくなる一方のこのカメが、 現状よりも更なる高みを目指すとなればもはやこれ以上の褒め言葉も思い浮かびません。 アカアシの飼い込み個体にありがちな甲羅表面の腐食もほぼ一切見られないスペシャルクオリティ、 近い将来貴方のお手元で目を見張る真価を発揮することを期待しています。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 背中に灯る赤い斑紋と頭部を覆う鮮烈な紅色が教科書通りの美貌を描き出す高品質な絶品! 扉の前で飼い主を呼び寄せるように右へ左へダンスを踊る類稀な明るさもまたこの個体の魅力のひとつ、 チェリーヘッドのアカアシガメ・オスが入荷しました。 この場においては繰り返し何度も申し上げていることですが、 リクガメという生き物の中で唯一ボディカラーに赤を採用した奇抜なデザインが持ち味で、 世間一般がリクガメと聞いて連想する茶褐色を主体とした多くの種類とは対照的に、 ダークかつコントラスト豊かな配色が個性的な雰囲気を漂わせる森林系の代表格。 どちらかと言えば水棲ガメ寄りとでも言いましょうか、 そのカラーリングから何となく陰気臭そうなイメージも付き纏う本種ですが、 本当は非常に明るい性格の持ち主で決して日陰者などではなく、 実際の動きのキレを見ると全てのリクガメの中でもその躍動感はずば抜けて優れており、 人一倍大きな黒い瞳をキラキラさせながら辺りを爆走しているシーンなどに出くわすと、 やはりリクガメとは歩いてこそだと改めて強く感じさせられるものです。 らしい、らしくないといった話題になるとどうしても好みの分かれるところがあって、 全ての飼育者がその対象として選択する種類ではないのかもしれませんが、 ガツガツ餌を食べてガブガブ水を飲みバタバタ走り回ることを知ってしまったが最後、 一気に欲しいリクガメの上位へと駆け上がることは間違いありません。 今回やって来たのはおおよそアダルトサイズと呼ぶに相応しい段階へと到達した、 育ちの良さが全体のバランスから色艶に至るまで随所に表れた立派なオス。 同じアカアシでも特に小型な個体群と評されるチェリーヘッドなだけあって、 片手で持ち上げられるこれぐらいのサイズでも高い成熟度が感じられ、 緩やかな成長こそ見られるものの室内のケージでも苦しくない程良いボリュームが嬉しいです。 甲羅や肌の表面が白く痛んでしまったような箇所も殆どなく、 甲羅は肩が張ったり尻がすぼんだりせず前後で綺麗な平行線を描き、 頭側から尻尾側にかけて下がってしまうようなこともない綺麗な俵型になっています。 頭の赤さも申し分ないクオリティでこれならば誰がどう見てもチェリーヘッド、 この毒々しいまでの鮮やかさが最大のアイデンティティであるだけに、 こればかりは妥協したくないところ。 日頃からまるでミズガメのように餌くれアピールの凄まじい人懐っこい一匹です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |




|
|
||||||||
| 綺麗に育ったお客様飼い込み個体です。アカアシガメ・オスの入荷です。 この個体はいわゆる”チェリーヘッドタイプ”で、 その名の通り顔は真紅に染まり非常に美しいです。 ミズガメで言えばさながらシルバチカ。また本タイプは”ドワーフタイプ”とも呼ばれており、 最大でも30cm程度にしか成長しないとされています。色味も派手でそこまで大きくならない為、 国内での飼育にはかなり向いており人気も高いです。 甲羅の形状も綺麗なドーム状に成長しています。 餌は雑食性なので葉野菜やバナナは勿論好みますし、市販のリクガメフードでも比較的綺麗に育ってくれる様です。 このサイズで流通する事はあまりありませんのでお探しの方は是非この機会に。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 湿潤系リクガメの育て方のお手本のよう! 思いのほか綺麗な個体がやってきたのでびっくりしました、 チェリーヘッドアカアシガメ・オスの入荷です。 ここ数年でビギナー向けリクガメとして台頭しているのがこのアカアシ。 昔はとりあえずまとめて捕まえてみました、 というような野性味溢れる大型個体を見かける機会が多くそのイメージが強かったのですが、 最近ではそのようなものの輸入はめっきり減ってしまい、 むしろファーミングで繁殖された可愛いベビーがメインになり雰囲気をガラッと変えてきました。 小さな幼体を見てまず初めに感じることは、ウルウルとみずみずしい瞳が愛らしいということだと思います。 乾燥系のタイプでは目が乾きすぎてしまうので、この特徴はまさに森林に暮らす仲間の特権と言えるでしょう。 しかしネックになるのはその飼育方法で、湿度が足りないと甲羅や肌にトラブルを抱えることもしばしば。 その例としては頭頂部が乾きせっかくの赤がくすんでしまうこと、 新しい成長線が乾燥によりぐずぐずになってしまうこと、 湿り気を気にし過ぎて腹甲がぐずぐずになってしまうことなどです。 しかし今回やってきたこの個体、 甲羅も肌も何もかもがピカピカで意外とここまで綺麗に育てるのは難しいと思います。 特にべっこり凹んだ腹は心配になるぐらいですが照りが眩しく、 最も起きやすい頭部の乾燥は微塵も見られずこれは実に優秀です。 今後もケージ内の湿度をある程度高く保つことでこの美肌を維持できるでしょう。 床材は最初に全体を湿らせあとは上面が乾燥してきたらスプレーで湿り気をキープし、 定期的に全体を耕し空気を入れ替えてあげるのがポイントです。 餌は好き嫌いせず何でも食べますので多様な食事メニューで可愛がってあげて下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ノーザンフォーム・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 赤や黄色、黒と言ったおもちゃのようなカラーリングが可愛らしい圧巻のアダルトサイズ! チェリーヘッドと同様に大きくなり過ぎないタイプとして昨今注目を集めている、 ノーザンフォームのアカアシガメ・オスが入荷しました。 その昔はご丁寧にアカアシリクガメとも呼ばれていた、 私たち日本人にとっては古くから馴染みのある南米産のリクガメで、 まだ飼育方法もろくに分からなかった時代には、 まるで岩のような野生個体がゴロゴロと輸入されていたと言います。 動物園では同じく南アメリカのオオハシなどと共に展示されていることも多く、 その色鮮やかな組み合わせと平和な雰囲気が興味を惹くのでしょうか、 何処かで目にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。 いずれにしてもそのリクガメ離れした配色は世界中何処を探してもアカアシかキアシぐらいのもので、 如何にも地域の特性を表した素晴らしい特徴だと思いますが、 飼育の際には湿度を高くしなければならないと言う謎の義務感から、 不思議と導入に躊躇ってしまうケースも少なくないようです。 実際には過度に湿った環境こそ悪影響を及ぼす原因となりますし、 また怪しげな見た目に反して性格はかなり明るく、 個人的にはタフでパワフルなケヅメなどとの同棲にも向いているのではと感じているほど、 本種もまた底無しの明るい性格を武器にアクティブな動きを楽しませてくれます。 物理的、精神的ストレスにもかなりの耐性があるため、 多少蹴飛ばされたぐらいではビクともせず、 自分よりも大きなカメを押しのけて餌を横取りするシーンも散見されるなど、 配役の仕方によっては更に幅広い楽しみ方ができる素晴らしいキャラクターの持ち主です。 今回やって来たのはあまり数を見かけないノーザンフォームのアダルトサイズで、 実は同じ名前でも色彩にバリエーションが存在するのですが、 この個体は頭と足の色が違う二色刷り仕様になっている、 いわゆる昔ながらの足だけ赤いアカアシガメ。 頭に広がる明色部の面積も平均より広めで華やかに見え、 遠目で見ても実寸以上のボリュームが感じられると思います。 ゴクゴクと水が飲める状態であれば多くは望みませんので、 早速野外に放牧して縦横無尽に歩き回る勇姿を堪能しましょう。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| ありがちなトラブルがひとつも当てはまらない見事な成長ぶり! これほど典型的な特徴が出ていてなおかつ綺麗に育っているとチェリーヘッドの美しさがより一層引き立ちます、 アカアシガメ・オスが入荷しました。 リクガメという生き物の生態や飼育法などがよく分かっていなかったその昔、 全体的に茶褐色のものは大抵が安価に販売されており、 柄が入ったようなものは見た目の華やかさから高値が付けられる、 本当に単純明快な仕組みをもって取引されていたのではないかと思います。 もちろん棲息数からの稀少性というのもあったのでしょうが、 リクガメ自体がまだまだ物珍しい時代には第一印象のインパクトが何よりの決め手だったに違いありません。 本種も古くから知られていた存在ではありましたが、如何せん大きくなるらしいという情報と、 森林棲というライフスタイルがどうしても特別視されてしまう要因となり、 いまいちメジャーにはなり切れませんでした。 しかしそのくすぶっていた人気が爆発したのも数年前、 きっかけは何を隠そうこのチェリーヘッドという個体群の登場によります。 成し遂げた偉業はふたつ、頭部が赤く染まり甲羅にも模様が出ることと、 飼育下でも大きくなり過ぎないアカアシ最小クラスのサイズであることです。 さくらんぼ頭の名の通り顔中が真っ赤に発色し、最大甲長はおよそ30cmですが、 現実的には20cm台でストップし日本人が扱うことのできるリアルな数値を叩き出しました。 そのような話を聞くとまるでその小ささが全てだと勘違いしてしまわれがちですが、 恐らくは良さを知りながらも躊躇していた所に小さいから大丈夫と耳元で囁かれ、 最後に背中を押されたという些細なきっかけに過ぎなかったのでしょう。 その潜在的な人気を証明するかのように、現在ではバリエーション豊富な他の地域個体群にも注目度が高まり、 アカアシガメ全体が盛り上がりを見せているようです。 この個体はチェリーヘッドとしては普通かもしれませんが、 多くの個体が早ければ甲長10cm台で陥る頭頂部のかさ付きが殆ど見られず、 また同じようにしばしば悩まされる腹甲の痛みも全く起きていないため、 いかに適切な管理と環境で育てられたかということが分かる優秀な一匹。 前方からのカットでは上半身が盛り上がっているようにも見えますが、 横から見れば綺麗な俵型で、 甲羅全体のボコ付きも許容範囲内に収まっています。 近頃頭が赤いだけでチェリーヘッドと呼ばれるケースを目にしますが、 本当は黒地に白く霜降りが出るこのお腹が特徴。 20cmに到達する前に手放されてしまうことも少なくないため、 実際にここまで仕上がった個体は貴重です。 梅雨のじめじめしたこの時期から早速野外へ放ちのびのびと飼育しましょう。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (パステルヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| ここはあえて言わせて下さい、パステルヘッドだと。 チェリーヘッドとは何かが違う極彩色、 アカアシガメ・オスが入荷しました。 国や地域、分布している場所によって様々な形態を見せるアカアシリクガメ。 その最たる例としては、昔の図鑑では最大甲長50cmと書かれ大型種という認識が当たり前だったものが、 ブラジルの辺りに棲息する個体群はあまり大きくならないらしいと評判になり ドワーフチェリーヘッドと呼ばれるタイプが流通し始めたことなど、 一口にアカアシとは言い切れない部分が初心者からマニアまで幅広く受け入れられている理由のひとつでしょうか。 同タイプはチェリーヘッドとも名付けられ、 単に小型というだけでなくより綺麗ともなれば人気の出ない訳がなく、 本種を爆発的にメジャーにした功績は非常に大きいと言えます。 そして今回やってきたこの個体、1枚目の写真からいきなり異様な雰囲気を漂わせているのですが、 何か名前を付けねばと思いついたのが実に安直なパステルヘッド。しかしながら実物を一度目にすれば、 名前負けしているどころか一言では言い表すことのできない深みのある魅力を備えていることが分かるでしょう。 記憶を辿って先の地域変異のいずれかに当てはめようとしましたがどうしても見当がつかず、 一番近いとすればチェリーヘッドのような気もするので、 バリエーションと言うよりは一種の色彩変異なのかもしれません。 頭頂部はパームマットの汚れで少しすすけていますが、 本当に黄色と橙色が混ざったこんな色彩を持っています。 と、どうしてもインパクトの強い顔面のカラーリングばかりに視線を取られてしまいますが、 注視してみると前肢に並んだ大きな鱗を筆頭に後肢や尾にも全力の赤が発色し、 背甲のブロッチも黒地を生かしてよく映え、全身ハイカラーだということに納得できます。 成長過程の問題で甲羅のフォルムは100%とは言えませんが許容範囲内だと思います。 こんなアカアシ初めて見ました、せっかくなので年の明ける前にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| よほど順風満帆に育ったのであろう表も裏もギラギラと黒光りした甲羅が絶品のフルサイズ! お腹もべっこりと凹んでいつでも準備万端と言った具合の超即戦力です、 チェリーヘッドアカアシガメ・オスが入荷しました。 日本の飼育環境に馴染み易いとかねてより評判の高いアカアシガメ、 その昔コンスタントに輸入されていたものは頭が黄色く足の赤いそのまんまアカアシだったのですが、 近頃目にする定番のタイプと言えば頭が赤くて足も赤いゴージャスな雰囲気が持ち味です。 以前はどちらかと言えば大型種の部類に入るとされるほど体格の良いリクガメでしたが、 ブラジルなどを原産とするチェリーヘッドは従来のイメージからは想像もできないほど小型で、 それこそヘルマンやギリシャから少し背伸びをしたような感覚で扱えるため、 ビギナー層にも受け入れられ易いともっぱらの評判。 しかし図鑑で言われているような30センチには現実的に到達するものなのでしょうか。 実際には例えばチェリーヘッドを幼体から育て始めたとしても、 並大抵の労力やスキルでは成し得ないことが殆どであり、 せいぜい20センチを超えた程度の出物ばかりですから却って貴重な大型個体を望む声もしばしば。 その活発な性格からどうやら運動量などが大いに関係しているらしいのですが、 確実に大きく育てるための秘訣は未だ完全に明かされてはおらず、 どのみち年数もかかるとあってなかなかお目にかかる機会には恵まれないようです。 今回やって来たのはパッと見の迫力から30センチクラスなのではと思えるほど、 何処に出しても恥ずかしくない大変立派に仕上げられたほぼフルアダルトのオス。 何が嬉しいのかと言えばとにかくその甲羅が魅せるしっとりと艶に満ちた外観でしょう、 全身から万遍無く輝きを放つその質感はベビーの頃からよほど気を遣わなければ実現不可能なクオリティで、 しかも床材を湿らせた時にありがちな腹甲の痛みも全く無い点はかなりの好印象です。 一度でもアカアシを育てたことがある方ならこの偉業が身に染みて分かると思います、 それほどこの個体の出来栄えはお見事と言う他ありません。 先日たまたま同じ場所に居合わせたヘルマンのオスに対し、 相手を押し潰すかのような勢いで盛りまくっていました。 相方がいれば繁殖成功への近道になるでしょうし、 また見ているこちらが心配になるほど終始歩き回りますので単独でもお庭の友として最適です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 巨大なチェリーヘッドが欲しいという矛盾を孕んだわがままリクエストに応え得る奇跡の育ち盛り! 頭部全体の赤味は言うまでもなく背中の花柄も嫌味にならない程度にバランス良く描かれた上質の逸品、 チェリーヘッドのアカアシガメ・オスが入荷しました。 思えば大きくなり過ぎずかつ美しいアカアシとして華々しくデビューしたのも早十数年前、 いつしかペットトータスの選択肢として定番のキャラクターに名を連ねるようになり、 無論その奇抜さもヘルマンなどのベーシックなものが流行していてのことなのでしょうが、 いずれにしても唯一無二の存在感を放ち続けることに変わりはない優秀なリクガメのひとつ。 どちらかと言えば大きく育つことが当初の売りであったはずの南米系ですから、 それを矮小化しようという発想にはどうしても限界がありますが、 反対に場合によっては程良いのかもしれないそのボリュームを欲していた方にとっては、 またとない選択肢として見事にピタリとハマる傾向にあります。 ヒョウモンガメのようにこちらが気を遣うほどのナイーブな面はおおむね感じられず、 それでいてケヅメのように大胆極まりない破壊行動により飼い主をうんざりさせることもない、 見た目だけの印象であればもはや謎の覆面レスラーの出で立ちと相違ありませんが、 見た目に似合わずやたらと明朗な性格は飼って初めて分かる秀でたポイントで、 外見のみならず中身についても一緒に暮らしていて楽しいと高く評価されています。 今回やって来たのは一見するとメスに見えないこともない幼さを残しながら、 実寸甲長は既に二十センチ台半ばにまで到達している化け物候補のサブアダルト。 正直、尻尾の大きさと形状だけを見ればメスと判断するのが無難なところでしたが、 何となく腹甲全体が凹んでいたため違和感を覚えていた矢先、 まさかの生殖器が露出するというハプニングから晴れてオスが確定した次第です。 全体的に若々しい雰囲気が漂っていることと前述の尻尾の大きさから、 ここから更なる成長が期待できる可能性はほぼ確実と考えられ、 メスに比べオスの方が大型化し易い傾向にあることも踏まえれば、 チェリーヘッドとしては極めて稀な三十センチクラスに仕上げることも夢ではありません。 全体のフォルムはもちろんそこに施された模様の出来栄えもまた見事な、 ペットにも種親候補にもその実力を遺憾なく発揮してくれる素晴らしい掘り出し物。 こんな見た目で元気がないはずもなく、 終始辺りを走り回り餌の選り好みもなく何でもバクバク平らげる優等生です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♂) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| チェリーヘッドとしてはかなり大きな完熟個体! ヴォーヴォー雄叫びをあげて交尾しそうな即戦力です、 フルアダルトのアカアシガメ・オスが入荷しました。 南米に広く分布するアカアシガメは各国や各島により地域変異があるとされ、 少なくとも昔輸入されていた個体と今現在では丸っきり外観が違い数タイプ存在することが認知されています。 近頃よく見かけるのはブラジル産のタイプはブラジリアンドワーフやブラジリアンチェリーヘッドとも呼ばれ、 その名が指すように熟したフルーツのような赤く染まる頭部を持つ個体は 比較的小型で成長がストップする傾向にあります。 今回やってきたのは頭部はもちろん四肢と尾の粗い鱗上にも毒々しい赤が発色し、 それでいて甲長は30cmに迫るというとても大きな個体。 また甲羅はボコつきの殆どない野生個体風の理想的な仕上がりで満足度も高いです。 小型ではありませんが飼育に現実的な最終サイズであり、また黒地のリクガメというのもなかなか珍しいです。 もし大きなメスをお持ちの方はすぐにでもあててやって下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♀) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 拳二個分の安心サイズ! 甲高でかさつきもなく綺麗に育っています、 ベビーサイズより国内で飼い込まれたチェリーヘッドのアカアシガメ・メスが入荷しました。 カメのイラストを描くとミズガメの場合は緑色、リクガメの場合は茶色っぽい感じであることが多いと思います。 直観的なイメージからそのように彩られるのでしょう、 しかし本種はブラックベースにレッドスポットと実に攻撃的な色合いをしています。 そこから推察するには森林棲のこのカメがより熱吸収の効率を上げるため、 と考えれば色々と理由も出てくるのでしょうが、 もっと単純にこの警戒色のような刺激の強いカラーリングを美しい、 格好良いと素直に捉えても良いと思います。 現地では湿度の高い熱帯雨林の付近に暮らしていると考えられており、 紫外線要求量がさほど多くないため飼育環境に適応しやすく、 また雑食なことから人工飼料メインでも綺麗に成長する個体が多いようです。 図鑑で見る最大甲長はとんでもない数字ですが、 近年流通するチェリーヘッドと呼ばれるタイプは最大30cm程度と無理なく飼えるレベルで人気も高まっています。 元来丈夫なことに加え夏場の湿度が高い日本の気候にも馴染みやすく、 また奇抜な色彩も魅力的なビギナーの方にもオススメのリクガメです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ハイレッド・♀) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| いくらチェリーだとしてもやり過ぎな激しい発色を見つめるだけで頭がくらくらする赤鬼仕様! 腹甲に映える挑戦的な模様ひとつ取っても強いエナジーを感じさせる特選極美個体、 チェリーヘッドのアカアシガメ・メスが入荷しました。 リクガメと言うひとつの括りで考えればもちろん唯一無二、 そしてカメ全体を見渡してもこれほど鮮烈な赤色を呈する種類はそうお目にかかれない、 あまりにも奇抜なその色合いを武器にたったの十年間で認知度を急速に高めた新時代のリクガメ。 やはり昔ながらの種類と言えばケヅメやヒョウモン、 それにホシガメやギリシャなど私たち日本人にとっても大変馴染み深いメンバーで、 そのどれもがおおよそ黒色から茶褐色、 ないしは黄色を取り入れたカラーリングにまとめられていることが殆どですから、 赤っぽいと言ってもせいぜいオレンジぐらいが精一杯で、 露骨に赤を剥き出しにしたようなデザインを楽しむ機会はまずありませんでした。 それもそのはず、かつて市場に流通していた本種はその和名に倣い文字通りのアカアシガメ、 つまり脚部のみが赤く染まることはあっても顔面までそれと同色にはならず、 大体が黄色と赤の二色刷りでしたからこれほど強烈なインパクトは無かったはずでした。 正式にはブラジリアンドワーフチェリーヘッドと呼ばれる、 実に長ったらしい名前の地域個体群が確認されたのがおよそ十数年前、 それを機に出回るアカアシのほぼ全てがチェリーヘッド一色になり、 初めは新鮮だったその姿もすっかり見慣れたものとなってしまいましたから、 最近では同じタイプの中でもより優れた形質を持つ個体に注目が集まっているようです。 今回やって来たのは一目見て並のチェリーヘッドとは質の違いが歴然としている、 マグマが噴き出したかのように頭部全体を覆い尽くす強烈なレッドが印象的な飼い込み個体。 あえて解説の必要も無いほどクオリティの高さは折り紙付きで、 通常パンダのように両目の周りぐらいは黒くなるはずなのですが、 このように眼球を残してほぼ全てが赤くなる現象は極めて稀であり、 首の部分にまで赤が染み出しているのには流石に参りました。 しかも数の少ないメスと言う嬉しいオプション付き、何処までも魅力的な一点ものの優良株です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♀) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 完熟間近の霜降りさくらんぼ! チェリーヘッドに加えて成長線に突如現れた霜降り模様が最高に美しい個体です、 アカアシガメ・メスが入荷しました。 小型で綺麗という飼うにあたって嬉しいポイントを見事に兼ね備えた地域個体群として人気急上昇中のブラジリアンチェリーヘッド。 この産地のアカアシがいたからこそ、現在日本のリクガメ飼育事情にすっかり馴染んだ本種のポジションがあると言っても過言ではありません。 南米のアカアシ・キアシとセットで巨大なリクガメというイメージが長年に渡り浸透していて、 実際に飼っているのはマニアだけという状況を見事に打破してくれました。 とても大きなフルアダルトでもMAX30cmぐらいと無理なく飼えるレベルであり、 多湿を好む性質から日本の夏に苦労させられる事もなく、 餌も幅広い食性により配合飼料も使いやすくいいことづくめ。 そして色彩感に乏しいリクガメの仲間でこれだけ発色する種類も他にはいません。 特にこの個体は黒字の甲羅に点在するクリーム色がまるで霜降りを再現しているかのようで、 最後の最後で花開くこの美しさは飼育者を喜ばせます。 のしのしと歩く姿はサイズ以上に重厚で迫力を感じさせてくれます。 国内飼い込みでここまで大きくなっているので状態に不安はありません、オススメ! | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・♀) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 期待を裏切らない真っ赤な頭に花を添える背面の白い斑紋もまた美しい星屑のチェリーヘッド! 成長過程を見守るように店内でコツコツと育てていた繁殖にもチャレンジしていきたい若奥様、 アカアシガメ・メスが入荷しました。 リクガメらしからぬ容姿の持ち主と言われればそうなってしまうのかもしれませんが、 全てのリクガメの中でも飛び抜けて飼育し易いと言っても決して大袈裟ではないほど、 恐らく実際に育ててみた人が口を揃えてそう断言する極めて優秀なペットトータスのひとつ。 一体何が彼らを掻き立てているのか、 体の中にサンバのリズムでも流れているのかしらと疑いたくなるぐらいに、 とても陽気で社交的な性格の良さが全身から滲み出ています。 黄色と黒色の組み合わせによってデザインされた種類が大半を占める中、 誰に断りを入れることもなく突如として激しい赤味を持ち出してしまったが最後、 後には引き下がれないインパクトの強さが賛否の分かれる見た目を描き出し、 それがまた刺激的だと新たなファン層を開拓し現在に至ります。 細かいことを気にしないざっくばらんな生き様に助けられているのか、 環境に対して細かな注文をせず機敏な動きを見せたかと思えば餌食いもアグレッシブで、 全体的に生き生きという言葉がぴったりな雰囲気は見ていて飽きない、 周りの空気をも明るいものへと変えてくれるムードメーカー的なキャラクターの持ち主は、 実は万人にお勧めしたい銘種のひとつと言えるのです。 今回やって来たのはオスに比べて出物の少ない嬉しいメスが確定した、 色合いも平均以上の申し分ないクオリティを実現したまだまだ年の若いアダルトサイズ。 実はヤングサイズと呼べる頃に入店しその当時より何となくメスっぽかったことと、 カラーリングもまた優れたものに仕上がるだろうとの見込みからバックヤードにて育てていた一匹で、 時折売り場のスペースが空くと登場する準レギュラーだったのですが、 ようやく見栄えのする様子に仕上がったため正式にデビューすることと相成りました。 Mazuriリクガメフードを中心に猛烈な勢いで食べさせてきましたが、 甲羅の形状も概ね綺麗に仕上がり特段違和感は感じられず、 知らぬ間に二十センチオーバーと豊満な体格に出来上がりましたから、 良い相手が見つかれば交尾、産卵にも期待したいところです。 サイズとクオリティには見合わぬお値打ちプライスにて。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (フルアダルト・♀) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| イエロー&レッドの長期飼い込み成熟個体! 国内のマニアが手塩にかけて育て上げた立派なフルアダルトです、 お客様委託のアカアシガメ・メスが入荷しました。 南米大陸のリクガメと言えばアカアシとキアシが真っ先に思い浮かぶでしょう。 いわゆるリクガメと聞いて想像される一様に茶色い体であまり派手な印象の無い姿ではなく、 ブラックをベースに赤や黄といった警戒色とも取れる色彩は、 見る者に毒々しいイメージさえ与える奇抜なカラーリングです。 ただこれだけで人気の出そうなものですが、昔から輸入されていたのは非常に大型の個体ばかりで、 図鑑で見ても最大甲長50cmだとか70cmだとかちょっと躊躇う数字が並んでいておいそれと手を出せなかったのだとか。 しかし最近になってドワーフタイプという大きくならないアカアシが紹介され、 これはどうやら棲息地域による形質の違いらしく、 それを思えばあの大きかったアカアシ達のことも理解できるでしょう。 今回やってきた個体は10年近く飼われ続けてきたそうで、このサイズで成長は止まっているとのこと。 いわゆるチェリーヘッドではなく頭は黄色いタイプですが、 この系統でも小さく収まるものが存在するのです。 屋外飼育メインで餌や運動量に不足は無かったはずですからその点も安心。 現在では前述のチェリーヘッドが圧倒的に人気ですが、この個体も黄色部分の面積は十分広いですし、 2色使われているという点でもなかなか魅力的だと思います。 長年同タイプの相方をお探しであった方もこの機会にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (特大サイズ・ノーザンフォーム) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 磨き上げられた甲羅に顔まで写る地球の裏側より着の身着のままで来日したワイルドフルアダルト! いくらチェリーヘッドではない別のタイプとはいえ通常考えられない圧倒的なボリュームに平伏すしかない、 ノーザンフォームのアカアシガメ・メスが入荷しました。 カメにとって甲羅とは、カメがカメたる所以でありまた自らの生涯を表現するものでもあって、 楽しいことも悲しいことも、笑えることもへこんだこともみんなまとめてひとつにしたような、 彼らの生き様そのものと言っても過言ではないでしょう。 つまり私たちは目の前のカメを見る時、 その甲羅に着目することで背景に広がる幾多のドラマを感じ取ることができ、 それが人の手によって育てられたものであろうと自然によって育まれたものであろうと、 いずれにしても生かされてきた軌跡を目の当たりにできるという点では変わりません。 カメを育てている人々の価値観は言うまでもなく人それぞれなのでしょうが、 私が大切にしている考えのひとつに野生を切り取るという観念があります。 自己の所有物としての生き物が持つ意味や付加価値には、 この世界の何処かにぽつんと落ちていた生命を自らの手中に収めることで、 そこに広がっていたはずの風景をも眼前に描き出すという効果があり、 このアカアシガメの場合は乾季になると限られた食物を求め森の中を彷徨い、 雨季には大雨に降られながら泥にまみれながら大好きな果実を貪り、 天敵が少なく平和で温暖な気候の中で生き永らえるものもいれば、 今日でも密林の奥に暮らす先住民族たちの貴重な蛋白源になってしまうものまで、 彼らの辿る運命は一様ではなく、 それが命の繋がりにおいて重要な役割を果たしていることを示しているのです。 今回やって来たのは一同仰天産地直送正真正銘野外採集完熟個体。 その昔アカアシと言えばおおむね巨大なリクガメとしての印象が強く、 丸太を切り落としたような塊がドスドス歩いているような先入観さえありましたが、 昨今主流の小型個体群は商業的に大きな成功を収めたものの、 古くからのファンにとってその体格は決して十分ではなく、 最近では却って稀少になってしまった大きなアカアシを懐かしむ声も多数聞かれます。 国内で数年飼い込まれていたお陰で今ではMazuriリクガメフードを主食にしており、 飼育について面倒な癖を感じるところは一切ありません。 これを逃せば二度と巡り合うことのない素晴らしき掘り出し物を前に、 どうかこの憂いを帯びた眼差しだけでも目に焼き付けておいて下さい。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・Pr) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 一息つく暇も無いほど毎晩お盛んな、 形だけの雌雄一対ではない正真正銘のおしどり夫婦! オスの底無しのやる気とメスの懐の広さは遅かれ早かれ良い成果を結ぶことでしょう、 チェリーヘッドのアカアシガメ・ペアが入荷しました。 南アメリカにおいて最も有名なリクガメと言えばガラパゴスゾウガメに違いありませんが、 ホビーの世界で最も世に貢献したポピュラー種と言えばこのアカアシガメ以外には考えられません。 長い歴史の中で様々な表情を見せてくれた本種は、 棲息する地域によって複数のタイプに分かれることが知られており、 かつてはその名の通り足だけ赤いカメと言うイメージが強かったはずが、 いつの間にやらここ数年で頭まで赤いことが当たり前のようになってしまいました。 主にブラジルを原産とするチェリーヘッドはそういった系統の中でも特に有名であり、 時に美しく時にえげつないその見事な発色が瞬く間に人々の心を魅了し、 どちらかと言えばマニアックで風変わりなキャラクターだったマイナー種を、 誰もが認めるペットトータスの代表種へと成長させたのです。 今回やって来たのはいよいよ繁殖の二文字が現実味を帯びてきたであろう、 運命の出会いを予感させる相性の良さが前面に押し出された最高のペア。 まずは特徴の確認として腹側の色合いに注目すれば、 黒を基調としながらも黄色いマーブル模様が映えるこのデザインはチェリーヘッドであることの証。 気になる頭部の発色はメスが平均的な程度であるのに対し、 オスは目の周りまで隈なく発色したこれぞ赤鬼仕様で、 子孫にも良い形質が受け継がれそうな美血統として華々しい活躍が期待されます。 このペアはそれぞれが全く関係のない所から飼い込み個体として当店に漂着し、 実を言うとつい先日まで在庫していた同サイズのメスを加えた三頭で一ヶ月以上同居を続けていたのですが、 不思議とそちらのメスには一切目もくれずただひたすらに一途な愛を貫く、 大変に操正しいオスの姿勢に大切なことを思い知らされたような気がしました。 甲長だけを見るとまだ少し小さいようにも感じてしまいますが、 性別判定の難しい本種においてこのしっかりと長く伸びた尾は成熟していないと言えば嘘になり、 腹甲もべっこりと凹んでいてサイズの割りに完成度が高く実に頼もしいです。 マウントもただ声を上げて乗っかるだけではなく、ヘミペニスの露出と結合を目視で確認しているため、 メスの機嫌が良い時にはきちんと受容している模様。 時に二個体の性別が異なればそれを組み合わせてペアとしてご紹介することもありますが、 この二匹に関しては何が何でもバラ売り無しでお願いしたい、 繁殖成功が目前に迫る夢と希望に満ち溢れたスペシャルペアです。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ノーザンフォーム・Pr) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| よく見ると微妙に色合いや雰囲気の違った珍しいタイプのペアで目指せ国内ブリード! ひたすらチェリーヘッドばかりが蔓延る中で優しい目元が印象的な久々のノーザンフォーム、 アカアシガメ・ペアが入荷しました。 今やすっかり市民権を獲得したと言っても過言では無い、 ヘルマンやギリシャなどチチュウカイリクガメの仲間たちに食い込むように、 ビギナー向けリクガメの新たな選択肢として頭角を現し始めた南アメリカの代表種。 かつてはどちらかと言えばマニアックな位置付けにいたため、 十年以上前にも遡れば正直注目度はそれほど高くなかったものの、 当時は大型の野生個体がしばしば輸入されていたこともあり、 いくつかの異なる個体群が代わる代わる輸入されていたらしく、 今更になってきちんと系統分けされていなかったことが悔やまれます。 決して研究の進んでいる分野では無いもののざっくり四つから六つほどのタイプが存在するとされ、 その中で最も有名なチェリーヘッドは既にアカアシの代名詞として説明不要の知名度を誇りますが、 海外の書籍に目を通すとチャコ、ブラジル、コロンビアなど主に地名を用いた呼称が与えられ、 それぞれが外観に少しずつ変わった特徴を示しているのですから上手く出来ていると感心させられます。 今回やって来たのはノーザンフォームの呼び名で紹介されている、 腹甲の大部分がほぼ褐色に統一されることで簡単に見分けられるタイプのペア。 横腹のくびれはその昔ちらほら見かけた大型個体群を想起させますが、 最終サイズは前述のチェリーヘッドに毛が生えた程度だそうで、 なるほど確かに僅か20センチ少々の現時点でオスの腹甲はべっこりと凹み、 ここから倍以上にぐんぐん伸びることは考え難いと思います。 オスはお腹を見れば分かるように赤味が強く顔色も同様で、 反対にメスはすっきりとした黄色が主張し頭頂部にも同様のデザインが施されています。 チェリーヘッドとの違いは優しい目鼻立ちにあり、 黒目がしっかり黒々とした柔和な表情はなかなか捨て難いものがあるでしょう。 アカアシのオスは求愛行動が暴力的では無いことが多いため、 繁殖が第一優先では無くとも二匹一緒に仲良く暮らしている様には見応えがあり、 激レアとまでは言いませんが頻繁に巡り合えるタイプでは無いため、 単品をそれぞれ集めてのペアリングは困難を極め、 初めから相性の良さそうな雌雄をご紹介できるケースは稀です。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (チェリーヘッド・Pr) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| 店にやって来て直ぐ、油断していたら有精卵と思しきタマゴを早速産んでしまいました! もう即戦力でしょう、 お客様委託のアカアシリクガメ・ブラジリアンチェリーヘッド・ペアの入荷です。 南アメリカの湿った森林などに棲息する為、 他の定番種と言われるリクガメらとは一風変わった雰囲気を持つアカアシ。 そのせいかこの仲間ばかりを集めるマニアもいる程です。そして今回は小型個体群として知られるブラジル産で、 いわれの通り強烈な赤みが魅力的な2匹です。 葉野菜よりも果実類を好む食性のお陰かいわゆるリクガメ用の人工飼料のみで育成しても良い結果が出る事が多いそうで、 また多湿を好む為に国内飼育も比較的楽な様子です。なかなか立派なペアですがリクガメとしてはそれ程大きく無く、 また国内繁殖の例もありますので是非ともチャレンジして頂きたいです。 現在店内放し飼いで四六時中歩き回っています。 | ||||||||||
|
アカアシガメ (ガイアナ産・Pr) Geochelone carbonaria |





|
|
||||||||
| ガイアナ産ワイルドとして入荷後4年に渡って飼い込まれ、日本の気候にも大分馴染んできた様です。 お客様委託のアカアシガメ・ペアが入荷しました。 南米大陸を南北に広く分布する代表的な湿潤系リクガメ。アカアシガメと一口に言っても様々なタイプが存在し、 産地名が付いて輸入される度にあそこが違うここが違うと盛り上げてくれる種でもあります。 今回の2匹の特徴としてはその名の通り脚部の大きな鱗にエグい程の鮮明な赤が発色し、 頭部は抑えめの柿色という最近では逆に珍しい、 以前主流だったタイプです。昔はこういったものをよく見かけましたが今となってはワイルドの、 特に大型の個体は希少。特にオスは完全なる成熟を迎えているのか、 腹甲の凄まじい凹み方は一見の価値ありです。 腰の部分も若干くびれています。それに対してメスはサイズ的に少し小ぶりなのですが産卵も経験しているそうで、 近頃は別々に飼育されていた事もあってこれから一緒に暮らしていく内にブリーディングにも期待できるのではないでしょうか。 さすがはワイルドのツルツルで素晴らしいフォルムをした甲羅に、 また足取りも軽やかな状態抜群のペア、是非ご検討下さい。 | ||||||||||
|
チャコリクガメ (ベビー) Geochelone chilensis |





|
|
||||||||
| 名前はおろか容姿から動きに至るまで隙の無い可愛らしさで埋め尽くされた南米原産の稀少種! あまりにも無敵過ぎるそのコンディションに惚れ込み再び群れの中から招聘した選抜個体、 チャコリクガメが入荷しました。 しばしばケヅメリクガメのミニチュア版と例えられていたのも無理は無い、 南アメリカはグランチャコと名付けられた高温乾燥の厳しい半砂漠地帯に息衝く、 ナンベイリクガメのグループでは異端的な暮らしぶりを展開する属内最小種。 あちら方面のリクガメと言えば片手で十分に数えられるぐらいしか存在しないものの、 かの有名なアカアシとキアシは湿潤系の最たる例として認知されていますから、 収斂進化的にケヅメっぽくなってしまったチャコの思惑は極めて自然な行為であると言えるでしょう。 時にゴファーガメのようだと形容されることもあるように、 つまりは過乾燥に対して地中へ避難することにより過酷な環境に適応したものと思われ、 森の中に棲む仲間たちとは違いむやみに体を大きくすることを避けたのにも納得がいきます。 このカメが可愛いと評価されるためのパーツとして、 甲羅に対して四肢が大きくがっしりと見えることの説明は穴を掘るための一言で解決され、 他にも顔が縦に分厚く顎周りがしっかりして見えることについては、 やはり乾燥地に有りがちな多肉系の植物を主食とするためと説明することができ、 細部に宿る機能美が人の目から見てプラスに働くことの素晴らしさを改めて感じさせられました。 今回やって来たのはおよそ二か月前にこの場にて掲載した元気ハツラツベビー軍団の残党に当たる個体で、 甲羅の色抜けが強くまた綺麗な赤味が感じられる個体がひっそりとキープされていたため、 状態をチェックしながら満を持して確保したそんな一匹。 輸入された当初はそのロットの中でも小振りだったため初めは回避したのですが、 その後輸入元での適切な管理が功を奏したことは言うまでも無く、 当店に迎え入れてからも早速Mazuriリクガメフードに餌付かせ、 今では皿に盛っただけでケージの隅から駆け寄って来るほどに鍛え上げておきました。 かつて育てるのが難しいと噂されていた頃には全て初期状態が災いしていたものと考えられ、 野生ではハッチした幼体が翌々年の雨季を狙って地表に出て来ることもあるほど辛抱強いカメですから、 暫く思い焦がれていた方にとってこのヘルシーな出物を狙わない術はありません。 | ||||||||||
|
チャコリクガメ (ベビー) Geochelone chilensis |





|
|
||||||||
| 導入時には心配事が付き物ですが未だかつて味わったことの無い史上最高の初期状態がここに! バスキングスポットの有無を問わずトコトコ歩きパクパク食べる謎の活力に溢れたスペシャルベビー、 チャコリクガメが入荷しました。 我々の本音を申し上げればもう二度とケヅメみたいだなんて言われたくは無い、 確かに外観の特徴がまるで似ていないなどと強く言い切るつもりはありませんが、 そんな無粋な発言を受ければ周囲のムードが一気に盛り下がるのは容易に想像できますし、 違いを楽しむことこそがこのマイノリティな趣味の醍醐味であると考える方は少なくないと思います。 少し視点を変えて同じ乾燥地帯に息衝く逞しいリクガメとして捉えれば、 北米のゴファーガメの仲間たちにも通ずるものが感じられるでしょうか。 前肢は大きくがっしりとそれでいてやや扁平なつくりをしていて、 甲羅は過乾燥に負けない厚みを備えながらも天辺はフラットになっており、 これはつまり安定した温度や湿度を求め地中へ潜り易くすることを目的としているものと推察されます。 鼻先が短く後頭部の幅広い独特な表情もまたゴファーのそれによく似ていて、 同じ南米のアカアシやキアシのような派手さは無いものの持ち前の可愛らしさを前面に押し出し、 今後新たなペットトータスの選択肢として適度に普及してくれることを願うばかりです。 今回やって来たのは名前も見た目もチャーミングなチャコのベビー軍団、 しかしながらこのサイズにして有り得ないほどの着状態は感動すら覚えるレベルで、 これは冗談ですがアメリカやヨーロッパからのブリード個体だと言われても信じ込んでしまいそう。 その姿を目の当たりにしただけで不安と興奮が交錯する何とも微妙なポジションにいる稀少種ですから、 手に入れるのが難しいのは分かっていても気になるのはコンディション、 言い換えればそれさえクリアしていればもはや何の躊躇いも無いはずです。 グランチャコと呼ばれる過酷な乾燥地に棲んでいるのは事実ですが、 甲羅の質感などを見る限り通常の飼育では恐らく適度な湿度が求められるはずで、 ある意味他のリクガメとそう変わらない環境下で上手に育てられると考えています。 詳しい管理方法はお問い合わせの際に伝授致しますので、 まずはこの躍動感たっぷりなピチピチのベビーから受ける感動を是非とも共有しましょう。 | ||||||||||
|
チャコリクガメ (CB・S) Geochelone chilensis |




|
|
||||||||
| チャコリクガメです。ケヅメリクガメに似てますが、分類学上はガラパゴスやキアシガメに近縁だそうです。穴を掘って その中で生活するようで、大きくなるにつれて前脚はシャベルのようになってきます。飼育には若干のコツが有り、幼体か ら亜生体までは温度を高めにし、乾燥気味の床材で身体が浸かれる水入れを設置し、朝晩に軽く霧吹をすると良く、亜生体 からは幼体時より、より乾燥と温度差を好みますので、温度設定を2~3℃低くしケージ内の温度に高低差を、昼夜も温度差 を付けると良いでしょう。床材も乾燥気味で、岩陰などに隠れたがるのでシェルターと、身体が浸かれる水入れを設置する とさらにBESTです。食が細いと言われる種類ですが、当店では葉野菜にMazuriリクガメフードをまぶした物を良く食べ、 歩き回っています。野生下では最大甲長が40cmを超えるようですが、飼育下では20cmほどで止まるようです。大きくなりす ぎるゾウガメはちょっと… と思われる方にオススメです。 | ||||||||||
|
チャコリクガメ (M) Geochelone chilensis |





|
|
||||||||
| 出くわす機会の極めて稀な長期飼い込みミドルサイズ! ただでさえ流通量が少ないのに飼育下で育てられたというだけで更に貴重です、チャコリクガメが入荷しました。 南米にはケヅメに似たリクガメがいる、 そんな触れ込みとかつてはしばしば見かけたこともありそれなりの知名度はありましたが、 近頃では同地域に棲息するのはアカアシとキアシ、 それ以外に別の種類がいようがいまいがあまり気にされなくなってしまったように感じます。 確かにさほど派手な訳でもなく、特別目新しい特徴がある訳でもないのですが、 図鑑を開けば名前だけでも目にすることぐらいはできるでしょう。 某海岸物語とは全く関係ありませんがどこか可愛らしい印象を受けるこのネーミング、 由来は分布域に広がる乾燥地帯グランチャコから。 同じような暮らしを送ってきたからなのか、 焼け焦げたような茶色い甲羅に四肢を覆うゴツゴツした大型の鱗など、 確かにケヅメを連想させる共通点をいくらか垣間見ることができます。 そして穴を掘ることが得意らしいという生活史に触れると、 大きな頭や頑丈そうな前肢は自ずと北米のゴファーガメを思い起こさせます。 しかしこのカメと本当に近縁なのは実はあのガラパゴスゾウガメ、 確かに棲んでいる所が近いと言えば近いのですが意外な盲点でした。 普段ゾウガメと言えばアルダブラばかり見慣れてしまっているため、 黒色と茶色でカラーリングは違えどガラパゴスの雰囲気を楽しむことができるかもしれません。 属内最小種で順調に大きくなったとしても現実的には30cm前後、 ないしはそれをやや上回る程度でしょうか、家庭内での飼育にも無理がありません。 ベビーにすら出会うチャンスも珍しくなってしまった今、 ある程度の大きさから飼い始めることができるというのは本当に有難いです。 背甲後縁部がめくれ上がったようになっていますが、 歩行に問題はなくいたって健康体、 何より状態の良い個体が少ないのでそういう意味では貴重な存在と言えるでしょう。 現状ではメスっぽいので、 もしこのままなら繁殖にも活躍してくれそうです。 幼い頃には分かりにくかった迫力の風貌がようやく理解できるようになってきたこのサイズ、 一応B品扱いのため特価にて! | ||||||||||
|
チャコリクガメ (Pr) Geochelone chilensis |





|
|
||||||||
|
綺麗に育っている飼い込み安心サイズでしかもペア揃ってます!
南米の稀少種、チャコリクガメ・ペアが入荷しました。
その昔は比較的多く流通していたそうですが現地の個体数減少からCITES入りした途端、
急激に流通量が減りしばしば見かけたワイルドの大型個体も姿を消してしまい、
現在では原産国などで繁殖された幼体が輸入され細々と見かける程度になってしまいました。
南米のリクガメと言えばアカアシとキアシが有名で現在ではチャコは知名度すらあまり高くないような気がします。
よくケヅメリクガメに似ていると言われますが
色合いと前肢の粗く発達した鱗がそう見せるのでしょう。
ですが分類学上ではガラパゴスゾウガメに近縁とされ、
確かに顔つきなどはそれを連想とさせる特徴を持っています。
また北米に棲息するゴファーガメの仲間のように長い巣穴を掘ることも明らかになっていて、
発達した前肢を見ればそれも容易に頷けます。
乾燥地を中心に棲息すると言われていますが前述の穴掘り行為はその乾燥を避けるためのものであるとも言われているので、
乾燥を意識するよりも湿り過ぎないことに気を配る方がより適した飼育環境を実現できるかもしれません。
昔のように大型個体の輸入はほぼ皆無ですから、
繁殖を目指す方はこの貴重なオスとメスを飼い込み育て上げて下さい。
特によく見かけるベビーサイズでは乾燥に弱かったりと気を使う面もありますが今回はボコつきも殆どなく成長した個体です、オススメ!
オス: 背甲 ・腹甲 メス: 背甲 ・腹甲 | ||||||||||
|
キアシガメ (ベビー) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| その眩い輝きは足元だけに留まらず全身を黄色という黄色で埋め尽くすリクガメ界屈指の美麗種! 数年に一度しか巡り会えない稀有な存在であるが故に健康なベビーの出物は絶対に見逃せない、 キアシガメが入荷しました。 最もシンプルで耳馴染みの良いネーミングを持つリクガメのひとつ、キアシガメ。 彼の盟友として見事に対になっているのが皆さんご存知同じく南米のアカアシガメで、 なるほど確かに全体の配色はおおむね似通ってはいるものの、 最終サイズが異なるという点でキャラクターが被ってしまうのを防いでいます。 ものの本によれば最大甲長は60センチだとか80センチだとか凄まじい数字が目に留まり、 何でも世界で三番目に巨大なリクガメとしてカウントされているらしく、 つまりその上にはもうゾウガメぐらいしか残っていないことになりますから、 とても通常のペットとしては考えられないようなスペックになってしまいます。 しかしながら現実には30センチを超えた出物に遭遇できれば幸せといった具合で、 言い方を換えれば本当に大きく育てられるかどうかというチャレンジこそが、 このカメと暮らしていく中で味わえる最高の喜びなのかもしれません。 誰かが嘘を言っていると考えるのは不自然で、 アカアシにも棲息地域によって色柄のみならず体格にもバリエーションが見られますから、 もしかしたらこちらキアシにもロカリティによってサイズ差が生じる可能性も考えられますが、 まずは何も考えずにひたすら綺麗に育て上げることだけに集中し課題に取り組みたいものです。 今回やって来たのはまるでアカアシと同じような最高に可愛らしいベビーサイズで、 相方のアカアシよりもずっと黒目のみずみずしさが愛くるしい顔立ちが印象的です。 その昔キアシの方が神経質で育てるのが難しいといった噂が流れていた時代もありましたが、 結局は初期状態の良し悪しが全てを左右するようなところがあって、 このように華麗なスタートダッシュを切れている個体を手にしてしまえば、 酷く苦労させられるような場面に遭遇することもないでしょう。 既にMazuriリクガメフードを呑気にたらふく平らげており、 甲羅の湿り気にさえ留意すればほぼ自動的に理想的な成長が見込めると思います。 最後になりますがこのカメを稀少性なくして語ることはできず、 多くのファンにとって憧れの存在であったことは間違いありませんから、 こうして現物が目の前で歩いている時にこそ真剣にご検討下さい。 | ||||||||||
|
キアシガメ (国内CBベビー) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| 南米を代表するリクガメのひとつですがここ数年はほとんど姿を見かけなくなりました。 しかしそんな中で国内のマニアが繁殖に成功しているブリード個体がやってきました、キアシガメの入荷です。 アカアシ・キアシとセットで取り上げられる事も多い南アメリカに棲息する森林棲のリクガメ。 他種とは明らかに違う黒地に暖色の斑が入る色柄や、 湿潤系らしくウルウルとした愛らしい目つきがコアなマニアを生み出す程の隠れた人気種です。 アカアシは最近になってチェリーヘッドなどのタイプが輸入され注目を浴びていますが、 一方のキアシは全くと言っていいほど輸入されなくなり陰を潜めています。 ずっと大柄な体格に憧れていた方もいるのではないでしょうか、 しかもこんなに可愛らしいサイズから飼育できるチャンスはなかなか無いでしょう。 小さな頃は全体的に黄色味を帯びた体色ですが、 次第にお馴染みの姿へと変貌していきます。 しかもこの2匹はなかなかのクオリティで、 前肢にも 後肢にもド派手なスポットが早くも表れています。 食性は幅広くいわゆる普通のリクガメとはやや異なり、リクガメフードは勿論、 雑食性トカゲ用のリザードフードや鯉餌などで動物性のタンパク質を与える事も重要です。 実際に当店ではリザードフードを与え結構な評判ですし、 またこのサイズから鯉餌のみで育てられた例もあるそうです。 湿度を保つことも大切で成長具合など見た目の問題だけでなく状態にも関わってくる様です。 ハッチリングがかなり大きいのでこれでも少し育った位ですが、 撮影時も常に歩きまわるわんぱくな2匹ですので今後の成長も一層楽しみです。 | ||||||||||
|
キアシガメ (S) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| 直視するのも憚られるほどに燦然と輝く色彩はもはやイエローを超越したゴールデントータス! 少々思う所があり店頭にて暫く育ててみましたが作戦通り良好な成長過程を辿っています、 キアシガメが入荷しました。 リクガメと言うジャンルは独立したいかにも大きなカテゴリであるかのように感じられますが、 実際にはカメ全体のほんの一部を総称しただけの小さなグループに過ぎず、 かつほぼ全ての種類が絶滅に瀕している都合上ペットとして付き合えるのはほんの僅かです。 定番種と言えば五本の指に数えられるぐらいですが、 一方で南米の仲間たちは強い個性を持ちながら普通に飼うことのできる貴重な存在であり、 種数にこそ恵まれていませんがアカアシガメなどはこの頃特に注目が高まっているでしょう。 その相方として昔から親しまれているのがご存知キアシガメ、 野生では恐ろしく巨大化するらしいスペックにより一般的には避けられ易い傾向にあるものの、 最近では数十センチのリクガメを飼育することに対する抵抗感が薄れてきたのか、 例えばケヅメやムツアシ、果てはゾウガメなどと同じ括りで捉えられるようになり、 コンスタントに見かけられない稀少種であるだけに時折リクエストを頂くことも多くなりました。 別段繊細だとか神経質な性格の持ち主と言う訳では無く、 きちんと大きくなった個体であれば複数間での同居も難なくこなせるため、 ある程度のスペースがあれば群れに彩りを加えるキャラクターとしても活躍できるでしょう。 今回ご紹介するのは初見から非常に強い黄色味が目を惹く極上個体で、 頭部などはどちらかと言えばオレンジ色に見える大変結構なクオリティなのですが、 入荷当初は小振りでひ弱なように感じられたため勝手ながら成長の軌道へと乗せてみました。 アカアシに比べナイーブで扱いが難しいイメージがあるかもしれませんが、 よく走りよく食べよく出す単純明快な暮らしぶりにそんな心配は無用となり、 今のところ甲羅や皮膚がカサついたり形が悪くなるようなことも無く上手に育てられそうです。 しばしば動物質の必要性について議論されるタイプのカメですが、 ひとまず毎日普通に葉野菜やフードを与えていれば問題無いと思われ、 また加湿の方法については手段を誤ると却って汚くなってしまうケースもあり、 この機会にずっとツヤツヤのまま綺麗に育てる方法を色々と考えてみましたので、 宜しければお渡しの際にでもお伝え致します。 最大サイズについてはとりあえず30センチを超えた辺りから悩み始めても遅くはありません、 見た目良し動き良しの飼って面白い銘種です。 | ||||||||||
|
キアシガメ (S) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| 放たれた黄金の輝きはもはや足が黄色いどころの騒ぎではない大変に飼育欲をそそられる極上品! ひょっとすると今年一番のサプライズにもなり得る前代未聞のハイクオリティ、 キアシガメが入荷しました。 今となってはギリシャやケヅメ、 ホシガメなどに次ぐ高い知名度を誇るのではないかと思われるアカアシガメ、 南米に棲息するちょっと奇抜な配色のリクガメであることは皆さんご存知の通りですが、 それとはまるで相方のように認知されている近似種キアシガメについても、 とりあえず名前ぐらいなら知っていると言う方も少なくないでしょう。 両種とも大型種の変化球的なポジションにいた昔から馴染みのある存在で、 アカアシについては近年小型個体群であるチェリーヘッドが紹介されるや否や、 それこそ爆発的な人気を獲得するに至った訳ですが、 こちらキアシはかねてよりのファンが根強く残ってはいるものの、 流通がグッと減ってしまった現在では実物を拝む機会にもなかなか恵まれず、 ある時パタリと姿を消してしまいやしないかとハラハラさせられるほど。 赤や黄色、オレンジなどの暖色が複雑に入り混じるアカアシとは異なり、 おおよそ黄色一色に統一されていることの多い本種は一見華が無さそうにも思えますが、 成熟した個体のとろりとした柔らかなはちみつ色には深みのある上品さを味わうことができ、 それは即ち綺麗に育て上げることができた人だけが楽しめる特権なのです。 今回やって来たのはずっと待ち望んでいた方にとっては念願の、 僅かながら現地より輸入された素敵過ぎるベビーたち。 ファーストコンタクトで誰しもが普通では無いと気付かされる鮮やかな発色は一見の価値あり、 大きくなれば当然の如く全身真っ黄色に包み込まれること請け合いの極美個体が揃いました。 通常はアカアシと同様に各甲板の中心部をぼんやりとした明色部が飾り、 成長線はいきなり暗色に伸びることがスタンダードなはずなのですが、 表も裏も何処から覗いても激しいカラーリングが盛り沢山で、 茶色でも褐色でも無く正真正銘黄色のリクガメへと仕上げることも夢ではありません。 本種には何故か線の細いイメージが付き纏うようですが、 到着初日からリクガメフードをがっつく貪欲ぶりに繊細な様子は見受けられず、 大変明るい性格を武器にケージ内を所狭しと走り回る日々を送っています。 上手に育てるコツもいくつかご用意していますので詳しくはお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
キアシガメ (S) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| この上ないグッドサイズ! 何はともあれこの大きさから飼い始めることができるのは有難いです、キアシガメが入荷しました。 世界には各地に色々な種類のリクガメが棲息していますが、南米と言えばずばりアカアシとキアシ。 この2種は名前もそうですが姿形が似ていることもありセットで捉えられる機会が多いですが、 今現在日本で普通に見られるアカアシとは違い、 キアシは昔に比べて流通量が極端に減りちょっとしたレア種のような扱いになってしまいました。 当店でも過去に取り扱ったことは殆どなく、大きさが大きさなのですごく人気というわけではないにしろ、 やはり隠れたファンは確実にいるようでお問い合わせを頂くこともしばしば。 ワイルド個体の輸入がパッタリ止まった所に国内繁殖成功という大変嬉しいニュースがあり、 近頃はCB個体が販売されることもありますが、 本種のベビーは乾燥に弱いというイメージがどうしても離れません。 しかし今回やってきたこの一匹のキアシ、 ケロッとした顔で写真に写っていますがまさにその通り、 何事もなかったかのように二ケタ甲長まで育っており、 湿潤系の種類に時折見られる甲羅表面の乾燥ないしは腐食のような跡は一切ありません。 特にお腹側が痛んでしまうケースが多い中この健康的な照り具合はポイント高し。 今までそのような理由でこの辺りの仲間を敬遠していた、飼い方がいまいち掴めず手を出せないでいた、 そんな方にも受け入れてもらえると思います。前述の通り入荷の機会は殆どありませんのでお早めに。 | ||||||||||
|
キアシガメ (S) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| その奇抜な配色も然ることながら早くも理想的なシルエットを描き出した育て主の腕が光る絶品! 漠然と飼育が難しいのではと考えられている幼年期から脱却した育ちぶりも見事な安心サイズ、 キアシガメが入荷しました。 リクガメの仲間はオーストラリアを除けば主要な大陸の殆どに分布していて、 私たちにとっては残念ながらそれらは決して馴染みのある生き物ではありませんが、 却ってそこに生ずるエキゾチシズムが様々な欲求を掻き立てる大変に罪深い存在です。 往年の銘種として知られるのはケヅメやヒョウモンなどのアフリカ代表に始まり、 その煌びやかな容姿が目を惹くホシガメ、 そして最近ではその育て易さにも注目が集まっているヘルマンやギリシャなど、 どちらかと言えば俗に旧大陸と呼ばれるエリアに群がっているようですが、 新大陸は南アメリカに暮らすアカアシとキアシはその面白いカラーリングから知名度は高く、 しかしながらこれまでペットとしての密な関係はあまり育まれてこなかったのかもしれません。 目鼻立ちは一般的なリクガメと比べて妙に可愛らしく、 湿潤系という生活様式もあくまで先入観ではありますがやや難解そうなイメージで、 そして何よりかつて流通の大半を占めていた大型の野生個体がハードルをグンと上げてしまっていたこともあり、 とても万人受けする分かり易いキャラクターとは言い難い面がありました。 ところが最近ではより見かける機会の多いアカアシが幼体で見かけるようになり、 飼育者層の拡大に努め実際にファンもじわじわと増えてきたことから、 相方のキアシについても人々の興味や注目が相乗効果によって集まるようになったのだと思います。 今回やって来たのは教科書に載せたくなるようなパーフェクトな成長過程を辿っている、 標準的な外観を持つことがこれほど有難いことなのかと改めて考えさせられる素晴らしい飼い込み個体。 個体差やクオリティの違いはあれど色味によって期待を裏切られるケースは稀ですが、 正直甲羅のフォルムが何となく変形し易いような気がする本種において、 表面にボコ付きがなく肩の張りもなければ腰回りの妙なくびれもない、 俗に俵型と称される天辺が平らで地面と平行になったサイドビューは、 多くのキアシキーパーが辛酸を舐めた重要課題のひとつと言えるでしょう。 大半の人がぼんやりと想像しているほど過剰な湿度は必要とせず、 呑気にMazuriリクガメフードを爆食していますので扱い辛さはありません。 放出されるケースの少ない種類ですからこのチャンスをお見逃しなく。 | ||||||||||
|
キアシガメ (M) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| リクガメ界のキレンジャーも今やレア種の仲間入り! ツルンとこんもり綺麗に育った納得の安心サイズ、キアシガメが入荷しました。 アジアに住む我々日本人にとってカメと言えば水の中を泳ぐもので、 それは地面を歩き回る草食のカメがそもそも存在していないため心に根付いたものがそのようにイメージさせるからでしょう。 しかし世界中を見渡してみれば南北アメリカ大陸、中東およびヨーロッパ、そしてアフリカ大陸に至るまで、 殆どの地域にリクガメと呼ばれる仲間が棲息していることが分かります。 つまり長きに渡って生き残り繁栄したグループと言うことができ、 その生態をひも解いてみればエリア毎に様々な特徴を見つけることができます。 本種はアカアシガメと並ぶ南米を代表するリクガメのひとつで、 それらが似ているということは名前や棲息域からも容易に想像することができますが、 近年の新しい分類ではダーウィンの進化論で知られるガラパゴスゾウガメにも近縁であることが明らかになっています。 そんな話を聞いた後だとキアシの顔がゾウガメと似ているように見えてくるかもしれません。 かつては兄弟分のアカアシと共に大型種の一員として名を馳せていましたが、 リクガメ全体で小型種人気の傾向が強くなり、 アカアシさえもドワーフ系統と呼ばれる小型個体群が一世を風靡したりと、 どことなく行き場を失ってしまったこの類のカメは流通することすら殆ど無くなってしまいました。 わがままなことにいなくなると同時に探し始められるものですが、 幸いにしてキアシはまさかの国内繁殖が成功していることから最悪の事態だけは免れています。 今回やって来たのはそんなベビーから育ったものと思われるしっかりしたサイズの一匹ですが、 そこそこの図体にしてどこかあどけなくまだまだやんちゃな雰囲気が残るのは流石。 全身イエローのポップなカラーリングはやはり特徴的で、 特に四肢の鱗に着色されたスポットがチャームポイントです。 甲羅の継ぎ目が白くなる、腹甲がガサガサに乾いたようになってしまう、 同じく頭頂部も乾いて剥げたようになってしまう、 アカアシやキアシではこのような苦い経験をされた方も少なくないと思いますが、 しっかりポイントが守られていたのかこの個体はほぼノントラブルという大変な優秀ぶり。 今後もよく歩きよく食べる環境を整えてあげましょう、 温浴をすると嬉しそうに首を伸ばしウルウルした瞳でこちらを見つめる可愛いやつです。 | ||||||||||
|
キアシガメ (M) Geochelone denticulata |





|
|
||||||||
| 鼈甲細工の透明感をそのままに甲羅表面のクリア層がしっとりとした輝きを放つ名品! うるおいたっぷりの美肌美フォルムが大切に育てられてきたことを証明しています、 キアシガメが入荷しました。 南アメリカ大陸におけるリクガメの大将と言えばこのキアシ、 西側に浮かぶガラパゴス諸島には更なる強敵のゾウガメが暮らしているのですが、 それを尻目に同大陸の北半分をのさばるようにして分布域を広げた指折りの大型種です。 文献によるとその最大甲長はなんと82センチ、 これはブラジルの動物園で飼育されている個体を計測したもので信憑性の高い数値とは言え、 大きな丸太棒がのしのしと歩いている光景は容易に想像し難いものがあります。 しかし旅先で訪れたハワイの動物園に展示されているカメを見て、 ゾウガメかと思ったらあれは確かにキアシだったという実話もあるぐらいですから、 やはり伝説などではなく本当に存在するものなのでしょう。 お仲間のアカアシガメには色彩や成熟する大きさなどに地域性が見られることが分かっていますが、 どうやら本種にはそのような研究結果が発表されていないようです。 同ロカリティ内でもサイズにバラつきがあるとすればそれは単に個体差として片付けられるか、 もしかすると棲息密度が関係しているのかもしれません。 密度が高い場合、 個体同士の出会いのチャンスが増えるため繁殖にエネルギーを注ぐようになるのですが、 反対に低い場合はただひたすら成長することを考えるようになると言われています。 だとすれば飼育下で独り暮らしを続けていればずんずん大きくなるのかといえばそうでもなさそうで、 現地では長年の過剰な採集により50センチを超える個体は稀であると言われていますから、 自然で育たないものが人の手によって育てられるものなのか気長に挑戦するも良し、 ある程度の大きさから鈍化することを見越して飼ってみるも良し、 単純な数字に臆することなく実物のカメと向き合っていきたいものです。 今回やって来たのは手の平に乗る頃から飼い込まれているミドルサイズの個体で、 とにかくその仕上がりの良さに注目したい上質の一匹。 逆にありがちなのは背中の各甲板が盛り上がるないしは凹む、 お腹全体にみずみずしさがなくかさつきによるダメージを受けている、 同じく頭頂部の鱗が白く粉を吹いたようになる、 甲羅の肩辺りが張り出したように横へ膨張するなど様々な状態が挙げられますが、 それらがひとつも当てはまらないこのクオリティはお見事。 地面を土にして乾燥防止のため頻繁に水を撒いていたそうですが、 お陰で床が相当硬くなったのでしょう、 爪が伸び過ぎるはずもなくよく鍛えられたのか非常に健脚な様子が伺えます。 森のリクガメは一般的にあまり人気がないと言われてしまいますが、 アカアシとキアシはその美しさは言うまでもなくアグレッシブな性格も愛好家から好評なので、 これからもっと普及していくことを願っています。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (べビー) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| シーズンイン!ピンポンサイズより少し育った元気な個体ばかりです。リクガメ人気不動のNo.1、 インドホシガメ・ベビーの入荷です。昔からコンスタントに輸入され、その鮮やかな柄から人気は高く 国内繁殖の成功例もあります。輸送状態が悪く小さなサイズから育てあげる事は至難の業とされていましたが、 最近では初期状態も改善され普通に育て上げるのも容易になってきたようです。今回はより活発で、 かなり色味の濃いオレンジ個体ばかりをセレクトしました。 写真を撮ろうとしてもどんどん歩いてしまい、 撮影待機中の容器でもこの活発さです。 ちょっと口元が餌で汚れているのもご愛敬、 健康に餌を食べている証拠です。 油断は禁物ですがきちんと飼えば素直に育ってくれる事でしょう。 既に葉野菜は勿論、Mazuriリクガメフードに餌付いているのも嬉しいです。 ホシガメが大好きな高温多湿のこの季節は飼育開始にピッタリです。リクガメ飼育が初めての方には喜んでご指導致します。 | ||||||||||
|
インドホシガメ
Geochelone elegans |




|
|
||||||||
| リクガメ人気No.1がやってきました。ピンポンサイズからやや育った、煌びやかなホシガメです。 このサイズだとケージ隅で脅えてしまう場合もよくありますが、この2個体はせわしく歩き回り、 かつ葉野菜やMazuriリクガメフードをこよなく愛する優良個体です。 背甲のラインの出方も美しく、飼い込み大きくするのが楽しみです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ベビー) Geochelone elegans |




|
|
||||||||
| 人気No.1のインドホシガメのベビーが再入荷しました。半年ぐらい育ち成長線も出ている安心サイズです。インドホシの イメージとして殆ど寝ていたり大人しかったりする印象が有りますが、この個体達は良く動き回り、ケヅメの血が入って いるのではないかと疑いたくなるほどです。餌は葉野菜とMazuriリクガメフードを交互に与えており、寝ていたとしても 起き出し突進してきます。ぜひ、この素晴らしい個体達をを綺麗なドーム型に育て上げてみてください。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (メニー・ボールド) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| ホシガメなるたったひとつの種類が秘める無限の可能性を最大限に引き出した超選抜! 数百匹に一匹の割合でしか出現しないメニーラインとボールドラインの真骨頂がここに集結、 インドホシガメが入荷しました。 決してカメに詳しくなくともその姿を見れば名前だけなら答えられる方も多い、 これぞまさしくリクガメの顔と言うべき昔ながらの最人気種にして最美種。 ホシガメと言うフレーズに目を輝かせる人とそうでない人に分かれてしまうのは、 かつて本種が悪名高き初心者キラーとされていたためですが、 この数年で日本への着状態が格段に向上すると共に、 飼育のいろはがしっかりと世間に浸透し始めたことも手伝って、 こちら側が勝手に敷居を上げなければ随分と接し易い存在に生まれ変わったのではないでしょうか。 当店でも昨年までは選りすぐりの個体を抜群のコンディションでご紹介し、 ビギナーさんのデビュートータスとしても果敢に採用して頂いた経緯がありますが、 今年に入ってからは新たな入荷が絶望的な状態へと陥ってしまい、 これまで当たり前のように見かけられた幼体に全国的な品薄が続いていました。 確かに昨年辺りから嫌な予感はしていたのですが、 少々値が上がるのはまだ良いとして本当に姿を消されては元も子もありませんので、 やはり今後も一匹一匹に対する意識の向上に努めなければと痛感させられる次第です。 今回やって来たのは事実上今年初となるまとまって輸入された中から、 我ながらえげつないセレクトをしてしまったと半ば後悔している凄まじい二匹。 人は刺激が強くなればなるほどそれに慣れてしまうもので、 こんな大変なものを見せられてはもう普通の生活に戻れない、 そんな不安さえ煽るほどのハイクオリティに良い意味で将来が心配になるほど。 メニーラインとした方は細めの線が無数に走る珍しい模様で、 初生甲板にぼんやりと浮かび上がる赤味もこの先の成長線上での暴れっぷりを期待させ、 一センチ毎に更なる強烈な変貌を遂げて行くのではないでしょうか。 そしてもう一方は個人的にマッチョタイプと呼んでいる極太のラインがガツンと引かれたデザインで、 同じく体中の赤味も強く否応無しに綺麗なホシガメへ仕上がること請け合いです。 たった五センチ程度のサイズにしては甲羅の硬さや四肢の肉付き、 歩くスピードから餌への執着心まで細部にまで妥協の無い所が嬉しい、 見た目も中身も素晴らし過ぎる一級品をどうぞ。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイカラー) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
|
店内でひと月以上ストックしている色良し模様良し状態良しと三拍子揃った有望株が集結!
各々カラーパターンが異なりますがどれを手に取るか迷ってしまうスーパーセレクト集団、
インドホシガメが入荷しました。
その姿を一目見ただけで誰にでも良さや魅力が分かってしまう、
リクガメの顔として歴史にその名を残す永久不滅の人気種ホシガメ。
こんもりと盛り上がる可愛らしいシルエットに描かれた文字通り星形の放射模様が甲羅全体を彩り、
最大サイズも手頃とあってペットとしてこれほど最適な種類もなかなか見当たらないでしょう。
かつては輸入状態の悪さから初めての人は絶対に手を出してはいけない、
あたかも危険な存在として認識されていた時代も長かったのですが、
最近では稀少性の高まりと共に取引額をじわじわと上げており、
その分が個体のクオリティにも反映されたのか実際に育て易くなっているのも事実。
昨年から嫌な予感がしていたのですが今年に入りそれが本格化し、
この四匹が輸入された便も実に久しぶりで数も少なかったようですが、
大部分が状態を崩すことなく到着しており選ぶのにもさほど苦労を要しませんでした。
今後は国内CB化が強く望まれますが供給量には限界がありますので、
手に入る内にとつい気持ちが急いてしまうのも無理はありません。
今回やって来たのは群れの中でも特に色合いの優れた個体から、
入荷時の初期状態が良好なのはもちろんのこと更に店頭で飼育を続けていたプチ飼い込み個体。
ラインの太さに拘りたい方、
或いはラインの本数に夢を追い求める方、
はたまた | ||||||||||
|
インドホシガメ (セレクション) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 餌食いをチェックする一次選考をパスした上でスター性を見極める二次選考をもクリアした精鋭たち! ただのホシガメでは満足できない方へお贈りする当店自慢の個性派揃いです、インドホシガメが入荷しました。 世間が認める不動のリクガメ人気ナンバーワンであり、 誰もが頷く国民的美種と言えば一片の迷いも無しにこのホシガメが堂々と名乗りを上げることでしょう。 世界中のどんな高級種にも引けを取らないそのゴージャスな身なりとは裏腹に、 昔から流通に恵まれる庶民派という意外な一面が生じさせるギャップが、 本種に対する高い好感度を恒久的に約束していると言っても過言ではありません。 唯一の欠点があるとすれば、名前を聞いただけで飼育難度の高さが連想されてしまうことでしょうか。 しかし最近ではそのような時代も終焉を迎えつつあり、良好な輸送状態で到着した数多くの個体の中から、 初期状態に注目してきちんと選び抜かれたものであれば、 野生本来の逞しさを残したまま飼育をスタートすることが可能なのです。 もちろんピンポンと呼ばれる些細なミスが命取りになりかねないサイズは除きますが、 我々がショップとして推薦できるコンディションであれば初めてのリクガメとしても十分に楽しんで頂くことができます。 よく歩きよく食べるのはもはや当たり前、 そんな最低基準だけで引っ張ってきてもあまり面白味がありませんから、 今回は個人的な趣味を思いっ切り詰め込んだスペシャルセレクションをご紹介します。 まずは目の前で普通に餌を食べる所を直に確認した上で、 群れの中にも埋もれることなく光る何かを持った目を惹く個体を一匹ずつ選出しました。 本数の少ない太バンドに同種とは思えぬ雰囲気が漂う個体、 ある意味通好みのビルマホシガメにそっくりな色合いと質感を持つ個体、 そして皆さんお探しのド派手なメニーバンドはイエロー系と オレンジ系の二匹を揃えてみました。 もちろん皆さんにお渡しするためのはずが、段々自分のためのようにのめり込んでしまうのが悪い癖で、 後から気が付いたのですが前者の珍タイプはいずれもオスっぽく、後者のバンドが多いタイプはメスっぽく、 絶対とは言い切れませんがかなり確証に近い手応えを感じています。 この時期はまだまだ飼育をスタートするのに無理のないタイミングですので、 本格的に寒くなる前にお迎えしておきたいとお考えの方も少なくないと思います。 今の所基本的には葉野菜を中心に給餌していますが、 それを食べ尽くした後におかわり分としてMazuriリクガメフードを平らげるという貪欲ぶりには驚きました。 何処に出しても恥ずかしくないお気に入りの一匹をこの中から見つけてあげて下さい。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (極太バンド) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 極太ビッグバン! えげつなさ全開の星型模様が生み出す最上のクオリティに驚きを隠せません、インドホシガメが入荷しました。 世界中に棲息するリクガメの中で、一部の特権階級だけが持つことを許された甲羅を彩るこのような柄。 ホウシャガメやクモノスガメなど他に挙げればいくつか出てきますが、 その殆どが入手困難もしくは飼育が禁じられているなど、残念ながらあまり身近に感じることはできないでしょう。 その中で我々がペットとしてまともに触れ合うことのできる唯一の存在と言っても良いのが、このホシガメです。 古くから他の大勢を牽引するかのように先頭に立ち続けてきただけあり、 現在でも変わらず不動の人気を誇るリクガメ界のリーダー的存在。 近頃ではチチュウカイリクガメの台頭により首位の座も危ぶまれましたが、 初心者にとっては難しいらしいというハンディキャップを跳ね除けてなお、 その美しさを裏付けるかの如く堂々と大切なポジションを保守してきました。 皆の人気者であるが故に当然ホシガメの飼育者は多く、 また個体差により生み出される幅広いバリエーションが無限の可能性を秘めているため、 ただ飼うだけでは済まされない、 平均点から一歩でも二歩でも抜きん出た何かを求めるのは全くもって自然な行為です。 この個体を見る前にもう一度、普通のホシガメがどんな姿をしていたのかを明確に思い出して下さい。 ガツンと力強く引かれたラインは一本一本が壮大なエネルギーを内包し、 そこに表現される世界観はまさに星の誕生を幾度となく繰り返す宇宙そのもの。 そのダイナミックな全体像がまるっきり別種の様相を作り上げていると言っても過言ではありません。 大胆なベタ塗りは見ていて気持ちの良いほどですが、これではまるでお遊びで作られたフィギュアのようです。 甲高のフォルムも未だ安心サイズの現時点で完成度の高さを予感させ、 比較的明るい性格のため撮影時に物怖じする様子もありませんでした。 甲羅もすっかり硬く仕上がり歩みも逞しいコンディションの良さですから、 ホシガメだからと必要以上に気張ることはせず素直に受け止めることができるでしょう。 細部を注視すると左第4肋甲板が小さくなっていますが、 お隣の第3肋甲板がうまくカバーしてくれたお陰で大事には至りませんでした。 もはや将来有望という問題ではありません、ホシガメ好きを自負する方にお届けしたい渾身の一匹です。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (セレクション) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 願わくば恒例にしていきたいこの企画、群がる数十匹の中から拾い上げたスペシャルセレクション! 一刻も早くこの場でご紹介したい気持ちを抑えに抑えて一ヶ月我慢した安心のストック個体、 インドホシガメが入荷しました。 最近では勇気を出して初めての、 そうでなくとも二番目のリクガメにインドを選んで頂く機会が少しずつ増えてきました。 私がカメの勉強を始めたばかりの頃、 最も苦手な種類がこのホシガメであったことは今でも鮮明に覚えています。 お店に到着するや否やお湯に浸け込み、浮かれ気分でケージに入れてもその後ピクリとも動かず、 暫くして忘れた頃に再び見に行くと全員が隅の方でおしくらまんじゅう状態、 見た目はこの上なく派手なのに何と地味な性格なのだろうと何度がっかりさせられたでしょうか。 当時はとにかく掴み所の無いヤツでしたから人に勧めようにも勧められず、 正直あまり良い思い出はありませんでしたが、最近では徐々に稀少性が高まってきたことが功を奏し、 初めの個体選びさえ間違えなければ当たりを引くこともそう難しくは無く、 望めばダッシュ力に優れた健康優良児を見抜くことさえ可能な時代を迎えています。 何故これほど前評判が芳しくないカメがビギナー層に受け入れられ始めているのでしょう、 それはきっと水槽の前に立つだけで元気を分けてもらえそうなほど朗らかな彼らの姿に、 まさか飼育の難しい種類だなんて信じられないと感じ始めたからだと思います。 少なくとも現在面倒を見ているホシガメたちは目が合った途端、 こちらに駆け寄って来ては指を出すとガラス越しに食べようとするほどアグレッシブで、 それは初心者向けと言われる種類の行動と何ら変わりはないのです。 今回は八月上旬から今日まで丹精込めて鍛え上げてきた、 個人的には何処に出しても恥ずかしくないと思っている三銃士をご紹介します。 ご覧頂ければお分かりの通りここに集うのは只者では無い美個体ばかりで、 黄色が濃い太バンドの正統派から、 赤味が強く細いバンドが無数に入りそうなタイプ、 そしてマイブームの極太バンドが少なめに入るマッチョタイプまで、 アクの強い一点ものばかりが贅沢にも勢揃いしています。 あえて言う必要もありませんが今では一番好きなリクガメとなったインドホシガメ、 せっかくの豊富なバリエーションを生かして思う存分楽しみましょう。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (セレクション) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 個体差のデパートが魅せる数々のバリエーションから尖った三匹を満面の笑みでチョイス! それなりに群れていたとしても条件反射的にセレクトしてしまう面白さの、 インドホシガメが入荷しました。 かつてはペットとして一般家庭で飼われるべきでは無いと強く反対されていたリクガメも、 昨今目覚ましく成長している飼育技術があれほどもがき苦しんだ過去を忘れさせてくれるほど、 ありとあらゆる状況がすっかり様変わりしてしまったように思います。 野生本来の食性が明らかになるなどごく当たり前のことはもちろん、 多少状態を落としていたとしてもそれをカムバックさせるだけの新たなスキルに加え、 それを助ける器具やサプリメントなどのアイテムも日に日に充実感を増しており、 獣医学の進歩もあって世の中が平和になりつつあるような気がします。 そもそも昔ほどぐったりスカスカのコンディションで目にする機会が減り、 中には繁殖や養殖の進んだ種類もあって初期状態が大幅に改善されたため、 ショップ側としても新しい飼い主へお渡しする際の心配が無くなり、 より多くの人がリクガメと言う生き物に触れられるようになりました。 それでも難しさへのイメージは根強く特定の種については最初から諦められがちで、 やはりこのホシガメも例外ではありませんが、 我々としてはそれを逆手に取ったサプライズの意味も込めて、 見事に元気印を勝ち取った個体を数多く輩出できるよう心掛けています。 今回やって来たのは久々に少数ながらまとまって輸入された中から、 とにかく色柄を優先して頭からハンドピックしたこんなタイプ。 と言うのもこの便に関しては何となく勝算が感じられたため、 立ち上げは全て請け負うことにして多少の軽さには目をつぶり、 動きにキレがあれば構わず連れて来たのですが、 実に一か月以上の集中トレーニングの甲斐あって今ではすっかりハツラツとしています。 よく当店では初めの一か月は特に緊張状態を保って下さいと申し上げていますが、 まさにその出だしが全て完了しているので安心してお選び下さい。 色彩や模様のインパクトはご覧の通り、 王道の極太バンドからスパルタンな雰囲気のブラック系、 それに成長後の美しい姿が待ち遠しい濃厚なオレンジが目立つものまでより取り見取り。 ケージ内を駆け回るエネルギッシュな状態でお待ちしております。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (S) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| カラー・ライン・成長具合のどれにも文句のつけようがない将来有望美個体! 有難いことにベビーから少し育った安心サイズです、インドホシガメが入荷しました。 その名の通りリクガメ界のスターの座をほしいままにする誰もが認めた超人気種。 最大の特徴である甲羅の模様は生息地の草むらにて身を隠すためと言いますが、 そのようなエピソードも我々にとってはもはや何の関係もありません。 ただただ美しいその色柄に魅了されてしまったが最後、 バリエーション豊富なホシガメの世界にどっぷりと浸かって頂くことになってしまいます。 人々を虜にする美しさとは裏腹に飼育の難しいカメという印象もありますが、 最近では輸送状態が随分と改善されたそうでシャキシャキ動く状態の良い個体が多くなり嬉しい限りです。 出回っている殆どの割合を占めるのが所謂ピンポンサイズと呼ばれる小さなベビーですが、 何もわざわざピンポンから始める必要はありません。 今回やってきたのは大きさはベビーに近くとも安心度は段違いの一匹で、 単に少し育っているだけではなくゼロに限りなく近いボコつきの無さはお見事。 またこのサイズになってもなお体中に赤みが出ており、 成長線からドバっと溢れ出した新たなラインは将来の華麗な姿を想像させて止みません。 これだけ立派な見栄えに期待を裏切るようなことはなく、 写真からもお伝えできるかと思いますが足取りは大変軽やかです。 暖かくなってきたこの季節からリクガメ飼育を始めましょう。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ボールド) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 洗濯用洗剤ではありません、 同じ種類だとは到底信じ難い荒削りで奇抜なデザインが刺激的! 個人的に将来の姿がどのようになるのか物凄く楽しみで仕方がないスペシャルセレクトです、 インドホシガメが入荷しました。 この場で改まって申し上げる必要もなく、 名前の由来となった背中の色柄に様々なバリエーションが存在することは周知の事実ですが、 それでもデザインの幅については限界がありたかが知れていると思われて当然かもしれません。 背甲の各甲板から黄色い直線が数本ずつ、放射状に拡散するというお馴染みの意匠は確かに美しいのだけれども、 見慣れてしまっているだけに新たな発見や意外性という部分では強気になれないと言うのもあるでしょう。 種としてのアイデンティティを崩壊させるほどの勢いを求めるのならば、 それはもはや突然変異の域に突入してしまいますから、 あくまでも原種の状態を維持しながら如何ほどまで楽しめるのかを追求するためには、 わらわらとした中から両目が充血するまで標的を見定め選び抜くしか方法はありません。 雌雄の性差も踏まえてほぼ完成したようなサイズで良ければ、 その時点でおおよその外観が確定しているため好みに合わせることは容易でも、 それでは育てる楽しみが殆ど失われてしまっていますから、 見えないはずの未来を予測しそれを的中させることに全神経を注ぐこともまた一興、 経験と勘、それに運の要素を加えて思う存分ホシガメの奥深さを味わいましょう。 今回ご紹介するこの個体、ひょっとして何処かで見覚えがある方も多いのではないでしょうか。 それもそのはず、何を隠そう実は先日までセレクションとして掲載していた四匹の内の一匹なのであり、 ひょんなことから店頭に居残ることになったのですがこれが私としては幸運な出来事になりました。 何故なら数十匹の大群の中から最も素早く的確にセレクトした個体であり、 己の直観を信じただけに世話をしていく中で最も思い入れの強いものとなっていたからです。 線の本数が少なくビルマホシガメのように見えるタイプは探せば時折見かけるものの、 それを遥か通り越してここまでラインが極太になるバージョンは意外にも新鮮で、 売り切れにしてお蔵入りさせてしまおうかと何度も考えましたが勇気を出してここに再掲載する決心をしました。 正直に申し上げると綺麗になるか否かは全く分かりませんし、 かなり主観が入っているため評価がどちらに転ぶかも分かりかねますが、 いずれにしても光るものを感じさせる何だか面白そうな個体だという意図がお伝えできれば幸いです。 入荷後知らぬ間に甲羅が五ミリほど伸び、 撮影前の温浴では自分の頭ほどもある排泄物を二発もお見舞いしてくれた、 皆さんが想像している以上にアクティブで非常に魅力的な一匹、 餌は何でも食べますのでご心配なく。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイオレンジ) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 星形模様のみならず体中が暑苦しくも激しく燃え上がった季節外れの極上フルオレンジ! バンドが太い細い云々よりもまず第一にボディカラーへと焦点を当てた行く末が楽しみで仕方ないスペシャルセレクト、 インドホシガメが入荷しました。 ホシガメは見かけが美しいけれども飼育がとても難しいらしいですね、 そんな言葉を投げかけられる度に味わう羽目になるこのもやもや感は一体何なのでしょうか。 仰る通り確かにどの本や資料を開いてもそのような記述が見られ、 これから楽しくリクガメを始めようという方にそういったイメージを与えてしまうのも仕方がないのですが、 即座に買ってはいけないリストに入ってしまう不遇な扱われ方は如何なものかと思います。 現地では畑の作物を食い荒らす害獣とまで言われ、 分布域を示す地図のマーキングを見ると近縁とされるビルマホシガメとは比べ物にならないほど広範囲に渡って棲息していることが分かり、 本来の生態を見る限りでは別段か弱い種類という印象はありません。 輸送方法から生体の初期状態、飼育法に関するデータやそれに必要な器材など、 全てが一昔前より改善されているこの恵まれた時代においては、 先入観による偏ったマイナスイメージをばっさりと切り捨てていかねばならないのです。 当店では初めてのリクガメに新たな選択肢としてあえてホシガメを提案すべく、 機会が許す限り状態の良い個体をコンスタントに仕入れては、 店頭にて並の環境に耐え得るレベルに整えることを繰り返していますが、 このような地道な活動によりどれほどの成果を上げることができるのかは正直分かりません。 それでも本当にホシガメのことが好きな方がその第一歩を思い切り踏み出せるよう、 日頃から実績を積み重ねています。 今回は十一月の末にまとめて入荷した中から、 明らかな赤味の強さに惹かれて贔屓にしていたこんな個体をご紹介します。 勘の良い方は甲羅の色合いを見た瞬間に何かがおかしいと気が付くと思います、 ですが頭や体の部分を覗き込めば誰しもがその美しさに見惚れてしまうでしょう。 過去に数回アダルトサイズにして全身がオレンジ色の個体を見たことがありますが、 基本色がノーマルとは全く異なるその佇まいはまるで別種のようなインパクトを放っていました。 これまでも何度か体色がやや赤味がかったものを引っ張って来たことはあったにしても、 この個体ほどはっきり赤いと断言できるクオリティに巡り会ったのは初めてかもしれません。 普段なら撮影前に全身の汚れをブラッシングしてしまうのですが、 本日はあえて口元の緑色を残してみました。 よく見ると左の縁甲板が一枚少なく、 お尻の部分ですからまず目立ちませんが念のため。 定期的にニンジンを与え続ければ更なる発色が望めるでしょうか、 冗談はさておき今後の成長に大きな期待を込めてこの逸品をリリースしたいと思います。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (S) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| ピンポンサイズを脱出し子どもの拳ぐらいにまで育った将来有望の美個体が嬉しい安心サイズで! そろそろ暖房器具が不要になり本格的にリクガメが飼いたくなるシーズンにぴったりの出物です、 インドホシガメが入荷しました。 色、形、大きさ、どれをとっても日本人、 いやそれどころか世界中の人々に愛されて当然と言っても過言ではないこのホシガメは、 今も昔も我が国のリクガメ人気を支えてくれる重要なポジションを担っています。 誰が見ても美しいと思えるその類稀な美貌はどんな稀少種に勝るとも劣らないですし、 こんもりと盛り上がるシルエットはいわゆるリクガメのイメージにぴったり、 そして最大サイズはより大きくなるメスでも20センチ程度と非常に現実的で、 これを飼育するなと言う方に無理があるのではないかと思えるほど優れたスペックを備えています。 唯一の弱点と言えば輸入状態および初期状態が悪く、 初めての方にとってはどうしても鬼門になってしまう所なのですが、 昨今ではきちんと立ち上がった個体であれば言われるほど難しくもなくなってきており、 当店では初めてリクガメを飼いたいという方にも万全の態勢でお勧めしています。 今回やって来たのはそこらで見かけるホシガメに比べれば化ける可能性が数段高いであろう、 見栄えの華やかさに拘った全く別ラインよりセレクトされた二匹。 やたらと背が高く全体的に赤味の強い方を個体A、 ラグビーボールのような体型でこの先バンドが増えていきそうな方を個体Bとしました。 Aの方はまるでヘサキかホウシャかと言わんばかりの天井を突き抜くようなガツンと盛り上がった甲羅が印象的で、 各甲板のラインは本数多めでメリハリも利いているため大変鮮やかに見えます。 外観に赤味を帯びているのも特徴で、お好きな方の多そうな優等生タイプとも言えるでしょう。 Bの方はすっきりとしたイエローを基調とし、 体に入る黒斑も少なく見た目にキツそうな雰囲気は殆どありません。 模様の入り方はまだまだ駆け出しと言った感じで、 今後の成長具合でやや細めの放射模様が数多く現れることが期待されます。 両個体とも餌食い、排泄、運動量の基本的なサイクルに全く問題は無く、 当然ながら書籍などに書いてあるホシガメの最悪なエピソードとは無縁です。 いくら育てるのが大変な印象が強いとは言え、 小さな頃から大きくする醍醐味も堪能して頂きたいと考えていますので、 このようにお手頃な飼い込み個体の存在は貴重です。 お好みのカラーリングやフォルムでお選び下さい。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイカラー) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| あまりにも美し過ぎる色彩に万が一のことがあっては困るとしこたま温め続けたウルトラセレクト! 目も眩むようなメニーバンドにイエローとオレンジが映えるこれぞひとつの究極体、 インドホシガメが入荷しました。 昨今ではペットブームの波に乗り需要が格段に増え続けているリクガメの仲間たち、 中でも本種はその恒久的な美貌から昔ながらの人気種として名を馳せていますが、 果たしてこれほどまでに美しくそして入手が容易いものが他に考えられるでしょうか。 もちろん外観については稀少性を付与すればいくらか候補は出るものの、 しかしながらこのホシガメがそれらに引けを取るはずがありませんし、 何しろ自分の手元に置くことができなければ飼育の醍醐味すら味わえませんから、 そういった意味では実に恐るべきスペックを有しているとつくづく思い知らされます。 ほんのつい最近の出来事ですが、 相方であるビルマホシガメを失って以来一層注目度が高まっているこちらインドは、 有り余るバリエーションにより毎度見れば見るほど一匹毎に異なる容姿が遊び心に溢れ、 お好みの個体を探すと言う素敵なイベントを皆さんに提供してくれるのです。 今回ご紹介するのはもうかれこれ数か月は優に経過しているでしょうか、 意図的な長期ストックにより良い意味で店内のペットとなりつつある綺麗所の二匹。 一方はハイイエロー、 そしてもう一方はハイオレンジなどと称して差し支えないであろう極めて高いクオリティを引っ提げ、 金額に見合った扱い易さを実現すべく我々が責任を持って抜群の状態まで仕上げた、 見た目も中身も数段上の違いを実感して頂けるであろう自信満々のセレクト個体です。 百万発の花火を甲羅に背負ったような激しい星形模様は単体で見てもその勢いがよく分かり、 イエローの方は特にその本数が多く、 対するオレンジの方は真っ赤に燃える肌の色に並々ならぬ気合いが感じられ、 どちらの個体も成熟する頃には一体どのような姿へと変貌しているのでしょうか。 肉付きはリクガメにあるまじきパンパンのプニプニ状態、甲羅の成長線はグッと力強く伸び、 ケージ内でのダッシュ力も並大抵のものではない初心者向けとさえ言い切れる元気っぷり。 最終サイズを加味しても飼育し易いお手頃感は本当に有難い限り、文字通りのスーパースターです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (S) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| ちょうど良いサイズ、太く鮮やかなライン、均整のとれたフォルムと三拍子揃った優等生! せっかく飼育を始めるのなら納得のクオリティで選びましょう、インドホシガメが入荷しました。 永遠のリクガメ最人気種、その称号は今も昔も変わらぬ我々の揺るぎない信念が創り出したまさに結晶です。 英名Star tortoise、ホシガメという和名はそれをただ直訳しただけの実に単調なネーミングですが、 このたった四文字に込められた人々の思いは到底計り知れません。 世界中を見渡せば似たような色柄を持つ他のリクガメを見つけることができますが、 本種ほど愛され続けた例は未だ存在しないでしょう。今まで何匹のホシガメを紹介してきたのか、 そう考えただけでも様々な思い出が甦ってくるようですが、 一見ワンパターンとも取れるこの模様が多くの物語を綴ってきました。 毎回見かける度に異なる表情を見せてくれる、なんて芸当は容易に真似のできることではありません。 これだけの持ち味を並べてみると、カメ好き一人につき一匹のホシガメを飼っていてもおかしくなさそうですが、 長年言われ続けている通り特に幼体時では飼育の難しい種類としても有名です。 高温かつ多湿、それも極端に高い水準を要求するとされ、ビギナーにとってはこれが最大の鬼門となっているのですが、 流通の殆どがベビーという悪条件にも阻まれ、いざ飼い始めるとなっても必ず躊躇されてしまいます。 しかしよく考えてみると、野生個体がそんなぬくぬくとした温室のような環境で暮らしているとは考えにくく、 実際には初期状態の見極めと個体に合った環境設定でいくらでも解決できる問題です。 もうホシガメが難しいとは言わせません、 今回やって来た個体は10cm未満というベビーの様相を保ったギリギリのサイズで、 かつこれまでの成長過程に全くと言って良いほどトラブルの形跡を感じさせない優秀ぶり。 温度管理は市販の飼育器具を普通に用いるレベルで問題なく、 気になる湿度も成長の過程にさえ乗ってしまえば床材の湿り気をキープするような感覚でOK。 今の時期的には温度も上り調子で過乾燥に留意する必要もありませんので、 飼い始めるには1年の間でも極めてベストに近いシーズンと言えます。 そして最も気になるのは柄の品質ですが、パッと見た印象ではどうでしょうか。 第一印象はまず明るいということ、 これは線の本数が多いからというのもありますが、 要所要所でかなり太めのラインがバッチリ決まっていることで全体のメリハリを強くする効果が生じています。 また全身を見渡して素直に綺麗だと思えるのは、 模様だけではなく基礎である甲羅の形がしっかりと土台を作ってくれているからでしょう。 餌は葉野菜からMazuriリクガメフードまでよく食べ、 ここ数日は気温も上がってきているので心なしか一度に平らげる量も日に日に増大しています。 カラーリングが気に入ったから、という理由で選ばれればそれこそホシガメとしては本望だと思いますが、 こういったコンディションの整った個体こそ初めての方やあまり自信のない方の下へ行き、 今まで難しいと思っていたホシガメが普通に飼えた、そんな喜びを実感してもらえればと思います。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (S) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| こう言ってはカメに失礼かもしれませんが見ていて気味が悪くなるほどに明朗快活な爆走インド! 餌を与える訳でもないのにケージをノックすると親しげに駆け寄って来るスーパーグッドコンディション、 インドホシガメが入荷しました。 昔ながらの良くも悪くも定番の人気種としてリクガメ界随一の知名度を誇るホシガメ、 誰がどう見ても美しいと言われるその美貌にやられてしまう人も多い中、 どうしても飼育難関種としてのイメージが拭い切れないせいか、 図鑑や雑誌などでは初心者キラーの異名を取る何とも不遇な扱いを受けています。 そもそも現地では畑の農作物を荒らす天敵として認知されているほど、 本来は逞しいカメであることはこの場でも度々触れているのですが、 元々持っている生命力をきちんと引き出した状態であれば言われるほど飼い難い種類とも思えません。 商売的な言い方をすればよく売れる割に安価な商材ですから、 数を豊富に取り扱うためにどうしても粗雑に扱われてきた歴史があり、 こういった悪循環が全てを狂わせてしまったのでしょう。 実はここ最近、正規輸出枠がかなり危機的な状況にまで削減されているらしく、 暫く見慣れた姿とご無沙汰だったのはそのためですが、 久しぶりに顔を合わせてみると皆が皆かなりリフレッシュしたご様子で、 悲しいかなそれだけ流通ルートでのケアがしっかりなされるようになったということでしょうか。 いずれにしても我々ショップの元へ届いた時点でメンテナンスの必要性が大分薄れたことは、 結果的にこれから飼育される皆さんにとってもプラスに働くものと考えています。 今回やって来たのはここ数年で取り扱った中でもかなりの自信作、 初期状態から素晴らしいスタートダッシュを切った上に、 店内で更なるパワーアップを図り数週間温めてきた凄まじく元気なホシガメたち。 念のためお気に召して頂けるよう太いバンドの個体ばかりをセレクトしましたが、 実はそんな見た目の話よりもとにかく体調に気を配り、 初めてリクガメを飼う方でも安心してお迎えできるレベルにまで仕立ててみました。 主食は間違いの無いMazuriリクガメフード、 しかも全員が折り重なるようにして奪い合いながら食べる姿は圧巻、 まさしく野生の生物そのものと言った様相を呈しています。 一度店頭まで足を運んで見て下さい、 きっとあまりにもクイックかつスピーディな動きに驚かれることでしょう。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイカラー) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| この華やかな光景を再び見せてくれたことに感謝の気持ちが溢れ出す不動の人気ナンバーワン! 今や稀少種の仲間入りを果たしつつある願わくばいつまでも大切にしたい業界の宝、 インドホシガメが入荷しました。 この僅か数年の内にリクガメのことを知り始めた方々にとって、 それは俄かに信じ難いことかもしれませんが、 一昔前には彼らがまるで消耗品のように扱われていた時代が確かにありました。 今でこそきちんとした環境設備を整えた上で、 基本的な飼い方を押さえ先輩からの経験談を参考にすることにより、 少なくとも最低限のレベルでリクガメを育てられるようにはなりましたが、 それこそ十年やそれ以上前には運の要素がかなり高い割合を占めていたり、 数を打てば当たると言うような発想の下で流通していたことも否めませんでしたから、 半分仕方の無いこととは言え改めて反省させられる部分は多々あると思います。 もちろんその頃から蓄積され続けている何かしらが今日の飼育方法の基礎であり、 根幹を成す部分になっているのですから頭ごなしに否定するのも憚られますが、 いずれにしてもただ同じことを繰り返している訳にはいかず、 状況の変わった今だからこそできること、 やるべきことを明確に見極めた上で目の前のカメと接することが大切だと思います。 かつて初心者キラーとして名を馳せた色々な意味で思い出深いホシガメも、 最近ではCITESの輸出許可が思うように取得できず苦労させられる場面が多々あるようで、 実は一般の飼い主よりも我々販売業者の方がずっと気持ちに焦りが生じていて、 昔のように店内をホシガメで埋め尽くすことができればどれほど幸せか、 そんなことを考えながら一匹一匹とかつて無い距離感で真摯に向き合っています。 今回やって来たのは入手困難になったお陰で初期状態がすこぶる良好になった、 体から四肢まで従来のホシガメとは比にならないほど充実した肉付きを見せるセレクト個体。 正直、群れの多くは健康なものばかりだったのでシンプルに色柄で選ぶことができ、 皆さんの好みに合わせられるよう思い思いのデザインを甲羅にぶつけてみました。 あえて個々の解説はこの場では避けますが、 ハイカラーとのフレーズには正統派の美しさと言った意味が込められていますので、 直観と閃きでピンと来た個体をお迎え頂けたら嬉しいです。 少しずつ店内の環境に慣れMazuriリクガメフードも口にし始めた、 食い付きから体重まで何の心配も抱かせない高品質なものばかりです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (S) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 完全なる個人的な嗜好ではありますがバンドが太く赤味の強い優等生タイプばかりをセレクト! 実に生々しくも年々国内での取引量が目減りしている実態に胸の奥が否応無しにざわついてしまう、 インドホシガメが入荷しました。 兎にも角にも我が国におけるホビーとしてのリクガメ、 と言うよりもその需要は世界規模に及ぶことまで視野に入れねばなりませんが、 長きに渡り絶対的王者として君臨するほどの類稀な人気を誇る、 未来永劫無くてはならない究極のマストアイテム。 もし何かの間違いで姿を消そうものなら日本が、 世界が震撼する大事件になろうことは火を見るよりも明らかであり、 私たちの心に宿る永遠のスターとしてその場に居続けて欲しいと皆が皆願って止まない、 これほどまでに愛されたリクガメが他に存在したでしょうか。 こんなことを私の口から申し上げるのは適切でないかもしれませんが、 ほんの数年前まではさほど高価なカメでは無かったのもご存知の通りで、 しかしながら如何ほどの価格帯で売買されようとも彼ら自身の魅力には一切の影響を及ぼさないであろう、 決してぶれることの無い芯の強さが我々の意識するずっと前より出来上がっているのです。 あまりお金の話ばかりに触れても如何なものかと思いながらも、 そのような外的要因ばかりに囚われること無く正しい眼で本質を見抜いてあげたい、 見抜いてあげるべき逸材がそっと目の前に用意されていることに、 何故もっと早く気が付いてあげられなかったのか、今更ながら悔やまれます。 今回やって来たのは何だか久々のご対面に胸を撫で下ろす、 かつて主流であったいわゆるピンポンサイズなどとは訳が違うふっくら安心サイズ。 本種の美しさはもはや語るまでも無い周知の事実ですが、 そんな前評判に違わぬクオリティを追求し、 冒頭でも触れた通り背甲の象徴的な星形バンド模様は太めに、 体色は黒斑が少なくほんのり赤味がかるぐらいのタイプばかりを選抜しています。 こうして美しい個体ばかりを並べると分かり難いかもしれませんが、 誰が見ても綺麗だと口走るほど質の高いホシガメは、 案外いそうでいないことを改めて実感して頂ければ幸いです。 早くもMazuriリクガメフードに餌付き、 と言うよりもそちらの方が好物なのではとさえ感じさせる餌食いの良さに、 恵まれた初期状態を滲ませる素晴らしい三銃士は、どれを選んでも外れることはありません。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (CITES確認証付) Geochelone elegans |






|
|
||||||||
| 不動のリクガメ人気No.1、ホシガメの入荷です。 今回入荷した個体は非常に珍しいCITES確認証付きのホシガメです。 やはりいつかはⅠ類への移行は免れないリクガメ類ですからこういった形での入荷はとても将来性があり、非常に喜ばしい事です。 サイズもピンポンより幾分成長しており、多少の低温や乾燥にも耐性がある為初心者の方にもお勧めです。 最近では国内のブリーダーズイベントでも出品される事が増えてきたカメですから、将来的に繁殖を目指される方にもお勧めです。 今回ラインの綺麗に繋がった個体 や数の多い個体などお選び頂けます。 まだ小さいですが性別はこちらの写真でご確認下さい。 やはり少々お値段は高いですが、過去のマダガスカルのリクガメ等の例もありますから是非ご検討下さい。 勿論ご購入頂いた方にはCITES確認証をお付けします。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (M) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 中粒揃いの1年飼い込み安心サイズ! 多少の寒さや乾燥にはびくともしない個性豊かな3匹です、インドホシガメが入荷しました。 ほぼ全ての生き物に当てはまることでしょうが、 何か新しいペットを飼い始める時は小さくて可愛らしい頃からお世話をしたくなるものです。 このホシガメは長年に渡ってリクガメの人気を支えてきた存在であるだけに、 カメのことをまだそれほど知らない方でも不意に目を奪われ見入ってしまうというのはよくある話。 そうして家に帰って何かしら情報を引っ張ってきては勉強を進めていくと、 どうやらホシガメというのはベビーから飼育するのは難しいらしい、という所に行き着くことになると思います。 生まれたばかりの幼体は急な低温に対して非常に敏感なことや湿度の高い環境を好むこと、 そしてなかなか内気な性格の持ち主であるため結局何もできずに終わってしまうというケースも珍しくありません。 実際に流通している個体の多くが所謂ピンポンサイズであることも、 そういった本種のイメージを形成する大きな要因のひとつになっています。 しかし今回は本当に有難いことに、 そのピンポンから一年間じっくり育て上げられた実に丁度良いスターターサイズがこんなにやって来ました。 確かにベビーは安価に入手することができるかもしれませんが、 全ての個体に対してこれだけ世話の行き届いた感を見せられると愛好家の底力には唸らざるを得ません。 全体的に色彩は明るく甲羅にもツヤがあり、 バンドの入り方は三者三様でただ並べて眺めているだけですがとても賑やかです。 色味も良いのですが一番のお勧めポイントはとにかくそのコンディションの良さ。 ちょっと汚い話ですがまとめて温浴させると信じられない量のうんちを捻り出し、 体が軽くなったと思えばスタスタ歩き出しさっきしたはずなのに歩きながらまたするというのは、 それだけ沢山食べることのできる胃袋の大きさを見せつけられているようです。 性別は不明としましたが、何となく全個体メスのような気がします。 季節の変わり目という心配事も全くもって当てはまりそうにありません、 文句無しに良いと太鼓判を押せるオススメの3匹です。 | ||||||||||
|
インドホシガメ
Geochelone elegans |




|
|
||||||||
| お客様飼い込みの、しっかり育ったホシガメが入荷しました。なんとこの個体、ピンポンサイズから 大きくされたそうです。もう夏本番、寒さに弱いホシガメの飼育を始める季節としては、丁度良いと 思います。今回はお客様買取個体のため格安でお出しします。背甲のラインには個体差がありますが、 今回のは線が多く繋がったタイプです。葉野菜をムシャムシャと食べています。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (太バンド) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 草原の中ですら外敵に見つかってしまいそうな極太バンド! ビギナーや経験者など関係なしにお勧めしたい2ケタ甲長飼い込み個体、インドホシガメが入荷しました。 いつの時代もリクガメ人気ナンバーワンの座を一向に譲らないのはこのホシガメです。 派手すぎる甲羅の模様は自然の流れに逆らっているかと思いきや、 これが棲息環境に置くと上手いこと目立たない仕様になっているとか。 しかしながら今回の個体は何処で暮らしても擬態に失敗してしまうのではと心配になるぐらい、 視覚に響く強烈な柄を持っています。 ですがこんなに美しいリクガメもベビーからある程度育つまでの飼育難易度があまりに高いと言われ、 これまで飼育を断念されている方も少なくないのではないでしょうか。 10cmぐらいになれば甲羅もしっかり硬くなり、 元来の性質上時間帯によっては大人しい一面はあるものの餌入れに葉っぱやMazuriリクガメフードを入れるとしっかり自分の足で立ち上がり、 腹甲を持ち上げながら嬉しそうに食べに寄ってきます。 冬期の十分な加温をする必要はありますが、 昨今では保温器具も充実しているためさほど問題にはならないと思います。 性別は不明としましたがメスっぽいこの個体、 まだまだ長い成長期を楽しんで下さい。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 甲羅のすっかり硬くなった安心&性別確定サイズ! 初めての方にもオススメの二ケタ甲長です、 インドホシガメ・オスが入荷しました。 リクガメと言えばホシガメ、そう言われても大袈裟ではないかもしれません。 甲板のひとつひとつに燦然と輝く黄色いラインが星のような模様をかたどることからこの名前が付けられました。 手にとって見てもケージに収めてみてもあまりに目立ち過ぎる外観ですが、 これが現地の草原に潜んでいると保護色のような役割を果たすのだとか。 つまりシマウマのような原理でしょうか、 何だか腑に落ちない心持もいたしますが我々にとって派手で悪いことはありません。 その美しい姿が放っておかれる訳もなく、 国内でも古くから飼育対象とされ大変な個体数が輸入されてきたと言いますが、 最近では飼育法なども分かってきてかつてのようなイメージは大分薄れてきました。 今回やってきたのは定番のピンポンサイズからの飼い込み個体で、 ボコつきの極めて少ない全体のフォルムとほぼ均一に刻まれた成長線から、 これまでずっと大切に育てられてきたことが伝わってきます。甲羅表面の質感も申し分なく、 たまに見かける腹側の甲板が荒れた様子などもありませんので適切な飼育がなされていたのでしょう。 バンド模様も黒と黄色がバランス良く配色され、典型的でお手本のような個体です。 性別はオス確定で、1匹だけでじっくり楽しみたいという方は、 メスに比べて大きくならないのでコンパクトに飼育を楽しめると思います。 餌も良く食べていますので、バランスの良い給餌を心がけこの調子で綺麗に成長させてあげて下さい。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| いわゆる太バンドという括りになるのでしょうか、少し変わった雰囲気を持つ一匹です。 全身のイエローがじんわりと濃く発色した納得の美個体、 インドホシガメ・オスが入荷しました。 今も昔もその座は決して揺らぐことのない、不動のリクガメ人気ナンバーワン。 ラテン語で書かれた学名は英語のelegantと同じ優美な、という意味ですが、英名はstar tortoiseで和名もホシガメ、 つまりこの美しい色柄はいずれの国でも星の形に形容されるということが分かります。 世界中どこにいても同じ夜空の景色を見上げる私たち、黒い地色を暗闇に、 その上にさんざめく黄色いラインを輝く星々に例えた名前はなんと簡潔で惚れ惚れとする響きなのでしょう。 ただしこの自然にあみ出されたある種究極のパターンも、 全てが整然と均一に並んでいたとしたら仮に幾何学的な魅力はあったとしても、 そこに生命を感じるという段階までには至らなかったかもしれません。 ホシガメ最大の特徴は何と言っても個体毎に見られるバリエーションの豊富さ。 とにかく沢山の絵柄と出会い自らのセンスを養い、時には歴史まで振り返るほど拘った結果、 いつか納得のいく最高のデザインに巡り会うことがひとつの夢だと思います。 しかし現実的にひとつに決めれるとしたらそれほど楽なことはなく、 気に入ったという条件がクリアできれば数匹飼っていても悪いことではありません。 今回やって来たのはバンドも太ければその色も濃いという全体から底力の強さを感じる美個体。 この手のホシガメは一見優等生タイプとして認識されがちですが、 よく観察してみると線の所々が核となる初生甲板から離れ、 隣の線と手を繋ぐように融合しそこに独立した新たなバンドが生まれています。 このスポット状のバンドが点在することで全体を引き締めるアクセントのような効果が生まれ、 冒頭で述べたように独特なセンスを醸しているのです。 こんなホシガメが群れの中にいてもまた面白いでしょう、 ハイカラーという一直線な言葉では単純に言い表せない奇抜さです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 模範的な成長を遂げながらもそれぞれがそれぞれの味わいを醸し出す飼い込みサブアダルト! ここまで育ってくれればもう一安心、 フルサイズ一歩手前の握り拳大が嬉しいインドホシガメ・オスが入荷しました。 世界で最も愛されるリクガメのひとつに数えられる、 類稀な美貌とそれにそぐわぬ親しみ易さを兼ね備えた、 ペットとして非常に優れたスペックを発揮する稀代の人気種。 人々が最も意識しているであろう本種の魅力は今更言葉にして説明するまでも無く、 それはつまり外観およびホシガメと言うそのネーミングが全てを表しており、 誰がどう見たって美しいに決まっているのですから大したものです。 あえてそれ以外、それ以上の長所を付け加えるとすればまず色柄に個体差があること、 これはホシガメのアイデンティティを語る上で絶対に外せない重要なファクターで、 そのあまりにも豊富なバリエーションがあってこそ我々の視界を彩るまでに至る訳です。 選べると言う要素がまたもや新たな需要を創出し、 ただ単に綺麗なだけでは無く自分の好みをそこに表現することができる、 これが無ければ今日の他を寄せ付けない人気振りは成し得なかったことでしょう。 また一般家庭で飼育する上でとても重要なサイズ感の問題、 雌雄で最大甲長が異なるもののオスはちょうど手の平を広げたぐらいの十センチ台半ば、 メスはハンドボールぐらいの二十センチ少々となかなか手頃であり、 室内のケージに収めるのにそれなりに現実的なボリュームに収まりますから、 いくらか思い浮かぶリクガメの選択肢の中でも圧倒的上位に君臨するのは当然のことのようです。 今回やって来たのはそろそろ交尾のためにマウントでもし始めそうな、 甲羅が硬いのはもちろんのことシャキシャキ動く躍動感まで身に付けたヤングサイズのオスが二匹。 それぞれ全く別のところで育てられた放出個体で、 個体Aは太めのバンドに艶たっぷりの磨き上げられたような甲羅が印象的、 対する個体Bは線の太さこそ少し繊細であるものの頭部にははっきりと赤味が差し、 なかなか選ぶのに迷ってしまう組み合わせになっていると思います。 どちらも店頭で暫く面倒をみていたためコンディションは抜群、 Mazuriリクガメフードをむしゃむしゃ食べながら元気いっぱいでお待ちしております。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 今時流行りのピカピカな美個体とは少々雰囲気が異なる何処か懐かしさの漂うクラシカルタイプ! 色合い、形状、そして人懐こい性格とどれをとっても不足の無い素晴らしい個体です、 インドホシガメ・オスが入荷しました。 美しさは罪とでも言いましょうか、 人の手によってほんの数十年が過ぎる間に激動の変遷を辿って来た、 言わずと知れたリクガメ界における文字通りのスーパースター。 かつては飛び抜けて高価な種類でしたからまさに時代を象徴するカメとして、 単なる稀少性のみならず指折りの美麗種として名を馳せたものの、 暫くすると多大な輸入量に後押しされ良くも悪くも日頃から見かけられるようになり、 場合によっては扱いが粗末になってしまうことも少なくありませんでした。 それでも需要が衰えることは無く多くの人を魅了してきましたが、 ほんの少し前までは初心者キラー的な位置付けとしても有名で、 初めての人は絶対に手を出してはいけないとまで言われる始末。 元来ひ弱なカメではないはずなので、最近では初期状態も良くなりビギナー層への普及も進む中、 それに相反するかのように流通量が激減してしまい、 今年に入っていよいよ危機感を募らせるまでになっています。 この頃はブームの再燃によりまたもや注目を浴びるようになってきましたが、 この先も変わらぬ姿を見続けることができるよう祈るばかりです。 今回やって来たのは昨今ではますます貴重になりつつある、 繁殖を視野に入れることができるほぼ即戦力と言って差し支えない長期飼い込みのオス。 甲羅のボコ付きがデフォルトの特徴であると勘違いされてしまうほど、 確かに本種にはボコボコとした形に育った個体が多いのは事実ですが、 何を隠そう真の野生の姿はここにご覧頂けるようなツルンとリクガメらしいシルエットであり、 皆が皆こうなれば良いのですがここまで理想に近いクオリティのものは珍しいです。 ベビーのタマ数がわんさかいた頃であれば話は別ですが、 今後も飼育されている絶対数が年々目減りしていくことは避けられず、 魅力的な個体を探すのも至難の業になってきました。 表情にも落ち着きがありサイズ以上の風格が感じられる一匹、 撮影に備えて体全体を磨いたためか写真では少し緊張気味ですが、 ケージ越しに愛想良く近寄って来る大変に人慣れした良い子です。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (アダルト・♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
|
前回、前々回に引き続きお客様飼い込み委託個体のインドホシガメが入荷です。10年程の間、ゴールデンウィーク明けか
ら9月半ばまで庭でお日様の紫外線を充分に浴びさせよく歩かせていたそうで、繁殖に使えるメスがおらず今回の放出です。
ある程度育ってからのワイルドの長期飼い込みですので、背甲はツルツル・ピカピカで飼育のきめ細かさを感じさせられます。
甲羅に若干のスレが有りますが、ブラックとクリーム色のバランスも良く、CB個体との違いはこのサイズでも
眼が優しく頭部が大きく
四肢もしっかりとしている事でしょうか。ヤル気も充分で違う種の個体でも雌雄を問わず交尾行動を始め、年に1度位信頼のおける獣医で
駆虫もしていて、健康状態もバッチリです。餌もMazuriリクガメフードなどの人工飼料から、もちろん葉野菜も大好物です。
無精卵を産んで繁殖可能なメスのみをお持ちの方や、CB個体のPrで血が濃くなる事が嫌だなとお思いの方、 優良個体のオスでお勧めです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 野生下における真のホシガメの姿をものの見事に再現した当店に過去入荷した中でも史上最高の絶品! やや細めのラインが数多く描かれたこのクラシカルなデザインも高評価に値します、 インドホシガメ・オスが入荷しました。 リクガメの成長具合を表現するために用いられるボコ付きという概念、 近頃ではボの字もないぐらいツルツルの方が理想的であるという認識が一般的ですが、 かつて生態や飼育に関する情報が乏しかった時代には、 反対に尖っていた方が格好良いと考えられていたのは有名な話。 確かにシルエットとしてはまるで怪獣のような、 空想上の生き物を連想させるため一瞬気を取られてしまうのは分からなくもないのですが、 このご時世ではそれが間違っていることを野生個体が証明しています。 多くの種類が当然フルサイズなどではなく幼体に近い大きさで輸入され、 どのように成長するのかという指標はあくまでも人の手によって育てられたものがお手本となりますから、 これまでは理想とすべき対象がペットの世界だけで完結してしまっていました。 もちろん自然状態を捉えた資料が丸っきり皆無という訳ではなかったので、 コアなマニアは当時より正しい知識を得ていたのだと思われますが、 やはりエキゾチックアニマルの一種として見た場合には、 本当の姿かたちが一般に認知されるにはそれなりの時間を要したのでしょう。 ただし今でもリクガメを綺麗に育てるための正攻法が存在する訳ではなく、 環境の違いや個体差も加味した各々の飼育方法が絶対条件となってきますので、 そこには飼い主の愛情という目に見えない要素が必要不可欠なのです。 今回やって来たのはつい先程インドから到着し、 体中の泥を落として写真を撮影したと説明しても何ら不思議のないほど、 非常にまろやかなカーブを描く甲羅の造形が素敵な一匹。 何よりも感動的なのが計ったように刻まれた均等に伸びる成長線、 これを実現するためにはベビーの頃から規則正しい生活を人とカメが共に送ることが重要で、 これを愛と呼ばずしてなんと言うのでしょうか。 模様の入り方も何だか昔ながらのという表現がお似合いのメニーラインタイプで、 個人的には頭頂部がきっちり黒くなっている所もお気に入りです。 野に放たれた状態ではごく普通ということはつまり、 人の手によって育てられた状態ではハイグレードの極上品と言って差し支えないでしょう。 明るい性格で扱い易いのも嬉しいポイントです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| メスへのしかかるには十分な体格を備えたペットにもブリードにもうってつけの大型美個体! もう初心者キラーとは呼ばせない春の訪れに相応しい元気ハツラツの長期飼い込み、 インドホシガメ・オスが入荷しました。 数あるリクガメの中で最も見栄えが良く、 かつペットとして見た場合に私たちにとっては最も身近ではないかと思われる、 今も昔もずば抜けて高い人気を誇る云わば文字通りのスター的存在。 派手な色彩がよほど苦手な方を除けば誰も彼もが愛して止まないであろうその容姿に、 特段カメには興味の無かった人でも思わず惹かれてしまう強い訴求力を感じて止みません。 哀しいことに飼育が難しい、 ことになっている都合上どんな資料を紐解いても安易な飼育は勧められない、 ことになっている訳ですが、 自然界におけるホシガメの勇姿を想像した場合には果たしてどうでしょうか。 例えば比較対象として本種よりも強健であるとしばしば謳われるビルマホシガメ、 両者の分布域を見比べても明らかにインドの方が広大な範囲に棲息していることが分かり、 その一点だけに着目しても言われているほど華奢でどうしようもないカメであるとは俄かに信じ難いのです。 つまり我々の手元に到着した時点で既に弱っている個体が多かった、 それもかつて消費的な流通が横行していた頃は尚更その傾向が強かっただけで、 元来備わる性質に目を向けそれを上手く引き出すことができたとすれば、 今まで知る由も無かったホシガメの本当の正体を垣間見れるのかもしれません。 今回やって来たのはケージに放つや否や、 凄まじい勢いで走り回る姿を見せてくれた実に快調なアダルトサイズのオス。 リクガメは全般にオスの方がメスよりも体質やメンタルが弱い傾向にあり、 本種については最終的な大きさに違いがあることを考慮しても、 屈強なメスにも負けないアグレッシブなオスの存在は様々な場面で効力を発揮すると思います。 この個体は背面の象徴的なバンド模様も太めに描かれ、 太陽光の下では目がチカチカするほどの輝きを楽しませてくれることでしょう。 小型で綺麗なリクガメを飼育してみたい、 そんな一見わがままなお願いもインドのオスであれば実現可能、 このサイズ感で収まることも多いため60センチの水槽でも終生飼育ができてしまうほど。 お腹の摩耗したまだまだ若々しい種親候補、 ペアを揃えてみたけれどちっとも乗らずに困っていると言う方にもお勧めです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイカラー・♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| これは黒地に黄色い模様を持つカメでしょうか、いいえ違います。 まるで世界が逆転してしまったような奇妙さです、 超絶クオリティのインドホシガメ・オスが入荷しました。 あまり写真をまじまじと見ていると目がチカチカして感覚が麻痺してくる恐れがありますので、 目を閉じたら一度頭の中で常識的なホシガメの姿を思い浮かべてみて下さい。 そこまでしても駄目であれば、既にこの周りを取り囲む異次元の空間にのみ込まれてしまったということでしょうか。 いつかこの場でも申し上げたようにあの星型模様はあくまでも擬態のために存在しているのであって、 格好をつけて他の人より目立ってやろうなどという考えとは全くもって真逆の発想であり、 その点を踏まえて見れば大失敗の三文字を導き出すことも決して難しくはありません。 このオスの気取った様子が仲間からの賛成票を集める可能性はかなり低いと思います、 でも失敗することといけないことは同じではなく安易にイコールで結び付けることもできません。 野外に放り出せば目立って仕方のないカラーリング、 つまりケージの中に何匹ホシガメがいようともお構いなしに別格のオーラを漂わせるカラーリングというのはホビーの世界では大歓迎です。 あまりにも綺麗過ぎるため逆にケチをつけてみようと取り組んではみたものの、 甲羅がほんの気持ち若干程度ボコついている、それぐらいしか思い付きませんでした。 このことから分かるようにその品質を支えているのは極太バンドだけではなく、 それは黄色味の濃さであったり、体に表れる黒斑の少なさであったり、 全体のフォルムの良さであったりとトータルコーディネイトがきちんとなされているということです。 勿論コンディションに不安はありません、ただ気に入ったというシンプルな動機に突き動かされて下さい。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (アダルト・♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 前回に引き続きお客様飼い込み委託個体のインドホシガメの入荷です。10年間程、5月の連休明けから9月中旬まで外で充分に日光浴をさせ て飼育し、良く運動をさせていたそうです。メスを落としてしまったそうで今回の放出です。飼い込み個体の多くは、背甲がデコボコに なりがちですがその様な事も無く綺麗に育っていて、愛情の込め具合が垣間見えます。ブラック地にクリーム色のホシガタラインが太めに 入り、コントラストが上品です。凄くヤル気が有り、同サイズのリクガメを見付けると果敢にアタックしていきます。餌はMazuriリクガメ フードなどの人工飼料をはじめ、葉野菜もバクバク食べています。メスのみをお持ちで無精卵を産んでいて仔ガメのハッチをお考えの方、 良いオスでお勧めです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| たった2匹でも並べているだけで目がチカチカします! とても分かりやすい特徴の出た優秀な個体が揃いました、 インドホシガメ・オスの入荷です。 古くからリクガメの人気を支えてきた重鎮であり、誰がどう見ても華やかで美しい柄を持つ、 ふたつの意味でスターと呼べる存在感を放つのがこのホシガメ。 野生動物には時折信じられないほど鮮やかな色柄を持つものがいますが本種も例外ではありません。 現地では草むらの中に隠れるとこの模様のお陰で目立たなくなるらしく、 つまり発想としてはシマウマと同じような感覚なのでしょうか。 かなり嘘くさくにわかには信じがたいことですが、 我々はそのカメを飼育して楽しんでいる立場ですから文句を付ける訳にも参りません。 昔はある意味恐怖のカメでベビーから育てるのは至難の業と言われてきましたが、 最近では着状態も良く少し育った安心サイズも出回っているため、 最初のリクガメとして選んでも問題ないほどになってきました。 しかし気になるのがそのサイズ、 図鑑を見てみると最大甲長は30cmに迫るもしくは超えるようなことが書いてあるため、 比較的小型な地中海の仲間と迷ってしまうケースもしばしば。 ですが実際に育ててみると大きくなったメスでも20cmを超えるぐらい、 より小さいオスに至ってはこのサイズでも十分アダルトと呼べる大きさなので、 家庭内での飼育環境にも十分適応することが可能です。 そして今回やってきたのは世間一般で綺麗なホシガメと呼ばれるものに見事に当てはまる2匹のオス。 1匹はバンドが太く明瞭で地色もしっかり黒々しており、 なおかつ体の色は薄めで全体に均整の取れた優等生タイプ。 もう1匹は黄色の濃さに更に上回るものがあり、ラインは少し細目ですが数が多く、 昔よく見かけたような気がするクラシックタイプです。 どちらもベビーから育てられた個体で、前の飼い主さんによると前者は4年、後者は8年ほどの飼い込みだそう。 年齢的にはちょうど成熟してくる頃で寿命を考えればまだまだ先は長いですし、 繁殖を目指す方にとってはうってつけの旬な時期。 餌食い抜群で足取りも軽快、気楽に付き合っていけるホシガメです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (フルアダルト・♂) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 20センチクラスの巨大なメスを相手取るにはこちらもパワフルなサイズで勝負! 赤みの入らないすっきりとした全身のイエローに何だか懐かしさを感じます、 インドホシガメ・オスが入荷しました。 いつでもいつまでもナンバーワンの座は決して譲らない、 国民的リクガメ最人気種として名高い通称ホシガメ。 ケヅメやヒョウモン、ギリシャやヘルマン、 そしてアカアシなど他にも名の通ったものが数多く存在する中で、 最後に笑うのは誰が何と言おうとやはりこのホシガメしか考えられないのでしょう。 陸上をトコトコと歩き回るというだけで十分人目を惹くはずが、 甲羅には花火のような放射模様が何発も打ち上げられるという贅沢ぶりに、 他の種類がまとめてかかってきても殆ど効き目はありません。 最終的にそれほど大きくなり過ぎるという訳でもなく、 価格帯は比較的リーズナブルなラインで安定しており、 唯一のウィークポイントとして飼育の難しさが挙げられますが、 近頃では初期状態の良い個体が増え飼い方についての情報も随分とブラッシュアップされており、 初めての方でも普通に飼えてしまうというまさしく鬼に金棒状態となっています。 そんな状況で長年課題とされてきたのが繁殖について。 幼体を中心に半ば消費的な流通が続くだけに急務とすべき所なのですが、 飼育頭数の割りに成功の声があまり聞かれないというのはやる気だけの問題なのでしょうか。 実際にハッチからきちんと育つ過程まで上手くいった例を参照しても、 特別変わった様子はなく至って基本的なメカニズムを抑えるだけのようで、 あとは挑戦する機会さえ増えればもっと多くの国内CBが出回ってもおかしくないのかもしれません。 経験談から気になった点を挙げるとすれば雌雄のサイズについてバランスの問題があり、 健康な卵を数多く産ませようと体の大きなメスを用いても、 肝心のオスが10センチ前半とまだまだお子様の状態ではメスの背中へ乗るに乗れず、 結局はふがふが言っているだけで終わってしまうのだとか。 カメ本来の体質から考えてもメスの方が明らかに頑丈ですから、 ひ弱なオスが大きく成長するには人一倍の苦労が伴う可能性も否めません。 今回やって来たのは当店で過去取り扱った個体も含め最大クラスの、 ピンポンサイズから育て上げられた15センチの巨体を誇る歴とした肉食系男子。 群れの中でも真っ先に餌場へ突進し明らかに他の個体よりも量を食べるという、 貪欲が甲羅を背負って歩いているというような図太い神経の持ち主で、 入荷後の仕草を見ていても四肢を伸ばして歩き回る様や、 雌雄構わずそそくさと交尾の練習を開始するバイタリティに明るい未来が待っているような気がします。 このサイズに達するには選ばれし個体であるという運命的な条件が欠かせません、 巨漢の淑女を持て余している方に。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (アダルト・♂) Geochelone elegans |




|
|
||||||||
| お客様飼い込み委託個体のインドホシガメの入荷です。10年程、ゴールデンウィーク明けから9月中頃まで屋外で飼育し、充分に紫外線を 浴びさせて飼育していたそうです。ホシガメ飼い込み個体と聞くと多くが金平糖になっている事が有りますが、綺麗なドーム型に仕上て いて、愛情の込め方が伝わってきます。ヤル気も満々で同じ位の大きさのリクガメを見ると、躊躇無く乗っていきます。餌はMazuriリク ガメフードなどの人工飼料をはじめ、葉野菜も良く食べています。無精卵を産んでいるメスをお持ちで オスを探している方、お勧めです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 本種特有の気難しさをまるで感じさせない機敏な動きが嬉しい皆さんお探しの貴重なメス! ちょっぴり表情に個性がありますが模様も綺麗なことですし種親候補としての活躍を期待したい、 インドホシガメ・メスが入荷しました。 昨日までリクガメのことを何も知らなかった人でも、 ほんの少し勉強し始めれば誰しもが必ずと言って良いほど魅力的に感じてしまうであろう、 不朽の銘種として名高いこのホシガメ。 甲羅に描かれる美麗な紋様は時代を超えて人々の心を掴んで離さず、 年を追う毎に次から次へと新たなファンを誕生させてきたその実力はもはや説明するまでもなく、 きっと多くの方が初めてのリクガメにこの種類を選びたいと考えるはずですし、 それを提供する我々としてもその願いは同じであると思います。 しかし現実はそう上手くはいかないようで、如何なる資料に目を通しても必ず一言、 初心者手を出すべからずの記述が添えられることがもはやお約束となっています。 しかしそこに書かれたことが本当に真実を表しているのでしょうか、 実際にコンディションの整った個体を飼育してみれば信じられないほどに良い動きを見せてくれますし、 それもそのはず、野生におけるインドホシガメの分布域は決して狭くはないどころか、 むしろ現地では野畑を荒らす害獣として煙たがられる場合もあるほど、 よく考えれば当たり前の話ですが厳しい自然を生き抜く逞しさを十分に備えているのです。 近年では輸送状態の改善も手伝って、 いわゆるピンポンよりもう少し育ったサイズであれば十分飼育に耐え得る状態が整っており、 それも性別が判断できるほどまでに育った個体であれば尚更。 当店でもスタートの一匹にご提案するケースが別段珍しくなくなってきた感があり、 思い切ってその扉を開けてみようというビギナーが年々増加しています。 今回やって来たのはとにかく探している方がむやみやたらに多く、 入荷しても毎回直ぐにいなくなってしまうのが恒例となったメス確定のこんな個体。 インドの飼い込みと言うだけで私たちショップにとっても非常に頼もしい存在な訳ですが、 不思議とオスが多いのかはたまた単に探している方が多いのか、 メスであることの事実が大きな付加価値を与えてくれます。 甲羅にややボコ付きが見られるものの十分許容の範囲内であると思われ、 艶に満ちた甲板に走るバンド模様は太めで見栄え良く、 体のイエローもすっきりとしていて色鮮やかな印象を受けることでしょう。 かつて甲長6センチぐらいの頃に拒食を経験し、 その頃に病院で受けていた強制給餌の際に嘴が破損する悲劇に見舞われたそうで、 少々ファニーな顔立ちになってしまったものの幸い採餌や健康状態には一切影響ありません。 水槽内を所狭しと駆け回りMazuriリクガメフードを食い散らかす元気いっぱいのおてんば娘、 成長した暁には是非とも産卵まで経験させてあげたいところです。 グッドサイズのメスではまず出ないロープライスにて! | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイカラー・♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 本人の美意識の高さにこちらが平伏してしまいそう! このレベルのクオリティにはそうそう出会えるものではありません、 インドホシガメ・メスが入荷しました。 今回やってきたのは、ホシガメが好きで一匹だけ単独で飼育を楽しんでいた方からの放出個体。 事情でやむなく手放されたそうですが変な思いの過ぎる所や心配な点などは一切ありません、 それは写真からでも伝わるはつらつとした様子で納得頂けると思います。 素朴なプロフィールですが良い個体は意外な所に潜んでいました。 まずこの極太バンド、一体誰のデザインによるものでしょうか。 そんなことまで考えてしまうほどに非ナチュラル、 直線を主体とした見慣れぬ雰囲気は他個体には容易に真似することすらできない芸当です。 そして大抵のインドホシでは背甲の模様だけしか注目を浴びませんが、ここはひとつ裏返して見てみましょう。 誰が勝手にこんなツルツルに磨いてしまったのか、 不自然極まりない表面の質感とはっきりとし過ぎた模様が不気味、 もはや生き物の柄では無いような気さえしてきます。 そしてもれなく着目しておきたい点がもうひとつ、肌の色。 見事な城に住んでいるのは上品なお姫様でなくてはいけません。 しかしどうでしょう、中から現れたのは全身オレンジの息を呑むような素晴らしいお姿でした。 背甲、腹甲、体、三位一体の贅の限りを尽くした一点ものです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (ハイカラー・♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 大宇宙の意志を体中で表現した奇想天外なカラーリングに直視するのも憚られる絶世の美女! 並のスペックでは何をどうしても再現不可能な天性の素質に行き場の無い嫉妬心さえ芽生える、 インドホシガメ・メスが入荷しました。 その名の通りペットトータスの世界におけるスターとして絶大な支持を集める、 リクガメを愛する者にとって無くてはならない永遠の人気種として知られるホシガメ。 本種がそこまでの地位を確立することになった最大の要因は、 捉え方によっては暗い過去でもありますが長きに渡り商品として大量に流通した結果、 良くも悪くも他に類を見ないほどの強烈な知名度を獲得することになり、 その余波が今もなお継続して影響していることだと考えられます。 最近ではいよいよ現地からの輸入量も減少の一途を辿っており、 輸入許可を取得するのに相当苦労させられるとは輸入に携わる人々からの生々しい経験談ですが、 時折国内での繁殖例も聞かれるとは言えまだまだその莫大な需要を満たすほどでは無いと言うのが現状です。 かつてそれなりに成長したものも含め野生個体がしばしば出回っていた頃、 ふと気が付けば平常見慣れない風変わりなタイプが散見されることもあって、 あくまでも噂話の域を出ませんでしたが何かの地域変異では無いかと話題になったのも懐かしい、 古き良きあの時代にタイムスリップすることができればとどれほどの人々が願ったでしょうか。 今回やって来たのはその姿を拝むや否や思わずひっくり返りそうになってしまうほど、 記憶の奥底から掘り返してみれば確かにこんなタイプを見かけたことがあるような気がする、 リバースパターンなどと称して紹介されていた伝説の一匹。 甲羅全体を彩るバンド模様の太さについては余計な説明を付け加えるまでも無く、 腹甲の大部分までもが黄色く染め上げられていることで説得力は十分、 頭部の地色は妙に白っぽくそもそも生まれつきの姿からして異質であり、 体全体の赤味の濃さにも幾多のマニアを唸らせるだけの訴求力が感じられます。 ご承知の通り探して見つかるものでは無く狙って入手することは無理難題、 本当にたまたまとある愛好家の下で長年暮らしていたお宝の掘り出し物で、 単にコレクションとして扱って下さっても構いませんが、 この素晴らしさを後世に伝えるべく何とか繁殖に漕ぎ着けることができれば本当に素敵だと思います。 正真正銘のオンリーワン! | ||||||||||
|
インドホシガメ (アダルト・♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| お待ちかねのブリーディングサイズ! こんもりと盛り上がった甲羅が長さ以上にボリュームを感じさせます、 長期飼い込みのインドホシガメ・メスが入荷しました。 ベビーから手の平サイズまで多くの個体が流通するホシガメですが こういった繁殖も間近の特大サイズとなると途端に数が減ってしまい、 また探している方が多いのもこのクラスではないでしょうか。 ベビーサイズから飼い込まれた割にとてもナチュラルなフォルムに育っている辺りも嬉しいポイントです。 さすがにここまで人の手で育てられただけあってコンディションも非常に安定しており、 今回屋外での撮影でしたが地面に置くなり歩きはじめ、 しっかりと腹甲まで持ち上げて歩行する健脚さも伺えます。 このメスに乗れる大きなオスを見つけるのも難しいかもしれませんが、 大きなメスもそうおりませんのでお探しの方はいる時に手に入れておいた方が良いかもしれません。 5月に入ってようやく陽気を感じられる気候になってきましたので、 これからリクガメ飼育も熱くなってくると思います。もちろん餌食い良好の素晴らしい個体です。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (特大ハイカラー・♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 文字通りスターの座を射止めるに相応しい稀代のスーパー優等生! 特大ボディにゴリゴリの極太ラインで描かれた眩いばかりの星型模様がくっきりと目に焼き付いて離れません、 インドホシガメ・メスが入荷しました。 今まで一体何匹の個体を見てきたのだろうか、 そしてこれからも変わらず同じような時を過ごすことができるのだろうか、 この姿を目にするといつも必ず頭の中にこのことが思い浮かびます。 今現在飼育が続けられている個体も含めるとそれこそ星の数ほどのホシガメが日本にやって来たことでしょうが、 私たちはその一匹一匹に特徴を見出してはバリエーションの豊富さをたっぷりと味わってきました。 人の欲求とは飽くなきものですから興味関心があるというのはもちろんのこと、 目の前に実物が現れ続ければその度合いは限りなく高まっていくようで、 知らず知らずの内に自分の意識の中でホシガメに対する願望が膨れ上がっていくのもごく自然な行為だと考えられます。 今回のメスを前にして咄嗟に連想されるのは夜空を彩る打ち上げ花火、 それもとびきりの大玉が惜しみなく何発も盛り込まれた何とも豪勢なデザインで、 今日まで嫌と言うほどの数を見てきているのに、 いえむしろ数を見てきたからこそ自らの経験に裏打ちされた確固たる信念を以って、 改めてこの個体の素晴らしい部分を素晴らしいと真っ直ぐに評することができます。 ただしこのままではいわゆる太バンドという括りに収まるのみでそれ以上の発展がありませんので、 今度は全体の色合いに着目してみましょう。 ホシガメは何色ですかと問われれば、恐らくほぼ全ての人が黄色と黒色のリクガメですと答えると思います。 しかし実際には大きくなるに連れて色褪せてしまうことも多く、 黄色味が失せてはこちらの気分も白けてしまいますから、 この基本に忠実な所もまた高評価に繋がっていると言えるのです。 そして最後に触れておきたいのはこの大きさ、写真では何の気なしに片手で持ち上げているように見えますが、 実はこれがかなりの重労働で伊達に当店過去取り扱い最大サイズに並んでいるだけのことはあります。 しかも現時点でまだ新しい成長線が伸びるのを止めず、 さすがにこれにはぶったまげましたが国内にはより大きな猛者が眠っているという話も耳にしますので、 この巨大なメスも年齢を重ねていずれは下克上と意気込みたいところ。 美血統という名目で種親候補にするも良し、純粋に美しさを独り占めするも良し、 これほどのハイクオリティであればどちらに転んでもきっと貴方を満足させてくれること請け合いです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂・♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
|
ピンポン玉の恐怖から脱してなお可愛らしく更に性別まで分かってしまうある意味究極のベストサイズ!
成長の程度が良くそれでいて線の入り方や色彩のメリハリに拘ったセレクト揃いです、
インドホシガメが入荷しました。
カメという生き物は世間一般においても非常に認知度が高く、
大概の人がその名前を聞いただけでおおまかなシルエットを思い浮かべることができると思いますが、
それはあくまでもミドリガメやゼニガメに限った話。
ウミガメは飼育ができないためここでは除外するとして、
リクガメというそのたった四文字を目にした途端、
急にエキゾチックな感覚に襲われるのも無理はないでしょう。
実際にそれらの仲間は日本には棲息していませんし、
カメが主に陸上を歩行しているという光景にはとびきりの異国情緒が漂うようなのです。
それでは皆さんにとって最も素晴らしいと言えるのはどのようなリクガメでしょうか。
もちろんその答えは千差万別ですが模範解答例をいくつか挙げるとすれば、
世界で最も美しいとされるホウシャガメ、世界で最も大きくなるゾウガメなど、
いかにもな種類が瞬時にラインナップしてきます。
しかしここでよく考えたいのは実際に飼育ができるのか否か、
ホウシャはCITESⅠなので潔く諦めた方が良く、
ゾウガメは飼育するための条件があまりにも人と環境を選び過ぎてしまうため、
リクガメが好きな人全員が賛同するには無理が生じてしまいます。
そこで今回は伝統的な慣習に倣い、
言わずと知れた人気種であるこのホシガメを再度プッシュしたいと思います。
今更声に出して騒ぐようなことではないと感じる方もいるかもしれません、
ですが良いものはやはり良いというこのやはりとは、
改めて実物を前にした時に改めて沸き上がる感情をそのまま表しており、
かく言う私自身もお馴染みの見慣れたキャラクターなだけに再びその魅力を実感している所です。
今回はまとまった出物の知らせを受け、
その中から色柄や形状に妥協せず質の高い良品ばかりをピックアップしてきました。
まず初めに考慮したのは各個体の大きさ、
小さなサイズが敬遠されがちなのはもちろんこちらも承知していますが、
あまり大きいと今度は育てたいという気持ちを蔑ろにしかねないため、
まだまだベビーの感覚を残した安心サイズを選出。
カラーリングについてはラインと地色のコントラストを大事にし、
イエローからオレンジまで好みに合わせて選べるようにしてみました。
もちろん線の太さや本数も重要なポイントになってくるでしょう。
最後にまさかそこまでは期待していなかったのですが、
現状で何とか雌雄も判別できたのでいきなりペアが組めてしまう贅沢チョイスも可能です。
リクガメを飼うのは暖かくなってからにしようと考えていた貴方、
一旦その作戦を白紙に戻して今一度ご検討してみては如何でしょうか。
店頭の場合はスタートに必要なフルセットも詳しくご案内致します。
オス:背甲 ・腹甲 メス:背甲 ・腹甲 | ||||||||||
|
インドホシガメ (♂・♀) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| カッチリ甲羅に四肢をグッと伸ばして歩き回る飼い込み安心サイズ! 興味深い2匹をセレクトしてみました、インドホシガメの入荷です。 今も昔も変わらずリクガメ人気ナンバーワンはこのホシガメ。 野生では景色に擬態しているという言われも怪しく思える、 明らかに派手な様相は我々の心を掴んで離しません。 聞いたところではこの柄が草原に生える草に溶け込むのだそうで、 いまいち信用できませんがペットとして楽しむに飾り立てが豪華なことには何の不満も無くむしろ有難いぐらいです。 その昔は人気は高くとも飼育が難しいリクガメの代表を務めていましたが、 最近ではベビーサイズでも輸送状態が良くなり初期状態に悩まされることも少なくなりました。 しかしそれでもなお安心して飼育を始めたいという方はこのサイズからどうぞ。 今回やってきたこの2匹、早くもペア確定ですがあえてバラでご紹介します。 メスはパッと見て優等生、 太いラインに体の黄色い面積も大きく何より甲羅の形が尋常ではないほどに綺麗です。 ビルホシではあっても インドホシでここまでパーフェクトなフォルムは珍しいでしょう。 オスは明らかに体のオレンジ色が濃く、 甲羅はなんとなくビルホシ風のライン取り。 顔や四肢に入る黒斑も変わっていて、 特に頭頂部の黒くなった様子はこんなことを言うと怒られそうですがホウシャみたい。 この発言に他意はありませんが個人的に気になった個体なので連れて来ました。 一応ペア割も効くようにしておきますが、両者とも見事に異なった個性を発揮していますので拘りません。 餌食い抜群、足取り軽やか、あとはお好み次第です。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (Pr) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 安心サイズでいきなりペアを揃えたいという方へ! まるっきり似たもの同士で組んでも面白くないのでそれぞれ個性の光る個体を選びました、 インドホシガメ・ペアの入荷です。 ホシガメがホシガメとして販売される場合その殆どはベビー、 いわゆるピンポンサイズと呼ばれる大きさで見かけることが多く、 とにかくこれが厄介でそれこそ昔は飼うべきではないとまで言われてしまう程でした。 しかしよく考えればそれも当たり前のこと、 生まれたばかりの赤ちゃんを海の向こうまで飛ばすというのは実に大胆な作戦です。 かつての消費的な売買には疑問の声も多く、 ここ最近では量より質という感覚で初期状態の良いものが増えてきました。 それでも一旦染み付いてしまったイメージはなかなか拭い切れず、 今でもホシガメはある程度育ったサイズから始めるのが良いと言われています。 今回はその有難い忠告にどんぴしゃの2匹をご紹介、 幼体時の可愛らしさと成長に連れて備わる頑丈さを兼ね備えたナイスサイズです。 小さな方から紹介すると、メスはベビーのフォルムをそのまま踏襲したこんもりと丸い形状で、 この調子でボリュームのある体格に育っていくことでしょう。 ラインは本種らしい派手な色使いに、 ぶつぶつと所々が途切れた感じもまた面白いです。 そして現時点で大きな方がオス、こちらは早くも細長く男らしいスタイルの原型が出来上がりつつあり、 上から見ただけでも性別が判定できてしまいます。 体もメス以上にオレンジが強く、 このサイズまで赤みが維持されていれば将来的にもこの調子でいくのではないでしょうか。 そして個人的に気に入っているのは甲羅の柄、 しっとりと落ち着いたラインの色調と多すぎない本数がそう見せるのでしょうか、 間違いなくインドホシガメなのですがどこかビルマ風の味を出している所が面白いです。 かわいそうという訳ではないけれども何となく1匹だけでは寂しい、 という方は繁殖を狙うかどうかは別にしてまずはオスとメスを一緒に飼ってみては如何でしょうか。 現在のサイズ差は後々逆転するのでさほど問題にはなりませんし、 それぞれ違う見た目なので単に2匹いるだけでも楽しいです。 甲羅の成長具合に文句なし、入荷後ある程度店内でストックしていますのでコンディションにも不安はありません。 | ||||||||||
|
インドホシガメ
Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 飼育開始に丁度良い、いわゆるピンポン玉サイズから大分育ったホシガメが入荷しました。 今回性別はペアですが、片割れはいるがペアがなかなか揃わないという方のお声に応え、 あえて別売りでUPしました。写真ではびっくりしてしまっていますが餌食いも良く、何より凹つきが 殆ど無く育っているのが嬉しいです。ラインのタイプの雌雄で違い、オスはラインの数が多く、メスは ビルマホシガメを思わせる様なラインです。こういった個体差も飼育者を悩ませてくれて面白いですね。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (サブアダルト・Pr) Geochelone elegans |




|
|
||||||||
|
意外と性別確定サイズ、しかもペア揃っての紹介は少ないと思います。
インドホシガメ・ペアの入荷です。
今回は当店在庫のオスと、お客様飼い込みのメスが来たので無事ペアが揃いました。
夫婦揃ってピンポンサイズから大切に飼い込まれた個体達で、状態は抜群に良く普段から走り回りホシガメの常識を覆す
アグレッシブな優良ペアです。
近頃では大分飼育法が確立されつつあり、国内のブリーダーズイベントでも国内CBが登場した程です。
リクガメはいつ輸入規制がかかってもおかしくない状況ですから、今の内に特に人気の高いホシガメは
国内繁殖を確立する必要があるのではないでしょうか。このペアを大切に飼い込んで是非繁殖に挑戦して下さい。
寒い時期が続きますが、発送には専用発泡スチロール容器と長時間対応カイロを使いますのでご安心下さい。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (サブアダルト・Pr) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| お客様の下でベビーサイズから大切に飼い込まれいいサイズに育った、ホシガメのサブアダルト・ペアの入荷です。 オスはラインの数が非常に多い派手な個体。一方メスは、ビルマホシガメの様なライン取りで黒い面積の多い個体です。 このペアが凄いのは、(いい意味で)ホシガメらしくない所です。例えるなら地中海リクガメの仲間の様な、 あのシャキシャキとした動きを常にしており、ちょっと違和感があって気持ち悪いぐらいの元気さです。 日本の環境に完全に慣れてしまったのでしょうか、特に湿度に気を使う事もありません。 ガンガン交尾もしかけている非常に期待度の大きいペアです。 | ||||||||||
|
インドホシガメ (アダルト・Pr) Geochelone elegans |





|
|
||||||||
| 極美太ライン巨大ペア! 長期飼い込みの成せる業に素晴らしいとしか言い様がありません、 お客様委託のインドホシガメ・ペアが入荷しました。 古くよりリクガメ飼育を底辺から支えてきた不朽の人気種ホシガメ、 この甲羅の模様の美しさに目を奪われた人が過去どれだけいたのでしょうか。 そして今もなお小さなベビーが毎年輸入され、多くのビギナーからの支持も熱いリクガメ代表種となっています。 しかしながら育てるのは決して楽とは言えず、特にピンポンサイズと呼ばれるベビーからの生育はクセがあり 経験者でもしばしば苦労させられます。それ故か飼い込みの大きなサイズの個体を見かける事は少なく、 特に最終サイズに近づけば近づく程その稀少性は増すばかり。 今回はお客様の下でおよそ7年間大切に育てられたオスとメスで、 甲羅表面のツヤと肌質は写真で見ても長く愛情が注がれていたのが見て取れる見事なものです。 甲羅の形状も特別気になるようなボコつきは無く、 なんと言っても背甲のライン一本一本がとても太く入りたった2色でここまで派手になるかという印象を受けます。 オスは既にやる気満々でちょっと手に持って裏返すと直ぐにヘミペニスを出してしまう程。 メスは今もなお成長しており、20cm台の特大サイズまで育て上げるのも夢ではありません。 少なくとも普通に飼っているだけでかなり楽しめるのは間違いありませんが、是非この2匹で国内ブリードを目指して下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (国内CBベビー) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 俗にホワイトと称される美血統より得られた生まれた時から黄色味の濃さが際立つ国内CB! 輸入ものを遥かに凌ぐ肉付きの良さとキレのある動きが品質の違いを物語る、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 リクガメなる生き物はただそれだけで人目を引く力があるらしく、 日本人にとっては水の中にいる種類が普通のカメだと言うのであれば、 陸上を主な生活圏とするその名もリクガメは異国情緒に溢れ、 本人はただ移動しているだけのつもりでも歩くと言う行為にすら感動が生まれるようです。 加えてほぼ全ての仲間が草食であることもイメージアップに大きく貢献しており、 まるでサラダのように皿へ盛り付けられた野菜をむしゃむしゃ食べたり、 庭先へ放てばそこらの雑草も含めて自らの栄養としてしまう、 そんな光景には何の悪意も感じられず人を嫌な気持ちにさせないような効果もあるのでしょう。 このようにエキゾチック極まりないものをペットとして飼育するからには、 やはりいくらか憧れを抱いてしまうポイントがあって、 例えば大きなサイズへと成長することにより一段と見栄えが良くなりますし、 甲羅に描かれる模様が綺麗であればあるほど思わず他人に自慢したくなるなど、 飼い主に与えられる喜びの大きさは計り知れません。 決して種数の多くは無いグループながらホビーの世界には様々な選択肢が用意され、 しかしながら皆が喜びそうなポイントをいくつも備えているものは珍しく、 飼育対象種を選ぶ際に頭を悩ませることもひとつの楽しみではないかと思います。 今回やって来たのは国内で繁殖された色味の明るい個体で、 まだ幼く柔らかい甲羅が内側からはち切れそうなほど、 ブリーダーご本人により十分に体力が付くまで仕上げられた生後一か月ほどのベビー。 ヒョウモンガメほど大きさと美しさを兼ね備えたリクガメもいないでしょう、 ケヅメでは色合いが乏しくホシガメではあまりグッとくるサイズになりませんから、 まるで一般種として流通しているのが不思議なほど高いスペックを誇っています。 入荷当初は葉野菜のみを重点的に与えていましたが、 ようやくMazuriリクガメフードにも餌付いたためここへ掲載することになりました。 出だしの二週間ほど気を遣えば後は大丈夫だと思います、 心配な方はお渡し前にみっちりご指導致しますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 現地からの輸入ものながら幼体より日本国内で育てられたような品質に拍子抜けする絶品! どちらの個体も明色部の広さが際立つホワイトヒョウモンの原石とも言うべきハイクオリティ、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 ヒョウモンガメ、またの名をヒョウモンリクガメとも言いますが、 ケヅメやホシガメなどと並びこの業界に古くから居座る看板キャラクターのような存在で、 ペットに向いているか否かはさておき、絶対に手放すことのできないマストアイテムのひとつです。 こんな話を冒頭に持ってくるのはあまり本意ではないのですが、 前述のそれらに共通するのは総じて極端に高価ではないことであり、 その結果多くの人々の目に留まることによって票を集めてきた実績から、 色々な意味で人気種としての地位を確立するまでに至ったのだと考えられます。 言い方を変えれば、 更に稀少な種類でずっと美しいリクガメも他にいくらか知られているにもかかわらず、 このヒョウモンがそれでも主戦力として一線級の活躍を見せているのは、 そこに伝承された馴染み深さがあったからではないでしょうか。 いくら素晴らしいカメがいたとしてもそれが人々に知らされていなければ、 突如として目の前に現れたところであまり印象に残らない可能性もあり、 何十年と多くの人々の目に留まり続けてきたからこそ、 今もなお変わらぬ愛情を注がれる対象として過ごせているのだと思います。 今回やって来たのはその経緯から明らかに現地の養殖ものだと認識せざるを得ないはずが、 とてもはるばる海を渡って来たとは考えられないツヤとハリが体中から滲み出ている、 一言で言えばまるで国内CBのような安心感さえ見て取れる健康体の二匹。 正直なところ、有名であることと育て易いことは必ずしも一致する訳ではなく、 本種の場合は長らくお隣のケヅメと同一視されていたことが足かせとなり、 適切な環境を与えてもらえなかったことが災いしたため、 初期状態の悪さから隠れた飼育難関種として要らぬ悪評を積み重ねてしまったことから、 健康な個体が相対的に高く評価されるという妙な現象が起きています。 この二匹は入荷直後よりMazuriリクガメフードにも餌付き始め、 ほぼ理想的なスタートダッシュを切れているビギナーにこそお勧めしたい健康状態ですから、 憧れのヒョウモン飼育を何とか良き方向へお導きできればという願いを込めてご紹介する掘り出し物です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| はっきりとしたブラックに濃厚なイエロー、そして互いのコントラストが際立った将来有望個体! 入荷後の丹念なケアにより中身がぎっしり詰まった文鎮のような重さを獲得した文字通りの安心サイズ、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 リクガメと言えばそれに含まれる殆どの種類が茶褐色であることが多く、 これはある限定された棲息域にしか現存できなかったためと考えられ、 言い換えれば今日のリクガメは世界広しと言えどもその多くが近しい野生環境で生き永らえていることを意味しています。 しかしながらその中でも特に存在感を露わにしている通称柄モノと呼ばれるグループ、 即ち主に甲羅に対して美しい模様が描かれるものたちをそう呼んでいる訳ですが、 かの有名なホシガメが幅を利かせている中で昔から鎬を削ってきた、 ライバルのような関係性にあるのが一方の人気種であるこのヒョウモンリクガメです。 前述の通り使われている色彩は概ね黒色から黄色にかけてのグラデーションに収まる程度ですが、 あとはそれらをどのように生かしてデザインされているかが勝負どころで、 生まれたばかりの頃からおおよその雰囲気が見て取れるホシガメとは異なり、 こちらヒョウモンは成長するに従い真の姿が少しずつ明らかになる仕組みになっていて、 幼体の頃には知り得なかった個性が時間を掛けて花開くタイプなのです。 最大サイズやそれに伴うボリュームについては同じアフリカのケヅメに近しいものがあり、 質量の面でも見栄えの面でも色々な意味で育てる楽しみに溢れた、 ペットとしての歴史も長い今後末永く愛され続けるであろう必要不可欠なキャラクターなのです。 今回やって来たのは本種としては最も見かける機会の多い定番のスモールサイズで、 見た目に黄色と黒がバランス良く散りばめられそうな煌びやかな個体をセレクトしました。 俗にホワイトヒョウモンなどと称される明色部の目立つタイプは、 ただそれだけで人目を引く同種の看板のような存在ですが、 やはりベーシックに模様の多さを楽しみたい方にとってはこれぐらい黒味が強い方が却って好印象です。 輸入時のコンディションにより飼育難易度もまちまちですが、 この二匹については入店当初から明らかに体重の重さが感じられた上に、 葉野菜からMazuriリクガメフードへの切り替えも早く、 調子に乗って毎日餌を詰め込めるだけ詰め込んだ結果、 かなり重たくなりましたのでビギナー向けとさえ言える最高の状態です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 生まれた瞬間から人の手で育てられたような肉付きとキレの良さが嬉し過ぎる程良い安心サイズ! 明暗の違いは今後の成長に作用する重要なアイデンティティなのでお好みの個体をどうぞ、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 遡れば何十年と前の話になるのでしょうか、 きっと日本人で初めてこのカメを目にした人はさぞ感銘を受けたことでしょうし、 その衝撃の強さは未来へと語り継がれ今日の愛好家にとっても変わらない、 ヒョウモンガメだけに宿る唯一無二の魅力として末永く楽しまれていることでしょう。 リクガメらしさを象徴する天高く盛り上がった甲高のフォルムが何よりの特徴であり、 これがあるのと無いのとでは人気の高さが桁違いとまで言われる重要事項で、 それほどまでに人々はリクガメに対して背高のシルエットを夢想して止まないのです。 また甲羅に描かれる緻密な模様な和名の通り豹紋と呼ばれ、 アフリカの草原地帯を闊歩する彼らににとっては保護色となるのかもしれませんが、 私たちにとってはもっと直感的にお洒落な装いとして捉えられ、 世界中を見渡してもトップクラスに美しいリクガメのひとつに名を連ねる銘種と言えます。 最大サイズは流石に誰でも扱い易いコンパクトなものとは言えませんが、 かのケヅメと比べれば成長も緩やかで馬鹿力を暴発されるようなこともありませんし、 大きさと色合いに絶妙な存在感が漂う身近な人気者です。 今回やって来たのは鶏卵よりはやや大きい子どもの握り拳ほどのスモールサイズで、 最もよく見かけられる大きさながら最も需要のある定番のお年頃。 やはり殆ど野生に近い環境からはるばる来日して来るため、 初期状態の良し悪しに伴うリスクには敏感にならざるを得ないのですが、 四肢のパンパンに太った様子やバタつきを見ていれば無用な心配であることがよく分かります。 当たり前のことかもしれませんが成長線の伸び方も極めてナチュラルで、 ハッチリングに近いふわふわの状態では甲羅が変形し易いこともあり、 ある程度表面が硬くなったこの段階からであれば大きく崩れる不安もありません。 時に乾燥系だとされることもありますがそこそこの湿り気は必要で、 ある意味普通に扱っていれば綺麗に育てられると思います。 全体が黄色めの方を選ぶか、黒が多く模様が沢山表れそうな方を選ぶか迷いどころですが、 既にMazuriリクガメフードにも餌付いていて準備万端の二匹です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 未だ安心サイズに留まる幼体ながら模様の細かさに注目してセレクトした将来有望の二匹! こんなに素敵なリクガメが素敵なサイズ感で安定供給されているのが不思議なぐらい有難い定番種、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 世界中のリクガメを全て見渡したとして、 カメへの関心が薄い人でさえ美しいとの言葉を漏らしてしまうような種類はごく限られており、 そもそものコンセプトが色柄よりもシルエットや佇まいで勝負するタイプの生き物なのですから、 奇抜なデザインで他を圧倒しようといった発想に乏しいのも無理はありません。 そういった考えはそれ自体がむしろ贅沢であるとさえ感じられますし、 畑違いだという指摘があったとしても真っ向から否定することは難しく、 それでも神様がもし僅かでも甘えを許してくれるのであれば、 私たち人間にとって最も都合の良いかたちを目指したくなるのも当然でしょう。 中でもストレートで分かり易い例として真っ先に挙げられるのがホシガメの存在、 もう名前からしてナンバーワンにでも君臨しそうな勢いが漂っており、 用いられる色彩は黒色と黄褐色という極めてシンプルなものだったとしても、 あとはアイディア勝負といった具合で非常に優れた美貌を描き出しています。 それを踏まえた上でふとアフリカ大陸に目を向ければ、 色調こそ似通っていながらまるで異なる装いに身を包む、 恵まれた体格によって圧倒的な存在感を見せ付ける素晴らしいリクガメに出会うことができるのです。 今回やって来たのはヒョウモンガメの需要を満たす上では絶対に手放せない、 大き過ぎず小さ過ぎずの絶妙な体格に食指が動かずにはいられないお約束のスモールサイズ。 時期になれば必ずと言って良いほど見かけられる季節商品のようなものですが、 当店では初期状態のチェックから入店後の立ち上げも含め、 初めての方にも喜んでお渡しできるよう日々のメンテナンスに取り組んでいます。 この二匹はまるで文鎮のような重量感で到着し初日から餌食い良好、 既にMazuriリクガメフードにも餌付き始め体調面で何も申し上げることはありません。 見た目にも拘り明色部がはっきりとしているのはもちろんのこと、 現時点で模様の入り方が密になり細かく散らばっているものをチョイスしています。 飼育方法やセッティングに必要な器材、餌やサプリメントなど周辺のことは全てお任せ下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| リクガメ人気の秘訣となり得る要素を全て兼ね備えていると思われる嗚呼憧れの豹紋陸亀! すっかりくたびれて眠たそうにしていることの多い本種には珍しくアクティブでエネルギッシュなグッドコンディション、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 我が国におけるペットとして見た場合のカメと言う生き物が持つ潜在的な需要の高さは今更語るまでもありませんが、 最近ではミドリガメやゼニガメに代表される昔ながらの水棲ガメよりも、 エキゾチック感溢れるリクガメの仲間たちに視線が集まっているように感じます。 もちろんかつては飼育動物として扱い切れなかったと言う事実もあろうことと思いますが、 それとて先人らの経験と情熱があってこそようやく普通に育てられるようになった訳で、 何とかしてでも飼ってみたいと思わせる強い訴求力が備わっていてこその結果なのでしょう。 冒頭でも触れたリクガメがペットとして支持される所以を考えてみた所、 まず初めに思い浮かぶのはこんもりとしたシルエットに他ならず、 一匹のカメが持つ存在感を決定付けるあの佇まいに夢を抱く方も多いはずです。 歩く動作の擬音語としてはトコトコないしはノシノシなどが当てはまり、 餌欲しさにこちらの顔色を窺いながら近寄って来る際に見せる愛らしい表情、 そのキラキラとした瞳の輝きは残念ながらミズガメではなかなか真似できない芸当と言えます。 残るは甲羅のサイズから感じられるボリューム、 最後まで飼い切れるかどうかは別として大きなリクガメが家の中を歩き回っている、 そんな光景はカメ好きであればもれなく憧れてしまう夢のワンシーンなのです。 今回やって来たのは前述の素敵な条件を全て満たしていると言っても過言では無い、 過去何十年に渡りリクガメブームを先頭で牽引してきた不朽の銘種ヒョウモンリクガメ。 よく見かけるのは10センチを超えた拳大ぐらいのサイズか、 それよりも小さいと殆どピンポンサイズに近いベビーばかりなのですが、 この個体は大き過ぎず小さ過ぎずの何とも飼育欲をそそるちょうど良さで、 今まで興味が無かった人も思わず惹かれてしまう魅力があると思います。 背甲のデザインは成長してみないと分かりませんが、 比較的早い段階で適度に散らばり始めているこの雰囲気からすると、 やや白多めのスタンダードな出来栄えに仕上がるのではないかと予想しています。 ヒョウモンにありがちなビビリ体質では無く、 他種との同居にも耐え得るタフな精神力は写真からでも伝わって来るでしょうか。 葉野菜からMazuriリクガメフードまでもりもり平らげる屈強な一匹です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (シルバーアイリス) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 通常は真っ黒な瞳が可愛らしいヒョウモンガメですが、 この個体は鋭い目付きが格好良い、虹彩が明色に変異したまさかの稀少シルバーアイリス! ひとたび育て始めれば一生ものとも言える大型のリクガメですから、 他とは丸っきり違ったオンリーワンの特徴に惹かれてみるのも悪くないでしょう。 言うまでもなく餌食いなどに問題はありませんので、我こそはという方へ。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 色味の良さ、甲羅の高さ、初期状態の良さと三拍子揃ったものだけに拘って厳選した渾身の二匹! 最近は当たり年なのか見かける機会も多くなっているからこそ素敵な出会いを演出したい、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 長きに渡りビギナーズリクガメの御三家と言われ続けてきたギリシャ、 ヘルマン、ホルスフィールドの天下無双状態に待ったをかけるかの如く、 何だかこちらも同じく初心者向けのリクガメであるかのような顔をして、 しれっと店頭に並んでいることの多くなったヒョウモンリクガメ。 あまり好ましい表現ではありませんが妙にリーズナブルな価格帯で並んでいるが故に、 何となくハードルが低く手を出し易い雰囲気さえ漂っていますが、 実際には全ての人が終生飼い続けることが難しいと思われる種類であり、 と言うのもやはり30センチとか40センチという最大甲長については、 やはり扱い切れなくなる可能性が大いに考えられるものと思われます。 ただしそのようなボリュームについてむしろ大歓迎であるという方にとっては、 例えばケヅメやゾウガメなどに比べ遥かに現実的な選択肢となり得るでしょうから、 結局のところ一周回って見逃すことのできないキャラクターだと評価される訳です。 性格はどちらかと言えば穏やかで成長速度も同じく緩やかに、 リクガメの世界では決して多くはない背甲に見栄えの良い模様が描かれ、 全体のシルエットも俗に言うドーム型へと仕立てられる、 非常に都合の良い特長が惜しみなく搭載されそうなるべくして誕生した人気種なのです。 今回やって来たのは現地よりコンスタントにもたらされるスモールサイズの群れより、 冒頭で触れたポイントをきちんと重要視して私が直々にセレクトした二匹。 誠に残念ながらそんな条件を満たすことのできるものが僅か二匹しかおらず、 同等の性能を備えていれば沢山集めてきたいのはやまやまなのですが、 こればかりは殆ど野生のカメという状態で輸入されている以上仕方のないことです。 とにかく初期状態こそが飼育難度を全て決めてしまうほどに重要なのですが、 それだけに入店直後からMazuriリクガメフードを無遠慮に食べまくるコンディションを見せ、 日に日に体重が増加し続けているような状態でお渡しします。 まるで当たり前のように入手できる今のうちに迎え入れておきたい銘種です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 比較的大勢の中から、成長線に白色が強く出ているホワイトヒョウモン候補生を目ざとくチョイス! しかしヒョウモンガメは昔に比べて本当に初期状態が改善され、随分と育て易くなりました。 今日ではきちんと個体を選び、適切な飼育環境を与えれば、 たとえビギナーでも安心して付き合うことができます。 この二匹も、もちろんMazuriリクガメフードに餌付いた状態でいつでも準備オーケー。 やはり白いヒョウモンはいつでもリクエスト多数、お早めに! | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 甲板の継ぎ目から止めどなく噴出する黒がどのような模様を描き出すのか待ち遠しい! 飼い始めるにはベストなサイズと言わざるを得ない絶妙な可愛らしさと安心感を併せ持つ拳サイズ、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 一般家庭でカメを飼育するとなればミドリガメやゼニガメが当たり前だったのも今や昔の話、 いわゆる爬虫類ブーム真っ只中の昨今ではむしろリクガメの存在が急速に台頭して来ていると思います。 先人たちはその異国情緒溢れる姿に一度は憧れてみたものの、 やはり知識不足や適切な環境が満足に用意できないなどの現実的な問題に悩まされ、 最後にはどうしてもマニアの持ち物と称されて当然の珍獣のような存在でした。 しかし近頃では専門的な書籍が充実し始めているほか、 ウェブ上に公開された簡単な指南書から愛好家によるリアルな飼育記録に至るまで、 内容の正誤は問わないにしてもそれらを目にするだけでついつい欲求を刺激されてしまいます。 元々数が少ない上に商品としてまともに流通する種類も限られてはいるのですが、 そのような状況においても高い人気を保ち続けているリクガメが持つポテンシャルには本当に感心しきりです。 今回やって来たのは昔ながらの定番種としてよく知られた、みんな大好きヒョウモンリクガメ。 こんもり高々と盛り上がったお馴染みのシルエットに、 アフリカのサバンナやステップの景色を想起させる色柄は非常に受けが良く、 上品な小顔がつくる美貌に惹かれて誰しもが一度は目に留めるのではないでしょうか。 殆どの人がその最大甲長を知った時点で諦めてしまうと思いますが、 実際には仮に30センチまで育てるだけでも並々ならぬ時間と労力が必要であり、 40センチクラスともなれば日本全国探しても実物をお目にかかることができるかどうかという代物ですから、 少し気合を入れ直せば現実離れしているとも考え難いのです。 実は最近よく見かける本当のベビーサイズはなかなか育てるのが大変で、 それはよく言われるホシガメのピンポンサイズと同等かもしれません。 また少し育っていたとしても輸入直後では体重が軽いなどの問題点に見舞われ、 結局は如何にして初期状態の優れた一匹を選出できるかという点に懸かっているのです。 この個体は日本に入って来てから少なくとも一年以上は経過しており、 加えて店頭でもこっそり数ヶ月ケアを続けてきましたから、 よほど大幅に環境設定を誤りさえしなければいつか立派なヒョウモンガメを庭で歩かせることも夢ではありません。 大切なのは長期的にストレスを溜め込まないよう運動量を確保し、 特に冬場は呼吸器を守り体全体の潤いを損なわないためにも保湿に気を配ることなどですが、 具体的な解決策や抑えるべきポイントは別途詳しくご説明します。 ホワイト系よりも黒斑がびっしり敷き詰められたこってりブラック系をお探しの方へ、 明るい性格が持ち味のトコトコとよく歩く健康優良児です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 定番の拳サイズの中でもパッと見の色味の明るさと動きのキレに拘ってセレクトした美個体揃い! 背甲の明色部が黒い豹柄に負けじと存在感を主張しているホワイト候補生、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 人々がリクガメに対して求めるものには様々な要素が考えられますが、 その中のひとつにこんもりと盛り上がった大きな甲羅があると思います。 もちろん大きくなり過ぎるカメは飼えないと言われてしまえばそれまでなのですが、 反対に大きく育ってこそのリクガメと言うイメージは依然強く、 ただ目の前をのしのしと歩いているだけでついつい見入ってしまうものです。 またある種のステレオタイプとして背の高さが挙げられ、 天高くこんもりと盛り上がった甲羅こそリクガメとしての理想像である、 そんな風にお考えの方も多いのではないでしょうか。 ただしこればかりは冷静に考えると一部の種類にだけ許された特権であることに気付かされ、 それでも水棲ガメとは対照的なリクガメなる生物にこうあって欲しいと願う、 愛好家であれば誰しもが抱いてしまう憧れのようなものなのかもしれません。 その他にリクガメの人気を決定付ける重大な要点として色や柄の素晴らしさもまた忘れる訳には参らず、 時にアーティスティックなデザインが一目惚れと言う運命的な出会いを演出する、 そのような出来事も決して珍しいケースでは無いのです。 ここにご紹介するヒョウモンガメはリクガメの仲間で唯一と言っても良いほど、 先に並べた全ての条件をたった一匹で満たすことのできる、 非常に優れたポテンシャルを有するペットトータスの定番種。 得てして巨大に成長するカメには模様の類は期待できず、 或いは色柄の美しいカメに限ってどちらかと言えば小振りな種類が多い、 そんなジレンマを一気に解消してくれる素晴らしい逸材であると言えるでしょう。 嬉しいポイントは成長速度が決して早過ぎないことと、 その名の由来となった背中の豹紋は大きくなるに連れて次第に完成していくことの二点。 つまり早々に飽きたり持て余したりすること無く長い間じっくり時間をかけて楽しめる、 そんな風にして小さな喜びをコツコツ積み上げていく趣きが詰まっているのです。 今回は数ある中から各甲板の白い部分が大きい個体をチョイス、 地色がほんのり黄色味がかったタイプと、 一見似ていますがより白さを際立たせたタイプがいますのでお好きな方をお選び下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 最も重要な見せ場となる豹柄がびっしり描かれそうなブラック強めのスタンダードタイプ! こんもりシルエットでトコトコ歩くリクガメに求められる二大要素を兼ね備えた不動の人気種、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 ペットとしてのリクガメがすっかり普及し早数年が経ちますが、 未だに育てていく上での悩みや心配事が尽きることは無く、 それでもなお新たな飼育志願者は増加の一途を辿っているようで、 ここにリクガメの仲間が秘めたる底力を感じて止みません。 これから飼育を始めようと言う場合にも大きく分けて二種類、 失敗を避けるためにいわゆる飼い易さに着目して種類を選ぶ方法と、 それとも己の欲望に忠実な一番欲しいと思った種類を選ぶ方法とで、 大体どの辺りに落ち着くかは初めの内に決まっているような気がします。 後者の存在自体がまだまだ根強いリクガメ人気を象徴しているかのようで、 特にこのヒョウモンや近縁種のケヅメなどはそうして選ばれる代表的なキャラクターであり、 両者に共通しているのはやはり大型化への夢に他ありません。 しかしながら同じく大型種とされるヒョウモンにあってケヅメに無いもの、 それは何よりも絶妙なお淑やかさであると考えられ、 あの破壊衝動の塊のようなケヅメを長年扱い続けるのはなかなか骨折りなのですが、 本種はどちらかと言えばナイーブで繊細な中身の持ち主ですから、 上手に付き合えば人とカメとがお互いにぶつかり合うこと無く飼育することができると思います。 今回やって来たのは最もよく見かける安心サイズながら、 輸入されたてでは無くしばらくの間国内で飼い込まれていた個体。 黄色味が強く暖かみのあるボディと、 成長線の隅々まで黒斑に覆い尽くされたこってりとした色合いが印象的な一匹で、 いかにもヒョウモンガメらしい模様の密に入ったタイプに仕上がると考えられます。 頭と四肢がすっぽりと甲羅に収まるデザインをしているため、 シャイな性格だと持ち上げただけで閉じ籠ってしまう場合もありますが、 この個体は良好な写真写りが明るく朗らかな雰囲気を表しています。 Mazuriリクガメフードの他、 葉野菜や野草の類もバランス良く与えて綺麗に育つようケアをしていますので、 初めての方にも安心してチャレンジして頂きたいと思います。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| ふたりまでならギリギリ手の平に乗せられる定番であり一番欲しいスモールサイズからの特選個体! 何が特選かと言えば初期状態から餌食いまで完璧な仕上がりでMazuriリクガメフードを爆食している、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 何となく湿っぽい雰囲気からスタートするのは本意ではありませんが、 昨今のヒョウモンガメを眺めているとその陰にチラリとよぎるのが、 今やその姿を拝むだけで精一杯とでも言わんばかりに稀少になってしまったホシガメの存在。 柄モノのリクガメという必ず欲しい人がいるジャンルの定番キャラクターであり、 リクガメのことをそもそも知らなかった層に対しても猛烈にアピールできる、 業界としては絶対に手放してはならなかった逸材中の逸材でした。 そのすっぽりと抜けたかに見えた穴をできる限り塞ぐべく白羽の矢が立ったのが、 もしかしたらこのヒョウモンなのではないかと最近では考え始めるようになり、 あちらホシガメの方がより顕著ではありましたが、 こちらもまたかつて輸入状態が芳しくなかった時代が長く続いていたため、 正直あまり良い印象を抱いていない方も少なくないと思います。 またある程度大型に成長することもホシガメとの違いで、 しかしそれについては大きくなることを歓迎する向きも強まっているため、 一概にデメリットとは言えずむしろメリットになる場合も多いようです。 最近では飼育方法がある程度解明され、 日本に到着したばかりのコンディションもいくらか改善されたお陰で、 ようやくペットとして普通に育てられるだけの土台が整ってきた感があります。 今回やって来たのは指で押してもカチカチの甲羅が嬉しい安心サイズで、 当店に入荷して間もなくというタイミングではなく、 バックヤードでしっかりとキープしてからアップしてみました。 どれだけ元気そうに見えても最初の頃は餌を選り好みするものですが、 この二匹は初めての給餌より前述のMazuriをいきなり口にしてくれたため、 その後は立ち上げという表現が不適切なほど良好な暮らしぶりを展開しています。 成長はゆっくりなのでいきなり大きなケージを要する訳ではありませんから、 将来的に大きなリクガメをと夢見る方にはうってつけの有効な選択肢です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| ケヅメと並んで人気の高いアフリカ系のリクガメです。お客様飼い込みのヒョウモンリクガメの入荷です。 和名の指す通り成長に連れ甲羅に細かい豹柄が現れる、柄モノ系の種類です。 やっぱりリクガメはこんもりとした甲羅が魅力的! という方はまさに好みのタイプでしょう。 生まれた時から既にハイボディで、 大きな野生個体などの写真を見ると一つの山の様に盛り上がった甲羅に驚かされる事だと思います。 やはり大きくなる種類ですので飼える人も限られてしまいますが、 夏の間に外でたっぷり歩かせればスクスク大きくなってくれます。 基本的に丈夫な種ですが実はベビーから育て上げるのは一苦労だったりしますが、 今回はちょっと恐いサイズをクリアした拳サイズの2匹ですので、 これからの成長がますます楽しみです。夏の多湿に弱いとも言われますがそんな苦手な季節ももう終わり、 寒い季節は屋内でぬくぬくと、暖かくなったら外の太陽光の下で野草などをたっぷりあげるのも待ち遠しいですね。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト・S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 肝心の豹の紋が何処にも見当たらない辺り一面が柔らかな乳白色に包まれたパラドックスビューティー! 黒のまとまり具合が出だしから快調の美個体で目指せホワイトヒョウモン、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 カメはどのような仕組みで育っていくのか、それを説明するためには成長線という言葉が欠かせません。 初生甲板と呼ばれる、卵の中でカメとして形作られた時に初めから体を覆う甲板は、 その一枚一枚が周りへ広がるように伸びていくことで体全体を大きくし、 その新しく伸びた部分のことを私たちは成長線と呼んでいます。 全身が単色で特別柄のないカメについては単に成長するためのものという意味合いだけにしか過ぎませんが、 反対に甲羅に柄のあるもの、千差万別多かれ少なかれバリエーションを持つカメについては尚更、 線の伸び方は柄の出方という見方に変わりその注目度も一気に高まることでしょう。 成長の過程とは即ち個体のアイデンティティを形成する過程であり、 その神秘的な出来事が目に見えて実感できるとなれば関心を持たないでいられるはずがありません。 本種の場合、第一印象として目で見て確認することができるのは太い枠線とランダムに表れた黒斑のただそれだけであり、 その後の姿は実際に育ち始めることで次第に分かってくるという、 まるで印刷機が白い紙に情報を打ち出していくかのような期待と不安が入り乱れるメカニズムとなっています。 特にヒョウモンは黒く出た部分がばらばらと分散するように模様を描き出していく手法を採るため、 最終的な完成図は本人すらも把握できていないのではないかと思わせるほど、 本当に最後の最後まで成長のステージを堪能することができると思います。 今回やって来たのはベビーから飼い込まれ手の平ちょうど乗るようになった安心サイズの個体、 単純にそう紹介してしまえばさほど珍しさを感じることもなかったのですが、 あえてこちらから申し上げなくとも他とは違う何かしらのオーラは感じ取って頂けたことでしょう。 誰がどう見ても明色部の面積が広過ぎるというのは一目瞭然で、 そうなってしまった原因には豹柄の元になる黒色が周りの仲間を巻き込み凝縮し過ぎていることが挙げられます。 ベースになる色質で勝負するのも大切なことですが、 ホワイトヒョウモンとして美麗な姿に大成するためには協力者の力添えが必要不可欠であり、 普段は上から覆い被さっていたまだら模様がこの場に限り主役の座を譲ることで、 下で控えていた真の英雄が雲間から覗くように燦然と光り輝くのです。 ハッチリングの時点では予想だにしなかった秀逸な特徴であるだけに、 本当の意味で掘り出し物と言える最高の素材を、貴方の手で最高の形に仕上げていって下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| ワイルド由来の見事なまでに美しいフォルムと飼い込み故のコンディションを兼ね備えた特選個体! 成長線を埋め尽くすように塗りたくられた黒色の多さも要チェックです、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 我々がペットショップなどで普通に見かけることができるリクガメの中で、 最も美しい形を持つ種類と言っても良いかもしれません。 何しろカメに対して真っ先にイメージされるこんもりとした甲羅と言うのは、 実はごく限られた種にのみ与えられた特権のようなものであり、 残念ながら皆が皆そのような形をしているとは限らないからです。 しかも本種の場合はふっくらとボリュームあるシルエットの割に小顔ですから、 相対的に大きく見える甲羅が欲しかった高さをより稼いでいるようにも見えます。 模様も綺麗な上にどちらかと言えばリーズナブルに入手することができますから、 時に誤って入門種として紹介されることもあるようですが、 初心者にとっては鬼門とされるかのホシガメに匹敵するほど気難しい場合もあり、 特にピンポンサイズが労せずして普通に育てられるケースは悲しいかな決して多いとは言えないでしょう。 まだまだ野生個体の多いヒョウモンはこのような安心サイズでさえも初期状態を崩していることが多く、 結局はそれを立ち上げ切れずに残念な思いをしてしまうこともしばしば。 お店側としても普通に飼育できる個体をご案内することができればと常々考えさせられますが、 本日ご紹介するのは恥ずかしながら店頭で数ヶ月の飼育期間を経てホームページデビューが決まった一匹です。 どうしても状態に不安のあるリクガメをご案内するのに抵抗があるため、 個人的に納得できるレベルまで仕上げるのには結構時間が掛かってしまいました。 かなりしぶとく面倒を看た甲斐あってMazuriリクガメフードを美味しそうに平らげるまでになり、 ケージ内をトコトコ歩く姿を見ればあの時の塞ぎ込んでいた気配は一切無く、 同じ空間に同居人がいても全く気にせず自分のペースで暮らしを立てられるようになりました。 色柄についてはまだまだどのようになるのか分かりませんが、 かなりの度合いで黒が多めな配色が将来どのような豹紋を描き出すのか非常に楽しみです。 憧れのリクガメとしてよく名前の挙がる人気種なだけに、自身を持ってピーアールしたいと思います。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| ホワイト強めのカラーリングにハイドームと皆さんに喜ばれそうな要素ばかりが目立つ特選個体! 高密度な肉付きを表す十分な体重に加えダッシュ力と餌に対する貪欲さにも自信あり、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 リクガメの飼い方がひよこ電球に猫の砂とレタスだった黎明期とされる時代より、 ザ・リクガメとも言うべき代名詞的な存在感を発揮し続けてきた往年の人気種。 種類問わず全てを乾燥させて飼うべきなどはちゃめちゃな情報しか無かった頃、 私たちは完全に見た目だけでそれらのカメを評価していたのだと思いますが、 黙っていてもリクガメだと分かる天高く盛り上がった甲羅を背負い、 そこへ描かれたサバンナの草原地帯を思い起こさせる豹柄に一目惚れする人が後を絶ちませんでした。 その当時より積み上げてきた知名度と支持率は未だ衰えることは無く、 多くの愛好家にとって憧れのヒョウモンリクガメであり続けることに変わりはありません。 自然界では抱え上げるのも困難なほど巨大に成長することになっていますが、 現実的には飼育下で30センチを超えれば御の字、40センチクラスにもなると稀少性が極端に増すなど、 意外にも何とか屋内のケージ飼育のレベルでやり過ごせてしまう辺りに、 この先ペットとしての需要について更なる将来性を感じて止まないのです。 今回やって来たのは状態のよく分からない輸入されたてのものとはまるで異なる、 一年以上の飼い込み期間を経て良い意味で野生を取り戻した活力溢れる一匹。 甲羅の成長線が飼育下でも再び伸び始めているだけでもう安心なのですが、 それ以上に足並みの軽やかさや誰よりも早く誰よりも多く餌を平らげようとする姿勢に、 厳しい野生を生き残るためのしぶとさと逞しさを改めて感じさせられました。 色合いは模様の隙間から覗く明るめのクリームホワイトを基調とし、 黒色は全てを埋め尽くすこと無く絶妙な配分にまとめられているため、 斑紋がバランス良く散りばめられそうなスタンダードかつ平均以上の美しさを実感できるデザインに仕上がりそうです。 同大陸に暮らす屈指の強健種ケヅメを引き合いに出されることもありますが、 実は本種の方がずっとナイーブで初期状態には殊更気を配る必要があり、 初めに受けた第一印象をとにかく重要視して頂きたいと思います。 体質の強弱など生まれつき備わったポテンシャルを含めれば、 こういった当たり個体は決して見逃すべきではありません。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 拳大のサイズにて細かな豹紋が早くも散らばり始めた今後の成長に期待のスタンダードビューティ! 色も形も教科書通りの分かり易く綺麗な個体に仕上がることを願って止まない、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 リクガメと呼ばれるジャンルはあたかも大きなグループであるかのように扱われ、 実際に爬虫類飼育者の中でも明確に認知されているひとつの集団であるには違いないのですが、 分類上の話をするとあくまでも広義のカメに内包された少数派に過ぎず、 更には現実的に飼育可能な種類と言えば数えるほどしかありません。 これはリクガメと言う名の特殊な一群が多くの場合ある特定の環境でしか生活することができず、 地球中の殆どの大陸に分布しているもののどうしても似通った形質に収束するためなのですが、 ペットとして見た場合にもそれほど豊富なキャラクター性を有している訳では無いため、 全体的に一様な特徴を示す結果となってしまいがちです。 そこで一際目を惹く強い個性となり得るのが柄モノ、 おおよそ黒色から茶褐色で構成された配色のいくつかのカメを並べた場合でも、 何かしらの模様が描かれていればただそれだけで個性が発揮できるチャンスとなり、 飼育対象として捉えた場合には殊更魅力的に映る傾向が見られます。 つまり身体の何処かに何かしらの意匠が施された種に対して人気が生まれるのは必然的なことであり、 彼らこそリクガメ飼育の文化を根底から支える重大な責務を担っているのです。 今回やって来たのはホシガメなどと同じくナイーブな性質が多々見られる本種には珍しい、 餌食いから運動量に至るまで中身が別のカメではないかと疑いたくなるほど、 健康が甲羅を背負って歩いているかのような生来の元気印。 現地からの輸入個体に多いちょうど拳ぐらいの大きさから幾分成長し、 飼育開始のスタートダッシュで甲羅に歪が生ずることも無くスマートな育ちぶりで、 どの角度から見ても美しい曲線を描くシルエットはお見事。 歩き方にもワンポイントあり、 四肢を垂直に立てるその姿勢は人に例えるのならヒールを履いたような、 甲高なフォルムをより一層強調すると共に健康であることの何よりの証となるのです。 同居している他個体にも動じない図太い神経は嬉しい限り。 高く幅広く盛り上がったドーム状の背中がヒョウモンならではの存在感を主張する、 この先も順調に大きくなること以外考えられない特選個体です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S・M) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| お互いが全く違うベクトルで活躍する姿が目に浮かぶブラックアンドホワイトセレクション! ものの見事に白黒はっきりと分かれた光景に個体差の大切さを改めて感じさせられる、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 我ながら何を今更と思うほどペットシーンにおいてはもはや常識となっていますが、 ホビーとしてのリクガメを語る上で絶対に外すことはできない主要キャラクターのひとりとして、 長きに渡り凄まじい存在感を放ち続けてきた業界の立役者であるヒョウモンリクガメ。 ヒョウモンと名の付く生き物は数あれど、 どちらかと言えば色柄に乏しいと言わざるを得ないリクガメの世界においては、 その華やかな雰囲気が持つ付加価値の高さが相対的により大きなものとなり、 異様なまでに豪華で贅沢な仕上がりとして感じられるのは決して気のせいではありません。 たった二色の絵の具だけでここまでやれるものかと感心し切りですが、 それはきっと人の手が加わらず自然な状態で出来上がったものだからこそなのだと思います。 最近では同様の理由で一世を風靡してきたホシガメの仲間が途端に姿を消し、 いくら需要があったところでなかなか思うように入手できないこともあって、 より一層このヒョウモンガメのニーズが高まっているものと考えられます。 もちろん最終サイズなど基本スペックに異なる部分はありますが、 柄物のリクガメというのは実のところ選べるだけのバリエーションがなく、 皆の視線が一点に集中してしまうのも無理はないのです。 今回やって来たのは初生甲板よりもずっと成長線のデザインが強く主張し始めた安心サイズから、 殆ど隙間なく黒斑に埋め尽くされたなかなか見かけられない黒々としたタイプと、 一方で明瞭な黒斑とその隙間に映える地色とのコントラストがはっきりとした白っぽいタイプ、 それぞれがそれぞれの方向性で際立った個性を見せる素敵な飼い込み個体。 こればかりは良し悪しと言うよりも好みの問題と言わざるを得ませんが、 こんな面白い組み合わせで片手の上に並べられる機会もそうそうありませんので、 一風変わった個体をお探しの方にとっては絶好のチャンスだと思います。 どちらもMazuriリクガメフードを顔面に押し付けながら爆食しており、 ずっしりと重く高い密度を以って飼い主を安心させてくれるコンディションの持ち主です。 状態の整った小さめサイズはいつも人気なのでお早めに。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| ヒョウモンだからこそ分かる育った個体の安心感! 初めての方もそうでない方も是非このサイズから、拳大に育ったヒョウモンリクガメが入荷しました。 アフリカ大陸を代表するリクガメと言えばケヅメと並びこのヒョウモンが挙げられます。 名前を並べると語呂が良いからかケヅメ、ヒョウモンという順番になりがちですが、 それはこの二種間の人気の差をも表しているのでしょうか。 大人になった姿を見比べてみるとケヅメは柄なし、 ヒョウモンは柄ありとその軍配はたやすく後者に傾きそうなもの。 しかしペットショップという実際の現場で見かける彼らはその殆どがファーミングハッチのベビーであり、 その段階で比べてみるとケヅメはもちろん無地のあっさりした容姿ですが終始よく動き、 ヒョウモンはどちらかと言うと大人しめで肝心の柄もぽつぽつと斑点があるだけと、 どうしても人目を惹くパワーに欠けてしまいます。 実際問題、神経質ともとれる臆病な個体もいてケヅメとは全く別ものとして考えなくてはいけませんが、 対決する相手があまりに悪かったとも言えるでしょう。 ライバルは屈指の強健さを誇る種類ですし、 ヒョウモンも育ってしまえばそこは過酷な乾燥大地で暮らすリクガメ、 ベビーの頃に感じた癖が嘘のように強いカメへと生まれ変わります。 今回やってきたのは見ての通りサイズ良し、フォルム良しの何もかもが絶妙な飼い込み個体。 動き、餌食いともに見た目通りで、 4本の足をしっかりと伸ばして歩くのは当たり前、 心ゆくまで運動した後は与えた餌を葉野菜からフードまで毎日もりもり食べてくれます。 どうしてもボコつきやすい椎甲板も最小限の程度に抑えられており、 模様も細分化が起こりヒョウモンガメたる由縁を発揮し始め、 ここからの成長が一層楽しみになってきました。素晴らしいコンディションでお届けする優良個体です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (S) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 子どもの握り拳ぐらいで出回ることが多い中ちょっと珍しく大人のそれぐらいあるモア安心サイズ! 葉野菜にしか反応しなかったものをフードへと完全移行させた最強の店内飼い込み個体たち、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 末永く愛されるべきキャラクターであっただろうあのホシガメがパタリと姿を消して以来、 次世代の柄ものリクガメとして一際脚光を浴びているのがヒョウモンガメの仲間たち。 予め申し上げておくと最大サイズについては避けて通れない課題であるものの、 多くの人々が想像しているようなボリュームに到達することは極めて稀であり、 数十センチも半ばから後半になるケヅメであればまだしも、 そこまで手に余る巨体へと仕上げる方が却って難しいですから、 現実的には三十センチから四十センチクラスを想定しておけば後で驚きはしないでしょう。 話は戻りますが甲羅全体に色柄が描かれるようなそんな素敵なリクガメなんて、 世界中をぐるっと見渡してもそれほど豊富にいる訳ではなく、 本種は新参者なのかといえば歴史的にはホシガメと同等かそれ以上の実績を誇り、 昔から往年の銘種として長きに渡り活躍し続けています。 しかしながらかつて流通していたものは往々にして初期状態が芳しくなく、 誰もが等しく容易に育てられる種類とは言い難い面がありましたから、 そういう意味では昨今見かけるヒョウモンガメにはいくらか別人の要素が感じられます。 今日においてもスタートダッシュの大切さをよりシビアに考えるべきではありますが、 個体選びに気を遣うことで驚くほどの躍動感で私たちを楽しませてくれる素晴らしいリクガメのひとつです。 今回やって来たのは当店でも日頃から取り扱う見慣れたサイズよりも一回り大きめの二匹で、 どうせ時が過ぎれば大きくなるのだからとか、 ベビーから僅かに育ったぐらいではまだまだ心配という方にお勧めの出物。 輸入された一群の中から流石に健康体のみを選りすぐってはみたものの、 入荷当初は緑色の葉っぱしか口にしてくれなかったため、 根気良くケアを続けていたらMazuriリクガメフードだけでお腹いっぱい食べてくれるようになりました。 この大きさまで現地で暮らしていたという点もポイントで、 甲高のフォルムから歩く姿の凛々しさまで非常にスペックの高い優良物件です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 濃厚なクリームソースを煮込んで仕上げた心も体もホッと温まる上品なミルキーホワイト! いざ育ててみなければ分からない色や柄について拘る方にとっては見逃せないセレクト個体です、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 昔ながらのリクガメと言えばいくつか候補が挙げられますが、 このヒョウモンもまだひよこ電球にレタスと猫の砂がセオリーであった時代から親しまれている不朽の銘種です。 かつてはアフリカの大地から大きなサイズを中心に直接輸入されて来ることが多く、 すっかり体重の軽くなったそのカメをひとまず即席の水槽にセッティングし、 有り合わせの暖房器具でひたすら熱を加えながら野菜や九官鳥の餌を食べさせていた、 そんな苦労を経て今もなおビギナーからマニアにまで愛され続けています。 ヒョウモンにあって他の種類にはないもの、 それは何と言っても成長に連れてより顕著になっていく甲羅の高さではないでしょうか。 我々にとってだけなのか世界基準なのかは分かりませんが、 リクガメと聞けばこんもり盛り上がった形のものがトコトコ歩いてるという印象になるらしく、 半ば強制的にそのような残像が刷り込まれていると言っても過言ではありません。 しかし全体を見渡してみると特にビギナー向けとされるホルス、 ギリシャ、ヘルマンなどはいずれも中程度か扁平気味のシルエットですし、 あの憧れの大型種ケヅメですらも同様の結果なのですから、 身近であって意外と貴重な存在であることが分かります。 形だけであればホシガメも好い線を行っていると思うのですが、 やはりダイナミックさへの未練が残ってしまうという点で満足できない方も大勢いらっしゃるでしょう。 小さな頃から重たそうな甲羅を背負って歩くその健気な姿に、たくさんの愛好家が癒されてきたのです。 今回やって来たのは俗に言うホワイトヒョウモンにカテゴライズされる、 全身の基調色に殆ど黄色味を感じさせない実に上品な佇まいが高い人気を誇るタイプ。 名前の由来である斑紋もどちらかと言えば大柄で、 まるでホルスタインのような可愛らしいデザインはより支持者が多いのではないかと思われます。 見栄えの華やかさとは裏腹にシャイな性格の個体が多いことが心配の種ですが、 この一匹に限っては撮影前の控室である狭いケースの中でも脱走しそうな勢いで走りまくり、 仕舞いにはその場を多量の糞まみれにしてしまうほどの大食漢でもあります。 葉野菜からMazuriリクガメフードまで人を押しのけるように食べ散らかしており、 サイズを合わせれば他種との同居にもへこたれないタフさは嬉しいポイントです。 性別は不明としましたが参考までに尾のアップはこちら、 甲羅には定期的に霧を吹くことで艶と照りに満ちた美ボディを維持することができるでしょう。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (M) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 手の平からダイブしそうな勢いで懸命に大地を蹴るトルク十分のエネルギッシュな安心サイズ! 黄色味の濃い甲羅に黒斑が散るスタンダードなデザインとその造形に何の不満も見当たらない、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 貴重な柄モノとしてこの業界に無くてはならないマストアイテムとされる、 今やホシガメと双璧を成す屈指の人気種に成り上がったお馴染みのヒョウモンリクガメ。 あちらが類稀な美貌と手頃なサイズ感を売りにしているとすれば、 こちらヒョウモンはやはりまず第一にそのダイナミックなボディ、 それに加えて次第にゴージャスな風貌へと仕上がっていく豹柄の甲羅が見所と言えるでしょう。 単純に直線的な長さであれば同じくアフリカ出身のケヅメリクガメも候補に挙がるのですが、 こと地上高となると明らかに本種の方へと軍配が上がり、 即ちこんもりと盛り上がったいわゆるところのリクガメらしさを前面に押し出した、 非常に存在感のあるシルエットが何よりの魅力と考えられています。 甲羅に描かれる模様には幼い頃こそ他のリクガメを圧倒するような訴求力は無いものの、 大きくなるに連れて複雑に変化するヒョウモンにしかないこの外観は、 特に野生個体の写真を見た時に改めてその憧れが強まるものと思われます。 それこそ何十年も前からここ日本ではペットとして認知されていましたが、 如何せん輸入時の初期状態に恵まれず飼育困難な種類としても知られており、 しかしながら最近ではその辺りのケアも進み随分と育て易く生まれ変わったことから、 往年の銘種でありかつビギナーにとっては新鮮な驚きにもなっているようです。 今回やって来たのはようやくヒョウモンらしい色柄が表に現れ始めた、 ようやくここからが本当に楽しみながら育てられる良いところ取りのミドルサイズ。 これぐらいのボコ付きは許容範囲内、 甲羅全体は天高く突き上がった見栄えのする形に出来上がり、 力強く伸びた新しい成長線が未来への希望を匂わせています。 直ぐに頭を引っ込めてしまうシャイな性格の個体も多い中、 極めて明るい性格の持ち主でMazuriリクガメフードを見ている前でバクバク食べまくる優等生。 リクガメ自体が初めての方にもお勧めの安心感たっぷりな掘り出し物です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (M) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 大人の拳よりもずっと大きく育った安心サイズです。 クリーム地に散らばる黒斑がさながらネコ科動物の模様を演出しています、 飼い込みのヒョウモンガメが入荷しました。 近縁種のケヅメと共に毎年可愛らしいベビーをみかけることができるアフリカを代表するリクガメですが、 飼育にはケヅメ以上に気を使う場合もありベビーから育て上げるのが意外と難しいという声も聞きます。 今回ご紹介するのは手に持って十分に重みを感じられるボリュームに育った個体で、 ベビー時の柄の面影はほとんどなくなり大人顔負けの豹柄が表れはじめたグッドサイズ。 紫外線ライトの影響で少し黄色っぽく見えますが、 ライトを消すとこんな感じ。 見事なアイボリーの成長線です。 時に全身アイボリーで黒斑も消えかかったような見事なヒョウモンに出会う事もありますが、 ヒョウモンはヒョウモンでなくちゃという方にはこの様に色味と模様のバランスがとれたタイプもよろしいかと思います。 この模様は成長に連れ細かく変化していきますので記録をつけても面白いでしょう。 第五椎甲板がラインから少し外れていますが甲板はズレていません。 暖かい季節も間近ですので独特のハイボディな体格を目指して大きくして下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| これぞホワイトヒョウモンを名乗るに相応しい体中に荘厳な輝きを纏ったハイグレード美個体! その色合いも然ることながら癒着跡の無いこんもりフォルムの育ちぶりもお見事な、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 今やホシガメと双璧を成すほどの高い人気を誇る、 貴重な柄モノのリクガメとして人々に愛され続ける銘種のひとつ、ヒョウモンリクガメ。 文字通り業界のスター選手として不動の地位を確立したホシガメに対し、 本種は幼い頃のデザイン性においてやや劣る面があるものの、 彼には無い縦にも横にもダイナミックなサイズ感が強力な武器となっています。 単に大きさだけで比べればケヅメやゾウガメなどまだまだライバルは存在していますが、 ヒョウモンはその恵まれたボディサイズに加え華やかさまで兼ね備えており、 綺麗な上に大きくなることがメリット以外の何物でもないと考える方にとって、 これ以上の有効な選択肢は他に見当たらないかもしれません。 当店では平常、とりあえずバスケットボールぐらいは覚悟して下さいと説明していますが、 それとてあくまでも通過点に過ぎず、 もう一段上の高いレベルで根気良く愛情を注ぎ続けることにより、 時間はかかりますが更なる高みを目指すことも決して夢物語では無いのです。 生まれた時から煌びやかなホシガメとは異なり、 成熟したその頃にようやく美しさの全貌が明らかになるのですが、 成長過程でどのように模様が描かれていくのかが少しずつ分かり始める様子に、 飼い主だけが味わえる無上の喜びが秘められているのだと思います。 今回やって来たのはパッと見ただけでその美貌が手に取るように分かる、 僅か十センチ台半ばにして文句無しの仕上がりを見せ付ける久々の優良株。 その白さはまさに素質のもの、 この世に生を受けた時から定めとして背負っていた才能が開花し、 誰もが羨む素敵なヒョウモンガメへと育っていくことでしょう。 各甲板同士がくっついたようになる癒着と呼ばれる現象も無く、 あらゆる部分で育ち方に何の不満も抱かせないふっくらと盛り上がったシルエットには、 前飼育者の愛情が形として表されているようです。 性格も明るくよく動きよく食べる健康優良児、 内からも外からも磨きに磨かれたハイクオリティをどうぞご堪能下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (M) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 幼体時には見られない美しいクリーム色が出始めています。 手に持つとズッシリくる安心サイズ、国内飼い込みのヒョウモンガメが入荷しました。 近縁種のケヅメリクガメと並び、アフリカ大陸を代表する大型リクガメのひとつ。 その人気は古く、今でも変わらず多くの人に愛されている定番の人気種となっています。 アメリカなどから繁殖されたベビーサイズが輸入されることが多いのですが、 今回はそんなあどけない頃から幾分育ち本種の特徴がようやく表れ始めた個体。 まだまだ序の口ですが甲羅の模様はこれからどんどん細かくなっていき、 最終的には名前の通りのヒョウ柄へと変貌していきます。 そしてもう一つの特徴として挙げられるこんもり高く盛り上がった甲羅はこの大きさでも既に顕著で、 甲板のひとつひとつも全体のフォルムもここまでいい感じにきています。 性格の差もあると思いますがこの個体はとにかく明るい活発な様子で、 写真を撮ろうとするとちょっと信じられない足の速さで辺りをウロウロするので一苦労しました。 甲高のお陰か17cmのリクガメとしてはやたらと背中が大きく感じられ迫力満点です。 第一椎甲板に生まれつきと思われる配置のずれがありますが、 幸いにもここまで育ってそれを感じさせない綺麗な成長の仕方をしています。 ようやく梅雨も明けはじめ、屋外でのリクガメ飼育も本番スタートという感じになってきました。 この夏で一皮も二皮もむけそうな健康優良児です。 性別は不明としましたが、今のところメスのようです。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト・M) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 雪原にひっそりとしかし直向きに命を繋ぐユキヒョウのように上品でミステリアスなこれぞホワイトヒョウモン! その色彩も然ることながら全体のフォルムや各甲板の仕上がりひとつとっても大満足の絶品です、 バブコックヒョウモンガメが入荷しました。 我が国におけるリクガメ飼育の黎明期には現代にも劣らぬ様々な種類が実際に輸入されていたようですが、 当時の感覚からすると単に外国産の爬虫類全てが珍しいという風潮がとても強く、 日本には棲息していないタイプの稀少なカメというイメージばかりが先行し、 まるで珍獣のような扱われ方が大多数を占めていたのではないでしょうか。 当時高額だったケヅメリクガメなどはその良い例で、 巨大なカメが家の中ないしは庭をのしのしと歩いていたらどれほど素晴らしいだろうという、 至ってシンプルな思考や動機が人気を呼ぶ理由のひとつであったと考えられます。 時代は移り繁殖された幼体などが出回るようになると、 人間とカメとの距離感はグッと近付きある種のエキゾチックアニマルのような、 家族の一員として迎え入れられるケースも増えてきました。 そうなるとあまりにも大きくなる種類は飼育困難であると判断され、 今度はチチュウカイリクガメをはじめとする小型種の評判が高くなっていきました。 しかしここ最近ではそのトレンドにも若干の変化が出てきたようで、 知識や技術、器材などの発展と充実が諦めかけていた夢を次々と叶えてくれるようになり、 それに伴い飼育対象の幅も広がったように思います。 このヒョウモンガメは同じアフリカのケヅメとも全く異なる、 どことなく線の細い印象が長年に渡り拭い切れなかったためか、 国内での長期飼育例もさほど多くない鬼門となっていたのですが、 やはり大型種への憧れや美しい紋様の魅力に対する人々の未練や執着とは相当なものだったようで、 近頃では体調のみならず甲羅の仕上がりにまでその成果が確かめられるようになりました。 今回やって来たのはすっきりとした白みが印象的な、 ベビーより育てられた拳二個分サイズの一匹。 カラーリングは黄色と白色のツータイプに大別されるようですが、 当然どちらとも言えない中間的な個体も存在する中でその一方に偏った特徴を示すものは需要が高く、 特に白系統は成熟するに連れてまるで色彩変異であるかのようにエレガントな美貌を誇ることから、 純粋なホワイトカラーに拘って探し求める方も多いようです。 本種にしばしば見受けられる過度に臆病な性質も今の所は感じられず、 何よりもノントラブルでこの大きさに到達したことは非常に高く評価すべきでしょう。 均等に刻まれ続ける成長線にこの先の長い付き合いを思い描き、 立派なスノーレパードを目指して日々の糧を積み重ねていきましょう。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 腹を持ち上げて暴れまくるヒョウモンの元気印! ぼっこり盛り上がり始めた甲羅と細かく乱れ始めた模様はここからが本領の見せ所です、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 ペットとしてリクガメが売られ始めた頃から今日まで、 いつの時代も欠かさず我々の前に姿を見せてくれるお馴染みのキャラクターだけあって、 同じアフリカに棲息するケヅメと並び大型種としての知名度は十分過ぎるほど。 昔は柄の派手さからなかなかの人気を誇っていましたが、 飼い方にややコツが必要なため飼育対象として選ぶ人が次第に減少し、 小型で扱いやすいチチュウカイのグループへ移っていったように思います。 それでも最近では随分と定番化してきたヘルマンやギリシャ、 そこで今度は一味違う別系統の種類を求める声も増えてきました。 知らぬ間にスタンダードなリクガメとなっているだけに物珍しさはありませんが、 常に気になる存在ではあるヒョウモンガメ、最近では懐かしさ半分に人気が再燃してきているような気がします。 大きくなって困ったという話はケヅメであってもヒョウモンではあまり聞かれません。 ベビーから10cm近くの手の平サイズを入手するのはさほど難しくありませんが、 大きくなればなるほど探し出すのに苦労させられるでしょう。 今回やって来たのは4年かけてとうとう20cm台に到達した立派なオス。 このようにフォルムがしっかりと出来上がり模様も散らばり始めるのはある程度育ってからなので、 本当の魅力を殆ど味わうことなく手放してしまうケースも時折見かけるだけに、 これほどまでに仕上がった状態での放出はとても珍しいです。 ケヅメのように物凄く育ちが早い訳でもなく小さい内は何かと苦労させられることも多いのですが、 写真でご覧の通り何より状態の良さが目を惹く一匹で、 人が手を差し出そうが顔を引っ込めるどころか全くの無関心で大変に肝が据わっており、 ここまで堂々と撮影させてくれるヒョウモンに出会ったのは初めてかもしれません。 更に甲羅のボコ付きは最低限に抑えられ基本形状もしっかりとしており、 個体差の中で比較すると豹柄も細かく変化していきそうでこの先の成長が楽しみです。 雌雄間で最大甲長に違いはないと言われていますので、単純に好みで選んでみても良いでしょう。 狙っていた方はお早めに。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 豹柄と言うよりは大胆にまとまったホルスタイン柄に色塗られた珍デザイン! 道路へ放った瞬間から終始爆走状態をキープし続ける無限の体力を持つ超健康体です、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 カメを飼うと言えば真っ先に思い浮かぶのは水棲ガメ、 これは恐らく世間一般の殆どの人がそう思っているに違いなく、 何故なら日本国内には一部例外を除き水の中をスイスイと泳ぐことのできる種類しか棲息していないのと、 昔からミドリガメやゼニガメと呼ばれるものたちが縁日やペットショップを賑わしてきたからです。 カメはカメという生き物なのであって、 実は爬虫類に含まれているのですと聞かされ驚かされるケースも決して珍しくないほど、 そこには歴史に裏打ちされた固定概念が実在しています。 ただし近頃では社会的にカメを爬虫類という従来とは異なる角度から捉える志向が高まり、 つい妙な言い方になってしまいましたが、 それだけペットのひとつとして爬虫類の存在意義が次第に認知され始めている証と言えるでしょう。 最近のトレンドを探るとどうやら水換え離れが年々増加する傾向にあり、 同じカメでも何となくヘビやトカゲなどと並列に並べることのできるリクガメに注目が集まっています。 しかしミズガメのこともよくご存知の方は痛感していることと思いますが、 リクガメは種類数が限られていてかつ色や模様なども大まかに集約されてしまうため、 飼い主の個性を表現し辛いとお悩みの声が聞かれることもしばしば。 色味は大体黒から黄色ないしは褐色、 そこに斑紋か放射状のラインかもしくは全くの無地という雰囲気ですから、 あとはそれぞれの種内で起こり得る個体差のバリエーションを武器に戦っていくしかないのです。 今回やって来たのはリクガメ界における貴重な柄ものの中でも、 特にお洒落度の高さで厚い支持を集めるヒョウモンガメ。 亜種の有効性はさて置き少なくともホビーの世界ではドットの細かいものを基亜種ナミビア、 粗いものを亜種バブコックというように区別していますが、 この個体はその粗さの程度が並大抵のものではなく、 一見して全く別の種類であるような錯覚を引き起こすほどのインパクトがあります。 黄色と黒の住み分けがあまりにもはっきりとし過ぎていて、 全体にまろやかでまったりとした空気にはとてもネコ科の肉食獣が放つ緊張感はなく、 ただひたすらにエレガントな美しさだけが目立ってしまうのです。 本種の幼体はまるでピンポンサイズのホシガメの如く、 いわゆるビギナー泣かせの飼育難度を思わせる面がありますが、 このオスは特別性格が明るいようで歩行中にズカズカと近寄っても首ひとつ引っ込めず、 むしろ全く写真を撮らせてくれない落ち着きの無さに大変安心させられました。 飼い込みのヒョウモンは一点ものの要素が非常に強いため、気に入った個体は早めに押さえておいて下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト・♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| いわゆるホワイトヒョウモンと呼ばれる明色部の際立った美麗タイプ! この個体は天高くそして滑らかに盛り上がったシルエットの美しさも然ることながら、 人の顔を見るとまるで子犬のように後ろをついて歩いてくるほどの人懐っこさが素晴らしく、 本当に家族のように親しい間柄で末永く付き合っていけると思います。 メスよりも小振りなオスですから、最大でも三十センチ少々にしかならないと考えられ、 ケヅメやゾウガメのようにあまりにも巨大なリクガメは手に負えない、という方にもピッタリ。 食生活は当店で販売しているMazuriリクガメフードオンリーで大丈夫な、状態抜群の絶品です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| その大きさも然ることながら全体のフォルムや描かれた模様の雰囲気までもがグッドテイストな十年選手! ホシガメなき今その後継者として再び注目を集めている貴重な柄入りリクガメとして昔からお馴染みの、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 ケヅメとヒョウモン、昔からこの両者は切っても切れない仲と呼んで差し支えないような、 ファンの間でも何となくコンビとして認知されていることの多い組み合わせで、 というのも同じくアフリカに産するリクガメであるという事実だけに留まらず、 そのサイズ感もまた大型種という括りに入れられていることから、 まさにキングとクイーンといったような位置付けで人気を博してきました。 大きく育つという点については確かに前者のケヅメなどはその圧倒的エナジーにより、 ゾウガメを除いたほぼ全てのリクガメの中でもトップクラスのずば抜けた体躯を誇り、 正直一般的な感覚では殆どの人が扱い切れないようなカメが出来上がってしまうのですが、 こちらヒョウモンガメについては真の実態があまり知らされていないのかもしれません。 もちろん真偽のほどは諸説ありますがどうやら最大甲長と棲息域が密接に関わっているらしく、 つまり大きなヒョウモンもいればさほど大きくないヒョウモンもいるという話もあって、 ヒョウモンと名の付く全てのリクガメがもれなく巨大化する訳ではなさそうとのこと。 無論、最終形態を鑑みることなく無茶な導入をすることは避けられるべきでしょうが、 リアルな実態を目の当たりにすることで新たに切り開ける可能性があるのならば、 あくまでも前向きにその道筋が明るく照らされることがあっても良いのではと感じる今日この頃です。 今回やって来たのは最も流通量が多く単にヒョウモンガメと言われればこれに該当する、 バブコックヒョウモンガメの大変に立派な長期飼い込み個体。 まず目を惹くのはこんもりと高く盛り上がったその象徴的なシルエットであり、 元来備わるスペックがそうさせるのですが育て方の良し悪しに左右される部分も大きく、 大勢が願って止まない天を突き破るような甲羅の高さが実に魅力的。 豹柄の雰囲気もなかなかに秀逸で、 これこそ図鑑に載せたいスタンダードビューティ、 黒斑の散らばり方に何の嫌味もない素直な表情が大変に宜しいです。 バブコックは例えば他のナミビアやソマリアなどに比べてあまり大きくならない印象が強く、 この個体もなんと十年ほど国内で育てられていた秘蔵の一匹なのですが、 決して意地悪をされていた訳ではなくそこそこのボリュームに収まるちょうど良さ。 極めて明朗な性格も特筆すべきものがあり、 地面に置いた途端に延々とダッシュし続けるだけに留まらず、 ケージ内でもガラス越しに人影へとすり寄って来るなどそのあざとさがまた堪らないのです。 こんなスペシャルな掘り出し物はもちろん一匹のみ、お早めに! | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 如何にもオスらしいスマートなボディにヒョウモンらしからぬポジティブな性格が大変好印象! メスほど大きくなり難いだけに30センチに届かんばかりの大型サイズは貴重な出物です、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 その昔リクガメと言えば総じて高嶺の花であり、 それらの代替えとしてハコガメやヤマガメの類が売られていたぐらいですから、 今のように多くの種類が年がら年中可愛らしい手の平サイズで流通するなんて、 当時からすればとても考えられない夢のような話となるでしょう。 このヒョウモンとて例に漏れず、 それこそ段ボールにネコの砂を敷いてレタスを与える時代を経験してきた方にとっては、 紫外線灯から保温器具に至るまで全てが至れり尽くせりの現状に驚きを隠せないと思います。 最近ではすっかりペットとしての地位を確立したリクガメの仲間は、 トコトコ歩き回る姿と草食性のイメージがつくり出す平和な雰囲気が好評なようで、 かつての難しさも大分薄まり初めての方でも十分トライできるようになってきました。 この先世の中に十年選手、二十年選手のリクガメたちがどんどん増えていくのかと思うと、 爬虫類飼育の文化の進歩を感じて止まないのです。 今回やって来たのは意外にも大きくなり過ぎて困ったという話が聞こえてこないヒョウモンガメから、 十年近くに渡って育てられいよいよ片手で持ち上げるのは大変なぐらい立派に育った大きなオス。 こればかりは好みの問題と言わざるを得ませんが、 ふっくらと幅広く形作られるメスの甲羅に対しオスはスラッと細長くすっきりとしたフォルムが印象的で、 腰のくびれた後ろ辺りからお尻にかけて広がるフレアー状の甲羅は、 無駄な厚みが無いだけに中央のキールが余計に切り立って見え高さが強調される、 しかし結局の所は雌雄で異なる形状にどちらからも魅力を感じてしまうのです。 幼体から飼育するとより考えさせられますが、時にホシガメよりも育てるのが困難であると言われる本種は、 環境が少し変わっただけで塞ぎ込んでしまう性格の個体も少なくない中で、 このオスは温浴時に全身を磨いた後でも気にせず辺りを走り回り、 撮影時にもカメラを向けるとなかなか良い表情を見せてくれました。 こういった放出個体の一点ものを手に入れるには巡り会いが命、 いよいよ夏本番ですからお迎えのし易い時季に是非ご検討下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (特大サイズ・♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 地面に置いたが最後、よーいドンで延々と路上を走り続ける底なしの体力と驚異的なフィジカル! 腰元のくびれたボディにリアがフレアー状に広がったスタイルがセクシーな美男子です、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 リクガメ界におけるアフリカ大陸の二大巨頭と言えばケヅメとヒョウモン、 大型種だからと警鐘を鳴らされながらもかつてより屈指の人気者として名を馳せ、 幼体を中心に流通し多くの飼育者に夢を与え続けています。 両者はしばしば似た者同士のように捉えられることもありますがむしろ真逆で、 それは例えば甲羅の色柄にもよく表れているでしょう。 全くの無地にやや扁平で叩いても壊れない頑丈な鎧を身に付けた前者と、 こんもりを超えてガツンと盛り上がった背中に力強いペインティングが施された後者、 両者を比べてみるとシルエットからパターンまでまるで異なることがよく分かります。 そしてもうひとつ比較されたいのが内面について、性格と言えばより分かり易いかと思いますが、 傍若無人で周囲の視線を気にすることなくやりたい放題振る舞うのはご存知の通りケヅメ、 それに対しヒョウモンは常に辺りの様子を伺っているようで、 何か気に入らないことがあったり驚いたりした時にはすぐさま内に籠ってしまいがちです。 大きな体と大胆な模様にもっと胸を張って歩いて欲しいと願っても、 実際には多くの個体がシークレティブで恐る恐る行動しているのが現実ですから、 飼育難度云々の前にその陰気な性質に対して不満が漏れることも少なくありません。 そこで今回ご紹介するのはか弱さのかの字もほぼ全く感じられない、 本当は中に別のカメが入っているのではないかと疑いたくなるほど大胆不敵な性格の持ち主。 ここで少々撮影秘話、写真を撮る前にはおめかしの意味も込めて必ず洗体してから臨むのですが、 大抵はこれによるショックでしばし立ち直るのに時間を要するのが通例です。 しかしこの個体は甲羅から体まで隈なくブラシで擦られた直後、 およそ五秒後には早くもダッシュを開始するという異端児ぶりを発揮し、 その後何十分と動き回っていたためにピントの甘い写真ばかりになってしまいました。 ヒョウモンの殆どが野外に出したり人が触れたりしただけで噴気音を出しながら縮こまるものですが、 そんな心配を他所にアスファルトの上を暴走してくれたことは嬉しい悲鳴以外の何物でもありません。 オスで30センチクラスの大型個体というのもまた珍しく、 店内には夜な夜な発情の雄叫びが響き渡っています。 産卵も間近に迫る巨大なメスを持て余している方にこのやり手を是非ご案内したいと思います。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ライトカラー・♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 走る、 走る、 走る、 程良く暖まったアスファルトの上を縦横無尽に駆け回る特大飼い込み個体! ヒョウモンらしからぬまろやかなデザインが斬新なほぼパターンレスの色薄タイプ、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 大きなカメと言うものはただそれだけで人の気持ちを盛り上げたり、 時に和らげたりと様々な作用をもたらしてくれますが、 何時如何なる状況においても嫌な印象を与えることはせず、 ただひたすらに良いところばかりが際立つのも決して気のせいではありません。 特にリクガメの場合はそれが平和の象徴のような存在感を示すものであって、 ただそこにいるだけで場の空気をほんわかとしたムードに仕立ててくれますから、 ペットとしてだけでは無く移動動物園や映像作品などにおいても、 しばしば必要とされている場面に出くわすことがあるのだと思います。 本種は仲間内でもそれなりに大型化することから一目置かれるキャラクターであり、 かつ美しい模様を呈することから柄ものとしての需要も満たすことのできる、 リクガメの中でも色々な意味で重宝される重要なポジションを担っています。 どうしても同じアフリカを原産とするケヅメリクガメと比較されがちですが、 小顔のすっきりとしたシルエットが好みと言う方がヒョウモン派には多く、 良い意味で繊細なイメージが何処か女性的な雰囲気を漂わせているところなどが、 ケヅメ派とは大きく異なる趣味嗜好の違いが表れる部分なのではないでしょうか。 今回やって来たのはオスにしては極めて稀だと言わざるを得ない、 相当にしっかりと育てられ過去に入荷した記録を見ても特大だと呼べる、 立派な体躯を見せ付ける本当に貴重なサイズの一匹。 一目見て黒斑の少なさに心を奪われる素敵なカラーリングの持ち主で、 俗にホワイトヒョウモンと括られるタイプとはまた少し異なる趣きの、 カスタードクリームをべったりと塗り込んだようなイエローがとても美しい、 その大きさも然ることながら仕上がりの部分でも一目置かれる存在です。 撮影時には休むことを知らない類稀な躍動感を見せ付け、 延々と辺り一面を動き回るため付き合っていたこちらが疲れてしまいました。 何度も申し上げますがこのサイズ感のオスは滅多に出てこないので、 模様のバッチリ綺麗なヒョウモンガメとは少し違いますが、 こんな面白味のある変わり種がお好きな方にはかなりお勧めです。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (特大サイズ・♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 相方のケヅメに比べ成長が緩やかなだけあり尚更稀少性の高さが滲み出る夢の30センチクラス! 強めの黄色地に綺麗な豹柄を描き出す黒い斑紋が均一に散りばめられた高いデザイン性も評価したい、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 この場においては何度もしつこく繰り返し申し上げていることですが、 大型に成長するリクガメの中で殆ど唯一と言っても過言ではない、 類稀な巨体のみならずそこへ鮮やかな模様が添えられるという事例は、 このヒョウモンリクガメを除いて他にはなかなか見当たらないでしょう。 もちろん非常に珍しい高価な種類まで含めればその限りではないのかもしれませんが、 言い換えれば一般的な水準に収まる種類の中にこれほどの逸材が埋もれていたかと思うと、 改めてその存在価値の高さには驚きを隠せません。 しかしながら大衆にその優れた魅力の数々が知れ渡ったとしても、 全ての愛好家が本種を選択する訳ではないのにはきっと何か理由があって、 少し考えただけでも思い当たる節をいくらか挙げることができます。 甲羅に対して小振りな頭部や、 それを引っ込めただけで完全に覆い隠すことのできる前肢の構造から見るに、 決して明るい性格とは言い難くむしろ周囲の環境に対して敏感な面があり、 それ故に不慣れな土地や環境では塞ぎ込み躍動感に欠けるシーンが散見されます。 また誠に残念ながら流通状態が芳しくないものも見受けられ、 上手に育てられないといったビギナー泣かせのシンプルな悩みも聞かれるなど、 大きくなり過ぎて困ってしまうだなんて悩みは贅沢の極みであり、 初めから大きくさせること自体が困難である可能性すら考えられます。 事実先に挙げた近縁種のケヅメとは放出される件数が圧倒的に少なく、 それ自体は健全な話なのかと思いきや何処か前向きとも言い難い面があり、 嫌なところで帳尻合わせができてしまっていることが絶妙な寂しさを募らせるのです。 今回やって来たのはその裏側に数値や見た目以上のレアリティを感じて頂きたい、 定番種バブコックのオスにしては珍しく巨大に成長した長期飼い込み個体。 連日続く寒さのため野外での撮影は叶いませんでしたが、 それにしても片手一本で持ち上げるのには全く適していない重量感たっぷりのボディは迫力満点。 何が正解なのかもはや分かりませんが前肢の鱗がトゲトゲしているところなど、 単なるヒョウモンガメでは味わえなかった謎の格好良さが盛り込まれています。 Mazuriリクガメフードを食べ散らかす超健康体ながら、 ビッグサイズに見合わぬ驚きのリーズナブルプライスにて! | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (特大サイズ・♂) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 30センチオーバーという未だ嘗てない大男の登場に動揺を隠せない圧巻の超迫力! 最大サイズに雌雄差はないとされていますがいずれにしてもこのボリュームは稀少です、 バブコックヒョウモンガメ・オスが入荷しました。 ゾウガメやケヅメに匹敵する巨大種の一員であるヒョウモンガメ、 アルダブラの最大甲長は一メートルを優に超えケヅメでもおよそ80センチ、 本種はそれに次ぐおよそ70センチという記録を持ってはいるのですが、 果たして本当にそれほど大きくなるのでしょうか。 詳細な数値までは分からずとも現地より届く写真に収められている個体を見ると、 確かに40センチや50センチでは利かないとても大きな甲羅を背負っているのですが、 その殆どがナミビアと呼ばれる基亜種の特徴である細やかな柄を有していると思われます。 気になったので資料を紐解いてみると、 亜種を認めない説が有力ではあるがバブコックは比較的小型で基亜種はそれよりも大型に成長する傾向にあると記されていました。 つまりヒョウモンガメは総じて大型であるという一説はホビーの世界で肥大化してしまっただけに過ぎず、 実寸としてはまだ飼育に現実的な範疇に収まるのではないかと考えられます。 もちろん十年単位で大切に飼育されている個体については、 現実に大きなサイズに到達し国内に潜んでいる見込みも捨て切れませんが、 少なくとも飼育継続困難により放出されるものはようやく30センチに到達するかどうかというサイズばかりで、 その基準を更に超えてくることは極めて稀なのです。 当店で以前に取り扱った中で最も大きかったのはメスの31センチ、 対してオスには27センチという猛者がいましたが、 メスに関しては過去数年を遡ると30センチクラスが数匹挙げられるものの、 オスの20センチ後半というのはそれ以来出会うチャンスに恵まれず今日まで過ごしてきました。 しかし今回、 最高記録を塗り替えると共にそれがオスであるという奇跡の一匹がここに現れました。 誕生してから恐らく十年以上、 全飼育者の所でも七年ほどの歳月を経て育まれたその甲羅は 特徴的なハイドームの貫禄を如何なく発揮し、 荒々しく飛び散った墨汁が描き出す大柄の豹紋の存在感も相まって非常にダイナミックな風格を轟かせています。 濃厚なイエローが地色として全身に冴え渡る様は一目見た時の印象をより鮮明にし、 美しいリクガメのひとつとして数えられるに恥じぬ十分な実力を備えていることも納得できます。 本種の成長過程にはしばしば起きる甲板の癒着が見られる箇所もありますが、 我が家の大き過ぎるメスにマウントできるオスを長年探し求めていたという方にとっては千載一遇の好機ではないでしょうか。 決して気温が高いとは言えない本日でしたが、 日光を浴びた途端に店内では見せなかった本性を露わにし終始駆け回る姿に安心しました。 滅多に拝むことのできない巨体ですが多少ボコ付きがあるため特価にて! | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 文句なしのツルツルドームに黄色も黒色もベッタリ濃厚なコントラストが眩しい絶品美個体! ひとたび外に出せばなかなかじっと座っていてくれないアクティブな性格もまた好印象でしかない、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 リクガメがペットとして飼われるようになった黎明期より我が国にもたらされ、 正直あの頃は大きな声でペットだと呼ぶのが辛かった時代でもあり、 ようやく家族の一員として安心していられるようになった現在に至るまで、 最も美しい種類のひとつとして上層部に君臨し続ける定番の人気種。 今でこそカメと向き合う上でどのように成すべきかのガイドラインが出来上がり、 それなりの意欲や関心があれば大きく脱線するようなこともなくなりましたが、 昔は乾燥させなければならないとか水を飲ませてはいけないとか、 まるで体育会系の悪しき慣習のように酷な状況を強いるやり方が広まっていたこともあり、 それを思うと今日ではカメに対するそんな気まずさも大分薄れたように思います。 リクガメの甲羅がヒョウ柄をしているだなんで何ともメルヘンチックで、 野生ではこれが見事な保護色になっているという設定なのですが、 結果的に人間の目に留まってしまったことは彼らにとっては複雑な問題でしょう。 用いられた色彩自体はそれほど奇抜なものではないにしても、 そのデザイン性の高さにはホシガメやホウシャガメなどと並ぶインパクトがあって、 普通に見かけられる今だからこそ大切にしてあげたくなる銘種のひとつです。 今回やって来たのは非常に出現率が低く全国のファンが血眼になって探している、 貴重なメスであり尚且つ出来栄えも良好な一目見て上物だと分かる飼い込み個体。 あまりにも太陽光が似合い過ぎるために撮影は屋外で行いましたが、 甲羅に描かれた美しい模様は初夏の強い陽射しにも負けじとその存在を主張し、 ファインダー越しに映るそれは実物と寸分の狂いもありません。 まるで言うことを聞かず終始走り回っているためカメラを構えるこちらがのぼせそうでしたが、 ちょこんとお座りすればやけに愛嬌のある表情でこちらを見つめてくるため、 ついつい長時間のお散歩に付き合わされてしまいました。 地面に餌を設置するや否や二秒後には爆食を開始する底なしの食欲で、 入店後早くもMazuriリクガメフードを主食にしている最高の一匹です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト・♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 天高くそびえ立つ甲羅に描かれた大柄の斑模様が印象的な存在感抜群のホワイトヒョウモン! 頭部や四肢の鱗もまた澄み渡る象牙色に彩られたこの先の成長過程もまだまだ楽しめる一級品、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 リクガメと言う生き物はただそれだけで人々の視線を釘付けにし、 たちまち虜にしてしまうだけの優れた魅力が備わっていますが、 中でも背面に特別な意匠を掲げた柄モノなどと呼ばれる仲間たちは、 とりわけその傾向が強く現れるように思われます。 そもそも陸上を気ままに歩いている光景が我々の目には早くも喜ばしく映り、 その上象徴的なパーツである甲羅に対し素敵なペインティングが施されることによって、 更なる喜びや感動がそこから得られ増幅するようになると言う寸法です。 ここで厄介なのが種類を選んだ上に個体差まで気にしなければならなくなった結果、 このたったふたつの組み合わせが無限の可能性を生み出してしまうリスクが想定されること。 ただでさえお気に入りの種類を決めるだけでも色々なデザインがある上に、 中に入ったら入ったでものの良し悪しやクオリティの高低を意識せざるを得なくなりますから、 その悩みから永遠に解放されることの無い事実が底知れぬ奥深さを生み出しているのです。 今回やって来たのは同じヒョウモンガメと言う括りの中では最も評価の高いタイプのひとつ、 通称ホワイトヒョウモンと称される体全体から黄色味がすっきりと抜けるのが特徴の、 数年飼い込まれ健やかなる成長を遂げた貴重なメスの大型個体。 より幅広によりふっくらと仕上がるメスはオスに比べ需要が高まる印象で、 しかしながらいくらヒョウモンとは言え同種内で比較しても妙に背高なフォルムはこの個体最大の持ち味であり、 また成熟までに余力を残した現状のサイズで粗削りにも感じられる模様の入り方はむしろ好印象。 突然黄色く染まり始めることなど到底考え難いですから、 今後の成長に伴い少しずつ柄が変化していく様も見所と言えるでしょう。 性格は底抜けの明るさであるがために撮影は困難を極め、 呑気に写っているように見えますがその陰では延々と歩きっ放しだったのでした。 Mazuriリクガメフードにも餌付きころころうんちをもりもりしていて準備万端、 ひとまず30センチオーバーを目指して頑張りましょう。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| このやり過ぎなぐらいがちょうどよい見事なトールボディ! 非常に典型的かつ魅力的な上質の個体です、 国内飼い込みのヒョウモンリクガメ・メスが入荷しました。 まず一目見て心奪われるのは、 誰もが頷いてしまうその名の通りの豹紋柄ではないでしょうか。 原産地アフリカの情景にぴったりなこのド派手な柄はベビーの頃はすっかり影を潜めていますが、 さすがにこのサイズにもなればランダムに彩られる黒ぶちがすっかり姿を現しています。 また柄と合わせて凄いのがこのカメのシンボルとも言える甲高のフォルムで、 リクガメらしさとは何かと問われた時にこんなシルエットを頭に思い浮かべる方も多いと思いますが、 まさにあの憧れの像がこの個体では再現されていると思います。 ケヅメと並んでアフリカ大陸を代表するリクガメでそれは日本のペットトレードの歴史でも同じですが、 ごく小さいサイズでも強健なケヅメに対し本種はどこかデリケートなイメージもあるかと思います。 どちらも大型になりますが本種は何と言っても柄入りですから、 体質の面で不安な方はすっかり仕上がりつつあるこのサイズから初めてみては如何でしょうか。 長い付き合いのできるとても格好良い個体です。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト・♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 淡色で甲高なこの光景こそまさしく白い巨塔! 皆さんお待ちかねの本種では貴重な長期飼い込みビッグサイズ、 ヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 アフリカ大陸代表としてケヅメと双璧を成す、古くから日本でも良く知られているリクガメのひとつ。 名実共にどちらの種類も大型化することが知られ、そのせいか常にセットで捉えられることも多いのですが、 ケヅメが大きくなり過ぎて飼い切れなくなったというのはよくある話でも、 不思議なことにヒョウモンの場合はガツンと巨大になって困っているというケースを殆ど耳にしません。 理由を簡単に推察するならば、まず第一に飼育環境を疑うべきでしょう。 先程申し上げたようにケヅメとヒョウモンは同じ仲間という認識が極めて強いのですが、 現在ヒョウモンガメは本種のためだけに新属を設けるという説も有力で、 その時点でケヅメとは全く異なるカメだと切り替えるのが自然だと思います。 つまりケヅメと同じような飼い方では持て余す所か、長きに渡り飼い続けることも難しい場合があるということです。 今回やって来たのはボコ付きのボの字すらも感じられない理想的なフォルムを実現しながら、 色彩までも魅力的な容姿を持つ素晴らしい大型個体。 模様が細かく散らばりやすいナミビアに対しいくらかまとまりやすいバブコック、 その中でも極端に豹柄が結合するとこのようになるのでしょうか。 黒斑が退けた後には黄色味がすっきりと抜けて白に近付いた地色が存在感を主張し、 正面から見れば頭部周辺や四肢までもが淡い色調を呈しており、 ホワイトヒョウモンと呼ぶに相応しい大変美しい姿を表しています。 その様はネコ科の動物というよりも、大きなぶちと白い素肌がホルスタインを想像させるほど。 現時点でのサイズ、フォルム、カラーリング、全てにおいて満足のいく結果を残しながら唯一残念な点と言えば、 先天的な甲板ズレの一種なのでしょうか、 第3、4椎甲板がやや曲がってしまっています。 正直遠目から見れば全く気にならない、 というのは右から見ても 左から見てもとにかくこんもりとしているからという一言に尽きるのですが、 さすがに無視することはできずB品特価に設定しました。 色合いはもちろん実際ここまで滑らかなハイドームは本当に珍しいと思います、でかいヒョウモン狙いの方はお早めに。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (ホワイト・♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 稀少なメスの出物であることに始まり、優に十年以上飼い込まれ今や三十センチ近くもある巨体を持ち、 多くの人々が羨む白地の強いボディカラーや、各甲板が癒着せず見事に並んだ美しい仕上がりなど、 本種を愛するファンが思わず手を伸ばしてしまう、喜び要素満載の壮絶ハイクオリティ! ホシガメなき今、綺麗なヒョウモンガメに対する需要増は避けられません。 泣いても笑ってもオンリーワンの限定一匹、お早めに! | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| こんもりだなんて生易しい言葉では表現し切れません! 天に向かって爆発したハイドームな甲羅が象徴的な非常に珍しい大型個体、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 ヒョウモンと言えばケヅメと並びアフリカ大陸を代表する大型リクガメ、 というのがお決まりの文句ですがこの並びという言葉が全ての元凶だったのかもしれません。 結論から言えば決して並んではいませんし、並ばせてもいけなかったのです。 あちらには過酷な環境でも屈強な肉体と精神で乗り切る高いポテンシャルがありますが、 反対にこちらはがさつとは程遠い良く言えば聡明な、悪く言えばナイーブな心の持ち主。 外観を見ても何でも食べちゃうぞという大きな頭が目立つケヅメに対し、 ヒョウモンは小振りの頭が作り出すシルエットがどこか女性的で大きくイメージが異なり、 何より最新の分類で本種が独立し一属一種となっていることが全てを証明しています。 現にこれまでケヅメの大型個体はよく見かけてきましたが、 ヒョウモンは長期飼育例が少ないと言われる通りその数は圧倒的に少なく、 あえて直接的な表現をするならば持て余される状況にすらなり得なかったのです。 しかしながら今回、 マニアが手塩にかけて育ててきた最高のメスに出会うことができました。 まず一目見て驚いたのは15cm以上もある甲羅の高さ。 椎甲板の中央が天辺で目立っているので余計にそう見えるのかもしれませんが、 こんなスタイリッシュな姿だと距離を置こうがお構いなしにその存在感に圧倒されてしまいます。 現在は亜種を認めない説もありますがこの個体は超典型的なバブコックの表現で、 茶色っぽくなりがちな地色は鮮やかなレモンイエローに染まり、 ナミビアに比べて大柄の豹紋はこのサイズになってようやくその美しさを解き放とうとしています。 柄モノのリクガメと言えばホシガメなどが挙げられますがこれも立派な柄モノ、 ずっと見慣れたふりをしてきましたが野生個体の流通なき今、 成長に連れて徐々に仕上がっていくヒョウモンガメの柄をまじまじと堪能できる機会はそう多くありません。 すっかり育っているので今後シビアに環境を選ぶこともないと思いますが、 乾燥系と言われながらも幼体や手の平サイズではある程度湿っていた方がむしろ調子が良いような気がします。 持てるだけのスペースを駆使してこの美しい体をガツガツと歩き回らせてやって下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 溶かしバターのような濃い黄色をベースに黒斑が豪快に飛び散るこの美しい姿に与えるべきはグッドデザイン賞! 十年近くの歳月をもって積み上げられたトールボディは最上の喜びです、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 ケヅメリクガメとヒョウモンガメ、古くから一般的に流通しているため共に知名度は高く、 大型種という共通点からあたかも近縁な仲間のように扱われていますが、 近年の新しい研究によると同じアフリカ大陸出身でも双方の間には大きな隔たりがあることが分かっています。 単系統群など分類上の小難しい話はさておいて、 昔から何となく気にかかっていた両者の違いは確かなものだと判明した以上、 これからはそれぞれを全く別のリクガメとして再認識する動きが強まることでしょう。 本種は粗雑さや荒々しさとは全く無縁の上品で華麗な正反対のキャラクターを持ち、 甲羅の模様はもちろんのこと小振りでスマートな頭部ひとつとっても、 実際に対面した時に受ける印象は大きく異なります。 その見た目通り性質もどこか繊細であることが多く、飼育するにはやや癖があるとされてきました。 特に輸入されたばかりのベビーサイズではそれが顕著で、 いまいち掴み所がなく苦戦を強いられることもしばしばありますが、 近頃では特性が次第に分かってきたようでそれに伴い長期飼育例も増えてきたように感じます。 今回やって来たのは遂に30cmというヒョウモンにとっては夢の大台に突入した皆さんお探しの巨大なメス。 ハイスピードに育ち過ぎて困るぐらい頑丈なケヅメとは違い、まだまだ大型個体の貴重な種類ですから、 目で見て手に持った時の感動はとても普通種とは思えない、 むしろ普通種と言われているからこそ得られる特別な満足感をもたらしてくれます。 全体のフォルムも然ることながら、 ヒョウモンと言うからにはやはり如何に本物のヒョウへ近付けるかというのもポイントになってくると思いますが、 この個体は地色がレモンイエローに妥協せずしっかりと黄色味を帯びているため、 ヒョウになるための最低条件をクリアしています。 柄がまとまり過ぎると牛のようになってしまいますが、 筆に墨を染み込ませ殴りつけるように描かれた大きなスポットはひとつひとつが躍動感を内包し、 甲羅というキャンバスの上で理想的なバランスを実現していると言えるでしょう。 特徴の全てが個体差という性質により変容するからこそ、人々はそこに広がる可能性に夢を抱き、 秀逸な美個体という唯一無二の存在が誕生するのです。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 濃厚なクリームイエローに大変美しく散らばる豹柄が激しく炸裂した30センチオーバーの貴重なメス! ただでさえオスが多めなのにこれほど綺麗にそして大きく育った出物は極めて貴重です、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 単に体格の良さやアグレッシブさだけを取ればその人気ナンバーワンはケヅメに間違いないのでしょうが、 そこへ色柄の華やかさや見栄えの良さと言った要素を盛り込んだ場合、 時にかの有名なホシガメをも凌ぐ実力を誇るのがこのヒョウモンガメだと思います。 自然が創り出した偶然の産物に我々人間がとやかく言うべきではないのかもしれませんが、 こんなに派手な容姿で表をうろつかれては目立って仕方ないと感じつつも、 きっと現地の風景にはすんなり馴染んでしまうものなのでしょう。 ただしそうは言っても庭先やアスファルトの上を歩くその姿には相当なインパクトがあり、 たとえカメに詳しくない人が見てもその所作のひとつひとつが優雅に映るはずです。 大型種には珍しくなかなかの小顔でかつ甲羅は高く盛り上がるため、 全体のバランスの中で顔面が主張し過ぎない所もエレガントな雰囲気を生み出す要因のひとつと考えられますが、 やはりしっかりと育てられたその時にこそ持ち味が存分に発揮されるのではないでしょうか。 小さな時にはどのような外観になるのか全く想像が付かないため、 こうして十分に巨大化した個体を一目拝むだけでその印象は良くなるばかりで、 改めて種の持つ奥深い魅力を思い知らされるのです。 今回やって来たのはオスに比べてなかなか巡り合うチャンスに恵まれることのない皆さんお探しの嬉しいメスで、 しかも久々の30センチを超えた誰がどう見ても立派な大型個体。 何故だか甲羅がボコついたり、 特に背甲で各甲板の癒着が出やすかったり何かとトラブルに見舞われがちな本種ですが、 このメスにはそういった様子もほぼ見受けられずまさにお手本のような仕上がりには脱帽の一言。 この絶妙な色合いも何と表現して良いのやら、パッと見た時の印象がとてもスタンダードと言いますか、 決して並、普通というニュアンスではなく本来の特徴を凄く分かり易く伝えてくれる外観に、 もしかすると今まで特に興味が無かった方でも思わず食指が動いてしまう恐れすらあるでしょう。 撮影前には顔中にこびり付いた餌の汚れを強めにブラッシングして落としたにもかかわらず、 その数秒後には平然と道端を走り回る図太さに驚かされ、 ヒョウモンにはあまりない性格の明るさをまざまざと見せ付けられました。 ここまで良いこと尽くめの放出品は数年に一度の逸材です、お早めにお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (特大サイズ・♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 濃厚なイエローにバランス良く配置された大粒の黒斑が見事な豹柄を描く圧巻の十年選手! 繊細な性格のものが多い本種にしては珍しく気丈に振る舞うことのできる愛情たっぷりビッグサイズ、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 アフリカ大陸のみならずリクガメ界を代表するキャラクターとして知られるケヅメとヒョウモン、 長きに渡りこの業界を大いに盛り上げてきたそれらの功労者たちは、 最人気種と呼んでも差し支えない名実共に人々から認められた二大巨頭です。 無色無斑のシンプルなデザインのままただひたすらに大きく育ち、 持ち前の愛想で人々から注目を集めているケヅメとは対照的に、 何処か女性的でツンとすましたような表情からは気品が漂い、 甲羅に描かれた美しい模様も相まってとてもお洒落なのがこちらヒョウモンガメ。 柄の入るリクガメというのは科全体を見渡してもなかなか珍しい存在で、 尚且つペットとしては十分過ぎるほどに大きく育つものも数少なく、 他の種類では太刀打ちできないヒョウモンならではの魅力というものが確かに感じられ、 それ故に黎明期より一線級で活躍し続けている意味もよく分かります。 ハイスピードで巨大化し多くの人々を困らせてきたケヅメとは異なり、 成長が意外と緩やかで実際に大きく育った個体をなかなかお目にかかれないのも、 プラスアルファの付加価値が味わえるポイントのひとつ。 こんもりとしたドーム型のシルエットが如何にもリクガメらしいとファンの心を掴んで離さない、 愛好家が一度は必ず憧れる最高の銘種と言っても過言ではないのです。 今回やって来たのはその飼い込み期間も冗談抜きで本当に十年以上、 期待を裏切らないハイドームの立派なサイズに育て上げられた嬉し過ぎるメスの掘り出し物。 生育期間の大半を他人が多く集まる環境にて過ごしていたといい、 印象的だったのは人間を恐がることを知らず頭を撫でてもむしろ首を伸ばしてくるほどで、 ビビリでナイーブなイメージの強いヒョウモンにあるまじき反則的な愛嬌を身に付けています。 足腰もかなり鍛えられているのか甲羅から飛び出したそれはいつも以上に長く感じられ、 その美脚を軽やかに操り路上を闊歩する様は行き交う人々が思わず振り返ってしまうほど。 麗らかな春の陽気が訪れた絶妙なタイミングでの引き合わせに、運命を感じずにはいられません。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (特大サイズ・♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 一センチの重みがずっしりと伝わって来る十年以上の歳月を経て育て上げられた特盛サイズ! 色や形、それに四肢の筋力や動きのキレにまで一分の隙も見当たらない最高の出来栄え、 バブコックヒョウモンガメ・メスが入荷しました。 決して並外れた稀少性のある珍しい種類と言う訳でも無く、 はたまた恐ろしく飼育管理にテクニックを要する難関種と言う訳でも無い、 どちらかと言えばいつも私たちの傍にいてこちらが望みさえすれば手に入れることのできる、 ペットとしての歴史も長い代表的な銘種のひとつ、ヒョウモンリクガメ。 かつてリクガメには水を飲ませてはいけない、 カラッと乾燥した暖かい場所でドッグフードや九官鳥の餌を与えて育てる、 そんなあやふやな迷信がすっかり信じ込まれていた時代より、 立派なエキゾチックアニマルとしてここ日本でも飼育されていました。 皆さんご存知の通りカメとは元来強健な生き物ですから、 そんな風にピントのズレた状態でも何となく生き延びてしまい、 しぶとく命を繋いでいた個体も中にはいたのではないかと思われますが、 最終的には無理がたたって命を落としてしまうケースの方が圧倒的に多く、 可能性としての寿命とはかけ離れた短い期間で生涯を終えることは、 こちらとしても望んでいた結果ではありませんでしたから、 先人の試行錯誤の積み重ねによって今日の飼育マニュアルのようなものが確立され、 多くの愛好家が一匹のリクガメを逞しく育てられるようになりました。 しかしながら他種に比べて長い生育期間を設けなければならないこのヒョウモンガメについては、 未だに大型個体の出物と巡り合えるケースは稀であって、 これほど素敵は出会いは十年に一度、 いやそれ以上の感動を呼ぶ出来事ではないかと強く感じています。 今回やって来たのはほぼ40センチクラスに到達したあまりにも巨大なメスで、 本種にしばしば起こる各甲板の癒着跡もほぼ全く見当たらない、 何処から見渡しても仕上がり最良なクオリティの高さに脱帽の一言。 シンプルにメスの方が少ないためレアリティの高さはお墨付きで、 加えてこれまでの運動量を証明するかのような強靭な足回りは、 少し野外を散歩させればじっくりと感じ取れる目に見えない付加価値となっています。 彼女の一生はもちろんこれでおしまいではありません、 当面の目標はひとまず40センチオーバーとして、 更なる高みを目指し再び目の前の一歩を踏み出しましょう。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (♂・♀) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| 夏のジメジメにも負けないボリューミーな飼い込み安心サイズ! 性別確定のしっかり育った2匹です、ヒョウモンガメが入荷しました。 アフリカ出身の柄モノリクガメで、同地域に棲息するケヅメリクガメとは兄弟分のような関係。 どちらもかなり大型化することで知られていますが、 大きなケヅメは見慣れていてもそれに近いサイズのヒョウモンはなかなか見かけません。 現地の写真を見るとヒョウモンでもこんなに大きくなるんだ、 というような甲羅の高々と盛り上がった大型個体が紹介されていますが、 にもかかわらず国内での出会いが少ないのは何故でしょうか。 アロハシャツの絵柄にもなりそうなファンキーな外観は陽気で活発な雰囲気でも、 実際に飼育してみると意外な所でケヅメとの違いを思わされます。 特にベビーサイズでは良い意味での図々しさもあまり無く、 少し繊細なイメージさえ受けるかもしれません。 しかしここまで育ってしまえばなんのその、 湿気の多いこのシーズンでもスラっと長い足を伸ばしてケージ内を所狭しと歩き回り、 見栄えの面でも黒斑が適度にバラけ美しい豹柄をつくり始めています。 またメスはサイズの大きいこともあってか甲羅がどんどんと高く盛り上がり、 いわゆる理想のリクガメ体型になりつつあります。 今回はたまたま2匹やってきたのがオスとメスだったので、 バラでも大丈夫ですしペア価格もご用意しておきます。 全体のフォルムが綺麗なので一見分かり難いですが、 オスと メスそれぞれに甲板の偏りがあるためお値打ち価格。 このサイズから始めて巨大ヒョウモンを目指しましょう。 | ||||||||||
|
バブコックヒョウモンガメ (サブアダルト・Pr) Geochelone p. babcocki |





|
|
||||||||
| これはでかい!お客様がベビーサイズよりたっぷりの愛情を注ぎ育て上げた、 ヒョウモンリクガメ・ペアの入荷です。 模様が綺麗で状態の良かったベビー2匹をセレクトし飼っていたらたまたまペアになったそうで、 多少のボコつきもありますがこのサイズで考えれば許容範囲でしょう。 何より嬉しいのがこんもり甲高に育ってくれた事で、 甲長以上にその存在感に驚かされます。しかもメスは既に産卵経験アリ。 まだまだ成長盛りのヤングペアですので、これからの暖かい季節には是非お外に連れ出し十分な運動量と日光を確保して上げて下さい。 全国発送も可能ですので通販をご希望の方もご心配無く。 | ||||||||||
|
ナミビアヒョウモンガメ (ベビー) Geochelone p. pardalis |





|
|
||||||||
| 到着して間もなく誰に遠慮することもなくMazuriリクガメフードを爆食した過去最強クラスの優等生! ただのヒョウモンガメに非ず、模様が異なり並のヒョウモンに比べより大型化する珍しいタイプの、 ナミビアヒョウモンガメが入荷しました。 最新の分類ではStigmochelys属にたった一種で独立したことになっている、 今日では貴重な柄付きリクガメとして有難がられている言わずと知れた往年の銘種。 つまりホシガメやパンケーキガメなどが軒並みCITES入りする中で、 一般に広く流通するリクガメの中では唯一と言っても良いほど、 背中にそれらしいデザインが施されたものは却って少数派となっており、 陳腐な表現ではありますが如何にもリクガメらしいシルエットも相まって、 特にこの数年では歴史的に見ても人気が最高潮に達しつつあるものと思われます。 先に触れたStigmochelys属に移行する際に、 かつて基亜種ナミビア、亜種バブコックとされた分類は無効になる説が強まり、 というのも結局は中間的な個体群がその境目を曖昧にしているからなのだそうですが、 とは言え我々の認識ではナミビアやバブコックだけではなく、 妙に巨大化することで知られるソマリアや、最近になって輸入され始めたケニアを由来とする個体群など、 下手をすれば大きく二分することさえ難しい、 四つにも五つにも分けたくなるようなバリエーションが実在するために、 ホビー的には今後も面白おかしく見分けていければと思う次第です。 今回やって来たのはピカピカのベビーサイズで輸入された美しきナミビアヒョウモンより、 初期状態に拘ってセレクトしたところ恐るべきスタートダッシュを切ってくれたこんな一匹。 正直、初見の印象としては小さ過ぎやしないかとハラハラしていましたが、 そんな心配を他所に初給餌からいきなりMazuriのみでお腹いっぱい平らげ、 入店してまだ数日のはずが早くも成長線がうっすら伸び始めた、 気味が悪いほどに明朗快活な誰でも育てられる最高のコンディションです。 気になる外観はナミビアらしく焦げ茶主体のカラーリングに、 甲羅の縁がギザギザとする辺りもバブコックに比べ明らかに異質で、 何処となくチャコリクガメなどを思わせる野生的な風貌に惚れ惚れします。 体の模様についてはよく言われているように地肌にびっしりとごま塩が入り、 くるりと後ろを向ければお尻の周りにも同じようなスポットがはっきりと見て取れます。 せっかくの一生ものですから綺麗な絶品に仕上げたいとお考えの方へ、 お渡しの際には誰もが振り返るほどのシルエットに仕立てるべく、 抑えるべきポイントを詳細な飼育方法と合わせてご案内したいと思いますので、 リクガメ飼育が初めての方でもご安心下さい。 | ||||||||||
|
ナミビアヒョウモンガメ (S) Geochelone p. pardalis |





|
|
||||||||
| か弱いイメージを払拭する健康優良児! 全く真逆の印象すら覚えるとても元気な個体です、ナミビアヒョウモンガメが入荷しました。 いわゆるヒョウモンリクガメ、ではないもう一つのヒョウモンがこのナミビア。 亜種バブコックに比べると地色が濃い黄色になり象徴的な甲羅の柄は細かく緻密に描かれ、 その二つの特徴を見るによりヒョウという生き物に寄った外観を持つのは基亜種ナミビアではないかと思います。 バブコックも見た目の派手さは優秀で同じネコ科には似たような柄を持つものがいるかもしれませんが、 ヒョウに限った再現度に着目してしまうと一歩劣ると言わざるを得ないでしょう。 おまけに基亜種には体中にもごく小さいながら確実に細かいスポット模様が密集することで、 甲羅だけでなく全体像として着飾ることに成功しています。 同じアフリカ地域に棲息するケヅメリクガメと比べると一見似たような雰囲気を持ちながら性質には大きな違いがあり、 亜種問わず神経質だと感じてしまう線の細い体質はいつも悩み所として挙げられます。 導入当初から大人しいものは心を開くのに随分と時間がかかったりするものですが、 しかし今回やってきたこの一匹はいつ見てもケージ内を走り回り、 餌のにおいを嗅ごうものなら喜び勇んでこちらに向かって全力で駆け寄ってくる姿などは実に微笑ましいです。 そんな光景もやはりヒョウモンにしてみれば貴重なワンシーンで、 こちらを安心させてくれる何よりの材料だと思います。 新しい成長線も出始め軌道に乗り出した様子、 この勢いで大きなナミビアへとじっくり育て上げましょう。 | ||||||||||
|
ナミビアヒョウモンガメ (EUCB・S) Geochelone p. pardalis |





|
|
||||||||
| 言葉は悪いですがヒョウモンのちびのくせに大手を振ってケージ内を闊歩する超健康体! 今までの苦労は何だったのかと呆れ返るほど達者な安心サイズです、 EUCBのナミビアヒョウモンガメが入荷しました。 当店ではこうして年がら年中様々な種類のリクガメを扱っている訳ですが、 近頃俄かに支持率の高まりを感じられるのがこのヒョウモンガメ。 時代を遡れば日本にリクガメという生き物がペットとして出回り始めた頃からの顔ですから、 今更珍しさがクローズアップようなこともなく古参メンバーとしてすっかり定着しているぐらいなので、 人目に触れる機会はずっと多くビギナーからマニアまで幅広い層からのファンを獲得しています。 しかし知名度が飼育数に必ずしも反映されるとは限らないようで、 これまでに敬遠されてきた理由としてはまず第一に大型になること、 それを言ってはおしまいな気もしますがお陰で少なくとも万人向けとはならず、 加えて同様に巨大化するケヅメなどと比べると神経質で飼い辛いイメージが抜け切れなかったため、 知らず知らずの内に敷居が高くなってしまいました。 それが最近ではどうでしょう、ヒョウモンが大きくなり過ぎて困るという話は現実的に意外と少なく、 蓋を開けてみれば30センチ程度に育て上げることすら至難の業であることが分かり、 更には散々見慣れたはずがこの頃は何故かセンセーショナルに思える豹柄の美しさが再認識され、 多方面からのニーズが急速に上昇しているようです。 どちらかと言えば飼育の難しい部類だったことも今では随分と状況が良くなり、 それは繁殖個体の流通や長期飼育例の増加にもよく表れているのではないでしょうか。 今回やって来たのはヨーロッパから輸入されたCBベビーがやや育ったもので、 どうせずっと頭を引っ込めたまま写真を撮ることも許してくれないだろうと思っていたら、 60センチのケージを明け渡した瞬間所狭しと一面を走り回り、 その後即座に餌を爆食し始めたことには大変驚きました。 大型個体を放し飼いにしようとしても隠れたまま一歩も動かないことも珍しくないヒョウモンが、 こんなに小さな年頃で早くも怖いもの知らずな躍動感を見せてくれたら、 これから逆に何に気を遣って付き合っていけば良いのでしょうか。 環境としては床材にヤシガラなど保湿性のあるものを選び、 それなりに湿らせておけばあとはカメ任せでやっていけるはずです。 同じヒョウモンでもバブコックかナミビアで迷う所ですが、 模様の細かさと体中に染み渡る濃い目の橙色が上品だと感じられればこちらで決まり。 飼い込み個体の放出も前者ではしばしば見かけるものの後者ではあまり例がなく、 それだけに力の注ぎ甲斐も存分に味わえるのではないかと思います。 とにかく性格の明るさが一押しの是非とも大きく育てて上げたい素晴らしいナミビアです。 | ||||||||||
|
ヒョウモンガメ (ケニア東部産・ベビー) Geochelone pardalis ssp. |





|
|
||||||||
| 茶褐色の隙間から白い模様がとろとろ溢れ出すまるでチーズインハンバーグのような将来有望のベビー! 入荷して暫くバックヤードにて訓練を積み晴れてMazuriリクガメフードオンリーで育てられるようになった、 ケニア東部産のヒョウモンガメが入荷しました。 これから申し上げることに妥協の念は一切含まれていないことを予めお伝えしておきますが、 今日のペットトータスを取り巻く様々な状況を一通り加味した上で、 私たちが利用可能な資源の中で最も有用な選択肢のひとつではないかと思われる、 特にここ数年でその人気ぶりが一段と上昇しているのが、 まさしく本日ご紹介するこのヒョウモンガメではないでしょうか。 飼育対象としては実に数十年も前より常に最前線で活躍し続けているキャラクターですから、 今改めて持ち上げてみたところで何を今更と思われるかもしれませんが、 世界中のリクガメが束になって掛かって来たとしても、 本種が特に秀でている点をいくつも挙げることはさほど難しくはありません。 まず真っ先に思い浮かぶのはリクガメでは貴重な柄モノである、 つまり多くの種類が色合い一本で勝負せざるを得ない場面に出くわす中で、 こちらヒョウモンは亜種やタイプにより色彩にも模様にもバリエーションが存在する上に、 更に突き詰めれば各個体一匹一匹がオリジナルのデザインを持つことも不可能ではないほど、 世界中のファンをまず視覚から徹底的に楽しませてくれる点が優れています。 そしてもうひとつ大切なのは彼らが想像通りのこんもりとした甲羅を背負っていることで、 これはリクガメという生き物は総じて背が高くあるべきだという、 人間が勝手に想像し勝手に描き出したある種の暴力的な偶像だったはずなのですが、 そんなぼんやりとした理想を見事現実のものとして歩かせてしまったのが、 このカメが持つ平和で嫌味のない天高くカーブを描くそのシルエットだったのです。 他にも探せばまだまだその魅力を発掘することは困難ではないのでしょうが、 たったこれだけでも十分な衝撃を与えてくれる確かな実力者なのだとお分かり頂ければ幸いです。 今回やって来たのは近年になり目立って出回るようになった、 かのホワイトヒョウモンが産出され易いと評判の名産地、ケニア東部産として輸入された幼体たち。 流石に生まれたばかりの姿では並のヒョウモンと大差ないように見えるかもしれませんが、 早速伸び始めた新たな成長線にはいきなり見事な白さが際立ち、 このままフォルムを崩さずに仕立てられれば嫌でも綺麗になること間違いなし。 そもそもベビーサイズという時点で嬉しいはずなのに、 その上これほどの高い潜在能力を見せられれば食指が動かぬはずがありません。 | ||||||||||
|
ヒョウモンガメ (ケニア東部産・ベビー) Geochelone pardalis ssp. |





|
|
||||||||
| 白さ際立つ大人気のケニア東部産も遂にラスト一匹! 最後まで残ったのは何故かこの個体、成長線にはしっかりと黒い模様を残しつつも、 甲羅のベースから四肢に至るまで全身美白な将来有望の注目株です。 今や快食快便、Mazuriリクガメフードしか与えていませんが無問題、 誰にでも育てられるハイスペックな安心サイズ。最新の写真と共に再アップ! | ||||||||||
|
ヒョウモンガメ (ケニア東部産・ベビー) Geochelone pardalis ssp. |





|
|
||||||||
| 大きくなるに連れて少しずつ白く白く仕上がっていくと噂される魅惑のニューロカリティ! 分類事情の混沌としている今だからこそ確実にロカリティの分かるタイプを選びたい、 ケニア東部産のヒョウモンガメが入荷しました。 かつてGeocheloneと呼ばれる大所帯が存在していた頃、 もちろん未だに認められたリクガメ科の一属として残されてはいるものの、 数多くの仲間たちがここから巣立ち新たな属を立ち上げ、 今日ではリクガメ全種もかなり緻密な分け方へと変容しています。 そんな流れの中でこのヒョウモンガメにはStigmochelysと言う新しい名称が与えられ、 一属一種のリクガメとして旗揚げをすることと相成った訳ですが、 従来のナミビアやバブコックと呼ばれ亜種分けされていたものが全て統括され、 ひとつの大きなヒョウモンガメとして考える説が生物学においては主流となっているそうです。 しかしながら我々にとってヒョウモンは決して一種類のカメでは無く、 外観から多様な形質差を見出して来た経緯がありますから、 今更全部同じだなんて言われても納得できるはずがありませんでした。 そこでいくつかの呼称は従来のルールに則りそのまま残され、 それに伴う付加価値はさて置き便宜上タイプを分けて流通しています。 今回やって来たのは最近話題に上がるようになった新産地、 ケニアは沿岸部の東部産として紹介されているファームハッチのベビー。 そもそも幼体と成体では色合いが異なるデザインなので、 この時点では似たような見た目だとしても致し方ありませんが、 成長に伴い全体的に明色部が広がり易い傾向にあるらしく、 平たく言えばホワイトヒョウモンの名産地として一躍有名になった個体群です。 変な言い方ですがいわゆるバブコックと呼ばれる普通のヒョウモンと比べて、 幸い飛び抜けて取引額が高いことも無いので単純に選び易く、 また心なしか初期状態も並のヒョウモンより上質で輸入されたてでもより扱い易い印象です。 最も巨大化するとされるソマリアに近い形質が見られるとの話もあり、 まだまだ謎に包まれていますがそのもやもやで暫くは楽しめそうな気がします。 決して乾燥系のリクガメではありませんのでご注意下さい、 詳しい育て方はお渡し時にお伝えしたいと思います。 | ||||||||||
|
ヒョウモンガメ (ハイカラー・ケニア東部産) Geochelone pardalis ssp. |





|
|
||||||||
| 象牙色に包まれた淑やかな雰囲気が近い将来の美貌を予感させるセレクトハイホワイト! 白くなり易いと定評のあるケニア東部産の中でも飛び抜けて色味の良いミラクルな一匹、 ヒョウモンガメが入荷しました。 私たちが主な活動拠点としているペットの世界においては、 長きに渡り同じアフリカ大陸に産するケヅメリクガメの相方として扱われて来た、 やはりこちらも大型に成長することで有名なヒョウモンガメ。 単純に棲息地域と最終サイズがよく似ていることから同じ括りに入れられてしまった訳ですが、 最近の研究では本種のみで単系統を形成する説が有力であり、 つまりケヅメとは特別な類縁関係を持たないと考える方が自然なのだそう。 それに伴って基亜種ナミビアと亜種バブコックのふたつに分けられていた従来の分類が、 全てを一緒くたにしてしまったり別のやり方で再分割を行うなど、 これまでとはいくらか異なる説が提唱されるようになりました。 この話の流れで真っ先に思い浮かぶのはソマリアと呼ばれるあのタイプだと思いますが、 それ以外にも未だ見ぬ謎に包まれた部分はいくらでも存在する可能性があり、 例えば最近輸入されているケニア東部のタイプについても同じことが言え、 成長に伴い甲羅の明色部が広がる傾向があるなど一定の特徴が見られるようです。 少なくとも普通のバブコック、普通のナミビアとは違った形質を有するだけあって、 趣味の分野においては別のものとして捉えるべきではないかと思います。 今回やって来たのは同じケニア東部産の他個体と比較しても明らかに優れた外観を持つ、 甲羅はもちろん頭部や四肢まで体中が白く色抜けした選りすぐりのこんな個体。 生まれ持った初生甲板の色味からしてやや薄めのラインが引かれていますが、 成長線も次々と白っぽい部分が広がるように伸び、 お肌の色も心なしか薄く明るい感じに仕上がっていて、 顔の表情にはまるでエロンガータリクガメのような優しさが感じられます。 仕入れ元にて暫くストックされていたお陰でコンディションは至って安定しており、 現時点で目視できる成長線も日本にやって来てから現れたもので、 今後の環境設定を大きく誤らなければ甲羅もツルンと高く盛り上がってくれそうです。 同じ名前で陳列されていてもなかなかお目にかかれないハイクオリティ、お見逃し無く。 | ||||||||||
|
ケヅメヒョウモンリクガメ (♂) G. sulcata × S. pardalis |





|
|
||||||||
| リクガメ界の二大スターによる夢の豪華競演! 本当に久しぶりに実物をお目にかかりましたが誰もが目を見張る抜群の仕上がりです、 ケヅメヒョウモンリクガメ・オスが入荷しました。 パッと見せられただけではただただ混乱を招くのみの非常に罪深い存在です。 その正体とは一昔前、ほんの一瞬の出来事だったように思いますが確かに流通した経緯のある、 ケヅメリクガメとヒョウモンガメのハイブリッド。 ご存知の通りどちらともアフリカを代表する大型種としてよく知られており、当時は遂にこんなものまでという衝撃と、 これからの時代はこんな珍しいリクガメが飼えるようになるのかという期待感を覚えました。 しかし決して安価なものではなく、また繁殖個体ということもありつい先送りにしてしまった方も少なくないと思いますが、 少し目を離した隙に影も形もなくなってしまい、その後は幻の存在として語り継がれるのみとなってしまいました。 当然この個体を単なる交雑として見た場合には賛否両論あるのでしょうが、 そもそもケヅメやヒョウモンを飼育している人の中で繁殖まで志すような人はほんの一握り、 圧倒的大多数は一匹を大切に育て上げることだけでも精一杯ですから、 あくまでもペットとして割り切る姿勢であれば品種として捉えることで面白いキャラクターになると思います。 ところで話は少し変わりますが、現在両者は別属として分類されているため結果的には属間交雑ということになり、 当時は何も考えなかっただけにますます興味深いと感じる次第です。 いよいよ今回やって来た個体について見ていきますが、 その全貌はケヅメともヒョウモンともはっきりどちらとも言い難い、 限りなく完璧に近いセンターを一直線に攻めた様子が芸術性をふんだんに発揮しています。 細長く背の高い甲羅の形はヒョウモンをベースにしながら所々にケヅメの逞しさがチラつき、 豹柄は随分ぼんやりとマイルドに描かれています。 顔を伸ばすと輪郭はヒョウモンそのものなだけに、ケヅメの表情の中にはどこか愁いを帯びた雰囲気が垣間見え、 頭を引っ込めた時にすっぽりと収まる所は実にヒョウモンらしいのですが、 それをシャットアウトする前肢の鱗は完全にケヅメのそれ。 一通り特徴を列挙してみましたが見れば見るほど思考が混乱するような、 不思議な世界へと連れて行ってくれる貴重な一匹であることがお分かり頂けたでしょうか。 そんなせっかくの優良素材も生かされなければ全く意味がありませんが、 この見事な育ち具合に誰が文句を付けるのでしょう。 ヒョウモンらしいハイドームなシルエットにケヅメが持つカラーリングが混ざり合い、 出来上がったキャラメル仕立ての美しい姿は見ているだけで堪らず惚れ惚れしてしまいます。 前飼育者は常に放し飼いを意識していたそうで、定期的に屋外へ散歩に連れて行くなど日頃かけてきた愛情の成果が、 均一に削れ整った爪などの細部にもその証としてきちんと表れています。 その後輸入されなくなってしまったものはどうしようもありませんので、 ケヅメヒョウモンがどうしても欲しいという方に捧ぐ、魅惑の一点ものです。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (ベビー) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| 激動の時代を経てここまで辿り着きまた新たな課題へと挑み始めた不朽の人気種が待望のベビーにて再び! しかしそんな小難しいことは綺麗さっぱり忘れさせてくれる底抜けに可愛いあどけない表情が素敵です、 ビルマホシガメが入荷しました。 初めてこのカメが世に出た頃は近縁種インドホシガメの対抗馬というような位置付けだったのでしょうか、 原産のビルマが国名をミャンマーと変えてから既に二十年以上が経過していますが、 ひとつの生き物にとっては本当に僅かなその期間にこのカメは様々な境地を体験し味わったのではないかと思います。 種としての記載は今から百五十年近く前まで遡りますが、 分布域があまりにも狭いために1990年代初頭には遂に絶滅したのではないかと騒がれ、 その後ペットトレードにて再起を果たしたものの依然現地の状況はあまり好ましいものではないようです。 初めて来日して暫くは超がいくつ付くのか分からないほどの高額生体でしたが、 その後は少ないながらもじわじわと流通量が増え遂には国内繁殖成功のニュースも飛び出し、 庶民的とは言えませんが手を伸ばせば何とか届く距離にまで近付くことができたのではないでしょうか。 決して安くはないけれど丈夫で飼いやすく美しい初学者にとってもお勧めのリクガメ、 そう言われるようになったのも諸ブリーダーによる努力と功績の賜物だと思いますが、 この度遂にCITES審議においてⅠ類への昇格が懸念されています。 これだけ人工繁殖に成功しているのだからという楽観的な考えと、 ミャンマーのごく一部にしか棲息しておらずその数もさすがに減っているだろうという慎重論が入り乱れていますが、 我々にできることと言えば今こうして日本で暮らしているビルマホシガメたちを、 一匹ずつ愛好家の手によって大切に育ててあげること、 そしてゆくゆくはそれらが種親となり次世代を残すまでに至ること、 それぐらいのことと言われてしまうかもしれませんがこれもひとつの愛情表現です。 今回は星型模様も三者三様、 ハッチリングではなく一回りも二回りもきちんと成長線が出ていて甲羅全体に張りがあり、 コンディションは軒並み抜群という最高のセレクト個体をご紹介できる運びとなりました。 既に葉野菜からMazuriリクガメフードまで満遍なく餌付けてありますので、 CITES入りのピンチをチャンスに変えるべくそれが最後に背中を押してくれるきっかけになればと考える次第です。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (S) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| 手の平に乗せてしっくりくるツルンと上手に育てられた安心サイズ! いくら丈夫と言われてもさすがにベビーでは不安という方はこの大きさから始めましょう、 ビルマホシガメが入荷しました。 単純にホシガメと無印で呼ばれる場合、それは近縁種インドホシガメのことを指すことになっていますが、 頭の三文字が異なる以外に両者にはどのような違いがあるのでしょうか。 インドホシガメはその名の通りインドやスリランカ、パキスタンと中東方面にも分布していますが、 本種はビルマ、ちょうど平成生まれぐらいの世代にとってはあまり耳馴染みのない言葉ですが、 インドとはバングラデシュを間に挟み中国の南に位置する、ミャンマーの固有種です。 インドは棲息域も広いだけに昔から国内で出回り、 初心者向けとは言われないまでも圧倒的な知名度を誇るご存知の通りリクガメの代表種ですが、 対してビルマは90年代初頭には絶滅したのではと囁かれるほど現地では激減しており、 いつまでも変わらず高級種の座を守り続けています。 同じホシガメでも流通量や価格帯には大幅な違いが見られますが、飼育が難しいとされるのはインドホシガメの方で、 これがビルマホシガメの話になるとむしろ飼育は簡単な部類と全く正反対のことが言われています。 元来持つ性質からなのか、未だにその理由がはっきりとしませんがとにかく頑丈で、 生まれたばかりのいわゆるピンポンサイズでもインドのように怯える必要はさほどありません。 性格についても明るく活発な個体がかなりの割合で存在し、 大股開きでバタバタと走り回ったり餌場に滑り込むように突進してはガツガツと食べ散らかしたり、 一般的なホシガメのイメージをあっさりとぶち壊す驚異的なポテンシャルを秘めています。 全体のカラーリングについては好みによる所もありますが、 ラインの本数は若干少なめながらも一本一本が綺麗に繋がり整いやすく、 頭部や四肢などには殆ど黒斑が入らないため、表情がすっきりとして可愛らしく見えるのも隠れたポイントです。 今回やって来たのはベビーサイズから飼い込まれすっかり成長の軌道に乗った一匹。 リクガメ飼育では小さな頃から育てたいという希望が常々聞かれますが、 9cmという数字を見るとやや大きいように感じられるものの、幼体として販売されているのは大体6cmぐらいなので、 まだまだ幼少期から面倒を見ているという感覚を十分に味わうことができるでしょう。 それでいて成長線はもう何回りか分からないほど順調に刻まれていますから、 あまり自信がないという方にも手放しでお勧めできますし、 夏と言うこの季節も飼育をスタートするにはうってつけのタイミングと言えます。 サイズアップすれば当然か弱いベビーよりも値は張ってくるのですが、 この個体は右第4肋甲板が二つに分かれているため、 ベビーと同等かややお値打ちな価格に設定しました。 しかし前飼育者も最後まで気が付かなかったと言うほど目立ち難い程度なので、 気にされない方にとっては絶好のチャンスです。 性別は不明としましたが、 この調子でいけば貴重なメスになってくれそう。 葉野菜、Mazuriリクガメフード、餌の選り好みもないグッドコンディションにてお届けします。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ
Geochelone platynota |



|
|
||||||||
| ビルマホシガメですが、やっぱりホシガメとビルホシは一見似てますが、 全然違いますね。少々温度低くても平気だし、何でも食べるし警戒心も少ないし。 ピンポンサイズのホシガメ飼うなら絶対ビルホシをオススメします。高いですが。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (国内CB・♂) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| 均一に整った良好なフォルムと地味でなければ華美にもなり過ぎない秀逸なデザインに一目惚れ! ブラックベースにもかかわらずパッと明るい印象を与えてくれるのは流石です、 ビルマホシガメ・オスが入荷しました。 市場で見かけることすら不可能なあまりにも珍しい種類は除くとして、 もしリクガメ四天王というものが形成されるとすれば間違いなくその一員に加わるであろう、 言わずと知れた永遠の銘種ビルマホシガメ。 インドホシガメよりも高価だが活発な上に強健であるという謳い文句はあまりにも有名で、 どのような書籍や資料にも必ずと言って良いほどもれなく登場することから、 ビギナーにとって真っ先に憧れの的と成り得る可能性が最も高くその人気の高さにも頷けます。 あれから二十年ほど経つでしょうか、 一時は絶滅したとも騒がれ事態は一旦沈静したものの本来の分布域は確実に狭まっているという話ですが、 まとまった集落がいくらか新たに確認されたため現地では密猟を減らすべくファーミングを設け、 そこで繁殖された幼体を輸出する試みも実際に行われているようです。 そんな背景を無視することもできず、 いま最もCITESⅠ類に昇格する可能性の高いリクガメという実に不名誉な称号を与えられてもう何年も経過していますが、 この度遂に定例のCITES締約国会議において厳しく取り上げられることが分かっています。 これまで苦し紛れに何とかしぶとく堪えてきたのもお国の事情、 大人の事情が潜んでいることはこちらも察しなければならないとは思うのですが、 ミャンマーという一国の限られた範囲にしか棲息していないカメを守りたいとなれば、 我々の立場では為す術もなくただただ首を縦に振り現実を受け入れるしかないのです。 今回やって来たのは国産のベビーから立派に育て上げられた手頃なサイズの一匹。 放出の理由には何の疚しいこともなく、 単純にメスになれば嬉しいなという気持ちで育成していたらオスになり、 手元には既に付き合いの長い先輩のオスがいるためとのことでした。 各甲板の多少の盛り上がりは許容の域、 飼育法にはある程度通じていたようで成長線は図ったように規則正しく刻まれており、 何よりもケージ内をグルグル歩き回る明朗な性格が大切にされていたことを物語っています。 次の飼い主へのバトンタッチまで想定していたと言うのは考え過ぎかもしれませんが、 店頭である程度寝かしていてもトラブルの欠片すら見当たりませんでした。 そして知れば知るほど拘って追求したくなる星型模様、 この個体はいわゆる極太ではありませんが究極の自然体を目指しているようで、 違和感なくぴたりと収まる様子はイメージ通りと言えるのかもしれません。 特に繁殖を考えないのであれば大きくなり過ぎないオスの方が絶対にお勧め、 残り一ヶ月少々ですが心を決めるには絶好のチャンスと捉えましょう。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (♂) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| 世代を超え歴史を遡るクラシックな長期飼い込み個体! 栄光の時代を物語るような今や入手困難のワイルドです、 ビルマホシガメ・オスが入荷しました。 過去の図鑑を開いてみれば激動の変遷を垣間見ることができるでしょう。 今でこそインドより明るい性格で飼いやすいなんて言われることもありますが、 何年間も姿を見かけることができない時期が続いたことから一時は絶滅したとまで囁かれる程の超稀少種でした。 その後大型の野生個体が少ないながら日本にもやってくるようになり、 数年後にはそれらが種親になり国内ブリードのベビーも出回るようになりました。 現在では繁殖個体数もじわじわと増えてきたようで高値安定ながら毎年コンスタントに姿を見かけるようになりましたが、 逆にその流れで全く姿を消してしまったのが野生個体。 今の時代ワイルドが輸入されたという話はほぼ聞かないと思います。 チラホラ出てくるのは当時からの飼い込み個体で、 ということは今日本国内にいる分しか野生のビルマはいないということになります。 そして今回やってきたのはよりにもよって時代を固めてつくったような迫力の一匹。 サイズはそれ程ですが逆に小さくまとまった感じが素敵で、 8年近くの飼い込みだそうですが顔付きや風貌にもその様子は現れています。 そしてこの個体最大の特徴は、 こんなの始めて見ましたがぴろんと長く伸びた尾先のトゲ。 全く意味が分かりませんがどこか卑猥でどこか逞しく、思わずにやけてしまう面白い個性です。 ごく小さい剥離跡は輸入当時からのもので、 これ以上治りもしないがノントラブルでここまで来ているとのこと。 もうひとつ、オスにしても妙に細長いと思ったら椎甲板と両側の縁甲板が一枚ずつ多いのですが、 言われなければ全く気がつかないほど自然な仕上がりです。 少し前までこの位のビルホシはたまに見かけましたが最近は出物も減ってきました、 繁殖などは関係なしに個体として興味深い一匹です。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (アダルト・♂) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| フルサイズも間近の太バンド美個体! お客様委託のビルマホシガメ・オスが入荷しました。 先日までメスを2匹加えたトリオで販売しておりましたが、本日よりオスのみでのご紹介です。 今まで交尾し放題の恵まれた環境にいたこのオスは、 小柄ながら30cmクラスのメスにも果敢に挑む性欲の強さを持っています。 そんなやる気は認めてあげたいのですが、やはり最大サイズにはそれぞれ個体差があると思いますので、 より適した大きさのメスと組み合わせてやった方がこのオスももっと幸せになれるかもしれません。 また、前飼育者様のお宅ではブリードを視野に入れた飼育がなされていたそうですが、 必ずしも全ての人が繁殖を目的としなくても良いと思います。 本種はリクガメの仲間で比べると巨大種とは言えませんが、 現実的に30cm近くなるカメを飼うにはそれなりの設備が必要です。その点でオスはメスほど大型になりませし、 20cmちょっとの個体であればこの美しいリクガメと無理なく付き合っていけるのではないでしょうか。 見た目もお好みがあるでしょうが、 今回の個体は1本1本のラインが太くクッキリ入って見栄えも宜しいかと思います。 ほぼアダルトサイズですが委託の為の特別価格ですのでなかなかこの値段では出せません、 是非ともこの機会にご検討下さい。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (M・♀) Geochelone platynota |




|
|
||||||||
| クリーム色のラインとジェットブラックの下地とのバランスが絶妙なビルマホシガメが入荷しました。飼いこみ個体で とても元気が良く写真を撮るときも、じっとしてくれません(笑) 背甲も美しいドーム型で見ていても時間を忘れるくらいです。餌を与えようとケージの前に行くと寄って来て、 手を差し出すとアマ咬みしてくるほど人馴れしています。 Mazuriリクガメフード・葉野菜を手からでも食べています。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (♀) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| 性別確定安心サイズ!上品なライン取りが美しいセレクト個体です、 ビルマホシガメ・メスが入荷しました。 1本1本全てが綺麗に繋がったラインは、 まるで細筆でなぞったようなエレガントさを表現しています。 この辺りは好みの問題だと思いますが、この個体はスラッと細バンドタイプといった感じで、 コテコテの派手な見た目で勝負するインドホシガメとは似た模様でも全くの対極でおもしろいです。 やはりCBものなので完全につるんと真ん丸とはいきませんが、 それでもこのようなしっかりと甲高の出たバランスの良い体型に育て上げるのも一苦労でしょう。 性格の明るさがウリのビルホシですがこの個体も例に漏れず、 バスキングスポットのついた暖かい所と反対の涼しい所をせわしなく行き来し、 足を踏ん張って腹甲をしっかりと持ち上げながら歩行する姿にはリクガメらしさが十分に伺えます。 また動き回るだけではなく、見た目とは裏腹に大食漢なカメで、 口先に染み付いた野菜の色で分かると思いますがよく食べますので サプリメントなども上手に添加しながら沢山食べさせてあげて下さい。 ちょうどこの時期は湿度が高いので、外飼いにすると甲羅のツヤを保ちながら上手に飼育できると思います。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (♀) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| 体の中に野菜がぎっしり詰まったような拘りの一匹! 文句無しのフォルムを誇る性別確定安心サイズ、 お客様委託のビルマホシガメ・メスが入荷しました。 同じホシガメでもインドとビルマでは大違い、とは昔から呪文のように唱えられているお決まりの文句。 ビルマというのは現ミャンマーの古い呼び名で今の若い世代にはあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、 和名も英名もずばりミャンマーの固有種であることを表しています。 一時、野生個体が長期に渡り確認されず絶滅したと騒がれたというのも有名なエピソードで、 当時日本で刊行された図鑑などにもそのような記述が見られます。 言うまでもなく稀少な種類であり、 つい最近まで先のインドとはすっかりかけ離れた超高額で取引されることも珍しくありませんでしたが、 多くの愛好家がCB化を目指した結果近頃ではベビーを中心に随分と入手しやすくなってきました。 今回やってきたこの個体、まず冒頭にて意味不明な文言を掲げてしまいましたが、 つまりはベビーから実に5年近く葉野菜のみで成長させたということです。 その成果はあえて説明する必要も無さそうですが、 気になる方はこの均等に刻まれた成長線と全体の仕上がりをご覧下さい。 インドに比して快活で陽気な性質が特徴のビルマですがこの個体も例に漏れず、 果たして疲れやしないかと心配になるほど終始動き回っています。 甲羅の柔らかい時期はとうに過ぎていますので、この先も順調に大きくなってくれることでしょう。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (特大即戦力・♀) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
| とてつもなく巨大な素晴らしい個体です、今すぐにでも繁殖に使ってあげて下さい。 お客様委託のビルマホシガメ・メスの入荷です。 その時から既に飼い込み個体として委託主様の下にやって来て早3年半、 毎年5月と11月にきちんとタマゴを産んでくれる優秀なメス親です。今回スペースの関係上泣く泣く手放されたという事でしたが、 花火型の太いラインが目立つ綺麗な個体でしかも即戦力というブリーダーさんにとっては朗報では無いでしょうか。 種親用として飼われていた為に与える餌の栄養にも気を使われており、市販の葉野菜やMazuriリクガメフード、 それに季節の野草を加えたバランスの良い給餌を心がけていたそうです。肝心のタマゴも産みっぱなしでは無く、 十分に深さのある産卵床ではきちんと穴を掘り丁寧に埋め戻す作業まで確認されています。 さすがに飼い込み個体だけあって状態は良好、屋外での撮影だったので大喜びで辺りを歩き回っていました。 委託なので価格はかなりお値打ちに致しました。勿論全国発送も可能です。 エクストラクリーパー最新号でも紹介されていた様に近頃は国内繁殖も盛んに行われておりますので、 この大きなメスを用いて沢山タマゴをとって下さい。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (ジャンボトリオ) Geochelone platynota |





|
|
||||||||
|
委託主様のご意向により価格を下げて再UP! 泣く泣くの放出品! 繁殖を試みて丹念に飼い込まれたジャンボトリオです、 お客様委託のビルマホシガメ・トリオが入荷しました。 今回どれも5年10年単位の長きにわたる育成期間を経てここまで大きくなった、まさに目玉個体ばかり。 待ってましたと言うと申し訳ないのですが、 こういった即ブリードに繋がるサイズのものは新しく輸入される機会が全く無くなってしまいましたので、 実質国内で飼われていたものに頼るしかないのが現実ではないでしょうか。 一番大きなメスはラグビーボールの様な綺麗に育った甲羅が迫力抜群で、 この個体は何回か産卵も経験しベビーの誕生を今か今かと待ちわびている個体。 (参考:タマゴの写真) オスと小さい方のメスはミドルサイズからお客様宅でこの大きさまで成長したもので、 少しボコ付きはありますがそれよりも太いライン取りがとても美しい個体です。 特にメスは未だに成長線が出続けており、まだまだ大きくなろうとしているようです。 飼育環境は専用の小屋内で赤玉土・ヤシガラ・鹿沼土などをミックスした土壌で、 餌は季節の野草や葉野菜、Mazuriリクガメフードなどをバランスよく給餌しよいペースで成長しています。 あとは新しい環境に慣らしながら十分なサイズまで大きくして、豪華なトリオで繁殖を目指すだけです。 一番大きなメスは甲板の寄った部分がありますがフォルムは崩れていません。 暖かくなって来ましたので発送もできるようになりました。気になった方、お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ビルマホシガメ (スーパーアダルト・トリオ) Geochelone platynota |













|
|
||||||||
| お客様が長期に渡り飼い込んで来た委託個体のビルホシがオス2頭・メス1頭で入荷です。毎年、卵(有精卵)を産んでいて、このトリオで ハッチもされた事が有るそうです。メスは 甲長30cmも有り、ラインも太く綺麗なドーム型をしています。委託者様が仰る には『産み場を探しているからもう直ぐ卵を産むだろう』との事でした。オス1は、 若干シャイな所が有りますが、イエローのラインとブラックの背甲の色のバランスが抜群です。甲長21cmでこれからに期待大です。 オス2は、甲長22cmで多少凹つきが有りますが、ビルホシのパワフルさが伝わって来る 非常に良い個体です。全個体とも葉野菜がとても好きですが、Mazuriリクガメフードもバリバリ食べています。愛情を込められた滅多に お目にかかれないこの巨大ビルホシで、仔ガメをハッチしてみませんか? | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (ベビー) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| アンバランスに逞しい前足のパワフルさでそこら中を走り回る恐いもの知らずの元気なベビー! どうせ長い付き合いになるのなら幼い頃からと言う皆さんの願いを叶えてくれる、 ケヅメリクガメが入荷しました。 誰に聞かされる訳でも無くリクガメのことを少しかじった全ての人が知っている、 これぞリクガメと言わんばかりの圧倒的な存在感を誇るキングオブペットトータス。 単純に最大甲長だけを見れば上にはゾウガメが待ち構えていますし、 或いは美貌を追求すればホシガメの右に出るものはおらず、 大きさと美しさのどちらも妥協したくないわがままな方にはヒョウモンガメがお似合いなのかもしれませんが、 そんな強豪がひしめく中で他の追随を許さない抜群の人気を誇るこのケヅメリクガメに、 人々は一体何を求め何に心を満たされると言うのでしょうか。 真っ先にひとつだけ思い浮かぶ最大にして唯一と言っても過言では無い特徴、 それは生まれた瞬間から容赦無く発揮される底抜けの明るさです。 私たちはあらゆる動物を飼育し始める上でどうしても幼体を選んでしまいがちですが、 リクガメのそれは外界の環境に対して殊更神経質になっていることが多く、 期待していた動きをしてくれないことも全く以って珍しくはありません。 しかしながら本種の場合は謎の陽気さとふてぶてしさによりそれが無効化され、 本来であれば捕食者に対する警戒心があって然るべき状況だったとしても、 全てを覆し意気揚々とケージのど真ん中を大手を振って歩き回ります。 これこそがケヅメの支持率を高い水準でキープし続けている何よりの根拠であり、 巨大になるため安易な飼育は避けるべきだといくら口酸っぱく言われ続けようとも、 全てをなぎ倒すように蹴散らしてしまうのです。 今回やって来たのは淡めの焦げ茶に色付いていきそうな、 とにかくもりもり食べ尽くして仕方の無い健康が甲羅を背負って歩いているようなベビーサイズ。 前肢の太さが余計に際立つのもこの時期限定、 幼くとも凛々しい顔立ちは将来安泰と言った雰囲気を醸し、 ケージ内を闊歩する勇姿には不思議と重厚感が漂っています。 綺麗に育てるコツは乾燥系だからと環境設定を履き違えずツヤツヤの甲羅をキープすること、 そして膨大な運動量を陰で支えるしっかりとした大地を再現することです。 いよいよ気候も良くなって来たこの初夏に生涯の友との出会いを。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (ファーミングCBベビー) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 甲羅のギザギザが残った可愛いベビーサイズ! 本場アフリカはガーナよりやってきたファーミングCBです、ケヅメリクガメが入荷しました。 昔からペットとしてポピュラーなリクガメであり最近ではTVやCMの出演も時折見かけるケヅメですが、 繁殖技術が進み毎年ピッカピカの可愛らしいサイズで入手できるようになりました。 しかしそれにしても今回の個体は甲羅も肌もとてもみずみずしく、 乾燥系のリクガメとは思えないほどに全体から潤いを感じます。 色味も明るくスッキリとしていてこれはもしかしたら将来かなりの美人になるかもしれません。 甲ズレはもちろんありませんが各甲板の配列も見事で、 綺麗に育て上げたいという欲を掻き立てます。 ケヅメを何匹も飼える人はそういないでしょうし、 長く付き合っていく1匹を選ぶわけですから渾身のセレクトをして下さい。 現在の丸く整った甲羅がそのまま大きくなれば感動もひとしおと思います。 小さくて可愛いのは当たり前ですが、このサイズから既に迫力の片鱗を感じ取れるリクガメはなかなかいません。 お勧めの個体です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (ベビー) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 全身が柔らかな乳白色に包まれた将来有望美個体! ひょっとすると綺麗なライトブラウンに仕上がるかもしれないただならぬ気配を感じます、 ケヅメリクガメ・ベビーが入荷しました。 現在の日本では様々な種類のリクガメを見かけることができますが、 これ程までに皆に愛され懲りずに飼育され続けているカメもそう滅多にいるものではありません。 アフリカ大陸に広く分布する本種は最大で70cmや80cmにも達するとされ、 一般家庭での飼育は極めて困難だと常日頃から警鐘を鳴らされている訳ですが、 そのようなことを言われ続けてもう何年が経過したのでしょうか。 お陰様で可愛らしい幼体は毎年安定して流通しており、 一体何匹のケヅメが日本に輸入されているのか見当すら付かないほど。 尋常でない食欲と運動量をもって物凄いスピードで大きくなっていきますので、 実際に飼い切れなくなってしまう例も度々聞かれるのですが、 サイズ問わず不思議とそのバトンタッチはすんなりといくことが多いというのも事実です。 このメカニズムには突き詰めてみると興味深い答えが潜んでいそうですが、 平たく言えばベビーから育てたい人とある程度のサイズから飼い始めたい人、 更には十年選手のような巨体のみに絞って探している人まで、 何故だかそこに存在する需要と供給のバランスが奇跡的に釣り合っているのだと考えられます。 しかし次の飼い主が見つかるためには、誰かがその個体を欲しいと思わなければなりません。 最近では飼育技術の向上ならびに情報伝達の進歩により、 決してスーパーマニアでなくとも上手に育て上げる人が増えてきているようで、 数々の放出個体を見てもどうして手放してしまうのか、 こちらが思い悩んでしまうぐらいの質の高さに唸ることもしばしば。 栄養価のバランス、給餌頻度、総運動量、紫外線照射量など様々な問題が取り上げられる中で、 現代のリクガメ飼育においては多くが比較的解決されているようです。 この個体は数あるベビーの中から直感と閃きによりハンドピックされた一匹で、 初生甲板や地肌の薄さが際立ち群れている中でも目立つレベルでした。 成長線の色もいきなり淡めに出始めているので、全体的にすっきりとした明るい色合いが好みな方はお見逃しなく。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (ベビー) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 少し前には映画にも出演し話題になりました。このサイズの可愛らしさは反則です、ケヅメリクガメ・ベビーの入荷です。 言わずと知れた人気種で、初めて見たリクガメがケヅメだった、なんて方も少なくないと思います。 甲羅はこんもりと盛り上がりよく歩き回る、私達がイメージする”リクガメ”像にピッタリで昔から人気のある種類です。 が、ゾウガメの次に大きくなる超巨大種なので飼う人を選ぶカメでもあります。成長はとても早く、 育て方次第ではわずか1年で10cmは楽々超え、5年ほどで40cm位、最大では60cm以上になるとされています。 写真などで見る子供が背中に乗るシーンには憧れてしまいますね。低栄養・高繊維質の餌を大量に確保する事と広大なスペース、 冬季の加温をクリアすれば終生飼育する事も不可能ではありません。現在葉野菜とMazuriリクガメフードをよく食べグングン成長中です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (ベビー) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 生まれたてとも見間違えるベビーから一回り大きくなったグッドサイズです。 国内飼い込みのケヅメリクガメ・ベビーが入荷しました。 ”大きくなるリクガメ”の代名詞的な存在としてゾウガメとも肩を並べるほどの知名度ですが、 このような手の平にちょこんと乗ってしまう可愛らしいサイズではそのことも一瞬忘れさせてくれます。 しかしそこはさすがに大型種、 この大きさでも前肢の鱗を見ても両親譲りの迫力をチラつかせ、 顔付きひとつとってもすっかり大人顔負けな頼りがいのあるたくましい風貌を持っています。 当然まだまだ先は長いですが最初の成長線はいい感じ、 甲羅もこんもりと丸い感じで楽しみが詰まった安心の大きさです。 急成長させなくても勝手に大きくなってしまうこともあってか歪な形になる場合もありますが、 十分な紫外線と毎日の規則正しい食生活、 そして適切な運動量とリクガメの基本的な飼育のポイントを抑えれば臆することではありません。 何よりも日々よく観察して愛情をかけてやることで立派に育ってくれることでしょう。 今ではデータも多く最終的に誰もが飼えるリクガメではないことは容易に分かりますが、 やはり人気種ですのでお探しの方はお早めに。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (S) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 幼体特有の恐さは微塵も無いソフトボールよりも小さめのやたら飼育欲をそそられるベストサイズ! 全体的に赤味の強い焦げ茶の成長線が今後どのような全体像を描き出すのか見物です、 ケヅメリクガメが入荷しました。 リクガメ界のスターと言うものをひとつに決めてしまうのはなかなか難しい作業で、 やはり部門毎に評価が分かれますからヘルマンにしてもホシガメにしても皆に愛されて当然なのですが、 大型種の中でランク付けを行えば文句なしのトップに躍り出るのはこのケヅメを除いて他には考えられません。 まず第一にリクガメとしてのイメージを決定付ける褐色のボディ、 それに加えて全体に程良くこんもりと盛り上がった甲羅のシルエット、 更に大きな体がのしのし歩くというまさしくファン憧れの仕草を見せ付けられれば、 頭に思い描いていた庭に暮らすリクガメ像にぴたりと当てはまるという訳。 加えて頑丈な体質と明るい性格が功を奏し、 ベビーで販売されているにもかかわらず外敵に臆することなくトコトコと動き回りますから、 十分な事前準備と将来への気合いを入れるだけで初めての方でも飼育を始めることが可能なのです。 今回やって来たのは普段見かけるピンポン玉より少し大きなサイズではなく、 かと言って如何にも飼育し切れなくなったような両手で抱きかかえるサイズでもなく、 これを以ってちょうど良いと言わずして何と言うのか妙に物欲が沸いてしまう手の平サイズ。 いくらケヅメと言えども右も左も分からない状態でか弱いベビーに手を出すのは些か抵抗があるでしょうし、 それに成長線の伸びも不十分な時期では成長に従いどのような色合いを呈するのか読むこともできず、 だからと言って初めからボリューミーな個体では育てる楽しみを奪われたような心持ちになりますから、 このサイズはこれらの条件を全て満たす何とも我侭な最高のタイミングと言えるでしょう。 カメのコンディションを見る限りそこには疾しさの欠片も見当たらず、 甲羅の成長線はみずみずしくフォルムも申し分ありませんし、 何よりも歩き回るその姿は文字通り健康体そのものですから喜ばしいことこの上なし。 変な言い方ですが最近ではある程度きちんとした情報が出回ることもあり、 無計画な飼育により手放されるケヅメも減少しているようで、 飼い込み個体の出物があまり見かけられなくなってきたような気がします。 性別は何となくメスっぽいのですが、適当に言っている訳ではありませんので理由は別でお話しします。 美白の顔に全体の地色がなかなか濃いめで成長後の発色も楽しみな一匹、 是非大切に可愛がってあげて下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (S) Geochelone sulcata |




|
|
||||||||
| お客様委託のベビーより少し育ったケヅメリクガメの入荷です。 よく見かけるベビーサイズではケヅメとは言え低温に弱かったりうまく育たなかったりと心配は尽きませんが、 既に成長の流れに乗っているこのサイズでは一切の心配は無用です。将来的には子供なら背中に乗れたり、 広々とした屋外の施設で放牧したり、ペットタートルの域を超えた楽しみ方ができると思います。 餌食いは当然良く葉野菜の硬い部分まで残さず平らげます。十分な紫外線・カルシウム・運動量を確保してあげて下さい。 昔からその活発な性格と勇ましい風貌から非常に人気の高いリクガメですが、 その飼育下ですら最大50cm近くになる巨体の事もお忘れなく。今回委託ですのでお値打ち価格でのご提供です。是非ご検討下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (国内CB・S) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 正真正銘日本生まれの日本育ち、昨年の秋に誕生日を迎えた子どもの拳二つ分サイズ! 愛情たっぷりの放ったらかし飼育がつくり上げたボコ付きの少ないフォルムに感心します、 ケヅメリクガメが入荷しました。 人によって感じ方は様々ですが、 ペットショップが持つ魔力と言うのはあらゆる生き物を飼育する上での動機に繋がるのではないかと思います。 最も分かり易いのは子犬や子猫から発せられるあの胸キュンオーラ、 若干死語のような気がしないでもないのですが、 ちょこなんと座ってこちらを見つめる姿に母性を擽られるとでも言いましょうか、 私がお世話を買って出なければという実に不思議な感情に襲われることでしょう。 もちろん他の動物にも様々なアピールポイントが存在し、 ことリクガメについてはご想像の通り、ケージ内を所狭しと歩き回るあの光景が脳裏に過ります。 擬音語で表すのならばトコトコが適切ではないかと思うのですが、 残念ながら最も可愛らしいベビーサイズのカメは外敵から身を守る術としてなのか、 必要以上の活動を避ける種類も決して珍しくはなく、 せっかくのご対面時に顔を引っ込めてスヤスヤと眠っているケースも少なくありません。 いくら巨大になるからやめておきなさいと言われても本種が支持される理由はここにあり、 リクガメとしての魅力を存分に発揮することをいとも簡単にやってのけてしまうのです。 今回やって来たのは噂に聞いていても実際にお目にかかることは稀な、 アマチュアブリーダーによる渾身の自家繁殖個体。 かれこれ三年以上コンスタントにベビーを採り続け、 昨年父親を手放したため今年の分は生まれなかったそうですが、 この個体は成長記録のために自身で残しておいた2012CBです。 飼い方は至ってアバウト、庭に建てられたカメ小屋なるスペースに十分な暖房を施し、 餌は近所から伐採した有り余るほどの野草が好きなだけぶち込まれるというバイキング方式、 運動量にも栄養価にも困ることのない天国のような空間で健康に育たない訳がありません。 そのお陰でスタートダッシュはほぼ完璧、 ふっくらと盛り上がった甲羅は歪な箇所も無く、 しっかりと太さのある四肢が美しいボディバランスを生み出しています。 あと数年間は水槽での飼育が可能と思われますので、 ステージに合わせた計画は今から早めに練り始める必要があるものの、 初めからゴールを見据えるまでの覚悟はあまりにも酷かと存じますので、 カメの成長に沿って飼い主も同様に成長することができれば良いのではないでしょうか。 今日では専用の器材や実際の飼育例などの情報にも困りませんから、 是非この機会に夢を叶えるきっかけを掴み取って下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 色白美人の安心サイズ! いくら10cmオーバーでもまだまだ幼さしか感じられない所はさすが大型種です、 ケヅメリクガメが入荷しました。 熱帯域を中心として世界中に分布するリクガメの中で、 なんとなく一番リクガメらしいのはどれと尋ねられれば、恐らくは多くの方がケヅメと答えてしまうでしょう。 茶色をベースとした体色にこんもりと盛り上がった甲羅、 そして何よりも四肢を伸ばしお腹を持ち上げて堂々と闊歩する様には、 リクガメ代表種としての迫力を存分に感じることができます。 もはや言わずと知れたことかもしれませんが、 現在国内で一般に飼育できるリクガメの中では最大級の大きさを誇り、 その活力と有り余るパワーも合わさって飼育する喜びは格別です。 故に誰しもが終世飼育できる種ではありませんがそうと知られていながら古今東西多くの人を惹き付ける、 このケヅメには他のリクガメにない並外れた魅力があるのかもしれません。 今回やってきたのは明るい色合いの飼い込み個体で、 ボコつきも程度良く抑えられ順調に大きくなりつつある成長期真っ盛りの1匹。 食に対する関心の高さと食べる量の多さはケヅメらしく、 自分よりも大きい先輩たちを押しのけ一心不乱に餌場へ直行するコンディションの良さも見せてくれます。 もうベビーではないので育てるにあたって特別気をつけることもありませんが、 やはり圧倒的な食欲には素直に従うことと、 一歩でも多く歩かせれるようスペースを確保することが必要です。 葉野菜、Mazuriリクガメフードどちらにも餌付いています、この調子で大きく育てて下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (ブラウン・M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 程度の良いフォルムに育てられたあどけなさのそろそろ抜け始める安心サイズの飼い込み個体! 成長線が一周目からいきなりの焦げ茶というこの濃い目カラーがお好きな方も多いと思います、 ケヅメリクガメが入荷しました。 水陸問わず大きなカメの代名詞とも言えるこのケヅメ、 もちろん上を見ればウミガメやゾウガメなど更なる巨体と出会うことも不可能ではありませんが、 どちらかと言えば水族館や動物園のイメージがあまりにも強く根付いてしまっているため、 ペットとして触れ合うことのできる機会の多い本種の方がより馴染み深いのかもしれません。 初めは手の平にちょこんと乗せられる大きさだったのも、 最終的には女性や子どもでは持ち上げられなくなるほどに成長してしまうのですが、 不思議とそこに恐怖心が抱かれることは殆どなく、 かえって好奇心の方が勝ってしまうケースが多いのは一体何故でしょうか。 日本人にとってトカゲやヘビなどのいわゆる爬虫類が苦手ということはあっても、 カメのことを真正面から嫌う人は滅多にいないと思いますが、 本種の場合は持ち前の明るくて大胆な性格が功を奏し、当人も気が付かない内に周囲の人気を集めてしまいます。 最近ではドラマにコマーシャルと多忙なスケジュールをこなすリクガメ界の大スターは、 今日も日本全国何処かの庭先を自由気ままにで走り回っているのです。 今回やって来たのはちょうど拳二個分ぐらいのヤングサイズで、 一見して甲羅の濃厚なブラウンに目を奪われるなかなかの美麗個体。 オリジナルが茶褐色のためほぼ白に近いアイボリー調の淡いタイプか、 それともこのように全体が引き締まって見えるダークなタイプか、 大抵は両極端なこのどちらかに人気が集中するようです。 ところで明るい色味を持つものはベビーの時点でチェックすれば何となく予想はできても、 この背中を見れば分かるように全体が黒がちになるか否かは育ててみなければ分からないため、 幼体に拘らずお好みのカラータイプで生涯の友をセレクトしてみては如何でしょうか。 ふっくらと丸みを帯びたシルエットが何となくメスっぽい雰囲気を漂わせる、 現時点でとても綺麗に成長中のハイクオリティな一匹です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| この丸さ、初体験! 妙に幅の広い飼い込み個体です、安心サイズのケヅメリクガメが入荷しました。 飼育できるリクガメでは最大級の大きさを誇るペットトータス代表種。 原産はアフリカで過去には様々なサイズの野生個体が輸入されてきましたが、 現在ではそれらの保護が厳しくなり、 代わりにファーミングで繁殖された可愛いベビーを毎年見かけることができます。 今回やってきたのも国内でベビーから飼い込まれた1匹ですが、 その姿を一目見ただけで異変に気が付きました。 この個体、今まで扱ってきたどの個体を思い出しても似たものが見つからない、 甲幅がかなり広がった独自のスタイルを持っています。 何故だろうと即座に甲板の数を確認しましたが正常でした。 かと言って成長異常かと疑う余地は微塵も無く、 成長線の極々均等に刻まれた甲羅はワックスがけを済ましたかのような艶に満ちており、 文句の付け所が一切見つからないまるでお手本のような仕上がり。 手に持てばハンドボール、 歩かせれば蠢くテントウムシのように見えるのも、 このケヅメが持つ全体的なプロポーションの美しさが成せる業でしょう。 突飛な形をしていますがその行動は普通のケヅメと何ら変わりはなくマイナス要素は感じられません。 性別は不明としておりますが、 肛甲板の湾入が狭いことと尻尾がかなり短いことからメスではないかと考えています。 もし本当にメスであればその数はかなり少ないので大変貴重です。 この幅を持ったまま大きくなれば段違いの迫力を持つケヅメに育ち上がることでしょう、 この調子で綺麗に大きく育てて下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| この頃流行りのダークブラウンな甲羅が綺麗に盛り上がった人気の高いハンドボールサイズ! ボコ付きや腰の落ち込みもあまり感じられず全体の丸みが何だかメスっぽい、 ケヅメリクガメが入荷しました。 その愛すべきキャラクターから今も昔もまるで人気の衰えを知らない、 家庭用大型リクガメとしては断トツナンバーワンの支持率を誇る不朽の名種。 動物園、水族館、ペットショップなど生き物を専門に扱う施設のみならず、 例えば病院や介護施設、喫茶店などあらゆるシーンで強大な存在感を発揮し続け、 テレビやコマーシャルなどでも異常なまでの採用率を誇るその活躍ぶりはまさしく業界の顔。 果たしてごくごく一般の家庭にそのボリュームが収まり切るものなのか、 明らかに無理だと分かっていてもええい、 ままよと数々の愛好家を飛び込ませてしまう訴求力の高さには目を見張るものがあり、 いくら駄目だと言われどれだけ肩身が狭くなろうともこの愛され具合は永久に変わらないのでしょう。 色柄に乏しい外観からはお世辞にも綺麗だとか美しいと言った類の魅力は感じられず、 何もそこまで無理をして飼育に挑むことは無いような気もするのですが、 ただただダイナミックにただただ人懐っこいと言うだけの不器用なところが、 人々の心を魅了して止まないと言うのは本当に凄いと思います。 今回やって来たのは成人男性でも片手で持ち上げるのがやっとなほどの、 リクガメとしてはようやく安定期に差し掛かったと言える安心サイズの飼い込み個体。 最近ではそれほどえげつない状態になったケヅメを見なくなったものの、 やはり遠目で見たシルエットは育て主の腕が光る部分でもあるため、 少しでも印象の良い個体にはそれだけ注目が集まります。 長い付き合いになるのだからベビーから育て始めたいと誰しもが考えるところを、 だからこそしっかりと気に入った一匹を見極めたいとの意見もあり、 はたまた幼体では体力が十分についていないため心配だとか、 甲羅を綺麗に育てるのは難しそうなので不安だと言った声も多く、 これぐらいの大きさに到達してしまえば甲羅の基礎はあらかた出来上がっていますし、 また温度管理を大幅に失敗しなければ勝手気ままに暮らしてくれるだけの体力は備わっていますから、 出物としては最も人気があるのにも頷けます。 個人的にはかなりの確率でメスだと考えている、 もし本当にそうなってくれればラッキーなおてんば娘です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| ようやく青年サイズでしょうか、ここからが楽しい盛りです。 ファーミングハッチのベビーからおよそ1年飼い込まれたケヅメリクガメが入荷しました。 アフリカ大陸に棲息する大型のリクガメで、リクガメの仲間で比べてもトップクラスのサイズであり、 また我々が飼育することのできるリクガメの中でも最大級の大きさを誇っています。 そのため動物番組やテレビコマーシャルに出演したり、 動物園や爬虫類イベントで見かけたりと目にする機会も多く、 ベビーサイズで手頃な価格帯の個体が多く流通することもあり人気の高まりはとどまる所を知りません。 大人と呼べるぐらいに育った個体には人の子供が上に乗っても大丈夫、というエピソードも有名。 赤ちゃんの頃は当然可愛いわけですがどこか危なっかしい感じもして、 庭に放して飼うにも見失ってしまったり外敵に襲われやすいというリスクもあります。 しかしこれ位に育った個体であれば甲羅もしっかり硬くなり、 それでいてまだまだ成長期の真っ最中ですから日ごとにグングン大きくなる姿には常々驚かされることでしょう。 なんとなく頭の大きめなこの個体、 全体のプロポーションがよく将来が楽しみ。 ケヅメらしく餌食い、動きともに非常に活発です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 甲羅の表面にしっかりと焼き目が付けられた濃厚な焦げ茶色が美しいラグビーボールサイズ! いつも見慣れた姿に比べて随分と存在感の際立った珍しいカラーリングです、 ケヅメリクガメが入荷しました。 リクガメの人気種と一口に言ってもそこには色々な形があろうことと思いますが、 現実的に飼い切れるか否かは別として、誰しもが一度は夢に思い描く大型種への憧れを叶えてくれる、 そんな身近な存在として長く愛されて続けているのがこのケヅメです。 良くも悪くも最終的に大きくなり過ぎることが日々論じられている中、 確かに皆が皆満足のいく飼育を実現することはできないのかもしれませんが、 その一方で技術の発達や豊富に出回る情報を武器に、 以前に比べてかなり多くの人が健康な個体を育てられるようになってきたのも事実ではないでしょうか。 ただ単に大きいと言うだけなら他に選択肢もあったでしょう、 しかしケヅメには活発に動き回る野生的な躍動感を始め、 人間に対して親しみを持っているかのような愛嬌ある仕草が我々の心を魅了して止まない、 他の種類では替えのきかない銘種なのです。 今回やって来たのは一般に知られる標準的なタイプとは一線を画す、 かなりの色黒であることが一目見て分かる安心サイズの飼い込み個体。 ベビーの時期には色白の方が集団の中でもかなり目立ち易いのですが、 ある程度成長した段階では一見してダークな色彩が全体像に重厚感を与え、 実寸の甲長以上にいくらか大きく見えると思います。 実際にはまだ何とか片手でも持ち上げられるほどのボリュームしかありませんが、 一歩前に進む度にズシンと足音の聞こえてきそうな迫力は、 まだまだ伸び盛りの若年期では本来味わうことのできない特典です。 顔立ちはまだ幼く表情も何処か惚けたような様子ですが、 前肢の鱗は大人顔負けと言った具合にびっしりと生え揃い、 写真に大きさの比較対象が無ければ実物を見るまで錯覚を起こしてしまうかもしれません。 甲羅の成長具合も申し分無く、 少しぽこぽことしてはいますが全体のシルエットを乱すほどではないため許容範囲でしょう。 縁甲板が一枚少ないのですが見た目に殆ど気付かない程度です。 過去に取り扱った中でも稀に見るクオリティのカラーリング、色目に拘りのある方はこの機会に。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (M) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 体重は4.8kg! 赤ちゃんを抱くよりも重たい飼い込み亜生体サイズです、お馴染みの人気種ケヅメリクガメの入荷です。 リクガメの仲間の中でも特に人気の高い本種のベビー、 そんな小さなサイズからここまで見事に成長しています。 食欲旺盛で成長スピードがケタ違いに早いケヅメは、 それ故か紫外線の供給やエサの栄養価などの要因により育ち方に違いが出てしまい、 きちんとした環境でそれらのバランスを崩さずに綺麗に育て上げるのはなかなか至難の業。 この個体は甲羅の前も後ろも均一にこんもりと盛り上がり、 大切に飼育されてきた事がひしひしと伝わってきます。 ゴツゴツとした格好良いフォルムとCB特有の黄色味の強いピカピカの甲羅が素晴らしいです。 またこのサイズになってくるとさすがに四肢は立派になり、 手で触ると少し痛いぐらい。大きさだけでなく重さもずっしりとしているのもポイントで、 時々店内に放してやると嬉しそうにあたりを見まわしながら重い体をしっかりと持ち上げて行進しています。 葉野菜や人工飼料などにカルシウムを振りかけて色々なものを与えて育てて下さい。 性別はメスでしょうか、ご参考下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (L) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| どこを見ても綺麗に成長している教科書通りの美個体! 国内長期飼い込みのケヅメリクガメが入荷しました。 甲羅はしっかりとした厚みに非常に完成度の高い理想的な形状、 爪はどの足を見ても丁度良い長さで生え揃っていて、どこにも文句のつけようがありません。 今回お客様からの放出品ですが最後まで愛情を注がれていたのが丸わかりで、 ワイルドの大型個体が輸入されてこない今こうした野性味を存分に感じさせる個体は大変貴重です。 写真だけでも伝わってくると思いますがこんなにプロポーションが素晴らしい個体の状態が良くない訳がなく、 ふやかそうと思って出したMazuriリクガメフードを スナック菓子よろしくボリボリ食べ始めたのにはちょっとびっくりしてしまいました。 歩行能力もケヅメらしさ全開で、 お腹をすくっと持ち上げ重さも結構あろうかというその巨体で実にスムーズに動き回ります。 昔から輸入されているお馴染みのリクガメで今でもその人気は衰えることはありません。 非常に大型になることから何頭も飼える種類ではありませんので、 渾身のセレクトで選んだ一匹を大切に育てあげて下さい。 参考までに尾のアップ写真はこちら。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (L) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 全体的なフォルムの美しさや内面の明るさに育ちの良さが窺える人気のバトンタッチサイズ! 本来備わる雄大な魅力がようやく滲み出て来たまだまだひょいと持ち上げられる折り返し地点、 ケヅメリクガメが入荷しました。 各々の趣味嗜好によってそのランキングには多少の変動があるものの、 みんなが好きなリクガメなどと題してアンケートを取ればよほど上位に食い込んで来るのであろう、 誰に教わったのか分かりませんが不思議と大衆からの支持率を集めがちなこのケヅメは、 やはり実際にペットとして飼育することを想定した場合にも何十年と前から高い需要を誇っています。 別段華やかな色柄に彩られている訳ではありませんし、 どちらかと言えばノーマルでベーシックな外観に強い物珍しさは感じられないはずなのですが、 ひとまずただただデカいと言う絶対的な特徴を武器に今日までトップグループをひた走って来た感があります。 そこへ何か付け加えるとすれば性格の明るさが挙げられるでしょうか、 とにかく人懐っこくそして物怖じしない底抜けの明るさの持ち主で、 その堂々とした佇まいには自然環境の厳しいアフリカの大地で鍛え上げられた強さそのものが描き出されており、 見ているこちらを決して不安にさせることの無い包容力のようなものがひしひしと伝わって来ます。 しばしば移動動物園などで子どもたちの人気者となっているのも象徴的なエピソードで、 今後も変わらず私たちにとって必要なキャラクターとして未来に語り継がれることでしょう。 今回やって来たのはかなりしっかりとそして丁寧に育てられた印象のラージサイズで、 甲羅全体がおおむね綺麗に仕上がっていると判断できる良質な掘り出し物。 一番分かり易いのは四肢の筋肉の発達具合および爪の揃った様子で、 しっかりと歩いていればよく食べ、 またしっかりと食べていればよく歩くと言う相互作用を感じ取ることができ、 心身共に健康な様子を体全体で見事に表現していると思います。 輸送時に甲羅の縁との干渉で肌に少し赤味を帯びた箇所がありますが、 痛々しい傷にはなっておらず何よりもコンディションがすこぶる好調なため、 あえて完治を待たずして掲載することにしました。 幼体から飼い始めた人がまず初めに憧れ、 どうせ飼うのならある程度育ったものをと考える人が一番欲しくなるベストなお年頃です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 成長期真っ盛りの安心30cmクラス! 大人の階段を昇り始めたヤングサイズです、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 アフリカの大地を闊歩する大型リクガメのひとつがこのケヅメ。 同じくアフリカ産で巨大になるものとしてはヒョウモンリクガメなども知られていますが、 何より本種はそのアグレッシブでエネルギッシュな性格と、 それに見劣りしない勇ましい姿が高い人気を誇る理由でしょう。 生まれたばかりの小さなベビーでさえ餌を食べる時などはその片鱗をうかがうことができ、 最大サイズでは負けてしまうゾウガメにもパワフルさでは引けを取らず、 動物園などではメータークラスのゾウガメ達に交じって一緒に暮らしているシーンを見かけます。 昔は高価な種であったようですが、 今では現地ファーミングやアメリカからの繁殖個体が輸入されメジャーなリクガメのひとつになりつつあるでしょう。 今回やってきたのもベビーサイズから飼い込まれ育った個体で、 マットな質感ながらも丹念に磨かれたようなピカピカの甲羅や、 触ると怪我をしそうな前肢の鎧は流石CB。 それでいて爪や足裏、嘴などの使い込まれた感じはこの個体の健康状態を物語っています。 またこの手の成長が早いリクガメでしばしば見かける腰の落ち込みなども現時点でほぼ確認できず、 甲羅の硬くなったこのサイズまで順調であれば今後も安心でしょう。 尻尾はまだそれほど大きくありませんが生殖器を露出したのでオス確定です。 甲羅全体に若干のボコつきがあることと、 甲ズレはありませんが右第3、4肋甲板の間に癒着があるため、 このサイズにしてはお値打ち特価! | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| ぷっくり持ち上がった鼻先と張りのある後頭部が実に漢らしい程良いボリュームの中堅サイズ! 小さな戦車のように武骨な体躯は早くもこの大きさから表れ始めているようです、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 特別な事情が無い限り初級者はできるだけ避けた方が良い、 そんなマイナスの状況からスタートするリクガメの代表格がこのケヅメです。 その理由は至って単純明快、ただひたすらに途方もなく大きく育ち、 辺り一面の草という草を食べ尽くしたかと思えば膨大な量の排泄物をひり出した挙句、 いずれは自らの家屋までをも滅茶苦茶にしてしまう破壊行動に出るという、 誰もが認める立派なモンスターになる可能性を存分に秘めているからです。 それでは人々は何故このカメをそこまでの苦労を承知の上で選ぼうとするのか、 飼ってはいけないと言われると飼いたくなってしまう、まさかそんな面白い答えではないと思いますが、 私なりに色々と考えてみた結果それは意外と簡単なものでした。 結論から申し上げると恐らくは格好良いという一言に尽きるのでしょう、 仮にそう言い切られてしまえばこちらとしては反論する術もなく、 むしろそれでは頑張って下さいと背中を押したくなるぐらいに気持ちの良い回答だと思います。 茶褐色というリクガメとしては平均的かつシンプルな色合いに、 ゴツゴツとしたまるで鎧のように頑丈そうな甲羅、 前肢の鱗は一粒一粒が異様に大きく何処か攻撃的で顔立ちも勇ましい、 確かに誰が見ても思わず声を上げてしまうほどの迫力が至る所に備わっています。 特にオスの場合は出で立ちにサイズ以上の威圧感がありその分見栄えも良好ですから、 巨大種の中では突出して人気が出るのも無理はないのです。 今回やって来たのはどちらかと言えばゆっくりじっくりと育成中の、 ようやく両手で抱えるぐらいに育ってきた飼い込み個体。 食事量と運動量の条件がマッチすれば恐るべきスピードで成長するケヅメですが、 あえて栄養価を制限することで飼育されたためか全体のバランスとしてやや頭が大きめに感じられ、 これは急成長を避け中身をぎっしりと詰め込んできたことの証なのでしょうか。 甲羅全体の色味もやや暗めで重みが感じられる好印象の外観で、 きっちりとサイズアップしていけばなかなかの二枚目に仕上がってくれるのではないかと期待しています。 あえて記す必要もないかもしれませんが餌に対する執着心は並大抵のものではなく、 人が見ていてもお構いなしによく歩き回る大変明るい性格の持ち主です。 この手の放出個体はタイミングが合わなければいくら探しても巡り会うことすら叶いません、 スタートが手の平ベビーからではとても満足できない方は是非。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 甲羅全体の形に表れた安定の成長具合ともりもり歩く底無しの躍動感に大満足のわがままサイズ! いきなり庭先で遊ばせることができこの先もまだまだ育てられる良いところ取りの飼い込み個体、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 誰が何と言おうと、 先人がどれほど反省の弁を述べようと永遠にこのカメの人気が衰えることは無いのでしょう。 よく考えてみればこれまでの過去を振り返ってもそうだったのだと思います、 書籍や雑誌、インターネットなどあらゆる媒体において初心者は絶対に手を出してはいけない、 巨大になるのだから無責任な飼育は慎むべきだと散々釘を刺されていたにもかかわらず、 そんな注意喚起が一体どれだけ役に立ったと言うのでしょうか。 しかしながらここでは飼育することの是非を問いたい訳では無く、 猛烈な逆境を常に跳ね除けて来たこのカメに備わる強大な魅力について、 暫し考える時間を設けてみたいと思う次第なのです。 昔から常々感じているのはとにかく行動力に溢れた種類なのだと言うこと、 それが仮にか弱き幼体だったとしてもケージ内では所狭しと走り回り、 如何にもリクガメらしい光景を見事に描き出してくれるのですから、 ある意味全てのカメから全幅の信頼を寄せられるだけの、 リスペクトされるだけの存在感が備わっていて然るべきなのだと思います。 また最大のネックとなっているその大きさについても、 明らかに矛盾しているのですが大きいことは良いことだと高評価を得てしまうがために、 他種ではなかなか代わりが利かないこともあってこのケヅメに指名が集中しているようです。 今回やって来たのは多少のボコ付きなど許容範囲内、 腰の辺りが落ち込むこと無く全体にふっくらと盛り上がったシルエットが美しい、 切り揃えたような四肢の爪が示す通りの歩きたがりなミドルサイズのオス。 身の詰まった感じは何も気のせいでは無く、 どうやら冬季にはソフトなクーリング期間を欠かさず設けじっくりと育てられていたようで、 積もり積もった成長の証が均一な成長線として見事に形作られています。 顔立ちも何処か凛々しく過去に取り扱った中でも美男子な方で、 こればかりは天からの授かりものとして神に感謝するしかありません。 日の射した暖かい時間帯を狙って野外にて撮影してみました、 ご覧の通り元気いっぱいの育ち盛りです。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| オスにしては珍しく黒々としたつぶらな瞳が可愛らしい折り返し地点を過ぎた頃合いのヤングマン! 春の訪れが感じられる今日この頃にベストマッチな野外を中心にいきなり楽しみたいミドルサイズの掘り出し物、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 カメが嫌いな日本人などいないという評判を全国のあちらこちらでしばしば耳にするぐらいに、 やはり私たちは爬虫類に括られるはずの彼らのことを何処かで特別視しているようで、 カメはカメという生き物であるだなんて目茶苦茶な理論に何故か納得できてしまうのが、 カメが生来持ち合わせている謎のパワーがまさしくそうさせているのだと思います。 中でもリクガメにはウミガメと並びそこはかとなく平和なムードがあり、 大海原を舞台とする後者を個人のペットとするのには流石に無理があるものの、 前者については我々ヒトと同じ陸上を主たる生活圏としている点にも親近感が味わえるのか、 ひとたび憧れの共同生活を想像するだけで胸が躍るのも本能に訴える何かがあるのでしょうか。 そもそもが自国に棲息していないエキゾチシズムを極めたようなリクガメなる生物を、 イヌやネコと同じような並びで迎え入れようという発想が実に愉快な訳で、 現実の二文字と一旦距離を置き、大きな夢をできる限り膨らませようと考えた結果、 カメ自体をより大きくしてしまおうと思い至るのは自然な流れなのかもしれません。 そんな前置きについて真偽のほどはともかく、今も昔も無敵の人気を誇るこのケヅメというヤツは、 野性味が描き出すダイナミズムに甲羅を着せたような非常に分かり易いデザインで、 特別な飾り付けを用いずとも迫力や愛嬌といった内から滲み出るものを剥き出しにしたような、 小細工の類に一切頼らないストレートな気持ち良さが人々の心を掴んで放しません。 何が魅力的なのかとこちらに考えさせる猶予を与えず、 全身を使って力いっぱい体当たりしてくるような裏表のない姿勢に世界中の人々が惚れ抜き、 巨大になるとは分かっていても数十年に渡り多くのファンを生み出し続けているのです。 今回やって来たのは体を持ち上げるのにそろそろ両手が必要な三十センチクラスの飼い込み個体で、 前飼育者の元を離れると途端に塞ぎ込んでしまう性格のものも少なくない中、 このオスは新生活に秒で慣れたのかあっという間に店先を走り回り、 環境が変わったはずの入荷直後から本性を露わにしてくれました。 早くもMazuriリクガメフードへ移行済みで何から何まで手の掛からない優等生は、 ここから夏に向けて更に一皮剥けてくれることでしょう。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 不思議な色抜けを起こしています! 縁甲板の前部も反り返り始めたどっしりサイズ、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 とても大食漢で巨大になることは今や周知の事実ですがそんな前置きがあっても関係なし、 現在でも衰えることを知らないNo.1クラスの人気を誇るリクガメがこのケヅメです。 単純に大きさだけで比べるとあのゾウガメにはさすがに負けてしまいますが、 ハッスルの塊とも言えるほど異常なまでのアクティブな精神とそれに伴う馬鹿力を合算すれば、 より大型のゾウガメと並べても何も遜色はないでしょう。 飼育下でも僅か幼い頃から自分より大きなものを押しのけて餌を食べに行こうとする程、 その生命力にはしばしば感動させられます。 今回やって来たのはすっかり大きくなった30cmオーバーのオスで、 腹甲中央部の凹みはまだ見られませんが尻尾はとても長くすぐにそれと分かりました。 単純に大きなサイズというだけでも貴重ですが、 この個体は鼻先が赤く見えるほど体だけが妙に白っぽく そのお陰か顔付きも気持ちやさしめ。 前肢はツートンカラーにも見え装甲のように発達した蹴爪がより際立っています。 甲羅の形状こそ100%ではありませんが爪も同じ長さで生え揃っていて動き、 餌食い、そしてカラーリングと非常に魅力的な1匹。末永く大切にして下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 一見乾燥地帯のリクガメとは思えぬほど艶やかな飴色の甲羅が美しい飼い込みラージサイズ! 環境の変化に伴う神経質な一面もそれほど感じられない肝の据わった堂々たる性格の持ち主、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 皆さんが選ぶ最強のリクガメとは一体何でしょうか、 もちろん各部門に様々な種類がノミネートすることでしょうから、 たったひとつに絞り込むことは決して容易ではありませんが、 仮にリクガメらしさと言うような概念があるとすれば、 それに見合った特徴を有するものは数えるほどしかいないのかもしれません。 そのひとつとして適役と思われるのがこのケヅメ、 無差別級の恵まれた体躯を武器に尊大な雰囲気を纏いながら辺りを闊歩し、 山のように盛り上がったシルエットと極めてオープンな性質がボリューム感を倍増しにする、 デザイン自体は非常にシンプルで何ら飾り付けられた様子はありませんが、 華やかさとは色合いや模様に寄るものだけでは無いことをまざまざと見せ付けるような、 これぞ唯一無二の存在感を振り回し生き残って来た生命力の塊のようなリクガメです。 かのゾウガメに次ぐあまりにも大きな体は万人が扱えるものでは無く、 内包された規格外のパワーもまた時に我々の想像を超えた衝撃を齎すほどで、 よく言われるように平常考え得るペットとしては全く以って勧められるべきではありませんが、 そこには本種を飼育した者だけが味わえる無上の喜びがあると言われ、 あくまでも趣味として、遊びとして楽しむのであればこれ以上の適役は見当たらないと思います。 少なくともここ日本では現実的に飼育動物としての歴史も長く、 カメと人とが幸せに暮らすための作法が色々と生み出されて来ましたから、 あとは飼い主自身の愛と勇気で何とか形にして頂ければ幸いです。 今回やって来たのは幼体より四年ほどかけて育てられた性別確定サイズの出物で、 中盤以降は極めて順調な成長過程を遂げている立派なオス。 一部腰辺りの落ち込みに出だしの苦労を感じさせますが、 滑らかな成長線や整った爪、 そして何よりも彼の朗らかな表情には幸せな時間を過ごしていた様子が滲み出ています。 環境不十分のためあえなく手放されることとなってしまいましたが、 この続きは是非とも貴方のお手元でお楽しみ下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| つぶらな瞳の優しい顔立ちが印象的な両脇で抱えるのもそろそろ辛くなってきた飼い込み大型個体! 少し腰の辺りが収縮していますが気にならない方にとってはお買い得プライス、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 一般家庭で飼い易いとか初心者向けであるとかそんな理屈を全部取っ払ってしまえば、 リクガメの顔として最も相応しいのはやはりこのケヅメが第一に選ばれるのかもしれません。 大きくなり過ぎるのだからできることなら飼わない方が良い、日本中の誰もが口を揃えてそう言い続ける中、 未だなお根強い人気を誇るにはきっと何か重大な理由があるはずですし、 それがはっきりと言葉にして言い表すことができないものだとしても、 人間の五感に直接訴えかけ無意識の内に感情を呼び覚ます効果があるのでしょう。 また面白いことに本種の幼体を見て思わず育てたくなってしまうタイプの人がいれば、 はたまた最初から大きめの個体を見つけてドカンと始めてみたいという人まで、 様々な考えの人種がいるからこそこういった既にしっかりと育っている放出個体の行き先も見つかるのだと思います。 今回やって来たのはいよいよ40センチ台の扉を開けた立派なオスで、 前の飼い主さんが性別がどちらであるかはっきりと分からなかったと仰っていたほど、 大変に温和な性格の持ち主。 一ヶ所に向かって執拗に突進を続ける破壊行動を取るようなことも無ければ、 黒目の大きな何処となく柔和な表情もその性質をよく表していると言え、 俗に言われるオスケヅメのどうしようもない男臭さはあまり感じられません。 これまで育ってきた環境があまりにも恵まれていたのか、 入店当初は幾分緊張気味でおっかなびっくりなご様子でしたが、 この頃はケージ内をルームランナーのようにひたすら駆け回り、 撮影時にこそ屋外の空気に触れて再び引っ込み思案になっていたものの、 気の優しい一面がよく表れた出来事だったのではないかと感じています。 残念ながら第四肋甲板の辺りにへこみが生じやや体が丸っこく短めにも見えますが、 走るスピードなどを見る限り至って健康そのものですし、 何しろ庭先の小屋で冬越しをしていたほどですから風邪を引きやすいなどのマイナートラブルも無さそうです。 当店では早くも爆食態勢に入り一安心ですが甲羅の件もありますのでお値打ち価格に設定してみました、 今の季節なら巨大なリクガメをお迎えするのにも都合が良いと思いますのでこの機会に是非ご検討下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| デカさ爆発! 40cmオーバーのダイナミックな大型個体、 国内長期飼い込みのケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 毎年目の真ん丸な可愛らしいベビーが多く流通していますが、 決まって言われるのが”大きくなるから初心者は注意”の一言。 しかしながら20~30cmクラスの個体はしばしば見かけるものの、 40cmを超えてくる個体というのは実際に出回ることがあまりありません。 さらに性別が確定するのがこれ位でないと厳しいというのもあり、片方を飼っていてもう一匹という場合にも良いかと思います。 今回やってきたのは四肢の太さ際立つとてもヘルシーな個体で、 特徴的な首元の甲羅の反り返りもワイルドの大型個体を思わせる迫力ぶり。 蹴爪という名前の意味もこのサイズでようやくお分かり頂けます。 爪も伸び過ぎることなく綺麗に生え揃っている所を見るとよく歩き回っていた証拠でしょう。 大きいのはなりだけではなく、 ひとたび噴気音を立てればモビルアーマーを彷彿とさせる迫力のサウンドが楽しめます。 難点を挙げるとすれば腰の辺りに少し落ち込みが見られるのと、 腹甲に甲ズレのような歪みがあります。 貴重な性別確定のビッグサイズ、発送もできますのでご興味のある方はお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 表情から幼さが一切消え、 ツンと上がった鼻先と筋肉質な前肢が漢らしい青年サイズ! 相方のヒョウモンとは反対にここのところ要望の増えているこげ茶タイプ、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 一般家庭で飼育できるか否かはひとまず置いておくとして、大きな動物と小さな動物、 必ずしもどちらが良いと決め付けることはできず種類によってそれぞれ利点は異なっています。 例えば動物園の定番にしてヒーローであるゾウやキリンなどはその大きさに対して好意を寄せられることが多く、 はたまたリスやハムスターはその小ささに心惹かれる場合が圧倒的に多いでしょう。 サルの仲間でもゴリラやテナガザルには身の危険を感じるため近寄ることすら考えませんが、 マーモセットやロリスにはついつい手を差し伸べたくなる可愛らしさがあります。 こと爬虫類については、例えばニシキヘビなどのいわゆる大蛇、 そしてイグアナやオオトカゲなどトカゲの仲間から果てはワニに至るまで、 体の大きさに比例して人間に対して余計な恐怖心を抱かせてしまうため、 常識的な感覚からすると忌み嫌われるのが当然のように思われていますが、 何故かカメだけはその法則が当てはまらない不思議な存在と言えます。 もちろんワニガメなど一部危険なものはいてもそれはあくまで例外中の例外、 基本的には手の平サイズよりも人が乗れるぐらいのサイズがあった方が注目されますし、 赤ちゃんや小さな子どもが触れ合っても急に泣き出してしまうことはなく、 むしろ大きなことが安心に繋がるのか無意識の内に頭や甲羅を撫でてしまうのです。 カメが大きいからと言って嫌な心持ちがする人は滅多にいないでしょうし、 日本人にとっては何となく有難味のある縁起の良い事物として捉えられていますから、 長寿のご利益にあやかろうと触ったり声を掛けたり、 時にはお辞儀を済ませてからご丁寧に拝み始める方もいるほど。 まさかこんなものを自分の家で飼える訳がないとその場限りでお別れするのが正常なのでしょうが、 夢見がちで諦めの悪い人は何とかして飼えないものかと必死に知恵を絞り、 明らかに非現実的と思われたことを根気強くやってのけてしまうのです。 今回やって来たのはようやくひとりで庭を歩かせても手放しで任せられるようになった、 40センチオーバーの中堅個体。当然これぐらいで音を上げている場合ではありませんが、 それにしてもやはり間近で見るとケヅメを選んで良かったと思える迫力を実感することができます。 カメラを向けられようがお構いなしにアスファルトの上を走り回り、 当たり前のように近所の方々の視線を独り占めにしてしまう、 老若男女に愛される兎にも角にも元気一本の健康体です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 綺麗なこげ茶色が印象深いボコ付きもなく上手に育てられたどっしりサイズ! 明朗快活な性格で外に出した途端お日様の下を元気いっぱいに走り回ります、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 飼ってはいけないと言われると余計に飼いたくなってしまう、 もちろんそれは別段やましい意味などではなく、 この場合は一般家庭において扱い切るのが困難なほど大きく成長することを指しており、 世間ではビギナーが特に注意すべき類のペットとして警鐘を鳴らされています。 最近では法律が強化され販売時に適切な説明を受けることが必要不可欠ですから、 購入者にとってもその辺りの話は事前に耳が痛くなるほど聞かされている訳ですが、 それを踏まえた上でどうしても欲しい、 頑張って飼育していこうと決心させてしまうこのカメのポテンシャルには恐ろしささえ覚えます。 初めから巨大なリクガメが飼いたいという、 単純に大きくなることがデメリットにならないケースは除くとしても、 他のどんな種類よりもエネルギッシュに躍動する様にはリクガメに求められる最も大切な歩くという要素がふんだんに詰まっていますし、 野生的な表情が見せる逞しさと漢らしさ、 重量感のある甲羅の質感や前肢を覆う大型の鱗は鎧のようで、 長年人気種であり続けることには容易に納得できると思います。 誰でも気軽に飼うことができないのは承知の上、 綿密な計画を立ててから臨む方もいればいざ迎え入れてから気合いを入れる方もいるでしょう。 初めから全てを見通すことは不可能ですし付き合って初めて分かることもありますから、 大切なのは自分の愛したケヅメに対してどれほどその思いを表現できるか、 その結果遠い日本に連れて来られてもなお生き生きと暮らしてくれれば、 我々の役目は果たされたと言えるのかもしれません。 今回やって来たのはおよそ七年間に渡り育て上げられた、 40センチオーバーの迫力あるボリュームを誇るオス。 年数から換算すると決して早くはないものの問題のないペースで成長しており、 甲羅の形状や表面の艶を見ても大切にそして適切な飼育法が続けられていたことがよく分かります。 この大きさになると全体が真っ白になっていることも少なくありませんが、 この個体は成長線の濃厚な茶色が現時点でも明瞭に残っており、 全身の色合いが持つ雰囲気も相まって実寸値以上の貫禄が感じられます。 四肢を伸ばし首を持ち上げて歩行するシーンを目の当たりにすれば全てが報われるでしょう、 新しい環境でも人に脅えることのないよく慣れた健康児です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 乾燥系のリクガメにあるまじき潤いたっぷりの甲羅が描き出したあまりにも美し過ぎるそのシルエット! カメラを向けると何故かこちらを見つめてくる明るい性格も実に好印象です、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 誰に何と言われようともリクガメ好きの皆さん永遠の憧れ、それが大型種。 同じ括りでも大まかにケヅメ派とゾウガメ派に分かれるであろうかと存じますが、 さすがに後者は最大甲長メートル級と将来的に桁外れの巨体に仕上がることや、 近年ではいくら流通量が増えたからと言ってもまだまだ稀少種の域を出ませんから、 より一般的で身近に感じられるのはこちらケヅメで間違いないでしょう。 世界各国のトータスフリークに愛されるキャラクターは一体何処から来ているのか、 考えれば考えるほど本種の様々な魅力と特徴が思い浮かびますが、 一番は何と言っても好奇心旺盛でよく歩き回る性質に尽きると思います。 リクガメとは歩いてなんぼの生き物ですから、 そういったテーマに沿ったこのカメは自ずと周囲から暖かい眼差しを送られると言う訳です。 今回やって来たのは実に八年間に渡って飼い込まれた大変綺麗なビッグサイズのオス。 一目見た瞬間にこの個体が如何に健康であるかと言うのがよく分かりました。 甲羅のフォルムがばっちり仕上がっていることは言うまでもありませんが、 切り揃えたように整った四肢の爪や、 歩き過ぎて象の足になった後肢の足裏など、 適切な環境で恵まれた暮らしを送っていたことが随所より一目瞭然です。 リクガメの特に大型になるものには体の各部位にチェックポイントがあり、 それらを統合して観察することは生育環境や内面のコンディションを窺い知る術となるのですが、 そんな細かい理屈を抜きにしても全体像を目の当たりにしただけで全てが伝わってくるような気がします。 とにかく歩きたがりなので毎日決められた時間内のお散歩では満足できないのか、 それ以外の時にはタブの中で常にウォーキングを繰り返している状況で、 代謝が良過ぎるため店頭に到着して三日間出し続けた糞の中には大量の桑の葉らしき繊維質が。 容器の中で尿酸と混じり合い大変なことになっていたので水洗いをするのですが、 とにかく水道に詰まって仕方がないため掃除するのが大変でした。 更なる巨体をお探しとあれば50センチオーバーも見つからないことはありませんが、 現状のサイズと言うのはある意味時間が解決してくれることですし、 何よりも出来栄えを重視するのであれば絶対に見逃せない逸品です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 濃厚な黄土色が太陽光に眩く映える短い爪と俵型のフォルムに育ちの良さが表れた極上個体! 野草畑を一瞬にして吹き飛ばさんばかりの勢いで草刈り機の如く強引に食べ散らかす超健康体、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 元気、活力、躍動感、 見ているこちらが思わず力んでしまいそうなほどのキーワードがお似合いの、 強大なエネルギーの塊のようなとんでもないリクガメとして古くから飼育されている、 ペットとしての歴史も長い業界屈指の有名人。 もちろんそれを長きに渡り扱い切れるかと言うところはいくら議論しても収拾がつかず、 明らかに飼い主を選ぶ種類であることには違いないありませんが、 それでも今日まで多くの愛好家たちがその底無しの魅力に酔い痴れ、 再三に渡り忠告を続けられているにもかかわらず何とかしてそのハードルを越えようと日々奮闘する、 色々な意味で大変に夢のあるペットトータスだと思います。 それではこのカメの何がそれほど人々の心を惹き付けて止まないのか、 深く考えたところで事態は収まらないような気もしますが、 恐らくそれはきっとやんちゃ坊主と言うキャッチフレーズがぴたりと当てはまるような、 自分の欲望に素直で何処か憎めない彼らの無邪気な気質そのものでは無いでしょうか。 決して飼い易いなどと申し上げるつもりはありませんが、 何となく動物的で時にこちらの心情を汲み取ってくれるような、 本能と本能で通じ合うような関係を築き上げられるところが、 リクガメの存在意義を超越した新たな生物としての生き様を感じさせてくれるのです。 今回やって来たのは実に五年以上の歳月をかけて満足に育てられた、 いよいよ大台の五十センチクラスの座も目前に迫る大変立派なサブアダルトのオス。 一般的には長く付き合えば付き合うほど更なる巨大化が見込まれ、 経験上この世に生を受けてから十年ぐらいはコツコツと成長を続けてくれますので、 現時点でもある意味通過点と考えて差し支えないと思います。 とにかく性格の良さが前面に押し出されており、 時に環境が変わると途端にシャイな性格になってしまう個体も少なくない中、 当店に到着してものの数分で店内の様子を興味深げに探索し、 翌日からはまるで住み慣れた我が家のように意気揚々とお散歩していたのには流石に驚きました。 サイドから見たシルエットも腰元の落ち込みが全く感じられない素晴らしい仕上がりで、 サイズのみならずなかなか巡り合えない優れたクオリティの持ち主です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大サイズ・♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 大きな地鳴りを轟かせ堂々たる登場を見せたのは久方振りとなる十年クラスのビッグケヅメ! 相変わらずの需要量は変わらずも数年前より明らかに出物が減少している貴重な大型個体、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 一昔前の状況とは打って変わって、 今時店先に並べられているカメがどれぐらいのサイズにまで到達するのか、 全くの予備知識無しで導入を検討される方は殆どいなくなったのではないでしょうか。 かつては無責任な販売と飼育との言葉にて表現される通り、 幼体時の雰囲気だけで飼育対象種が選ばれてしまいがちで、 それは例えば金魚すくいの魚がどのように成長するのかを想像しないのと同じように、 その場限りの印象が判断材料の大きな割合を占めていたのだと思います。 同様の事例は何もカメだけに留まらずあらゆるジャンルの生き物に対して当てはまり、 問題視され始めて久しい今日においては事前の説明が行われることにより、 不幸な出会いと別れを未然に防ぐ取り組みが広まっています。 またユーザー側もインターネットや書籍などの情報を駆使し、 予めリスクを察知することで自己防衛の意識も高まっているものと思われます。 だからと言って人々の巨大生物への憧れが弱まるのかと言えばそれはまた別の問題であり、 規格外の最終サイズを知りながらあえてそれを選択したいと強く望む方にとって、 現在の状況は半ば足を引っ張る格好になっていると言っても過言ではありません。 何故ならそれらを商品として目にするのは決まって巨大になる前の段階であり、 特別なことが無い限り既に育ち切った状態で輸入されるケースは考え難いですから、 入手する時点である程度の大きさを望む場合には、 やはりある程度の期間を国内で過ごしている必要があるのです。 年々飼育者の意識が高まれば自ずと放出される絶対数も減っていくのは当然の結果であり、 初めから大物を手に入れるいわゆるタイムスリップを狙う方にとって厳しい時代を迎えています。 今回やって来たのは見た目通りのやんちゃな性格がこちらの期待を裏切らない、 かれこれ十年近くはここ日本で過ごしているであろう久しぶりの飼い込み個体。 少し前までは年間かなりの頭数をご紹介できたこのケヅメも、 特に50センチオーバーとの出会いが極めて少なくなるのと同時に、 一センチの重みを余計に感じられるようになりました。 餌食い爆発、 いくら走り回っても物足りなさそうにしている元気印の男の子です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大サイズ・♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| またもや50cmオーバーのとんでもないヤツが登場! 何度やってきても決して見慣れることはありません、 特大サイズのケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 私たちがペットとして飼育することのリクガメ、 その中でゾウガメを除けばこのケヅメが群を抜いて最大級の大きさを誇るでしょう。 野生での最大甲長は70cmだとか80cmだとか色々な情報が飛び交っていますが、 飼育下での強欲な食事風景や尋常でない成長スピードを見る分には信じられない話でもありません。 ベビーの時点で他種に比べて圧倒的に活発で運動量も格段に多いため、 ずらっと並んだリクガメのチビ軍団の中からケヅメが選ばれるのもある意味自然な行為なのでしょうか。 そして本種が大きさ以上にパワフルさを感じさせてくれるのは、 小さな頃のやんちゃな性格そのままに大きくなるからだと思います。 本日は大変お日柄も良く日光浴がてら撮影のために店の表で歩かせてみましたが、 テンションはベビーの頃のまま結構な早足で歩き回るものですから近所の注目を集めて大変でした。 しかし50m以上も離れた場所からあれはリクガメかという声が聞こえてくるぐらいインパクトは強いらしく、 それだけの存在感を見せつけてくれるのが一番の魅力です。 第4椎甲板にくぼみと偏りがありますが全体像ではおおむね気にならないでしょう。 そして何より擦り切れて綺麗に揃った四肢の爪が今まで健康に歩き続けてきた証拠です。 当店では過去にも何度か育ったケヅメを扱ってきましたが、 この個体のように50cmの大台に乗せるにはやはり10年近くという極めて長い育成期間が必要ですので、 家のこの辺りに大きなリクガメを歩かせたいという願望を叶えるためには一気にタイムスリップしない手はありません。 発送についてもご相談下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大・♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
|
二頭の荒獅子が鼻息も荒く登場!
とんでもないものがやってきました、
ダブル50cmオーバーのケヅメリクガメ・オスの入荷です。
これまで飼い込みケヅメは何度か扱ってきましたが、
今回は普通に姿を拝むだけでは済まされず初めて後ずさりしてしまいました。
当然ながら当店過去取扱最大サイズの記録も楽々塗り替えてしまい、店内は軽くパニックに陥っています。
図鑑には最大甲長80cmと書かれていますがとんでもありません。
いくら大型種と言えど40cmクラスでさえ探すのは困難であり、
50cmクラスともなれば仮に国内で飼育されていたとしてもこうして販売ルートに乗ることは滅多にありません。
文献の通り現地にはもっと大きな個体がいることに間違いはないと思いますが、
ファーミングベビー以外のサイズで輸入されてくることが無くなった今、
このような飼い込み個体は有難いことこの上ない存在です。
という訳で実はこの2匹、なんとベビーサイズから国内で10年飼い込まれ育った個体なのです。
最初見た時は本気でワイルドかと思いましたが、
どうしてこの日本でこうもアフリカチックに育つのでしょうか、脱帽です。
1頭(A個体)は文句なしのフォルムで、
今日までの運動量は揃いに揃った10本の爪と何度も擦り切れた足の裏を見れば心配ご無用。
もう1頭(B個体)は
残念ながら1ヶ所凹みありですが、
飼育環境が同じということと甲板の形が少しずつ歪なので成長異常ではなく先天的なものかと思います。
このボリュームの稀少性は重々承知していますが何分店内の飼育スペースにも限界がありますので今回特価にて、
B個体は形状を気にされない方には更に特価です。
通販発送も原則受け付けております、まずは一度お問い合わせ下さい。
A個体: 背甲 ・腹甲 B個体: 背甲 ・腹甲 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大サイズ・♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| ドカンと一発56cm巨大ケヅメ! またもや当店過去取り扱い最大サイズを更新しました、 お客様委託のケヅメリクガメ・オスの入荷です。 一般に飼育できるリクガメの中でも最大クラスを誇るアフリカ出身の大型種。 大きくなるから安易な飼育はお勧めしません、というのはお決まりの文句ですが、 ではファーミングで繁殖され輸入されてくるベビーの何匹が本当に大きくなるのでしょうか。 個人で飼われている個体の中に埋もれている可能性はありますが、 出物としてオープンになる個体の数は本当に限られているのが現実です。 過去に入荷した中でも40cmクラスの時点で探して出てくるものではなく、 ましてや50cmクラスになると一期一会のタイミングに懸けるしかありません。 今回やってきたのは四捨五入すれば60cmにも達してしまう恐るべき巨体の持ち主。 しかも嬉しいことに甲羅のフォルムはスレの少ないワイルド個体に匹敵する美しさで、 またふちに妙な反りが見られたりというようなこともありません。 更に驚くことには、過去にメスを一緒に飼われていたそうで、 ペアで何年か連続でコンスタントに繁殖していた真の意味でのフルアダルトのオスです。 主に屋外で管理されていたらしく体全体のスレはありますが、 その分全ての爪が綺麗に短く揃い嘴の伸びや噛み合わせの心配も一切ありません。 余談ですが寒さへの耐性もじっくり鍛えられていたそうでそこそこいけるのだとか。 今回委託のためサイズに合わない特別価格です、発送にも対応しますので一度お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大サイズ・♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 実に六年ぶりの快挙となる当店過去取り扱い最長記録タイのダイナミックボディをとくとご覧あれ! 十年以上の長い年月を経ておおよそ完成と呼べるサイズに育ち切った最高のインパクトが此処に、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 並のペットとしては規格外と言われてもおかしくはない、 大変に大きく成長するリクガメとして最も有名な種類のひとつに数えられるであろう、 決して珍しいキャラクターではないが故にある種の親しみ易さにも溢れた、 ゾウガメと肩を並べる知名度を誇るアフリカ代表のケヅメリクガメ。 良くも悪くも一般的に入手し易い状態にあるがために、 非常にアグレッシブでよく動き回るために飼っていて楽しいだとか、 大きくなるのでよく考えてから飼育を始めましょうだとか、 一般家庭ではとても飼い切れるサイズではないためビギナーは諦めましょうだとか、 他にもまだまだ数多くの逸話を残してきたカメ界の看板とも言える銘種ですが、 巨大に育った個体をしかもペットの状態で実物として拝むことのできる機会は相当稀であると、 こんな機会でも無ければ声高に宣言することは難しいと思います。 確かに大半の人々が抱く大きなリクガメのイメージを成長過程で軽く超えてしまうため、 育ち過ぎて困ったと感じるタイミングはずっと手前の段階で訪れるため、 本当に困ったと言うべきマックスサイズでお目にかかる方がむしろ困難であり、 そのようなものに対して数字では容易に計ることのできない価値観を見出してあげたいものです。 今回やって来たのはかつて我々の下に舞い込んだ最も大きなオス個体と全く同じ甲長を持つ、 逆にこのボリュームを更に上回る個体がいれば目の前に連れて来て欲しいと思ってしまう、 それほどに素晴らしい体格を見せ付けてくれた当然のことながら長期飼い込みのオス。 本種が持つ最大の魅力がその体積、質量にあるとすれば、 この個体はケヅメとして最も魅力的な状態にあると言っても過言ではなく、 斜め上から見た甲羅全体のシルエットも申し分ないため、 見栄えの良さに強い付加価値を感じて頂けると思います。 前飼育者の下では相当に可愛がられていたらしく、 顔の前に手をかざしただけで親しげに近寄って来るほどよく慣れています。 冒頭でも触れた通り本当に数年に一度の稀有な出物ですから、 何か特別な思い入れのある方にとってはこれが千載一遇のチャンスに違いありません。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (マンモスサイズ・♂) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| もはや不可能とさえ思われた60センチオーバーのK点越えを達成し未だ成長の余力を残す巨漢の若獅子! 当店入荷過去最大記録をなんと6センチも塗り替えた化け物を前にただ恐れ戦くことしかできないまさに未知との遭遇、 ケヅメリクガメ・オスが入荷しました。 これまで日本国内では様々な種類のリクガメが姿を見せてくれましたが、 ある意味これがペットトータス最強の種類であると考えて差し支えないのかもしれません。 世界最大のリクガメとして最高の名声を獲得したかのゾウガメと比べてしまえば、 言うまでもなくその甲長という絶対的な数値で勝ることは叶わないものの、 彼らはやはり高嶺の花として良くも悪くも馴染み深いとは言い難い崇高な存在ですから、 こちらケヅメなどは庶民的の三文字を体現したような親しみ易さ全開のキャラクターが売りで、 近い将来いつかは必ず飼育してみたいと強く憧れているファンの数も相当に多いことと思われます。 しかしながら現地ではアフリカ大陸の果てなき地平線をひとり孤独に耐えながら闊歩するような、 正直私たち日本人の感覚では到底分かり得ないダイナミック極まりない暮らしを展開していますから、 そんな勇ましき生き様をそっくりそのまま再現しようなどとは考えない方が無難であり、 できることの最大限を思い描いた上で懸命に取り組む姿勢が求められるのではないかと思います。 つまり幼い頃からコツコツと育て始めても数年後、 十数年後に拝むことのできるかもしれない明るい未来は全ての人々に約束された成果ではなく、 落胆こそしないまでも大多数が到達し得ない表向きには隠された境地が絶対に存在しているため、 そこでようやく自然の驚異と初めて対峙することになるのでしょう。 ただし時にはケヅメリクガメの持つ潜在能力が遺憾なく発揮された状況に出くわすこともあり、 見慣れたはずのカメに対しこれまで以上の感動を覚えることもまた覚悟しておかねばならないのです。 今回やって来たのは凄まじき轟音を身に纏い突如我々の前に姿を現した恐るべき巨象。 過去に当店で取り扱ったケヅメとはまるで比にならない未曾有の体躯を振り回す、 甲長62センチという最大記録の56センチを軽々上回る世界的な大記録を打ち立てた大魔王です。 その大きさも然ることながらカメとしての仕上がりも拍手喝采の高品質で、 甲羅のフォルムからみずみずしい質感まで何処にも落ち度がなく、 その素晴らしさがありとあらゆる角度から称えられるべき絶品中の絶品。 百年に一度の幸福な巡り合わせを更に盛り上げるべく、 近所の子どもとの可愛いツーショットまで撮影し店内は大盛り上がり、 これほどの掘り出しものは二度と手に入らないと覚悟の上でご検討下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 日々甲羅をピカピカに磨き上げたくなるほど丸みの粋を極めた絶妙な仕上がり! ベビーからでは怖くともまだまだ育てる楽しみが十分に残されたやんちゃ盛りの安心サイズ、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 アジア圏の人々にとってカメとは非常に身近な存在である、 こういった類のエピソードについてここでは度々触れてきましたが、こと日本においてもそれは例外ではなく、 爬虫類特有の厭らしさがかなりの割合で取り除かれそこから独立した生き物として認識されています。 では世間一般のカメが持つイメージの正体とはどのようなものでしょうか。 ある種の先入観がそのぼんやりとした像に多大な影響を与えるに違いありませんから、 きっと幼少期の体験が最も重要になるのだと思います。 日本のお伽噺の代表作のひとつ浦島太郎、ここに登場するのはウミガメである可能性が高く、 浜で子どもにいじめられるシーンが陸上ではうまく活動できなかったことを物語っています。 そして海外作品からのノミネートは勿論うさぎとかめ、こちらでは反対に歩くことがメインテーマですし、 舞台がヨーロッパであることからリクガメがモデルになっているとされています。 我々がペットとして馴染み深いと感じるのはミドリガメやゼニガメですが、 水棲ガメというジャンルは前述のどちらにも当てはまりませんし、 万が一カメは歩くものとして強く思い込んでしまっていた場合、 その欲求が満たされることは永遠に起こりえないのです。 同時に私たちは図鑑や自然番組などからゾウガメという巨大な生物を印象付けられ、 歩くカメと言えばとても大きなものなのだと憧れにも似た感情を抱いていますから、 無意識の内にリクガメの大型種へ心が奪われようとも何の不思議もないのです。 ペットにすることができるリクガメの中では最大級を誇る本種、 その恵まれた体格と明るさいっぱいの性格は長年に渡り多くの愛好家を魅了してきましたが、 例えば50センチなど本当に大きくなり過ぎてしまうことから安易な選択には注意が喚起されます。 しかし野生状態と同様にそこまで極端に巨大化するのはオスに限られ、 メスは40センチにすら到達しない段階で成長が鈍くなりますから、 現実的には30センチ台で産卵を経験することも決して珍しいことではありません。 その気質についてもオスは有り余るパワーを全力で発揮してきますが、 メスの場合は程良く温和になることで他個体への排他的な行為や飼育環境への破壊行動も抑えられますから、 飼い続ける上で想定外のアクシデントが起こる危険性も低くなります。 この個体は甲羅全体の艶気や四肢の爪がしっかり生え揃っていることなど、 健康体の証が随所に表れ四六時中歩き回る典型的なケヅメです。 しかもオスに比べて流通量の少ないメスですからお探しの方はお早めに。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 綺麗にまとまったその姿に文句のつけようがありません! 色、形、そして性別と嬉しい所がいっぱいです、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 毎年シーズンになるとアフリカからやってくるベビーたちは本当に可愛らしく、 リクガメの代表として非常に人気の高い本種。 大きくなると分かっていてもつい育てたくなってしまうのは、 それだけこのカメに魅力が潜在しているからでしょう。 当店ではこれまで色々なサイズのケヅメを扱ってきましたが、ベビーから育てたい派は前述の通りで、 安心サイズやある程度大きく育ったサイズから育てたい派の方も多いと思います。 実際、特に上手に育てられた個体はベビー以上に有難みがあり競争率は他のどれよりも高いです。 今回やってきた一匹はパッと見て栗色の甲羅が特徴的なメス。 そう、メスなんです。 育ったサイズで入荷するとやたらオスが多く、ペアで揃えようと思っても相方が見つからなかったり、 オス特有の発情期に見られる気の荒さを回避するためにもメスはお勧め。 甲羅の色合いは薄いベージュ系統のものが多い中少し変わった印象を受ける茶系統で、 その仕上がりも表面までツヤツヤの手入れが行き届いた様子や、 均等に正確無比に刻まれた成長線と併せて前飼い主の愛情をたっぷりと受けていたことが伺えます。 こうなれば全体のフォルムというのは悪くなるわけもなく、 綺麗な俵型をしたリクガメらしい姿は観賞価値の高さも抜群。 これから長い付き合いになるだけに納得の一匹を選びたいものです、 もちろん餌食いなどコンディションの良さもバッチリなのでご安心下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 淡い栗色が照り輝く理想的なてんとう虫体型! 女性的でふくよかなスタイルが飼育技術の高さをもってより一層引き出されています、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメで一番人気の高い種類は何ですかという問いに対して、 ずばりこれですとたった一種に絞った明確な答えを出すことは難しいでしょう。 例えば模様の綺麗なホシガメ、例えば飼いやすく親しみやすいギリシャリクガメ、 各々がそれぞれの分野で魅力を振りまいているのと同様に、 本種もまた世界中で幅広い層のファンを獲得しているトップクラスの人気者です。 最も長所と呼べる部分はやはり大きく成長すること、 もちろん大きくなり過ぎるため飼育には向かないという否定的な意見もありますが、 ケヅメのことが好きな人にとってそれはポジティブに捉えるべき特徴と言えます。 図鑑でアフリカの大地に暮らすこのカメの存在を知った、自然番組で野生の勇姿を見た、 動物園で実際の大きさを目の当たりにした、憧れを抱く瞬間は人それぞれですが皆思いはひとつ、 大型のリクガメをペットとして自宅で飼育したい、シンプルにただそれに尽きるのではないかと思います。 では同じ考えを持つ日本国民全員が現実にこの夢を叶えられるのでしょうか。 先述の忠告に従えば衝動的に飼育を始めるのは危険な行為なのかもしれませんが、 これほど注意を喚起されていてもなお人気が衰える様子がない所を見ると、 改めてこのリクガメが持つ不思議な力のようなものが感じられます。 今回やって来たのは極めて満足度の高い状態に仕上げられつつある飼い込み個体で、 それでいて更に嬉しいことに性別はメスというこの上ない貴重な出物です。 どうでしょうかこのツルツル具合、 初生甲板の僅かなボコ付きも許さない十分に膨らみの出た体型は、生半可な思いで実現するものではありません。 縁の反りも殆ど見当たらず、 嘴の伸び過ぎや噛み合せの不具合もなく、 四肢の爪一本一本もだらしなく伸びたり曲がったりすることなくびしっと生え揃っています。 総合点が高い水準にあるため腰の落ち込みが余計気になってしまいますが、 まだ20cm台ですから今後の育て方でカバーできる可能性もあります。 性別については何故メスを求める声が大きいのか、 それはオスに比べて性格が温和な個体が多くいざ巨大になった時の取り扱いが幾分容易なこと、 そして何より本種はオスの方が大きく成長するからです。 オスの場合、放っておいても年月が過ぎればその多くが50cm近くになり、 自然界では70cmを超えることもあるようなのですが、 最新の研究ではメスはそれの一回りも二回りも小さいとされています。 これから長い付き合いになるのですから最初の選択が重要であることに間違いありません、 ケヅメを飼いたいけれども大き過ぎるのは困る、という実にわがままな要求にもメスであれば応えてくれるでしょう。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| メス求むの声に何とかお応えすべく全国各地から探し出しようやく引き抜いて来た秘蔵っ子! 最終サイズから性格まで全てを考慮した上でオスよりも強く推薦します、 素材の良さもキラリと光るケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 自宅の庭で大きなリクガメをのっしのっしと歩かせる、 これはカメが好きという条件の下であれば恐らく万人に通ずる皆の夢であり、 もしもそんなことが現実的に可能だと分かればまず間違いなく実践してしまうであろう、 我々の欲求を存分に満たすのに必要な幸福というものを高いレベルで享受するための非常に有意義な手段です。 ケヅメリクガメはアフリカ大陸のみならず、全てのリクガメと呼ばれる生き物を代表する大型種で、 単にその大きさだけに着目するとおよそ家庭での飼育には向かないとされていますが、 彼らとはあくまでも趣味として接する訳ですから一般論はさて置いて、 そこは何としてでも課題をクリアし逆境を乗り越えなければならないでしょう。 慣例的に似たもの同士と捉えられるヒョウモンガメには甲長の性差がないとされていますが、 反対にケヅメの場合は条件のひとつとして検討する余地があり、 文献によるとオスの最大は70cmとも80cmとも言われていますが、 そうかと思えばメスの場合は50cm程度で収まるとされています。 しかし飼育下でそこまで大きくなったオス個体を見かけることがあるでしょうか、 実際には十数年の付き合いを経ても60センチに迫ることができれば上等、 環境によっては50センチに到達しないことさえも珍しくはないのです。 さて、この場面における最大の注目点はそれがメスにもそのまま適用できるのかということに尽きますが、 巨大になるというイメージとは裏腹にメスは30センチ台で早くも産卵を経験することが知られており、 このことからオスに比べると随分小さく収まる可能性が高いのではないかと考えることができます。 また性格もオスのように盛りがつくことはありませんし、 そうでなくとも破壊願望や他人に迷惑をかけるような行為が少ないので単純に扱いやすいと言えるでしょう。 当店では過去に何度も放出もののケヅメを取り扱ってきましたがメス確定の個体は数えるほどです、 フォルムや栄養状態も全く問題のないこの一匹で有意義なケヅメライフを末永くお楽しみ下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 数が少なくいつも人気のメスなのでお探しの方はお早めに! ようやく30cmに到達しようかという節目の両腕抱っこサイズ、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 日本では昔から今までリクガメ科に属する種類の殆どをペットルートないしは動物園などで見かけることができましたが、 このケヅメほど我々人間に与える影響力が強いものもなかなかいないと思います。 リクガメの仲間では何が人気ですかと問われた時、 とっさにホシガメやヘルマンリクガメなどが頭に思い浮かぶことでしょう。 それらは飼育に必要な環境を無理なくセッティングできるため、 あとは知識と愛情さえあれば終生飼育もさほど困難ではありませんが、 この超巨大なカメの一生を見届けるとなるとそう簡単にはいきません。 それは今更述べる必要もない周知の事実ですが、 しかしそうと分かっていてなお惹き付けられてしまうこの不思議な魔力は一体何なのでしょうか。 今回やって来たのは4、5年間ほど飼い込まれたミドルサイズで、ようやく一人歩きさせても危なげない感じ。 ただ室内で見ると結構大きいような気がしても、 ひとたび天日の下に出せばまだまだこれからだという印象を受けます。 本日の名古屋は春の陽気が感じられる晴天だったので外へ散歩がてら撮影を行いましたが、 最初は無限に広がる空の景色に戸惑いつつも逞しく闊歩する姿が見られました。 正直甲羅の形は万全ではなく、爪と蹴爪の伸び方から運動不足の気が見られますが、 先程申し上げた通りここからがケヅメの本領を発揮するステージですから、 環境さえ整えてやればあとは自分で勝手放題歩き回り餌を爆食する元来の姿に返り咲くはず。 実際この日光浴で数分後には大股開きで軽やかに走り回っていたので、 コンクリートやタイルなど硬い地面の上で爪を磨耗させるようにしてやると良いでしょう。 甲羅の色は深みのある栗色で何だか上品、 日差しを浴びた時にはなお美しさが際立ちます。 野生でもメスはオスに比べて小型という報告があり、 オス特有の発情期にどうしようもなくなる現象が回避できるなど、 どうしてもメスでなければとお考えの方も多いと思います。 こんなことを言うとカメには悪いのですが、 外観なりのお値打ち設定にしてありますので是非可愛がってやって下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 形良し、性格良し、そして性別良しと三拍子揃った掘り出しもので繁殖にもトライしたい稀少なメス! 春の陽気が漂うこのシーズンからバスケットボール大に育ったリクガメとの新生活を始めてみたい、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 それが初心者でも扱える種類であるかどうかは別にしても、 本種の存在を以ってリクガメという生き物を知り、 まさかペットとして飼うことができるだなんて夢にも思わなかったところへ、 どこぞのカフェにいた、病院にいた、果ては路上で散歩していたなどなど、 様々なシチュエーションにおいて目撃例が多々聞かれる業界きっての有名人。 母国は遠いアフリカ大陸の中央部ながら数十年前より輸入されており、 一般家庭で飼育されていたり動物園の展示として用いられていたり、 リクガメのことを知りケヅメのことを知らない人はいないとまで言わしめるほど、 最も高い知名度を誇る重要なキャラクターであることに違いないでしょう。 ゾウガメを除けば我々が通常手にし得るものの中では最大級のボリュームを誇り、 無論誰しもが育てられるというような生易しい条件ではないにしても、 全てのリクガメ好きに憧れの念を抱かせるには十分過ぎるスペックが堪りません。 大きくなり過ぎるため飼い切れなくなる恐れがあると、 いつの時代にも例外なく言われ続けているはずなのですが、 世の中の動きはそれほど大きく変わっていないところから察するに、 人々の心を揺さぶる強大なパワーがそこに内包されていることが証明されています。 今回やって来たのはオスに比べ出現率が圧倒的に少ないとされるメス確定の飼い込み個体で、 当店でもこれまでに数度取り扱った経験はあるものの、 記録上一年に一匹手に入るかと問われればそれは叶いません。 多数のファンがメスを追い求めるのにはいくつかの理由が考えられ、 やはり夢の自家繁殖にチャレンジするためにはオスのみでは話が始まりませんので、 大きく育ったメスというものはただそれだけで付加価値が跳ね上がります。 またメスの方がオスほど巨大になり過ぎないのも大切なポイントで、 それはケヅメという選択をしながらスペースの節約が実現できると共に、 性格も穏やかなものが多いため破壊行動が軽減できるというのもミソ。 多くの証言によると四十センチ前後で産卵も可能だそうですから、 その頃には大人になっていると考えても良さそうです。 爆発的な食欲は野外での撮影時にもそのエネルギッシュぶりが遠慮なく発揮され、 バックショットから見るに腰元の仕上がりも悪くない、 素敵なフォルムで新しい成長線もバリバリ伸びている絶品です。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大サイズ・♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| この凄まじい体躯を見るにとてもメスだとは信じられない過去最高クラスの即戦力ビッグママ! 温室育ちでピカピカに仕上げられた貴重な種親候補をここからビシバシ鍛え上げましょう、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 当店ではこれまでに何頭ものケヅメを取り扱ってきましたが、 それらは数多くのペットショップでよく見かけられる可愛らしいベビーではなく、 世間の人々が思う所の可愛らしさがおおよそ抜け切ったミドルサイズ以上のものが殆どです。 日本全国で一体何百頭、何千頭のケヅメが飼育されているのか想像も付きませんが、 中には諸々の事情で手放されてしまう個体も少なくありません。 それは様々な理由があってのことだと思いますが、 あえて問うことはないものの育ちを見ればどのような思いで飼われていたのかがしみじみと伝わって来ます。 もちろん細かい所で知識や工夫が少々追い付かなかった部分が見られたりはするものの、 明らかに間違った愛情でなければそれはきちんと形として表れるもので、 放出前夜の最後まで飼い主としての責任を果たされた結果は自ずと滲み出るものなのです。 今回やって来たのは幼体からおよそ四年間、みっちり歩かされみっちり食べさせられた結果、 全身がとてつもなく潤いに満ちた極上の仕上がりを味わわせる一頭のメス。 まるで家族のように付き合って来たというエピソードは真であり、 この素晴らしい成長具合を見て何の疾しさが感じられると言うのでしょうか。 お洒落なダークブラウンの甲羅は成長線の一本一本が艶っ気を帯び、 殆どボコ付きがないどころか腰の落ち込みもほぼ全く見られず、 女性的なふっくらとしたシルエットもまたセクシーな魅力を漂わせています。 基本的には年中ぬくぬくと飼われていたようで、 甲羅の表面に擦れや傷があまりなく鱗のひとつひとつまで先が尖っているため、 亜成体をそのまま大きくした芸術品のようでもあります。 とここまではあくまでもペット的な見方をした場合の見解で、 我々ホビイストとしてはやはり繁殖についても視野に入れて行かねばなりません。 オスであれば50センチに到達してようやく威張れる所ですが、 メスの場合は40センチ台になれば遂に産卵が可能になるため、 本当に繁殖を目指している方にとってはこれ以上有難い出物は考えられないと思います。 こちらとしても直ぐに交尾できるオスを探すのはある程度容易なのですが、 今すぐ産めるメスをと言われてもまず見つかりませんので、 あの時手に入れておけばと後悔することのないよう確実に押さえておいて下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (特大サイズ・♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 誰が何と言おうと文句無しのリアル即戦力を決意の大放出、 メスの過去入荷最長記録をまたもや更新した泣く子も黙る進撃のビッグママ! 何を隠そう先日ご紹介した国内CBの実母がこの個体です、 ケヅメリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメはペットとして飼育してはいけないと言われ始めて早十年以上が経った今、 それでもリクガメを愛して止まない我々日本人が出した答えとは一体どのようなものなのでしょうか。 優先されるべき事項はいくつもありそのどれもが欠かせない要素ではあるのですが、 まずこれが無いとお話にならないのが十分な運動量を確保するためのスペース。 その昔某研究所にて一日の移動総距離を調査した結果では、 一般的な60センチ水槽の外周をなんと百回以上も回らなければならないことが分かり、 流石にそれを丸々再現することは難しくとも如何にして歩かせるかが課題となりました。 そして次に思い付くのはカメの成長を助ける十分な紫外線量、 これは近年開発が進んでいる専用の蛍光灯やメタハラなどの優れた器材の他に、 自然の太陽光を惜しみなく与えることにより解決することができ、 飼育者はそういった環境を与える必要があることも分かりました。 その他にも栄養価の適切なバランスやカルシウムの摂取量など、 考えるべきことを挙げればキリがありませんが、 今まで実体として見えてこなかった数々の必要事項を守るよう努めた結果、 こういった大型種の本当に大型な個体が日常的に登場するようになったのです。 今回やって来たのは先日この場に掲載した国内CBの一年ものと血縁関係のある実の母親で、 別のオスを用い実際に種親として使われていたまさしく実働確認済みの巨大なメス。 オスで50センチオーバーとなると今日ではさほど珍しくもなくなってきたようですが、 文献によるとオスよりも小型なメスで40センチ台半ばにもなるとその迫力は段違い。 甲板の配列に少し歪みがありますがそれとて今更気になるものではなく、 サイズは勿論のことその実績を考慮すれば十二分に評価されて然るべきでしょう。 顔立ちをよく見ると鼻先があまり尖らず丸みを帯びた表情で、 目元も柔和な如何にも女性らしい雰囲気を感じさせます。 昨季は雌雄離れ離れとなり交尾をさせなかったためか無精卵のみだったそうですが、 その前に三年間も続けて子孫を残しており、 実年齢も十歳に満たないそうですからまだまだ産み足りないと思います。 メス自体の出物が極端に少なく繁殖経験ありともなると尚更見逃す訳にはいきません、 ケヅメのブリーディングを本気で志す方にとってはまたとない大きなチャンスです。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (♂・♀) Geochelone sulcata |





|
|
||||||||
| 暖かくなってきたので外に出したら終始活発に歩き回っています。 バスケットボールからお米の袋ぐらいに大きく育った飼い込み個体、ケヅメリクガメが入荷しました。 アフリカが原産の古くからリクガメを代表する種類で、最近では某タレントさんとCMで共演するほどの人気者。 さほど興味がない人ですら目の前にすればついつい見入ってしまう圧倒的な存在感が何と言ってもこのカメの魅力です。 名前の由来である鎧のような爪状の突起を備えた太い脚でずんずんと歩む様は迫力抜群で、 明るい性格も手伝っていつも元気よく歩き回っていますから眺めているだけでも楽しいです。 飼育については十分な紫外線を与えること、 十分な運動スペース・運動量を確保すること、低栄養・高繊維質の餌を十分に与えることが基本で、 あとは愛情をかけてあげればそれにちゃんと応えてくれます。 両個体 (オス・ メス)とも第四椎甲板の部分が少しへこんでしまっていますが、 MAXサイズを考えればここから立て直せば最終的にはかなり目立たなくなると思います。 またオスは腹甲板のシームにずれがあります。 状態はどちらもとてもよく、餌はきちんと与えているのですが外に出すとそこに野草があれば常に食べているような状態です。 オスはもう盛り始めていて、時折小さなメスを追い回して練習に励んでいます。 今年の春はなかなか暖かくなりませんでしたが5月に入って大分気温が高くなってきましたので、 このような大型のリクガメでも飼育スタートしやすいと思います。 既にボリュームのある大きさに育っていますがまだまだ成長期で、 まだ先の話ですが一応ペアになっていますので2頭まとめてのペア価格もあります、お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ケヅメリクガメ (アイボリー) Geochelone sulcata "var" |





|
|
||||||||
| 極上クオリティの上に安心サイズで文句無し! 丹念に飼い込まれた稀少なミューテーション、ケヅメリクガメ・アイボリーが入荷しました。 アイボリーとはすなわち象牙、これまた見事なネーミングです。 普通のケヅメの甲羅をとって、 代わりに象牙製の甲羅と着せかえた様な奇抜なカラーリングはお見事。 色抜けはもちろん甲羅だけではなく 頭部も四肢も純白とはまた違った味のあるクリームホワイトで、 両眼ともブドウ目でさりげない雰囲気の違いが感じられます。 アルビノもアイボリーも、 こうして見せられるといかにアメリカでケヅメが愛されているかがひしひしと伝わってくるようです。 暖かい日差しを浴び神々しさを増したその姿を目の当たりにするとちょっとびびってしまいますが、 撮影の為に一瞬外に出しただけで本当によく歩きますし、 餌を食べる時も葉野菜の塊りに豪快にかぶりつき、 排泄物も大小モンスター級な所は中身は普通のケヅメとなんら変わりはありません。 リクガメの色変わりは依然高額なのですが、今回は少しお値打ちに設定してあります。 この立派な個体を更に仕上げて頂ける方、お待ちしております。 参考までに尾のアップはこちら。 | ||||||||||
|
アナホリゴファーガメ
Gopherus polyphemus |





|
|
||||||||
| こんなに大きく育ったゴファーはそうそうお目にかかれません! お客様がよく見かけるベビーサイズから丹精込めて飼い込み大きく育て上げた、ゴファーの中のゴファー、アナホリゴファーの入荷です。 その名の通り、穴を掘るためだけに設計されたその体つきは他のリクガメには無い特徴を持ち、 前肢は薄く幅広くシャベルの様な形状でガリガリと穴を掘り進む事ができ、 甲羅は扁平気味で邪魔になりません。現地では穴を掘り過ぎて家屋を傾けてしまう事もあるそうです。 温度・湿度共に安定した穴の中に潜み暮らしている為、丁度良い温度・湿度を保つ事が飼育の肝です。 特に湿度に敏感な様で、高いと鼻水を垂らしたり低いと目が乾燥してしまう様なのでサインを見逃さない様にしましょう。 とは言ってもここまで成長していますから、多少の環境変化には動じない丈夫な個体です。 店頭では隠れたがる事もあまりなくケージ内を活発に歩き回り、 葉野菜をよく食べています。 飼育時に左目まぶたを傷付けてしまった様で少し眼球がむき出しになっています。 現在では治りつつあり視力に影響もなさそうですが、今回特価にてお出ししますのでご購入検討中の方はお問合せ下さい。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (CBベビー) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
|
反則的な可愛らしさでこちらを見つめる黒く澄んだ瞳に思わず吸い込まれてしまいそう!
小さな体でも懸命に餌を食べる姿を眺めていると何だか元気を分けてもらったような気持ちになれます、
エロンガータリクガメが入荷しました。
西はインドから東はベトナムまで、
東アジア南部の国々にまたがって広く分布しているインドリクガメ属の一種で、
お隣中国では南側の国境が主要な原産国の多くと接しているせいか殆ど地のカメという扱いらしく、
ホルスかエロンかと言われるほど初心者層を中心に広まり盛んに飼育されているそうですが、
残念なことに日本では未だ普及が遅れているようで知見もあまり多くありません。
昔から流通自体はあったのですがそのほぼ全てを野生個体が占めており、
輸入が散発的かつ初めから状態を崩したものも少なくなかったため、
いまいち正体を掴めぬままファンが育ち難い状況が続いています。
基本的には森林棲とされていますが別段乾燥に弱い訳でもなく、
棲息地から考えても分かるように低温への耐久性も持ち合わせており、
薄明薄暮性の傾向が強いことから強力な日光を進んで浴び続けることはしないため紫外線要求量も他種に比べ少なく、
草原から雑木林まで広範な自然環境を採餌のフィールドとしているため食性が幅広いと言った、
書き連ねると落ちがないため何が何だか分かり難いと感じてしまうかもしれませんが、
ここは反対に多様な飼育環境へ馴染むことのできる高いポテンシャルを秘めていると表現したい場面です。
何処となくクセのあるイメージが抜け切れないというのは初期状態に原因があるケースが大半で、
立ち上がった個体の目覚ましい回復振りと生まれ変わったような躍動感にそのことが証明されています。
この辺りで一旗上げて一躍人気の定番種へ仲間入りを果たしたい所ですが、
今回は現地で捕獲された訳でもなく、その実在は未確認ながらファーミングで殖えた訳でもなく、
正真正銘ペットとして趣味で飼育され繁殖にも成功した、
エロンガータの啓蒙活動にこの上なく相応しい歴としたCBの三匹がやって来ました。
ハッチリングにある程度の大きさがあるため弱々しい雰囲気は一切なく、
むしろ成長線の特に出ている個体に関しては早くも力強ささえ感じられるほど。
全て裏返すとバタバタ暴れて撮影どころではなくなりますが、
パンと張りに満ちた腹甲には内側からの圧力がしっかりと感じられ、
衰弱して水分が抜けてしまった状態とは真逆のグッドコンディションです。
さすがのCB個体ですから野草や葉野菜は勿論のことすんなりMazuriリクガメフードにも餌付きましたが、
多彩な食性を生かし餌にバリエーションを付けるのも面白く、
キノコ類や豆腐など一見怪しいものに喜び勇んで食らい付くシーンにはまた異なった表情を観察することができます。
持ち前の特徴である甲羅の色艶が存分に生かせるというのもCBの魅力と言えるでしょう、
状態は軒並み安定していますのでカラータイプのお好みでお選び下さい。
ムービー | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (ベビー) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| ルール無用の反則的な可愛らしさに放射模様を伴う僅かな成長線が安心感を添える最強のベビー! 入荷して間もなくMazuriリクガメフードに餌付きいきなり及第点を獲得した期待の一匹、 エロンガータリクガメが入荷しました。 かつて本種の置かれた立ち位置としては綺麗な言い方をすれば個性的な、 言葉を選ばずに言えば一軍よりは二軍選手というようなイメージに近く、 レギュラーの定番種たちと比べて明らかに雰囲気が異なるために、 好きな人は好きと呼ばれるような部類で頑張ってきたようなキャラクターでした。 つまり普通の人たちがヘルマンやホシガメなどの人気種を選ぶような場面で、 わざわざ、あえて、そうではない方を選ぶというような感覚が先行し、 好き好んで自らの意思でマイナーな方向へと突き進みたいファンを喜ばせていたのです。 しかしながら最近ではスタンダードな種類に見慣れ少し目を逸らしたとしても、 脇役として配されていた彼らが流通を減らしてしまったがために目にする機会がなくなり、 リクガメ全体のバリエーションに乏しくなってきた感も否めませんから、 これまで後回しにされていたようなアブノーマルな珍種たちが、 時代の流れと共に再び脚光を浴びているような気がしてなりません。 大昔には輸入状態が悪くとてもペットとして扱えるような品ではなかったものが、 昨今に見られる飼育技術の改善と併せてきちんと育てられるものになり、 選べるほどはいないにしてもリクガメ社会が新たな局面を迎えているのです。 今回やって来たのはそこそこ出回っていた頃であっても珍しかったベビーサイズのエロンで、 顔の愛くるしさは言うまでもなくアグレッシブな動きもまた見ていて飽きない、 いわゆるポピュラー種に勝るとも劣らぬ魅力全開で頑張っています。 これらの仲間たちが自ずと敬遠されてしまうのは情報の少なさからなのでしょうが、 はっきり言って現物を見てしまえば殆ど全ての悩みは一瞬にして吹き飛びますし、 そんじょそこらの一般種と同等かむしろ飼い易そうとさえ感じて頂けると思います。 ベビーと表記されつつも背中には力強い成長線がはっきりと確認でき、 この艶やかな質感のまま大きくなってくれればどれほど美しい姿に仕上がるのか、 今から待ち遠しくて仕方ありません。泣いても笑っても一匹のみ! | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (S) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| ふんわりカラーに特有のキュートな顔立ちに思わず食指が動いてしまうナイスエロン! 面白がってMazuriをバクバク食べさせていたらこんなに大きくなりました、エロンガータリクガメの入荷です。 この場では幾度となく申し上げており今後もそれを続けていく所存ですが、 湿潤系のリクガメが難しいという漠然としたイメージはこの際いっそ捨ててしまいましょう。 もちろん湿度を管理しなければならないという条件が増えることで、 湿度をさほど気にしなくても良い種類と比較すればその点については難度が上がるように感じますが、 この場合その他の要素との兼ね合いについてはあまり考えられていないと思います。 本種は他種と比較しても殊の外頑健であり、 とあるエピソードでは本州の山の中で逃亡を図った個体がそのまま越冬し再会に至ったという事例もあるほど、 飼育下で想定されるあらゆる場面において幅広い適応力を有しています。 分布域の広さなどもそういった特質を表していると言え、 元々が森に潜み堪え忍ぶように暮らしているためか、 実際には乾燥に晒されたところで生命の危機に直結する訳ではありませんし、 温度変化や食生活もざっくばらんで良く環境に対してシビアな要求をするとはとても考えられません。 仮に湿度の面をごく真面目に注意するとすれば、床材を適度にしっとりとキープしておくぐらいの話で、 どうしても気になるのであれば甲羅に直接水をかけて濡らしてやれば大部分の問題は解決しますから、 あまり思い詰める必要もないのです。 過去に紹介され尽くした定番中の定番に飽き飽きしていた方、 これで今までは気に留めることも無かった新たなジャンルが開拓され、 有意義な選択肢が増えたと思って頂けたでしょうか。 今回やって来たのは体中の黒斑が消失したパターンレス系に程近い、 柔和な褐色が全身を包み込む最も分かり易くかつ人気の高いタイプのエロンガータ。 やや透明感のある色白の顔に大きくて吸い込まれそうな黒い瞳が抜群の可愛らしさを放ったかと思えば、 これまた高級感溢れる象牙でつくられたような甲羅は何処までも上品で、 いわゆるビギナー向けとされるどの種にも似つかない新感覚の魅力が満載です。 ただひとつネックになるのは野生個体で調子を落とした個体が時折見かけられること、 しかしながらこの個体はベビーからの飼い込みですからバシバシ成長線が伸びており、 店頭でも調子に乗って育てていたら育ち過ぎてしまったため慌てて掲載することにしました。 多くのリクガメでは大きなサイズであることに価値がありますが、 エロンの場合はその反対に小さな頃から面倒を見れることに大きな価値があるでしょう。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ
Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| いいサイズに育ったエロンガータが入荷しました。艶やかな白い美肌に、潤いたっぷりの つぶらな瞳が輝いています。背甲のイエローの面積も多く、目立ったキズもなくて非常に綺麗です。 性別は不明としましたが、かなりオスっぽいです。写真でのご確認お願いします。 多湿系ですので、日本での飼育にも適しているのでは無いでしょうか。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (ブラック) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 生来のピュアで愛らしいイメージなど何処吹く風、 一瞬にして辺りを包み込む邪悪なオーラに痺れさせられる貴重なブラックタイプ! 本当の真価が問われるのは成熟サイズを迎えたその時です、エロンガータリクガメが入荷しました。 ペットとして私たちが触れ合うことのできるリクガメには多様な生活史を見ることができ、 それは例えば砂漠に暮らしているものやはたまた草原に暮らしているものなど様々ですが、 森林に暮らしているものの代表と言えばこのエロンガータが当てはまるのではないでしょうか。 流れる空気はしっとりと湿り気を帯び、こぼれる光は木々の隙間からやさしく降り注ぐ、 そんな環境に息衝くこのカメの特徴は今にも泣き出しそうな程にうるうるとした黒い瞳に他ありません。 そこから少しフェードアウトして全体像を眺めて見ても、 甲羅の模様は同種内でも個体によりバリエーションがあるものの、 多少の黒斑が入った所で全体の柔らかな色調が揺らぐことはなく、 ふんわりのほほんとした温和で穏やかな雰囲気がつくり上げられています。 そんな癒し系のキャラクターも必要不可欠だと思うのですが、 一般的にリクガメの人気はどうやら乾燥系の種類に集中しているようで、 それらとは正反対な多湿系の仲間には何となく気難しい印象もあるのでしょう。 反対にそういった多湿系は水棲ガメの愛好家に好まれてはいるものの、 この可愛い感じがどうにも受け入れ難いようで居場所に迷っている感も否めません。 そこで今回ご紹介するのは、同じエロンでもなかなか珍しい黒を基調とした一匹のミドルサイズ。 単なる個体差か、それとも地域個体群として認められるのか、 全身が黒く染め上げられると聞いただけでも実に刺激的で、 心なしか表情も凛々しく特に目元などにはキレの良ささえ感じられます。 このタイプがとにかく面白いのは、今後の成長に連れてどんどん黒味が増していくということ。 初生甲板にしぼり出された色が徐々に成長線へと染み出すように、 少しずつその面積が広がっていくというのは感動すら覚えるものです。 でなければ現状で観察することのできる新しい成長線のみが白く、それ以外、 つまり初生甲板の周りがしっかりと黒くなっていることへの説明が付きません。 体の特に四肢はブラックペッパーを散らしたかのようで、 鱗の隙間に墨入れを施したような仕上がりは実に渋く格好良いです。 撮影中も落ち着きがなく、餌はMazuriリクガメフードをはじめ葉野菜や果実など選り好みなく爆食しており、 心配して損したと思わせる位の快調ぶり。 あとは綺麗に育て上げるだけで漆黒のエロンが出来上がります、 この姿を見せられてしまっては今から待ち遠しくて仕方ありません。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (パターンレス・Pr?) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
|
オレンジ&レモンヘッド、
どちらとも選びきれない嬉しい2パターン!
珍しいスモールサイズで機敏に動き回っています、パターンレスのエロンガータリクガメが入荷しました。
格好良いのか可愛いのか、私たちにとってリクガメという生き物はどちらかと言えば後者のイメージが強く、
それは表情や仕草などがそう見せるのでしょう。
しかし目元をよく見ると多くの種類が意外と厳しい目付きをしていることに気が付き、
その鋭い眼差しを浴びると今までの印象が少し変わってしまうかもしれません。
本種のようにウルウルとした瞳を持つタイプというのは、森林など余程湿潤な環境で暮らしているものに限られ、
そこには目をパッチリと開いていてもすぐに乾いたりしないという理由があるのではないかと考えられます。
したがって、キャラクターチックな表情を持つこんなリクガメを飼育したいと願うならば、
必然的に対象とすべき種が絞られてくるのです。
似たようなものは決して多くありませんが、
このエロンガータは同系統の中で比較しても純粋に愛らしいと言える逸材ではないでしょうか。
対抗馬としてパッと思い付くのはアカアシガメ、目だけを見れば同じような雰囲気を漂わせてはいるものの、
あの配色は毒々しさを嫌う人にはどうしても受け入れ難いとなってしまい、
それならばセオレガメの場合はどうかと言うと、やはり同じ目をしていてもこちらは鳥顔、
あまりにもシャープ過ぎる顔付きが可愛らしさを減少させてしまうという声もしばしば耳にします。
そこで登場するのがこのエロン、こんもりと盛り上がった丸っこい体型は極めて理想的で、
かつ頭部もふっくらとしているため自ずと目鼻立ちにも柔和な雰囲気があり、
そのまとまり具合はストレートに可愛気だけを狙っているとしか思えません。
そして何よりも大きな黒目を強調させる模様の入らない頭部が大切な要素ですが、
それが全身に渡って統一されるとまさにこれが大当たり、
余計なものを排除することで純然たるキュートなリクガメが完成する結果となりました。
今回やって来たのは現時点で限りなくペアに近い二匹のパターンレス。
この手のタイプは柄と一緒に色味も抜けさせてしまうことがありますが、
オスっぽい個体は
頭や四肢がジューシーなオレンジに、
反対にメスっぽい個体は
すっきりとしたレモンイエローにそれぞれべったりと染まっており、
色の濃さも充実している辺りにクオリティの高さが感じられます。
また大きさもあまり見かけない手頃な10cmクラスの安心サイズで、小さなお陰で傷やスレも殆どなく表面は艶々。
餌は面白がって色々試すと与えた側から何でも平らげるほど貪欲で、
最終的にはMazuriリクガメフードも普通に食べてくれました。
見た目と同様に中身もきちんと仕上がりコンディションは良好、初めての方にもお勧めできる素晴らしい上物です。
ムービー | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ
Indotesutudo elongata |




|
|
||||||||
| 極美!! 色彩の個体差が幅広いエロンガータですが、今回は中でも黒斑の少ない透き通ったタイプが 入荷しました。インドリクガメ属の中でも黒斑があるタイプ~殆ど黄色のタイプまで様々です。 実は今、タートルプディングに次ぐオリジナルフード、「トータスプディング」を開発中なのですが、 青臭さが食欲をそそるのでしょうか、早速この個体には効果アリです。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (M) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 御淑やかな雰囲気が持ち味の本種にしてはえらく攻撃的なデザインが印象深いパンサーエロン! 元はワイルドのはずが見た目も中身も随分と健康的な選別個体です、 エロンガータリクガメが入荷しました。 初めから決め付けるようでカメに対しては申し訳無いのですが、 正直ペットとして飼育されているリクガメの中では脇役の部類に入るこのエロンは、 何も知らない方がさあリクガメを飼おうと意気込んだ時にとても候補に挙がるとは思えないため、 紹介するこちらとしては却って気合いが入るそんな種類です。 飼い易い部類に選ばれることなどどうしても考え難いですし、 その怪しげな名前はそれほど知れ渡っておらず飼育例および情報量にも恵まれていないため、 誰にでもむやみにお勧めできるタイプのカメでないことは確かでしょう。 しかしマイナーポジションにいるからこそ見た目だけに惹かれて飼ってみたくなるのも事実で、 実の所は初期状態さえ良ければ過度に神経質になる場面もそう多くは無いため、 私共はとにかくコンディションをキープして来たるべき日に備えていると言う訳なのです。 今回やって来たのは健康状態の好ましさに加え、 ただ単に柄の面白さが気に入ったがために入荷することとなったやや店頭キープの一匹。 大抵エロンの選定基準と言えば模様がまるで消えかかったパターンレスか、 その反対に黒多めのブラック系統を連れて来るのが鉄則なのですが、 この個体はリング状の黒斑が花火のように激しく飛び散った様が美しく、 こうしたデザイン性に富んだタイプはその場限りの出会い一本で勝負しなければならないため、 毎回お決まりのように手に入れることが難しいのです。 マニアックなだけに自分だけのお気に入りを見つけ出したいとお考えの方、 中型種であるが故に数を多く保有するのが難しいと感じている方、 最近では取引額もじわじわ高騰し我々も思うように仕入れができなくなっているため、 気に入った個体は確実にゲットして頂きたいと願うばかりです。 ひとまず葉野菜からスタートしてMazuriリクガメフードにも餌付いたため、 初めてリクガメを飼う方でも大丈夫なラインまで仕上げましたが、 やはり通好みの風合いが捨て切れないエロンのことが好きで堪りません。 もし初めの内は心配なようでしたら、 頻繁に温浴をしてよく水を飲ませてあげればまず間違い無いと思います。 性別は不明としましたが恐らくメスではないかと。 陰気臭い見た目とは裏腹に立ち上がるとケージ内を爆走するほど活発なので、 是非ともこの醍醐味を骨の髄まで味わってみて下さい。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (パターンレス) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| まるで別種のような透明感溢れる琥珀色の甲を背負った純度の高いハイクオリティパターンレス! 店頭にて半年以上のトリートメント期間を経て実現した不安要素のない極上ワイルド、 エロンガータリクガメが入荷しました。 インドリクガメ属とはあまり聞きなれない響きかもしれませんが、 確かにペットとしてまともに流通が成り立っているのは本種ぐらいのもので、 セレベスは何かの拍子にふと姿を見かけるのみで安定的な輸入は全く見込めず、 トラバンコアに至っては日本に来たことがあるかどうかさえも怪しいという、 少数派に追いやられても仕方のない気がしてしまう実にか弱い立場のグループです。 構成種が少ない上に、あとの二種については分布がそれぞれインドネシアはスラウェシ島と、 もう一方はインド亜大陸の先端と非常に限られているため、 ペットとして普及させようと言う方に無理があるのでしょう。 しかしながらその間に挟まれたエロンガータについては、 中国南部に位置する国々をほぼ全て網羅する広大な棲息域と、 それに伴う豊富なカラーバリエーションが人々を楽しませる要素を十分に備えていますので、 たった一種でもひとつの属を牽引していく力は十分にあると思います。 セレベスは黒、トラバンコアは白というイメージが強く根付いていますが、 エロンはその隙間を埋めるように色彩の幅がかなり大きいので、 選ぶ人のセンスで好まれる雰囲気ががらりと変わるのもまた面白いです。 今回やって来たのは一言で表すと上品、 全身がクリーミーな乳白色に包まれ黒い染みは限りなく消失し、 他のリクガメにはそうそう真似できない神々しいオーラが放たれる人気のタイプ。 この系統では黒斑の少なさが最も分かりやすい特徴ではあるのですが、 それ以上に注目して頂きたいのがベースカラーの品質です。 上から覆い被さる模様が無くなるということはつまり、 自動的に地色一本での勝負を強いられることになりますから、 その部分が明るいのか暗いのかでこちらが受ける印象も随分と変わってしまいます。 この個体の場合は単に明るく見えるだけではなく、 ついつい手に取って裏表をひっくり返してはまじまじと観察したくなるような、 大変に奥ゆかしく幻想的な佇まいがエロンガータの持つ素質を更なる高みへと押し上げているのです。 入荷当初はバナナのみを頑なに食べていたのが嘘のように、 現在では葉野菜はもちろんMazuriリクガメフードもかなりの量を平らげてしまうほどになり、 手に取って持ち上げると文鎮のような重みを感じられるように仕上がっています。 撮影前の温浴でも大量の糞をもりもりと排泄したのですが、 水に溶けてしまったのとさすがに糞は糞ですから写真を撮ることは控えました。 輸入されたての個体では絶対に成しえない抜群のコンディションでお届けします。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (Pr?) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| ベビーは可愛く、大きくなると上品な美しいリクガメです。 国内飼い込み個体で安心、エロンガータリクガメが入荷しました。 多湿系のリクガメには大きくて艶やかな瞳を持つ種類がたくさんいますが、 その中でもエロンガータの可愛らしさは大差をつけてのトップではないでしょうか。 見つめていると今にも泣き出しそうなか弱い容姿に心を奪われた方も多いと思います。 しかしそれだけではなくこのカメは屈指の美肌を持ち、 透き通るような白い肌はアジアンビューティーの名誉を独り占めにしてしまいそうです。 更に最近では本種のベビーも国内で殖やされ始めているようで、 きっと飼い易いでしょうし何よりピカピカですから将来的には定番の人気種に名を連ねることでしょう。 色味には個体差がありますが今回入荷した2匹は背甲の黒斑が小さく少なくてよりエレガントなイメージ。 実はこの2匹、肛甲板の形状から高い確率でペアだと思われますので今回は2匹セットでの販売です。 ワイルドのため少々甲羅の痛みも見られますが、 今まで飼い込まれて出てきた新しい成長線も確認できますし お腹を持ち上げてスタスタ歩いていますので、 繁殖目指してこの調子で育てて下さい。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (オレンジ) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 背中いっぱいに夕日を浴びたような眩い発色がワイルドとは思えぬ輝きを放つ極上オレンジ! 来日して半年以上が過ぎメキメキと伸び行く成長線の力強さは何よりの安心感、 エロンガータリクガメが入荷しました。 同じカメでもウミガメの仲間が他とはまるで異なった存在感を示しているように、 リクガメもまたホビーの世界ではいくらか特別視されているのではないかと思います。 水棲ガメ、いわゆるミズガメとは明確にジャンルを分かち、 そこには独特の世界観が広がっているように感じられますが、 実の所はペットとして需要の高い人気種ばかりが目立っているだけに過ぎず、 中には日陰でひっそりと暮らすものも少なからず存在しています。 飼育されるからにはやはり家族的な付き合いで可愛がられることの多いリクガメには、 ある種の清潔感とでも言いましょうか、野生で捕獲された感丸出しの野暮ったさはあまり好まれず、 キラキラピカピカとしていた方が万人に受けが良いのでしょう。 本種のようにあくまでも自然体が持ち味で幾分怪しげな雰囲気すら漂っていると、 どうしても煌びやかさに欠けるのかあまり注目されず、 悲しいかなマニア好みの種類として認知されてしまいがちなのかもしれません。 少しでもマイナーになると飼うのが難しいのではと誤解されることも多いのですが、 ことエロンに関しては初期状態さえ見極めればかなり強健な部類に属し、 強烈な紫外線を必要とせずアジア出身なだけあり温度耐性にも優れていて、 陰気臭そうな見た目とは裏腹に至って明るい性格の持ち主ですから、 今後はもっと見直され愛されるべきリクガメだと思います。 今回やって来たのは色味の良さで従来の固定概念を覆す、 野生にこれほど美しいリクガメが歩いていることを想像するだけで興奮させられる素晴らしきセレクト個体。 外観をパッと見た時の第一印象はオレンジ色、 そして新たに形成されていく甲板は一歩間違えればサーモンピンクに見えるほど、 透明感溢れる鮮やかなカラーリングが目立ちます。 元がワイルドであるが故にコンディションへの心配事がどうしても付き纏う中、 国内へ輸入された直後から今日までスムーズかつ着実に成長を続けていることで、 余計な不安は全て消え去っていると言っても過言ではありません。 時にチワワのような優しい眼差しのこんな顔立ちですが内面は明朗快活、 大股開きでケージ内を走り回り餌と言う餌をお行儀悪く爆食しています。 何度でも申し上げますが黄色でも茶色でも無くまさかのオレンジ色、 この感動と喜びを分かち合いましょう。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (国内CB) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 深く温かく鈍い輝きを放つこの色合いこそまさにゴールデン! 人知れず埋もれていた金塊を発掘したようなとても清々しい心持ちです、 国内CB飼い込みのエロンガータリクガメが入荷しました。 リクガメという生き物は日本やその周辺には分布していないため、 我々にとってはあまり馴染みがなくエキゾチックなとして感じられますが、 実は世界中の様々な国や地域にそれぞれ形を変えて繁栄しています。 ペットとしての需要は高く国内にも多くの種類が輸入されてきた経緯がありますが、 中にはみんな大好きな分かりやすい特徴を持つものもいれば、 見た目やその生態にややクセを持つ通好みなものまでいるでしょう。 アフリカにはケヅメやヒョウモン、ヨーロッパにはチチュウカイリクガメなどお馴染みの定番種が、 そしてアジアにはホシガメという絶対的な人気種が待ち構えているのですが、 同じくインドやその付近にはその名もインドリクガメ属というグループが棲息しています。 リクガメ全般を取り巻く風潮として、多湿系とカテゴライズされる種類は広く支持を集め難い傾向にあるのですが、 このインドリクガメの仲間は確かに一般的ではないものの、 上品かつ可愛らしい独特の風貌から長年人気を保ち続けてきました。 しかしアジアのカメの常として、野生個体が状態の整わないまま流通してしまうという逆風にも悩まされ、 惜しくもポピュラー種としての地位を確立し切れないままの状況が続いています。 そして近頃では、いつか訪れると心配され続けていた流通量の絶対的な減少を肌で感じる度合いが強くなり、 せっかくの魅力的なリクガメが世に広まることなく消えてしまう、 少々大袈裟ではありますがそんな心配もされるようになってきたように思います。 それでも苦しい現実を甘んじて受け入れる訳にはいかず国内繁殖成功という嬉しいニュースも聞かれますが、 今回はそんなベビーが見事に成長した素晴らしい一匹がやって来ました。 すれ違う人々がこぞって振り返る、この個体にはそれほど周りを視線を惹き付ける力があるでしょう。 否応無しにクオリティの高さが伝わってきてしまうのは、全体的な黄色味の強さが何よりの原因です。 すっきりと色抜けした頭部はレモンイエローに発光し、 甲羅に至っては延棒に代表される金そのものを連想させる実に贅沢な色使いが見られるなど、 頭ひとつ抜きん出た美しさが辺り一面に冴え渡っています。 エロンガータという種の範囲内でも黒く塗られる面積には個体差があり、 その幅の中で単純に黒が少なければ派手に見えると考えられがちですが、 実際にはその割合よりもむしろ地色の質の高さが見栄えに直結してくる、 この個体に出会えたお陰でそんな事実を痛感することができました。 育った過程で多少歪んだ部分も見られますが、 中身のしっかり詰まったCBなので飼育に関しての不安はなくコンディション抜群です。 素直に美貌を愛でることだけに集中できるこの逸品をお楽しみ下さい。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (パターンレス・♂) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 99.9%パターンレス&スケルトンが織り成す異次元の美しさ! かの伝説の稀少種トラバンコアを思わせる驚異の姿です、 エロンガータリクガメ・オスが入荷しました。 近頃、リクガメの世界では大所帯であったGeochelone、その名もリクガメ属の大々的な再分類が検討され、 ケヅメやホシガメ、アカアシガメなど今や無くてはならない代表種たちを取り巻く環境が大きく変わろうとしています。 本種を含むインドリクガメ属も昔は同じリクガメ属に統合されていたのですが、 比較的早く分化したため構成種はたったの3種という小さなグループながらも、 独特のキャラクターがきちんと認知された上で一ペットトータスとして広く親しまれているように思います。 全体的に似通った外観を持つこれらの仲間は、最も流通量が多いエロンガータを基準にして、 黒斑の面積が比較的広いものがセレベス、 反対に黒が少ないか殆ど表れないものがトラバンコアとして認知されていますが、 現在では両種とも輸入の機会を失ってしまったようで全く見かけなくなりました。 前者は過去に国内でも販売されていたためそれなりの知名度があるものの、 後者の場合はまともな写真を探し出すだけでも一苦労ですから、 もはや存在自体をかき消されてしまったと言っても過言ではありません。 しかし今回、そんな空想上の生き物とニアイコールなトラバンコアとこれまたニアイコールな、 高品質極まりない最高のエロンガータがやって来ました。 この個体を手にしてまず初めに項甲板の有無をチェック、 これでどこにも見つからなければ大事件になる所でしたが、 そうでなくともこの個体が素晴らしいことには変わりありません。 ごく僅かな黒点はご愛嬌、 普通に見ればほぼパーフェクトに模様が消失したその様は色彩変異という訳でも無さそうですが、 逆に個体差の範疇だからこそ実現するのが非常に困難なクオリティと言えるでしょう。 漂白の度合いは甚だしく、表面の色味を消すどころか甲羅内面の背骨までをも浮かび上がらせてしまい、 前肢の色合いも何だかメタリック調で不気味にすら感じられるほど。 そして最後に会心の一撃となるのは、 左目の周りに小さいながらも確かに表れた赤い斑点です。 これぞまさしく白くなり過ぎて赤くなるというトラバンコアの教えを受け継いだ究極の特徴だと騒ぎたい所なのですが、 単なる擦れではないか入念に確認したものの現状では不確定なため、 本当に些細な部分なので話半分に面白がる程度にして下さい。 Mazuriリクガメフードにも餌付き準備完了、オンリーワン! | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (♂) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 別人が乗り移ったようなシャキシャキエロン! おっとりした雰囲気とのギャップがまた良いです、 エロンガータリクガメ・オスが入荷しました。 瞳ウルウル系のリクガメの中で圧倒的な人気を誇る本種。 恐らくその理由はただ黒目がキュートなだけでなく、 顔全体におしろいを塗りたくった様なその姿が大変上品な印象を与えるからでしょう。 しかしその美しい容貌も良いことばかりではないようで、 初見ではどうしてもガラスのハートを持つ超繊細なカメというイメージを抱きかねず、 実際過去にアジア特有の飼い辛さを経験された方も少なくないと思います。 初期状態に左右されてしまう感も否めませんが、 それでも近頃では国内CB化もじわじわ進んでいるようで愛好家の底力を思い知らされます。 そして今回やってきたこの個体、 詳しいルーツは分からないものの甲羅の育ち具合や痛みの無さから見るに小さなサイズから育てられたものでしょう。 その証かとにかくコンディションが良く、 今にも泣き出しそうな顔をしながらケージ前面でこちらに向かってゴツゴツとやられてもどうしたものか困ってしまいますが、 新しい環境にも怯えず堂々としてくれているのは何より。 甲羅の色はエロンの個体差の幅を考えてもかなり暗色寄りですが、 こちらの方が頭部のクリーム色が際立ち品の良さが一層味わえるかもしれません。 意外と大きくなることからこれまで躊躇されてきた方、 オスはメスに比べ小型なので一頭飼いで楽しむにはお勧めです。 リクガメとしては少々変り種で状態も良いので暫く店に置いていても良いかなと思ってしまいますが、 お探しの方はお早めにお声掛け下さい。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (♂) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 元々野生に暮らしていたとは俄かに信じ難い状態の良さと成長線の伸びに脱帽の長期飼い込み個体! ようやく20センチを超え男を上げてきている交尾がしたくて仕方なさそうなヤングマン、 エロンガータリクガメ・オスが入荷しました。 この個体に纏わるエピソードは色々とあるのですが、 まず初めに申し上げておきたいのは何を隠そう本当に入荷したのはおよそ一年前であり、 訳あって展示もしないままワンシーズン寝かしっ放しにしていたのでした。 やって来た当初は指を入れれば何とか手の平に乗るぐらいの中途半端なサイズで、 正直売り先もなかなか見つからないだろうと半ば諦めかけていたところ、 とあるきっかけから暫く育ててみようという話になったのです。 実は当店で今まさに準備を進めている繁殖施設があり、 用意したのは良いものの果たしてそこで四季を通じてカメを飼育できるのか否か、 その実験を行う必要があったため在庫からいくらかピックアップし移住させる計画が持ち上がりました。 少し可哀相な気もしますが、 エロンガータは上手に飼えば屋外でも冬を越せるかもしれないポテンシャルを秘めていますから、 昨年の冬はほぼ室内無加温状態にて管理し、 春になって餌をガツガツと食べるようになったため再び店頭に戻って来たという訳。 無事越冬に成功したのが嬉しかったのはもちろんですが、 意外なサプライズとして夏場に食べきれない量の野菜や野草に常時囲まれていたせいか、 尋常でないスピードで見違えるように成長してしまったことにもまた驚きました。 特に腹甲のセンターを見ると分かり易いかと思いますが、 まるで別人へと生まれ変わったかのようにフレッシュな成長線は喜び以外の何物でもなく、 四肢の筋肉も相当発達しているようでその健康状態の良さは折り紙付き。 自分の頭と比べて二、三個分の糞であれば一度に軽くひねり出してくれる辺りも気分爽快、 リクガメがこんなに飼い易い生き物だったのかと感心してしまうこと請け合いです。 コンディションの良さとは対照的な妙に顔色の悪いダークなカラーリングも非常にクールで、 分布域の広い本種は様々な地域変異が知られているだけに勉強し集め始めるとキリがありません。 今の所餌を選り好みすることもなくMazuriリクガメフードを主に給餌しており、 細長い直方体の甲羅から生えるすらっと長い足がとてもセクシーです。 大半の方にとってはどうでも良いことと存じますが、 上から見ると項甲板が消失しているなんちゃってトラバンコア的な面白味も。 気候も良好ですからいきなり外へ出してしまってもそろそろ大丈夫でしょう、 毎日体に水をかけたくなる活発さが売りの最強のエロンガータをお届けします。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (ミャンマー産・♂) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 黒も黄色も体中にとことん詰め込んだ欲張りカラーの稀少なミャンマー個体群! ここまで極端に格好良さを追求した例は本種のみならず他のリクガメにも殆ど見られません、 エロンガータリクガメ・オスが入荷しました。 ここ最近でペットトータスの世界に新風を巻き起こし、 あわよくば掻き乱してやろうと秘かに企んでいると思われるのがインドリクガメ属の代表種エロンガータです。 名前だけ聞くと男子小学生がはしゃぎそうな一風変わったネーミングだと思われるかもしれませんが、 その本当の意味は細長いという意味を持つ英単語elongateと同義で、 幼体時には丸みを帯びていた甲羅の形が次第に細長くなっていくこのカメの姿形をそのまま表しています。 分布域はインドから中国南部までと幅広く、 そうした広範囲に棲息することから地域性を伴った豊富なバリエーションが知られており、 それは色彩や斑紋の程度に限らず頭部の形状や全身のフォルムにまで関わってくる様子。 日本には昔から輸入されていましたが、 現地の住民らにとっては食用にしたりペット用にもしたりといずれにしても身近な存在であることに変わりはなく、 せっかく海を挟んで近隣の国々に暮らしているのですから今後は何とか大衆性の獲得と地位向上を目指していきたい所です。 先に述べた形質にバラつきがあることについて、 エロン自体を見慣れている我々にとっては包括された中の個体差として容易に識別することが可能ですが、 原産国の一般人にとってはどうやら全く別のカメにさえ見えてしまうらしく、 それ故に多くのカラータイプについてそれぞれに全く異なった認識を有しています。 今回やって来たミャンマーに産するグループは日本語に直すとビルマリクガメという意味合いで呼ばれているそうで、 そこにはエロンガータという文字が一度たりとも登場しませんが、 反対に現地人にとっては細かな違いを捉えては好き勝手にタイプ分けを施しているがために、 土地の事情に精通している分アプローチは異なれどもしかするとマニアにも負けない程の知識や感覚を身に付けているのかもしれません。 背甲の甲板ごとに分かれた黒い部分の面積はとても広く、 それもまだら模様に乱れることなくほぼブロック状に塗り分けられているのはお見事。 全体的にトーンの大人しいブラック系統かと思いきや、 にゅっと伸びた頭部のイエローも今まであまり見たことがないような深みを持ち、 まさしく絵の具セットのレモン色に程近いこの色に只者ではないオーラを感じました。 長期飼い込みのため餌食いと動きは完璧で、葉野菜からMazuriリクガメフードまで選り好みなく餌付いており、 外で散歩させれば長過ぎる四肢を巧みに使ってのエネルギッシュな一面を見ることも決して難しくありません。 さすがに野性個体なのでフォルムは抜群に完璧、 ボコ付きのボの字も知らぬ文句なしの仕上がり、 当たり前ですがこれが正解と言わんばかりのこの上ない産物です。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (ブラック・♂) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 周囲を凍り付かせるほどの重厚な威圧感が黒味の強いボディより放たれる逆襲のブラックエロン! 決してメジャーな種類ではありませんがそこがまた味のひとつなのかもしれない往年の銘種、 エロンガータリクガメ・オスが入荷しました。 その奇妙な名前はお約束である学名をカタカナ読みしたものですが、 原義としてはおおよそ細長いというような意味合いが適切でしょうか。 その部分はもちろんのこと、 全体的にいわゆるリクガメらしくない雰囲気を醸し出しているのが最大の特徴で、 時にヤマガメやハコガメなどの水棲ガメチックだと形容されることもあるように、 可愛らしさよりもある種の妖しさが先行してしまう辺りに良くも悪くもエロンらしさが窺えます。 多くのリクガメファンが求めている要素とは少々異なる風合いは、 やはり大衆向けとは言い難く多量の票を集めるには至らないと思いますが、 そんな意外性も含めて魅力のひとつだと捉えて頂き、 他者が気にも留めなかった楽しみに気が付ければ幸いと言えるでしょう。 顔立ちこそ柔和で愛らしいもののよく観察すると瞳の奥には鋭さが見え隠れし、 四肢のトルクは並のリクガメでは考えられないほど力強く、 それによって生み出される悪路走破性は森の中に棲んでいることを示唆していて、 地面を歩き回る姿には微笑ましさよりもむしろ逞しさが描き出されています。 体内の構造もどちらかと言えば単純なのでしょうか、 それほど凝った環境設備でなくとも健康状態が維持され易く、 俗にペット向きとも表現できる扱い易さはもはや長所でしかありません。 誰もが選ぶメジャーな存在になってほしいとは思いませんが、 こんな素敵なリクガメがこの世に暮らしていることを少しでも多くの人に知って頂ければ嬉しいです。 今回やって来たのは丸焦げの背中が最高のアイデンティティとして視界に飛び込む、 幼き頃より選ばれし個体として今日まで育てられていたブラックタイプのオス。 要するに各甲板の大部分が暗色で占められている訳ですが、 それが大きくなるに連れて程度を増し更なるブラックへと仕立てられ、 甲羅のみならず四肢や肌までもがモノトーン調に、 それでいて頭部全体は柔らかなクリームイエローというギャップが堪りません。 かつて野生個体の輸入が盛んであった時代とは違い、 昨今ではそのバラエティ豊かな個体差を愛でることも叶わなくなってきましたから、 こういった稀有な出物をより一層大切にしたいものです。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (ハイイエロー・♀) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| しっとりと焼き上げたシフォンケーキのように柔らかな発色が美しいゴールデンタイプ! 未だ貪欲に成長を続ける産卵までカウントダウンと言った具合の立派な種親候補、 エロンガータリクガメ・メスが入荷しました。 比較的手軽に入手できるもののあまり状態が好ましくなかったからなのか、 一昔前はいまいち人気の出辛かったアジア系のリクガメ。 ギリシャやヘルマン、そしてケヅメなど今時の定番種が軒並み高価であった頃、 やはり花形のポジションはそちら側に取られてしまいがちで、 どちらかと言えばハコガメなどと共に代役のような扱いを受けることの方が多かったのでしょう。 いわゆる森のカメにカテゴライズされることもあって世間が思うリクガメらしさに乏しく、 酷い言い方をすれば何だか訳の分からない存在とさえ思われていたのかもしれません。 それが最近では輸入量の減少も手伝ってか、 広範囲に棲息することに由来する個体差の豊富なバリエーションに注目が集まり、 自分の気に入った色や形のエロンを選ぼうとする動きが強まり始めています。 今回やって来たのは甲羅の模様こそスタンダードな雰囲気を醸しながらも、 その奥に光る地色の明るさや頭部全体の脱色具合などに過激さが見え隠れする非常に魅力的な飼い込み個体。 まず一目見て印象に残るのはねっとりとした飴色に照り輝くボディの鮮やかなこと、 じっと見つめていると体の奥底まで露わになってしまいそうな透明感は只ならぬオーラを感じさせ、 適度にまぶされた各甲板の黒斑がエロンガータらしさを取り戻してくれます。 もうひとつ注目したいのが顔面の色彩、 ほぼ白色に近いブライトなレモンイエローは一度脳裏に焼き付いたら離れないインパクトがあり、 目元や鼻先などにやや赤味を生じさせるほど。 多くのパターンが知られる中でこの組み合わせはかなり高評価を得られ易く、 原種の持ち味を生かしながら所々の品質向上に努めた点を褒め称えたいと思います。 およそ手の平サイズからの育てられたが故に成長のスピードも極めて良好で、 20センチをオーバーした現在でもしぶとく大きくなり続けようとしている辺りは流石です。 産卵経験こそありませんがそれも年齢が若いことの証、 甲羅の摩耗したフルアダルトも格好良いですがより実戦向きなのはこちらでしょう。 全体的にオスが多い傾向にある本種は同居飼育で揉めることもあり、 反対に平和主義な個体の多いメスが放出されるケースは決して多くありません。 ケージの隅で壁に向かって突進している精力を持て余したオスをお持ちの方、 この機会に相方を招き入れては如何でしょうか。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (♂・♀) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| 頭部全体がしっかりと黄色味を帯び甲羅も明るめの色調でまとめられたセレクトペア! 大地を引き裂かんばかりにバリッと現れた新しい成長線が良好な健康状態を物語る、 エロンガータリクガメ・ペアが入荷しました。 カメはカメでも水棲ガメとリクガメでは体の構造からキャラクター性まで丸っきり異なる別の生き物で、 野生での暮らしぶりはもちろんペットにした場合でも何もかもが異質であり、 単純に泳ぐから、歩くからとパッと見の先入観だけで選べるものでは無いと思います。 一般的に飼い易いとされる種類は前者に多く、 結局のところ環境に対して要求するものの少なさがそうさせるのですが、 反対に後者の場合はチェックポイントが多くなってしまうため、 用意する物や知っておかなければならない知識が増えていくと言う仕組みになっています。 それでも与えられた環境に対する適応力の高さに甘え、 ビギナーでも飼育できるとされる有名な人気種はいくらか存在しますが、 ではあまり名前を聞かないマイナー種が難しいのかと言えば決してそうとは限りません。 個人的にこのエロンガータは最も飼育に向いたリクガメのひとつではないかと感じていて、 そこには紫外線要求量がさほど多くは無かったり、 餌の栄養バランスに対してあまりシビアでは無かったり、 多湿系と言う先入観をぶち壊してくれるほどそこまで乾燥に弱くも無かったり、 お淑やかな表情とは裏腹に結構アクティブで動きの面白さがあったり、 箇条書きにすればいくらでも出てくるほど数々の魅力が詰まっています。 お隣アジア諸国の出身なので時折野生個体が出回る程度ですが、 そこに緊張感を覚えずとも許されてしまう現状が何とも歯痒く、 却って急に姿を見なくなると結構後悔させられるタイプのカメのはずですから、 普通に入手できる内にきちんと囲っておく必要性を感じて止みません。 今回ご紹介するのはバックヤードにて数か月間ひっそりと育てていた、 この上なくコンディションの整った将来楽しみなヤングアダルト。 甲羅の色合いなどが気に入ってキープしておいたペアですが、 その良好な生育状態は写真を見て頂ければお分かりの通りで、 特に腹甲の成長線は見事なまでにヘルシーさを主張し、 ひとたび歩き出せばリフトアップされたSUVの如く、 体全体を持ち上げ長い四肢をいっぱいに伸ばしてくれます。 バラでも良いのですがせっかくなので雌雄揃っての導入をご検討下さい、 二匹とも同じケージ内で仲良く暮らしています。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (Pr) Indotesutudo elongata |



|
|
||||||||
| サブアダルトサイズのPrです。この種類は、♂♀にかかわらず多くの個体が気性が荒く 1頭飼いが好まれますが、相性が良い様で仲良く暮らしています。♂の入荷量は少なく、 Prは貴重です。最大甲長が36cm程になりますが、日本でも繁殖例が有るようです。 我こそはと思われる方、チャレンジして下さい。 | ||||||||||
|
エロンガータリクガメ (アダルト・Pr) Indotesutudo elongata |





|
|
||||||||
| こんなに素晴らしい巨体がまだ国内にいたとは正直感動です。 輸入後長期飼い込みのエロンガータリクガメ・ペアが入荷しました。 どちらも20cmオーバーのいかにもワイルドらしい大柄の個体で、 近頃では殆ど見る事ができない野性味を残したペア。規制が入ってからすっかり流通量は減ってしまい、 許可も降りないらしく新たなワイルドが入ってくる機会は皆無に等しいのではないでしょうか。 湿潤系リクガメの野生個体は導入に気を使うイメージもあるかもしれませんが、 今回の様に既にトリートメントを終え日本での暮らしが長い個体であればそれほど気にする事はないでしょう。 実際チンゲンサイ一把を丸ごと与えても端から順にムシャムシャやってます。 オスは琥珀色を主体とした甲羅がとても上品で 頭部も綺麗に色抜けし典型的かつ理想的な色彩。 反対にメスは少し変わったブラックを基調とした重厚感のある雰囲気で、 とても甲高なため収縮色であるはずなのに十分な大きさが伝わってきます。 近頃では雑誌などでも国内繁殖のデータなどが掲載される様になり、 また新しく入ってくることもありませんから是非このペアでも狙っていきたい所です。 本種のベビーは他のリクガメと並べても格別に可愛らしく、 優美な姿で生まれてきますから今から待ち遠しいです。 | ||||||||||
|
セレベスリクガメ (S) Indotestudo forstenii |





|
|
||||||||
| 現地からの来訪者にしては不思議と元気過ぎる飛び跳ねるような走りっぷりに気合い十分! 漠然とした不安からこれまで食指の動かなかった方にとってまたと無い千載一遇の大チャンス、 セレベスリクガメが入荷しました。 知る人ぞ知ると言えば少し大袈裟かもしれませんが、 ペットとしてはマイナーな部類に入るエロンガータの親戚に当たる、 これまたマイナーなインドネシアはスラウェシ島に産する稀少種セレベス。 そこまで名が知れていないのもある意味仕方の無いことと言えるでしょう、 あくまでも広大な分布域を誇るエロンガータがひとりで張り切り過ぎているだけであって、 同じ属に含まれる本種やトラバンコアはごくごく狭い地域にしか暮らすことを許されず、 前者はセレベス島とも呼ばれる島内の一部のエリアにしか現存していないとされていますし、 後者に至ってはインド亜大陸の先っちょへ追いやられるように何とか生き続けている有様で、 とにかくこうしてペットトレード上で出会えただけでも大変有難いことなのです。 形質的な違いは背甲の項甲板を持たないか矢尻状に小さくなっている点、 腹甲の肩甲板のシームと胸甲板のシームの比率が異なる点、 成体ではより顕著ですがエロンに比べてやや鼻の短い顔立ちになり、 各甲板の黒斑が大柄になり易いなどどれも非常にマニアックなのですが、 やはりこの仲間がお好きな方にとっては堪らなく魅力的に写る佇まいだと思います。 今回やって来たのは地色のイエローの鮮やかさと黒斑とのコントラストに拘ってセレクトしたはずが、 そんな売り文句が必要無くなるほど状態の良さだけで十分勝負できるこんな個体。 間違って国内飼い込み個体を仕入れてしまったのではと疑いたくなるほど妙にはつらつとしていて、 入荷直後ケージに入れるとまるで動物園のトラの如く右に左に地面を掘り返しながら歩き続け、 少し体を休ませた翌日に餌を放り込んだ途端、 待ってましたと言わんばかりに自ら近寄って来て即行で食べ始めたのには流石に驚きました。 従来のセレベス像と言えば根拠の無い何となくの心配事が付き物で、 何もしていないのに初めからヘトヘトになっているイメージが強かったのですが、 この個体は中にCBのヘルマンでも入っているのではと思えるほどの躍動感で、 今の所かなり上手に育てられそうな予感しかしないのは本当に凄いことです。 この先を考えれば毎年コンスタントに手に入るような種類ではありませんので、 ここで押さえておくのはシンプルに賢い選択だと思います。 | ||||||||||
|
セレベスリクガメ (フルアダルト・♀) Indotestudo forstenii |





|
|
||||||||
| 遡ることおよそ十年前、インドネシアはスラウェシ島よりはるばる漂着した紛れもなく真のセレベス! 色合いや模様などと言ったあやふやな特徴に惑わされず典型的で間違いの無い個体を選びましょう、 セレベスリクガメ・メスが入荷しました。 黄色地に散らばる黒い斑紋、透き通るような白き素肌に大きくてつぶらな瞳、 この個性的な出で立ちを見れば誰もがインドリクガメの名を叫ぶことでしょう。 知名度はそこそこながら以外にもペットとして流通してきた歴史は古く、 良くも悪くもアジアに産するカメ類の流通が盛んであった時代にはしばしば見かける種類でした。 何を以ってそう定めるのかは分かりませんが、 いわゆる所のリクガメらしさは薄くその風貌や仕草などは明らかに森のカメのそれであり、 どちらかと言えばハコガメやヤマガメと呼ばれるものに近い雰囲気を醸しています。 一見すると目元のキュートな顔立ちは女性受けしそうなものですが、 歴としたリクガメであるにもかかわらず不思議とミズガメ特有の妖しさが漂い、 それ故にある種の男性的な楽しみ方がなされるケースが殆どだと思います。 それは例えば甲羅の色彩などに表れる個体差のバリエーションであったり、 明確な分類情報に基づく正しい種の同定を重んじるなど何処かアカデミックな感覚で、 訳の分からない不可解な存在を排除してしまうような傾向すらあります。 ここ数年で本物のセレベスとして納得できる個体に出会う機会が相当減っていますが、 今回は国内に十年近く眠っていた長期飼い込みの掘り出し物をご紹介します。 セレベスっぽいエロンガータとの明らかな違いがお分かり頂けるでしょうか、 雌雄問わず甲羅はフラットかつシャープなシルエットで、 鼻先の突出が弱く正面から見るとまるで人の顔のようにも見えてしまう、 ただ単に黒色の面積が広いと言うだけでは説明し切れない独特の空気が堪りません。 エロンガータを見る度にひっくり返して甲板をチェックしていた昨日までの苦労は何だったのでしょう、 まず真っ先に目をやるのは項甲板、矢尻状の細長い一枚がある場合も認められているそうですが、 マニアの観点からすれば無い方が嬉しいに決まっていますし、 最も重要な腹甲の間肩甲板と間胸甲板のシーム長の比率もパーフェクト。 忘れた頃に輸入されるワイルドは体重と状態を落としていることが大半ですが、 この個体は手の平サイズから飼育下で成長してこの大きさですから、 底無しの食欲にしっかりとした糞は天に向かってそびえ立つなど最早言うことなし。 エロンと同様に本種もオスの方が多いらしく、 きっちり産卵まで視野に入れることのできる成熟個体の出物など今後も期待できません。 もちろん単独飼育でもその最良な健康状態と稀少性から満足度は実に高し、 雨上がりに気分が高揚し活性が上がる様などもいとをかしです。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (S) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| 木彫りのような質感が醸す素朴さとウルウル黒目のキュートな表情が堪らない稀少なチビセオレ! 定番のヘルマンやヒョウモンガメみたいに当たり前のようには手に入らない偶然の掘り出し物、 ニシベルセオレガメが入荷しました。 その昔セオレガメと言えばアフリカからの荷物に居候するような格好で、 何だかついでとかおまけのような存在感で一応こんなものもいますというような、 何しろ同エリアにはケヅメやヒョウモンに始まりリクガメの定番種が目白押しですし、 変わりどころでパンケーキなど隙がなく端から端まで徹底された布陣で攻めてくるものですから、 こんな如何にも脇役な感が満載のマイナー種が居場所に困るのも無理はありませんでした。 セオレがアフリカを代表するリクガメであることは周知の事実ですが、 それでも飼育対象として好意的に見られなかったのには訳があり、 かつては安価で粗雑に扱われ輸入直後のコンディションもグズグズでくたびれていたため、 それをわざわざ選ぼうとするのは余程の物好きと言われても仕方がありませんでした。 それが最近では金銭的な相場は兎も角としてあまり頻繁には見かけられないようになり、 その影響かペットとしての飼育に耐え得る状態で入ってくるようになったため、 個性的なキャラクターを求める声も高まったお陰で、 新たなファン層を獲得することに成功したのでした。 今回やって来たのはセオレのことを知らなかった方々に対しても十分アピールできる、 極めて稀なCBでもなければまずお目にかかれないであろう珍しいスモールサイズのベルセオレ。 本種の瞳が潤いを帯びキラキラとして可愛らしいことは知っていましたが、 流石に幼体ともなるとその愛おしさは倍増しかそれ以上の威力があり、 日毎の成長が楽しみで仕方なくなる驚異的な訴求力を有しています。 たとえ小さくともトレードマークの鳥顔は健在、 これはセオレがセオレであるために最も重要なファクターのひとつです。 輸入され暫く飼い込まれていたお陰で早速Mazuriリクガメフードをガツガツ平らげ、 新規の成長線もごく自然に伸び始めているところがグッド。 色々な先入観はあるかと存じますが実はヘルマンなどと変わらない草原タイプのリクガメ、 きちんとご指導しますので面白くて新しい選択肢として如何でしょうか。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (S) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| セオレ特有の涙ぐんだようなウル目が余計に際立ったまあるいおしりの可愛いお年頃! 元がワイルドだなんて想像も付かないフードから葉野菜にまでバッチリ餌付いた安心の飼い込み個体、 ニシベルセオレガメが入荷しました。 アフリカ大陸とその周辺に暮らすリクガメと言えばスター選手が目白押し、 例えば巨大になることで有名なケヅメやヒョウモンは言うまでも無く、 薄っぺらい特異なフォルムが一度見たら忘れられないパンケーキ、 離島には最も美しいリクガメと謳われるホウシャガメ、 そして唯一飼育可能なゾウガメとして知られるアルダブラなど、 まだまだ挙げればキリが無いほど有名どころが勢揃いと言った具合なのですが、 残念なことにセオレガメの仲間たちはそれらの陰に埋もれて話題になることが少なく、 日本の歴史上ブームのように派手な盛り上がりを見せたことは殆ど例が無いかもしれません。 属内の構成種はそれなりに多く、 背甲の後部がヒンジによって稼働すると言う類稀な特徴を持つにもかかわらず、 何がどうしてかペットとしての人気がいまいち確立されない理由とは、 安価に流通する上に飼育の難しいイメージが植え付けられていることに他ありません。 確かに甲羅の中へ閉じ籠りっ放しでちっとも顔を見せない癖のあるものも中にはいますが、 きちんと種類を選べば育てて楽しい明るい性格の持ち主も存在しますし、 他の人とは少し変わったリクガメを選びたいと言う方にとっても、 決して高いハードルを感じる必要は無い優れた選択肢のひとつだと思います。 今回やって来たのは国内で暫く飼い込まれた野生個体として入荷した、 セオレガメの入門種として昔から定番とされるお馴染みのベルセオレ。 大きく分けて二系統、いわゆる陰気な性質のタイプは甲羅がギザギザしているのに対し、 本種のようにツルンとしたタイプはむしろ環境を選り好みせず活動的で、 却ってそのギャップを体感すると途端に魅力的なカメに感じられるでしょう。 輸入された直後はストレスによりバナナなど特定の餌しか口にしないケースもありますが、 ひとたび環境に慣れてしまえば下手なビギナー種よりもむしろ扱い易いと思えるほどで、 キュートな顔立ちやフォルムの面白さなど開拓のしどころがたっぷり。 セオレイコールべちゃべちゃと言う誤った図式は、少なくともベルセオレには当てはまりません。 あまり流通しないスモールサイズで人工飼料にも問題なく餌付いている、 初めての方にも強くプッシュできる嬉しい出物です。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (ハイイエロー) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| 南米のキアシガメも驚きの甲羅も頭も手足も何もかもが黄色く染め上げられたスーパーセレクト! 基本的に無地であることが多い本亜種においてはこれぞ最高傑作のひとつとも言える極上の一匹、 ニシベルセオレガメが入荷しました。 まだまだ脇役の感は否めないもののこの数年で従来のイメージをガラリと変えてきた、 少し突っ込んだその先にあるリクガメとして話題を集めるセオレガメの仲間たち。 その名前からしてかなり奇抜なキャラクターであることが予想されるのも無理はありませんが、 確かに構成種の一部は色々な意味でエキセントリックな性質を有しているものの、 中には一般に飼育されるリクガメとさほど変わらない性質のものも含まれ、 実はペットとして扱うのにも無理がないのではと感じさせられることもしばしば。 森の中、それもかなり奥深くにひっそりと暮らしていそうなものでもなければ、 いわゆる草原に近いエリアにも普通に進出しているタイプのリクガメですから、 例えばヘルマンやギリシャにも近い捉え方で育てることができます。 かつては安価で大量に流通する実態から体調の悪化も懸念され、 手元に迎え入れた時点でマイナスからのスタートを余儀なくされることも珍しくありませんでしたが、 最近では以前ほど過剰な頭数が出回らない代わりに初期状態が良くなり、 まともに育てられそうな個体が増えているのは本当に喜ばしいことです。 今回やって来たのは数あるセオレの中でも良い意味で普通染みているベルセオレから、 体中の隅々まで眩い輝きを放って止まない一級品の選抜個体。 茶褐色が黄色っぽい、黄色味を帯びているようなものは時折見かけますが、 はっきり黄色いカメだと言い切れるこのカラーリングには初めてお目にかかりました。 染みひとつない背中はまるで真鍮のような鈍い輝きに覆われ、 同様の色味が鼻先や四肢の鱗にまで及ぶ様はもはやキアシガメのそれ。 初見では流石に目の錯覚かと思い何度も甲羅や体を磨いてみたのですが、 余計に美しくなる一方で呪縛から解き放たれるには至りませんでした。 ベルセオレは見た目にこそ一癖あるものの中身は結構ノーマルで、 世間で言われているほど高い湿度を求めている訳でもなく、 飼育するのに最も現実的なセオレだと思います。 既にMazuriリクガメフードなど人工飼料にも餌付いていますので、 より良いコンディションに整えながらお待ちしております。 | ||||||||||
|
ベルセオレガメ (♂) Kinixys bellianai |




|
|
||||||||
| 楽しそうにトコトコ歩いていても常に涙目です。愛くるしい表情が魅力のベルセオレが入荷しました。このサイズでも尻尾が大きく はっきりと オスと分かります。撮影前にぬるま湯で身体を綺麗にしたら、 大量に糞をし体が温まり軽くなったのかどんどん歩き回り、撮影に苦労しました。腹甲の写真で四肢がブレているのはご了承下さい。 お客様長期飼い込み個体でヤル気の無さは全く感じられず、餌も葉野菜から果物、Mazuriリクガメフードまで好んでよく食べます。 頭部のイエローの色合いが素敵です。まだ背甲に柄がありませんが発色は これからです。大きくするのが楽しみですね。 | ||||||||||
|
ベルセオレガメ (♀) Kinixys bellianai |




|
|
||||||||
| 霜降りの背甲の柄が美しいです。お客様長期飼い込みで状態抜群のベルセオレ・アダルト メスが入荷しました。ベルセオレの背甲の柄が発色するのは大きくなってからと よく言いますが、その言葉がそのまま見た目に表れた素晴らしい個体です。リクガメの中でもかなり鳥っぽい独特な顔つきをしており、 目はウルウルで可愛らしいです。その和名が示すのは背甲後部にあるヒンジ の事で、ここを動かす事で産卵をしやすくしていると考えられています。湿度の高い環境を好み、飼育下では水入れからよく水を飲み、 ケージ内に霧吹きをすると待ってましたと言う様に体を持ち上げ、嬉しそうに水浴びを楽しみます。撮影時にケージから出すと手の上から ズンズン前に進もうとし非常に元気です。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (ブラック・Pr) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| マホガニーの表面を更にバーナーで炙ったような黒々とした体色が実に格好良いセレクトカラー! 同じ産地のしかも同じ色合いでしかも雌雄が揃ってしまうこの奇跡に巡り会えたことに感謝したい、 ニシベルセオレガメ・ペアが入荷しました。 かつての人々が描いていたセオレガメ像にはどちらかと言えば負の要素が多く、 彼らが集団で群がろうものなら辺り一帯に陰気なオーラを撒き散らし、 一般的には華やかなイメージであったリクガメの世界においては、 まるで臭いものに蓋をするような本当に酷い扱われ方がされていました。 今考えればそれは何もカメ自身が悪いことをしていた訳ではなくて、 強引に輸入されたものが体調を落としていたために起きた惨事以外の何物でもなく、 綺麗な言い方をすればコアな世界、 しかし心の中では誰がこのようなものをわざわざ好むのかと侮辱されてもおかしくはなかった、 にっちもさっちもいかない状況が長く続いた不遇な時代を過ごしていました。 そんな背景を知った上で改めて今日のセオレガメ像に向き合ってみると、 チチュウカイリクガメをはじめとした定番種らにすっかり支配された環境の中で、 何か風変わりな面白いものはないかと模索した結果、 何故このような興味深い選択肢があることに気が付かなかったのだと驚かされるような、 あえて脱線することを好むようなファンを喜ばせる存在へと進化していました。 私などは当時パッとしない彼らの姿ばかりを目にし続け、 バナナでも自発的に食べてくれれば大成功というような有様が体に染み付いていますから、 何だか普通のカメの振りをしてただただそこらを歩き回ったり、 目の前の餌をお腹いっぱい召し上がったりする光景を目の当たりにするだけで、 体中の力が抜けその場にへたり込んでしまうほどの感動を覚えるのです。 今回やって来たのは同じ便で輸入されたチームの中からカラーリングに拘ってハンドピックした、 大量にひしめき合う中でも一際目を惹く存在感を放つブラックタイプのベルセオレ。 甲羅や頭はもちろん前肢の鱗までベッタリと黒色に染め上げられ、 いつも以上に重厚な雰囲気が非常にクールだと思います。 ワイルドながら傷などのダメージが少ないだけに留まらず、 やけに体重がしっかりあると思えばMazuriリクガメフードを平然と食べまくる状態の良さで、 並のチチュウカイリクガメなどと近い感覚で容易く育てられるでしょう。 ペットとして二匹揃えて並べておくのも悪くありませんが、 将来的には是非ともこの組み合わせで繁殖を目指して下さい。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (ヤングサイズ・Pr) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| 長期の飼い込み同士で先日ペアが揃いました。アフリカを代表する森林系リクガメ、 ベルセオレガメ・ペアの入荷です。 亜種がヒガシとニシとありますが、前肢のツメが5本ある方がヒガシ、 4本の方がニシと比較的簡単に判別する事ができます。今回はニシ。セオレ特有の後ろまで長く伸びた甲羅と、 嘴の発達した鳥顔には他のリクガメにはない独特な味わいがあり、 この辺りの仲間のみしか愛せないマニアもいる程です。 リクガメとしては大きくなり過ぎず森林棲という事から紫外線要求量もそれほど多くなく、 また雑食性なので人工フードなども躊躇なく使える所など掘り返すと意外とメリットのある仲間でもあります。 今回のペアは非常に状態が良く、餌は葉野菜やMazuriリクガメフードをもりもりと食べ、 短い脚で一生懸命ポコポコと歩き回った後はもりもりと糞をしています。 そして人の目を盗んでは交尾の練習と、 彼らなりにせっせと励んでいる様です。 オスは成長線に模様が出始め、 メスは頭部が白く色抜けし上品な感じ。 即結果の出るペアではありませんが、ゆったりと飼い込みたいそんな2匹です。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (♂・♀) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| 何となく嫌な予感がするのは初期状態に因るだけという説を身を以って証明してくれる史上最強のトリオ! 自由気ままに歩き回り排泄を生業としているかのようなあまりにも健康過ぎる理想的な飼い込み個体、 ニシベルセオレガメ・トリオが入荷しました。 世の中に普及しているペットとしての爬虫類に共通した課題として、 一定の、ないしは高い湿度が求められそうな種類というのはそうでないものに対して、 やんわりと敬遠される傾向にあるのではないかと感じています。 ただしこれはあくまでも多くの人々が勝手に想像している部分の話であり、 仮に湿度がさほど必要ないとされているキャラクターがいたとして、 それが本当に乾燥した環境を好んでいるのかと言えば決してそうではない可能性もあって、 言い換えれば乾燥した状態で飼育したいという飼育者側の願いによって、 半ば無理矢理そのような設定に押し込められていることさえ懸念されます。 つまり乾燥系という便利な言葉によって括られる爬虫類の一部には実はそうではないものが含まれていたり、 反対に湿潤系と括られる種類の中にも意外とそうではないものが含まれているのかもしれず、 例えばこのセオレガメについて、 属内にはご想像の通りじめじめとした状況を好む種が存在してはいるものの、 セオレと名の付く全てのカメが一律同じルールで生活しているはずもなく、 少なくともベルセオレガメについては案外並のペットトータスとして扱うことができ、 ここで取り上げた湿度についてはかのヘルマンと殆ど同じような条件で飼育されるべきだと考えられます。 そこに違和感が生じる場合にはむしろヘルマン側の湿度をあまりにも低く見積もっているケースもありますが、 兎にも角にもつまらない前提を一旦壊してみることで今まで以上に視野が広がり、 意識してなのかまた無意識のうちにでも遠ざけていた外側の領域に対しても、 果敢にチャレンジできるきっかけが生まれることがあれば幸いに思います。 今回やって来たのはアフリカのリクガメでは影の定番種として我々を盛り上げてくれる、 昔ながらのベルセオレから妙にコンディションの整えられた最高のトリオ。 私が勝手にMazuriチャレンジと心の中でそう呼んでいる、 Mazuriリクガメフードへの餌付けから更にそれのみで何処まで上手に育てられるかという、 実験的な試みによって誕生したのがここに揃った三匹で、 誰に遠慮することなくビュンビュン伸びたこのみずみずしい成長線を見れば、 そこに孕む疑念などは全て綺麗に消え去ることでしょう。 入店して以来ずっとトリオで同居生活を続けていますので、 宜しければ三匹セットでお渡しできれば嬉しいです。 | ||||||||||
|
ベルセオレガメ (Pr) Kinixys bellianai |



|
|
||||||||
| セオレガメはヤル気が無いとお嘆きの方も多いと思います。しかしこのPrは違います。 何度も交尾している所を確認し、餌の時間になると寄って来て、人前でも普通に餌を食べます。 他のリクガメと違い、鳥顔なのも魅力の1つでしょう。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (Pr) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| ほんのり温もりを帯びた飴色に照り輝くその甲羅に上品さを感じずにはいられません! 今日まで常識としてまかり通っていたマイナスイメージを全て吹き飛ばす入魂のクオリティです、 ニシベルセオレガメ・ペアが入荷しました。 ベルセオレは背中に放射模様の入った個体が来たら手を出そう、 そんなのん気なことを言っている場合ではなくなってしまったかもしれません。 やはり昔味わった衝撃というのは後を引くごとにより大きなものへと感じられ、 その記憶も次第に美化されていくのでしょうか。 過去一時的に出回った経緯のある基亜種ヒガシのマダガスカル個体群、本種に関してはとにかくこれが曲者で、 甲羅に放射状の柄が出ると分かった瞬間から皆の関心はそちらに奪われてしまい、 反対に通常見かけるシンプルなタイプの肩身が極端に狭くなってしまったことは言うまでもありません。 同じセオレでもマイナーな稀少種だったのならまだしも群を抜いて流通量が多い種類ですから、 手に取られる度に模様の有無を確認されていては見られる側もさぞ辛かったことと思います。 こういった経緯からいわゆる無地に近いデザインのものはいつでも入手できるという見方が広まり、 いつしか地味で色気のない印象が定着してしまいました。 しかし今回はそんな不人気の集団から勢い良く出馬した優秀な二匹をご紹介します。 一目見た瞬間に驚きと納得の念が入り乱れ同時に襲い掛かるこの不思議な感覚は一体何なのでしょう。 決して派手な絵柄が描かれている訳ではないのですが、 限界まで品質の底上げに尽力したことが見て取れる甲羅は辺り一面に黄金色の輝きを放ち、 鼈甲の如く透き通る素材の鮮度も従来とはまるで異なるクオリティです。 しかも両者のサイズがまた見慣れぬボリュームで、これも飼育下で丹念に育て上げられた成果と言えるでしょう。 オスは頭部までゴールデンに、 そしてメスは頬を赤らめた様子がそれぞれ程良い味付けとなっています。 雌雄とも華奢な後肢までピンと伸ばして軽やかなステップを披露するほど状態抜群で、 ただただ歩かせておくだけで見栄えもするのですが、 本種のベビーが持つ反則的な可愛らしさをご存知の方は貪欲に繁殖への挑戦も忘れないで下さい。 ベルを飼うならこれで決まりです。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (フルアダルト・Pr) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| 二十一世紀に入ってからはもはや拝むことすら困難と思われていた追憶の巨漢ペア! 西アフリカの景色をもう一度回顧させてくれる今や貴重なフルアダルトです、 ニシベルセオレガメ・ペアが入荷しました。 アフリカと言えば多様な生物相を持つことで知られており、 この地域特有の種類が存在することや人類もまた同大陸に起源を持つのではないかとされていますが、 リクガメ好きにとっても決して見逃すことのできない魅惑のエリアと言えるでしょう。 ケヅメやヒョウモンの大型種に始まり、パンケーキやソリガメなどの個性派や、 残念ながら入手は困難ですがヤブガメやヒラセリクガメと言った未知の領域まで、 更に少し足を伸ばせばホウシャやクモノスなどの美種も加わるという、 蓋を開けてみれば大変に贅沢な豪華メンバーに酔い潰れそうです。 その中にまるでリクガメらしからぬ風貌を持つ仲間がこのセオレガメ、 らしいらしくないというのは人間側の都合で勝手に決めたことですから、 本人らは全く気にも留めていませんし迷惑がってすらいるのかもしれません。 世の中は森林棲のカメによく見られるウルウルとした大きな瞳を指して可愛らしいと決め付けたがる傾向にあるようですが、 その中途半端な評価がセオレ全体に対して負の影響を与えてしまったと言っても過言ではありません。 可愛いという前評判を受けて実物を見てみたら思ったより可愛くなかった、 そんな悲劇が全国各地至る所で頻発したのでしょう、 以来まるで日陰者のような扱いを受け続けたセオレは、 それから浮かび上がることもままならずにずぶずぶと沈んでいってしまったのです。 繁殖方法など確立される間もなく流通量に陰りを見せ、 人気を盛り返そうにも肝心のカメがいなければそれも叶わず、 本当に困ってしまったのは真のセオレ好きに他なりません。 しかし今回、何処に埋もれていたんだと泣いて抱きしめたくなるような、 仰天の大型ペアが地鳴りを響かせて我々の前に姿を現しました。 そう、この二匹の出で立ちこそまさしく知られざるセオレガメの正体、 可愛いと呼ぶべき箇所など一切見当たらずむしろ格好良いと呼ぶべきリクガメなのです。 一般に扱いが難しいとされるのも実際はギザギザとした森の仲間たちに限定され、 ベルやスピークなどのツルンとしたこの手の系統は極度な多湿環境にする必要がなく、 普通に歩かせて葉野菜やフードを与える並の方法で飼育が可能です。 しかもこれらの個体は長期に渡り飼い込まれていただけあり体重はずっしりと、 そしてケージに入れればお構いなしに甲羅を壁にぶつけながら爆走しています。 卵は少なくハッチリングが大きいタイプですからのんびりと繁殖を目指してみるのも良いでしょう、 久々に大興奮の掘り出し物です。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (ハイカラー・Pr) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| ニシベルは柄なしだからと敬遠していた方にこそ捧げたいイエローとオレンジのミラクルペア! 世界中で野生のリクガメが軒並み減少の一途を辿る中まず考えられないと思われた良質過ぎる掘り出し物、 ニシベルセオレガメ・ペアが入荷しました。 俗に野生の王国などと称されるアフリカ大陸は、 私たち爬虫類の愛好家にとっても到底無視できない非常に心踊らされるエリアであり、 例えばリクガメというひとつの分野だけを抜き出しただけでも、 そこに豊富で多様な生態を窺い知ることができます。 ケヅメやヒョウモンなどはアフリカのみならずリクガメ全体を代表する存在であり、 パンケーキはその特異な形状がいつの時代も話題をさらう個性派として認知され、 ソリガメはその稀少性も然ることながら抜群の美しい姿で人気を博す、 そんな豪華メンバーのひしめく中でセオレガメの仲間たちもまた独特な雰囲気を放っています。 正直なところ、 ペットとしての人気および知名度はこれほど情報化が進んだ今日においても決して高いとは言えず、 かつては生きていること自体が奇跡とまで言われるほどに酷い扱いを受けていましたから、 そんなバッドなイメージが忽ち払拭されるというのもそれはそれで虫の良過ぎる話。 しかしながら多くのリクガメが一般家庭のペットとして普及しつつある昨今、 元々マニアックな空気感で勝負していた彼らの立場が追われるような格好となってしまい、 何とかその居場所を探るべく改めてその魅力や持ち味にクローズアップしてみたくなるのです。 今回やって来たのはセオレの中のセオレ、 無印でセオレガメと言えばまず間違いなく本種のことであろうと皆が認識していたほど、 その昔定番種としてありふれていたのも懐かしいベルセオレのペア。 ツルンとしたタイプの中では初期状態さえ常識の範囲内であればとても扱い易く、 広大な分布域のお陰か同種、同亜種内でもバラエティに富んだ外観を楽しませてくれるため、 仕入れる側の人間にとっても未知との遭遇に心躍る瞬間があります。 雌雄共に背部のデザインが贅沢な仕様のものを目ざとくチョイス。 オスは何処か透き通った感さえ窺える眩しいレモンイエローが素敵で、 もう少し成長する過程で各甲板の放射模様も徐々に増えていきそうです。 メスは見たこともない巨体が最大級の迫力に満ち溢れ、 赤味の強いベースにやんちゃな模様が大胆に力強く描かれています。 それぞれMazuriリクガメフードにきちんと餌付いた抜群のコンディションでお渡しできる、 あえてセオレが初めての方にお勧めしたい絶品です。 | ||||||||||
|
ニシベルセオレガメ (ライトカラー・Pr) Kinixys b. nogueyi |





|
|
||||||||
| 琥珀のように透明度の高い柔らかな配色が美しいサイズとカラーに拘ってセレクトしたペアです。 オスはパターンレスながら派手に着飾ることを忘れないデザインで、 メスはオスと同系統の色合いに各甲板には放射模様の名残が感じられます。 どちらも稀に見る巨漢の持ち主で、シャキシャキ歩いてバクバク食べる自慢の店内飼い込みの二匹です。 | ||||||||||
|
モリセオレガメ (M) Kinixys erosa |





|
|
||||||||
| 本当は長かった四肢を振り回しケージ内を駆け巡る奇跡の爆走エローサ! 肌艶に満ちたむちむちボディにフードまで好き嫌いなく平らげる気味の悪さ全開の長期飼い込み個体です、 モリセオレガメが入荷しました。 その名前を聞く限りでは特に何も思わない、 もしくはついつい悪い状況ばかりを頭に思い浮かべてしまうかのどちらかに転ぶことでしょう。 きっと本人には何一つとして悪気がないことはこちらも承知しているのですが、 ワイルドとして流通するほぼ全てに近い個体が動き、重さ、餌食いの三要素において、 いずれも最低点に近い評価を付けられてしまうという所に哀愁が漂います。 木彫りの熊ならぬ木彫りのカメ、 ゴツゴツと湾曲した独特の風貌に魅せられて飼い始めてみたもののぴくりとも動かない、 それどころか顔立ちや表情すらもまともに拝ませてもらえないもどかしさに、 私は彼らに対して一体何をしてやれるのだろうか、 そんな罪悪感に苛まれ自問自答の日々を送ることとなるのです。 自然に放っておけば良かったものを、人間の手によって採集し飼育してしまったがために起きる悲劇、 せめて輸送状態の改善など手を尽くすことのできる課題は残されているのでしょうが、 一度押されてしまった烙印を拭い去るには尋常でない労力を必要とします。 立ちはだかる高い壁に挑む国内外のマニアは、 せめてペットとしてでしか付き合うことのできない自分に何ができるのか、 世間の常識へと抗うかの如く輸入直後の立ち上げへと挑み続けるのです。 今回やって来たのはなんと苦節四年半、今にも宙を舞いそうな勢いで辺り一帯を所狭しと走り回る、 シャキシャキという言葉がお似合いの非常に不気味な動きを展開するベストコンディションの一匹。 何と申し上げたら良いのでしょう、 その行動を眺めているだけで口元はにやつき全身には妙な鳥肌が立ち、 陰気のいの字も感じられない明朗快活な姿には皮肉混じりの台詞しか思い浮かびません。 Mazuriリクガメフードを躊躇うことなく主食にしているという事実が全てを証明してくれるでしょうか、 とにかく軽やか過ぎる小気味良いステップを目の当たりにすれば世界が一変します。 まるで果物のように鮮やかな頭部を全力でお披露目してくれる辺りに余裕が見え、 狐か狸に化かされているような心持ちです。 拒食時代の名残か甲板の癒着した箇所も見られますが、 横から見てもシルエット自体に大きな乱れは無く、 それよりも新たに踏み出した成長の跡のみずみずしいこと。 今までは傍から見ているだけだった貴方も、実はこっそり繁殖に挑戦しようとしている貴方も、 この絶好の機会をお見逃しなく。本当に楽ちんです。 | ||||||||||
|
モリセオレガメ (M) Kinixys erosa |





|
|
||||||||
| 悲しいかな負のイメージが付き纏う中でそれを大きく覆す態度で魅せた奇跡のスーパーヘルシー! もしも普通に育てられるのなら絶対飼ってみたいに決まっている最高にクールなセオレの隠れた人気種、 モリセオレガメが入荷しました。 エローサ、その学名から漂う甘美な雰囲気にあっさりと裏切られるように、 数あるセオレガメの中でも悪名高いキャラクターのひとつに数えられる本種は、 とにかく甲羅から頭を出すところを拝むことさえできれば儲けもの、 目の前で餌を食べることなどまず考えられないほどに神経質で、 そもそもどんな顔をしていたのか分からないままお別れを迎えることも珍しくはない、 この業界では数十年もの間そんな風に酷く揶揄され続けてきた、色々な意味で稀少なリクガメ。 冒頭からこんなに最悪な始まり方で大丈夫なのかと私自身不安になりますが、 実は多くの人々が見て見ぬふりをしてきただけで、 普通に考えれば一番格好良くて一番綺麗な魅力溢れるセオレガメと言っても過言ではなく、 あまりにも恐ろしくて手元へ引き寄せることに躊躇いが生じ過ぎるために、 なかなか飼育が現実のものとならない事例が多々あるという可哀想なヤツです。 資源の無駄遣いをしてしまっている感も否めませんし、 どうしようもなかった状況ばかりだったのも事実であるはずなのですが、 その悪い流れに歯止めをかけたいと願うファンも決して少なくありません。 何よりも三十センチオーバーのセオレなどは化け物としか言いようがなく、 そこに夢はあっても本当に夢のまま終わってしまうような、 そもそも目前で生きていること自体が夢のようなカメなので、 何とかその夢を現実のものにすべく活路を見出したいと、 ここに過去最高と呼ぶに相応しい渾身の一匹を招聘するに至りました。 今回やって来たのは遂に絶対大丈夫だと確信できる最強のエローサで、 入店して間もなく葉野菜を与えると何食わぬ顔で平然と食らい付き、 そんなまさかと翌日にはふやかしたMazuriリクガメフードを差し出してみると、 あたかも以前から食べ慣れていたかのような素振りであっさり食べてしまいました。 これが全てを証明してくれる最高の材料となりましたので、 もはや余計な説明は要らないぐらいなのですが、 肉付きや体重も十分なことからどなたでも安心して育てられることでしょう。 何年待っても特大ギネスサイズのエローサなど現われやしないのですから、 たとえ何年かけてでもそれを自らの手で作り出す価値は十分にあると思います。 後にも先にも考えられないこんな素晴らしい贈り物を是非。 | ||||||||||
|
スピークセオレガメ (EUCB・S) Kinixys spekii |





|
|
||||||||
| もはや本種との再会は絶望的かと思われたところへ突如現れた俄かに信じ難いまさかのヨーロッパブリード! そのスペックからして恐らく最も飼い易いセオレガメと称して差し支えない往年の銘種が再び、 スピークセオレガメが入荷しました。 かつてはベルセオレガメの亜種とされていた過去があるように、 その昔タンザニアなど東アフリカからの出荷が相次いでいた爬虫類業界では、 常時ではないにしろ比較的流通量の多いセオレというイメージと共に、 前述のベルセオレや本種が輸入されていたように記憶しています。 セオレガメと一口に言ってもその形態や生態には様々なバリエーションがあって、 ざっくり二分するとエローサやホームのようにギザギザゴツゴツしたタイプでは、 ご案内の通り下手をすればジュクジュクとするぐらいの高湿度が好まれ、 反対にベルやスピークのようなツルンと丸まったタイプでは、 それこそヘルマンなどにも近しい爽やかで草原チックな環境が好まれるとされ、 その特徴に合わせ認識を変えて飼育に臨む必要がありました。 だからこそ育て易いとされていたスピークは稀少というような認識が全くされてこなかったものの、 これぞまさしくタンザニア便が業界に齎した数々の遺産のひとつに数えられるでしょうか、 あれほど湧き出すように出回っていたものが今では完全に輸入がストップしてしまい、 この数年でリクガメをスタートされた方々にとってはまるで耳馴染みのない、 そんなリクガメがいたのかしらとぼんやりしてしまうほど隠れた存在になってしまいました。 私個人としては今後国内の飼い込み個体ぐらいでしか再び巡り会う機会はないと諦めていましたし、 図鑑などの資料でその姿を見かけたとしても脳内では既に懐かしいカメリストへ追加されていますから、 昔はこんなに素敵なカメがいたもんだと呟くぐらいのもので、 こうしてフレッシュな入荷を前に妙な恥じらいを覚えるような心持ちです。 今回やって来たのはベテラン飼育者でも耳を疑うほどに珍しいEUCBのスピーク。 その強い黄色味からしていきなりワイルドとの違いは明白なのですが、 期待していた通りのキレに満ちた動きやそれに伴う餌食いの良さを目前にすれば、 改めてこのセオレガメが如何に優れたものであったかを再認識させられることでしょう。 早くもMazuriリクガメフードに餌付きもう何も心配することはありません。 今後コンスタントに都合良く入手できるはずもないと思われますから、 何かの間違いで海を渡ってしまったということにしてお早めにご検討下さい。 | ||||||||||
|
スピークセオレガメ
Kinixys spekii |



|
|
||||||||
| 長期飼い込み個体。入荷は稀な種類です。背甲のコントラストも綺麗で、 環境に慣れてしまえば丈夫で飼い易いリクガメです。葉野菜はもちろん、 果物・配合飼料も良く食べます。蒸れない様にして、多湿で飼養すると良いでしょう。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (国内CBベビー) Malacochersus tornieri |




|
|
||||||||
| お客様ハッチのパンケーキガメのベビーの入荷です。この頃はチョコチップクッキーに頭・手足を取り付けたような丸い容姿ですが、 アダルトサイズにもなると長方形になり、放射模様の迷彩色が現れ、ベビーの頃のひ弱さは微塵も感じられません。カメの中でも異色で 立体行動が出来、脱走で泣かされた方も少なくないはずです。自然下でも捕食者に襲われると岩などの隙間に逃げ込みその柔らかな 甲羅に空気をためて身体を膨らませ難を逃れるそうです。このカメの特性を考えると脱走に気を付け、立体的なレイアウトを組んで 見たいですね。今回入荷の個体にとりあえずチンゲン菜や白菜を与えたら 直ぐに食べ始め、Mazuriリクガメフードもバッチリです。 背甲に多甲が有るのが玉に瑕です。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (国内CBベビー) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| ちょっと育ったかわいいプチパンケーキ! このサイズだと本当に焼き菓子と勘違いしてしまいそうです、国内CBのパンケーキガメが入荷しました。 リクガメと言えばこんもりと盛り上がった甲羅のフォルムでトコトコと歩き回る愛らしいイメージが非常に強い生き物ですが、 どんな世界にも異端児というのは存在するようで、 全く間逆の考え方でもって今日まで生き抜いてきたのがこのパンケーキ。 名は体を表す、というよりは人間が直感で命名したであろうこの名前、 実は形だけではなく素材もホットケーキのように柔らかく、 初めて手に取った時のショッキングさはカメ全体を見渡しても群を抜くインパクトがあります。 所謂リクガメらしさの欠片もない所が人気の分かれ目ですが、 単に外観や生態の物珍しさで自然系の番組に登場することもしばしば。 ほんの最近までは野生個体が輸入されてきては安定した価格帯で出回っていたのですが、 ふと気を抜いた途端にパッタリと姿を見かけなくなったような気がします。 現地でも生息数の圧迫を受けているようで理解に苦しむことはありませんが、 そんな時に嬉しい国産パンケーキがやって来ました。 飼育について一癖も二癖もあり、 かつ産卵数が一度に1、2個という生産性に乏しいこの手のカメをきっちり殖やされるというのは、 それこそ趣味の延長でなければ難しくそれだけにやりがいのあるチャレンジだと思います。 へんてこな風貌ですが食性はまさにリクガメの王道で葉野菜メインがベター。 湿度については色々と言われますが乾燥地の岩場に好んで暮らしている、 つまり乾燥した中でも湿度のある場所を選んでいると考えられるため、 ウェットシェルター的な発想を取り入れてみるのも良いでしょう。 岩場の再現についても悩み所ですが、 床材を厚めに敷いておくと隅に窪みを作ってプライベートスペースを確保しているので、 穴掘りだけでは物足りないかもしれません。CBだけあって甲羅は軽いつくりでも中身はパンパンのパンケーキ、 日本生まれの日本育ちという強みを生かして従来の印象を払拭してくれることを期待しています。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (S) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 小さいながらも肉付き良く仕上がったケージ内を元気いっぱい駆け回るやんちゃ坊主! 相変わらずメジャーなのかマイナーなのかさっぱり分からない名前だけなら超有名な、 パンケーキガメが入荷しました。 ネーミングセンスの秀逸さで考えれば恐らく全てのカメの中でもトップクラス、 そう言われて納得しない人はいないであろうこれでも立派なリクガメの一種。 何がパンケーキなのかと言えばまずはそのフォルム、 つまり多くのリクガメがこんもりと盛り上がった形状になることが殆どなのに対し、 一体誰に教わったのかまるで踏み潰されたかのような扁平な体は、 ある種の常識を逸脱した本種だけが持つ特質です。 しかしながらただぺちゃんこなだけでは物足りなかったのか、 指で摘まめばあら不思議、 甲羅全体がふわふわと軽く本当にホットケーキみたいな手触りなのですから、 初めて触った人はきっと驚くこと間違い無しのこれまた常識破りな質感が病み付きになります。 ペットとして付き合った時に感じられる味わいはもちろん見た目の奇抜さだけでは無く、 その身軽な体を生かした素早い動きに他ありません。 時にクイックな動きで魅せる敏捷性の高さはもはやリクガメのそれでは無く、 その機能美には隙間に身を隠すだとか熱効率だとか諸説ありますが、 やはり防御力を犠牲にしてでも素早さを手に入れたかったと言う強い目的意識が窺えます。 ゴクゴクとよく水を飲んだり葉野菜を好んだりする光景も意外性に溢れていて、 とにかく一から十までへんてこりんなところがパンケーキの良さだと思います。 今回やって来たのはまとまって輸入された中から状態に拘って選抜した、 既に入国後数か月が経過しているコンディションの安定したスモールサイズ。 どうしても少々くたびれた野生個体が多い中、 早くも元来備わる凄まじき生命力を取り戻しつつあり、 もちろん更に高みを目指す伸びしろは残されているものの、 初期状態としては十分過ぎるエナジーを感じて止みません。 その高過ぎる知名度に反して飼育例は意外と少なく、 それ故に何が正解かさっぱり分からないと言う声もチラホラ聞かれる中、 ある程度のツボは押さえていますのでお渡しの際に伝授します。 幼体だからと遠慮せずやや広めのスペースで活発に走り回る姿を楽しみましょう、 きっと他のリクガメでは味わえなかったパンケーキだけの魅力が堪能できるはずです。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (S) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| あまり見かけないスモールサイズの中でもとびっきり動きと餌食いの良い二匹を渾身のセレクト! 誰がどう見ても変なリクガメですが初期状態さえ間違えなければきちんと飼える選択肢になり得る、 パンケーキガメが入荷しました。ただ漠然とリクガメと呼ばれる生き物に憧れの念を抱き、 いざそれをペットとして飼育しようと思い立った時、 もし目の前にパンケーキばかりが並べられたとしたらショックを隠し切れないでしょう。 何故ならそれはいわゆるリクガメの姿とはかけ離れた、 やけに向こう側の見晴らしが良いフラットなシルエットなのですから、 こんなのリクガメじゃないと泣き出されても文句は言えないのかもしれません。 邪道とは王道あってのものですからどちらが良いとは言い切れず、 お互いがお互いにその存在を認め合い高め合う関係こそ美しいのだと思われますから、 本種はやはり王道のリクガメとは言い難い奇抜な生き様が持ち味なのであって、 それと真正面から立ち向かえる人々に分配されるべき特異なキャラクターなのです。 今回やって来たのはいつ見ても草鞋ぐらいのイメージが強いパンケーキから、 ヘルマンやヒョウモンガメなど定番のリクガメにいかにもありそうな、 60センチぐらいのケージで可愛らしくスタートするのにちょうど良い大きさの二匹。 もちろんこんなベストサイズが頻繁に入手できるような種類ではありませんが、 これまで興味を示さなかった方に対してもアピール力の強い、 何となく育ててみたくなってしまう絶妙な魔力が本当に素晴らしいと思います。 俗に安心サイズと呼ばれるベビーから少し育ったお年頃ながら、 既に全力のパンケーキを演じていることが甲羅や頭部、 そして四肢の形状や軽やかな身のこなしからよく分かります。 特に足の速さは天下一品、薄くて軽い甲羅から生み出される身のこなしを生かし、 直線的に突撃していく様や障害物をまるでトカゲのように平気でかわしていく様など、 パンケーキだけでしか味わえない独特の世界観が外見のみならず随所に宿っているようです。 個体Aは全体的に黄色味が強く花火模様が特に目立つデザインに、 一方の個体Bは黒めのトーンながら健康状態の良さには大差なく、 早くもMazuriリクガメフードを奪い合って平らげるベストコンディションに仕上がっています。 金額はそれぞれ異なりますのでお好みでお選び下さい。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (国内CB・M) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 極太の放射模様が脳裏に焼き付く美麗CB! この先いつまでも継続されることばかりを願う有難い国内繁殖ものです、パンケーキガメが入荷しました。 原産国はケニアやタンザニアなど、どこかで耳馴染みのある国々ですが遠い遠いアフリカの大地で、 決して広くはない分布域にこのカメは暮らしています。 リクガメと言えばこんもりと盛り上がった甲羅が可愛らしいというのが通念ですが、 パンケーキに限ってはその名の通り極限まで薄さを求めたまるっきり正反対の格好で、 そのらしくなさは人気を大きく二分している要素に違いありません。 形だけではなく触感まで柔らかくなっており、手に取ると本当に焼き菓子のような印象を受けてしまいます。 生物学的には大変珍しい事例として取り上げられると思うのですが、 ペットとして見た場合にはどうしても見た目のイメージが重要になってくるため、 可愛いという路線から大きく外れてしまった本種はどうしても不利な状況に立たされてしまうのでしょう。 そんなこととは裏腹に国内ではパンケーキが比較的よく見られ、さほど高額でもない価格帯で販売されていますが、 実は現地での保護政策は急ピッチで進められているらしく、 ヨーロッパでは輸入自体が禁止されているなどあまり良い実情は聞かれません。 と言うのも輸出割り当ての殆どが日本に来ているのがその原因のようで、 本当の価値観が蔑ろにされたまま流通してしまっている気がします。 実際に繁殖を試みてもコンディションの良いペアを維持することが既に難しく、 産卵数も基本的には1個と生産性に恵まれていないため、野生個体に頼る今の状態から何とか脱却しなければなりません。 この個体はブリーダー宅で生後3年ほど育てられた安心手の平サイズ。 殖えたのは良いものの手放すタイミングを伺っていたら、 しっかりとした大きさに加えド派手な模様が出てきてしまったので結果オーライと言えるでしょうか。 それにしてもひたすらに薄っぺらい甲羅がキープされているので、 何か飼育環境を工夫されていたのですかと尋ねた所、 こちらから手を加えたことはないがそういえばよく親個体の腹に潜っていたとのこと。 両親と同居していたベビーは、 親ガメの下に子ガメ状態でこのフラットなフォルムを維持していたのだと知り、 とても微笑ましい気持ちになりました。 小さな頃から育てていると分厚くなると聞きますがこんな解決策もあるようです。 甲羅のふちに欠けがありますがそう目立ちません、それよりもパタパタと走り回る状態の良さを称賛して上げましょう。 ずっと大切にしていきたい貴重な血統のパンケーキです。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (M) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 美セレクト! ライトカラーで放射模様とのコントラストが素晴らしい稀に見る逸品です、 平ぺったい甲羅で有名なパンケーキガメが入荷しました。 リクガメと聞けばこんもりと盛り上がった甲羅を思い浮かべることが多いのですが、 アフリカが原産のこのカメは極限まで薄さを追求した、 常識を覆すようなフォルムでとても変わっています。 またパンケーキなのは形だけではなく、甲板自体も薄いつくりになっているようで触るとフワフワとしており、 何も知らずに触れてしまった時は思わず何か異常があるのではと内心疑ってしまうでしょう。 頭部を見ても体のわりに大きく、 ヘルメットを被ったような独特な形状はさすが一属一種といったところでしょうか。 こう見えて背中の模様には色々とバリエーションがあり特に近頃では放射模様の際立ったものもいて、 この個体もクリームの地色が全体的に淡いイメージなのを黒い放射線がバッチリと引き締め、美しい見た目をしています。 その特異な生活ぶりを楽しむ為にコルクバーグを何気なく置いておくとしっかりとその下の隙間に潜りますし、 時には一番潜って欲しくない水入れの下など場所を選ばずに閉所を好みます。 是非とも狭い所をご用意してお迎えして下さい。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (M) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 細かい柄の密集したド派手美個体! 見栄え・コンディション共に最高です、飼い込み安心サイズのパンケーキリクガメが入荷しました。 あまりに特異な形質を持つことからとある食べ物の名前が付いてしまったリクガメですが、 確かにカメ類屈指の薄さを誇るその甲羅を形容するにはこの言葉しか無かったかもしれません。 日本ではどちらかと言えばホットケーキと呼ばれることの多いあの食品を指していますが、 色合いもちょうどそのような雰囲気で実にキャラクター性溢れる生き物です。 昔から輸入され国内でもしばしば見かけることができますが、 その知名度とは裏腹に飼育には少々コツがいると言われ決して初心者向きではありませんでした。 しかしながらここ最近では輸入状態も改善されたのか初期状態の良い個体が多く、 それを証明するかのように国内繁殖の成功例も所々で聞かれるようになるなど随分身近な存在になってきたような心持がします。 今回やってきたのはやたらピカピカしているので小さなサイズから育った個体でしょうか、 それはともかく背面の見事な柄が真っ先に目に飛び込んできました。 綺麗なパンケーキというと太い放射状模様が目立つのが典型ですが、 豹柄にも見える短いラインが数多く表れたこのタイプは新鮮で、 アロハシャツよろしくびっしりと敷き詰められた模様を見ると今後の成長も楽しみです。 成長具合の関係か横から見ると少し膨らんだ箇所もありますが、 餌入れのコマツナに突進していく大変活発健康な個体です。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (♂) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| バリバリに仕上げられた長期飼い込み個体! 随所に光る色味の濃さも見応えがあります、 パンケーキガメ・オスが入荷しました。 特別マニアを相手にする訳でない場合、 このカメを説明する際には名前と写真のふたつがあれば殆どの場合に事足りてしまうでしょう。 名は体を表すとはよく言ったもので、和名だけではなく英名も勿論Pancake tortoise。 しかしその国際的に認められたネーミングが表すのは決して見た目だけではありません。 平たいからパンケーキか、と手に取れば指先から伝わるのはふんわりと焼き上がった菓子が持つあの触感。 カメの甲羅は硬いという概念を瞬時にぶち壊し、触れた者に対しこれが甲羅の軟化という病気か、 と心配の種さえをも植え付けるほど強烈なインパクトを放ちます。 つまりこのカメについて知るには名前と写真だけではなく、 実際に触ってみることも必要であると言えるでしょう。 今回やってきたのは数年間という長期に渡って飼い込まれた一匹のオス個体。 パンケーキはコンディションを把握するのに少々厄介な面を持ちますが、 食う寝る歩くのメリハリがはっきりしておりまずは一安心。 元々が軽量仕上げのカメですが手に持てばしっかりと体重を感じることができ、 何より驚いたのがその欲求不満な態度。 瞬間的にホシガメと同じ場所に入れておいたら何を思ったかいきなり盛り始めたので即隔離しました。 甲羅の模様もさることながら頭部と四肢に色付けされたオレンジはベッタリと濃く、 少々贅沢な感想ですがくどいと感じるほどに見事な発色です。 縁甲板が1枚分かれていますがフォルムに影響はありません。 キビキビとしていて見栄えも良いと来れば言うことなし、オススメです。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (ライトカラー・♀) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 本来であれば黒地に模様の入るはずだった関係性が逆転してしまった極美リバースパターン! 輸入後のケアも済みケージ内のありとあらゆるものをなぎ倒すバタバタ系健康優良児、 パンケーキガメ・メスが入荷しました。 誰がどう見ても珍ガメであることに異論は無いであろう、 見た目から触感までものの見事にあの食べ物を再現した歴としたリクガメの一種。 日本語ではそれをホットケーキと呼ぶのが一般的ですが、 実は英語圏では出来上がりがしっかりと厚みのある方をホットケーキ、 反対に薄く平たい方をパンケーキとはっきり呼び分ける風習があるようで、 我々もそれに倣い親しみを込めてパンケーキと呼んであげた方が良さそうです。 リクガメはふっくらこんもりと言った固定概念を全てぶち壊す容姿は好みの分かれる所ですが、 ある種のトカゲのようにスタスタと軽やかに走り回る姿は躍動感に溢れ、 見た目だけの出落ちだけでは無く飼っていても引き続き面白い通好みの一面が光ります。 一般にはリクガメ好きに受けないとされている都合上、 飼育者は必然的にマニア層が一定の割合を占め、 その恩恵からかじわじわと国内CB化まで進んでいる時代を先取りしたカメなのですが、 現地では厳しい保護の対象になっている上いざ殖えても生産効率に恵まれているとは言えず、 ペットとして向き合う私たちが高い意識をもって接しなければならないと常日頃から考えさせられます。 今回やって来たのはそんじょそこらの並パンケーキとは一味違う、 ネガポジが反転したような薄い黄色地に黒くて細い放射模様が入った美麗個体。 この変わり様は横に比較対象を置かずとも容易に理解して頂けることでしょう、 冷静に考えるとぺちゃんこにしたホシガメと言えるほどの美貌を持つ本種に対し、 あえて美しさを望まない理由があるのでしょうか。 イエローと表現するよりはどちらかと言えばホワイト、 象牙製の作り物のように硬質なのかと思いきや触れると柔らかい所に矛盾を孕み、 腹甲に描かれるべき柄が一切見当たらない暴れっぷりにはもはや言葉がありません。 このような個体を親に用いたとすれば子孫に如何ほどの影響を及ぼすのか、 まだ何とか流通のある内に挑戦すべき課題だと思います。 縁甲板に一枚多甲がありますが指摘されなければ気が付かない程度のもの、 そんなことより何よりこの色薄パンケーキの周りで繰り広げられるドラマから当分目が離せません。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (♀) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 薄さと軽さが売りであるはずの本種において厚さと重さで勝負できる史上最強の飼い込み個体! いつ新鮮な卵を沢山産み始めてもおかしくはない餌食いから体重まで万事順調なフルアダルト、 パンケーキガメ・メスが入荷しました。 まるでリクガメのようでもリクガメではない水棲ガメの仲間は数多く存在しますが、 せっかくリクガメであるのにもかかわらずそのらしさを殆ど捨ててしまった、 リクガメの中で最もリクガメらしくないリクガメと言えばこのパンケーキをおいて他にあるでしょうか。 いつもより眺めが良い左に少し戸惑ってしまいそうな、 向こう側が楽に見通せるさっぱりとしたそのシルエットはまさしくパンケーキ。 もちろん彼らが小麦粉を焼いたその食べ物のことを知るはずもありませんが、 あまりにもフラットな甲羅は他の種類ではまず考えられない独特な造形であり、 その手触りもまた本当に柔らかく一体何処まで再現すれば気が済むのでしょうか。 普通のリクガメを普通に育てたい方にはまず選ばれることはないでしょう、 ただしパンケーキを愛しパンケーキと生涯を共にしたいと考える方にとって、 他の選択肢では到底代わりになるようなことは有り得ませんから、 こんなに素敵な生物が同じ地球上に存在することを改めて感謝すべきだと思います。 今回やって来たのはワイルドのアダルトサイズからずっと日本でコツコツと仕上げられていた、 何もかもが健康になり一切の心配がなくなった色々な意味で即戦力のメス。 放射柄の綺麗なものが選出されたお陰で美しさと機動力を見事に兼ね備え、 下手なヘルマンなどよりもずっと飼い易いかもしれないスペックが出来上がっています。 はっきり言ってしまえば悲しいことにパンケーキの運命は初期状態にあり、 最初の選択によってはどれだけ頑張っても報われないケースも珍しくありませんから、 そんなおみくじのようなフェイズをすっ飛ばし初めから大吉を引ける喜びの大きさは計り知れません。 餌の時間になると右へ左へケージ内をやかましく爆走し始め、 ふやかしたMazuriリクガメフードを皿に盛った途端に突撃、 顔面をくちゃくちゃに汚しながら一心不乱に食べまくる光景は、 遠いアフリカより連れ去ってしまった罪悪感のようなものをかき消してくれるでしょう。 こんな絶品を必要としている方のところへ、 つまり収まるべきところへ収まってほしい選ばれし一匹です。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (ヤングサイズ・Pr) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 可愛らしいサイズですがもうペア組めちゃいます。 リクガメのイメージをぶち壊す特異な体型はこのカメでしか味わえません、 お客様飼い込みのパンケーキガメ・ペアの入荷です。 パンケーキという名前は平たいのもそうですが大人になっても触るとフワフワした甲羅を持つ事でも知られており 初めて触った時はびっくりしますが、これは甲羅を薄くし軽量化を図る事で素早い動きをものにする為と考えられています。 また現地では熱い岩の上でバスキングをし、薄くて暖まり易い体が十分な体温になると 岩の隙間に隠れるという行動も観察されているそうです。 また、敵に襲われそうになった時は素早く隠れ息を吸い込んで体を膨らまし隙間に密着させ、 引っ張っても出せない様になるとか。 棲息地が近いからなのか、あのクレオパトラが愛したと言われるモロヘイヤなど緑の濃い葉野菜を非常に好みます。 この個体達はMazuriリクガメフードも普通に食べています。 オスは黒っぽく円形にラインが入り、 メスは白い放射模様が鮮やかで2タイプのカラーを楽しめます。 国内繁殖の例もありますから、 まずはこのペアを気長に飼い込んでゆくゆくは繁殖にもチャレンジしてみて下さい。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (Pr) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 放射模様が綺麗で初期状態が良いという完全なる我がままセレクトにより実現したナイスペア! 買い時の難しい珍種ですが興味を抱いたその瞬間に目の前にいさえすればそれこそが最高のチャンス、 パンケーキガメ・ペアが入荷しました。 私事で誠に恐縮ですが初めてこのカメの存在を知った時、 一度で良いから実物を拝んでみたいと率直にそう感じましたし、 またそれを実際に手に取って感触を確かめてみたいとも思いました。 まだ学生だった私のその願いは程なくして現実のものとなるのですが、 不意に目の前に現れたそれを自らの手で持ち上げることにより得られた情報は、 あまりにも軽く柔らかい甲羅に病気を患っているのではと心配になり、 僅か数分後にはそれが正常なのだと知り本当に恥ずかしい思いをしましたが、 以来パンケーキという存在は私にとって大変思い出深いカメとなりました。 名前の面白さは何も冗談などではなくて、 形状から質感まで本当にパンケーキなのは現物がいてこそ確かめられる事実であり、 有名な逸話に岩場の隙間へ挟まって息を吸い込むと膨らんで固定されるという、 未だに真偽の定かではない伝説めいたエピソードが生まれるのも無理はない、 人々に夢と感動を与えるその生き様は本当に格好良いと思います。 詳しく解説すると、 つまり甲羅自体を薄くすることで軟化する代わりに体重がかなり軽量化され、 ほんの一瞬でも気を許した隙に何かに踏まれでもしたら命に関わるような脆さと引き換えに、 ご想像の通りそれによって得られた高い俊敏性により外敵からの攻撃をかわしたり、 ごく短い時間の中で効率的なバスキングを実現するなど、 あまりにも機能美を意識し過ぎた先駆的なコンセプトには脱帽の一言。 日本では何故か昔から比較的安価に流通しているため、 その有難味が気付かれていないというのが正直なところだと思われ、 今の内からもっと大切に扱われるべき銘種であることは間違いありません。 今回やって来たのはまとまって輸入された中から状態に拘ってセレクトした、 餌食いが良好で肉付きも十分な美麗ペア。 やはりこの鮮やかな背中の柄は説得力抜群で、 既に葉野菜をもりもり食べていますので、 Mazuriリクガメフードに餌付けられるのも時間の問題でしょう。 個人的には幅広の独特な顔立ちがお気に入り。 飼育については押さえるべき簡単なポイントが数点ありますので、 お渡しの際には是非とも詳しくお伝えしたいと思います。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (Pr) Malacochersus tornieri |


|
|
||||||||
| 今回、白が多く綺麗な個体をセレクトしました。完全に成体になると重戦車のようになりカッコ良いです。卵数は少ないですが、 ハッチしやすいカメです。リクガメの種類でも立体活動ができ、石組のレイアウトで飼育すると楽しみが 倍増するでしょう。でも、逃亡には気を付けて下さいね。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (Pr) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| CITES騒動の渦中にいる最も話題性のあるカメのひとつが輸入されて数年間飼い込まれていた抜群の状態にて! いつの時代も好き嫌いの分かれる種類なだけに真に必要とする方の下へ速やかにお届けしたい、 パンケーキガメ・ペアが入荷しました。 カメと一口に言ってもよくよく見ればその中には多彩なジャンルが含まれていて、 例えば水棲ガメの中には日本人が普通に連想するカメらしいカメもいれば、 何だかイメージとはかけ離れていてちっともカメらしくない、 それには例えばスッポンモドキやマタマタなどの珍奇なキャラクターが挙げられるのでしょうが、 ことリクガメにおいては殆ど全ての種類が私たちの持つステレオタイプの範疇に収まるものばかりなのかと思いきや、 ここにひとつとんでもない例外を発見してしまいました。 パンケーキだなんて本当にジョークの塊みたいなネーミングで呼ばれていますが、 何もふざけている訳ではなく本当にそれがパンケーキなのですから致し方ないでしょう。 そのスタイリングは一般的なリクガメ像とはまるで正反対の奇抜な様相を呈していて、 横から見ると向こう側の景色がはっきり眺められるのが堪らなく面白いのですが、 本当に驚かされるのは実際に手を触れてみたその瞬間だと思います。 ただ平たいだけに飽き足らず甲羅全体がふわふわと柔らかい質感に仕立てられており、 何も知らされていなければ体の調子が悪いのではと思わず心配してしまうところですが、 これも彼らの戦略のひとつであり予め備えられた仕様なのです。 それ故に普通のリクガメが欲しかった人にとっては意外性ばかりが目立ち、 その勢いが却ってパンケーキが心底大好きな特定のファン層を育むまでになりました。 流石に捕まえられ過ぎだろうと現在CITESのⅠ類に昇格してしまうのではとも囁かれていますが、 いずれにしても本当に欲しい人が手に入れられるタイミングで手に入れられれば良いと思う今日この頃です。 今回やって来たのはそろそろ繁殖にもチャレンジしていきたくなるような大人サイズの二匹で、 当店に迎え入れてから少しばかり鍛えてやった結果、 今ではMazuriリクガメフードオンリーの食生活でも問題なく過ごせるようになりました。 変わった見た目をしていますが食生活は並のリクガメと概ね変わりなく、 一般的な草食のものを想像して頂ければ差し支えありませんので、 ここでも当店で頻繁にお勧めしているフードが登場する訳です。 見た目の出落ち感はなく機敏な動きでシャキシャキ走り回る様は見ていて飽きませんし、 このままいなくなってしまうのは本当に寂しいと思えるずばり往年の銘種です。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (Pr) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| 飼い込み個体の素晴らしさを知る貴方へ軽さの中に背負い切れないほどの重みを備えた健康体! もっと評価されてもおかしくはないカメナンバーワンの称号をほしいままにするご存知アフリカの珍種です、 パンケーキガメ・ペアが入荷しました。 全てのリクガメを集めてもこれほど多方面に抜群の知名度を誇る種類はなかなかいませんし、 有難いことに定期的な輸入があってしかも何故かリーズナブルな価格帯で手に入るにもかかわらず、 実際に飼育していると言う話は不思議と聞かれない謎が謎を呼ぶ怪しい奴。 いわゆるリクガメ好きには一向に好かれる気配が無いのは百も承知、 むしろパンケーキ好きにのみ愛されていれば当人にとっては何の問題も無いのですが、 食わず嫌いなのか本当は欲しくても結局最後には別の種類が選ばれてしまうこの哀しさは一体何なのでしょうか。 ひとつはワイルドばかりで状態に不安を抱えていることが挙げられ、 更にはあまりにも奇抜過ぎるスタイリングが飼育環境を惑わせる、 その癖まみれな体質が一般の飼育者を遠ざけているような気がしてなりません。 しかしその陰でコツコツと国内CB化が進められているのも事実で、 下手な初心者向けの種類よりも見かけるのではないかと思う時がありますが、 繁殖を目指す方にとっても実は見逃せない殖やせるリクガメと呼べる逸材なのです。 詳しくはお問い合わせ頂いた際にお話ししますが、 とにかく押さえるべきポイントはバスキングと湿度、 それに飲み水と覚えておけばほぼ間違い無いでしょう。 もちろんこれを実現するためにはそれなりに開けたスペースを要しますが、 何しろ元のカメが20センチにも満たない小型種ですから、 仮に90センチクラスの環境が与えられればそれだけで贅沢に感じられるほど。 初期状態さえ問題無ければあとはフードや葉野菜中心の食生活で問題無く、 見た目は変てこでも極端にぶっ飛んだ飼育方法が必要な訳では無いことが分かります。 今回やって来たのは輸入されたてのものとは比べ物にならない躍動感を見せる、 国内で長期に渡り育てられていた間もなく繁殖可能なほぼアダルトのペア。 コンディションの良さが決め手となり当店でも久々に取り扱いましたが、 最近ではもし姿を消したら絶対に後悔するカメだと日々痛感させられます。 手に挟めば業界最薄の超軽量ボディ、 初めて触るとまるで紙か何かで出来ているのではと疑いたくなるぐらいの衝撃で、 私事ですが中学生の時これが噂のクル病かと手を震わせながら驚いたことは今でも忘れられません。 ワイルド便の美個体をセレクトするのも楽しいですが、 美しさよりも何よりも健康であることを優先したい真の意味での稀少種です。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (Pr) Malacochersus tornieri |





|
|
||||||||
| パッと見て分かりやすい華やかな模様と輸入後のトリートメントも済み状態の安定した良い所取りの飼い込みペア! 稀少性云々を全て差っ引いてただ純粋に生物としての珍しさを慈しみたい往年の名種、 お客様委託のパンケーキガメ・ペアが入荷しました。 こんなにへんてこりんなカメが暮らしているのはケニア、ザンビア、タンザニア、 あんまり語呂が良いのでちょっと言ってみたかっただけというのもあるのですが、 ふと現地の週間天気予報を調べてみると当たり前ですが今も相当に暖かいですし、 特にケニアは思いっ切り赤道直下の国ですからそれが年中続いているということを改めて認識させられます。 動物園のスターである大型哺乳類たちが多数在籍している広い広いアフリカ大陸の中でもそのたった三国にしか棲息しておらず、 完全に調査が達成されていないという事情ももちろんあるのでしょうが、 各国における分布域はそれぞれが孤立していて全てを合わせた総面積は非常に狭い、 いわゆる局所分布と呼ばれる性質を有しています。 名前の由来は甲羅の形状および質感から、 まさか焼き立てのお菓子が放つ芳ばしい香りまで漂って来たら面白かったのですが、 それでも甲板自体のつくりが極度に軽量化されているために触感はふわふわとして柔らかいという、 甲羅を持つカメとしては有るまじき行為を堂々とやってのけたその度胸は賞賛に値するでしょう。 何度見直しても俄かには信じ難い本当にぺらっぺらのボディは、 気持ち成人男性の親指ほどの厚さしかありませんので普段生活していて息苦しくないかと心配になるほどです。 ここまでは何を今更当たり前のことを、というような内容でお送りしてきましたが、 これだけ当たり前のように奇抜で興味深いリクガメが何故日本では安価で容易に入手できるのでしょうか。 距離がさほど離れていないだけにその緊迫した状況が如実に伝わってくるのでしょう、 EUでは1998年より本種の輸入が禁止されており、 と言うことはつまり我々のようにパンケーキを普通に飼育することは叶わないのです。 飼い方にはコツがあると散々言われ続けてきましたが、 現地での暮らしぶりを想像すると何となく見えてくるのは、 はっきりとしたケージ内の温度と湿度の勾配が重要ではないかと思われます。 両個体とも葉野菜を中心に十分な量をきちんと食べており、 何よりもシャキシャキと走り回ってくれるその姿がこちらを安心させてくれます。 今回は委託販売のためお値打ちに設定しましたので、 国内繁殖例もチラホラ聞かれる貴重な種類であるだけに是非ともこのペアからも成果を上げて下さい。 | ||||||||||
|
パンケーキガメ (Pr) Malacochersus tornieri |




|
|
||||||||
| 初見だとかなりの衝撃を受けるカメの代表では無いでしょうか、パンケーキガメです。 あまりに薄く柔らかい甲羅は、物事を悪い方向へ考えてしまう事も。けれどこれは本種の特徴で、 この身軽な装備のお陰で、険しい道もスイスイと走ったり、岩場に身を隠す事もできます。 甲羅のホウシャ模様もよく出ており、葉野菜もよく食べています。 | ||||||||||
|
スマトラムツアシガメ (ベビー) Manouria e. emys |





|
|
||||||||
| 掴み所の分からないワイルドとは違い大股でシャキシャキと歩き回る成長が楽しみな可愛いベビー! 他種に見られる丸く収まったような雰囲気がまるで感じられない武骨さと野性味が持ち味です、 スマトラムツアシガメが入荷しました。 日本国内には棲息していないせいかあまりイメージの湧いてこないアジアのリクガメ、 インドの辺りまで含めるのであればホシガメという立派な人気種がいることはご承知の通りですが、 距離的には更に身近な東南アジアなどにもいくらかの種類が存在しています。 その代表例として挙げられるのがムツアシガメの仲間、 飼育難関種として名高いインプレッサは中国の山間部に分布し、 こちらエミスはと言うとスマトラやボルネオ、 タイ、マレーシアなど島々から大陸部にかけて分布することが知られており、 我々の住む日本よりこれほど近しい所にリクガメが暮らしている事実に驚きを覚えますが、 ペットとしてポピュラーな人気種たちとはまるで異なる、 良くも悪くもいわゆるリクガメらしさからは縁遠い外観が最大の特徴です。 こんもりのこの字も感じられない上から踏み潰したように扁平な甲羅、 触れただけで怪我をしてしまいそうな鋭利に発達した粗い四肢の大型鱗、 いつも不満気な表情を浮かべているむっつりとした厳しい顔付きなど、 雌雄問わずして全身から漢らしさが漲っているようです。 そのため愛好家の間でも好き嫌いの激しいマニアックなポジションに位置付けられていますが、 メジャーなカメでは飽き足らないちょっと変わった嗜好をお持ちの方や、 初めからがっつり屋外飼育を想定されているような方からは絶大な支持を受けています。 今回やって来たのはまだ手の平にちょこんと座ってしまう大変愛らしいベビーで、 ハッチサイズより幾分成長したためか性格はずばり遠慮知らず、 ケージ内を隅から隅まで走り回ったかと思えば、 餌皿をひょいと置いた途端に遠くからいそいそと駆け寄って来る、 大変に無邪気でエネルギッシュな健康優良児へと仕上がっています。 餌食いは良好で葉野菜や野草などはもちろんのこと、 Mazuriリクガメフードも好んで食べてくれるので後々困ることも無いでしょう。 夢はでっかく30センチオーバーと言ったところでしょうか、 当面はミニゾウガメ的な趣きを楽しめそうですが、 成長した時に見せるあのシルエットと重厚感は捨て難いものがあり、 一度見たら絶対に忘れられないインパクトがあります。 諸説ありますが亜種ビルマと比較しても遜色のない耐寒性を持つのも嬉しいポイント、 植物に水を与えるように毎日体に霧吹きをかけてピカピカに育て上げましょう。 | ||||||||||
|
スマトラムツアシガメ (S) Manouria e. emys |





|
|
||||||||
| 極小のひよっこではなくいきなり重たくもない絶妙なボリュームから楽しめるスターターサイズ! 成長段階の初期をリアルな磨耗と共に野生で済ませているためこの先もナチュラルな仕上がりが期待できる、 スマトラムツアシガメが入荷しました。 原始的という三文字は生き物の特徴を表すのに大変便利なキーワードとなり、 そう言っておくだけで何だか様になったような気がしますし、 太古の昔から生き延びてきたとか恐竜時代がどうのこうのとか、 対象となるものの高い生命力を感じさせるような魔法の言葉として用いられます。 ただしそれは何かしらの根拠に基づいているとは限らない場合もあって、 ただ単に見かけの雰囲気がそれっぽいというだけの場合もあれば、 生物学的に長く姿かたちを変えないまま暮らし続けてきたという場合もあるでしょう。 ムツアシガメとは現存する種類がたったの三つから成る小さなグループで、 ペットの世界においても明らかにマイナーなキャラクターであることは否めませんが、 その特異な容姿から長年に渡り一定のファン層を抱え愛され続けてきました。 パッと見の印象からして一般的なリクガメとはかなり異なっており、 実際に分類事情を紐解いてみるとリクガメをまず二つに大別する時、 それはリクガメ亜科とゴファーガメ亜科の二手に分かれ、前者には殆ど全てのリクガメが、 後者にはゴファーガメとムツアシガメのみが振り分けられる格好となります。 更に種小名のemysとは英語のtortoiseと同義のため、 ここに名付け親の思いが込められていないという方に無理があると思えるほど、 真の意味で原始的なリクガメであると考えても差し支えないのです。 今回やって来たのはイエローエミスという俗称も懐かしく感じられるほど、 すっかりご無沙汰であった久々のスマトラムツアシから、 これまたあまり見かけられない珍しい安心サイズの一匹。 輸入されるものの多くは性別が判別できる手前ぐらいの大柄なものが多く、 或いはベビーで来てしまうと甲羅がふわふわとした本当のベビーになってしまい、 セーフティな体格で育て甲斐もある都合の良い出物はなかなかありません。 見た目はカメというよりも戦車のようにメカニカルな迫力があり、 まるで果物の王様ドリアンがトランスフォームしたかのような、 全身トゲトゲの格好良さは唯一無二の特長です。 腹甲の甲板も見事に二手に分かれ混じり気なし。 神経質とされながらもやはり重要なのは初期状態、 早くもMazuriリクガメフードに餌付いてしまったこの個体と共に、 素敵なムツアシライフをお過ごし下さい。 | ||||||||||
|
スマトラムツアシガメ (S) Manouria e. emys |





|
|
||||||||
| まるで苔生したかの如く渋格好良いカラーリングが素敵なイエローエミスならぬグリーンエミス! カメがカメとしてこの地球上に誕生した瞬間に立ち会っているかのような、 まさしく原初のカメを見せ付けられた、そんな気分に浸ることのできる稀少な存在です。 磨かれれば磨かれるほど、つまり成熟すればするほどその魅力は何倍にも膨れ上がる、 ペットとしては色々な意味で規格外のスケールで勝負を挑んでくる凄まじきリクガメ。 入荷後程なくしてMazuriリクガメフードに餌付き、それをほぼオンリーで育ててみたところ、 Mazuriの性能も然ることながら個体の素質も讃えてやりたい、 極めて順調な成長過程を辿っているナチュラルテイストな超健康体です。 | ||||||||||
|
スマトラムツアシガメ (EUCB・S) Manouria e. emys |





|
|
||||||||
| 叩いても壊れないほど頑丈で強健な安心サイズで目指せアジアの巨大装甲車! まだまだ駆け出しの幼い頃ですが現時点での仕上がり具合は驚きのほぼ百点満点です、 スマトラムツアシガメが入荷しました。 一応リクガメ、そんなあやふやで煮え切らない紹介の仕方がぴったりな、 異端児のように扱われることの多いこのムツアシガメ。 何故一応なのかという理由はあえて説明しなくともお分かり頂けるかと思いますが、 その外観から動きまで全てがらしくなさを演出していることに拠ります。 扁平気味で色気が全くないどころか冷たい金属光沢さえ感じられる武骨な甲羅に、 持つ手に刺さるほど尖った爪と悪路走破性に長けた妙に歩幅の広い歩き方、 そして常に不機嫌そうなクールな表情も相まってそこにはとてもリクガメ特有の愛らしさは伺えません。 しかし近頃ではお馴染みの人気種がすっかり定着してしまったこともあり、 ホシガメに始まりケヅメ、ヒョウモン、アカアシ、ギリシャ、ヘルマンとある程度メンバーも固まってきていますから、 そこに新たな刺激を求めるべく様々なジャンルのカメが再び価値観を問われているようです。 特に本種の場合は大型化するという条件が何より大切な肝となり、 他に大きくなると言えばいきなりゾウガメとハードルが極端に上がり過ぎてしまいますから、 アフリカの二大巨頭ではなくあえて異なるものを選びたい、 個性派の貴方にとっては非常に重要な存在であると言えるのです。 今回やって来たのは基亜種イエローエミスの飼い込み個体で、 最近流行りのヨーロッパで繁殖されたベビーから育てられたとのことですが、 一目見てほぼ全く違和感の見当たらないとても満足度の高い出来栄えに心惹かれます。 言葉ではなかなか言い表しにくいのですが、 多くの個体がこのサイズに到達すると各甲板が凹み過ぎてしまったり、 過乾燥で頭頂部が白くなったり成長線も歪になるなど、 せっかくの重厚感に水を差すような結果を迎えてしまうことも少なくありません。 しかしこの個体は全体がバランス良くふっくらと育っているため、 成長不良の影響をもろに受けやすい時期をパスしただけにここからの展開が本当に楽しみなのです。 熱帯産ではありますが元来の性質から寒さにもよく耐え、 まさに日本国内で飼育できる大型リクガメの有効な選択肢のひとつと言えるでしょう。 特別人気が高い訳ではなく流通量もどちらかと言えば少ない部類ですから、 これほどまでに質の高さが全身に表れた個体は早い者勝ちです。 | ||||||||||
|
スマトラムツアシガメ (M) Manouria e. emys |





|
|
||||||||
| リクガメにしてこの重厚感はなんでしょうか。ミズガメ愛好家にも意外と人気が高いです、 エミスムツアシガメの基亜種スマトラムツアシの入荷です。亜種ビルマが60cm近くにまで大きくなるのに対し こちらは40cmを超える位と少し小型な種類で、黒っぽい体色が特徴的なビルマに比べ 黄色味がかった体色からイエローエミスとも呼ばれています。 亜種判別は左右の胸甲板の形状で見る事ができ、接する事無く左右に分かれているのが基亜種です。敵から身を守る為に発達したのか、 妙にゴツゴツとした 鎧の様な四肢の鱗や、 湿った環境を好み頻繁に水場に浸かりたがる習性などかなりヤマガメチックでとてもリクガメらしくない所が魅力的です。 ビルマ程ではないものの耐寒性も備えており、他種では少し心配な低温程度ではびくともしません。 今回は入荷したばかりではなく飼い込み個体なので、Mazuriリクガメフードをよく食べ普段は店内の床一面 四肢を踏み鳴らす様に歩き回っています。 かっこいい系のエミス、近頃は大分飼育もしやすくなってきたのでリクガメの変り種として如何でしょうか。 尾部のアップ写真はこちら。 | ||||||||||
|
スマトラムツアシガメ (M) Manouria e. emys |





|
|
||||||||
| 現地で見るムツアシ像を具現化したようなグッドコンディション! 飼い込みが吉と出た元気もりもりの一匹です、お客様委託のスマトラムツアシガメが入荷しました。 ムツアシガメ、名前だけ聞いてその姿を想像すると虫みたいで気持ちが悪いのですが、 その由来は後肢付け根にある2本の大きなトゲで、四肢にプラスするとムツアシになるという訳です。 アジアの森林に棲息する仲間ですがいわゆるリクガメと呼ばれる種類たちとは少々イメージが異なり、 扁平でがっしりとした甲羅に荒い鱗、短く先の尖った鋭い爪や攻撃的な目つきなど愛らしさの欠片も無く、 どちらかと言えば格好良いグループに入るでしょうか。 俗に言うミズガメ好きから支持の厚いムツアシ、というのはこのような特徴から来ているのだと思います。 基亜種はイエローエミスとも呼ばれるように全体をほのかな黄色が包み、 甲羅や頭頂部をその色で染めています。 今回やってきた個体は最大甲長から考えるとちょうど折り返し地点のミドルサイズ。 エミスとしてはよく見かける大きさですが手にとってびっくり、 いつもの感触とは違う腕にかかる重みは安心を超えて驚きへと変化し、 しかしその興奮を味わう間もないまま鎧のような鱗と爪がカメを持つ手にダメージを与えてきます。 手に取ってバタバタ、 写真を撮るため地面に置けば即ダッシュとてんやわんやで、 見えない何かに侵されたあのムツアシのイメージを見事にぶち壊しました。もちろん新しい成長線も出ています。 性別は不明としましたが尾のアップ写真はこちら。 今回は1ヶ月間限定の販売で、最初で最後のこの価格です。 金額と状態が全く合致していません、お早めにお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ビルマムツアシガメ (CBベビー) Manouria e. phayrei |





|
|
||||||||
| 同一ロットの中から初期状態はもちろん体色が最も黒々としたものを選抜したフルブラック候補生! いくら成長に連れて色彩が変化するとはいえ甲羅も地肌も初めからより黒いのに越したことはない、 ビルマムツアシガメが入荷しました。 これらの仲間をいわゆる並のリクガメたちと同一視して良いものか否かは、 彼らと向き合う度に毎回のように考えさせられるところですが、 その根拠になるエピソードとして近年注目されているのは、 リクガメ科の分化に関する最新の情報がそうさせているのだと思います。 世界中の人々が飼育対象としている種類のほぼ全て、 それはつまりヘルマンやホシガメ、ケヅメやアカアシなどの有名どころを指していますが、 そうではないムツアシガメとゴファーガメをまとめてゴファーガメ亜科とする説により、 メジャーな彼らとはそもそも異なった系統であることが示唆されています。 きっとこのムツアシたちにも何百年、何千年と遡れば他に仲間はいたのでしょう。 事実、琉球諸島にかつて存在したとされるオオヤマムツアシガメは化石として発見されていますし、 そういった背景ひとつひとつが俗に原始的だとかいうそれらしい表現を生み出すことで、 ペットとして向き合う私たちにとって非常に刺激的な要素となるのは間違いないのです。 今回やって来たのはごく久しぶりにお目にかかるCBのビルマムツアシで、 よく知った方であればまず真っ先に体を裏返し甲板の配列を確認するところですが、 同じ便で輸入された兄弟全てに左右の胸甲板が接する特徴が見られ、 どちらでもない曖昧な形質を持つ個体は含まれていなかったことで第一段階はクリアしました。 皆さんの中には何となくムツアシガメのベビーは難しいという先入観が植え付けられているかもしれませんが、 恐らくそれはあのインプレッサが創り出した誤った印象であると思われ、 こちらエミスについてはむしろ普通のリクガメよりも強健なイメージさえ感じられます。 ただしハッチサイズが巨大なため見た目よりはベビーであることを承知の上で、 まずはきちんと暖めるなど基本に忠実な飼育を実践することが大切でしょう。 今のところMazuriリクガメフードのみに拘って給餌していますが、 食べる量にも出す量にも何ら問題は見受けられませんので、 この調子で気が付けば十センチオーバーなんてスムーズな展開が予想されます。 頭部も四肢も腹甲も全てが強い黒味を呈する渾身のセレクト個体、 もちろんオンリーワンですからお早めに。 | ||||||||||
|
ビルマムツアシガメ (♀) Manouria e. phayrei |





|
|
||||||||
| ミャンマーの山奥で、森の中に潜む山のように巨大なムツアシガメと、出会った! アジアのゾウガメと呼ばれはしますがいくらなんでもこのボリュームにこの厚みはやり過ぎでしょう、 ビルマムツアシガメ・メスが入荷しました。 とりあえず冒頭の部分をスローテンポでもう一度。 さて、ムツアシガメと言えばカメ全体を見渡してもごくごくマイナーなグループであり、 一般に広く知られているようなことは絶対に無いと思いますが、何を隠そう歴としたリクガメの仲間です。 サイズと言い風貌と言い別段可愛らしさなどは感じられませんし、 冷静に考えればとても普通の家庭で飼い切れるような種類ではないのにもかかわらず、 それでも一部の層には受け入れられているのも事実で図鑑などでも度々紹介されています。 そこで皆さんの目に必ず留まるのは、何よりもまず耐寒性の高さについての記述でしょう。 正直足が六つだか八つだかそのような内容はどうでも良くて、 問題は如何にして飼育するかという部分なのですから、 大きくなったとしても冬場は寝かせられることが分かっただけで強く心を惹かれてしまいます。 平常時で全身が黒いだなんて他にはゾウガメぐらいしか目立った例がありませんし、 水槽に入ってしまうレベルでは全然満足できない我侭な方にとっては、 これほどうってつけの逸材も他に見当たらないのです。 今回やって来たのは棲息域からより寒さに強いとされる亜種ビルマムツアシの、 これまたとんでもないサイズに成長している長期飼い込みの貴重な出物。 文献によれば最大甲長は60センチ、 気持ち小型であるらしい基亜種スマトラでさえこのクラスのメスは存在するようなのですが、 実際に現物を前にしてはそのような能書きを垂れている余裕などありません。 同じ大きさやそれ以上のケヅメと対面したところで見慣れているせいかさほど衝撃は感じられませんが、 まるで大きな岩の塊のような、 いや岩にしても大き過ぎるこの生命体から発せられた有り余るエネルギーは腹の奥にずしんと響きます。 物々しい顔付きがリクガメにあるまじき攻撃的な印象を強め、 重厚な前肢の鎧は鼈甲細工のような美しさを併せ持ち、 こんな野蛮な生物が人知れず庭中を闊歩している光景を想像するだけで鳥肌が止みません。 よく観察すると平均的な個体に比べて妙な厚みがあるような気がしますが、 店内に展示していてもまず真っ先にアルダブラだと勘違いされるそのシルエットは神様の悪戯によるものなのでしょうか。 背甲に甲板の癒着した部分がありますが、 全体のバランスが上手いこと取れているため歪な箇所など一切無く、 元々が漆黒のカメですから殆ど気にならないと思います。 よく見かける種類のリクガメではちっとも物足りないという貴方に贈る、 後にも先にもお目に掛かれないであろう久方振りに心躍る一点ものです。 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ (CBベビー) Manouria impressa |





|
|
||||||||
| 願わくばもう一度と幾人のマニアが切望した本当にきちんと育てられる状態抜群のCBベビー! 一寸先は闇の言葉通り数年後には再び入手できる見通しが全く立たないであろう、 インプレッサムツアシガメが入荷しました。 またの名をベッコウムツアシガメ、通称エミスと呼ばれるスマトラ、 ビルマの他に第三のムツアシガメとして人知れず人気を博している、 ある意味世界一美しいリクガメと言っても過言では無い実にマニアックな稀少種。 和名の由来は言うまでも無く甲羅から放たれたその輝きのことで、 透明感に満ちた飴色のボディをはじめ、 大きな頭に太い鼻先、四肢の鱗は極めて粗く鎧を纏ったように硬質、 腕の可動域が広くまた鋭く発達した爪も山野における走破性の高さを表し、 体中の至るところが何処までもリクガメらしくない色々な意味で珍しい生物です。 かつては飼育最難関種として愛好家から恐れられていたにもかかわらず、 その美しさ故に何人もの人々がついつい手を出しては涙を呑んだ、 このエピソードだけでは本当に迷惑な奴としか言いようがありませんが、 それだけ我々の期待度は高く何としてでも何とかしてやりたいと、 そんな風に熱意を掻き立てる存在であり続けたのでした。 結局は初期状態の悪さが全ての元凶であったと判明した時にはもう手遅れ、 気が付けばインプレッサは市場からパタリと姿を消してしまっていたのですが、 実に四年前に突如流通したあのCBが全ての常識を覆すこととなったのです。 今回は最高のコンディションでお届けする待ちに待ったCBの再来、 記憶は美化されると言いますがあの時は本当に良い思いをさせて貰っただけあって、 苦手意識が湧き起こらないことが実に幸せに感じられます。 初めの一歩はとにかく乾燥にさえ気を付けていればつまづかないでしょう、 蒸れることはあまり恐れずにひたすら高湿度を目指すのが吉。 あくまでもベビーですから極端に涼しくする必要も無く、 お腹だけは冷やさないように暖めるような暖めないようなそんな感覚で。 餌はお約束のキノコを中心に給餌しており、 今は体重を増やすことだけに神経を集中し食べるものは何でも与え、 特にヒラタケとマイタケが群を抜いて良い成績を収めています。 あえて難しいとは言いませんが最初の一か月が勝負、 気を抜かなければワイルドとは比べ物にならない強健なリクガメが出来上がることでしょう。 細かなセッティングは過去の成功体験を元に綿密にご指導しますので、 我こそはと言う方の挑戦をお待ちしております。 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ (CBベビー) Manouria impressa |





|
|
||||||||
| はっきり言って奇跡です、今年は当たり年なのかまさかの再会が実現した待望のCBベビー! どれにするか悩むと言う精神状態がどれほど贅沢なことであるか今一度考え直してみたい、 インプレッサムツアシガメが入荷しました。 今月の初めにこの場へ掲載してからおよそ一か月、 早々に売り切れてしまった二匹に多数のお問い合わせを頂きましたが、 結局のところ次はいつになるのか分からないとお答えするのが精一杯で、 何しろこんなご時世ですから欲しいものは欲しい時、 では無く目の前にいる時に入手することの大切さを改めて学ばされた出来事でした。 それは何も実際の飼い主になる方だけの問題では無く、 私たち販売者側にとっても全く同様のことが言え、 図鑑を片手に世の中には色々な種類のリクガメがいますと説明したところで、 継続的な商業流通が実現しているものはほんの一握りなのですから、 仕入れと言う作業においても全く気の抜けない状況に追い込まれているのです。 数年後、少なくとも数十年後にはまともに飼育できるリクガメの種類が両手、 いや片手で数えるほどになってしまうかもしれないと囁かれる中で、 このような隅っこの世間一般には広く知られていない、 いわゆるマニアックな珍種を育ててみたいと願う人々にとって、 本当に苦しくて辛い時代が到来しようとしているのがひしひしと感じられます。 もし今チャンスがあるのならば是非とも積極的にトライして頂きたい、 そんな想いを添えて夢を実現するお手伝いができれば幸いです。 今回やって来たのは前回の便よりもややふっくらとしたサイズの幼体で、 この風情と感動は過去のコメントをご参照頂くこととして、 相変わらず体の艶と照りが眩しい魅力的極まりない容姿に加え、 早くも恒例のキノコ類を猛烈に食す姿にひとまず安心しました。 前便の個体はおよそ一か月の内に体重を10グラム増加させており、 その順風満帆な暮らしぶりを詳細なデータと共にお伝えしますので、 飼育環境の設定に不安のある方も恐れること無く前向きにご検討下さい。 色合いは赤っぽいタイプと、 反対に黄色っぽいタイプが揃いましたが、 後者は幼体時特有の鋭い目付きが和らいだ黒目の大きな可愛らしい顔立ちが印象的。 上手に扱えば並のリクガメよりも頑丈なのではと思わせる素振りも見受けられる、 見た目から中身まで本当に何処までも変わったオンリーワンなキャラクターです。 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ (CBベビー) Manouria impressa |





|
|
||||||||
|
もうこれ以上は何も望みません、
喉から手が出るほど欲しかった念願のCB!
今まで手を出しあぐねていた方にとってはどう考えてもまたとない絶好のチャンスです、
ピッカピカのインプレッサムツアシガメが入荷しました。
またの名をベッコウムツアシガメ、
本来であればウミガメの仲間であるタイマイからつくり出される鼈甲細工ですが、それを全くの無加工、
つまり生まれたままのナチュラルな状態で初めから綺麗という、とても羨ましい甲羅を持つリクガメ。
ムツアシガメ自体にデフォルトでニス塗りを施したような艶が出ているため、
その奥にある地色が鮮やかな黄色になる本種はほぼ自動的に見栄えがするという仕組みです。
中国南部やベトナムの竹林などに棲息し、標高の高い山間部でヤマガメのような暮らしをしていると言われ、
他のリクガメとは全く異なった野生環境がこのような変わった風貌を生み出したのでしょう。
その美貌から入荷を待ち望む声は多く、
日本では忘れた頃にと言うと失礼ですが時折採集された個体が輸入されてきます。
しかし元から状態を崩している個体も多いため立ち上げも含めると飼育は困難と言わざるを得ず、
残念ながら長期飼育例のあまり聞かれる種類ではありません。
それでも現地で目にする大型の成体は信じられないレベルの強靭な脚力を持ち、
発見してもダッシュで逃げられてしまうほどにスピーディだと言いますから、
日本に連れて来ても同じように走り回る姿を見ることがファンの夢と希望、そして目標ではないでしょうか。
今回はそんな積もり積もった長年の願いがいよいよ叶うのであろう、
待ちに待った繁殖もののインプレッサが到着しました。
間違ってもエミスではありません、どこからどう見ても正真正銘インプレッサのベビーです。
この色、この輝き、
そしてこの動き、
今まで散々頭を悩まされてきただけに感動もひとしおで、
抱きしめてしまいたくなるほどに愛しい最高の心持ちです。
初対面から尋常でない活発さを見せ、
集合写真の撮影ではよーいドンで一斉に駆け出し、
暫く放っておくとまるで外遊びを体いっぱいで満喫する子どものように土まるけになって帰って来ます。
無邪気な三匹の様子を観察していてふと頭を過ぎったのが、
ワイルドであれだけ透明感のある美しいカメがベビーから育てられると一体、
とこれ以上考えを巡らすのはあまりにも恐ろしいのでやめておきます。
幼体のこの大きさから既に個体差が見られましたので、
黄色いタイプ、
オレンジのタイプ、
ぶちの入るタイプをセレクトして来ました。
この度繁殖に成功したブリーダーにはどれほど感謝してもしきれません。
ムービー1・ ムービー2・ ムービー3 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ (CBベビー) Manouria impressa |





|
|
||||||||
| そのあまりにもエキセントリックな容姿を武器に業界を賑わすマニア垂涎の稀少種が再び! 何やらコンスタントに流通しているように見えますがそう感じる内に早めの入手を試みたい、 インプレッサムツアシガメが入荷しました。 リクガメにあるまじき妙に尖ったクールなネーミングと、決して名前負けしない、 それどころか他のリクガメでは絶対に味わえない最高の格好良さを見せ付ける、 かつてはリクガメ界きっての鬼門として良くも悪くも名を馳せた銘種のひとつ。 ムツアシガメと言えばあの黒々としたエミスの風貌が真っ先に思い浮かぶと同時に、 最大甲長の大きさばかりが記憶から呼び覚まされ、 とても一般向けの種類ではないと頭から瞬時にデリートしてしまう方も少なくないと思いますが、 本種はおおよそヘルマンよりも大きく、 そしてアカアシガメよりも小さいと言ったなかなか絶妙なサイズ感に、 この煌びやかさは他種の追随を許さない最高の武器として注目を集めて止まず、 他では絶対に代わりの利かないキャラクター性は今も昔も変わらぬ人気を誇っています。 かつてのインプレッサはそれこそ最難関種としてラスボス的な存在感を放っていましたが、 この数年で繁殖された個体が出回ると評価はガラリと変わることになり、 如何なる種類でも幼体には必ず付き纏う漠然とした不安さえ取り除かれれば、 飼育対象の極めて有力な候補として一気に最前線へと躍り出るのです。 今回やって来たのは一昨年、昨年に続きまるで風物詩のように今年も顔を見せてくれた、 それでいて何時いなくなってしまうのか今からハラハラしてしまう、 皆さんお待ちかねの現地CBピカピカのベビーサイズ。 過去に販売した個体たちの実績から決して育てるのが難しい種類ではないことが分かり、 一度環境にハマればむしろ他のどんなリクガメよりも扱い易いのではないか、 まるで陸棲のハコガメやヤマガメのようなアバウトささえ通用してしまう、 ある意味一番ペット向きかもしれないと思わせる内面のスペックが素敵過ぎます。 お約束通りキノコの類を懸命に食べ始めていますので、 この調子で葉野菜やMazuriリクガメフードへと早々に移行したいところ。 実は以前輸入されていたサイズは4.5センチほどで、 今回手に入ったのは5.5センチと随分成長していますから、 カラーリングについてもそれぞれが申し分ないデザインなので、 現物が目の前にいる間に我こそはという方に是非とも挑戦して頂きたい絶品たちです。 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ (CB・S) Manouria impressa |





|
|
||||||||
| 昨年の夏に話題をさらったピカピカのベビーが誠心誠意真心込めて育てられた無敵のインプ! 本当は出て来るはずでは無かった、出て来てはいけなかった後にも先にも無い魂の飼い込み個体、 インプレッサムツアシガメが入荷しました。 かつて幻のリクガメとして謳われた、 その表現にも様々な意味や感情が含まれているのでしょうが、 冗談抜きでそこに姿があるのにふと目をそらした隙に消え失せてしまうような、 そんな謎めいた儚さが往年のマニアを悩ませ弄んでいた本当にとんでもないヤツ。 最終的には飼育と言う概念がまるで通用しないことが分かり、 いよいよ剥製と紙一重のような扱いさえ受けることも珍しくありませんでしたが、 そうこうしている間に野生個体の流通が皆無となり、 人々の記憶からその忌まわしささえも忘れ去られようとしていた矢先、 何年か前に養殖されたようなベビーがポツリと輸入されてしまったからさあ大変、 再び血の滾る思いで手を伸ばした飼育者が続々と成功例を世に送り出し、 遂に初期状態さえ良ければ育てられるリクガメだと言うことが分かりました。 ふわふわのベビーに絶大の信頼を寄せることは難しいものの、 かつての惨劇を肌身に感じて来た方にとっては些末な問題に過ぎず、 どう考えても恵まれた時代に突入したと考えるのが妥当なのです。 今回やって来たのは当店で販売してから今日に至るまでその軌跡をつぶさに見守っていた、 正真正銘ベビーからの飼い込みでここまで大きく育った今世紀最大級の衝撃を放つ掘り出し物。 前の飼い主様は手放す気など更々無く話が決まった時には放心状態でしたが、 とにかく最後の最後までそのコンディションを注意深く見守られていただけあって、 改めて元気だと申し上げるのが少し恥ずかしいぐらい当たり前のように元気な姿を見せてくれています。 撮影前に甲羅を磨いていたら歯ブラシに噛み付きて来た時には流石に驚きましたが、 例によって全くリクガメらしくないキレのある動きには脱帽。 Mazuriリクガメフードから葉野菜、 それに大好きなキノコ数種類にももちろん餌付いた最強のベストコンディション、 使用していた器材からそれによってつくり出されていた環境まで、 お望みでしたらこの二匹が過ごしていたありのままを忠実に再現することも可能です。 もう二度と目の当たりにすることがあってはならない上半期で最も感動を呼ぶ物語が此処に。 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ
Manouria impressa |




|
|
||||||||
| 別名ベッコウムツアシと呼ばれるに相応しい奥深いべっ甲色に包まれたムツアシです。 ”アジアのゾウガメ”と称される同属のエミスムツアシは最大で70cm近くにもなりますが、 本種は30cmにもならずその点では非常に飼い易いと言えるのではないでしょうか。飼育が難しいと 悪名高い本種ですが、今回の個体は写真ではちょっとわかりにくいですが人工飼料も食べました。 どうもガツガツ食べるタイプではなくチビチビと何度にも分けて食べるようです。 シャイなカメですので高湿度にし、隠れ家を作ると調子も上がります。 | ||||||||||
|
インプレッサムツアシガメ
Manouria impressa |





|
|
||||||||
| 別名ベッコウムツアシの名に相応しい 吸い込まれそうな程に透き通った甲羅が極めて美しい極上個体! 一昔前より夢のリクガメとして語り継がれる珍種です、インプレッサムツアシガメが入荷しました。 当店でも過去に入荷例はありますが姿を見るのは実に久しぶりで、 この個体を見た時はこんなに綺麗だったかと目を疑ってしまいました。 やはりクオリティの相当高い個体のようで特に背甲の色の鮮やかさは格別であり、 一般に綺麗なカメと言われていますが全体的に黒っぽいものと比べると一目瞭然です。 そもそもどんなカメだろうと調べ始めると多くの資料にあまり良い事が書いていないリクガメですが、 近頃では色々と情報が出てきておりそれも一緒に仕入れてきました。 この個体は輸入後国内でトリートメント(フラジールにて駆虫済み)された後に入荷しましたが、 その時にはキノコ類と葉野菜をどちらも食べていたそうです。 キノコ食のイメージが強いですが状態が良ければ葉野菜も普通に食べるようで、 やはり環境の変化にはあまり強くありませんが落ち着けばうまく飼えそうです。 ここでは全て書けませんので今回ご購入頂いた方には飼育のポイントをお話します。 新しい成長線のもりもりと出た素晴らしい逸品です。 | ||||||||||
|
キバラクモノスガメ (国内CB・S) Pyxis a. arachnoides |





|
|
||||||||
| 快挙! 数年前に無事書類を取得した両親から誕生した正真正銘の国内2010CBです、 お客様委託のキバラクモノスガメが入荷しました。 マダガスカルを原産とする、リクガメ全体を通しても屈指の美種であるクモノスガメ。 英名はもちろんSpider tortoise、黒地に黄色い模様の入るリクガメはいくつか存在していますが、 この仲間は甲羅全体が蜘蛛の巣に覆われたようになる不思議な柄を持ち、 幾何学的にも大変美しく見る者を自然と惹き付ける力を持っています。 3亜種が知られていますがキバラはその中でも最も流通量の多かった亜種で、 次に見かける機会の多かったキタに比べて少し大き目の体格を持ち、 またなんとなくイエローラインの太い個体が多く見られるのも本亜種の特徴のひとつでしょうか。 現在ではクモノス全種がCITESⅠ類に掲載されていることから全盛期の勢いは全くなく、 飼い込み個体もしくは数少ない繁殖個体が細々と出回る程度です。 さて今回やってきたこの個体、 ブリーダー様のお宅で生まれてから1年が経過し体つきも大分しっかりしてきました。 実は一昨年、昨年、今年と3年連続繁殖に成功されておりそれらは全て次世代の種親候補だったということですが、 今回放出の理由を伺った所どうしても家族の反対で数を減らさなければならなかったとか。 ならばということで09CBは今後のために残し11CBはまだ小さいのでと話はまとまり、 間を取って10CBを出されることに。 個体のプロフィールを紹介すると「ハッチリングの時点で初甲版の黄色い面積が広く変わった印象で、 成長に連れてどう変化するかが楽しみだった」とのことでした。 参考までに同年ハッチの兄弟の色柄はこんな感じです。 クモノスを飼育するのにどの亜種を導入するか迷う所ですが、もし繁殖を志すことになった場合、 現状を考えるとかつて多くの個体数が輸入され現在でもかろうじてコンスタントに流通が望めるキバラがベターなのかもしれません。 縁甲板の一部と腹甲に甲板の乾いた部分がありますが、経年で元に戻ります。 蜘蛛の巣模様の完成はアダルトサイズになったその時ですのでまだ先は長いだけに非常に楽しみです、 世話のコツなども伝授致しますのでお問い合わせお待ちしております。 | ||||||||||
|
キバラクモノスガメ (♀) Pyxis a. arachnoides |





|
|
||||||||
| 数年間待ち侘びてもほぼ全く姿を見せなかった奇跡の即戦力フルアダルトメスがシングルで! 過去に有精卵を産み数匹の子孫を誕生させた実績を持つ極めて社会貢献度の高い一匹、 キバラクモノスガメ・メスが入荷しました。 CITESⅠ、その言葉は甘美であり、そして悲哀なる響きをも有する、 幾多のマニアを狂わせた稀少種が稀少種たる所以を示す最大のキーフレーズ。 昨今の爬虫類業界、 特にカメの世界においてはビルマホシガメやホウシャガメなどが巷を賑わせていますが、 かつてⅠ類のリクガメとして大きな顔をしていたのはマダガスカルのクモノスやヒラオでした。 彼らがその定めに従ったのは2005年、 あれから実に十年以上も経過していると思うと感慨深いものがあり、 それと同時にあれほど目にした数々の個体は何処へ消えてしまったのかと胸がざわつきます。 そう、数年前までは入手困難な珍種として付加価値が与えられながら商品として流通し、 様々な好事家たちがこれまた様々な思いを胸にそのカメを手にしていたのですが、 今やペットトレードにおいてはほぼ絶滅状態と言っても過言では無く、 やはり生産性の乏しさが悲劇を招いたと捉えるしか無いのでしょう。 つまり先に挙げた二種とクモノスらの絶対的な違いは産卵数にあり、 大きな卵で大きな幼体を数少なく産むタイプの典型例ですから、 どれほど種親をフル稼働させたところで繁殖できる頭数は限られており、 残念なことに供給よりも需要が上回っていたのか、 それともあまり考えたくはありませんが生産よりも消費の方が上回ってしまったのか、 いずれにしてもここ最近では影も形も無くなってしまったのです。 元々オスの出物が多かったためペアを組むのが非常に困難で、 未だに単体で飼育を頑張っていらっしゃる方も少なくないと存じますが、 こうして巡り合えた希望の光と共にミラクルを起こして頂きたいと強く願うばかりです。 今回やって来たのは真の意味で即戦力として活躍してくれること間違い無しの、 クモノスにしてはやたら豊満で恵まれた巨体を持つフルアダルトのメス。 甲羅のフォルムからそこへ描かれた模様にまで不満な要素は一切無く、 観賞価値と実用性の高さがどちらも秀でた魅力的にも程がある最高の逸材。 四肢のトルクもすこぶる良好で手の平から発射しそうな勢いがあり、 一発交尾すれば元気な卵をもりもり産んでくれそう。 ここ日本の何処かで再びその力を発揮してくれれば幸いです。 登録記号番号:第050-007210号 | ||||||||||
|
キバラクモノスガメ (Pr) Pyxis a. arachnoides |


|
|
||||||||
| 完璧なシンメトリーな模様を描く背甲のキバラのペアです。サイズもバランスが取れていますし 何よりまだ若そうで長期的に楽しめそうな個体です。よくいる大きいだけの老成個体と違います。 当然若いので餌も良く食べます。飼い込んでCBとって下さい。 | ||||||||||
|
キバラクモノスガメ (Pr) Pyxis a. arachnoides |





|
|
||||||||
|
もうこれより先には実現し得ないであろう繁殖にも十分役に立つ雌雄が揃う千載一遇の好機!
登録票取得時にはアンセクシュアルの幼体だったことが今となっては最強のメリットでしかない、
キバラクモノスガメ・ペアが入荷しました。
野生の王国マダガスカルに人知れず暮らしていたこんなちっぽけなカメを、
我々人間が目ざとく発見したかと思えばすぐさま面白がってペット業界に持ち込み、
散々弄んだ挙句には個体数が激しく減少してしまい今に至る、
どうしてこんなことになってしまったのかと悔やんでも悔やみ切れません。
比べては可哀想ですが同じくCITESⅠ類に掲げられたかの有名なホウシャガメ、
彼の場合はあまりにも過激な密猟や密輸出が頻発したためか早々に繁殖計画が試みられ、
少なくとも人工飼育下ではさほど危機的な状況では無いそれなりの個体数が回復しているようですが、
こちらクモノスやかつての相棒ヒラオリクガメについては年を追う毎に絶望的な雰囲気が拭えず、
とにかく繁殖によって供給が増加していく様子などは微塵も無く、
決して好ましい表現ではありませんがどうしても消費されているようにしか映らないのが現状です。
そもそも体格的に不利なことや抱卵できる数にも限りがあることなどがネックとなり、
明らかに量産などと言う行為とは縁遠い初期設定が災いしていて、
今後は趣味の世界における遊びの究極型として種の存続に少しでも力添えできれば、
そんな夢のようなミッションを問答無用で請け負わざるを得ないムードが続いています。
今回やって来たのは数えること十年少々の間せっせと育てられ、
前の飼育者曰く何となく同居させていたら偶然にもオスとメスになってしまった、
全てにおいて好条件が揃い過ぎている最初で最後のビッグチャンス。
ここで最も重要視したいのはそれぞれの年齢について、
フルアダルトの野生個体を長期飼育されている方なら嫌でも脳裏を過る老成の二文字、
その漠然とした不安から解放されることがどれほど大きな意味を持つのか、
クモノスマニアにとってこれ以上有難いことは無いはずです。
雌雄共に動きから餌食いにまで非常に躍動感があり、
当たり前のこととは分かっていても傍にいて安心させられるのは嬉しいポイント。
是非とも栄光の架橋へと一歩でも前進して頂きたく、
我こそはと言う貴方にこの二匹を捧げたいと思います。
登録記号番号:第050-000693号(♂)・
第050-003122号(♀)
餌食いムービー: オス・ メス | ||||||||||
|
キタクモノスガメ (♂) Pyxis a. brygooi |





|
|
||||||||
| クモノスにあるまじき性格の明るさが前面に押し出された不気味な躍動感で魅せる極上の一匹! 安定した餌食いや甲羅の質感はもちろんしっかりとした足取りにも若さが漲る仰天の掘り出し物、 キタクモノスガメ・オスが入荷しました。 これほど煌びやかな容貌の持ち主ですから写真の姿ぐらいは印象に残っているかもしれませんが、 何しろCITESⅠ類に掲載されたのは遡ること2005年のお話ですから、 この数年でリクガメと触れ合い始めた方々にとってはお初にお目にかかりますと言った具合になることでしょう。 そもそも流通実績がさほど豊富だった訳ではありませんので現存する個体もごく僅かで、 新規の輸入がストップし早十数年が経過した昨今においては、 マダガスカルのリクガメたちももはや空想上の生物のような扱いとなり、 そこへ来てかの有名なホウシャガメがまさかのリバイバルという逆転現象も起きていますが、 誠に残念ながら憧れることさえも許されないような厳しい状況が続いています。 長年隣で相方を務めてきたヒラオについては国内市場では絶滅に近い状態であり、 こちらクモノスについてもやはり継続的な国内繁殖の基盤が整備されているとは言い難く、 一匹一匹が本当に一点ものとなってしまうような何とも言えない儚さが拭い切れません。 カメという生き物自体は長寿ですから状態さえ整っていれば末永く付き合うことができ、 年齢という概念をも超越した永遠のペットとしての存在意義は、 他の動物では容易に成し得ないまさしくカメだけに備わった特権なのです。 今回やって来たのは三亜種の内こうしてお目にかかれる機会はさほど多くない、 ミナミよりは多くキバラよりは少ないイメージの亜種キタクモノスから、 シングルで育てられていたことが功を奏しフルパワーで入店した血気盛んなお年頃のオス。 辛うじて出物のあるキバラに比べ黒味の強いボディカラーが新鮮で、 はっきりとラインが目立つためよりクモノスらしいデザインと言えばそうなるでしょうか。 国内CB化が思うように進んでいない現段階では、 登録票の発行時に現在よりも小さなサイズだった個体はある程度年齢が推測し易く、 新たに迎え入れることに強く前向きになれる貴重な存在と言えます。 ムービーでご覧の通りMazuriリクガメフードを好んで爆食しており、 これまで見てきたクモノスの中でも飛び抜けて性格が明るく活発に走り回る、 見た目も中身もパーフェクトな国宝級の絶品との出会いは年の瀬の奇跡です。 登録記号番号:第050-008089号 | ||||||||||
|
キタクモノスガメ (Pr) Pyxis a. brygooi |


|
|
||||||||
| クモノスガメの仲間の中で背甲に黒色が目立つ綺麗な種類です。じっくり飼い込んで 貴方好みに仕上げて下さい。動きが少なく地味な印象は有りがちですが、 餌の前に霧吹をするとムクムクと起き出して生きてるなって実感させてくれるのも魅力の1つでしょうか | ||||||||||
|
ミナミクモノスガメ (♂) Pyxis a. oblonga |





|
|
||||||||
| 今まで探していた方、必見! 国内で5年以上飼い込まれてフルアダルトになった希少なクモノスです、 お客様委託のミナミクモノスガメ・オスが入荷しました。 マダガスカルのクモノス・ヒラオと言えば今やリクガメの高級種の代名詞ともなりつつありますが、 クモノスの中でも特に本亜種は昔から数が少なく現在ではペアを揃えるのは至難の業でしょう。 この個体も許可証を取得後、まさに手塩にかけて溺愛されここまで大きくなりましたが、 いかんせん良いメスとの巡り合いもなく現在に至っているようです。クモノスガメとはよく言ったもので、 背甲全体をびっしりと覆った幾何学模様はまさに自然が造り出した芸術です。 委託主様のお宅では小松菜、大根の葉、ウチワサボテン、タンポポ、オオバコなど バリエーションに富んだ野菜・野草類に、適宜L型乳酸カルシウムを添加して与えられていたそうで、 一般に気難しいイメージのあるクモノスにしてはそのような印象は一切無く、 この仲間に初めて挑戦される方にも自信を持ってお勧めできます。 体重は220gと小ぶりなカメに似合わない数値で手に持った感じは文鎮の様。 僅か10cmの甲長でも尻尾はとても太く成熟した様子を主張しています。 単独飼いで優雅な生き様を楽しむもよし、 更に最近では国内繁殖例もチラホラ聞かれるようになってきましたからメスをお持ちの方は是非ともブリードに挑戦して下さい。 | ||||||||||
|
キレーネギリシャリクガメ (S・♂) Testudo g. cyrenaica |





|
|
||||||||
| 嘘みたいなネーミングながら本当に綺麗なギリシャとして密かな人気を誇る年に一度会えるかどうかの稀少種! 入荷して暫く経過し有難いことにすっかりMazuriリクガメフードにも順応した状態最高の二匹、 キレーネギリシャリクガメが入荷しました。 今でこそヘルマン一強であるかのように持て囃されてはいますが、 かつてリクガメの定番種といえばギリシャとロシア、 このふたりの存在がなければ今日のリクガメ飼育は成立しなかったのではないかと思われるほど、 大変な功労者として長きに渡り日本中、いや世界中で活躍を続けてきたうちの一方。 今でこそ違和感に直ぐさま気が付ける訳ですが、当時は最も飼い易いビギナー種であるとされ、 仮にロシアことホルスフィールドがそうであったとしても、 リクガメ全種中最も広大かつ多様な分布域を誇るであろうギリシャについては、 その暮らしぶりも多彩であり一通りの扱い方でもれなくフィットするはずもありませんから、 私たちはそこに潜む罠にもっと早く気が付くべきでした。 そんなこんなで目の前に並んでいたいくつかのタイプがひとつ減りまたひとつ減り、 膨大な亜種を抱える点が最大の売りであったギリシャは、 いつの間にか余分な肉が削ぎ落とされたかのようになり、 いつ見ても同じような姿をしたギリシャリクガメへと画一化されてしまったのです。 それは取り扱う人間側が豊かな資源を活用し切れなかったことと、 同時にそういった資源を継続的に利用し続けることが現実的でなくなってしまったこと、 つまり手に負えなくなったり輸出入が困難になったりが重なってこのような結果を招いたと考えられます。 話は戻りますが今日ではファーストトータスとしてヘルマンの力が圧倒的に強くなり、 もはやギリシャの出る幕ではないのかとめそめそ嘆いていたところへ、 その昔世間を騒がせた懐かしのアイテムが突如目前に現れたりすると、 無意識のうちに興奮させられるのは私だけではないと思います。 今回やって来たのはキレナイカの愛称でもお馴染みのアフリカ大陸北部に産するとあるギリシャで、 ここから育て上げるのが楽しみなスモールサイズと、 頭部の妙な黒さがどうしても気になるクールなオスをチョイスしました。 両個体に共通するのは背甲の黒斑がなるべく多く、 そしていずれ細かく散らばってくれるように願いを込めたところ。 フルサイズのワイルドにしばしば見られるあのペインテッドな仕上がりこそキレナイカ、 上品な佇まいの中にあえて野性味を織り込んだ独特のデザインは本亜種ならではと言えます。 動きのキレは申し分なく、どちらもMazuriリクガメフードのみで育てられるよう調整済み。 詳しい育て方の肝は店頭にてお伝えします。 | ||||||||||
|
キレーネギリシャリクガメ (CB・Pr) Testudo g. cyrenaica |





|
|
||||||||
| 以前見かけたワイルドフルアダルトとは全く別物の絶大なる安心感でお送りする史上最高の贈り物! この決して大き過ぎないサイズ感で性別が分かるのも嬉しいまだまだ育て甲斐のある仲良し若夫婦、 キレーネギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 別名キレナイカ、これは亜種小名の学名をカタカナ読みした旧来の俗称であり、 近頃ではこれをキレーネと読み替えて流通することも増えてきましたが、 実はこのキレナイカの根強いファンというのは大昔からリクガメに触れてきた人々が多く、 あの頃に見た懐かしの美しいギリシャというイメージが脳裏に焼き付いているものと思われます。 原産はリビア北東部、アフリカ大陸の北部に分布する亜種とされている彼らの外見的な特徴は、 何と言っても明るい地色にくっきりと描かれたメリハリの利いた黒斑であり、 ギリシャと聞いて真っ先に思い浮かぶ典型的な色柄とは違った、 ぼんやりと色が滲むことのないパキッとしたカラーリングは実に見栄えがします。 頭部や四肢にも黒いチップが多めに散らばることから、 何処か南アフリカのソリガメにも似た風合いが見て取れ、 陳腐な表現ではありますが全体に高級感の漂うちょっと大人のギリシャという感じがします。 学術的には膨大な数の亜種を抱えることになっている本種ですが、 現実的にペットとして流通し外観から区別できるものはごく僅かで、 俗にイベラと呼ばれるタイプとシリア周辺から送られてくる定番のアラブぐらいですから、 こんなにはっきりと区別できるニューカマーと対面できるだけで嬉しくなるのは私だけではないでしょう。 数年前には同名のインボイスですっかり成熟したフルサイズの本亜種が輸入され業界を騒がせましたが、 あまりはっきりとは申し上げたくないものの芳しくない結果が続き、 当時すっかり胸を痛めてしまった方もいつかはリベンジとお考えでしょうから、 まさに今がその時だと気持ちを新たに再び奮起して頂ければ幸いです。 今回やって来たのはCBとして輸入された安心サイズのキレナイカより、 既に性別が明確に判別できる握り拳大のオスとメス。 一般論ではありますが到着した瞬間から両目の開き具合と動きのキレが段違い、 暖かい気候にも恵まれ無駄に鼻水を垂らすこともなく、 お陰様で今日まで穏やかなひと時を過ごしてきました。 Mazuriリクガメフードへの完全移行は流石にもう少し時間がかかりそうですが、 既に葉野菜や野草を交ぜた状態のフードであれば無遠慮にガツガツと食べていて、 体重の増加と共に楽々育てられるよう自ずと仕上がっていくでしょう。 泣いても笑ってもワンペアのみ! | ||||||||||
|
キレーネギリシャリクガメ (♀) Testudo g. cyrenaica |





|
|
||||||||
| 十年以上待ったと言う古参のマニアが歓喜した全亜種中屈指の美しさを誇る憧れのキレナイカ! 輸送中の発泡スチロールを破壊したとの逸話を持つパーフェクトコンディション、 キレーネギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 昨今の市場におけるリクガメを取り巻く環境を見るに、 良くも悪くも流通が安定し定番の種類がいつでも入手できる、 そんな雰囲気が窺えるのは一体いつの頃からなのでしょうか。 かつてはペットとして飼育してはならないとまで叫ばれたリクガメたちが、 今日では一般家庭で楽しまれる有力な選択肢のひとつとして数えられるようになり、 下手をすればビギナー向け、 初心者にお勧めなどと称し積極的に販売される風潮さえ見受けられます。 一部の種類は人工飼育下での養殖がほぼ確立され、 実際に初期状態の良いものが年間を通じてリーズナブルに入手できるようになりましたが、 その一方ではただ単に金額が安価だと言う理由で敷居を下げ、 決して容易に育てられるとは言えないものも混在しています。 いわゆるギリシャリクガメは広大な分布域と数多くの亜種を抱えているものの、 その大部分が現実的に姿を見かけることすら叶わないために、 表面上ただのギリシャとして認識されてしまうのは本当にむず痒いのですが、 まだ分類さえもはっきりとしていなかった時代にタイプスリップできるのならば、 愛好家にとってこの上なく素晴らしい楽園が広がっているのでしょうか。 今回やって来たのは十年単位で世界中がその流通を待ち侘びた、 豹柄の甲羅に見覚えのある方も多いリビア原産のキレナイカ亜種。 並のアラブかせいぜいイベラぐらいしか目にすることの無いこのタイミングで、 目玉の飛び出そうな稀少価値の高い本亜種のお目見えに、 ごく一部の人々が心の中でガッツポーズをしたことは言うまでもありません。 ご存知の通り数か月前に現地の動物園よりリリースされた群れからの一匹で、 背中のホワイトマーキングがその生々しさを如実に表現しつつも、 暫しの時をここ日本で過ごし随分シャキッと生まれ変わった、 来日直後とは比べ物にならない良好な状態で入手することができました。 当店へ運ばれてくる際に一重目の段ボールをぶち壊し、 外箱の発泡に前肢で穴をあけて顔を覗かせていたのはここだけの話。 夢にまで見た国内CBを拝むべく是非とも貴方のコロニーに加えてあげて下さい。 | ||||||||||
|
ギリシャリクガメ (イラン産・国内CB) Testudo graeca ssp. |





|
|
||||||||
| 一般流通ではまず見かけないハッチサイズ、そしてマニアックなロカリティ付き国内CB! 反則的な可愛らしさと大きさに比例しない安心度で生まれたてのリクガメを楽しみましょう、 イラン産のギリシャリクガメが入荷しました。 今更改まって紹介することの無いほど多くのファンに親しまれるリクガメ入門の代表種、 何処で何を調べても初めて飼う方には必ず勧められるであろう極めてメジャーな存在で、 全国各地の至る所で販売され飼育者数も相当に多いのではないかと思われます。 その大部分は単に無印のギリシャリクガメと呼ばれそれ以上追求することはありませんが、 実際にはとても広大な分布域とそれに伴う豊富なバリエーションを持ち、 本来であればその全てが研究対象となり謎が明らかにされることが望ましいのでしょう。 しかしながらペットトレードの現状や棲息地の情勢なども考慮すると、 いわゆる稀少性は少なくとも全体からは感じられませんし現地調査もままならないでしょうから、 今後も現地でかき集められた程良いサイズの個体がコンスタントに輸入されて来るままかもしれません。 同属でもヘルマンリクガメのヨーロッパCBについては、 特にニシヘルマンの産地情報が添えられた幼体をこの頃になって見かけるようになり、 同じ繁殖を目指すのであればより野生に近い状態を再現するというのも一興です。 大概がアラブギリシャではないかと推察される状況で個体毎の形質差を楽しむのも面白いのですが、 年々カメの輸出入が厳しくなることを考えると、 こうしてよりクリーンな繁殖個体が市場に出回った方が有意義な一面もあると思います。 今回ご紹介するのはイラン産として輸入されたとあるペアが日本に到着しておよそ三年半、 遂に産卵し見事孵化まで至った成果の一部である大変貴重なベビー。 イランに棲息するとされるギリシャは三亜種ほどおり、 正直この場で明確な亜種までを明らかにすることは不可能に近いのですが、 両親の特徴として最も目立ったのは甲長20センチにも至らず小振りなまま子孫を残したという点で、 少なくとも大きく育つことの無さそうな小型個体群である可能性が高いと言えます。 雌雄いずれも片手に乗せられるほどの小ささでしたから、 亜種云々以前に室内でも無理なく飼い切れる所に魅力があり、 種親の色彩はベージュに近い明るめのブラウンで、背中が高く盛り上がり意外と迫力ある姿に映りました。 普通に売られているギリシャはたとえ小さくとも5センチほどはありますが、 国内で繁殖された個体であればこの大きさでも決して不安要素はなく、 二匹とも葉野菜とMazuriリクガメフードに好き嫌いなく食らい付いています。 小さなB個体は極小の多甲板あり、 どちらもお腹パンパンでコンディション抜群なので初めての方にも強烈にお勧めです。 | ||||||||||
|
ギリシャリクガメ (アダルト・♂) Testudo graeca |





|
|
||||||||
| なにやらノスタルジックな雰囲気を醸し出しているのは、 お客様長期飼い込みのギリシャリクガメ・オスの入荷です。 何処か懐かしい感じなのは写真だけでなく、実は10年近く大切に飼い込まれていた貴重な個体で、長年メスがいなかったのでしょうか、 素焼きのシェルター相手に毎晩ハッスルしています。甲羅は末広がりの変わった形状をしており、 頭部は白く色抜けしたおもしろい個体です。 亜種は不明との事でやってきましたが、長期に渡って飼われている事から甲長はMAXサイズでしょう。 もし同じタイプのメスをお持ちの方はこの機会に如何でしょうか。 餌食いはとても良く葉野菜からMazuriリクガメフードまで何でも大好きな様です。 | ||||||||||
|
ギリシャリクガメ (ブラック・♂) Testudo graeca |





|
|
||||||||
| 見た目も中身もとことんギラついた即戦力! ケージに入れるや否やいきなり仕事してくれます、 飼い込みのギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 店頭に到着し箱から出してとりあえず同サイズのオスギリシャが入ったケージに入れてみたら、 ちょっと目を離した隙にもうマウントしていました。どうなるかと暫く一緒にさせてみましたが、 さすがに乗っかられたオスも疲労感を隠せない様子だったのですぐに別にしました。 しかしながら積極性がウリの地中海リクガメとは言え、 同種のオスでしかも同じ大きさの個体に参ったを言わせるのですから相当な欲求の持ち主なのでしょう。 この異常なまでにギラギラとした甲羅も、 ドリアンもびっくりの長く伸びて鎧の様になった鱗も、 全てはこのオスのパンクな性格を表していると言っても過言ではなさそうです。 また不思議なことにこの個体は腹甲の後葉部にある蝶番の稼働域が妙に広く奇妙です。 今回当店には亜種不明で入荷し、 恥ずかしながら亜種判別までには至りませんでしたがもしかしたら、があるかもしれません。 ちょっと売るのがもったいないぐらいかっこいいので価格は強気です。 フルブラックに近いギリシャをお探しの方は多いと思いますが、 その他にも所々から魅力を感じさせてくれる素晴らしいオンリーワン個体です。 | ||||||||||
|
ギリシャリクガメ (♀) Testudo graeca |





|
|
||||||||
| ちょうど手の平サイズのとても可愛らしいギリシャリクガメ・メスの入荷です。 地中海リクガメの仲間では比較的安価で見た目も愛らしい、リクガメの飼育を始めてみようかなと思わせてくれるカメです。 最大20cm程と大き過ぎず小さ過ぎず、 この仲間に共通する誰が見ても可愛い顔つきが人気です。 よく動き餌も葉野菜からMazuriリクガメフードまで選り好みせず、ビギナーの方にもオススメです。 これからの暖かい季節には外で放し飼いしてみるのも一興、四肢で体を持ち上げてトコトコ歩く野性本来の活発な姿が観察できるでしょう。 近縁種ヘルマンとの違いは後足付根の突起の有無で、 有る方がギリシャです。初めての方には安心して飼って頂ける様サポート致しますのでお気軽にお問合せ下さい。 | ||||||||||
|
ギリシャリクガメ (フルアダルト・♀) Testudo graeca |





|
|
||||||||
| 大満足メガ盛りサイズ! 長期飼い込みのギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 ギリシャもヘルマンも、この手のリクガメはフルアダルトのオスは時折見かけることがありますが、 メスに関しては少なくとも飼育されている個体はいると思いますがこうして流通することは極めて稀だと思います。 もう少しで20cm台に届きそうな勢いのその存在感たるやまさにビッグママ。 しかもこの個体は単に大きいだけではなく、甲羅表面のテリや黒味の強い体色がより重厚な雰囲気を演出し、 視覚に訴えるインパクトが実に強烈です。 小型種という文句が自慢のこのカメ、MAXサイズに近くもなればそのようなイメージはすっかり消え失せ、 荒々しい鱗の一枚や長い年月を掛けて刻まれた甲板の線の一本にこれまでの生きた証を感じ取ることができるでしょう。 当店でも盛り過ぎて困った本種のオスを何度か扱ってきましたが、 その度にメスはどこかにいないかと探し求めやっと出会うことができました。 現在ロンリーな青年を飼われている方、 あの若さに任せた激しい求愛にびくともしなさそうなこの巨体と一緒にするほかありません。 亜種は流通量から言えばアラブギリシャの可能性が高いですが不明としました。お早めにお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CBベビー) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| ゴルフボールにも満たないミニマムサイズながらてくてく歩く元気いっぱいの稀少亜種! そもそもこんなに小さなリクガメをペットとして飼い始められること自体が素敵過ぎる、 イベラギリシャリクガメが入荷しました。 野外で冬眠できるギリシャリクガメとして名を馳せた根強い人気を誇るイベラ亜種、 別名トルコギリシャリクガメとも呼ばれる知る人ぞ知る隠れた銘種ながら、 実際に見かける機会はごく僅かで知名度ばかりが先行してしまっている感も否めません。 今日のホビー界において圧倒的な支持率を誇るヘルマンと同等の性能を持つ、 つまり初めての人にとっても飼い易いと太鼓判を押せる優れたスペックを持ちながら、 商品として現実的に市場流通しないのは本当に勿体無いと思います。 しばしばヘルマン派とギリシャ派に分かれ、 例えば顔立ちや全体のシルエットなど好みについて話し合われることもありますが、 野生由来のアラブギリシャは決してビギナー向けとは言えないものの、 こちらイベラであれば幸いなことに手に入る殆どの個体がCBであるがために、 それこそヘルマンと同じ土俵で競わせても全く遜色が無い所も大事なポイント。 よく図鑑や資料などに恐ろしい最大甲長が書かれていることでも有名ですが、 それはあくまでも一部の大型個体群に限った話であるらしく、 サイズ感もいわゆるチチュウカイリクガメの平均的な範疇に収まるため、 あらゆる面から見てもなかなか見逃せない存在感を発揮しているのです。 今回やって来たのは今後コンスタントな繁殖が熱望される国内CBより、 今年生まれの幼体がある程度しっかりするまで育てられた二匹。 前述のヘルマンでも現地からの輸入ものについては流石にここまで小さな状態で見かけることは無く、 リクガメのベビーとはこんなに小さかったのかと驚かれる方も多いと思います。 それでいて海を渡って来た訳では無いので初めから躍動感の塊のような動きを見せ、 元来強健なイベラとあって初期導入の環境にもうるさくないのは本当に喜ばしいです。 ブリーダー曰く寒冷地で無ければ現状のサイズでも屋外越冬できるとのことですが、 無理にトライする必要はありませんのでそれだけ丈夫だと認識しておきましょう。 本格的な寒さを迎える前にリクガメデビューを検討されている方へ、 真冬の環境にまで配慮した飼育セットも含めてご案内致します。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (マケドニア産・ベビー) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| ギリシャを飼うならイベラ、と決めている方もいらっしゃると思います。 嬉しいロカリティ付きCB、イベラギリシャリクガメ・マケドニア産が入荷しました。 多くの亜種が含まれることで知られるギリシャリクガメ、 本亜種は古くはトルコギリシャという名前でも親しまれてきました。 近頃は無印のギリシャとして販売されているのは殆どがアラブギリシャであることが多く、 棲息地から寒さにはあまり強くありません。一方こちらのイベラは日本と似た気候のヨーロッパを中心に棲息し、 そのため耐寒性に優れることから通年屋外飼育の成功例も多く、根強い人気を誇っています。 地中海リクガメの仲間は小型で寒さに強い特徴から”庭でリクガメを飼う”という夢を果たしてくれる可能性を持っていますが、 ことギリシャに関してはきちんとした亜種判別のもとでさらにその亜種の特性を知らなければなりません。 しかし今回は自信を持ってお出しできる個体です。 状態については輸入されてきた頃より二回りほど成長線も出ているようで、 よく食べよく歩きよく出す模範的な健康児です。将来を見据えて大切に育てて下さい。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CBベビー) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 安心の日本生まれでありMazuriリクガメフードで破裂しそうな抜群の食欲が嬉しい艶ピカベビー! 実際に毎年野外で越冬している両親から得られた本当に冬眠させられる寒さに強いタイプのギリシャ、 イベラギリシャリクガメが入荷しました。 何でもその昔ギリシャリクガメとして流通していたのはこちらの方が主流であり、 昨今無印のギリシャとして紹介される亜種アラブについてはまだ歴史が浅いと言いますか、 十年単位のカメキャリアを持つ方にとってはまだまだ新しいものに感じられるかもしれません。 ただしリクガメがペットとして本格的に普及し始めた頃にはもうアラブにすり替わっていて、 ギリシャは熱帯のリクガメであり冬に冷やすなど以ての外という考えの方が一般的ですから、 少なくともビギナーの方々にとって耐寒性のあるギリシャというのは違和感でしかないと思います。 例えば今時分流行りに流行っているヘルマンなどは、 原産地の気候から日本の冬を外で越せるだけのスペックを有していますが、 同じ理由でこのイベラと呼ばれるタイプのギリシャもまた同様の技を持っています。 リクガメの愛好家にとって自分の家のお庭でカメがお散歩しているという光景は、 それこそカメを育てる上で一番期待していた夢のシーンのひとつではないかと思われますが、 それを屋内に取り込むことなく春夏秋冬続けていられるという状態もまた、 日本に暮らしていながら実現できるとすれば夢いっぱいの成果であり、 そんなわがままに付き合ってくれる種類もそれほど選択の幅がありませんから、 貴重なキャラクターとして今後末永く活躍し続けてくれることでしょう。 今回やって来たのは名前ばかりは有名でもなかなか商品として流通することが少ない、 かねてよりファンの間ではイベラと呼ばれ続けている即ち寒さに強いギリシャの国産ベビー。 変な話ですが一匹のギリシャをパッと出されても外観だけでその性質を全て判別するのは非常に難しく、 それこそ寒さに強いかどうかなどやってみなければ分からないというのが本音なのですが、 この子供たちの両親が現実に冬眠できているとなると、 それほど強力な付加価値も他にはないということです。 サイズだけ見ればすごく小さなカメに感じられるかもしれませんが、 そのダッシュ力と餌に対する執着心を目の当たりにして頂ければ、 漠然とした不安は忽ち強固な安心感へと変わるはずです。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (スロベニア産・ベビー) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 柔らかな乳白色をベースにギリシャらしい品のある模様が浮かび上がった粒揃いの美個体が大集合! 冬眠ができるリクガメとして数少ない選択肢の中でもプチレア感のある人気種が状態抜群の安心サイズにて、 スロベニア産のイベラギリシャリクガメが入荷しました。 その昔ギリシャリクガメと無印で呼ばれていたのはこのタイプだったそうですが、 かれこれ十数年前にはテレストリスことアラブギリシャに主流が置き換わり、 熱帯から亜熱帯のリクガメとして扱われそれが新たなスタンダードとなりました。 最近ではロシアやギリシャよりもヘルマンの方がずっと有名であり、 ビギナー層に対しても強くアピールされていることから人気もシフトし始め、 CB化されたことの強みも生かし下手をすればヘルマン一強のような様相を呈してきましたが、 そうなってくると懐かしのギリシャに対しても思い入れが募ってくるのは人の性でしょうか。 言うまでもなくヘルマンにはヘルマンの、ギリシャにはギリシャの良いところがあり、 それらが重なり合う領域もあればまるで異なる領域もある、 そんな中でヘルマンにあって多くのギリシャにはないもの、 そのひとつが耐寒性という実はかなり重要な特殊能力だったりするのかもしれません。 つまり外見はギリシャの方が好みでも寒さに強いという理由でヘルマンを選んでいる、 そんな一定の購買層が日本のリクガメファンには必ず存在するはずであり、 もしも寒さに強いギリシャがいればと一見ありもしない妄想を膨らませている方がいたとすれば、 それが現実に可能なのだということをいち早くお伝えしたいと考えるのが私の性なのです。 今回やって来たのはヘルマンと同等の耐寒性を持つことで知られるトルコギリシャことイベラより、 何年ぶりの出来事でしょうか、ごくごく久しぶりに輸入された海外産の繁殖個体たち。 最近ヘルマンの生産地のひとつとして知られるようになったスロベニア、 イタリアの東側、そしてオーストリアの南側に位置するこの国は、 年間の気温の推移が日本と殆ど変わらないため、 我が国においても通年屋外飼育が可能であると考えられます。 ギリシャという素材自体が強健であることに加え、 こんなにフレッシュなリクガメのベビーもなかなか見られないと言いたくなる、 とにかく心身共に優れた素質に恵まれた三匹の安心サイズベビーはまさしく鬼に金棒。 既にMazuriリクガメフードにもバッチリ餌付きそれのみでも育てられ、 飼育方法さえ間違えなければ誰もが羨むツヤピカギリシャを創り出すことも夢ではありません。 お好みで明暗のカラーが選べるうちに是非。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CBベビー) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 巷で旧イベラと呼ばれている個体群の両親より得られた正真正銘の純血コーカサスギリシャ! その付加価値は血統管理に留まらずリアルに屋外越冬を可能にしてくれるスペックもまた嬉しい、 イベラギリシャリクガメが入荷しました。 育て易いと評判のヘルマンやホルスフィールドと同じように野外で冬眠できるギリシャがいるらしい、 ある一部では昔から知られていた何のことはない当たり前のような話だったものが、 今日ではそれを何にも代え難い大きなメリットとして捉える傾向が強くなり、 しかしながらペットとしてのリクガメが需要の高まりを見せるその過程では、 かつて冬眠を可能にしていたギリシャの一タイプが流通量を次第に減少させ、 噂が噂のまま消えてなくなりかねない状況へとなりつつありました。 最近ではその状況を見かねてなのか、 本当に長年飼育されていたのであろう古株の種親から得られた子孫が珍重されたり、 海外から輸入される繁殖個体を元に再ブリーディングを試みるような動きも見られ、 とにかく高い意識を持って入手しようと積極的に動かなければ、 なかなか目の前には都合良く現れてはくれない稀少種だという認識が高まっているのです。 十年以上も遡ればかつてのヘルマンはビギナー向けと言うにはやや高価であり、 それも現実的に個体数が稼げなかったことが最大の要因と考えられていましたが、 昨今では大規模な養殖の成果が相場の安定化を生み出したことを思えば、 ゆくゆくはこのイベラも十分なニーズに支えられ似たような道筋を辿るのでしょうか。 いずれにしても最初のきっかけ作りには愛好家らの底力による働きかけが必要不可欠であり、 耐寒性を備えたギリシャがごく当たり前にありふれることなど現状では夢のまた夢ですが、 良いものは良いと後世に残そうとするアクションはいつ見ても本当に気持ちの良いものです。 今回やって来たのは元々EUCBとして日本に到着した幼体数匹が、 成長の末見事に雌雄が分かれ遂に繁殖にも成功した貴重な国内CBたち。 幼体の時点でカラーリングを含む容姿がそれらしいのも然ることながら、 やはり両親に当たる個体がそれぞれ共に通年屋外飼育されている事実に大きな魅力を感じます。 ちなみに昨年まで当店に入荷していたイベラの兄弟たちとは異なるラインなので、 血筋を分けるという意味でもこの出物は見逃せません。 早くもMazuriリクガメフードに餌付き体重も日に日に増えていますので、 初めての方でも安心のベビーです。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CB・S) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 親個体の管理から幼体のコンディションに至るまで全てが恵まれているハイスペック三兄弟! 昨年の冬を屋外で乗り越えたと言うまさかのプロフィールにも驚きを隠せない、 イベラギリシャリクガメが入荷しました。 日本の野外で冬眠できるギリシャリクガメがいるらしい、 そんな話が噂になるよりもずっと前から私たちはその存在を微かに感じ取り、 実際に目の前のリクガメを外にほったらかしていたのは何も迷信ではありません。 最近では一般家庭においてリクガメをペットとして迎え入れることが極めて現実的となり、 その現象は半ばブームとして捉えられることも珍しくは無いようですが、 その感覚からするとまさか水槽を飛び出してそんな危険に晒すなんてと驚かれる方も少なくないでしょう。 しかしながら元を正せば本来は太陽と共に暮らしているはずの生き物であり、 お日様の光を体いっぱいに受けて健康な生活を維持するのがあるべき姿ですから、 庭に一歩出ればそこにリクガメが歩いている光景は全ての愛好家にとっての憧れと言っても過言ではありません。 もちろんその願いを叶えてくれる種類が他に全く見当たらない訳ではありませんが、 決して贅沢とは言えないその狭い選択肢の中で選ばせてもらえるのであれば、 これほどまでに嬉しいことは無いと思います。 今回やって来たのは耐寒性に優れたタイプとして昔から長らく注目を集めている、 別名トルコギリシャリクガメとも呼ばれるイベラ亜種の国内CB。 名前ばかりが先行して有名になってしまったのも時に考えもので、 いくら図鑑やインターネットで情報を拾えたとしても実際に流通する機会は滅多に無く、 時に海外からの輸入が厳しくなった昨今においてはそれがより顕著になっています。 また外観から亜種や地域個体群の特定が難しい種類でもありますので、 仮にイベラと言われた所でその裏付けが非常に困難な訳ですが、 この三匹は特に温暖でも無い地域で通年屋外飼育されているペアから殖やされた、 評判通りの特徴を有することが何よりも安心の国産ベビーです。 冒頭でも触れましたが生まれたその年にいきなり過酷な現実を味わっていると言うのもミソで、 体の丈夫さは折り紙付き。 ブリーダー曰く常日頃から無加温でも飼育可能とのことですが、 言い方を変えれば普通の飼い方で状態を崩し難い強健さを持ち合わせているとも解釈でき、 初めてリクガメを育てる方にとっても素晴らしいパートナーになること請け合いです。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CB・S) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 昨年に引き続き今年も相変わらず元気な姿で登場してくれた今やかなり稀少なギリシャの珍しいタイプ! 亜種の有効性云々といった難しい話よりもまずは屋外越冬が可能なそのスペックを称賛したい、 イベラギリシャリクガメが入荷しました。 リクガメなる生き物はその名前にこそカメであると付けられているものの、 実は多くの日本人にとって馴染みのある水棲ガメの仲間たちとはまるで異なった、 もはや別次元の生物であると捉えた方が懸命なほどに奇抜な存在であり、 我が国においても古くから飼育動物として商業的な流通が行われているものの、 一般家庭できちんと育てられるようになったのはここ十数年の出来事ではないかと言われています。 かつて日本を代表する高名な研究者のひとりであったある人物により、 リクガメは飼育されるべきではないとまで言わしめたその難解な暮らしぶりに、 今日までに多くの愛好家らが楽しみと苦しみを同時に味わってきました。 そのような過程を経て今日のリクガメを取り巻く諸般の事情は大きく様変わりしており、 従来では明らかに野生個体の採集および輸出によって支えられてきたこの業界も、 最近ではペットとして飼われるために養殖された幼体が中心となって積極的に扱われるようになり、 そんな表面上では分かり難いちょっとした変化によって、 私たちが日頃目にするラインナップも知らず知らずのうちに変わってきています。 ここにご紹介するギリシャリクガメなどはまさに定番中の定番キャラクターであり、 一時その知名度では右に出るものはいないとまで考えられていたほどですが、 年を追う毎に強まる諸々の煽りを受けてか次第に安定供給が難しくなったと見え、 その反動もあってかこうした繁殖個体がお目にかかれるようになると、 それこそ国内の飼育者が長年温め続けてきた底力のようなものが感じられて止まないのです。 今回やって来たのは最近流行りのヘルマンなどと同様に温帯に棲息し、 日本の気候にも随分と馴染み易いことで高い評価を得ている、 同じギリシャでも一味違う知る人ぞ知るその名もイベラギリシャ。 冒頭でも触れた通り寒冷地を除けば一年を通じて野外にて飼育できる点が強力なアピールポイントで、 これらベビーに見える四頭についても既に昨シーズンの冬を生まれて間もなく屋外で越しているため、 その高い性能は早くも証明されているという訳です。 毎年探されているファンの方は必ずいらっしゃるのですが、 一年の間に何度も入荷するような代物ではありませんから母数の多いうちに一足早く選んでしまいましょう。 全ての個体がもれなくMazuriリクガメフードオンリーで育てられる、 準備万端の状態でお待ちしております。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (EUCB・S) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 目を凝らしてよく見てもつい間違えてしまいそうなニシヘルマン風イベラ! バリエーションのデパートだからこそ成せる業の傑作です、イベラギリシャリクガメが入荷しました。 地球上に存在するリクガメという生き物の殆どが黒色や黄色を主体としたカラーリングで彩られているというのは、 今までいくつもの種類を目にしてきた方であればより身に染みて感じられることでしょう。 その理由は考えればいくらでも思い付きそうなものですが、 やはり多くの種類が似通った野生環境で暮らしていることに起因するのかもしれません。 もちろん中には変わった着色が実践されるケースも見られますが、 そこにあまりにも奇抜な色使いは認められず基本的なルールはある程度守られているようです。 本種を含むチチュウカイリクガメ属もその例に漏れず、 いつしかビギナー向けの定番種ともなっているため見慣れた印象が強いのですが、 ギリシャが持つ特徴のひとつに個体差の豊富なことが挙げられ、 中には亜種や種の範疇を飛び越えてその個性を発揮する個体がいてもおかしくはありません。 今回やって来たのはイベラという亜種、確かに黒がちになるものや黒斑が大きく目立つものが頻出する傾向は見られますが、 この個体に関してはそのデザインをヘルマンリクガメに似せてしまったというのが一番の問題です。 しかもご丁寧に亜種まで特定されており、 背甲の大部分に各甲板を跨ぐように連なった模様がはっきりと表れた姿はまさしくニシヘルマンそのもの。 近頃現地から輸入されてくる典型的なタイプに程近いというのも憎い演出で、 同じ水槽内に並べて入れておくと必ず間違われるという実例も証明済みです。 意図的に仕込んでおいてこんなことを申し上げるのも失礼ですが、 用いられる色が近いと見慣れていなければ雰囲気の違いまで把握するのは難しいのでしょうか。 一発で区別する方法としてはお約束の後肢付け根にある一対の突起を確認すれば良いのですが、 発しているオーラを的確に察知することで何となく見分けることも可能です。 ヘルマンは受けた光を吸収するマットな質感を持ちますが、 対するギリシャは光を反射するどこかギラついた様子が伺え、 特にイベラについては体の鱗がメタリックに輝く個体を多く見かけます。 この黒光りがヘルマンの柔和な優しさに対するギリシャの切れの良い格好良さを演出しているのです。 未だに野生個体も多く流通する種類ですから、 もはや普通のギリシャでは飽き足らない方にとって変わった雰囲気を楽しむためのオンリーワンとなることを期待しています。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CB・S) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 決して大きいとは言えない体に二年分のエネルギーがぎっしり詰め込まれた貴重な国内CB! 弱冠このサイズにして既に屋外越冬を二度も経験しているスペックの高さが全てを物語る、 イベラギリシャリクガメが入荷しました。 ギリシャリクガメと言えば我々日本人がもう何十年もお世話になりっ放しの、 いわゆるビギナー向けのリクガメとして最高峰の知名度を誇る超有名なキャラクターで、 それこそ昔はリクガメそのものが上手に飼育できなかった時代でしたから、 当時の活躍ぶりと言えば相方のロシアと肩を並べるほど知らない人はいないぐらいの定番種でした。 今日では少しずつ解明されようとしている数多くの亜種も過去に遡ればチラホラ流通していた記録があり、 しかしながらそれらの殆どは失われた遺産として忘れ去られようとしていますが、 その中でもごく一部のものは亜種名や産地と言った情報が付与された状態で、 系統維持が実現しているケースも無きにしも非ずなのです。 かつての分類方法が見直され消滅してしまったとの噂もありながら、 未だに繁殖個体が手に入る唯一の存在と言っても良いのが、 ここにご紹介するイベラギリシャと呼ばれるタイプ。 もはや亜種として認められていなくとも関係無いと言わんばかりに、 少なくともここ日本ではよく知られたビッグネームのひとつで、 簡単に言えばまるでヘルマンなどのように野外で冬眠させることができる、 とても耐寒性に優れたギリシャのことを指していると理解して頂いて差し支えありません。 そういった前提が無ければ闇雲に挑戦させられない大切な儀式ですから、 並のギリシャとは一線を画すイベラならではの付加価値として認められているのです。 今回やって来たのは昨年に引き続き取り扱いが実現した、 親子共々驚きの通年屋外飼育を実践し続けているブリーダーより譲り受けた、 早くも三年目に突入している素晴らしい兄弟たち。 誠に残念ながら今年の繁殖状況は芳しくなかったそうで諦めムードが漂う中、 無理を言って手元にキープされていた最後の二匹を分けて頂きました。 シルバー調のモノトーンに近い涼しげなカラーリングが如何にもな雰囲気を演出し、 野草主体の自然任せな育て方がナチュラルな外観をつくり出した、 見た目も中身も良質極まりない付加価値のたっぷり盛り込まれた素敵な贈り物。 名前だけは有名ですがなかなか狙って入手することの難しい珍種です。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (国内CB・S) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 後から追加でやって来た兄弟も含め、ラスト三匹が極めて順調な成長ぶりを見せています。 当店ならではの取り組みとして、食事のほぼ全てをMazuriリクガメフードで賄っているのですが、 何処に出しても恥ずかしくないナチュラルなフォルムが実現できていると思います。 順調に育てられれば今年の冬から屋外越冬も可能な、安心のスモールサイズです。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (イーストアナトリアンジャイアント) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 外見は難なく成長しているように見えて内には壮大なパワーを秘める巨人と呼ばれた噂のレアロカリティ! 冬眠が可能なことに加えて最も大きくなるとされる人気のタイプです、 イーストアナトリアンジャイアントが入荷しました。 まずはその呪文のようなワードから読み解いていくことにしましょう。 初めはイースト、この場合はパンやお酒に欠かせない酵母ではなく、 方角を表す東と言う意味で用いられていますから、 自動的に棲息地であるヨーロッパ、つまり東欧のことを指しています。 そしてアナトリアンとはアナトリアのないしはアナトリア人ということなのですが、 普段の私生活ではその言葉にぶち当たったり、 それを知らなかったがために途方に暮れたりすることもまずないでしょう。 本亜種は別名トルコギリシャとも呼ばれていますが、トルコ共和国は時にアジア、 時にヨーロッパと両方の顔を持つため、贅沢なことにひとつの国がふたつの大州に跨っており、 小アジアと言われるアジア側の地域がお待ちかねのアナトリア半島に当たるのです。 言葉の綾のようで面白いのが、 イーストから連想される東ヨーロッパはアナトリアに到着した途端に西アジアへと見解が変わってしまいますから、 何か矛盾しているような気もしますがそこはご愛嬌でしょうか。 そして最後はジャイアント、 この趣味を続けているとついこの単純明快でストレートな言葉に打たれ弱くなってしまいますが、 兎にも角にもギリシャリクガメの中で最も大きくなる地域個体群であるという見方が強く、 実際に欧州ブリーダーの間では明確に区別されているそうで、 種親も片手で持ち上げるのがやっとなほどに巨大であるそうです。 今回やって来たのは2011年のベビーが極めて順調に育った飼い込み個体。 どうでしょうこのツルンとしたフォルム、 紫外線量、運動量、 毎日の餌の栄養バランス、適度に湿度が保たれた良好な環境、 ずらっと挙げたこれらの要素は全て前飼育者がこの個体のためを思い特別気を遣ったポイントで、 カメもその期待に応えるかのようにベストな仕上がりをキープしています。 甲羅自体がしっかりと出来上がっていない幼体時にはどうしても歪みなどのトラブルが起きやすいのですが、 基盤がしっかりと固まってきたこれぐらいの時期になると、 飼い主が変わり新たな環境に移っても良好なコンディションの引継ぎは決して難しくありません。 性別は未だ確定には至りませんが、 メスになってくれればより大きくなる楽しみが増えて嬉しいのではないかと思います。 全体的に黄色が目立ち色味はバッチリ、 頭を目一杯持ち上げ愛嬌を振りまきながらトコトコ歩き、 人目も憚らず無我夢中で餌に食らい付く可愛いやつです。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (イーストアナトリアンジャイアント) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| まるで呪文か必殺技のような長い名前に込められた爆発的成長エネルギーをとくとご覧あれ! 巷では30センチを超えるとさえ噂される同じギリシャでも特別大きなレアロカリティ、 イーストアナトリアンジャイアントのイベラギリシャリクガメが入荷しました。 とりあえずその余りにも長ったらしいネーミングを丁寧に分解していくと、 現在のトルコ共和国のアジア地域に該当する部分をアナトリア半島と呼び、 その更に東側へ棲息する地域個体群のことを指す通称名なのですが、 これがギリシャリクガメにしてはやたらと巨大に成長することが知られており、 冒頭でも触れた通り例えば30センチ以上に育ってしまうのではないかとされ、 ひとまず只者では無いことを示す説明としてこのように呼ばれています。 ある種の品種名のようでもありますが、 間違っても飼育下で作出された突然変異だとかそういった意味合いでは無く、 あくまでも野生の状態で自然に分布しているものを系統維持しているだけの話なのですが、 遠く離れたここ日本に居ながらにしてこれほどの特殊な品を入手できること自体、 如何に大変な労力を伴い如何に幸せなことであるか改めてその喜びを噛み締める思いです。 数多くの亜種に恵まれた本種も残念ながら外見のみでそれらを判別することは極めて困難であり、 言い換えればその繊細な部分を血統管理により付加価値に変えてしまう行為こそが、 極めてマニアックな嗜好であって強く好感が持てる要素だと思います。 今回やって来たのは並のギリシャであればそろそろ終着点に差し掛かろうと言うところを、 更なる成長の余力を十分に残した状態で日々呑気に餌をバクバク平らげる、 同種内では最大級の体躯を誇るご存知イーストアナトリアンジャイアントの飼い込み個体。 もはやブランドと化した同タイプの魅力は既にご案内の通りですが、 体調に無理のない範囲で基本的には屋外飼育を実践されていた一匹で、 ほぼ凹凸の見当たらないツルンと高く盛り上がった甲羅からは、 まるで育て主に対する恩返しの念が込められたかのような美しさが感じられます。 亜種としてはいわゆるイベラと呼ばれるタイプに該当するはずなので、 その耐寒性の高さについても興味深いところですし、 ひとまず難しいことは考えずに何処まで大きく育ってしまうのか暖かく見守っていきましょう。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (ブラック・♂) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 妖しい黒光りがやめられないとまらないガンメタリックボディ! 甲羅から地肌までどこもかしこも漆黒に染め上げられた極上のクオリティです、 イベラギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 チチュウカイリクガメ属のみならず、 リクガメ界を代表するポピュラー種として長きに渡り親しまれているギリシャリクガメ。 地中海でギリシャと言うと実に紛らわしいのですが名前の由来はギリシャに住んでいるということではなく、 ギリシャの織物に見られる模様が甲羅の外観と似ているからなのだそう。 広い棲息域を持つことから多様な亜種分類が認められ、欧州から中東にかけて一大勢力を築き上げてきました。 その中のひとつ、 トルコギリシャとも呼ばれる本亜種は黒海とカスピ海に挟まれたアゼルバイジャンやグルジア、 ロシア南西部と北方に分布するため耐寒性に優れていると言われています。 テレストリス、つまりアラブギリシャ以外はまともに認知されておらず殆ど区別されることもありませんが、 イベラは国内でも繁殖が為されるほど確かな血統が維持され、 一風変わったギリシャとして愛好家の支持を集めているようです。 少々マニアックな雰囲気を味わえるのも心地良いのですが、 今回はそんな生易しい説明では物足りない衝撃的な一匹がやって来ました。 確かに時折黒味の強いタイプを見かける亜種ではありますが、 ここまで大胆に自己を主張して果たして許されるものなのでしょうか。 黒いリクガメと聞けば真っ先にゾウガメが思い浮かぶ、それは多くの方々が持つ共通認識かと存じますが、 その既成概念が入り込む隙を一切与えぬ凄まじい勢いをこの個体からは感じます。 ただただ黒一色に仕上げられているというだけでかなりのポイントを稼いでいることはもう丸分かり、 甲板の隙間へ僅かに顔を出した黄色も成長に連れ次第に変色していくので、 最終的にはフルブラックの完全体となってしまうのかもしれません。 育ちの良さも相まってその質感も大変に良く、 四肢の鱗などはまるで雨に濡れたアスファルトのように冷淡で無機質な光沢を放っています。 前述の通り数多くの亜種を含むギリシャですが、 その中でもイベラは最大になると言われていますので迫力は段違い。 万が一、見たこともないサイズと見たこともない黒さの両方を一体のカメの中で同時に実現することができれば、 そこに出来上がるのはオンリーワンの素晴らしい逸品です。 前飼育者が既に屋外越冬を経験させているため、 夏も始まったばかりの今からであれば早速今年の冬眠にも間に合わせることができます。 自宅の庭で一年中リクガメをのびのびと飼育するという夢を、このジェットブラックイベラで叶えましょう。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (♂) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 何処かメカニカルな雰囲気さえ漂うシックなカラーに痺れるリクガメ界のクールビューティ! ギリシャには珍しく耐寒性を備えたタイプとして昨今注目を集めている大人気の小型強健種、 イベラギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 私たちがリクガメに対して求める要素は様々ですが、 第一に良く動き回り視覚的に楽しませてくれることが挙げられると思います。 与えられたケージなり庭先なりのスペースを一杯に使って、 所狭しと忙しなく歩いたり走ったりする光景に人々は癒しを求め、 その何とも平和な生き様に惚れ惚れとしてしまうものです。 中には極端に大きく成長してしまう種類も含まれる中で、 次に求められるのは日本の一般家庭において無理なく暮らしていけるサイズ感でしょう。 デカ過ぎるわ動き過ぎるわでは仕舞いに収拾がつかなくなってしまうのも目に見えていて、 初めの頃は楽しく遊んでいても段々とこちらがくたびれてしまうからです。 最後にあったらいいなと思える要素として挙げられるのは、 あわよくば冬季に保温をせずとも共に暮らしていける耐寒性の高さかもしれません。 日本の四季に合わせて無理のない距離感で向き合いたいという意見もあれば、 原則加温はすることにしていても万が一の備えとして我慢できる強さが欲しいとの声もあり、 それがないよりはあった方が良かろうと考える方も決して少なくはないようです。 今回やって来たのは上に挙げた三要素を見事に兼ね備えていると思われる、 別名トルコギリシャとも呼ばれる亜種や地域個体群として認められたイベラのオス。 分類には諸説あるものの一般にはシンプルに屋外越冬が可能なギリシャとして認知され、 例えばヘルマンやマルギナータなどと同様、 棲息地の関係で寒さに強い点が特長としてフィーチャーされています。 ホワイトヘッドと称しても差し支えない頬の白さが大変美しく、 これは全てのイベラに共通する訳ではなくこの個体が持つ立派な個性のひとつです。 各甲板のボコ付きの少なさや甲羅全体の盛り上がりからも大切に育てられていたことが窺え、 何よりも実際に冬場は室内無加温にて育てられていたことが真の付加価値となるでしょう。 ギリシャらしくいつでも活発に躍動するところが見ていて飽きないため、 庭で放し飼いできるリクガメの新たな選択肢としても近年再び支持率を高めている本亜種は、 入荷が散発的でいつでもコンスタントに手に入らないのが余計に興味をそそります。 春になり外へ出せるようになるのが今から待ち遠しいです。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (♂) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 夢の通年屋外飼育に向けて冬眠させるのも今ならまだ滑り込めるサイズとシーズン! 存在自体は知れていても実際に見かける機会は稀な全身がきちんと黒がちになるタイプです、 イベラギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 ペットトータスという概念を世界中に広めた立役者、 そう呼んでも差し支えない功績を果たすのが何を隠そうこのギリシャリクガメ。 あなたに出会えたからこそ今の楽しい生活がある、 そんな風に考えている人が世の中に一体何人いるのでしょうか。 最近ではテレビコマーシャルにも出演するほどの人気を博し、 その知名度と支持率の高まりは留まる所を知りません。 持ち前の頑丈さ、すなわち環境適応能力の高さが結果的には飼育下における飼い易さへと繋がり、 広大な分布域が成せる個体間の豊富なバリエーションが人々の心を掴んで離さないのです。 一般家庭でも終生付き合っていくことがさほど難しくない手頃な大きさは本当に有難く、 リクガメは人の手によって飼育されるべきではないという意見に待ったをかけ、 観賞目的から一家族として末永く付き合おうという考えまで、 今日もこのギリシャは各々の家庭で大切にされているのだと思います。 今回やって来たのは数えきれないほどの亜種が存在する中で、 最も耐寒性が高いとされるイベラギリシャの飼い込み個体。 分類上の詳細な話はさて置いて、ホビーの世界では従来よりこのように甲羅から頭、 四肢までが一様に暗色がかりシックな雰囲気へと仕上がるものがこの名前で呼ばれています。 通常見かけるいわゆるアラブギリシャにはないモノトーンな配色と、 最終的には一回り二回り明らかに大型化するらしいという情報が、 少し突っ込んだ愛好家らの間で受けが良いとのこと。 野外でも越冬ができるギリシャとして有名なのは言うまでもなく、 それを期待してこのイベラが選択されるケースも決して珍しくはありませんが、 実際の流通量はごく限られており毎回入ってもいつの間にかすぐにいなくなってしまいます。 やはり年中外で野放しにできると言うのはある種の憧れでもありますから、 そういった特定の需要を満たす上にヘルマンなどよりも一風変わった所がミソなのでしょう。 性別はオスですが性格のきつい様子は今の段階ではほぼ全く見られず、 嬉しいことに他のホルスやギリシャとも同じケージ内で仲良く餌を分け合っています。 甲羅の成長具合もよほど文句を付けられるような印象はありません、 これから外に出せばまだ冬眠の準備に間に合いますので、 この機会に是非お庭を散歩させるためのリクガメを入手して下さい。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (♂) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| 最大亜種の意地と誇りが育て上げた果敢に大地を踏み鳴らすラージサイズ! この先もまだまだ膨れ上がっていきそうな高いポテンシャルが全身からピリピリと伝わって来ます、 イベラギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 強靭な体質と飽くなき冒険心によりユーラシア大陸を股に掛ける、 言わずと知れたペットトータスの代表格のひとつがこのギリシャリクガメです。 あまりにも広大な分布域とそれに伴う多様な形質の分化は、 いつの時代も愛好家のみならず研究者までをも悩ませているようで、 昔に比べれば諸々の事情が随分進歩したと思われる現代においてさえ、 その分類は収束の域に達することなく未完のまま留まるばかり。 では一体何者が我々の欲求を妨げ歯止めをかけているのでしょうか。 注目すべきは言わずもがな亜種分けについての一点のみ、 そこを明らかにするためには当然現地調査に踏み入ることを避けては通れないのですが、 棲息地の多くが人間自身によって引き起こされる治安の危うさに悩まされているがために、 真相の究明が酷く阻まれ遅延や混乱が生じていると考えられるのです。 トルコギリシャとも呼ばれるこのイベラ、元々は学名の片仮名読みが愛称の由来となってはいるのですが、 最近の研究によると亜種としては認めない説も提唱されており、 しかしながらホビーの世界では根強い支持が続けられているため、 例えばタイプイベラと言った具合で明確に区別されることもしばしば。 それ故に同名で見かける成長した個体を見比べれば、 色彩や体格などには確かに共通した要素を見出すことができます。 チチュウカイリクガメが誇る安定した人気度については今更申し上げるまでもありませんが、 その可能性をより高める要素として通年屋外飼育が可能かという条件が挙げられます。 お馴染みのヘルマンやホルスでは日常的に行われていることでも、 前述の理由から本種にはそれをそのまま当てはめることができず、 単にギリシャリクガメとして入手したものでは実験的行為になる恐れすらあり、 東欧近辺の出身であるこのイベラが如何に貴重な存在であるかというのがお分かり頂けるでしょう。 全体のプロポーションに不満が漏れるような雰囲気はあまり感じられない今回の個体は、 既に十分なサイズに達しているため少なくとも来季の冬からは平気で野外での冬越しにチャレンジ可能です。 自宅の庭やベランダでリクガメを放し飼いにしたい、けれどもあまりに大型な種類は現実的でない、 そんなわがままにも全て応えてくれる良きパートナーとして強くお勧めします。 | ||||||||||
|
イベラギリシャリクガメ (ブラック・♂) Testudo g. ibera |





|
|
||||||||
| その力強い一歩に重たい足音が響き渡る巨像のブラックイベラ! 幼少期より自然の中で育まれたその黒さとデカさに一級品の香りが漂います、 イベラギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 その名前を聞いただけではギリシャとその周辺に暮らしているのかと思いきや、 それは全く関係なく実際はリクガメ界トップクラスの広大な分布域を誇り、 北アフリカからヨーロッパ、果ては中近東にまで勢力を伸ばしています。 単純に面積だけを比べるのではなく、 気候や風土の多様性を思えば最も環境適応能力に秀でている種類と言えるのかもしれません。 そのためまともに亜種を認めると大変なことになるのはご存知の通りですが、 同じ亜種内にも豊富なバリエーションが存在するため一目見て言い当てることは至難の業。 それでも外観にある一定の傾向は見出すことができますので、 ある程度お好みの色合いなどを亜種を頼りにセレクトすることも可能ですし、 亜種が不明なものは元々何処に棲息していたのかが分からないため、 飼育をする際に手を焼くことも考えられるのです。 ここに紹介するイベラとは別名トルコギリシャとも呼ばれ、 最新の分類では学名のibera自体を認めない説もあるようですが、 いわゆる昔ながらの冬眠できるギリシャを指していると考えて頂ければ問題ありません。 おおよそのカラーリングとしては赤みが殆ど抜け切った淡泊な黄褐色から、 全体的に黒っぽさが目立つという辺りで比較的安定しているのではないかと思いますが、 いつの時代も人気が高い、 全身が漆黒に染め上げられた個体の多くがこのイベラに該当しているのです。 今回やって来たのは俄かにオスとは思えない恐るべき体躯と、 鱗のひとつひとつに黒曜石でも埋め込んだかのような輝きが見る者を圧倒する、 未だかつて味わったことのない刺激を感じさせる絶品。 通常であれば甲羅の長さを聞いただけでメスと決め付けて差し支えないレベルにもかかわらず、 そこは最大亜種と言われていただけに周囲を薙ぎ倒さんばかりの威圧感を纏い、 運動量に不足がなかったことも関係しているのでしょうか、 四肢の太さを見る限りとてもリクガメの中では小型の部類と言い切る自信はありません。 少なくともビギナー向けと言われているだけあり可愛らしさも売りのひとつであったはずが、 この硬質かつ無機質で冷たい表情は一体何なのでしょうか。 実にストイックに己の道を突き進む姿勢はまさしく漢のリクガメ、 種の稀少性などというちっぽけな枠を簡単にぶち壊してくれる強烈なインパクトがボディの隅々まで漲っています。 もう何年も通年屋外飼育が続けられていたため明日からいきなり外に出しても問題なし、 真っ黒のギリシャは本当に探しても見つかるものではありませんのでお早めに。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ベビー) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 最もポピュラーであろう亜種の色違い3匹を揃えてみました。 リクガメ入門種としても非常に人気の高い種です、アラブギリシャリクガメの入荷です。 その愛らしい容姿と飼いやすさからビギナーからの支持も熱い地中海リクガメの仲間。 その中でも上品で凛々しい顔立ちとこんもりと盛り上がった所謂リクガメらしい体型から特に人気なのがギリシャです。 多くの亜種が知られていますが実際に流通するものは限られており、 中東の亜種アラブは寒さにはあまり強くないものの色柄の鮮やかさが魅力的。 今回は薄いクリーム色が目立つもの、濃い目のイエローと黒斑との対比が明瞭なもの、 全体的に黒味の強いものと3つのパターンをセレクトしました。 ホットスポットを設けた暖かいケージ内で葉野菜を与えるとおもむろにトコトコ歩いて来て、 美味しそうに食べる姿を見ていると癒されます。初めての方にはアドバイスさせて頂きます、お好みの個体をお選び下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (四枚甲板) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
|
委託主様のご意向により価格を下げて再UP! これぞまさしくハンドピックセレクト! 椎甲板が4枚のオンリーワン個体です、 お客様委託のアラブギリシャリクガメが入荷しました。 和名がギリシャでチチュウカイリクガメ属と来れば、 ヨーロッパの一国であるギリシャを中心に棲息するカメなんだというイメージを持たれるでしょう。 決して間違いではありませんがその名の由来はまた別で、 ギリシャ絨毯に施される模様と甲羅の幾何学模様が似ている所から来ているのだとか。 現在国内で流通している個体はアラブなど中近東の個体群、亜種が殆どですので、 地図上でヨーロッパではなく中近東のエリアをイメージしておくとすんなり飼育に臨めるかもしれません。 しかしながら耐寒性は思ったより高くない、 というぐらいでそれ以外の点では他のリクガメに比べ格段に飼いやすく、 それだけに現在ベビーサイズを中心に多くの個体数が輸入され、 初めてのリクガメとして選ばれる機会も多く重要なポジションを担っていると言えます。 そして今回やってきたこの個体はその大群とも呼べるギリシャ達の中から目を光らせて選び抜かれた渾身の一匹で、 力づくでなんとかつじつまを合わせた様な甲板の配置には アーティスティックなセンスさえ感じます。 もちろん背甲の椎甲板以外には甲ズレに該当する箇所はありません。 こればかりは見て気に入るかどうかという所ですのでこれ以上申し上げることはありませんが、 やはり多甲板よりも少甲板の方が見かける機会は少なく、6枚より4枚の方が稀少ではないかと思います。 まだ小さいサイズですがさすがはギリシャ、 動きは活発でおはようとおやすみのメリハリも良くしっかり食べてしっかり寝ています。 成長後も全体像の崩れるようなことは考えにくいですので、フルサイズまでしっかり育てて末永くお付き合い下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 永遠の庶民派だからこそ初期状態にはうんと拘って選びたいあらゆる餌をもりもり食べる健康児揃い! 今やビギナーズトータスの座をヘルマンに譲ってしまったからこそ逆襲を誓いたい、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 かつてはリクガメの顔として数十年もの長きに渡り最前線での活躍を続け、 ロシアことホルスフィールドとのツートップで日本中に幸せを送り届けてきた、 誰しもが一度はお世話になったと言っても過言ではない功労者のひとり。 時代の流れ故に致し方ないところもありますが、 あれほど大量に出回っていた野生個体の流通量が激減してしまった昨今では、 養殖がコンスタントに進められているヘルマンリクガメにその座を取って代わられてしまい、 最近でも定期的に輸入はあるものの当時の勢いからすれば寂しい限り。 もちろんこれ以上の消費的な供給を避けるべきという向きが強くなってのことですから、 再び同じことを繰り返していてはいけないのですが、 ギリシャにはギリシャの魅力があることは誰しもが分かっていることですし、 いくらヘルマンが流行していてもギリシャ求むの声が耐えないのは事実です。 昔と今で変わったことといえば目にする頻度や市場における相場観の他に、 明らかな初期状態の向上も含まれていることを忘れてはなりません。 生体の取り扱いに対してより慎重になっている今日だからこそ、 それを手にする未来の飼い主にとってはメリットが多分にあり、 彼らの持つ様々な素質をより多く引き出してやるのが私たちの務めではないでしょうか。 今回やって来たのは最近よく見かけるシリアからの来訪者たちで、 群れの中からコンディションの良いものだけを特別に選び抜き、 きちんと餌食いを確認してから店頭に並べています。 更にはワイルドばかりなので細かな注文が付けられない中で、 少しでもサイズの小さなものをセレクトするように気を付けていて、 この二匹は普段入手できるものより一センチほど小さく収まっているため、 伸びしろが多くより可愛がって頂けることでしょう。 ヘルマン全盛の中でギリシャのファンが必ず口にするのが、 顔立ちがこちらの方が圧倒的に可愛らしいということ。 もちろん主観の問題なので好みはありますが、 きっとそれぞれがそれぞれの長所を以ってこの世界に君臨しているのだと思います。 どちらの個体もMazuriリクガメフードオンリーで育てられるだけの健康体でお渡しします。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ライトカラー・S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| イエローアラブともまた異なったギリシャモザイクの消失具合に甘い香り漂うクリーミーラテ! 状態にバラつきのある本種ですがリクガメフードをもりもり食べるレベルまでトリートメント済み、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 生き物の名前には必ず何かしらの意味が込められていて、 特に爬虫類の和名については未だ安定しない呼び名はあるにしても、 かつて学名や英名で仕方なく呼ばれていたものに続々と新称が与えられており、 そのどれもが名前を聞いただけで特徴が分かるようにとの思いが込められています。 しかしながらロシアリクガメは現在のロシアに自然分布しておらず、 ギリシャリクガメもまたあの広大な棲息域を以ってしても厳密にはギリシャに分布していません。 ロシアについては何か誤解が生じてしまったのか、 現在ではヨツユビやホルスフィールドと言い換えられる動きが強まっていますが、 ギリシャは相変わらずギリシャのまま。 それもそのはず、本種については国名のギリシャが採用された訳では無く、 絨毯などに施されると言われる伝統的なギリシャ刺繍が由来となっており、 冒頭でも触れたギリシャモザイクと呼ばれる柄が背甲のデザインに似ているからなのだそう。 散々見慣れた外観もそんな話を聞いた途端にお洒落に見えてくるのですから、 ネーミングによって与えられる付加価値も侮れないと感じるのでした。 今回やって来たのはまとまって輸入されたよく見かける安心サイズからセレクトされた、 全身が淡く色抜けしたパターンレス気味の仕上がりが目を惹くこんな個体。 模様の消えかかった美しいタイプと言うとイエロー系のアラブギリシャを連想させますが、 あちらはド派手な発色が持ち味の昔から人気の高いある種ギリシャの顔とも言うべき存在で、 反対にこの個体にはパッと見の華やかさは無くとも品の良いカラーリングに魅力があり、 このぼんやりとしたゆるい雰囲気は成長に連れて次第にその存在感を示してくれると思います。 見た目は癒し系ですが動きは非常に活発で、 入荷当初は輸送の疲れも見せない類稀な運動量に驚かされると共に、 以前より店頭にいた他のリクガメから餌を奪い取るなど頼もしい姿を見せてくれました。 初めての方にも安心して頂けるよう、Mazuriリクガメフードから葉野菜、 野草まで選り好み無く爆食している抜群の状態にてお渡しします。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 昔流行ったゴールデンタイプとは一風異なる全身がカスタードに覆われたシリア産の珍カラー! 甲羅は兎も角として頭部から四肢までほぼ同一色に整えられたかなり美意識の高いセレクト個体、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 その昔リクガメといえばこれで決まりと言われんばかりの勢いで、 初めてのリクガメとして真っ先に選ばれていた誰もが知るところのギリシャリクガメですが、 近年ではその重要なポジションをヘルマンに取って代わられてしまい、 というのも野生個体が流通の中心であり今でもそれは変わらない本種にとって、 安定供給が売りのライバルにはどうしても追い付けない部分があり、 目にする機会の多い少ないで明らかに不利な状況に立たされています。 また輸入されたばかりの頃、 つまりショップに並べられた時点での最初のコンディションについても、 あくまでも人の手によって養殖されているヘルマンの方が落ち着いていますから、 如何せんワイルドのギリシャではビギナーに対する配慮も不十分といったところでしょうか。 しかしながらギリシャの凛々しくも優しい美形な顔立ちが好みというファンも依然多く、 またヘルマンに不敗神話がある訳でもなく状態は個体によりけりですから、 あまり前評判ばかりを気にしていては目の前のカメに対して失礼というものです。 当店では初期状態に十分気を配り毎度トリートメントを心掛けているのですが、 きちんとケアが行き届けばヘルマン並みの活発さを取り戻してくれるため、 常に選択肢としてアグレッシブに用意していきたい永遠の人気種だと考えています。 今回やって来たのはシリア産として輸入されたアラブギリシャの安心サイズで、 入店当初より体重もしっかりと感じられたため殆ど心配していませんでしたが、 案の定葉っぱ系に留まらずMazuriリクガメフードにも果敢に挑み、 現在ではMazuriのみで食生活を送ることができるまでにしっかりと立ち上げられました。 二匹とも全体的に黒斑の面積が少なく冒頭でも触れた通り体色もかなり黄色味が強い印象で、 同じ産地から過去に輸入されたものと比べても美しさが一味違います。 店頭では冬季の過ごし方も含めた飼育設備も併せてご案内しますので、 初めてリクガメにチャレンジされる方もお気軽にご相談下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (国内CB・S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| イエローやオレンジのパッと明るい色彩がよく映える流石にコンディション抜群な嬉しい国内CB! それぞれ全く異なる血筋からの来訪者ですがふたり仲良く水槽内を走り回っています、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 その昔ペットとしては高嶺の花であったリクガメの仲間たち、 しかしながら当時より屈指のリーズナブルさを誇っていたこのギリシャは、 いわゆるビギナー向けの一般種として普及し多大な功績を収めてきました。 何故それほど安価に入手することができたのか、 それにはもちろんかねてよりの相場も関係しているのでしょうが、 やはり流通するものの中に採集された野生のカメが多く実在していることこそ最も大きな要因であると考えられ、 それが定期的に数多く入ってくるとなれば取引額は高騰のしようもありません。 それ故に馴染みの顔として人々に知れ渡る一方で、 いつでもいるから良いという誤った安心感を抱かせてしまいがちです。 昨今のカメを取り巻く状況を見ていると、どうしてもこれが来なくなった、 あれが来なくなったと言った寂しい話題ばかりが飛び交い、 何処にでも居過ぎて余って仕方がないなんて羨ましい話はとても聞かれなくなりました。 それに喜ぶ人がどれほどいるのかはさて置いて、 種親候補がまだいくらでも手に入る可能性の高い種類こそ繁殖に挑み、 もしそれが成功した暁には皆でそれを有難がることで、 明日へのモチベーションへと繋げることができればと思う次第です。 今回ご紹介するのは全然関係の無い別ラインよりやって来た二匹のギリシャ、 どちらもいわゆるイエローアラブとして販売されていた個体を元に、 拳大ぐらいからフルサイズまで育て上げられた両親より得られた子孫と聞いています。 小さい方はむしろやや赤味の強い体色が印象的で、 サイズが小さいせいもあるのか透明感溢れるピュアな雰囲気がとても美しく感じられます。 反対に大きい方はすっきりとしかしベッタリとしたレモンイエローがよく目立ち、 甲羅のみならず頭部から四肢からそこら中黄色に染まっているため、 成長後も強い発色を維持していくことが期待されます。 目元がくりくりとした幼い顔立ちのオレンジに対し、 切れ長の面立ちがクールで格好良いイエローと表情の違いも要チェックなポイントでしょうか。 現在60センチのケージで同居させており、ライトが点けば足早に活動を始め餌食いも大変に活発ですので、 よく見かける輸入されたてのギリシャとは一味も二味も違うことを痛感させられると思います。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (カラーアソート) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| スタンダードカラーにイエロー、そしてオレンジと特徴的なものが一堂に会した選び放題の三色団子! もちろんセット販売ではありませんがついつい並べて紹介したくなる個体差のバリエーションが素敵な、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 かつてビギナー向けのリクガメといえばこれで決まりとでもいわんばかりに、 その代名詞のような存在感で時代を席巻したキャラクターであったギリシャリクガメ。 これと対になるものとしてはやはりロシアことホルスフィールドが挙げられ、 両者の特徴としてあまり申し上げたくないのは安価で大量に流通していた歴史があり、 とてもリクガメとは思えないリーズナブルな価格帯でばら撒かれていた頃などは、 見た目のインパクトやリクガメという絶対的なブランド力を武器にあちこちで販売されていました。 当時はリクガメなど飼えたものではないと諭されるような風潮もありましたから、 どうしても消耗品の感が拭えず運との勝負も避けられなかったために、 隠そうとしても隠し切れない光と影の部分が混在していたと思います。 時は流れ今日ではその座をヘルマンリクガメに譲ることとなり、 野生個体が輸入の大半を占めるギリシャはどうしても分が悪くなってしまうために、 表舞台からフェードアウトしかけている感も否めませんが、 ギリシャにはギリシャの元来備わった魅力がある訳ですから、 本当にギリシャを必要としている方にとってはなくてはならないものなのです。 今回やって来たのはそれぞれ全く別のところから集められた面白い三匹で、 冒頭でも申し上げた通り各々が異なるベクトルへ向かっているカラフルギリシャたち。 一番小さな個体はその名の由来にもなったギリシャ絨毯模様が顕著に描かれており、 かなり小さなサイズで輸入されているため体表の艶が凄く目立っています。 真ん中の個体は俗に言うところのイエローアラブの一種でしょうか、 甲羅はもちろんのこと頭部や四肢に至るまで、 色が付きそうなところがもれなく明るい黄色に染め上げられており、 全身に統一感のあるこのような外観が好みの方も多いことと存じます。 最後の個体は便宜上オレンジと表記しましたが、 肉眼で見る実際の色合いとしてはピンクオレンジと表現する方が適切かと思われ、 特に顔周りなどはまるでフラミンゴのように華やかな発色が見られる美しいタイプです。 店内では三匹を同一ケージにて同居させていますが、 誰かが虐げられることもなく均一にMazuriリクガメフードを爆食しており、 既に成長線も数ミリずつ伸び始めていますので、お好きなカラーを選べる間にお早めにどうぞ。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (シリア産) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| ツルピカのナチュラル美フォルムに内面のコンディションもパーフェクトな三者三様三色団子! イラクとトルコに挟まれた中東の国シリアより遥々やって来た安心のスターターサイズ、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 いよいよ待ちに待った春を迎えようとしているこのシーズンに、 今まで思いを募らせてきた憧れのリクガメを迎えたいと準備を進めてきた方へ、 拍子の良いことにビギナー種としては定番ながら長年に渡り根強い人気を誇る、 かの有名なギリシャリクガメの登場です。 他のリクガメには真似できない本種ならではの楽しみ方として、 広大な分布域が成せる彩り豊かな個体差のバリエーションを生かし、 自分の好みに合った拘りの一匹を選び抜くと言うのは如何でしょう。 たまたまこの場に集う三匹でさえその容貌は全く異なり、 例えば甲羅だけを見比べてみると全体的に模様が薄く乳白色に包まれたもの、 黒い影が均一な模様を作り出しそして黄色味が強いもの、 黒と黄色がフィフティフィフティで明瞭なコントラストが際立つものと、 各々が思い思いの格好で世界にひとつだけのデザインを描き出しています。 俗に初心者向けと言われるものの決してそうとは限らず、 飼育下で繁殖された幼体ばかりが安定して流通するヘルマンに比べ、 主に中東の至る所から採集されてくることも多いギリシャは、 それぞれのタイプや初期状態により面倒の見方を変えていく必要があり、 我々ショップの人間としても如何にして接するかという点が課題です。 昔に比べて最初から明らかに衰弱しているようなことは稀になったとは言え、 やはり些細なことから調子を崩してしまうことも無きにしも非ずですから、 到着してからの数日間は緊張の糸を緩めずきちんと状態を見極めるよう心掛けています。 今回ご紹介するのはシリア産として輸入されたベビーよりも少し育ったグッドサイズで、 幸運なことに初めから三匹ともにムラなく最高のパフォーマンスを発揮しており、 同じケージ内で均一に管理をしていても餌食いや動きに僅かばかりの差異も見受けられず、 いずれの個体についても至って健康で最も重要な心配事が解消されました。 既に葉野菜からMazuriリクガメフードへの切り替えも難なく済み、 カルシウムの粉を嫌がりもせず特段気を遣うことはありません。 ロカリティがきちんと分かっているだけで世話の仕方にブレは出ず、 瑕ひとつ見当たらない極上の質感が飼育欲を大いにそそります。 カラーリングは個々で全く違いますが、こればかりは皆さんのお好みで選んで頂きたいと思いますので、 是非一度店頭にてじっくり観察してみて下さい。 近年におけるリクガメ人気に拍車を掛けるこの素晴らしい三匹、 初めての方にも胸を張ってお渡しできる健康優良児揃いです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 今夏のリクガメ飼育スタートにちょうどいいベストサイズ! この時期から飼い始めればその醍醐味を存分に味わうことができるでしょう、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 言わずと知れたリクガメの定番種にしてビギナーからマニアまで幅広い層から支持の厚いポピュラー種。 同じチチュウカイリクガメの仲間であるヘルマンは人気を二分するライバルのような存在ですが、 本種の方が見かける機会も多くまたリーズナブルな価格で手に入りやすいことから、 こちらに軍配が上がるかもしれません。 そのライバルに対してもう一点強みなのが体色や柄のバリエーションが豊富なことで、 理由は棲息地の広大なことだけではないようで同亜種内でも全く別のカメに見えるほど個性に溢れています。 今回やってきたのはハッチサイズから二回りほど育ち甲羅もカッチリ硬くなった文字通りの安心サイズで、 2匹がそれぞれ上手いこと2つのカラーパターンに分かれてくれました。 一方は赤みが強く典型的なギリシャの色味を濃くしたような色合いで、 もう一方はヘルマンフェイズとでも呼びましょうか、 反対に黄色味が強くまた黒い部分とのコントラストも鮮やかなタイプです。 毎年何度か数多くのベビーサイズが輸入されてきますが、 入ってきたばかりの頃はしゅんとして引っ込み思案な個体も少なくありません。 しかしこの2匹は一定期間飼い込まれているためかガラスケージの壁に向かって延々と歩き続けるほどパワフルです。 お好みの個体はどちらでしょうか、初めての方にもオススメ! | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 定番かと思いきや最近ご無沙汰なベビーギリシャから濃厚な黄色味が目立つものをチョイス! ワイルドとCBそれぞれの良さがひとつの体に合わさったはっきり言って絶対に見逃せない絶品揃い、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 その昔はロシアとギリシャの両名が初心者向けの代表種とされ、 何故かと言えば低温や乾燥に対してそれなりに耐性を持っていることもそうですが、 何よりもまず安価に流通していたことがその大きな要因として考えられます。 つまり飼い易いではなく買い易いと書き改める必要があるほど、 たまたま金銭的なハードルの低さが持ち前の頑強さとマッチし、 色々な意味で都合の良いビギナーズトータスが出来上がっていたのです。 このことからやはりホシガメはいくら安価であったとしても初心者向けと言われることはなく、 前述の二種は偶然の産物として長い時間をかけて世の中に広く普及していきました。 ただし時が経つに連れて安定供給が難しくなるのは言うまでもなく、 その枠を虎視眈々と狙っていたヘルマンが養殖技術の向上と共に先頭へ立ち、 最近ではリクガメの代名詞であるかのように存在感を主張するようになりました。 本種が大量に出回っていたあの頃を古き良き時代と言うのであればそうなのかもしれませんが、 あまり姿を見かけなくなった今だからこそ再認識される魅力が備わっているようで、 ころんと丸っこいシルエットや優しい顔立ちなど、 可愛いリクガメのスタンダードとしてもう一度栄光を掴み取ってほしい永遠の人気種です。 今回やって来たのは飽き飽きするほど見慣れていただけあって余計にご無沙汰な感じのする、 初めてのリクガメに最も選ばれ易い種類のひとつに数えられるギリシャのスモールサイズ。 この便で来日したもの全てがそうなのかは分かりかねますが、 とにかく輸入直後とは信じ難い安定感抜群の健康状態が素晴らしく、 入店して間もなくMazuriリクガメフードを爆食されてはもう何も申し上げることはありません。 これまた最近見かけないイエローアラブ、 ゴールデンアラブと呼ばれていたタイプは少々気難しい面もありますが、 それを思わせる鮮やかなイエローが目立つ個体ばかりをセレクトしてみました。 理想的なツルツルのフォルムに将来の美しい仕上がりを想像しながら、 この夏の陽気を味方につけて一気に大きく育て上げましょう。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (S) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 濃厚なオレンジが体の奥から染み出した並のギリシャに比べてプレミア感のある美個体揃い! 気のせいかもしれませんが妙に黒目が大きくて可愛らしい顔立ちの二匹をチョイス、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 ビギナー向けの飼育に適したリクガメ、 そんな魔法の言葉を授けられて早数十年が経とうとしている本種も、 昔のように何時でも何処でも見かけられる一般種では無くなろうとしています。 そもそも何故飼い易いなどと言われ続けて来たのかを考えると、 もちろん元来強健であり大きさも手頃なのは間違い無いのですが、 実際にはただ単に買い易い、つまり目にする機会が多かっただけに過ぎず、 コンディションの良し悪しも含めると下手をすれば吉と凶が入り乱れたおみくじ状態に陥る危険性もあり、 誤って後者を引いてしまった上に育てるのが簡単だと思い込んだが最後、 その油断からあえなく幕切れとなるケースも少なからずあったことでしょう。 最近では間違っても消耗品のような扱いを受けることが殆ど無くなり、 一匹一匹がより大切にされているお陰か初期状態も随分と改善され、 改めて本当にギリシャが好きな初めての方にもお勧めできるようになりました。 変な言い回しですがリクガメらしい種類とそうでない種類に分けるとすれば、 本種は明らかにそれらしい部類の代表的な存在であるため、 環境設定においてもそれなりに気を配る必要があり、 反対にいい加減な扱いでは露骨に調子を崩してしまうことも多いのですが、 ルールさえきちんと守れば愛嬌たっぷりの姿を楽しませてくれると思います。 今回やって来たのはいわゆる普通のギリシャとして最も流通量の多い、 アラブギリシャと呼ばれるタイプの安心サイズから選抜した、 地色の発色が良好で甲羅の濃淡がそれぞれ異なるこんな組み合わせ。 両個体とも後頭部から奥の柔らかいところにしっかりとオレンジが乗り、 一方は甲羅の黒味と共に全体が色薄に仕立てられ、 もう一方は浅黒いようなベッタリとしたコントラストが印象的で、 お好みに合わせて選べるようにしてみました。 春到来とは言え保温設備などまだまだ気の抜けない季節ではありますが、 気持ちの上では厳寒期よりもお迎えし易いのは確かです。 新生活のスタートに合わせてリクガメデビューを応援すべく、 健康状態を整えてお待ちしております。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ハイカラー) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 乾燥系という表現を真に受けてはいけないことがよく分かるうる艶ボディを手に入れた極上品! 荒廃した大地に棲息していたことが信じられない乳白色の柔らかな雰囲気に可愛らしさ倍増の、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 初めてリクガメを育てる人はこれで決まりとでも言わんばかりの、 その昔何処かの何方かがビギナーズトータスの代表種であると決め付けてしまったがばかりに、 大多数の人々がその言葉を信じてひたすらに飼育していたものと思われる、 ある意味業界の立役者として大仕事を成し遂げた功労者のひとり。 とてつもない力技ではありますが、 膨大な情報の集積によりある程度現実的な飼育方法が確立してしまったことに恐ろしささえ感じられますが、 要するに元々安価で大量に流通していたことが発端となり、 加えて中東地域の乾燥したエリアから輸入されていたこともあって、 何となく森の中に棲んでいる種類よりは飼い易かろうと思い込まれてしまった結果、 決して適切とは言えない環境下でペットとして辛抱強く生き長らえ今日に至ったものと思われます。 持続する期間の長短はさておき乾季があれば雨季も訪れる訳で、 乾燥地に暮らしているからと言って永遠に乾かし続けることが親切なのではなく、 むしろ穏やかで快適に住まうことのできる雨季を再現してやった方が本当の親切なのではと考え、 このようなタイプのカメにも常識的なレベルの水気を供給してあげることにより、 これまでの間違った常識をひっくり返す望ましい未来が早々に訪れるような気がしてならないのです。 今回やって来たのは日々の入念な世話がしっかりと湿り気を与えることで達成された、 絶品という言葉がこれほどお似合いの飼い込み個体も珍しいスモールサイズのギリシャ。 一目見て真っ先に受けた印象はとにかく甲羅の表面がツルツルに仕上がっていることで、 凹凸の無さはおろか濡らした訳でもないのに内側から水分が浸み出すような潤いが大変美しく、 結果的に一体のカメとしてのトータルバランスに寄与しているところが素晴らしいと思いました。 全体的に色調の淡さが際立つ素質を持ち合わせていたのもラッキーな話で、 前肢のブラックチップがよく映える白い素肌と、 背甲はもちろん頭頂部から首元にかけてもまたオレンジにほんのりと色付き、 生まれ持ったポテンシャルの高さと育ちの良さが見事に絡み合った誰もが羨む一匹です。 | ||||||||||
|
ギリシャリクガメ (M) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 手の平安心サイズ、ではなく手の平いっぱいに乗るもっと安心サイズです。 リクガメ飼育の定番種、ギリシャリクガメが入荷しました。 飼育書やインターネットなどいたる所で入門種として紹介されるギリシャ、 本種からリクガメ飼育を始めた人は数知れずという位わたしたちにとって馴染み深いリクガメです。 中東からヨーロッパにかけて広く分布し多数の亜種を含みますが、 それ故か飼育環境に慣れやすい個体が多いです。しかし幼体では低温や乾燥に対して敏感な所もあり、 特に寒い時期から飼育を始められる方には心配が付きもの。ですが今回の個体はみなしっかり育っており、 甲羅は硬く四肢は太く頑丈さが出てきています。 また色合いもそれぞれ違い、 黄色と黒色のコントラストがくっきりしたものや、 反対に淡く明るい色彩のもの、 全体的にオレンジ色が強いものなどがいますのでお好みの個体をお選び下さい。 亜種によって好む環境は多少違いますが、大きくなってしまえばある程度の耐寒性も備わり 他のリクガメと比べてもかなり丈夫な部類に入ります。よく動き回ってお勧めの個体達です。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (M) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| ちょっと勿体ない位いいサイズに育った3匹のギリシャです。 お客様飼い込みのアラブギリシャリクガメが入荷しました。 今回都合により当店にやってきた元気な3匹ですが、 ベビーの頃にとびっきりライトカラーな個体を1匹と ダークな感じの個体を2匹選んで飼い始めたそうです。 現在ちょうど手の平にのる安心サイズまで育っていますが、 極めて順調な育ち方をしているのは写真で見てもお分かり頂けると思います。 更に最初のセレクトの甲斐あってか、ギリシャリクガメのバリエーションの豊富さを感じさせるラインナップになっています。 リクガメ飼育入門種として多くの個体が国内でも飼われていますが、 丈夫な体質と人懐こい性格は他のリクガメではなかなか真似できない地中海リクガメの特徴です。 また最大サイズもより大きくなるメスで20cmほどですから室内でも無理なく飼える扱いやすい大きさなのも嬉しいポイント。 餌は葉野菜から人工飼料まで色々なものを食べますのでビギナーの方も安心です。 これからの成長が益々楽しみな3匹、リクガメの季節真っ盛りな今こそ飼育をスタートするチャンスです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (イエロー・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| イエローアラブと言うよりもはやオレンジが主張し過ぎている大変色味の良いセレクト個体! 当然と言えば当然なのですが甲羅の形状もナチュラルで見応え十分な、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 言わずと知れたペットトータス代表種であり、 昔から馴染みのあるキャラクターは今もなお愛され続けている、 向こう数十年は人気の衰えを知らないのではと思わせるほどの実力を誇る銘種。 正直、かつてのギリシャはただ単に安価で大量に販売されていることだけが取り柄のような、 もちろん小振りなサイズ感と頑丈な体質は持って生まれた天性なのでしょうが、 取り立てて何が優れているだとかそういった話にもならないような粗末な扱われ方でした。 それが今日ではいくらでも飼育対象種を選択することができる、 云わば恵まれた時代が到来したと称されるほどの状況において、 未だ支持率を落とすことなく業界に君臨し続けているのは一体何故でしょうか。 もちろん何か理由があってのことなのだと思いますが、 古くから人々に愛されていたのには潜在的に備わる魅力が大いに関わっており、 きっとそれは言葉にできない何か抽象的なフェロモンのようなもので、 本人も知らず知らずの内に人間の心を惹き付けてしまうに違いありません。 そしてそれと同時に愛くるしい表情や甲羅のシルエットの可愛らしさ、 家族として迎え入れるのに無理のない大きさなどなど、 挙げ始めればキリが無いほど優れた長所にも溢れているようなのです。 今回やって来たのは俗にイエローアラブギリシャと呼ばれる数あるタイプの内のひとつで、 より小型なオスの方がペット的には扱い易いであろうこんな二匹。 一般的には砂漠など日照りが強く暑い環境に棲息しているとされ、 どちらかと言えば体の黒斑が薄く少なく地色が目立つデザインで、 日差しをはね返すためかそれとも砂地に対する擬態なのか、 少なくとも我々から見れば美しいとしか言いようの無い透き通った黄褐色は、 何処か高級感さえ漂わせるこのタイプ一番の魅力です。 全身がゴールデンに輝いているだけでも満足だったはずが、 顔面や首元を中心に濃厚なオレンジが染み出しており、 何となく探しただけでは手に入らない極上のクオリティが感じられます。 元は野生個体ですが入荷後暫し店内バックヤードにて調整し、 コンディションを整えるべく動きにキレが出るまで育ててみました。 Mazuriリクガメフードにもようやく餌付き準備万端、 暖かい時季だからと言って油断しないよう隙の無い環境にて迎え入れてあげて下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (イエロー・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| どこもかしこもベッタリイエローの美個体! そんな訳はありませんが何だかあの別種に見えてしまう素敵なカラーリングです、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 初めてリクガメを飼う時にお勧めされる、いわゆるビギナー向けの種にはどんなものがいるでしょうか。 もちろん色々な好みというのはあって然るべきですが、 このご時勢ではチチュウカイリクガメの仲間が名乗りを上げることが多くなりました。 昔は輸入量が多く見かける機会が多かったせいか注目度の薄いカメでしたが、 時は巡り次第にリクガメの飼育法が確立されてくると、小型で丈夫で飼いやすく可愛らしい所が良い、 というような結論に落ち着いたようです。 この仲間で特に人気なのがギリシャ党とヘルマン党の二派に分かれるような気がしますが、 ギリシャの魅力は産地や個体毎にバリエーションが豊富であることがひとつ挙げられるでしょう。 同じアラブ亜種内でさえ赤黒黄色と様々な色彩が混在し、 それぞれの個体がそれぞれの色味の度合いで個性を主張しています。 今回やってきたのはベッタベタの極端に黄色味が強いセレクト個体で、 かのCITESⅠに掲げられるエジプトリクガメをつい思い出してしまいました。 エジプト国籍を持つアラブ出身で日本在住のギリシャ、 というせわしないプロフィールが似合いそうです。 国内飼い込み期間は随分と長そうでコンディションは非常に安定しており、 動きの機敏さと餌食いの活発さから見て飼育について心配する点はありません。 あとは色合いさえ気に入ればクリアです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (イエロー・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| その美し過ぎるシルエットを全ての個体に見習って欲しいと思わせるハイドームオレンジギリシャ! くびれた腰元と背甲後縁部の見事なフレアーが緩やかなカーブを描く様も大変セクシーな、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 リクガメを飼い始めようと思い立つや否や、 飼育の容易なものを探し求めて必ず辿り着く種類のひとつに挙げられるのがこのギリシャ。 ひとまず調べてみた限りでは総じて頑丈そうな印象を受けることでしょうし、 また店頭に並ぶ価格帯もこなれていることを加味しても、 ビギナー種の中では文句無しにトップクラスの人気を誇って然るべきだと思います。 更に調査を進めていくと何やら膨大な亜種が存在していることに気付かされ、 しかしながら現実的に最も流通量の多いアラブ亜種しか入手するチャンスには恵まれず、 結局の所は何も気にせず無印のギリシャリクガメを選ぶことになるでしょう。 この時点では急に選択肢が狭まったような気がして少し寂しく感じられるかもしれませんが、 実際には外見のみで亜種を判別するのは極めて困難ですし、 同じアラブ同士を比較したとしても尋常でないほどのバリエーションが実在しているため、 お気に入りの一匹を見つけ出すのに困ることはありませんし、 それどころか違う個体を見れば見るほど次々に物欲が沸いてしまうトリックすら仕組まれているのです。 今回やって来たのは俗にイエローアラブと称されるタイプの中でも、 特に赤味が強く全身がオレンジ色に染まった美しい飼い込み個体。 せっかくの豊富な個体差を生かして人とは違う何かを求めたい方へ、 コントラストの明瞭なベッタリとした配色のこうした個体は、 幼体の頃から既に異彩を放ち目を惹くケースが多く、 またきちんと成熟して初めてその魅力を最大限に発揮することができるため、 本来であれば育てた人だけが味わうことのできるご褒美のようなものと言えます。 そして何が凄いのかと言えばその発色ももちろんなのですが、 この小振りなサイズにして大型個体並みに甲羅が高く盛り上がっており、 何ともアンバランスな体型が数値以上の迫力を生み出していることについては、 育ての親の腕前を心の底から褒め称えざるを得ないでしょう。 ボコ付きの少なさから生育過程も申し分無かったと見え、 なかなかこれほどの腕前を以って育てられた個体もたかが一般種とは言え滅多に巡り会えるものではありません。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ハイカラー・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 柔らかな色使いが上品な佇まいを描き出すミルク多めのココアブラウン! 同亜種内でも個体差が豊富なことは有名ですがこのように淡い色調はなかなか見られません、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 カメと一口に言っても世界中の海を股に掛けるウミガメから近所の川や池に泳ぐミドリガメまで様々ですが、 日本人にとって昔から身近な生き物であることに変わりはありません。 そんな我が国には水棲ガメ、いわゆるミズガメの仲間がいくらか暮らしているのですが、 某童話の影響からかカメはトコトコ歩くものであるというイメージが強く根付いているような気がしてなりません。 ご存知の通りここ日本にいる限りはスイスイ泳ぐカメが見れたとしても、 間違ってウサギと競争させようものなら少しばかり様子が変わってしまいますから、 ならば外国産のリクガメをと思考が働くのでしょう。 ビギナー向けとして紹介される種類も近頃では相場が決まっており、 大きくなり過ぎず活発な明るい性格でどうかすると耐寒性にも優れているといった、 一般家庭の殆どで実践されるであろう水槽内での飼育に適したものが選出されるようです。 少しリサーチすれば必ず登場するのがこのギリシャリクガメ、 ヨーロッパから中東に及ぶ広大な分布域がペットトレードにおいては重宝され、 古くから見かける馴染みの顔ながら未だにその人気が衰えることはありません。 こんもりと盛り上がったシルエットに優しい表情が女性からの受けも良く、 老若男女に好かれる要素は他にいくつも隠されているのでしょう。 それでいて多彩なカラーバリエーションが魅力とあれば、 自分の気に入った一匹を選びたくなるのも無理はないのです。 今回やって来たのは甲羅全体が妙な色抜けを起こしたこんな個体。 高く評価されやすい定番のタイプと言えばイエローやオレンジのように、 鮮やかな暖色が目立つものが重宝されるのは周知の事実ですが、 反対に地味だと切り捨てられる茶褐色をベースに据えてこれほどの美しさを表現した例はなかなか見られません。 バリスタの手により心を込めて注がれたエスプレッソが体中をほろ苦い香りで包み込み、 普通種とされるギリシャを上質な雰囲気に仕立て上げています。 リクガメの場合、色味が気に入っただけで数を増やしていくのは困難と思われがちですが、 本種のオスは15センチ程度に収まることが殆どですから、 片手で楽々扱えるコンパクトさが長い目で見た時に随分と敷居を下げてくれるのです。 四肢の爪がやや長い程度で甲羅のボコ付きもさほど気になるレベルではないと思います、 これからの暖かい季節に屋外で放牧させるのも楽しみです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ハイイエロー・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| まるで金塊より削り出したかのような眩い輝きを放つのはピンクヘッドゴールデンギリシャ! 数ある亜種の中でも特に人気が高いイエローアラブと呼ばれるタイプです、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 いわゆる初心者向けのリクガメとして長きに渡り親しまれているギリシャ、 実は初めて飼育する人にとってはあまり易しくないと思えるほど、 野生では非常に広大な分布域を持つことで知られています。 それによって得られた個体差と言う概念はこのカメを語る上で絶対に外せない要素であり、 そういった外観の差異が分類学的に認められるケースもあったり、 或いは学名こそ与えられずともホビーの世界では区別して認識されていたりと、 ペットとして向き合うのには大変面白味に溢れた素晴らしい逸材であると言えます。 家族的に見た場合は他とは違う我が子だけの特徴を見つけてあげたり、 何でも集めたがりの方にとっては格好のコレクションアイテムにもなり得る、 幅広い層に愛されて然るべきポテンシャルの高さは他の追随を許しません。 特に飼い込み個体が放出されると既にある程度育っている場合が多く、 個性が顕著に表れた状態ですから気に入ったものを選び易いと言うメリットがあります。 今回やって来たのは砂漠系に多いとされるカラーリングのイエロータイプで、 象徴的な甲板の黒斑がかなりの度合いで消え失せたなかなかクオリティの高い一匹。 殆ど無地に近いだけあってそれ一本で勝負できる質の高さが求められますが、 琥珀のように透き通る甲羅の黄土色が実に美しく、 小振りな体格ながら存在感は抜群。 また全てがこうなるとは思えませんがこの個体は頭部全体の色抜け具合が著しく、 ほんのりピンクがかった白い顔はとても野生の生き物とは思えぬ美貌を放っています。 ギリシャのオスは他のリクガメと比べても圧倒的に小型ですから、 省スペースで長く単独飼育を楽しむパートナーにも最適で、 それだけに拘りの強い一匹を選びたいところ。 ワイルドの輸入されたばかりでは状態に気を遣う場面もありますが、 数年単位の飼い込み故に入荷したその日から餌を爆食する安定したコンディション、 何も恐れることなく貴方の手元へお迎え下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ピンクヘッド・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 複雑な配色が入り乱れるトロピカルカラーの珍ギリシャ! 特に頭部のピンクオレンジがとても刺激的です、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 リクガメと言えばギリシャ、そのように紹介しても差し支えのないほど一般に広く知れ渡るポピュラー種。 もちろんケヅメやホシガメなどその他にも好感度の高いものをいくらか候補に挙げることはできますが、 サイズが大き過ぎて家庭での飼育に向かなかったり、 体調管理が難しいなど飼育に際して一定以上のスキルを要求したりと、 あまり万人受けが良いとは言えないのかもしれません。 それらと比べシンプルにリクガメらしさを追求したギリシャの場合は、 大衆に愛される嫌味のない風貌で好みの票が大きく割れることもなく、 それでいて適度なサイズが現実的な扱いやすさをも生み出しています。 何をもってリクガメらしいとするかはお国柄によっても変わってくると思いますが、 今の日本で本種がこれだけ愛されている実情を目の当たりにすればその答えは自ずと導き出されることでしょう。 こなれた価格帯というのも人気を支える理由のひとつで、 こうした話題を快く思わない方もいらっしゃるのかもしれませんが、 実際には初学者に対して余計な敷居の高さを感じさせないというのも大切なことです。 かくしてリクガメ飼育の入り口、入門種としてこのカメが大きく貢献しているのだと思います。 今回やって来たのは定番にして実に奥深いアラブギリシャのオスが一匹。 個体差のデパートと言っても過言ではないその豊かなバリエーションは時に我々を混乱させるほどですが、 特にアラブの場合は赤味や黄色味などが強く出ることもありペットとして見た時には非常に魅力的です。 この個体はパッと見るとイエロー系かと思いきや、 甲羅の継ぎ目にはじんわりとオレンジが滲み出し それが黒斑とまじり合うことで奥深い世界観をつくり出しています。 そのオレンジが四肢にも強い影響を与えているのは言わずもがな、 頭に至ってはまさかの蛍光色がべったりと塗りたくられることになり、 ピンクグレープフルーツの果汁を搾ったようなカラーリングは陽気で華やかな印象を与えてくれます。 その様はまるで南国のインコやオウムの面持ちを連想させます。 いくら変化に富んでいるとは言えこんなタイプには殆ど出会った例がありません、 甲羅のフォルムに不満はなくコンディションも抜群ですから気になってしまったら迷わず決めて下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 視界にメスを見つけるや否や秒速で接近し、なりふり構わず行為に及ぼうとする最強の即戦力! 一匹のカメとしても単に仕上がりの良さが感じられ、甲羅のシルエットなどはまさしく理想的、 メスよりも小振りなサイズで収まるオスとあってペット的に優秀であることは言うまでもありませんが、 仮にブリーディングを狙ってる方がいたとするならば、この個体以上に適役を探し出すのも難しいでしょう。 元々一般の飼育者によって数年単位できっちりと育てられていたのはもちろん、 入店してからも地味に飼い込んでしまったため、給餌はMazuriリクガメフードのみのストイックなメニューで、 餌が盛り付けられた皿が配膳されるのが待ち切れないのか、 毎日正面のガラス戸に向かって笑顔で駆け寄ってくる大変明るい性格の持ち主です。 近頃ではギリシャ自体の流通量が減少しているせいか、こういった出物と巡り合える機会も珍しくなってきました。 素敵なセカンドライフを謳歌してもらうべく、どなたかのお気に召してもらえれば幸いです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (アダルト・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 早く事を起こしたくてうずうずしています。 がっしりといい体格に育った即戦力サイズ、 飼い込みのアラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 当店のHPでもそうですが、多くの場合地中海リクガメの仲間は可愛らしい容貌が特徴として挙げられています。 しかしながら成熟したオスの場合はとても情熱的な繁殖行動を行うことが知られており、 これは見かけによらない相反する性質です。 この個体が以前飼われていた環境では数匹のリクガメが同居していたそうですが、 盛った時にはもれなく体当たりが目撃されていたそうです。 ただひとつ残念なのは同種のメスがいなかった為にオスの精力の行き場が全く無くなってしまっていたことでしょう。 しかし裏を返せばそれはメスさえいれば何とでもなるということです。 もしケージの隅で寂しそうにしているロンリーなメスをお持ちの方は、このパワフルなオスをあててやって下さい。 ハングリーなこの個体が自らの子孫を残すべく奮闘してくれることと思います。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ハイカラー・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 雌へのアピール大作戦なのかまるで何かの雄鳥のように頭や首を真っ赤に染めたド派手セレクト! 黄褐色を黒色のぶち模様が覆うネコ科の動物を思わせる攻撃的なデザインも魅力的な、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 間違っても単なるビギナー向けの入門種と言った扱いで終わらせてはいけない、 それはただ流通形態がそうさせてしまっただけに過ぎない本当は奥の深かったギリシャリクガメ。 今も昔もペットトータスの顔として十分な仕事をこなして来た本種は、 たまたま野生での個体数が他種に比べて幾分恵まれていたことや、 たまたま安価な価格帯で人々の下へ届けられていたがために、 買い易いリクガメとの評判がいつしか飼い易いリクガメへと移り変わり今に至ります。 よく考えれば当たり前の話ですが沢山いれば丈夫と言う考えは決して利口では無く、 もちろん他に類を見ない広大な分布域を獲得したことは評価されるべきですが、 それが人から人へ手渡しされて行く過程で粗末に扱われては意味がありません。 多数の亜種が認められているもののなかなか思うように研究が進まなかったり、 情勢の問題もあって各地方に散らばった複数のタイプが容易く手に入るはずも無く、 それでいて単一の亜種内でもバラエティに富んだ姿を楽しませてくれるのですから本当に有難い限りです。 最近では性別の判定できる大きさで出回る機会が露骨に減少していたり、 一匹毎の単価もじんわりと着実に上昇しているのを肌で感じますが、 その分人々の意識が向上し初期状態の改善や面白い形質の個体がピックアップされたりと、 以前にも増して大切に扱われているような様子が伝わって来ることを嬉しく思います。 今回やって来たのは首根っこを中心に肌の色が激しく紅潮した、 何が何でもその一点に注目せざるを得ない彩り豊かな選抜個体。 言うまでも無くリクガメに対しては色揚げだなんて小手先の技は通用せず、 つまり自然発生的にこのような色合いを獲得したことについては興奮も止む無しと言った具合で、 降り注ぐ陽射しをはね返すほどに赤く燃え上がる発色は見ていて大変に気持ちの良いものがあります。 全身に満遍なく広がった黒斑も特別な雰囲気を演出するためには欠かせなかったのか、 この個体のテーマを決定付ける重要なアイデンティティとして描き出されています。 既にワイルドであるが故のくたびれた感も彼方へ吹き飛ばされた、 トリートメント済みのグッドコンディションです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ホワイトヘッド・♂) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| ただのイエローアラブではありません、 首を伸ばせば神々しく輝く美顔ホワイトヘッド! ぽっと赤らんだ白い素肌に恥じらいが見え隠れするお上品な男の子です、 アラブギリシャリクガメ・オスが入荷しました。 敷居は低く奥は深く、単なるビギナー種の範疇に留まらないポテンシャルの高さを秘めた百面相は、 リクガメ屈指の広大な分布域を武器に様々な表情を私たちに見せてくれる、 ビギナーからマニアまで幅広く愛される指折りの人気種です。 もちろん日本に輸入されたことがない、 それどころかまともな写真すらも世に公開されていない亜種がいるというのも事実ですが、 例えばよく見かけるアラブギリシャひとつ取っても数えきれないほどのバリエーションが存在し、 たった一匹にしか表現することのできないオンリーワンの形質を備えていることもしばしば。 初めてのリクガメとして本種を迎えられた方にとっては、 ご自身の飼育する個体の特徴をよく知ることでそれだけ愛着が沸きますし、 もう一匹と新たに増やす予定があれば似たような個体を探すのか、 それとも今の個体とは異なる魅力を追い求めるのか、そんなことを頭の中に巡らしてしまったが最後、 その時点でギリシャの術中にはまっていると言っても過言ではありません。 決して個体間に優劣を付けるというだけの意味合いではなく、 単に目の前の個体が持つ良さを見つけてあげる、 その新たな認識が飼い主の喜びにも繋がるのではないかと思います。 今回やって来たのは本亜種において時折見かけられるイエロータイプで、 確かに甲羅の色抜け具合が著しく同時に黄色味も強いため、 この段階で既にクオリティの高さはお墨付きなのですが、 更に私はあるとんでもない異変に気が付いてしまいました。 そう、それは頭部全体から首元にかけてが不自然なほどに白く変色しているということ。 その程度はと言うと肌の奥が一部ピンクがかってしまうぐらい激しいものとなっており、 縁起でもないのであまりこのような表現は好ましくないのですが、 半ば生気を失ったような透明感溢れる美貌に思わず見惚れてしまいます。 夏場は野外でお日様の光を浴びながら飼われていたためやましいことは一切なく、 我々はただひたすらにその変わり果てた姿を見て呆然とし、 これが紛れもない珍品であることを徐々に確信していくのです。 甲羅の成長具合も申し分なし、個性的な一匹をお求めの方に。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (イエロー・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 南国フルーツのような完熟イエロー! すきっとした色合いはこの上ない美しさです、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 先日ご紹介したギリシャはブラックタイプでしたが、 今日のこの個体は反対に黒味が殆どなくまるで別種のようなイエロータイプ。 ちょっとでも強くフラッシュを焚いてしまうと大事な色がどこかへ飛んでいってしまう、 とてもデリケートな形質を持つ1匹ですが、とにかく一目見たその時から受ける印象は強烈です。 大きくなると若干でもくすんでしまうことが多い中、 幼体時の透明感をなんとか保ったままこのサイズまで育ってきていることには驚きました。 四肢の鱗や首元がかなり薄い色になっているのもその影響でしょうか。 また背甲の成長線にはダメ押しのオレンジが惜しみなく現れていて実に上品です。 写真だけでは情報の伝達に限界を感じてしまうのですが、 今リクガメのページに掲載している同系色のオス個体と比べてみても遜色のない、 どころかそれを更に上回るカラーリングを持つという事実はお伝えしなければなりません。 これだけ見事な色彩美を持ち安心サイズまで育っているのですが、 ただひとつ右肋甲板が3枚しかないというのが惜しい所。 しかしただでは引き下がりません、 前飼育者の徹底された管理が見て取れるのがはかった様に均等に刻まれた成長線で、 お陰で甲板ズレの影響をほぼ全くと言って良いほど受けておらずフォルム的な問題は一切ありません。 これぞ飼い込み個体の成せる業、一点ものの極美個体、在庫のイエローオスとのペア販売も大歓迎です。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ゴールデン・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 黄金に輝くセレクト美個体! ゴールデンギリシャという呼び名も差し支えありません、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 甲羅も顔も手足も、 全てが黄色味を帯びた非常に美しい1匹。 本種には時折このような色味の強い個体が現れるようで、反対に赤みの強いものはオレンジギリシャと呼ばれています。 その流れを汲めばこの個体の場合はイエローギリシャとなることが多いのですが、 マットな質感の甲羅が光源となっているかのように眩しく感じるためこのようなネーミングになりました。 飼い込みの個体で国内に入ってから成長線もしっかり出ており、 その色はくすむどころかむしろ明るく出ていますので、今後も同様のカラーリングが期待できると思います。 この仲間のオスは求愛行動が盛んで他の関係無いカメにもアタックすることから同居に向かない場合も少なくありませんが、 今回はメス個体なので他のリクガメと同居させながらコレクション目的にも良いかと思います。 フルアダルトになればさぞ立派に見えることでしょう、頑張って大きく育てて下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ホワイトヘッド・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 生まれ持ったその素質は言うまでも無く育ちの良さが全面に表れたベストヒットギリシャ! 細部の特徴云々よりもまず第一にただ漠然と全身から滲み出た雰囲気の良さに惹かれます、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメと言えばの質問にゾウガメと並び挙げられるであろう、 世の中でカメに興味を持つ人々全てが知っているのではないかと思われるほど、 ペットトータスとして長年に渡りホビーの世界を支えてきたキングオブポピュラー種。 その扱い易さは今更説明するまでもありませんが、 ギリシャがこれほどまでに高い人気を博してきた理由にはもうひとつ、 数え切れないほど存在する個体差のバリエーションが関係しているに違いありません。 時にビギナーの皆さんを混乱の渦に陥れてしまうほどの体色差はトップクラスで、 きっと広大な分布域が少なからず関係しているのでしょう、 まるで同じ種類とは思えない色取り取りのデザインには目移りしてしまうこともしばしば。 小さな頃から育てている方にとってはうちの子が一番となるのでしょうが、 暫くして数多くの個体と触れ合っていく内に、 そうして培われる自らの拘りをカメに対して投影するようになり、 頭の中につくり上げられた理想の偶像を求め彷徨うようになるのです。 今回やって来たのはここ数年で出会った中では最も強烈な衝撃を与え、 少なくとも私の頭の中では非常に高い得点を叩き出してくれたスペシャルセレクション。 初めは何故一匹のギリシャにこれほど見入ってしまうのか不思議で仕方ありませんでしたが、 サタデーナイトにわざわざ普通種を持ってきた理由が此処にあります。 まず一目見て気に入ったのが濃厚なイエローが惜しみなく塗りたくられた甲羅、 例えばイエローアラブと呼ばれるタイプにしてもこれ以上に明るめの色合いであることが殆どで、 しかしながらあの透明感も今ではすっかり見慣れてしまいましたから、 茶色になりそうでそうはならなかったこの濃さは称賛に値します。 次に頭の色、顔面蒼白と言い表せば何だか不健康な印象が強まりそうなものの、 澄んだ瞳の奥に宿る生命力が露わになったこの個体にそのようなマイナス要素は一切感じられず、 ただひたすらに美貌を追求した結果として判断されるのみです。 ギリシャモザイクのコントラストも見事でまだ他にも言うべきことは沢山ありますが、 このツルンと仕上がった背高フォルムの前にもはやこれ以上の小細工は必要ないのかもしれません。 あまりにも高過ぎるトータルバランスに加えて性別は嬉しいメス、 絶品なことこの上ないハイクオリティの真髄を目の当たりにして下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (イエロー・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 人気の高いイエロータイプであることに加え美しさの更なる高みへと誘うホワイトヘッド! 輸入直後のくたびれた感からおさらばしたメスには珍しい飼い込みの放出個体、 アラブギリシャリクガメが入荷しました。 ビギナー向けの飼い易いリクガメと称され早何年が経過したのでしょうか、 恐らくと言うよりもほぼ間違い無く、 リクガメがペットとして飼育され始めた黎明期よりそう言われ続けているのだと思います。 このカメにとっては野生での分布域があまりにも広大なことが運の尽きだったのかもしれません、 とにかく流通量が多くそれに伴い安価な水準が長らく維持されていたため、 色々な意味で手に入り易いとなれば自ずと敷居が下がるのも避けられず、 一度立ち上がってしまえばかなりタフな一面を見せることからも、 幸か不幸か簡単に育てられると言うイメージが根付いてしまったようなのです。 言うまでもありませんが百発百中で全てをパーフェクトに仕上げるのは至難の業であり、 野生個体ともなれば初期状態にバラつきが出るのも当然のことで、 決して高価な種類では無いがために粗雑な扱いを受けることもありますから、 流石に日本に到着したばかりでは様々なリスクが付き纏います。 しかも厄介なことに現地では多様な環境へ適応し繁栄したことが災いし、 タイプ毎に適切な環境を設定しなければ上手に立ち上げられないケースも多く、 最終的な飼い主の下へ届くまでにピントがずれてしまっていることも珍しくは無いようです。 今回やって来たのは最も見かける機会の多い定番の亜種アラブギリシャから、 全身の色合いが殆ど黄色一色に近い俗にイエローアラブと呼ばれるタイプ。 砂漠のような自然界ではこのような配色が目立ち難いのでしょうか、 しかしながら飼育下でのそれはただただ美しさを追い求めた姿でしか無く、 観賞価値の高さから長きに渡り珍重され今日に至ります。 飼育には高温のバスキングスポットがカギとなるなど、 例えば同じくチチュウカイのヘルマンのようにざっくばらんにはいきませんが、 導入時のコンディションだけクリアできていればこれほど心強いことはありません。 四肢にもしっかりと肉が付いておりトルクも十分、 わざわざ大型のメスがシングルで手放されることも滅多に無いためかなり狙い目の掘り出し物です。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (オーバル・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 愛嬌と迫力を兼ね備えた未曽有のフォルムで立ちはだかる唯一無二のてんとう虫ギリシャ! 特別なことは何もして来なかったそうですが鉄球のような重みが情の深さを表しています、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメを育ててみようと思い立った時、スタイルやデザイン、 カラーリングなどについつい目を奪われてしまうことはままありますが、 何はともあれまず初めに重要視するのは果たしてそれが飼い易いか否かでしょう。 右も左も分からない内は何もかも全てが不安に思えますし、 命を預かるという責任感から前もって準備を整えておくのは本当に大切なことです。 しかし実際にはいざ飼育を始めてみなければピンと来ないことばかりですから、 そうなるとやはり誰かしらの経験談や初心者向けの一言が有難味を増すことは否めません。 結果的に多くの人が選ぶ種類というのは一定の範囲に集約され、 気が付けば周囲が同じものを飼っていたというのもよくある話なので、 あとは如何に根気よく飽きずに世話をし続けられるかということに勝負所が移っていきます。 他の爬虫類と比べて特にカメの仲間は甲羅というパーツの特性上、 育ちの良し悪しが外観に直接影響してしまうため、 俗に飼い込み個体と呼ばれるものは辿って来た経緯により評価が真っ二つに分かれるのです。 種としての稀少性を語る前に野生動物としての持ち味を何処まで生かし切れたか、 それはビギナー、マニア問わず注視されるべき要件だと思います。 今回やって来たのは何の変哲もない、 なんて失礼な表現は絶対に当てはまらない実に興味深い格好をしたギリシャ。 一体何をどうすればこれほどまでに甲が高く盛り上がり、 そして両サイドにここまでの張りが生まれるのでしょうか。 生地に酵母でも練り込んだのかしらと疑いたくなるふっくらとしたフォルムに圧巻、 そしてボコ付きのボの字も見られない驚異のツルツル仕上げに脱帽、 昨日までの飼い方をしつこく尋ねてみたのですが別段変わった様子もなく、 残念ながら達人の極意を盗むことには失敗してしまいましたが、 結論としては何も特別なことではないカメ一匹への愛情が成せる業なのかもしれません。 参考までに主な食生活は市販の葉野菜を中心に基本的なサプリメントを少々、 紫外線は蛍光灯レベルですが温暖な日を見計らって度々お日様の恵みを受けていたとのこと。 男社会のチチュウカイリクガメにおいてメスは繁殖にも複数飼育にも重要な存在、 悪気がなくても思わず笑みのこぼれる素敵な造形をご堪能あれ。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 茶色と黄土色のアニマル柄が何処か野生的な丸々と大きく育ったつい繁殖に使いたくなる即戦力! 口をへの字に結んだ気難しい顔立ちもご愛嬌の貴重な大型サイズです、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 一体何処の誰がそう言い始めたのやら今となっては定かではありませんが、 初めてリクガメを飼うとなれば銘々が口を揃えてその名を挙げる、それがこのギリシャリクガメ。 安価かつお手頃な大きさで年中出回っているため人々の目に触れる機会も多く、 インターネットを使えばどう調べたって初心者向けというキーワードから逃れることができないほどですから、 ビギナーさんにとっては大変に心強いビッグネームのひとつです。 これほどまでに業界への貢献度が高いカメもそうはいないと思いますが、 やはり人気が人気を呼ぶという現象がそれを後押ししているようでもあり、 何か大きな問題が起こらない限り未来永劫この地位を保ち続けていくのでしょう。 初めてのカメになることが多いだけあって名前が付けられている確率も高いのですが、 小さな頃から育てるとほぼ全てとは言いませんが不思議とオスばかりが出来上がってしまい、 例えば最初は可愛いから、 寂しそうだからと複数匹で育て始めるといずれ男子校状態になることもしばしば。 盛りの付いたオス同士の殺伐とした空気は時に実害を生むケースもあり、 放出される個体の性比はどうしても偏りがちです。 また一匹目の飼育にある程度慣れてくると次の二匹目を探したくなるのは人情ですから、 既に性別がメスと確定した個体の人気は依然として高く、 如何せん出物が不足しがちなために需要過多となり毎度争奪戦が繰り広げられるのです。 今回やって来たのはほぼ完成に等しいその甲羅のシルエットに一目惚れしてしまう、 とても綺麗に仕上がりつつあるアダルトサイズの貴重なメス。 少し表現が大袈裟かもしれませんが各甲板に点在する黒いスポットは豹柄チックで、 普段見慣れたギリシャと比べると何となくワイルドな雰囲気が漂い、 片手に乗せるのが精一杯なそのボリュームも相まって非常に強い存在感が楽しめると思います。 頭部の色彩は鈍い輝きを放つ赤銅色が良い味を出しており、 目元もぱっちりとしていて女性らしい顔立ちが特徴的です。 ほぼ全てパーフェクトなのですが惜しいことに嘴の噛み合わせが交差しており、 何だか世の中に不満有り気な表情を浮かべていますが、 採餌への影響は全く無く当人も受け入れている様子ですので、 イカの甲やカルシウムブロックを常設するなどして予防を手助けしてあげて下さい。 別段繁殖を狙わずとも同居飼育が容易なメスはいつも大人気です。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (フルアダルト・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 外観はバリバリワイルドのくせに中身はまるでCBのようなキレを見せる貴重なフルサイズのメス! 野生で成熟を迎えたため当たり前なのですがそのパーフェクトなシルエットに惚れ惚れする、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメを飼育対象としている私たちにとっては最も馴染み深く、 そして最も飼い易い種類のひとつであり、 更には最も謎めいた存在ではないかと思われるご存知ギリシャリクガメ。 その名前とは裏腹に国としてのギリシャであったり、 或いはギリシャ神話などとは全くの無縁であることがそもそも面白いのですが、 もはやそんな小さなことはどうでも良いと感じられるほど、 この業界ではすっかり広く知れ渡ったビッグネームであって、 もう何十年とその大きな役目を果たし続けて来た功労者のひとりです。 一言で言えば初心者向けのリクガメとして大いに名を馳せ、 数多くの愛好家をこの趣味へと引きずり込んだ主犯格でもあるのですが、 近年ではいよいよ野生個体の流通量も減少の一途を辿り、 単にペットとして向き合うことも難しくならざるを得ないようなムードさえ漂っています。 やはり現地の野生環境からそれ相応の雰囲気を纏って海を渡った一匹に備わる風格とやらを、 もう一度心の底から味わってみたいと思うのは実に罪深く、 とは言え真のマニアにとってはそれこそが本当の願いなのだと思われ、 少しでもこういった骨董的付加価値の見込まれる個体を大切に取り扱っていければと考える次第です。 今回やって来たのは何処からどう見ても野生まる出しと言った大胆なビジュアルで真っ向から勝負する、 このご時世では大変に珍しいただただ大きく育っただけの飼い込み個体。 ご察しの通り今日ではフルサイズの野生個体をそっくりそのまま輸入すること自体現実的では無く、 それがまた良好なコンディションを保ち国内で飼育され続けこうして出物として再び現れることが、 どれほど素晴らしくまた今後どれほど難しくなっていくのかを想像するだけで胸が痛みます。 ほのかに摩耗した茶褐色の甲羅にこれ以上求めるものは何も無く、 ただ目の前で躍動していることが感動を生む素敵過ぎる逸品、 おまけに皆さんお探しの稀少なメスと言うこともあり然るべきところへお届けできれば幸いです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (シリア産・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| その美し過ぎる甲羅の育て方を手取り足取り教わりたいレジェンドクラスの腕前による究極の一品! 手の平サイズからよくぞここまで仕上げられたと感服させられる見事なお手本です、 シリア産のアラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメの人気種と聞いてまず初めに思い浮かぶのがホシガメ、 その美貌はいつの時代も世界中の人々を虜にして止みませんが、 如何せん飼育が難しいと言うイメージばかりが先行し市民権を得るのには苦戦しているかもしれません。 そして忘れてはいけないもうひとつは何と言ってもみんな大好きケヅメリクガメ、 しかしながらこちらもご想像の通り圧倒的な存在感が仇となり、 さすがに一般家庭で飼い切ることを考えると誰しもが挑戦できるカメではありません。 票を投じることと実際に手元へ置いてみるのでは大きなギャップが生じるため、 そう考えると最も庶民的で支持の厚いナンバーワンに君臨するのは、 やはりこのギリシャが選ばれるべきなのでしょうか。 いわゆるビギナー向けの御三家に数えられる本種は、 単なる飼い易さに加えて外観のデザインも豊富なことから好みの一匹を見つける楽しみがあり、 また長年リーズナブルな価格帯も敷居の低さを実現していると言えます。 始めたばかりで右も左も分からなかった頃から、 段々とディープな世界へ誘われるに連れて個体毎に異なる特徴にも気が付くようになり、 無意識の内にその奥深さへとはまり込んで行く、 そんな初心者からマニアまでどっぷり楽しめるリクガメの代表種です。 今回やって来たのはロカリティまでしっかりと付いたシリア出身の大柄なメス。 もちろんこの大きさで輸入された訳では無く国内で育てられた一匹なのですが、 昨日捕まえてきましたと言っても信じてもらえそうなほどツルツルの甲羅には文句の付け所が見当たりません。 一朝一夕では成し得ない仰天のクオリティ、 これを愛情の賜物と言わずして何と呼べば良いのでしょうか。 背中の模様は典型的なギリシャモザイクにやや地色のイエローが強めで、 そこから飛び出す体には濃いめの蛍光オレンジが光る美しさ。 何処にでもいる定番種だからこそ気に入った個体を末永く楽しみたい、 品質に拘る方にとっては特に見逃せない観賞価値に富んだ素敵な逸品です。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (特大サイズ・♀) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 重さを量れば1.5キロもある超ダイナミックボディ! 特大サイズのビッグママが満を持しての登場です、 アラブギリシャリクガメ・メスが入荷しました。 人気者が集まるチチュウカイリクガメの仲間で最も広大な分布域を誇るギリシャリクガメ。 他の種類はきちんと大人しく地中海沿岸ないしは欧州地域に棲息しているのですが、 本種やホルスフィールドは貪欲にも陸続きの中東地域にまで縄張りを拡大し、 特にこのギリシャは現在確認されている亜種をまともに数えると 大変なことになるという大層な繁栄ぶりを見せています。 お陰でビギナー向けのリクガメとして毎年コンスタントに出回り身近な存在として知られていますが、 いつも見慣れているだけに突然大きなものが現れると仰天してしまうのは世の常でしょうか。 今回やってきたのは、現地の人間にこの辺りで一番大きなカメをと注文してその場でとっ捕まえた、 としか思えないほど貫禄に満ちた、ベビーから8年余りの歳月をかけて育てられたメス個体。 この厚み、この重み、最高です。 甲長はもう少しで大台に乗る所でしたがそんな細かい数字は気にせずに全体像を愛でましょう。 調子の良い日はまるで発情したオスのようにケージの壁や他のカメにアタックし、 餌を与えても常に遠慮なく割り込み好きなだけ食べて帰っていきます。 このサイズのメスがいないかと言えば国内にも存在はしているのでしょう、 しかしそれが出回るかと言えば今回のような機会は本当に稀だと思います。 初生甲板の偏った箇所がありますが結果的に全体の歪みは出ていないので気になりません。 思い思いの環境でこの巨体に満悦して下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ
Testudo g. terrestris |




|
|
||||||||
| 物凄く分布域が広い本種ですが、今回入荷したのはいわゆる”テレストリスギリシャ”です。 2ペアで2タイプいますが、1つは全体を引き締めるように黒いラインが、もう1つは全体的に 黄色でありながらも仄かにオレンジが発色しています。餌食いも抜群で、 リクガメフードも大丈夫です。このサイズでこんもり綺麗に育った個体はなかなかいません。 単品で出していますが、ペア価格は30,000円になります。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| この夏からリクガメの屋外飼育を始めてみませんか。 お客様飼い込みのアラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 近縁のヘルマンと並んで飼育される事の多い定番種で、手頃なサイズと丈夫な体質からビギナーにも人気のリクガメ。 ギリシャに住んでいる訳でもないのにギリシャリクガメとはこれ如何にという感じですが、 名前の由来はカーペットの模様に使われるギリシャモザイクというブロック状の柄にちなんでいるそうです。 この類のカメはベビーから親ものまで出回っていますが成熟サイズに近いものでしかも雌雄が揃う事は意外と少なく、 しかも今回は飼い込みなので環境が変わっても直ぐにシャキシャキと動く辺りはさすがです。 オスは黒ぶちの入った全体的に暗色の外観で、 反対にメスは濃い黄色地にメリハリをつけるように黒斑が入っています。 可愛いベビーを見てしまうとどうしても欲しくなってしまいますが、 最初から外で飼う事を前提としている場合は大きなサイズがベター。 温度変化や些細なことに対して心配する事が少なく、安心して外に出しておけるでしょう。 ギリシャのCBというのはいそうであまりいませんから、ゆくゆくはこのペアで狙ってみては如何でしょうか。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (イエロー・Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 照り付ける太陽光をもはね返す明色のボディが眩しい典型的なイエローアラブのグッドサイズペア! パターンレス系の似たようなタイプでこれほど相性の良さそうな出物は稀、 アラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 世の中はリクガメブーム、 カメ目におけるたったひとつの科にしか過ぎない分類上はちっぽけなグループであるはずが、 こと趣味の世界においてはその存在感の大きさは計り知れません。 一昔前は単に珍しさばかりが全面に押し出されていたようでしたが、昨今ではそれと少々雰囲気が異なり、 ペットとしての飼育が現実的に可能になったことがただのエキゾチックアニマルを超えた、 新たな価値観を創造しているのです。 しかしながら古典的なマニアの作法に従うと、 如何せん種類数が限られているため集め始めた所で直ぐに終わりが見えてしまうと思いきや、 中には豊富な個体差がオリジナリティを発揮するためか終わりなき迷宮に誘い込まれてしまうケースも。 このギリシャこそまさしくその代表例、 個体差のデパートと言っても過言ではないその形質差は研究者でさえ舌を巻くほどで、 有り余るポテンシャルにより描かれた無限のデザインが一番の魅力であり、 そんな底無し沼に嵌ったまま延々と選び続けるのもまた楽しみなのです。 今回やって来たのは象徴的な背甲のギリシャモザイクがほぼ消失し、 全体的に黄土色からレモン色と大変綺麗にまとめられた素敵なペア。 この頃輸入されて来るのは殆どが手の平にすっぽりと収まるせいぜい安心サイズばかりで、 片手でやっと持ち上げられるような大型個体の流通は激減しています。 この二匹はそんな幼体から似たようなカラーリングを選出して育て上げられたとのことですが、 良い意味で疑いたくなる両者間のバランスの良さがお互いを引き立て合い、 大きく歪になった箇所も見当たらない結構な仕上がりを見せています。 特にオスは漢らしい体格が早くもシルエットとしてつくり出され、 頭部の色彩は白色から赤紫色のグラデーション仕立て。 メスの方はとにかく顔全体の白さが尋常ではなく、 甲羅から四肢の隅々まで色味の鮮やかさを追求しています。 今すぐ繁殖へと意気込みたいところですがメスはまだまだ成長期、 きちんと伸ばしてあげれば更に見栄えのする組み合わせになると思います。 餌食いは葉野菜からMazuriリクガメフードまで良好なことこの上なし、 同じケージに入れてもオスは四六時中交尾をしまくる訳でもないので、 同居飼育を念頭に置いても問題ないでしょう。 もう少し暖かくなったら外へ出すのも待ち遠しいですね。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| その色、質感、まさに象牙! 同亜種内でも形質に差が出る中でこれだけ似通った2匹が集うのも珍しいです、 アラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 その広大な分布域は地中海を囲み欧州からアフリカ大陸北部、 更には古代ギリシャ人が目指した中東エリアにまで進出し、それに伴い多くの亜種を擁するリクガメ。 その数は学説により増減するため全てを把握することは困難ですが、 単にギリシャと呼ばれて販売されているものも含み最も流通量の多いのがこのアラブです。 それこそ昔からリクガメのホビー界を支えてきた功労者でもありますが、 安価だからと言って決して甘く見ることはできません。 同じアラブの中でさえ個体差はバリエーションに富み、 図鑑を見たり情報を調べたりしている間に混乱してしまう恐れさえあります。 ですが裏を返せばお気に入りの色柄を選び抜くチャンスでもあり、 初心者から玄人まで人気を保ち続けている理由はそこにあるのかもしれません。 今回やってきたのは広く括るとすれば所謂イエローアラブ、 しかし黄色味の気持ち足りない変わった色合いを持ったペア。 特にオスは所々が白っぽく透き通っていてどこか飴細工のような質感が伺えます。 どちらも黒斑が限りなく小さくそして薄れ、 地色の良さを強調するにはこのやり方が一番手っ取り早かったのだと思います。 ギリシャは飼育例こそかなり多いものの意外と繁殖例が少なく、 同属のヘルマンに比べると国内CBというのはかなり珍しい存在です。 そこでこの豊富な色彩を利用し、 せっかく国内繁殖に挑戦するのなら同タイプのペアからどんな姿のベビーが生まれてくるのか確かめてみたくはありませんか。 オスもメスも甲羅の形状が完全なフォルムとは言い難いことと、 メスの両眼がやや白く曇ってしまっているため、 このサイズでこのカラーのペアにしてはお値打ち価格に設定しました。 ブリーディングを志す方に捧ぐ期待のアイボリーペアです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (マホガニー・Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| おかしなことにまるで別の人生を歩んできた二匹が同系色で夫婦となった完全なる奇跡の巡り合わせ! 可愛らしさよりも格好良さを重視したようなダークブラウンにひとつのテーマを感じる見事な出来栄えの、 アラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 かつて初心者向けのリクガメと謳われ日本中でその姿を見かけた往年の銘種は、 この数年で現地での採集量など生々しい部分に少しずつでも着実な変化が生じているらしく、 どうやっても流通が不安定になったり取引額が高騰したりしながら今日に至ります。 とは言え元々が信じられないほど安価に販売されていたギリシャですから、 流石に棲息数が減少していると指摘されれば誰ひとりとして文句は言えず、 よく考えてみればただ大量に輸入されていただけで最も飼い易いとは限りませんし、 これを機に人々の意識や実際の扱われ方が変わっても良いのではないかとさえ思います。 しばしばビギナーからマニアまでと評価されているように実はかなり奥の深いリクガメのひとつで、 例えば同じアラブギリシャという名前が付いているものだけに絞ったとしても、 無限とも言うべきえげつないバリエーションを誇る辺りにその凄みを感じて頂ければ、 彼らとしても正当な評価を受けられたと少しは喜んでくれるのではないでしょうか。 国境を跨いで来日するギリシャの全てが初期状態に恵まれている訳ではなく、 立ち上げも含めた長期飼育が意外と難しいことから雌雄が揃う機会にも乏しいでしょうし、 或いはペットというそれ以上でもそれ以下でもないポジションに落ち着いてしまいがちなところも相まって、 これほど出回っている割には国内での繁殖例がまだまだ少ないことも今後の課題ではないでしょうか。 未来のリクガメ愛好家にとっても絶対に必要なキャラクターであることは間違いなく、 後世へと上手に遺していくための工夫が必要であると、 誠に勝手ながら改めてそう感じさせられる今日この頃です。 今回やって来たのはオスもメスも全く別のところからお出ましし、 偶然当店にて結ばれることとなった見るからに同じタイプのペア。 ギリシャと一口に言っても色々ありますがこの個体たちは特に変わった雰囲気で、 殆ど模様の入らない落ち着いた色調の甲羅にはよく見ると各甲板に小さな黒斑が並び、 体全体にも色味はなく表面には金属光沢さえ施されているほどで、 これをなんと呼ぶべきかは決まっていないでしょうし今のところ決める必要もなさそうですが、 とにかく様々な色柄が選べるようで実は選べないギリシャの世界において、 即戦力とも言える大型の飼い込み個体で近しい形質を持つペアが揃うことなどまずありません。 欲を言えば国内繁殖の成功に向けて取り組んで頂きたいとも思いますが、 まずは見た目に同じような二匹のギリシャが手に入ったという喜びで満たされて下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ハイカラー・Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| その仕上がりに誰もが舌を巻く巨漢のメスとまさかの同じ模様で寄り添うオスとが奇跡のコラボレーション! 下手なマルギナータやその他リクガメらと比べても逆に珍しい同一デザインの雌雄が揃う空前絶後の、 アラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 ここでは便宜上、狭義のアラブギリシャとして紹介していますが、 恐らく今日ペットとして流通しているギリシャについてはその殆どが亜種アラブだと思われ、 他に明確な呼称が与えられ出回っているのはイベラことトルコギリシャぐらいのものでしょうか。 かのイーストアナトリアンジャイアントも結局はイベラの地域個体群ですし、 分類上は実に多彩な亜種や地域個体群を有する大所帯という設定にはなっていますが、 現実的に私たちが利用可能なものに絞り込めばその数十分の一、 いや数百分の一に過ぎなくなってしまうのかもしれません。 ただしこの場ではその見えない部分に果てしない可能性があることを示唆したい訳ではなく、 アラブというたったひとつの亜種内にも無数のバリエーションが存在し、 この何十年の間にギリシャリクガメがわんさと輸入されてきた事実に目を向けながら、 改めて埋没しかけていたポテンシャルの高さに気が付いて欲しいというのが本音です。 とにかく似たような色柄の組み合わせをピタリと当てるのが非常に困難で、 とても高度な神経衰弱ゲームに挑まされているような心持ちになるのですが、 有り余るほどのギリシャが抱えきれないレベルで海を越えて来ていた時代はとうに過ぎ去り、 初心者向けのリクガメという絶大なブランドも揺らぎ始めた現在の境遇を加味すれば、 たとえ同じロットの同じ便で来日した同胞より死に物狂いで選別を行ったとしても、 まさか同じ程度の同じ出来栄えでオスとメスを揃えるなど無謀極まりない、 まさしく雲を掴むような話だと考えられます。 こんなことを口にしているだけで悲しみが込み上げてくるのは私だけではないでしょうが、 千載一遇の好機を何処かで待ち望んでいる大変にイカれた嗜好を持つ自分がいることも事実です。 今回やって来たのは一目見てその凄みに圧倒される、 片手に乗せるには勿体ないほどずっしりと仕立てられた特大メスと、 それをそのまま縮小したかのようなほぼ同じ外観を有するオスとのミラクルペア。 二匹とも背中に一ミリの凹凸も許さない気味が悪いほどのツルツル具合で、 オスはまだまだ伸び盛り、 メスははち切れんばかりの甲羅を背負う平均以上の巨体を駆る絶品で、 既に交尾行動も見られるほどの相性の良さ。 念のため繰り返しておきますが、 例えばヘルマンなどでは雌雄が同じような見た目をしていることに驚く必要はなくとも、 これがギリシャともなれば天地が引っくり返るような衝撃的案件なのであって、 はっきり言って二度とお目にかかれないレベルの地上最強ブリーディングペアです。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (特大サイズ・Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| キング&クイーンサイズの超豪華ペア! リクガメにしては小さな体ですがたちまち地響きの聞こえてきそうな特大フルアダルトです、 アラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 ヨーロッパから中東にかけて広く分布するチチュウカイリクガメ属の中で、 極めて広大な棲息域を持ち昔から流通量も多く、 我々日本人にとって非常に馴染み深いリクガメのひとつがこのギリシャ。元来丈夫な性質はもとより、 リクガメ全体を見渡しても小ぶりなサイズと幅広い温湿度耐性から飼育に適した種とされ、 国内での繁殖例も近頃は特に多く聞かれるようになってきました。 今回やってきたこの2匹、まず恐ろしいのがそのサイズと生い立ち。 オスは文句なしの過去取り扱い最大サイズ、 メスも十分過ぎる豊満な体つきをしており、 なんと驚きどちらの個体もベビーサイズから実に8年近い年月をかけて国内のマニアが丹念に育て上げたとのこと。 このクラスは雌雄単体で入荷することはあれど、 ペアが揃った状態でご案内できる機会は滅多にありません。 ワイルド個体をそのまま捕まえて差し出されたような、 理想的な美しいフォルムは簡単に真似することのできない技術と愛情の賜物でしょう。 活発なギリシャは甲板や鱗の隙間に餌の残りや糞などがこびり付いてしまうことも多々ありますが、 前飼育者宅では時間の許す限りほぼ毎日のように温浴で体を清めていたそうです。 ご察しの通り既に産卵も経験済みで、 オスは別居せざるを得ない程に積極的ですから成果があげられるのも秒読みかと思います。 飼い込み個体の飼いやすさと野生個体の迫力を兼ね備えた非常に素晴らしい今回のペア、 お早めにお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ブラック・Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| 一口にブラックと言っても色々なものがいますが今回はまだらタイプ! 出身地も育った環境もまるで違うそっくりさんが運命的な出会いを果たしました、 アラブギリシャリクガメ・ペアの入荷です。 ここ最近のリクガメを取り巻く環境を大きく変化させてしまった今を時めく人気グループ、 チチュウカイリクガメの一角を担うのがこのギリシャ。 ホルスフィールドやヘルマンと共にペットとしてのリクガメのイメージを大きく変え、 その功績は周りの他種に対しても波及してしまうほど。 かつては安価で大量に流通していたことから良いイメージを持たれることのあまりなかったこのグループも、 小型で飼いやすく環境にも適応しやすいなど種としての特性が見直され、 今ではどの図鑑や飼育書を見てもビギナーにお勧めと大きく取り上げられるまでになりました。 さてこのギリシャリクガメという名前、 国としてのギリシャには一見棲んでいそうでも実際には分布が確認されていないらしく、 これは棲息地ではなくギリシャの織物に施されたモザイク状の模様がその由来なのだとか。 と言われても元ネタにピンと来ないのが辛い所ですが、 この2匹を見てみると確かにそんなエピソードにも納得できそうな雰囲気を感じ取ることができると思います。 雌雄どちらも地色はあくまでイエローですが、 その上に色付けされるのはオスがブラック、 メスはややブラウンと変わっていて、 両個体とも典型的なギリシャらしい柄を主張。 更に単調なデザインで終わることはなく、 隙間を有効活用するかのように細かいドットがチラホラ見られる所も興味深いです。 そして本日このペアを紹介することになった最大の決め手、 それは1ヶ月ほど多頭飼育していて何のトラブルも起きなかったオスが、 そこにこのメスを新しく投入した途端、何かを思い出したかのように突然盛り出したということ。 カメの場合は何色の糸か分かりませんが、両者がうまく結ばれた証でしょうか。 意外と繁殖例は少ないので一般種であるだけにやりがいがあると思います、是非このペアで挑戦して下さい。 | ||||||||||
|
アラブギリシャリクガメ (ブラック・Pr) Testudo g. terrestris |





|
|
||||||||
| ブラックベースの重厚な雰囲気を持つもの同士でペア! しっかりと成長した大変見栄えのする2匹です、 アラブギリシャリクガメ・ペアが入荷しました。 チチュウカイリクガメ属に分類されているためてっきり欧州に暮らすリクガメかと思いきや、 そのあり余る生命力からか中東方面にまで棲息域を広げてしまったペットトータス代表種。 名前も紛らわしいのがいけません、 ギリシャ絨毯に施されたモザイク模様が甲羅の色合いと似ていることが由来だそうです。 分布は広く亜種も多くさらには同一亜種内での個体差も激しく、 最も流通量の多いアラブでさえこれだけ楽しませてくれるというのは本当に有難い限り。 他のリクガメにはあまり見られないカラーリングだからでしょうか、 中でも黒を基調としたタイプはブラックギリシャとも称され根強い人気を誇っています。 今回やってきたのはそんな黒いタイプの2匹で、由来は別々ですが運良く雌雄が揃ってくれました。 オスはブラック&イエローのすっきりとした明るいイメージ、 それに対してメスはブラック&オレンジの毒々しささえ感じるきついイメージで、 同系色ながらそれぞれ異なる魅力を備えています。 撮影中にもオスはその気になってしまったらしく、 走るメスを執拗に追いかけ存在感をアピールすることを忘れていませんでした。 メスはよく見ると甲板が分かれていますが、 これだけ良い色の個体ですしまた大きくなった今ではさほど目立たないでしょう。 さらっと紹介してしまいましたが、 同サイズで色味も近いお似合いのペアは探して見つかるものでもありません、是非この機会に。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (マケドニア産) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 今年生まれの可愛いベビーがわらわらと! 産地直送のピカピカな個体ばかりです、ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 皆さんも既に感じ始めていることでしょう、近頃じわじわとヒートアップしているリクガメブーム、 その立役者の一翼を担うのはこのカメに間違いありません。 気候がよく似たヨーロッパ出身のチチュウカイリクガメは日本の環境に馴染みやすく飼いやすいと言われ始めて何年が過ぎたでしょうか、 その人気はとどまることを知らず全国各地で新たな愛好家をこの世界へいざなってきたことと思います。 ただ扱いやすいというだけならまだしも広く受け入れられる愛らしさを持ち合わせているというのが憎い所。 近縁種のギリシャやホルスは中東エリアにも分布し現地のベビーが輸入される機会も多いのですが、 ヘルマンの場合はむしろ国内繁殖が盛んで毎年のように国産CBが姿を見せてくれるというのは本当に有難いです。 しかし今回、当店としては久しぶりにEUからの繁殖個体がやって来ました。 親個体の由来はマケドニア産、恥ずかしいことにいまいち実感がわかず改めて地図で場所を確認してしまいました。 パッと見て感じるのは、 決して何となくではない頭部の黒さ。 地域差なのか親の形質の違いから生じるものでしょう、特に国内のものでは頭の黄色いタイプを見かける機会が殆どで、 どちらが綺麗だとかは関係なく単純に興味深い特徴です。 体全体も地黒で鱗のレモンイエローが妙に際立ちなんだか別のカメみたい。 実はもう少しまとまった数が入ったのですが生まれて間もないのか4cmにすら満たない個体も多く、 体格が良く既に成長線も出始めた強そうな4匹を本日ピックアップしてみました。 状況を伺うにとても1ペアから生まれた仔では無さそうなので、 この中から同産地ペア狙いで揃えてみても面白いかもしれません。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (国内CBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| ふっくらと蒸し上がったお饅頭のような可愛らしさはこの時期にしか味わえないベビーの特権! こんな小さな体でもよく走りよく食べよく潜る抜群のコンディションは流石国内CB、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 今やペットトータスの世界にとって無くてはならない究極のマストアイテムのひとつ、 それが一般に飼い易い、育て易いとされ需要の拡大は留まるところを知らないヘルマンリクガメ。 そんな噂は十年以上も前から囁かれており今更何をと思われるかもしれませんが、 かつて本種は原産国で厳しく保護されていたこともあって間違っても安価なカメでは無く、 まだ当時はギリシャやロシアが大変に幅を利かせていた時代でしたから、 どちらかと言えばよく知った方がわざわざ選ぶ少しマニアックな位置付けでした。 最近では現地で養殖が進み健康な幼体が毎年コンスタントに輸入されるようになり、 或いは国内で育てられたものが親となり子孫を残すようになるなど、 もはや野生とは切り離された状態で供給が持続する仕組みが出来上がったことで、 改めて飼育動物としての価値観が高まったように感じられます。 いずれは海外からのCBに頼ることなく自国内での生産力が高まり、 誰もが手にすることのできるチャンスが広がればより健全になるのではと思いながら、 リクガメを育てることに対するハードルが下がるよう願って止みません。 今回やって来たのはお客様が繁殖に成功したあまりにも可愛い幼体で、 日本生まれならではのミニマム感が嬉しい元気いっぱいの兄弟たち。 元々はアメリカハコガメなどを殖やされていたブリーダーが、 同じような感覚で通年屋外飼育を楽しまれていた両親から得られた子孫で、 ようやく成熟度が高まったと見え今年遂に念願のハッチへと漕ぎ着けたとのことでした。 甲羅や四肢のカラーリングに強いメリハリが感じられ、 頬の黄色味もよく目立つことから大きくなればかなり綺麗になるのではと期待しています。 体付きひとつ取っても餌食いの良さがひしひしと伝わって来る仕上がりで、 甲羅から中身がはち切れそうなほどパンパンになった様子が一匹一匹を手で摘まみ上げただけでよく分かります。 早くもMazuriリクガメフードに餌付くなど暮らしぶりは順風満帆で、 大きさに不安を感じること無くスムーズに成長させられることでしょう。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 手の中でコロコロ転がってしまいそうな一生の内で一番可愛らしいおチビちゃん! 小ささ故の餌食いや動きについての心配を全てクリアした最高のコンディションでお届けします、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 今やライバルのギリシャやホルスフィールドたちを豪快にぶち抜き、 初めてのリクガメという選択肢において圧倒的な人気を誇るのが言わずと知れたこのヘルマン。 大きくなっても愛らしい風貌はそのままに、 たとえマックスサイズを迎えたとしてもそう持て余すことのない適度なボリュームや、 そもそも日本の環境に馴染み易くやりようによっては通年屋外飼育までできてしまう、 飼い主を選ばないとはまさにこのことと言った具合に支持率をグイグイ伸ばしてきました。 あえて説明を加えなくとも良いカメだという事実は長年知られているものの、 昔は欧州から輸入される繁殖個体も今のように豊富な供給が得られなかったため、 野生個体も交じって同時に流通する前述の二種に比べるとやや高価であり、 ビギナー向けと言われつつもなかなか手が出辛い微妙なポジションに位置していました。 しかし一方でヨーロッパというある程度限定された分布域が現地の気候を把握し易くしてくれたり、 CBが主体であることにより状態にバラつきが出難かったりと、 多少値が張ったとしてもそれを選ぶメリットを大いに感じられたのでしょう。 最近では国内外問わずブリーディングが順調に進みさほど無理のない価格帯が実現した上に、 飼育方法の改善や技術、知識レベルの向上、 それにサプリメントや飼育器材なども充実し状況は良くなるばかりで、 今日の我が国におけるリクガメブームを強力に後押ししているのです。 今回やって来たのは最も飼い始めたくなってしまう恐れの高い危険なサイズであり、 かつ生まれたてから幾分育った安心サイズのベビーが三匹。 店頭に到着して間もなくバスキングスポットの周りをうろうろし始めたかと思えば、 あまりにも明朗快活だったためおもむろにMazuriリクガメフードを差し出した所、 我先にと一斉に食べ始めた良い意味で期待を裏切る健康優良児ばかり。 こういった元気有り余るベビーばかりだと私たちショップの人間としても取り扱いが本当に楽で、 初めて挑戦される方にお渡しすることになっても心配事は殆どありませんし、 少しでも長めに在庫していればその間にもみるみる内に成長していきますので、 ついついその様子を見守りたくなってしまうほど。 腹側の黒い面積が広めで背中の模様も濃くはっきりとしているため、 成長に連れて色彩にメリハリと深みが出てくると思います。 春の陽気が感じられるようになってきたこの時季はリクガメを飼い始めるのに最高のタイミング、 体色はレモン系の個体を一匹と、 クリーム系の個体を二匹セレクトしましたのでお好みでどうぞ。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (国内CBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 生後一か月を過ぎ体全体の重さや張りがしっかりと出て来た元気いっぱいの国内CBベビー! 初めてのリクガメには不安が付き物ですがそんなビギナーさんを全力でサポートする健康優良児、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 初心者にもお勧めできる育て易いリクガメ人気ランキング、 もしそんなものがあるとすれば今やぶっちぎりのナンバーワンを獲得するであろう、 多方面から高い評価を集めているのがこのヘルマンリクガメ。 かつてはヨツユビやロシアと呼ばれたホルスフィールドリクガメや、 これまた知名度の高いギリシャリクガメなどが上位を占めていたはずでしたが、 最近ではそれらの取引量が減少すると共に金額もじわじわ高騰していたり、 反対にヘルマンが昔に比べれば随分とリーズナブルになったこともあって、 上下関係が逆転する結果になったのではと考えています。 また飼育難易度の点から見ても、 ほぼ完全に飼育下で誕生した個体のみが流通する本種は丈夫であることが多く、 そういった現場の声が特にエンドユーザーからより多く発信されるようになったことも、 その絶大な人気に拍車を掛けているのでしょう。 かつては販売者側より大きくなり過ぎないとか、耐寒性に優れているとか、 明るい性格で活発に動き回るなどと言った、 いわゆるセールスポイントをいくつも掲げて販売していたのですが、 この頃は情報も豊富で既に皆さんご存知であるケースも多く、 却ってヘルマンは全て頑丈で誰でも簡単に飼育できると思い込まれている節もあり、 我々としてはその期待にお応えできるよう、 手にされた一匹のカメが評判通り本当に扱い易いと感じて頂けるよう、 より一層気を遣ってケアをするよう努めています。 今回やって来たのは生後二週間の状態で入荷した極小のベビーを、 店頭にておよそ一か月トリートメントした安心サイズの国産ヘルマン。 輸入ものにはあまり見かけないサイズも相当可愛らしかったのですが、 つい心配で毎日たらふく食べさせていたら気が付けば既にご覧の通り。 フレッシュな成長線が力強く伸びると共に、 甲羅や四肢の黄色味が体の奥からじわっと発色し始め、 かなり綺麗な仕上がりを見せてくれるのではと今から期待しています。 やはりEUCBに比べ明らかに初期状態が好ましく、 あまりにも走り回るため手の平の写真が大人しい感じに見えますが、 内から溢れ出るエナジーを是非現物でご確認下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (国内CBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| いくらビギナー向けであるとは言えその快挙にはなかなか巡り合えるものではない感動の国産ベビー! ある種のリクガメらしいストレートな容姿を武器にメキメキと支持率を高めている定番の人気種、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 いつの頃からか初めてリクガメを育ててみたいと思ったらこれで決まり、 そんな風に世間が口を揃えて評するようになったチチュウカイリクガメの一種、ヘルマン。 もちろん人間によって身勝手に無理やり与えられたイメージだなんてことはなくて、 実際に飼育してみると確かに日本の気候風土に合っていて大きな失敗が生じ難く、 最大甲長も手頃なボリュームで収まりますので無理がありませんから、 多くの場合思っていたのと違ったというがっかりな結果にはならないでしょう。 話は変わって全てのリクガメファンがヘルマンを一番愛しているのか、 本音を言えば他に好きな種類がいたりする場合にはあえてヘルマンを選ばなくとも、 初めから一番欲しかった種類を選ぶべきではないかと思うのですが、 言い換えると一番飼ってみたかった種類がたまたまヘルマンだったのであれば、 それは素直にラッキーだと考え喜んでヘルマンを選択すれば宜しいのではないかと思います。 最近ではテレビドラマの登場人物としてもフィーチャーされている本種ですが、 飼い易いと一言に言っても限度がありますのできちんとリクガメとして迎え入れる必要があり、 しかしながらリクガメを飼育するための作法を身に付けた状態であれば、 他の種類よりもリスクを抑えて互いに健康に付き合っていけるのは事実ですから、 これを機会に改めてヘルマンの持つ底力のようなものが世の中に浸透することを願うばかりです。 今回やって来たのはお客様により自家繁殖された兄弟で、 これほど騒がれている中で意外にも日本生まれのヘルマンというものは決して多くはなく、 流通の大半が現地からの養殖個体で賄われているために、 いつも以上に温もりのようなものを感じるのは私だけではないと思います。 甲長だけを見ればまだまだひよっ子と言われても仕方ないボリュームながら、 流石にクリーンな体なだけあって入荷直後からMazuriリクガメフードをもりもり食べ、 少し目を放した隙にグッと成長し厚みも出ていました。 片方の個体は本来五枚ある椎甲板が、なんと四枚になっていて面白いです。 見た目に小さ過ぎて心配という方にはもう少し育ったサイズが別で数匹在庫していますので、 気になった方は是非一度店頭まで足を運んでみて下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| キュッと口を結んだ顔付きはベビーサイズ限定のチャームポイント! そっと引き寄せて抱きしめたくなる実に愛らしい風貌です、 ヒガシヘルマンリクガメ・ベビーが入荷しました。 チチュウカイリクガメ属はその名の通りヨーロッパを中心に中東やアフリカなどに分布するグループで、 ギリシャリクガメやロシアリクガメなど昔から馴染み深い種もこの仲間です。 一般的な家庭での終生飼育が現実的なお手頃サイズ、 環境への適応力が高いことなどペットとして楽しむに相応しい数々の魅力を持つ仲間ですが、 ことヘルマンについてはそれらに加えて抜群に可愛らしいことが人気の秘訣。 しかしながら棲息地の多くで保護活動が進んでいるため流通量は少なくかつては比較的高価なカメでしたが、 それでもマニアの間でコツコツと国内繁殖が進められCBが多く出回るようになり、 一頃を思えば随分と身近な存在になりました。 今回やってきたのは小さなお饅頭ぐらいしかない可愛いサイズですが、 2週間以上店頭にて様子を見て動きもキビキビとしてきたので本日ご紹介します。 幼体時からの成長過程を共に過ごしたい、という方にはピッタリの大きさで、 餌は葉野菜とMazuriリクガメフードを交互に与えています。 殆ど気になりませんが項甲板が2つに別れているのでお値打ち価格にて、黄色味の強い綺麗な個体です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (EUCBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 店頭に到着してからおよそ三週間で納得のコンディションに鍛え上げられた小さな精鋭揃い! 甲羅の黄色い輝きが余計に眩しく映るシャキシャキ歩いてバクバク食べる健康体に仕上げました、 ヒガシヘルマンリクガメの入荷です。 誰が何と言おうとリクガメの中で最も飼い易い種類に君臨するのは、 このヘルマンをおいて右に出るものはいないでしょう。 もちろん近縁種にはそこそこの近い実力を持つものもいないことはありませんが、 気候の近いヨーロッパを原産としかつ繁殖された個体がコンスタントに流通することを考えれば、 失敗の少なさにおいては群を抜いていると思います。 四季があり夏と冬の寒暖差もおおよそ近しいイタリアやギリシャ出身の本種は、 寒冷地を除けば屋外で越冬できてしまうほどの順応性を誇り、 予測不能のトラブルは他種に比べて圧倒的に少ないと言えるでしょう。 更に現地では野生個体に対して規制がかかっているために輸出されるのはほぼ全てCBですから、 人間に与えられた飼育環境に順応し易いという訳。 しかしながらそれでも輸入されたての幼体には少なからず疲労感が漂い、 当然ながらきちんと育ち上がる個体なのか否かの見極めも難しいため、 バスキングをして餌を食べるという一連の動作に何ら問題は無さそうに見えても、 なかなか体重が増えてこないなどの悩みを抱えてしまうこともしばしば。 我々お店側としてもいくらピカピカだからと言って仕入れの際には気を遣いますし、 やはり出だしだけは十分過保護にしてやらなければという思いから、 今回は入荷してから暫く餌を食べるだけ食べさせまくり、 体の内側からはち切れんばかりのエネルギーが感じられるようになるまで面倒を見てみました。 最初の数日間は新鮮なタンポポをケージ内に余るほど放り込み、 徐々にMazuriリクガメフードへ移行していくという作戦を取りましたが見事大成功、 何なら初日からフードを食べる個体もいたぐらいでしたが現在では殆どの餌を選り好みなく食し、 甲羅全体を指で押しても明らかに硬さがアップしています。 消化と排泄のリズムも至って良好で、時にこの頭と同じぐらいの大きさの糞をひねり出すのですから驚き。 しかもこの三匹はいつも見慣れたタイプに比べてイエローの発色が強く、 コントラストが明瞭でぼんやりとしたイメージが全く無いため、 かなり派手な外観に仕上がることが期待されます。 初めての方には一番元気な個体から選別してご紹介致しますので、 少しでも安心が欲しいという方にはぴったりだと思います。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (EUCBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| ほんわかと柔らかな配色にお菓子のような可愛らしさが味わえる肌色の変わったタイプ! 輸出されるファームの違いなのかいつもと雰囲気の違うあまり見かけないカラーリングの、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 いつの間にやらビギナーズトータスの最有力候補として君臨するまでになった、 誰に聞いても飼育のし易さに太鼓判が押されるみんな大好きヘルマンリクガメ。 かつてはロシアの愛称で親しまれるホルスフィールドリクガメや、 これまた昔からの定番種として有名なギリシャリクガメなどが、 初心者が選ぶべき種類として推薦されていたのですが、 この十年間でリクガメ全体を取り巻く流通事情も刻一刻と変化し、 初期状態の安定した幼体がコンスタントかつリーズナブルに入手できる、 そのお株をヘルマンが見事に奪い取ったと言うことなのでしょう。 ヨーロッパ出身なだけあって日本の自然環境にすんなり馴染み易く、 もちろん屋外で飼育する機会が無くとも根本的に調子を崩し難いところが最大の利点で、 しかも出回る個体の殆どが半ば養殖に近い規模で殖やされているCBばかりですから、 着状態のフレッシュさが前述の二種とはまるで比べ物になりません。 つまり手にする瞬間から元気有り余る状態な上に、 活動的な性格で最終サイズも手頃となれば人気の出ないはずが無く、 飼育者層の裾野を広げてくれた功労者と言っても過言ではありません。 今回やって来たのはお馴染みと言いつつも実は半年ほど品薄感の続いていた、 店頭には必ず並べておきたい久々のベビーヘルマンたち。 いつも決まって仕入れるのは濃厚な黄色地にはっきりと黒斑が並んだイメージですが、 これらはどれも水彩画のようなぼんやりと淡いデザインが目を惹き、 間違っても双方のクオリティの高低を比較するだとかそんな話がしたい訳では無くて、 単純に色々な系統が見られた方が面白かろうとセレクトした四匹です。 輸入業者によると得意先のファームからなかなかオファーが無かったため、 他を当たってようやく見つけ出した苦労話も込みの荷物だったようですが、 そのお陰で珍しい色彩のヘルマンに出会えたのはむしろラッキーだったと思います。 早速Mazuriリクガメフードを爆食しており準備万端、 初めての方も一から飼育方法を直々に叩き込みますのでご安心下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 初めてのリクガメをお探しの方、お待たせしました。 ビギナー向けリクガメ人気ナンバーワン、ヘルマンリクガメ・ベビーが入荷しました。 コロコロと真ん丸な体つきに愛くるしい顔付きが絶大な人気を誇るリクガメ代表選手。 明るい性格で餌の時間以外でも活発に動き回ることもポイントで、見ていて飽きない所も評価を上げています。 他種と比べても圧倒的に丈夫なのはやはり日本と気候が似ているヨーロッパ原産だからでしょうか。 照明・保温器具で少し環境を整えてあげる程度で比較的無理なく飼う事ができます。 大きさも手頃で大きなメスでも20cm程度、オスではおよそ15cm程が平均サイズで日本の家庭事情でも持て余しにくいのでは。 親サイズになると耐寒性も備わりますので寒冷地以外では屋外越冬も可能になり、 非常に飼育環境に順応しやすいと思います。手放しでも安心な10cm頃まで育てばお庭などの外飼いで 自然下の生き生きとしたカメの姿を観察するのも良いでしょう。 当店では初心者の方にヘルマンをお勧めしており、 その他のビギナー向けと呼ばれるリクガメも一通り見て頂きますが、 最終的にヘルマンを選んでリクガメ飼育をスタートされる方が多いのも納得です。 細かく刻んだ葉野菜を一生懸命食べています。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (EUCBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 地色のイエローもぼやけた雰囲気でごまかさないメリハリの利いたボディカラーのセレクトベビー! わんぱく小僧とでも呼びたくなる飛び跳ねるような躍動感が安心のグッドコンディション、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 ありとあらゆる方向から見回してもキングオブ優等生の称号に相応しいリクガメと言えば、 ずばりヘルマンとの評判にもはや異論は無いでしょう。 今から遡ること十年以上も昔の話、 まだペットとしてリクガメを飼育することに些か引け目の感じられた時代には、 本種を含むヨーロッパ原産の種類はまだ豊富な数が出回っておらず、 今日のようにいつでも当たり前に手に入ることなど到底考えられませんでした。 確かに人気はありましたが元々野生の棲息数も格別に多い訳ではありませんし、 何しろ先進国のことですからむやみやたらと輸出されるはずも無く、 細々と殖やされたものが時折輸入されるマニアックな雰囲気すら漂っていたのです。 いかにもリクガメらしいスタンダードで分かり易い容姿や、 温帯性ならではの温度耐性とそれに伴うタフな体質も初心者向けと言え、 最大でも片手で持ち上げられる手頃なサイズに収まる点も忘れてはならない強みのひとつ。 お仲間のギリシャやロシアがバリバリの野生個体も並行して流通していた頃から、 ことヘルマンに関してはほぼ全てが繁殖個体により賄われており、 そう言った環境に配慮した部分も含めて高い評価を受けていたように記憶しています。 最近ではどんな飼育書を紐解いても必ずトップクラスの支持率を誇る定番種に君臨し、 老若男女問わず誰からも愛される可愛らしい風貌と、 繁殖が進み安価に入手できるようになった流通事情も手伝ってその人気の高まりは留まる所を知りません。 今回やって来たのは本当に有難い時代が到来したとつくづく感心させられる、 お馴染みの産地直送安心サイズベビーからのセレクト個体。 ベースとなる黄色は澄んだように美しく、 またその上に配置される黒斑とのコントラストにも拘ってピックアップしてみた所、 ヒガシにしてはかなり彩りの良いエクセレントな個体ばかりが勢揃いしました。 ここに秘められた高いポテンシャルは成長に連れて如実に表れることでしょう、 寝たり起きたり食べたり走り回ったり、 四六時中見ていても飽きない表情豊かな三匹です。 初めての方には餌や器材のフルセットから実際の飼育方法まで一からお教えします、この機会に是非。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (国内CBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 前回入荷したのはあまり耳馴染みのなかったスロベニア産でしたが、 今回やって来たのは、そう聞くだけで思わずほっこりとしてしまう日本生まれのベビーヘルマンたち。 世界に現存するリクガメの仲間では、最もペットとして普及している種類のひとつで、 今日では野生個体の流通は皆無に等しく、私たちが目にするのは何かしら人の手が加わった繁殖個体です。 原産であるEU諸国で養殖されたものが正味九割以上を占めている中で、僅かに見かけられる国産のヘルマン。 もちろん外見や暮らしぶりに大きな違いはありませんが、それでも何となく国産の二文字は心が弾む要素であり、 いずれにしても野生とは切り離されつつある彼らですが、 こうした出物にはより一層大切に扱いたいと思わせる温かみが感じられます。 昨年の冬を殆ど野外に近い環境で越している強健な兄弟たち、元気もりもりでお待ちしています。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (スロベニア産) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| より可愛らしい方かより安心な方か、大人気の定番種をスタート時期が選べるツーサイズ展開にてご用意! いつにも増して黄色い部分の面積が広い一目見て明るく美しく映える綺麗な個体ばかりをセレクト、 スロベニア産のヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 生き物の世界にはどのようなジャンルにおいても大抵初心者向けという枠が用意されていて、 それは意味を履き違えてしまうと大変なことになってしまうのですが、 無論いい加減に育てて良いだなんてそんな乱暴な意味合いではなく、 その種類自体に生まれながらにして備わる高い耐久力があったり、 或いは幅広い環境に対して適応できる力を持っていたりするパターンが多く、 そのため多くの人々がペットとして付き合う上で扱い易さが感じられるというものです。 このヘルマンというのは恐らく世界中に散らばる全てのリクガメの中で、 最も人間社会に順応できるスペックを有する非常に有力な選択肢のひとつであり、 実際に今日では養殖が進められいつでも私たちの手元に呼び込めるよう準備が進められています。 しかし彼らが偉いのは何も頑強な体を持っていたばかりではなく、 それが人間から見て飼ってみたい、育ててみたいと強く思わせる魅力に溢れているからでしょう。 具体的にどの部分がどのようにそう作用しているのかは分かりませんが、 如何にもリクガメらしい容姿や仕草がファンの期待を裏切ることなく、 みんながイメージしていたリクガメ像を地で行くぶれないスタンスが好評に繋がっているのかもしれません。 つまり我々が我々の都合や事情だけで一方的に決め付けることはできず、 ビギナーからマニアまで幅広く愛されるための素質はこの世に生を受けた最初から決まっていて、 全てが奇跡的に結び付いたその時に初めてこのようなスターが世に送り出されるのです。 今回やって来たのは過去に何度か取り扱っているスロベニア産のベビーより、 入荷して暫く店内で育成し全ての個体がMazuriリクガメフードにしっかりと餌付いた有望なメンバーたち。 かつてはマケドニア産など異なる地名が冠せられたタイプも流通していましたが、 あまりロカリティを気にし過ぎるのは窮屈になるため好ましくないとは思いつつも、 何も知らされないよりは彼らの故郷に思いを馳せるきっかけとなれば幸いです。 ニシではバンド状に太くなり易い背甲の黒い模様については、 墨汁を垂らしたような斑状になっていて如何にもヒガシらしいと感じさせるデザインになっています。 たとえリクガメの飼育が全く初めての方でも、 当店では何もかもゼロの段階から最高のステージにまで叩き上げるようご指導しますので、 まずは店頭にてお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 入荷後一か月足らずにして迅速なる成長線の伸びに夏の恩恵を感じる安心サイズのベビー! 輸入状態の良さを更なる高みへと引き上げたビギナーさんにも強くお勧めしたい自慢の我が子たち、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 ヤモリならヒョウモン、トカゲならフトアゴ、ヘビならコーンやボールとなるでしょうか。 そしてミズガメならミシシッピニオイガメと、 世間では俗に初心者向けと呼ばれる種類がおおむね定められており、 皆が揃いに揃ってそれを最初の相棒として迎える必要性は全く以って感じられないものの、 やはりそのような役柄を任されるからには何かしらの意味があると考えるのが自然です。 ことヘルマンについて特筆すべきは温度耐性の幅広さであり、原産がヨーロッパ、 具体的にはギリシャやイタリアなど地中海沿岸部から東欧エリアにかけてですが、 それ故に日本の四季に近い元来の暮らしがペットとして順応し易く、 誰が育ててもそれなりに無難なところへ落ち着くのではないかと言われています。 実際に手元で扱ってみるとその差は一目瞭然、 飼育を始めた初期の間は流石に地中へ潜りお休みタイムとなる場合があるものの、 そこから一週間経つか経たないかの内に早速新世界へと飛び込むかの如く冒険がスタートし、 遅かれ早かれ全てのリクガメの中で最も躍動感のある種類へと生まれ変わります。 そんな元気いっぱいでやんちゃな生き様こそがヘルマン最大の持ち味であり、 誰でも簡単に育てられるなどと安易な評価を下すつもりはありませんが、 少なくとも育てていて楽しいと感じられることには違いないと思います。 今回やって来たのは季節の風物詩のように感じられる定番のベビー軍団で、 基亜種ニシヘルマンとは少々異なるヒガシらしいレモンイエローが四肢を中心に際立った、 健康で美麗なものばかりを揃えた店内プチ飼い込み個体たち。 輸入元でわんさか群がる兄弟分から活きの良いものをチョイスするのは言うまでもありませんが、 最低条件として当店で平常扱っているMazuriリクガメフードにはしっかりと餌付けると共に、 葉野菜などもほぼ選り好みしないような状態に仕立ててありますから、 皆さんの飼育スタイルに合わせて育て始められるはずです。 体全体からみずみずしさの発せられたどれを選んでも間違いの無い元気印、 大きさや色合い、それに個々の性格も含めてお好みの一匹を探しに来て下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (スロベニア産) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| シーズンオフの品薄感が漂う中でパリッと育った安心サイズが珍しいルートよりまとまって来日! いわゆるベビーのあまりにもか弱い雰囲気が心配な方にお勧めなふっくらとした程良い大きさの、 スロベニア産のヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 最近ではその名前を聞かない日はないと言っても良いほど、 今では立派なリクガメ界の絶対的レギュラーとして定着した業界のマストアイテム、ヘルマンリクガメ。 図鑑を見てもインターネットを見ても、 初心者向けのリクガメとして何処も彼処も口を揃えて本種を紹介しているほど、 自他共に認める実力者としてきちんと功績を挙げ続けているのですが、 何も野生のカメを片っ端からひっ捕らえむやみやたらに流通させているのではなく、 ペット的な需要を見込んで人の手によってきちんと養殖が進められ、 非常にクリーンな実例として成功モデルにもなっていると思います。 ヨーロッパの各地から自慢の我が子を送り出すように出荷されるヘルマンたちは、 きっとファームそれぞれの違いなのでしょう、 そのロットによって色彩や表情にいくつもバリエーションがあるだけではなく、 元いた牧場主の思いが詰まっているような気がして温かい気持ちにもなります。 正直我々としては店頭から消えてしまうことを容認することはできず、 常時ヘルマンの幼体が待機している状態を作ろうと働きかけているのですが、 やはり相手は生き物故に絶対約束できるものではなく、 しかしながらこうして新たな集団を迎え入れる度に、 微妙な個体差を感じながらまたヘルマンの奥深さに魅了されていくのです。 今回やって来たのはスロベニア産として輸入された日頃あまり目にしないタイプで、 何よりも初期サイズが新たな飼い主さんに対して大変親切なところが嬉しく、 店頭へ到着した次の日からいきなりMazuriリクガメフードを奪い合うようにして食べてくれた時には、 彼らを育んでくれた現地の恵まれた環境へ感謝しない訳には参りませんでした。 ここからは余談ですがスロベニアとは亜種ヒガシヘルマンとしての分布域最西部に当たり、 更に西側のイタリアへ赴けばそこは基亜種ニシヘルマンの担当エリアなのであって、 反対に最も東にはブルガリアという噂の大型個体群が潜む棲息地があるのですが、 あくまでも憶測ではあるもののヒガシとしては最も小型な部類なのではないかとか、 そう言われてみると甲羅の色合いも何だかいつもと違うように見えてきて、 こんなことを考えているだけで楽しい気分になります。 ちょうど春の陽気も感じられるようになってきた今日この頃、 季節を先取りしてリクガメの飼育を始めてみては如何でしょうか。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ベビー) Testudo h. boettgeri |



|
|
||||||||
| ヒガシへルマンのEUCB個体です。地中海リクガメ特有のクリッとした目がとても可愛く、 動きも活発で、餌くれ~!って走って来て癒されます。 繁殖も比較的容易な種類ですので、将来期待大です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (国内CBベビー) Testudo h. boettgeri |



|
|
||||||||
| ヒガシへルマンの国内CB個体です。地中海リクガメ特有のクリッとした目がとても可愛く、 動きも活発で、餌くれ~!って走って来て癒されます。 繁殖も比較的容易な種類ですので、将来期待大です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (国内CBベビー) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 実に愛らしい、抱きしめたくなる様な風貌です。嬉しい国内CBのヘルマンが入荷しました。 写真1枚目の個体は健康児ですが、2,3枚目の個体は、先天的に左目の眼球がありません (獣医がレントゲンで確認)。ですが生命力があり、餌食いや活発さは 1枚目の個体となんら変わりはありません。お客様委託の為お値打ちです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (安心サイズ) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 丸っこい顔付きが特徴の地中海リクガメの仲間の中でも特に可愛く人気のリクガメです。ヘルマンリクガメ・ベビーの入荷です。 真ん丸な顔と甲羅にクリクリの目がとても可愛らしく、 近頃は繁殖個体も多く比較的安価で手に入る事や大きくなり過ぎない事から、着々と初心者向けリクガメの座を築きつつあり、 これからリクガメを飼おうと思っている方には特にオススメの1種です。原産はヨーロッパなので気候的にも近い日本では 温度湿度設定の苦労もあまりないのが嬉しい所。必要な器具があればリクガメの中でもかなり飼いやすい仲間なので、 お子さんでも上手に育てられると思います。 撮影中もトコトコとどこかへ歩いてしまう活発な個体達で、 餌の葉野菜やMazuriリクガメフードもムシャムシャと勢いよく食べています。 生まれたてではなく少し育った安心サイズなのでこれからの成長も早いでしょう。 最大でも20cm前後なので持て余す事なく終生飼育できると思います。初めての方にはアドバイスしますのでお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (S) Testudo h. boettgeri |




|
|
||||||||
| 体色鮮やかなヘルマンが入荷しました。ベビーよりちょっと育ったサイズで安心です。 地中海リクガメは大きくなっても今のままの風貌なので、いつまでも可愛らしい姿が楽しめます。 葉野菜をケージに投入すると、トコトコと歩いてきて美味しそうに食べています。 最近は品質の高い個体が多く流通する様になって嬉しいですね。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (S) Testudo h. boettgeri |




|
|
||||||||
| 実に愛らしい、抱きしめたくなる様な風貌です。昨年の繁殖個体が綺麗に成長しました、ヘルマンリクガメの入荷です。 可愛らしい・飼育しやすい・お手頃価格と三拍子揃った素晴らしいリクガメで、 ここ数年で繁殖個体が多く流通し次第に人気も定着してきました。また国内繁殖の例も多く聞かれる様になり、 野生個体が減少している事も考えると非常に理想的です。写真撮影時も地面に置いた瞬間からトコトコと どこかへ歩き去ってしまう程に活発で、餌をケージに入れると今まで潜っていた床材から這い出して直ぐに食べ始めます。 Mazuriリクガメフードにも餌付いていますので、初心者の方にもお勧めのリクガメです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (S) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| いくら初心者向けだと猛プッシュされても極小のベビーでは恐ろしいという方にはうってつけ! 甲羅を指で力強く握ってもビクともしないほどガチガチに鍛え上げられた超安心スモールサイズ、 ヒガシヘルマンリクガメが入荷しました。 本種が初めてのリクガメに最適であるという評判が上がり始めたのは何もここ数年の出来事ではなく、 遡ること十数年前より既にそのような記述や実績があったのではないかと思います。 その当時はロシアことホルスフィールドやギリシャなどが今よりも豊富に流通し、 あまりはっきりと口にしたくはありませんがそれらは決して高価な部類ではなく、 その傍らでヘルマンは明らかにワンランク上の扱いを受けていましたから、 個人的にはリクガメの仲間に対して初めて注目し始めた頃に、 安価とは言い難いものがビギナー向けと位置付けられていることに些かの違和感を覚えた記憶があります。 そこに込められた本当の意味を理解したのはこの仕事を始めてからでしたが、 結局は前述の二種は主に野生個体しか手に入れることができなかったのに対し、 こちらヘルマンは出回りだした当初より飼育下で繁殖されたものが多く売買され、 それは次第に養殖という一大事業へと変化を遂げていくのですが、 現在のようにペットとして安定供給されるための土台が整った背景には、 人々が人の手によって殖やされたリクガメの育て易さを心から理解し、 それによって生まれた豊かさのようなものが世界中に広まったからではないでしょうか。 最近では随分とリーズナブルな価格帯に落ち着いてくれたお陰で、 ようやく真のビギナーズトータスへと出来上がってきたのです。 今回やって来たのはカッチカチの甲羅にずしりと重みを感じられる安心サイズの二匹。 昔に比べ輸入される初期サイズが段々と小さくなっているような気がするヘルマンですが、 本当に小さいものはそれこそ風が吹いたら飛んでいきそうな雰囲気なので、 それは冗談としてもひとつ上のステージに上がった選択肢があっても良いと思います。 店内ではMazuriリクガメフードを爆食し成長を再開していて、 フレッシュな成長線が写真からもご覧頂けるように、 何をどうしても大丈夫な盤石の態勢が整った最高のコンディションにてお渡しします。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (M) Testudo h. boettgeri |




|
|
||||||||
| よく動きよく食べ、さほど大きくならない事から、リクガメの中でも人気の高いヘルマンリクガメ です。その活発さは折り紙つきで、当店にいるリクガメの中で一番歩き回っています。 同属のギリシャリクガメに似ていますが、後肢のスパイク状の突起が無いという点で 見分ける事ができます。とにかく状態が良いのでお勧め!! | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (Sサイズ) Testudo h. boettgeri |




|
|
||||||||
| ハッチサイズベビーからのお客様飼い込み個体のヒガシヘルマンが入荷しました。 やはり地中海リクガメの仲間は総じて顔が可愛らしく、特にベビー~Sサイズではそれが際立っており人気の秘訣となっています。 背甲の黄色と黒のコントラストも素晴らしく、ペットとして飼うリクガメとしてはまさにはまり役な本種です。 ひっくり返ると何故か万歳のポーズをする所もチャーミングポイントの一つでしょう。 性別はまだ確定しませんがメスっぽいです。 協調性が良いので他のヘルマンと一緒にしていますが、ケージに葉野菜やMazuriリクガメフードを入れると我先にと競う様に食べ出します。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (M) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 手のひらにちょうど乗るぐらいの可愛らしい安心サイズ、ヘルマンリクガメが入荷しました。 その飼育のしやすさからポピュラーなグループとなっている地中海リクガメの仲間でも、 特に人気の高いのはヘルマンではないでしょうか。 主な棲息地であるヨーロッパは緯度的にも日本と近く気候はかなり似通っており、 あちらの方がやや過ごしやすいとは言うものの四季がある事など温度変化としては殆ど同じで、 照明保温器具に頼り過ぎることなく飼育に望めることなどからビギナー向けのリクガメとしても普及しています。 そしてなによりコロコロと丸っこい顔つき、体つきや、 地味過ぎず派手過ぎないバランスの取れた色合いも好まれるポイントでしょう。 性格も基本的には穏やかですが活発な面もあり、飼育下でもケージ内を所狭しとトコトコ歩き回る姿がよく観察できます。 明るい性格と言ったら変かもしれませんが環境に馴染みやすい一面はあるようです。 餌は小松菜などの葉野菜から当店ではMazuriリクガメフードも与えており特に選り好みする様子はありません。 また今回繁殖個体では数の少ないメスっぽい個体で、 このままメスになればお買い得なお値打ち価格にしました。 初めての方も、既にオスをお持ちの方も頑張って大きく立派なメスヘルマンに育て上げて下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♂) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 二ケタ甲長の性別確定安心サイズ! 育て方のお手本にピッタリな文句なしの美個体です、 ヒガシヘルマンリクガメ・オスが入荷しました。 今日本で巻き起こっているチチュウカイリクガメブームを支えているのはこのカメに他ありません。 もちろんギリシャやホルスのことも忘れてはいけませんが、 ヘルマンからは実力でもぎ取った確固たる地位というのを感じることができます。 今でこそあまり感じることは無くなりましたが、 実に数年前まではビギナー向けと言われながらセミ高級種のような扱いでもあり、 当然人気も高かったため初心者がおいそれと手を出せるようなリクガメでは無かったと思います。 それが現在愛好家たちの手により国内CB化が着々と進み、 ここ最近では本当の意味でビギナー種と呼べるようになってきたかもしれません。 今回やってきたのはベビーサイズからこつこつと育て上げられたオスで、 この大きさにして大人顔負けの大きな尻尾には何か安堵感のようなものを覚えます。 そして先にも述べましたが甲羅のぼこつきは最低限に抑えられ、 全体的にヘルマンらしいこんもりとした形状を成している辺りは、 大切にされてきたことの裏付けとなるでしょう。 生まれたてのベビーと比べれば可愛らしさが少々もの足りないかもしれませんが、 小さなサイズから育てるのは不安、という方にはこれほどうってつけの個体もいません。 メスほど大きくならないため飼育スペースが心配という方にもオススメです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♂) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| この飼いやすさは初めてリクガメに挑戦される方には心強いです。 近年急激に人気上昇中の地中海リクガメ、ヒガシヘルマンリクガメ・オスの入荷です。 よく見かけるコロコロとしたベビーサイズも可愛らしいですが、今回はこの寒い季節にも安心な性別確定サイズです。 普段もそうですが写真を撮る際にも常にトコトコと何かを求めて歩き回り、 とても活発で見ていても飽きる事がありません。 顔つきはこの属のカメ特有の丸っこい形で愛くるしいです。 餌は葉野菜からフルーツ、人工飼料と選り好みせずに食べてくれるので飼育者も毎日のメニューに(良い意味で)悩まされてしまいます。 国内でも年中屋外で繁殖に成功するケースが増えてきているのでメスをお持ちの方は繁殖用(大きな個体は既に盛っています)に、 リクガメ初心者の方は体力の十分備わったこのサイズから飼育を始めてみて下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♂) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| ニシよりも大きくなるとされるヒガシですがオスはこれぐらいでほぼMAXです。 お客様委託のヒガシヘルマン・オスの入荷です。 可愛らしくかつ大きくなり過ぎず、餌もよく食べよく動き回り、おまけに耐寒性まで備えた、 まさにペットタートルのリクガメと言えばヘルマンでしょう。 昔はちょっと高かったのですが、最近では国内繁殖の勢いも増し価格も落ち着いてきました。 今回はお客様飼い込みにつきとてもパワフルな健康個体で、 葉野菜やMazuriリクガメフードを与えると我先にとガツガツ食べています。 性成熟もしているのかしきりに他のカメに乗りハッスルしています。 繁殖用には勿論、初めてリクガメを飼われる方にも安心な一匹です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (アダルト・♂) Testudo h. boettgeri |




|
|
||||||||
|
委託者様のご意向で価格を下げての再出品です。お客様長期飼い込み個体、ヒガシへルマントリオで入荷・オスです。4月半ばから
10月上旬まで屋外飼育で育てていたそうです。何故か地中海リクガメの仲間は、お日様を充分浴びさせても甲羅が凸になりがちですけど、
すこぶる元気が良くケージ内を走り回っています。現在はメスを分けて管理していますが、写真を撮るためにあわせたら、
いきなりこの個体も、交尾行動をし始めていました。
相性も良くメスも逃げずにじっとしています。餌は、葉野菜を中心に、Mazuriリクガメフードを食べさせています。地中海リクガ
メ属も、あまり見かけなくなってきましたので、是非この状態の良いオスで仔ガメのハッチにチャレンジして下さい。
オスは(1頭どちらか)ばら売り有り、メスはペア又はトリオでお願いします。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ブルガリアンジャイアント・♂) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| この何の変哲もない外観を再現するのが如何に難しいかを屋外飼育の素晴らしさと共に体感したい一級品! これはただのヘルマンに非ず、 全てのヘルマンの中で最も巨大な体格を手にすることで知られる名門ブルガリアンジャイアント、 ヒガシヘルマンリクガメ・オスが入荷しました。 この数年間における彼の働きぶりといえばもはや嗜好品ではなく生活必需品、 リクガメを愛しそれを育てたいと願う人々にとってなくてはならない存在となってしまった、 業界としてもこの逸材をみすみす手放すことなど到底考えられないみんな大好きヘルマンリクガメ。 初心者はヘルマンから、まるで何かの標語のように繰り返し叫ばれる常套句として成立したその言葉通り、 実際にリクガメの飼育をスタートする上では必ずお供にしたい重要なキャラクターであり、 備わった能力もまたそれに見合った活躍が期待できるスペックであることがただ素晴らしい、 現代のペットトータスとしての基盤を作った最大の功労者のひとりです。 いくらビギナー向けであると太鼓判を押されたからとはいえ、 それが万人に受け入れられるものでなければただの無意味な前評判となり、 真の人気には繋がらず支持率もそこまで上がらないことも考えられるのですが、 ヘルマンが凄いのは私たち売り手側によるいわゆるゴリ押しの状態ではなく、 もはやなるべくしてそうなったと言っても過言ではない、 世界中のファンから愛されるべく生まれてきたような天性のものが感じられるからなのです。 つまり有識者全員がだんまりを決め込んでいたとしても自然と人気者になっていたでしょうし、 結果としてリクガメ界全体を盛り上げることになったところも高く評価されています。 今回やって来たのはそんなファーストトータスとして選ばれがちなお馴染みのヘルマンより、 マックスサイズが通常の枠を超えて規格外のボリュームに育つことで知られる、 俗称ブルガリアンジャイアントとして認知された特殊な個体群の飼い込み個体。 ブルガリアといえばヨーグルトかヘルマンかとでもいった具合に名の知れたマニア垂涎の血統で、 小型であることが売りのひとつであるヘルマンにおいては邪道とも言うべき、 巨人の名を冠する男気に溢れた大変格好良いタイプなのですが、 如何せん流通はまばらで常時コンスタントに巡り合えるものではありません。 しかもこの個体はベビーの頃から毎年野外で越冬しているハードワーカーであり、 優れた耐寒性についての実働確認が散々行われているのは言うまでもなく、 成長線の刻みが見事なまでに均一である様などは本当にお見事。 平常このサイズのオスは既にリアフェンダーが伸びてくるものですが、 微妙に幼さを感じさせるところもまた巨人が巨人たる所以なのかもしれません。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (XL・♂) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 所詮小型種と侮ったこちらが返り討ちに遭いそうな豪傑ぶりが凄まじい迫力のキングサイズ! 雌雄問わず目の前の相手に眼を血走らせてのしかかる文句無しの即戦力種親候補、 ヒガシヘルマンリクガメ・オスが入荷しました。 世の中で一般にペットとして認識されている動物、 例えばイヌやネコは愛玩動物の最も有名な例として挙げられますし、 他にもハムスターや小鳥、 金魚など家族とも観賞用ともなり得るものまで含めればジャンルは多岐に渡りますが、 気が付くとそのどれもが幼体の姿で販売されていることが多く、 言い換えれば成熟の時を迎えた状態のそれを目にする機会にはあまり恵まれていないのかもしれません。 やはり飼育する以上は育てる楽しみが一番の醍醐味と考える人が多く、 また外見だけの話をしても小さな頃の方が可愛らしく魅力的に感じられることでしょうから、 売り手側もこぞってそういった性質の商品を取り扱う結果に至るようです。 しかしながら全ての生き物が同様に当てはまるとは限らず、 ひとつの個体が種として完成された状態を最も好む層も確実に存在し、 我々の業界はそれをフルアダルト、即戦力などと言って持て囃すこともしばしば。 それは繁殖行動が目前に迫っていることに対する付加価値でもあり、 或いはもっとシンプルに見た目が格好良いと言うことに対する付加価値でもあって、 普段見慣れたあどけない状態の時には想像もしなかった味わいが滲み出した瞬間を、 もっと真正面から受け止めて素直に評価してあげるべきだと私は思います。 今回やって来たのはほぼフルサイズと言って良い、 ただしまだまだこれから先も高みを目指すべきであろうかなり大柄なヘルマンのオス。 甲長16センチに対してその甲幅は最も広い所で14.5センチ、 手に取ってみて初めて分かる重量感は数値以上の衝撃を生み出し、 カメ一匹を実直に育て上げることの難しさと素晴らしさを物語ります。 単純に大きいだけの個体であればそれほど驚きはしなかったと思いますが、 ここまで甲羅のボコ付きを抑えツルンとバランス良く育てるのにも相当な技術を要するため、 全身の至る箇所に隙の見当たらない逸品と言えます。 年季の入った表情は何処か厳格で重々しい雰囲気に満ち、 前肢の太さには一朝一夕で鍛え上げることのできない相当なボリュームが感じられ、 一歩ずつ前へ歩く度に大地をつんざく轟音が辺りへこだましそうです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| まだまだ小さなサイズですが幾分成熟度の高まった皆さんお探しの貴重なメスヘルマン! じっくり育てられているためかこの大きさにして指で押してもビクともしない甲羅の硬さに驚き、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 ユーラシア大陸はおろか世界中の全大陸を見渡しても相当な支持を集めている、 リクガメ界のビギナー向け代表種として名高いのがこのヘルマンリクガメ。 ご要望の声を聞く度に、何がそこまで人々の意識を掻き立てるのかじっと考えてみるのですが、 顔の可愛らしさや下手をすれば手のひらにすっぽりと収まってしまう適度なボリュームなど、 小型種という要素の強みが相当に効いているものと思われます。 リクガメの飼育が決してマニアックなものでは無くなってきている昨今、 やはり卓上ペットの一員として加わるためには間違っても大掛かりなセッティングは好まれず、 飼い主への負荷が極力小さいものが選ばれる傾向にあります。 それはあくまでも家族の一員としての付き合い方の一例ですが、 一方で家の庭先にカメが勝手に暮らしているという状態を維持したい、 互いに干渉し過ぎない関係を望む際に注目されるのが本種の優れた耐寒性。 一年の半分近くは寝ているもしくは寝ぼけているのではないかと思われるほど、 日本の気候によく似たヨーロッパを原産としているため、 やり方を大きく間違えなければ通年屋外飼育が実現してしまうというメリットも、 ヘルマンの株をグンと上げているに違いありません。 各人の思う方向はどうであれ一体のカメに対する情熱は同じ、 流通するほぼ全ての個体がCBであると言うクリーンなイメージも功を奏し、 幅広いニーズに応え続けているのです。 今回は愛好家であれば決して見逃すことのできない素敵なお見合い話、 飼育相談と同じぐらい寄せられる相方探しのご相談を叶えるチャンスがやって来ました。 お馴染みの幼体から育て上げると何故かオスばかりが出来上がってしまう、 同居させていても体当たりの衝突音と盛りの鳴き声が交互にこだまするばかり、 その謎を解くのは温度性決定という爬虫類に多く見られる体の仕組みです。 飼い込み個体として流通するものの殆どはオスに偏ってしまいがちで、 実際当店にはほぼ常時即戦力のオス個体が複数在庫していますが、これがメスの出物となると毎回争奪戦。 同居のし易さやブリーディングに向けての囲い込みなど、 必然的にメスの需要が高まることになっているためまず停滞することの無い超人気物件で、 変な言い方ですがまだ販売する予定に無かったメスでも、 店頭に並べておくと目ざとく見つけられ持って行かれてしまうのですから困りものです。 正直まだ難しい年頃ではありますが、 現状での尻尾の大きさと幅広い甲羅の形状で判断しました。 嬉しいことに嘴の伸び過ぎも一切ない綺麗な顔立ちに育て甲斐溢れる、 早い者勝ちのメスヘルマンです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| いつも必ず問い合わせが殺到するメスを皆さんお待ちかねの単品にて! 出会える可能性の極めて低いアダルトサイズを待つぐらいなら自分で育ててしまいましょう、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 ホシガメやケヅメなど、確固たる地位を確立した不動の人気種が既に存在しているリクガメの世界で、 ここ数年の内にコツコツと支持率を上げ続け、 遂にはそれら代表に負けず劣らずのネームバリューを獲得したのがこのヘルマン。 同じチチュウカイリクガメ属にはロシアことホルスフィールドとギリシャという、 昔馴染みの安価で飼育しやすい強敵が迎え撃つ中で、 本種は基本的に野生個体の流通がないため少々値が張ることもあり、 ビギナー層にとってはなかなか手の出し辛い選択肢であったと思います。 それでも見た目の上品さは勿論のこと、繁殖個体故の扱いやすさから飼育者も次第に増え、 それに伴い国内ブリードの成功例がしばしば聞かれるようになるなど、 その甲斐もあって近頃では価格帯も少しずつマイルドになってきました。 皆に愛されているから、皆に愛して欲しいからという願いが生み出したこの結果により敷居は随分と下がり、 飼育者はいよいよ増加の一途を辿っています。 見かけるのは殆どがベビーサイズというこのカメ、 可愛らしいからと複数匹で飼い始めるとオスがダブってしまい喧嘩を始める、 当店でもしばしば相談のあったよくある話です。 性別が温度で決まってしまうというのが原因ですが、 とにかくチチュウカイはオスの発情行動の激しさが著しく、 ひとつの空間で同居を楽しむならメスばかりで暮らさなければなりませんし、 繁殖を目指す方にとってメスは何匹いても困りません。 そんな分かりやすい理由でヘルマンのメスは引っ張りだこなのですが、 今回は安心サイズでようやく性別の確定した飼い込み個体がやって来ました。 見て下さいこの理想的なフォルムを、 特別マニアという訳ではなくあくまでもペットとして可愛がっていた方からの放出ですが、 丁寧に刻まれた成長線の一本一本にこれまで注がれてきた愛情がしみ込んでいるかのよう。 幅が広くこんもりとしたオーバルな体型も女性的で柔和な雰囲気を醸し、 まだまだ大きくなりそうながっしりとした体格が逞しいです。 良い部分ばかりが目に入るのは特にマイナス要素がないことの証。 本当は店内のオスとペアを組みたい所ですが、まだ未熟なサイズのため特別大サービス! | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| ベビーから育ててオスになったヘルマンを飼育中の方は必見の手の平お手軽サイズな相方候補! 性別が確定するまで現地ファームにて欧州の風を呼吸し青空の下で暮らしていた半分ワイルド、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 一番ペットにしたいリクガメナンバーワンを競わせると沢山の候補が挙がって仕方ありませんが、 一番ペットに向いているリクガメを現実的に考えてみると、 誰しもが文句なしにその名を掲げるであろう今最も注目されているビギナー種、 それはこのヘルマンリクガメではないでしょうか。 図鑑、飼育書、インターネットなど、 ありとあらゆる情報源よりリサーチを重ねても全くブレることなく同じ評価が下される、 内面から容姿に至るまでリクガメ好きにはもれなく喜ばれるかけがえのない存在となっています。 原産はヨーロッパ、 かの有名なイソップ童話『うさぎとかめ』に登場するカメは本種がモデルだと言われており、 私たちは知らず知らずの間にヘルマンに対して親近感を抱いていたのかもしれません。 実際にショップが胸を張って推薦できる理由としては、現地の気候が日本と近しいことの他にも、 その殆どが繁殖個体であるが故に人との生活に馴染み易いことが大きく、 この辺りが大体同じ括りで見られるギリシャやロシアとの大きな違いにもなっています。 今回やって来たのは毎回同じことを申し上げるようで恐れ入りますが、 絶対数が極端に少ないとされているメスと確定した安心サイズ。 流通するのはいわゆるピンポン玉に程近いベビーサイズが大半ですが、 この個体は珍しく性別が判定できるまでブリーディングファームにて育てられ、 流石に本場の植物を餌としていたお陰か成長具合は申し分なく、 甲羅は何処を押してもカチカチでまるで石のようです。 小さな頃から面倒を見ていたカメにお嫁さんを迎え入れてやりたいと願うのはやはり人情なのでしょう、 性決定を温度に依存しているためか幼体の多くがオスに偏り易いことと、 オス同士では複数個体の同居飼育が困難になってしまうこと、 更には繁殖を目指すためにメスを多めに保有したいという事情から必然的にメスの需要が高まり、 同時に出物も少ないため状況が許せば早めに入手しておくことをお勧めします。 また血が濃くなるのを避けるために、全く異なった時期に片割れを見つけるのも得策でしょう。 店頭で暫くストックしていたため早くも新しい成長線が出てきました、 Mazuriリクガメフードにもしっかり餌付き準備万端です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 実は貴重なメス確定個体! 今の内から種親候補としてしっかり育てましょう、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 小型・丈夫・可愛らしいの3要素が詰まった最もペットトータスに相応しいと評判の人気グループ、チチュウカイリクガメ属。 ロシアリクガメ、ギリシャリクガメと昔から馴染み深いリクガメたちは本属に分類されることもあり、 初めてのリクガメとして選出されることも少なくありません。 この中でヘルマンは早々に取引規制が厳しくなったためか流通量が少なく、 しかし愛らしい風貌と強健な体質からメジャー化が熱望されていたカメでした。 時は流れかつての主流であったヨーロッパの繁殖個体の勢力を押し返すように現在では国内CB化が進み、 価格がこなれると同時に現在ではより広く認知されるようになっています。 普通に飼育していては気が付きにくいものですが、1匹で育てていたものをペアにしようと相方を探した所、 何故か見かけるのはオスばかりという経験をされた方も多いと思います。 本種は温度依存性決定のため繁殖個体が主流の現状では圧倒的にオスが多く、 1匹飼うだけであれば小型で良いかもしれませんがことペアリングともなればこれは見逃せません。 多甲板はありませんが第4椎甲板が小さめなので特価です、 幸い甲ズレを感じさせない素晴らしい育ち具合なのでこの調子でビッグなメスヘルマンに育て上げて下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 万年メス不足が叫ばれる中オスとの違いを顕著に示し始めた都合の良過ぎる飼い込みグッドサイズ! 屋内のケージ飼育でもメキメキと成長しその明瞭なコントラストで存在感を主張する美個体揃い、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 リクガメ飼育の定番種、ビギナー種と謳われて久しいみんな大好きヘルマンリクガメ。 何がそれほど人々の心を惹き付けるのか、 飼育対象種を選ぶに当たり最も気にされるポイントはずばり最大甲長ではないでしょうか。 リクガメと言えばケヅメやゾウガメなど名立たる大型種を抱え手のかかるイメージも強く、 そんな巨体にノシノシと歩かれてはとても家庭内で飼い続けるのは困難だろう、 そんなことを大勢の方が心配していることと存じますが、 分かり易く言えば大きくなっても女性や子どもが片手で持ち上げられる大きさ、 それぐらいのボリュームであれば室内での通年飼育にも無理なく順応することができ、 カメも飼い主もストレス無く共存できると考えられます。 またヨーロッパと言う土地柄は偶然にも我々の暮らす日本と気候風土が似通っていることもあり、 寒い季節でも外で冬越しできますよなんて謳い文句もよく聞かれますが、 何よりも緊急時に温度が保てなかった場合に起き得る事故のリスク、 それを極力軽減できるだけでも選択する価値は大いにあるのでしょう。 あとは言うまでも無くリクガメらしいリクガメであること、 別段派手で華やかな模様を持つ訳では無いにしろ、 全く隙の無いリクガメらしさを全力で打ち出した所が好感度を高めていると言えるのかもしれません。 今回やって来たのは拳よりも更に一回りほど大きく育った、 ここから性転換することもよほど無いであろうメスが確定した安心サイズの二匹。 一目見て驚いたのはとにかく真ん丸であること、 元がやや扁平気味な種類のためここまで甲高かつツルンとしたドーム状に仕上げるのは至難の業で、 成長線がメキメキと艶やかに伸びる様に健康状態を疑う余地も無く、 頭頂部がしっかりと黄色く色付いた部分も含めクオリティの高さを全面に押し出しています。 ベビーから育ててオスになってしまった、 できれば相方をあてがってやりたいとのご希望にすんなりお応えするのはもちろん、 オス特有のフレアー状に広がった甲羅がどうにも好きになれない、 リクガメなのだから丸々としていて欲しいとお望みの方にもお勧め。 何はともあれ外見にも中身にも文句の付け所が見当たらない、実に素晴らしい飼い込み個体です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 全国を探し歩いてもやっぱり見つからないペア取りにも多頭飼いにも嬉しい貴重なメス! とても明るい性格で他個体との協調性にも優れた素晴らしい模範生です、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 ポピュラーという言葉の原義は人気がある、または評判が良いなどを意味していますが、 和製英語ではこれを一般によく知られているとのニュアンスで用いることがあります。 リクガメにおけるポピュラー種については様々な考え方ができると思いますが、 あまりにも大き過ぎたり飼育に対して癖を感じたりと飼い主を選ぶ可能性のある種類を除けば、 自ずとチチュウカイリクガメの仲間が名乗りを上げることになるでしょう。 ギリシャ、ヘルマン、ホルスフィールド、今となってはすっかり聞きなれた名前ばかりですが、 これらが定番化するに至ったのも今日のある程度確立された飼育技術があってこそ。 正しい飼い方や自然本来の姿ないしは行動が広く認知されていなかった時代、 人々は見た目や雰囲気だけで購入するカメを選んでしまいがちでしたが、 終生飼育に対する意識が向上すると共に何が正しくて何が間違っているのか、 より理解を深めたその時にようやくこれら御三家の有難味が分かってきたのだと考えられます。 つまりただ単に見栄えの観賞価値ばかりを求めるのではなく、 例えばいつ見てもよく歩いてくれるという最も基本的なことから、 省スペースで無理なく飼い続けることができる、人懐っこく手から直接餌を食べてくれるなどと言った、 共に生活する楽しみを味わうために価値観が変容していったのではないでしょうか。 人気が高くなればそれがよく知られるようになり、 また有名になれば更に支持を集めやすくなるという互いの相乗効果が、 前述のポピュラー種という概念をつくり出しているのです。 今回ご紹介するのはいよいよ性別の確定した手の平いっぱいサイズの個体で、 幸運なことになかなか手に入らないメスがやって来てくれました。 日本中で本当に多くのファンを持つヘルマンですからその飼育数はもはや勘定し切れないほどですが、 温度性決定の関係なのかほぼ全ての個体がオスになってしまい、 メスは十頭に一頭かそれ以下という恐るべき稀少価値を有しています。 ちょうどベビーから育てた個体がオスだと確信するのがこれぐらいの大きさ、 盛り始めて他人に迷惑を掛けてしまうのもこれぐらいの大きさ、 もっと言えば初めての飼育が大分落ち着いてきてもう一匹お迎えしたくなるのもこれぐらいの大きさですから、 現在オスを飼われている方にはもちろんのこと、 メスをお持ちの方にも複数飼育のメンバーとしてお迎えするのは如何でしょうか。 以前から在庫しているヘルマンの群れと一緒にしても争うことはなく、 少なくともこの個体から攻撃するようなことは考え難いでしょう。 在庫のオスと併せてペアにしたいのが本音ですが、 毎度メスのみのお問い合わせを頂戴するため割り切って単品にてご案内しますので、 このチャンスをお見逃しなく。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (ライトカラー・♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| まるで何かの色彩変異かと見紛うほど体中から眩い輝きを放つ麗しのゴールデンヘルマン! その美しさも然ることながらメス確定であることも見逃せない種親候補としても有用な一匹、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 日本人にとってのカメと言えばやはりイシガメやクサガメなのでしょうが、 ヨーロッパの人々にとってのカメとはこのヘルマンがぴたりと当てはまるのだと思います。 かの有名なイソップ寓話に登場するカメのモデルは何を隠そう本種であると示唆されていますが、 なるほど確かに、水棲ガメが山でウサギと競争する光景など不自然なことこの上無く、 やはりそこは陸上を主な生活圏とするリクガメである必要性が大いに考えられ、 そんな異国のカメが巡り巡って我が国におけるペットトータスの定番種になろうとは、 偶然以外の何物でもありません。 気候の近い日本では非常に育て易いところがビギナー向けとされる所以であり、 現地で養殖されたものから国内で繁殖されたものまで安定的な供給が続けられていますが、 そんなヘルマンも意外とバラエティに溢れ、 よく見てみるとその体色にはいくらか個体差が確認できます。 今回やって来たのは体中の黒味と言う黒味が殆ど消失しかけた上に、 元々持っていたイエローがかなりこってりと発色した、 俗にハイポメラニスティックなどと称されるような淡い雰囲気に仕上がった選抜美個体。 ギリシャやヘルマンなどにはお約束のデザインである、 各甲板を横切るようなバンド状の黒斑はほぼ薄れ、 全体的に放射模様のような痕跡を残すのみとなっており、 しばしば亜種判別の根拠としても注目される腹甲の黒斑についても、 その大部分がかなり消えかかるなど高い精度で色抜けが起こっていることが確認できます。 嘴を中心とする顔面の前半分は仕方無いとしても、 後頭部から首にかけては緑がかった黄色に覆われていて、 四肢の鱗の鮮やかさも相まって非常にゴージャスなオーラを放っています。 幼少期の生育環境により甲羅がやや扁平になっていますが、 これは勿体無いと言うことで実は当店で引き上げバックヤードにて暫く育てていたところ、 随分と盛り上がりを見せ硬くしっかりとした成長を再開しています。 ヘルマンの群れに放てば一際異彩を放つお上品な雰囲気の飼い込み個体、 その潤沢な流通量に反してなかなかお目にかかれない絶品カラーです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (♀) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 油絵具を何度も塗り重ねたような強いコントラストが色彩の立体感をも生み出す特濃カラー! 持って生まれた高いクオリティと飼い主の腕が見事にマッチングした相乗効果の賜物です、 ヒガシヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 ペットとしてのリクガメ人気とは今に始まったことではありませんが、 現在では飼育技術の発展はもとよりそれに必要な機器が充実したことや、 更には肝心のカメについて選択肢が増えたことも大きく寄与しているのだと思います。 昔は素性もよく分からない野生個体が輸入されたは良いものの、 そもそも目の前にいるカメのコンディションに問題はないのか、 どのような設備でどのような餌を与えるのが正解なのか、 右も左も分からない状態で試行錯誤してきた先人たちには本当に感謝しなければなりません。 流通する種類が増えたと同時に健康な繁殖個体も数多く見かけるようになった現代、 敷居が下がった上に愛好家の裾野が随分と広がり多くの人が同じ趣味を楽しめるようになりました。 その中で流行を支える存在のひとつがこのヘルマン、 なかなか手の出し辛い価格帯で長らく販売されていた過去も信じられないほど着実に普及が進み、 最近ではビギナー向けの代表種として名を馳せるほどですが、 比較的小型なだけに一匹がうまく成長するともう一匹という流れになったり、 初めから複数匹を同時に飼育しようとする試みも珍しくありません。 そこで問題になるのがペアリングと個体同士の相性、 卵の孵化温度に性別が左右されてしまうせいか結果的にオスとなるケースが極めて多く、 またオス同士の不仲が原因で同居が困難になったりと、 悲しいかなオスを排除しメスを求める声が日々寄せられています。 反対にメスは温厚な性格の個体が多いというのもありますが、 繁殖を目指す場合にメス一匹ではオスの性欲を受け止めきれないことや、 メスが沢山いた方が単純に効率化を図れるという点で、 どうしてもメスの放出はごく限られたものになってしまうようです。 今回やって来たのは推定およそ三、四歳とまだまだ若いながらも、 サイズやボリュームについてはそろそろ産卵してもおかしくない段階に達しているメス。 前述の件を踏まえると、 ベビーから育て始めてロンリーなオスを単体で飼育している方にとってはお嫁さん候補に、 既にペアリングが達成されている方でもメンバーの増強には欠かせない貴重な一匹となるはずです。 色合いについては冒頭で触れた通りですが、 過去取り扱いの個体と比べて頂いても一目瞭然、 まるでおもちゃのようなはっきりと分かりやすい着色は溶き卵を表面に塗って焼き上げたようなコクがあり、 良好な環境で仕上げられたしっとりと滑らかな甲羅表面の質感もそれを助ける無くてはならない要素と言えるでしょう。 とにかく大きくて綺麗な珍しいメス、問い合わせを頂いた時には絶対に見つからないのに、 ふとしたタイミングで華々しく登場されるのは本当に困りものです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 小さな頃から育てたいけれどペアが欲しいと言うわがままな願いを無理矢理叶えたヤングサイズ! 新規の成長線も違和感無くごく自然に伸びているツルピカに育てたい方にもお勧めの二匹、 ヒガシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。 本種の登場が少なくとも我が国においては、 リクガメを飼育すると言う行為の敷居を格段に下げ、 より多くの人に喜びと楽しみを与えるようになったと言っても過言ではありません。 俗に飼い方と呼ばれるいくらかの作法がマニュアル化され、 それを忠実に再現すればお手元で元気がリクガメが育ち上がったり、 環境を構成する数々の専用器材がその性能を向上させていたりと、 本体の周りにあるものが総じて進歩していることも関係しているのでしょうが、 そうやって用意された暮らしにすんなり馴染んでくれるのはもちろんのこと、 下手をすれば日本の野外でもオールシーズン対応できるポテンシャルの高さは、 それだけで安心材料になりまた付加価値にもなり得るのです。 ベビーから飼い始める人の心理としてはほぼ間違い無くペット感覚であり、 その一匹が無事に育てば良いと言うことになるのですが、 欲望が高まりいずれは繁殖などと企み始めると相方の存在が必要不可欠に。 或いは頭から繁殖を目指しての飼育を志願した場合、 流石に成熟した雌雄を揃えようと思うと巡り合わせや予算の都合もあり、 入手するまでのハードルが上がってしまうのも避けられません。 初めから繁殖を視野に入れつつもそこまで急務では無い、 そんな絶妙なニーズにお応えするのはベビーでも無ければアダルトでも無い、 ようやく性別が確定するお年頃に達したまだまだ育て甲斐の残された拳サイズのペア。 ベビーから育てて性別が分かってから相方を探すのも悪くありませんが、 初めからペアを揃えるつもりでいるのならこんな出物も悪くないでしょう。 特に初めから通年屋外飼育に挑戦しようと企んでいる方にとって、 幼体と言うのはいきなり外に出せないデメリットを抱えていますから、 指で押してもビクともしないカチカチの甲羅を備えた中くらいの大きさになれば、 安定感が段違いで野放しにしていてもこちらはどっしり構えていられると言うものです。 現地より輸入された時点で不確定ながらも性別が分かるぐらいのサイズで、 育ち方を見ても殆どワイルドのようなナチュラル感はお見事。 それに加えて当店でしっかり食べさせ新たな成長線も出ていますのでご安心下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (マケドニア産・Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
|
同産地同サイズでこれからの未来を担う若い二人、こんなペアを待っていました!
あのベビーを見た後ですから数年タイムスリップしたような心持ちです、
マケドニア産のヒガシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。
せっかくロカリティの付いたリクガメを飼育するなら、まずはそのお国についておさらいしましょう。
正式名称はマケドニア共和国、アレクサンドロス大王の時代にまで遡る歴史ある土地に建ち、
隣にギリシャやブルガリア、周囲を黒海と地中海に囲まれた東欧の一国です。
近縁種のギリシャなどとは異なり現在野生個体が輸入されることは殆どなく国内CBが流通の多くを占める中、
現地で繁殖された個体を見かけるケースはかえって珍しく新鮮な出会いに感じてしまいます。
この6匹は在庫のマケドニアベビーが育ったものではなく、同じラインから放出されたヤングアダルト。
先日の文末に同産地ペア狙いで揃えてみても面白いかもしれないと書きましたが、
あんなにヘルマンにはメスが少ないと嘆いていたことが嘘のようで、
まさか3ペアも目の前に現れるとは思いませんでした。
甲羅の理想的なフォルムと正確無比な成長線の刻まれ方を見るに毎日平穏な暮らしを送っていたのでしょうか、
人が育てたと言うより自然が育てたと言うべきかもしれません。
ベビーからの飼い込み個体をいくつ並べてもこれほどまでの完成度を見せてくれることはそうそうなく、
あくまでも繁殖個体なので大きな傷がないというのも嬉しいポイント。
そして今回力を入れてプッシュしたいのが決して即戦力ではない、
一体何歳なのかも分からない大型個体ではなく、これからがまさに旬の次世代ペアという所で、
ピュアな系統を維持しながら外国産のリクガメを繁殖し飼育を続けることができるというのはどれだけ素晴らしいことでしょうか。
似たもの同士でペアを組みました、それぞれの特徴をよく見て将来のためにセレクトして下さい。
ペアA: 背甲 ・腹甲 ペアB: 背甲 ・腹甲 ペアC: 背甲 ・腹甲 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| しばし孤独と戦っていたオスが無事ゴールイン! 貴重なメスが加わって店内は幸せムードに包まれています、 ヒガシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。 その全てがほぼ絶滅危惧種というとても危うい境遇に陥っているリクガメ全般において、 ヘルマンほどクリーンにペットとして出回る種類も珍しいと思います。 野生個体こそ今現在輸入される見込みはほぼありませんが、 逆に繁殖個体しか流通しないこの状況下でビギナーにとっても射程範囲内のこなれた価格が実現できるのは何故でしょうか。 その答えはやはり、日本人のヘルマンに対する愛情の賜物ではないかと思います。 近縁種のホルスやギリシャ同様に現地CBもやっては来ますが、 全体のかなり高い割合を国内CBが占めるというのはつまり、 我々が単にヘルマンを好きで多くの方が繁殖までこぎつけているという成果の表れでしょう。 見た目のシンプルな美しさや顔付きの可愛らしさ、 そして何と言っても愛嬌溢れる明るい性格が人気の秘訣。 加えて気候の近いヨーロッパに棲息するため、飼育環境に馴染みやすいというのも嬉しいポイントです。 このペアはオスが国内CB、メスが欧州のブリーダーCBという異なる由来の組み合わせで、 どちらも性別確定の程よいサイズに育っています。 メスはパッと見た時黄色味の強さが印象的でしたが、 オスと並べてみるとかなりの上物であることがよく分かりました。 オスはのべつ盛り他人に迷惑をかけるため独房生活を強いられていましたが、 ようやく発散先が見つかったのでここから本領発揮して欲しい所です。 将来的には屋外越冬も夢ではありません、もりもり食べさせてグングン育てましょう。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 意外と数の少ないメスがやってきたので念願のペアが揃いました。 ビギナーから玄人までもれなく楽しめる素晴らしいリクガメです、 ヘルマンリクガメ・ペアの入荷です。 近年の地中海リクガメ人気の波に乗り、ここ数年は一層ブリーディングが進み価格もこなれてきました。 しかしながらベビーから育った個体は何故かオスばかり、今回貴重なメスがやっと入手できました。 どちらの個体もCBから育ったのでしょう、新しい成長線には潤みを帯びたツヤのある光沢があり、 ほとんどボコつく事もなく素晴らしいフォルムに仕上がりつつあります。 オスは早くから尻尾が大きくなるので性別判定は容易ですが、甲羅を上から見てもオスは末広がり、 メスは丸っこくこんもりとした形状で違いは歴然。オスは何を焦っているのかガツガツ盛る肉食系で、 メスはもう少し大きくした方が良いのでしょうが飼い込む内に良いペアになってくれそうです。 餌も選り好む事なく葉野菜からMazuriリクガメフードまでよく食べています。 今流行りの通年屋外飼育できるリクガメは今後ますます人気が高まっていきそうです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (即戦力・Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 見ているこちらまでうずうずしてしまう超即戦力ペア! 小洒落た雰囲気と相性の良さが嬉しい、 ヒガシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。 私たちが呼ぶリクガメとはカメ目リクガメ科という全体から見ればほんの一部にしか過ぎない小規模のグループですが、 それはあくまでも生物学的な分類上の話。 趣味の世界では決してそんなちっぽけなものではなく、 同じカメでもリクガメという新たな分野を創出してしまうほど強大な影響力を誇っています。 昔から一目置かれる目立った存在で、 ホシガメやケヅメなど長い歴史の中で人気の基盤を作りそれを支え続けてきた主役級のキャラクターが集う中、 新時代とも呼ぶべき新しい波の到来に本種とその仲間たちが大いに関わっていることはご存知でしょう。 それまで一部のマニアだけの持ち物だったのが一般層に普及する過程で、 最終的なサイズや扱いの容易さなどの課題を見事クリアし台頭してきたのがチチュウカイリクガメの一団です。 多くが最大でも20cm未満と持て余しにくい大きさ、 気候の近いヨーロッパ原産の種も多く飼育環境に馴染みやすい、あわよくば通年屋外飼育も可能、 そして何より明るい性格と顔付きの可愛らしさがとどめの一発。 特にヘルマンは見た目の上品さも相まってスポットを浴びた途端瞬く間に評判を集め、 原産国の関係上ホルスやギリシャと違い流通量が限られていましたが、 近年では熱心な愛好家らのお陰でビギナーにとっても手の届く範囲に落ち着いてきました。 ということは国内繁殖成功への道がかなり現実的であり、 すなわちベビーは出しても種親候補は出さないとなるのがこの世の常ですが、 今回は成熟サイズを迎えたばかりの若いペアをご紹介します。 とどのつまりは転居のためスペースにどうしても都合がつかなかったそうですが、 カメのためにも新しい飼い主のためにもこれほど嬉しいことはありません。 どちらもヘルマンとしては許容範囲内であろう最低限のボコつきで綺麗に成長し、 全体のこんもり感も申し分ないグッドコンディション。 色味も良く特にメスは四肢や頭頂部の鱗がレモンイエローに染まり見栄えがします。 さすがにそこまで期待はしていなかったのですが、撮影のため2匹をテーブルの上に置いた所、 いきなりオスがメスを背後から追い回しおしりかじり虫になっていました。 今のご時世、投機目的で導入しようと企む人はあまりいないと思いますが、広い庭で気長に飼育したい、 でもそのためには最初からカメにある程度の大きさがないと不安、というような方にお勧めします。 ゆくゆくは繁殖も見据えてじっくりと頑張ってみて下さい。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (フルアダルト・Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| しこたま見慣れた普及種ながら案外いそうでいない今直ぐにでも繁殖に挑めるフルサイズペア! 両者の育ちぶりも含め見た目についても中身についても色々な意味で手にする価値のある、 ヒガシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。 きちんと数えたことはありませんでしたがかれこれ十年以上にもなるのでしょうか、 表面上の話ではなく本当に飼い易いリクガメとは何かと問われた時、 その名前を挙げればまず間違いないであろうと多くのファンから支持されている、 ヨーロッパを原産とするその名もチチュウカイリクガメの一派から飛び出したのは、 例のウサギとカメが山で競争するお話のモデルになったとも噂されるこのヘルマンです。 まず見た目のスタンダードさが受けに受け、 リクガメらしいという表現をストレートに具現化してくれたことへの評価は高く、 妙に明るく警戒心の薄い気質のお陰で躍動感の三文字がピッタリなところもまた、 サイズ以上のダイナミックさを楽しませてくれる要因となっていて、 一言で表せば育てて楽しいということになるのだと思います。 そして原産地の気候と日本の四季との相性がバッチリなのもまた嬉しいポイントであり、 温度や湿度、その他の環境要因に対して不満を漏らすことが殆どないため、 飼い方が手に取るように分かるところが他のリクガメではなかなか再現できない最大の特徴と言えます。 かつてはビギナー向けと言われつつも幼体でさえ数万円の値が付けられていたため、 誰もが気安く手を出せるキャラクターではありませんでしたが、 昨今でははっきりとした需要が見込めることからペット向けの養殖が進み、 随分と身近な存在へとなってくれたことについてはもはや感謝の言葉しか見当たらないのです。 今回やって来たのは雌雄共に綺麗なドーム型のツルンとしたフォルムに仕立てられた、 それぞれが全く異なる場所で幼体より育て上げられた長期飼い込み同士のペア。 何とも愛情のたっぷりと注がれた様子が甲羅を始め体全体から漂っていて、 さすがに元々ペットであっただけあり外観の出来栄えに対する妥協の跡は見受けられません。 決して屋外ではなくとも屋内のソフトなクーリングをかけてやるだけで、 来春から直ぐにでも乗って直ぐにでも産んでくれそうな雰囲気満々なので、 ただ並べて眺めておくだけでもその魅力は存分に味わえることと思いますが、 憧れのブリーディングに挑戦するためにも見逃せない引く手数多の二匹です。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (特大アダルト・Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| もう繁殖の2文字が目前まで迫った素晴らしい個体達がやってきました。 このメスの大きさはなんでしょう、感動です。 ヒガシヘルマンリクガメ・ペアの入荷です。 日本と気候の近いヨーロッパを中心に棲息する地中海リクガメの仲間でも特に人気の高いヘルマン、 それはいつからか国内CBの可愛いベビーが数多く出回る様になったことが物語っています。 最大でも20cm頃と手頃なサイズ、温度・湿度ともに管理しやすく 果ては通年屋外飼育もできてしまうことからビギナー向けとしても取り上げられますが、 特に愛らしい顔つきや行動が何にも代えがたいです。 やはりこれだけ多くの人がブリードに成功しているカメですから是非挑戦してみたい所ですが いかんせん繁殖個体ではメスの数が極端に少なく、 更に大きなサイズのものとなると全くと言って良い程出回らないのが現状。 しかし今回とてつもない大きさのメスとそれに負けないオスが揃いました。 部屋に放すとメスの行く方行く方にオスが匂いを嗅ぎながら行進しやる気は十分。 これだけ大きいとオスも乗るのが大変そうですが、多少苦労した方が燃えるのかもしれません。 メスに甲板別れがありますが、 言わないと分からない程度であまり気にならないと思いますが念の為。 サイズと言い色味と言い大満足のペアです。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (特大即戦力・Pr) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
| 未だかつてないダイナミックなオスと産卵可能な即戦力のメスとの運命的な出会いが此処に! 今すぐ繁殖させたくてカメよりもむしろ人間が興奮してしまう程のド迫力、 飼い込みフルアダルトのヒガシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。 リクガメの飼育を志す初学者が必ず一度は耳にするであろうその名前、 ご存知の通り定番として数えられる入門種のひとつです。 今となっては安定供給が実現しているものの、棲息地の関係で野生個体を流通させることが困難なため、 繁殖が進んでいなかった昔は似た仲間のホルスやギリシャよりもずっと高級種扱いでした。 しかしながらその飼いやすさ、親しみやすさが注目を呼び、 継続的なブリーディングが軌道に乗り始めた現在では初めてのパートナーとして選ばれることも多くなりました。 いくら欲しがった所でどうしても手の出ない状態が続いていた時代のことを思えば、 今の我々を取り巻く環境は非常に恵まれていると思います。 やはりベビーサイズから飼い始められることが多く、育ててみるとオスになることが殆どで、 そうすれば誰でも自ずと相方を探すようになるのは人情でしょうか。 性別未確定の段階でも僅かにメスの香りがすればそれを嗅ぎ付けるように日本全国津々浦々、 何処からともなく必ずメス狙いの人が現れるというのは、 ヘルマン自体がいかに人気が高いのかを示す証拠と言えます。 今回やって来たその貴重なメスは、 ニシヘルマンもかくやと言わんばかりにべったりとしたイエローが発色し、 稀少性も然ることながらそのクオリティも申し分ありません。 同時に頭部や四肢の鱗ひとつひとつにも黄色が丁寧に浮かび上がり、 潜在する美意識の高さが全身から一杯に噴き出しています。 大概ペアでご紹介するとメス単品の希望が殺到してしまうのですが、 果たしてこのオスを素知らぬ顔で通り過ぎることができるでしょうか。 十分に成長したメスの甲長を抜き去るその有り余る体格は、 オスらしくフレアーが際立ったフォルムも相まって少なくとも私の眼には最高に格好良く映っています。 申し訳程度に生えたメスの小さな尻尾を根こそぎ引きちぎってしまわんばかりの極太下半身はまさに凶器、 妙にアンバランスな四肢も体からはみ出さんばかりの強靭ぶりで、 底知れぬバイタリティの高さに人もカメも慄くほど。 こんなオスなら単品で掲載しても良いレベルですが、 せっかく揃って飼われてきた相性の良いペアを引き離してしまうのも気が引けるため、 やはりこの一組で検討して頂きたいというのが正直な思いです。 季節的にも導入に踏み切るには最良のタイミング、 可能ならば今すぐ通年屋外飼育体制に入り来シーズンから貪欲に繁殖を狙っていきましょう。 | ||||||||||
|
ヒガシヘルマンリクガメ (アダルト・トリオ) Testudo h. boettgeri |





|
|
||||||||
|
お客様長期飼い込み委託個体、ヒガシへルマンがトリオで入荷です。4月半ばから10月上旬まで屋外飼育で育てていたそうです。何故か
地中海リクガメの仲間は、お日様を充分浴びさせても甲羅が凸になりがちですけど、すこぶる元気が良くケージ内を走り回っています。
現在はメスを分けて管理していますが、写真を撮るためにあわせたら、
いきなりオス2頭が、交尾行動をし始めました。
相性も良くメスも逃げずにじっとしています。餌は、葉野菜を中心に、Mazuriリクガメフードを食べさせています。地中海リクガメ属も、
あまり見かけなくなってきましたので、是非このトリオで仔ガメのハッチにチャレンジして下さい。
オスは(1頭どちらか)ばら売り有り、メスはペア又はトリオでお願いします。 | ||||||||||
|
ダルマティアヘルマンリクガメ (♀) Testudo herm. hercegovinensis |





|
|
||||||||
| 知る人ぞ知る第三のヘルマンとして数年前より細々と出回っている幻のヘルツェゴビエンシス! 最小亜種としては上々の出来栄えと言えるいつ産卵してもおかしくないフルサイズ、 ダルマティアヘルマンリクガメ・メスが入荷しました。 ヘルマンと言えば今やビギナー向けのペットトータスとして知らない人はいない、 誰しもが必ず最初に目にするリクガメとして厚い支持を受けるポピュラー種のひとつ。 かつてそのポジションを陣取っていたギリシャやロシアについては、 元々野生個体が流通の大半を占めていたこともあって、 年々取引額が高騰すると共にじわじわとその数をも減らしており、 もちろん目にする機会が全く無くなってしまった訳ではありませんが、 反対にほぼ全てが繁殖個体であるヘルマンに比べて分が悪いのは一目瞭然、 次第にその役目を引き継ぎつつあるようです。 そんなメジャーなキャラクターでありながら全国にはヘルマンに拘って愛好するマニアも少なからず存在し、 例えば基亜種ニシヘルマンに見られる産地別のコレクションであったり、 最近ではもうひとつの亜種として認知され始めたこのダルマティアヘルマンが、 新たな刺激物質としてハイアマチュアの欲望を満たし始めているようです。 今回やって来たのはヘルツェゴビナなどとも呼ばれる三つ目のヘルマンより、 いよいよ性別が確定するサイズにまで到達した立派な姿をした二匹のメス。 幸いオスの方が多く出現するとされる本種ですから、 いくら稀少な亜種であったとしても幼体から育てられたオスをお持ちの方がいるのではないかと考え、 前飼育者の元では何故か二匹とも揃ってメスになってしまったこの緊急事態に際し、 何処かで相方の登場を待ち望んでいる方の下へお届けしたいとの強い願いを受け、 長きに渡りきっちりと仕上げられた飼い込み個体を当店へ託されたと言うことです。 鼠蹊甲板と呼ばれる後肢の付け根辺りに現れる左右一対の小さな甲板が、 ニシやヒガシにはあってダルマティアには見当たらないと言うのが特徴とされ、 三亜種の中では最も小型であるとも言われています。 どちらの個体も満足な成長ぶりが窺える良好な仕上がりで、 常時同居させていますが特にトラブルも無く平穏無事な生活を送っています。 細かな情報を抜きにしても甲高のフォルムが立派な即戦力となり得るアダルトサイズ、 国内でのブリーディングも夢ではありません。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (南フランス産・EUCB) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| 東西の見分け方について議論を展開するまでも無く一目見てそれと分かる由緒正しき純血ベビー! 濃厚に発色したイエローやブラウンが見慣れたヒガシ亜種とはまるで異なる、 南フランス産のニシヘルマンリクガメが入荷しました。 その昔飼い易いリクガメと言えばロシアやギリシャぐらいしかまともに流通していなかった時代、 同じく飼育が容易な小型種として紹介されていたヘルマンは流通が安定しておらず、 高価なこともあって長らく手の届きそうで届かない位置にいたため、 一般に普及し始めたのはほんのつい最近の出来事と言っても良いでしょう。 その頃から囁かれていたのが同じヘルマンにも西と東が存在するとの説で、 しかしながら数多くの個体をお目にかかることが叶わなかった頃は、 何を以って典型として良いのかすらもさっぱり分からなかった訳ですから、 当時より個体数の少ないとされた基亜種が明確な付加価値を持つことになるのもまだ先の話だったのです。 思い起こせば何となくそれらしい見た目の個体を無理矢理ニシとしていた感も否めませんが、 仮に入手できたとしても同じタイプを複数匹はおろか上手にペアを揃えることすらも困難でしたから、 特に繁殖を視野に入れた場合には無難なヒガシを中心に集めていた方も多かったと思います。 時は流れ近頃では説明不要の特徴が分かり易い幼体がコンスタントに、 それもご丁寧にロカリティについての情報まで付与された状態で出回るようになり、 同じ基亜種でも更に突っ込んだ部分にまで拘りが持てるようになりました。 仮にベビーで入手したとしても将来的に相方を探すのが随分現実的になったため、 これまでただ単純にレアもの扱いだったニシヘルマンも、 ブリーディングを目指し易くなったと言う点では今後更に評価が上がっていくものと思われます。 今回やって来たのはヨーロッパより直輸入された、 南フランス産との表記でオファーのあったピカピカの極小ベビー。 国内CBでもあまり見かけないとても小さなサイズですが、 日本に到着して暫くトリートメントされていたお陰で体付きは幾分がっしりとしており、 60センチのケージに単独で入れてもかなりアグレッシブに歩き回るためだだっ広さを感じさせません。 稀少性はもちろんですが見慣れた黄色とはまた異なる、 絵の具で言えば本当のきいろに程近いこってりとした色合いがお好きな方は、 是非この可愛らしい大きさから育ててみて下さい。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (ベビー) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| ニシには珍しい小さめサイズながら早くもMazuriリクガメフードを爆食している期待の絶好調軍団! 初期状態としては申し分ない動きのキレが嬉しい初めての方にも安心のスペシャルセレクトたち、 ニシヘルマンリクガメが入荷しました。 過去十数年を遡ったとしても恐らく今現在が最高潮に達しているのではないかと思われるほど、 人気と知名度が爆発的に上昇しているリクガメの顔として活躍中のヘルマンリクガメ。 単にヘルマンとした場合には流通量が格段に多い亜種ヒガシの方が該当し、 無論シンプルにペットとして可愛がっていく分には何の支障もないのですが、 これが色や柄などに拘り始めるとそうもいかなくなるところが面白いです。 どちらが良いというのはあくまでも好みの問題ではありますが、 基亜種ニシヘルマンには傾向として濃厚な黄色味を呈するものが多く出現するとされ、 それについてももちろん地域差や個体差が見られるそうですが、 ヒガシとして典型的なあっさりとした雰囲気ではなく、 どちらかと言えばこってりとした風貌が印象深く映ることでしょう。 それが人によっては美しさという評価に繋がるばかりではなく、 世界的な需要を満たすための莫大な頭数を養殖によって賄うヒガシとは異なり、 主にあちらの愛好家らによってコツコツと殖やされていることの多いニシは、 頻繁にそれも数多く見かけられる機会があまりないせいか、 やはりその稀少性も相まってプレミアムなイメージが付与されているようです。 今回やって来たのは定番のヒガシでこの頃見られるベビーサイズに近い、 手の平に載せてもスペースが余ってしまうほどの可愛らしいおチビたち。 取引価額の影響もあるのかもしれませんが、 大抵のニシヘルマンは一年近く育てられたカッチリサイズでお目見えすることが多く、 それはもちろん単に安心材料として好意的に受け入れられるのでしょうが、 何処か楽しみが奪われてしまっている感も否めないと思います。 ただし重要なのは絶対的な体の大きさではなく中身の質であり、 ハイテンションで走り回り他人の餌まで奪い取る姿を見るに、 彼らの健康面や生命力を心配するのは失礼に当たるぐらいのものです。 現在店頭ではニシもヒガシも横に並べて見比べられるようになっていますので、 このチャンスをお見逃しなく。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (トスカーナ産) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| 体中にハチミツでもコーティングしたかのようなこってりとした黄色味が際立つ美個体揃い! ここ数年でようやくその良さが見直され始めたヒガシよりも濃厚なカラーリングの基亜種、 トスカーナ産のニシヘルマンリクガメが入荷しました。 ヘルマンと言えば今やペットトータスの世界に無くてはならない存在ですが、 よく調べてみるとニシとヒガシ、 それに最近ではダルマティアやヘルツェゴビナなどと呼ばれる第三のヘルマンも現れ、 かつてない盛り上がりを見せています。 通常特別な説明も無くただ単にヘルマンと呼ばれているのが亜種ヒガシで、 興味本位で様々な資料に目を通すとついつい気になってしまうのがここにご紹介する基亜種ニシ。 前者ではいけないと言う訳ではありませんが、 最大甲長が少し小さいらしいとか体色のコントラストがより明瞭になり易いとか、 流通がまばらでいつでも手に入る訳では無いとか色々言われてしまうと、 何となくこちらの方が良いのではなかろうかと感じてしまう方も多いと思います。 最終的なサイズについては育て方の問題もあって一概には言い切れませんが、 少なくとも色合いについてはやはり明色部が絵具セットのレモン色では無くあくまでも黄色に、 暗色部の面積がやや広くそれぞれの境界もはっきりと分かれていて、 何となく煌びやかに見えてしまうのも気のせいではありません。 昨今では一年を通し現地で計画的な養殖が進められているヒガシヘルマンとは違い、 ニシはあくまでもシーズンに入らなければ思うように入手することができず、 年間の取引量も圧倒的に少ないため稀少性が高いと言うよりは、 むしろ欲しい時に手に入らないことに対して不満を覚える場面の方が多いと思います。 今回やって来たのはトスカーナ産としてまとまって輸入された数十匹の中から、 特に体付きがしっかりとしていて初期状態の良いものばかりをセレクトしたベビーたち。 見た目の良さはそのまま中身の良さに直結してくれたようで、 入荷当初より葉野菜からMazuriリクガメフードまでしっかりと食べ始め、 中には早くも新たな成長線が伸び始めた個体もいるほど、 初めての方にも十分にお勧めできるほどのグッドコンディションです。 時季を逃すと丸っきり姿を消してしまいますから、是非ともこのチャンスをものにして下さい。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (EUCBベビー) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| おもちゃのようなコントラスト強めのカラーリングが如何にもそれらしい典型的な基亜種! 食べる量と歩くスピードが他の個体よりも桁違いに優れているやけに活発な選抜個体、 ニシヘルマンリクガメが入荷しました。 いくらチチュウカイリクガメの仲間たちが初心者向けだとは言っても、 その昔ヘルマンやマルギナータがまだまだ珍しかった時代には、 彼らには申し訳無いのですがロシアやギリシャを選ぶしか手段が無く、 何か持っている知識を語ろうだとかそんな気分には到底なり得ませんでした。 と言うのも実はヘルマンがふたつみっつの亜種に分けられるだとか、 何処の産地がどのようになり易いだとか、 そんな細か過ぎる情報は文献の上でのみ確認することのできる半ば空想に近い話であって、 それが目の前で具現化されたのはほんの数年前の出来事なのです。 思い起こせば本種のニシとヒガシを区別するポイントとしてよく知られていた、 腹甲の黒斑が前者は広く繋がり易く後者は狭く分断され易いと言う特徴を確かめるべく、 そこら中のヘルマンをひっくり返してはぶつぶつ何かを呟くように観察し、 僅かな個体差を取り上げ無理矢理にでもそれらを二系統に分けたものでした。 つまり今日のように説明を受ければ一目で違いの分かる教科書通りのタイプは大変貴重で、 あの時に見ていたものは一体何だったのかと自分を疑いたくなるほど、 本当に恵まれた時代が到来していると心底思うのです。 今回やって来たのは最近チラホラ見かけるようになったお馴染みのヨーロッパブリードから、 少し育ったベビー過ぎない大きさで動きにキレのあるものをチョイスしたこんな一匹。 ほっぺの黄色いパッチがより一層ニシヘルマンらしさを演出する、 甲羅から四肢まで全身のイエローがかなり濃厚に発色した大満足のクオリティで、 大きくなるに連れてヒガシとの違いを如実に味わうことができるでしょう。 言い換えれば昔はニシとヒガシの間にこれほど明確な差が見出せず、 どちらとも定義し辛い個体も多く存在していたため、 我々としても付加価値を与えることが困難だったのは今だからこそ言える話。 背中のしましまがくっきり目立つ育て甲斐の塊のようなベビーを、 Mazuriリクガメフードまでもりもり平らげる健康優良児に仕立てました。 価格もこなれた今だからこそ手に入れるチャンスです。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (EUCBベビー) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| 溶き卵を塗ったようなベッタリとした配色にトレードマークの黄色いほっぺが基亜種の証! 今便はいつもに比べリーズナブルにご案内できますので狙っていた方はチャンス、 ニシヘルマンリクガメが入荷しました。 今やリクガメ愛好家ならびに飼育志願者の間で知らない人はいないと思われる、 最も飼い易いペットトータスとしてあまりにも有名なヘルマンリクガメ。 現在ほどリクガメがブームになっていなかった十年以上も前から有名な種類ではあったのですが、 飼育の容易さと入手の容易さが必ずしも比例しておらず、 年中販売されていると言うことはまずありえませんし金額もそれなりに高価でしたから、 やはり多くの方がギリシャやロシアの野生個体を中心に飼われていたと思います。 しかし最近では現地での養殖技術が格段に進んだお陰か、 もはやヘルマンを見ない日は無いと感じるほど盛んに出回り価格帯も随分こなれてきたため、 以前にも増してその存在意義を強めているのではないかと考えられます。 単にヘルマンと言っても実は二亜種に分類することができるのですが、 無印で販売されるのは流通量の多いヒガシ亜種であり、 一方の基亜種は少し時代を遡ると現物を拝むことすらままならないほどの稀少性を誇っていました。 東西を見分ける識別ポイントはいくつかありますが、 当時は違いの明確では無い中間的な形質を示した個体も多かったと言い、 それどころか比較対象が手に入らないのでそもそも区別する必要すら無いとさえ言われていました。 近頃ではこちらが説明を加えなくとも一目見て違いの分かるタイプが販売されるようになり、 もはやマニアだけの持ち物では無くなってきたような気がします。 今回やって来たのは全身のイエローが発色良好なニシヘルマンの安心サイズで、 現地で少し育てられたお陰で入荷直後からコンディションはすこぶる良く、 特別なケアなども無しにケージ内を元気いっぱい走り回る優良個体。 幼体の時期は特に判別し易いと思いますが、 腹甲はその殆どが黒斑に覆われ背甲も同様に黒が強めで、 それに負けじとベースの黄色が応戦するようなデザインになっており、 四肢の鱗なども見慣れたヒガシヘルマンに比べると鮮やかな色合いであることが分かります。 最大サイズはこちらニシの方が一回り小さく収まるとされていますので、 屋内のケージで長い付き合いをお考えの方にもお勧めです。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (コルシカ産・S) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| この数年で明らかに知名度と人気度が急上昇しているニシヘルマン。 その昔、まだ日本中がその識別に疑念を抱いていた時代には、正直東西の区別が困難であり、 というのもかなり曖昧なものが入り交じって流通してたためと思われ、 基亜種ニシの持ち味といえば単に稀少性だけと揶揄されても仕方なかったのですが、 最近では一目見てニシとヒガシが区別できる、明確で典型的な個体がきちんと見かけられるようになり、 珍しさよりもむしろ見た目の美しさで選ばれるという、実に健全な逆転現象が起きています。 この個体は成育に不安のないふっくらと育った安心サイズで、 既にMazuriリクガメフードオンリーでも暮らしていけるよう鍛えてありますので、 ビギナーさんにもお勧めです。残り一匹のみ! | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (コルシカ産・国内CB) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| 並のヘルマンとはまるで違う基亜種ならではの濃厚な色彩美が如実に描かれた立派な安心サイズ! 血統管理の大切さや重要性を改めて思い知らされる大変にお見事なハイクオリティ国内CB、 コルシカ産のニシヘルマンリクガメが入荷しました。 かつてのビギナーズトータスと言えばギリシャとロシアの二本立て、 こればかりは他のどのような種類であってもその地位を脅かすことなど到底敵わず、 そういえば最近ではロシアよりもホルス、 ホルスフィールドと呼んであげた方が耳馴染みが良くなったのも時代の流れなのでしょうが、 ヘルマンやマルギナータなどは名前ぐらいであれば知られているものの、 何となくヨーロッパ出身の高貴で高級なリクガメというイメージが強かったと思います。 それはつまり後の二種が原産地において高い意識を以って保護されていることを示唆しており、 むやみに野生資源を利用できない事情が結果的にブリーディングを推し進める形となって、 今日ではそのどちらもが、 特にヘルマンの方が安定的に供給されペットとしての地位を完全に確立しました。 ただしそれはあくまでも亜種ヒガシに纏わるエピソードなのであって、 基亜種に当たるニシヘルマンはと言えば量産など夢のまた夢、 各地のブリーダーらがコツコツと系統維持に努める傍らで、 私たちのような一般ユーザーがそういった資源を有難く利用しているような、 非常に狭い範囲で趣味活動が行われているに過ぎないのです。 昔は東西の中間地点で合流したような紛らわしいものも少なくなかったため、 亜種判別に苦労させられることも珍しくありませんでしたが、 最近ではより明確にその形質差が表現されるようになり、 それぞれがそれぞれの付加価値を高め合う結果に落ち着いています。 今回やって来たのは元々はEUCBとして輸入されたコルシカ島を原産とする両親より、 国内でめでたく繁殖に成功した兄弟たちの中から直々にお裾分け頂いたおおよそ一年ものの二匹。 明色部のイエローが濃厚で暗色部の面積が広く互いのコントラストも明瞭、 そんな小難しい説明を一切抜きにしてもニシとしての高いプライドを存分に感じさせる、 こってりとした独特の色合いに食指が動く美しさが値打ちです。 ほっぺたが黄色く見えるのも余計に可愛らしい、 その稀少性を抜きにしても万人にお勧めしたい銘種だと思います。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (コルシカ産・♂) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| 黒と黄色の濃厚な取り合わせがヒガシとは一味違う嬉しいロカリティ付き飼い込み個体! 全体のバランスから細部の色合いまで典型的な基亜種らしさがよく出ています、 コルシカ島産のニシヘルマンリクガメ・オスが入荷しました。 欧州とアフリカ大陸北部を結ぶ地中海、 そこに浮かぶ島の中でもよく知られているシチリア島とサルディーニャ島、 そしてコルシカ島はブーツの形をしたイタリアの西側に配置されており、 先に挙げた二つはイタリア領ですがコルシカはフランス領とそれぞれ国政が異なっています。 チチュウカイリクガメの仲間ヘルマンリクガメは地中海沿岸諸国に繁栄し、 棲息域の東側に当たるギリシャやブルガリアなどバルカン半島の国々にはヒガシヘルマンが、 反対に西側のイタリア半島からその周辺の島々にはニシヘルマンが暮らしています。 両者は陸続きの分布になっていることから亜種の有効性が度々取り沙汰されているのですが、 確かに文献から得られる情報を元に同定を試みると中間的な特徴を示す個体が少なからずいるものの、 それはあくまでも個体差により生じる形質の微妙な違いである可能性も高く、 現在では亜種という単位から更にもう一歩踏み込んだ仕分けが実践されています。 皆さんも既にお気付きのことと思いますが、 この頃ヨーロッパより輸入される幼体は産地情報が添えられていることも多く、 ある棲息範囲の中でそれらの特徴に一定の傾向が見られたり、 仮にそうでなくとも現地の人々は外観よりも何よりも真っ先に採集地というデータを重要視するようで、 そういった考え方が近年の純粋な血統が維持されたブリーディングに繋がっているのでしょう。 例えば我々がニホンイシガメの捕獲された県名から川の水系までを知ろうとするように、 あちらのブリーダーは亜種という概念を超越した発想で繁殖に取り組んでいるのです。 今回やって来たのは冒頭でも紹介したフランス領コルシカ島の血筋を持つベビーサイズから育てられた一匹のオス。 お腹も背中も全身を覆う黒斑が広範囲に渡って強烈に塗りたくられ、 その隙間から顔を覗かせるイエローは絵の具セットで言う所のレモン色程度の薄さではなく、 その隣に置かれた黄色と同等の濃さを示しています。 体を見ても頬から四肢の鱗に渡る非常に明るい配色は妥協を感じさせず、 素直に美しいと評価できるクオリティです。 あまりにもマイナー過ぎる産地ではペアを組むのにも一苦労ですが、 コルシカはしばしば見かけることができるため将来的に繁殖へ前向きになれると思いますし、 島という特性上個体群の独立性が明確に保たれていますからこちらのモチベーションも上がります。 人が見ていない所でも四六時中走り回っている状態抜群の明朗な性格はペットとしてもお勧めです。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (コルシカ島産・♂) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| ベビーではよく見かけますがしっかり育ったこのサイズはレア、 お客様委託のニシヘルマンリクガメ・オスの入荷です。 ヨーロッパなどから繁殖された幼体が輸入されて来ますが、今回はそのベビーを育て上げたアダルトで 繁殖用にはうってつけではないでしょうか。しかもロカリティのはっきりしたコルシカ島産という事で、 そこに拘る方にもかなりオススメです。よく見かけるヒガシヘルマンとは、お腹の黒斑の面積が広くライン状に繋がる事、 目の下に明瞭な黄斑がある事で区別されます。 ヒガシの方は多くの方が国内繁殖に成功されていますがニシはまだまだ少ないので、 このオスで是非ブリーディングにチャレンジして下さい。 | ||||||||||
|
ニシヘルマンリクガメ (Pr) Testudo h. hermanni |





|
|
||||||||
| ふたりの背中を天より望むだけで即座に基亜種だと判る極めて特徴的な形質を持つヤングアダルト! このまま順調に育てば遅かれ早かれハッピーなライフイベントにも遭遇するであろう将来期待の二匹、 ニシヘルマンリクガメ・ペアが入荷しました。 かねてより業界では秀逸なペットトータスとしてプッシュされ続けた種類ではありましたが、 ここ最近ではメディアの影響も追い風となってますますその人気が高まっている、 今やなくてはならない存在として確固たる地位を築き上げたリクガメ界最人気種のひとつ、 ヘルマンリクガメ。単にヘルマンとした場合には亜種ヒガシを指すのが暗黙の了解であり、 そもそもヘルマン自体にふたつもみっつもバリエーションが存在していることなど、 広く世間には知れ渡っている訳ではないのかもしれませんが、 少しかじった人々にとってはその稀少性に惹かれ変わったタイプを求める声も聞かれます。 ヒガシよりもニシの方が良いとする価値観には様々なものがありますが、 やはり現存する個体の絶対数が少ないことから珍しいと考える向きが強く、 ごくシンプルに他の人が持っていないからというパターンは外せません。 或いはヒガシよりもニシの方が甲羅から体まで全身の体色が濃厚になる傾向があり、 黄色と黒色との見事な調和が美しさを演出してくれるため、 華やかに煌びやかに感じられるというのも重要なポイントのひとつでしょう。 他にもペットとして愛でるだけではなくブリーディングを視野に入れた場合、 ヒガシについては現地の養殖が殊更に進んでいますが、 対するニシはまだまだ飼育下での繁殖事例が決して多く聞かれる訳ではないため、 成功した暁には社会貢献度の高さがより強く味わえるというのもミソなのだと思います。 今回やって来たのは流通量の少なさから長くブランド化が進められてきた基亜種ニシから、 せーののタイミングではなかなか揃えられないオスとメスの二匹。 ヘルマンあるあるとしてメスが特に得られ難いためこうしておめでたい並びを実現することが困難であり、 当店でも具体的に商品としてご提案できる機会は数年に一度しかありません。 もちろんベビーからコツコツと育て上げていくのも一興ですが、 オス単品で入手しても後が大変と初めから諦めムードが漂っているのも事実で、 あと一歩で繁殖が目指せる年齢の若いペアは非常に前向きになれる最高の掘り出しものです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ベビー) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| ハイコントラストな甲羅が美しいセレクト個体! 別名ロシアリクガメ、ヨツユビリクガメとも呼ばれています、 ホルスフィールドリクガメ・ベビーが入荷しました。 日本とは比較的気候の近いヨーロッパ周辺に棲息するチチュウカイリクガメの仲間で、 その飼育のしやすさや可愛らしい表情から人気の高いリクガメのひとつ。 中でも本種は扁平で丸っこい体型が独特でその甲羅の形からしばしばメロンパンのようだと形容されますが、 今回の個体は暗色部分はより黒く、明色部分はより白く、 甲羅の色のコントラストがとても明瞭でまさにチョコチップメロンパンです。 柄もチップのように細かく分かれており不思議な美しさです。 サイズ的にはもっと小さなベビーも出回ることがありますがひとまず5cmを越えており、 シェルターの中で寝ていることも多いですが餌を置くとおもむろに出てきてよく食べています。 まだ春らしくない寒さも残っていますがこれからの季節は飼育スタートにぴったり、 日々大きくなるリクガメの姿をお楽しみ下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (CBベビー) Testudo horsfieldii |




|
|
||||||||
| 近頃まとまった入荷が少なくなってきたホルスフィールドです。CB個体で元気一杯です。地中海リクガメTestudoの仲間は 瞳も黒目がちでとても可愛い顔をしていて飼い主を癒してくれます。真ん丸の甲羅でこの大きさではお饅頭を想像させ 思わせ食べたくなるほど、いとおしい個体達です。綺麗に育てるとメロンパンに変身します(笑) 餌は葉野菜と Mazuriリクガメフードを交互に与えており、匂いを嗅ぎつけケージの前まで走ってきます。背甲や腹甲の カラーバリエーションも豊富で好みの個体をお選び下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ベビー) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| パンと言うよりもむしろクッキーのような愛らしさが際立つ一番欲しくなるベビーサイズ! 店内で暫しストックしていたら新しい成長線も伸び始めた安定感抜群のプチ飼い込み、 ホルスフィールドリクガメが入荷しました。 ロシアリクガメ、ヨツユビリクガメとまるで検索用ワードのように羅列したくなってしまう、 多様なネーミングで呼ばれる昔ながらのビギナーズトータス。 何故かねてより初心者向けと言われ続けているのかを考えると、 まずひとつは価格帯がリーズナブルであったことが大きく寄与していると思われ、 それに加えて元来強健な体質の持ち主であることも我々にとっては好都合でしか無く、 単なる育て易さに加え冬季を屋外にて過ごすことが可能な性能の高さもまた、 幅広い飼育者層を獲得する要因になっているものと思われます。 最近では近縁のヘルマンなどが台頭して来ていることもあり、 皆が皆本種ばかりを選ぶ訳では無くなってしまいましたが、 それでも長い方だと二十年から四十年ほどの飼育歴が現在進行形で今もなお続いているケースも聞かれるなど、 将来的にもまだまだリクガメ人気を底辺で支え続ける大切な役割を果たしてくれると思います。 今回やって来たのは未だに珍しい印象のある平常よりも一回りほど小さなベビーで、 現地で養殖されているのか極めてCBチックな心も体もピカピカの二匹。 和名のヨツユビが示す通り四肢の爪が全て四本に統一されており、 これはカメ全体を見渡しても珍しい特徴のひとつで、 本種が分類上特異な形質を有していることを意味しているのか、 よく言われる扁平な甲羅も大地に潜るために独自の進化を遂げた結果であり、 顔の形も鼻先や顎の辺りが角ばっていて、 もちろん好みは色々あるのでしょうが他のリクガメには無い可愛らしさが描かれています。 バリエーションを出すために黒斑が薄く甲羅が赤味がかったオレンジタイプと、 くっきりはっきりとした斑紋にレモン色が爽やかなイエロータイプの二系統をご用意しました。 入荷当初は葉野菜ばかりでしたが今ではMazuriリクガメフードにもしっかりと餌付き、 安心して飼育を始められる準備を整えてお待ちしております。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ベビー) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 今年も可愛いリクガメの季節がやってきました。人気の地中海リクガメの仲間の1つ、 ロシアことホルスフィールドリクガメの入荷です。昔はワイルド個体ばかりが来ていましたが 最近では現地で繁殖されているのでしょうか、 ピカピカで可愛らしいサイズが目立つ様になりました。 リクガメとしては大きくなり過ぎず、 また何と言っても一番の魅力は丸っこくて優しい顔付きです。 手を伸ばして落ち着いている姿などを見ると 特に女性はついキュンとしてしまうのではないでしょうか。 とても丈夫で寒さへの耐性も高く、大きくなれば室内無加温飼育は楽々、地域によっては屋外越冬も不可能ではありません。 葉野菜やMazuriリクガメフードなど何でも選り好みなく食べ、バスキングライトの下で日光浴をしたり、 日陰でお昼寝したりとよく動き回っています。小さなリクガメは急な寒さに弱い一面もありますから、 飼育開始には今のこの季節がベストです。初めての方には飼育法も一通りお教え致しますので 気になった方は一度お問い合わせ下さい。 2匹セットの場合にはお得な割引もあります。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ベビー) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 健康が甲羅を背負って歩いているかのようなビギナーさんにも強烈にお勧めの無敵ベビー! 餌食い以前にまず歩行時の首の伸ばし方が尋常では無い誰がどう見ても元気有り余る安心サイズ、 ホルスフィールドリクガメが入荷しました。 一体全体何処のどなたが仰ったのか今となっては迷宮入りの話なのですが、 どうやら世界各地に棲息する野生のリクガメの中で最も飼い易い種類のひとつであるらしい、 ロシアリクガメやヨツユビリクガメとも呼ばれているこのホルスフィールドは、 かつてリクガメをペットとして扱うべきでは無いと専門家が警鐘を鳴らしていた時代より、 そんな忠告を真っ向から否定するかのようにそれなりに飼えていた方も大変に多かったと思われる、 今も昔も全ての人が初心者向けと信じて疑わない素晴らしき逸材のひとつです。 結局のところ落ちは何だと問われれば現地の環境が厳し過ぎることがその答えであり、 その類稀な対応力の高さが人工飼育下においても如何無く発揮されるために、 多くの人がペットとして彼らと付き合い共に幸せな暮らしを送ることができていたのでした。 しかしながらいくら相手が強健で頑丈だからと言って、 長年に渡りややズレた扱い方をし続けていても良い訳では無く、 適応するための幅が広かろうが狭かろうがどのような性質の持ち主であっても、 やはりど真ん中にピントを合わせて育ててあげるのがマナーでは無いかと思います。 いくら簡単に育てられると評価されていたとしても決して油断すること無く、 いつ何時でも最高のおもてなしができればお互いに気持ちが良いと言うものです。 今回やって来たのはそれにしても初期状態が過剰なまでに整ってしまった、 カメ本来の性能が限界を超えた水準で発揮されているような、 何でもバクバク食べていくらでもブリブリ出しているフレッシュなベビーたち。 仮に人の手によってこの世に生を受けたとしても、 さすがにここまで大きくなる過程では現地の自然に近い状態で過ごしていたのでしょうが、 とても野生が育てたとは信じ難いツヤピカのボディが魅せるみずみずしさが全てを物語る、 普通に扱っていればまず大丈夫と声を大にして言いたい抜群のコンディションです。 カラーパターンはイエローとオレンジの二系統をセレクト、 二匹を同居させていますがどちらも状態に差はありませんのでお好みでお選び下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (S) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| ワイルドベビーで入荷したはずが随分と体付きがしっかりしてきた店頭ストックの三色団子! こんなにちっぽけな大きさでもきちんと個体差のあるカメですから是非ともお好きなものを、 ホルスフィールドリクガメが入荷しました。 いわゆるビギナーズトータスの御三家として名高いギリシャ、ヘルマン、ホルスフィールドの中で、 最も歴史が長くその分お世話になった人も多いのではないかと思われる本種は、 別名ロシアリクガメとも呼ばれていますが正式には現在のロシアに分布していないため、 最近では和名をヨツユビと改める資料が増えているように感じます。 良くも悪くも安価に流通することで敷居が低くなるのは確かですが、 実のところは野生個体の流通が大半を占めている都合上、 グループ内でも一番状態について気を遣わなければならない種類でもあります。 輸入されたばかりの段階ではよく歩き回って元気そうに見えても、 実際には体重が軽かったり餌食いが細かったりするケースもままあり、 初めての方が外見から全てを察することは事実上不可能ですから、 何よりも優先すべきは如何に良いスタートダッシュを切れるきちんとした個体を選ぶことでしょう。 いくら丈夫な種とはいえ初期状態が悪ければお話になりませんので、 初心者向けと言われるものだからこそお店側としては余計慎重になる訳です。 今回ご紹介するのは当店にやって来てから少なくとも一ヶ月以上は面倒を見て、 Mazuriリクガメフードにもしっかりと餌付いたのを確認してから毎日食べるだけ与え続けた結果、 少々やり過ぎなぐらい成長線がグイグイ伸びてきた健康優良児たち。 冒頭でも触れた通り当初は可愛いベビーとして売り出す予定だったのですが、 どうしても食いムラが出てしまうためしぶとくケアを続けていたら、 知らぬ間に大きくなっていたという落ちです。 よく見ると明るいレモンイエロー系、 ほんのり温かなオレンジ系、 背中の黒斑が濃厚なチョコチップ増量系など、 ただのホルスでは面白くないので一応カラフルになるようにセレクトしてみました。 フラットな体型は好みの分かれる所ですが、 将来的には屋外越冬も可能である点などは強みになると思います。 安価なカメだからと侮ることなかれ、 くたびれやしないかと心配になるほどせっせと歩き回り、 穴掘りも大好きでこれまたせっせと床材を耕してくれる活発な個体ばかりです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ
Testudo horsfieldii |



|
|
||||||||
| 最近すっかり姿を見せなくなってしまったロシアリクガメです。餌食いバッチリですので、 今回のロシアはあたりです。そろそろ保護されるんじゃないかな、 と感じている方も多いと思います。お急ぎ下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (国内CB・S) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| いそうでいない国内ブリードの兄弟から目ざとくセレクトしたイエローアンドブラックの二匹! 元々が入手し易い種類なだけに日本生まれだと知った途端ブリーダーの胸に秘められた愛情が感じられる、 ホルスフィールドリクガメが入荷しました。 ロシア、ヨツユビ、ホルスフィールド、三つ並べると合言葉か何かのようにも聞こえますが、 実はこれらの単語は全てある一種のリクガメを指す名前であり、 何を隠そうここに披露したこのカメこそがその正体です。 やはり長年に渡ってカメに馴染みがある方にとってはロシア、 外観の特徴から正しい和名を与えてあげようと思えばヨツユビ、 こじゃれた感じで学名をカタカナに直したものがホルスフィールドと、 それぞれがそう呼ばれるのに背景があって面白いです。 今回やって来たのはリーズナブルな価格帯であるが故なのか、 飼育されている頭数はかなり多いはずであるにもかかわらず、 なかなかその実例をお目にかかることは珍しい国内ブリードのホルスたち。 複数の群れの中からご覧の通り全身に黄色味が強く発色したものと、 反対にかなり黒味が強いものをそれぞれ選抜して掲載しました。 Mazuriリクガメフードをよく食べ良好な育ちぶりで、 非常に綺麗なフォルムに仕上がっている健康なベビーたちです。 (データの移行ミスにより原文が失われたため、短文にて復元しました) | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (M) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 表面をほんのり焼いたトーストのようにふんわりもちもちな雰囲気が可愛らしい色薄セレクト! 至ってノーマルな様子に見えますが実はここまで綺麗に育った飼い込み個体も珍しい、 ホルスフィールドリクガメが入荷しました。 ビギナー向けペットトータスの御三家として知られるギリシャ、ヘルマン、 ホルスフィールドの中で最も流通の歴史が古いのではないかと思われる本種は、 その当時から揺るぎないポジションを守り続け今日に至ります。 懐かしのニックネームであるあんパン、 メロンパンは現代でも十分通用する大変に愛のこもった呼称であり、 今更言うまでもありませんがこのカメの潰れたように扁平な甲羅を指したものです。 手に入れるのが容易い価格帯を維持しているだけに敷居が低い反面、 あまりの丈夫さ故に粗雑に扱われることも少なくはないようで、 これだけ普及している割には国内繁殖例も決して多い方ではありませんし、 最悪飼い方が分からずとも生き延びてしまう所は良し悪しなのでしょう。 リクガメのくせにあまりこんもりしていないと揶揄されることもありますが、 小さな体に不釣り合いのパンパンに鍛えられた四肢はいつまでも幼児体型のようで、 ギリシャなどとは微妙に違うちょっと惚けた表情がチャーミングな、 大きくなっても愛嬌を忘れない本当にペット向きなリクガメだと思います。 今回やって来たのは背中のカラーリングがかなり淡色寄りの、 いつも見かけるイメージよりも幾分上品な感じのするベビーから育てられた安心サイズ。 この段階のロシアリクガメにありがちなトラブルとして、 せっかくのパンみたいな体付きが台無しになってしまうほど早々にボコ付いていたり、 特に肩と呼ばれる両側の第一肋甲板が妙に盛り上がったりしがちなのですが、 横から見ると低い弾道で放物線を描いたように滑らかなカーブが露わになり、 甲羅表面の艶が示す通り並々ならぬ愛情が注がれていたことは一目見ただけで分かります。 前肢、後肢共にバランス良く筋肉がついた健康そのものの外観に、 葉野菜からリクガメフードまで選り好み無く爆食されればもう何も言うことはありません。 イエローとブラウンの眩しい配色は決して安価な種類とは侮れない高級感を醸していて、 育ちの良さと共に明るい未来を期待させて止まないのです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (S) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 全身アイボリーになりそうな眩しい個体です! ちょっと涼しくなってきましたがこのサイズなら安心、 リクガメ入門種としても人気の高いホルスフィールドリクガメが入荷しました。 別名ロシアリクガメとも呼ばれていますが現在のロシアには分布しておらず、 主に中東に分布しているチチュウカイリクガメの仲間です。 この属には他にもギリシャやヘルマンなど愛すべき人気種がひしめいていますが、 ホルスは他と違いメロンパンのようにモコモコとしてつぶれた甲羅が印象的。 また穴掘りホルスと呼びたくなるぐらい地中に潜るのが大好きで、 幼い頃から太く大きいシャベルのような前肢を持つのも大きな特徴です。 今回はベビーサイズから飼い込まれ成長の始まった個体がやってきましたが、 現時点で初甲板から殆ど黒斑が現れずに成長線が出ています。 今はまだ黒の割合が多いのですがこれは今後の成長でどうなっていくかが非常に見物です。 性格も明るく体質も丈夫でこれからリクガメ飼育を始めるビギナーの方にも強くお勧めできる種類です。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ブラック・♂) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| どれだけゲームを進めてもすぐさま白が黒に裏返されてしまう圧勝ムードの一局! 伸びた成長線が次々と黒く染め上げられていく恐怖のブラックタイプです、 ホルスフィールドリクガメ・オスが入荷しました。 ロシアガメ、メロンパン、アンパン、 もはや生き物なのかどうかすらも怪しい多様な呼び名で長年親しまれてきた最も庶民的なリクガメの代表種。 よく考えればすぐに気が付くことだったはずなのですが、 実際はロシアに分布していないという夢を壊すような残念なお知らせもありながら、 学名をそのまま読んだホルスフィールドの他に、 前肢の爪が四本しかないことを特徴付けたヨツユビリクガメという和名も使われています。 ギリシャやヘルマンなどと共にチチュウカイリクガメの仲間として分類されていたのも、 最近ではホルスを独立した一属一種にする動きも出てきているようで、 今まで多少なりとも滲み出ていた違和感がこれにてようやくすっきりするかもしれません。 厚みのある顔は四角くて寸詰まり、甲羅は天辺が潰れていながらそれなりにがっしりとしていて、 穴を掘りたくて仕方がないご様子の両腕は太く筋肉質、 そういった細部の特徴を洗い出していくと一見普通に見えても如何に変わったカメであるかということが分かります。 しかし流通量が多く入手困難になりそうな気配も殆どないためかそこに有難味は感じられず、 これほど潤沢に出回っているにもかかわらず国内繁殖例はさほど多くありません。 余談ですがお隣の中国では本種が国家一級重点保護野生動物に指定されており、 ペットとして飼育するなどとんでもないという世界ですから、 それを聞くとますます大切にしなければという思いが募ります。 今回やって来たのは数少ないカラーバリエーションの中から選りすぐりの個体をピックアップし、 全身が妙に黒々としている面白い一匹をご紹介します。 各甲板の斑紋が限りなく薄く消失した状態は基亜種アフガンホルスにて実現していますが、 その反対にぶわっと余分に溢れ出した状態と出くわすことは仮に意識していたとしても稀。 興味深いのは成長した部分が一瞬明るくなったとしても、 暫くすると再び黒い波が押し寄せては色を塗り替えてしまうようで、 ほんの僅かの期間しか白に対して隙を与えません。 前から見ると頭部全体と足の鱗も同じく黒ずんでおり、 またお腹側を見ても別種かと思うほどに通常のタイプと明らかな差異が見られますから、 成熟したその時、黒い岩石のように重厚な雰囲気を醸し出してくれればそれはそれは格好良いと思います。 尻尾はどう見てもメスにしか捉えられませんが、ヘミペニスを露出したのでオス確定です。 葉野菜やフードを爆食し、体が温まるとケージ内を爆走するグッドコンディションにてお待ちしております。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ブラック・♂) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 全体が焼き上がる前に焦げ目を付け過ぎてしまった出来上がりが楽しみで仕方ないブラックホルス! 手の平に乗せただけで何となく重量感倍増しのカラーリングが素敵過ぎる一点もの、 ホルスフィールドリクガメ・オスが入荷しました。 丈夫で健康な体質と大きくなり過ぎない手頃なサイズ、 それに加えてプライス的にも大変お値打ちなことから長きに渡り親しまれる別名ロシアリクガメ。 よく調べてみると実はロシアという国には分布していないようなのですが、 ペットの世界ではもはや通り名として知らない人はいないほど広く認知され、 今更訂正する必要すら感じられないお馴染みの存在となっています。 時にリクガメを十年以上飼い続けている方からお話を伺うと、 ケヅメやホシガメなど大御所の名前が挙がる中でこのホルスも必ずと言って良いほど登場し、 しかしながら水槽やケージでぬくぬくと飼育されていると言うよりは、 お庭やベランダに放牧状態のまるで腐れ縁のような付き合い方をされているケースも少なくありません。 人間が手を掛け過ぎることが必ずしも良い訳ではなく、 それだけ気兼ねなく互いに暮らしていけることを証明しているのでしょうか、 あまりこちらの生活に干渉しないさり気なさも支持を集めるポイントなのかもしれません。 今回やって来たのは写真を見て頂ければあえて説明する必要も無いほど、 体中の黒色部分が広大な面積によって描き出された、 一言で表せば単純にかなり格好良い飼い込み安心サイズ。 どのような生き物でも同じなのでしょうが、 ど真ん中ストレートとその両極端の特徴を持つ個体は喜ばれることが多く、 本種の場合は地色が明るく全体的に白っぽく見えたり、 或いはその反対に黒っぽくダークにまとめられていたりすると、自ずと競争倍率が高くなるようです。 体感的には白よりも黒寄りの個体を探す方が難しいような気がするため、 これほど程度の良い出物に巡り会える機会はそうそうありません。 その色彩も然ることながら甲羅の自然なフォルムはとても飼育下で育ったとは思えぬ美しさで、 第一椎甲板が出っ張ったり椎甲板の一列全てが小さくなったり、 その他ホルスにありがちな成長不良は一切見受けられない極上品。 色良し形良し状態良しと文句の付け所が見当たりません、年に一度出るか出ないかの大変興味深い逸品です。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♂) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 夜空に浮ぶまんまるお月さまのような美カラー美フォルム! 本来のアイデンティティを見事にぶち壊した分厚過ぎる甲羅に脱帽です、 ホルスフィールドリクガメ・オスが入荷しました。 ビギナー向けリクガメトリオとして昨今大変な功績を挙げ続けている、 ヘルマン、ギリシャ、ホルスフィールドの三種。 どれも環境適応能力が高く日本の四季にも馴染みやすいことから、 これまでリクガメを扱ったことがない人にとっても安心、というのが人気を支える理由のひとつで、 俗にチチュウカイリクガメと呼ばれるのはこれらが属しているグループのことを指しています。 そこにマルギナータなども加えてTestudo属を構成していますが、 最近ではロシア、ヨツユビとも呼ばれる本種を新たに一属一種として分類し直す説も提唱されています。 その根拠を探ると遺伝子レベルの話になってしまいますが、 あくまでも我々の視点からアプローチしてみると、 比較的甲は偏平で特に前肢の太さが際立ちやすいという特徴を持っていることが分かります。 では何故このような似て非なる形質を備えているのでしょうか。 その答えは生活史にあり、 とにかく穴を掘ることが好きなようで現地でも砂や土に埋もれている所を発見されたりするケースが多く、 ホルスという名前の響きですらとても偶然とは思えません。 というのは冗談ですが、穴を掘りたいから体に無駄な厚みは持たせず、 鍛え上げられた前肢はシャベルのように太く逞しい、外見の至る所に機能美すら感じられます。 それらを踏まえて今回やって来たオスを観察してみましょう。 確かに両腕は作業機械の役割を十分に果たすことができそうですが、 先程の前振りを全て台無しにしてしまうぼっこり膨れた体付きは全くもって予想外の展開です。 今日までのプロフィールをおさらいしてみると、 どうやら手の平サイズから飼育下で大事に育てられてきた経緯があるようで、 ワイルドのようにツルツルの光沢を持ちながらワイルドらしからぬ栄養状態の良さをアピールするという、 一匹の中に相反する要素が見事共存しているのです。 しかもそれだけでは終わりません、明らかに黄色の占める面積が広い甲羅は表面の艶のお陰もあり、 普段美しさとは縁遠いこのカメを立派なスターへと変身させてくれました。 たった15cmそこそこかと思いきや実物を拝めば20cm近くにも感じてしまう驚異の豊満ボディ、 アフガンホルスも尻尾を巻いて逃げ出しそうなこの重戦車っぷりを、類稀なその美貌とともに堪能して下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo horsfieldii |




|
|
||||||||
| かつてはリクガメ入門種として多くの個体が出回ったものの、ここ最近ではあまり見かけなくなりました。 ロシアリクガメことホルスフィールド・メスの入荷です。 今回はよく見かけるベビーサイズから大切に飼い込まれ、性別が判定できるまでに育った安心サイズの個体です。 本種は飼育し易いとされる地中海リクガメの仲間で、関東以南では土や葉っぱに潜らせて屋外越冬もできる事から人気は高いです。 甲羅はノーマルな色彩なのですが、頭部のみがやけに黒くガングロで格好良いです。 餌は葉野菜からMazuriリクガメフードにも餌付いているので問題ありません。 庭に放しての飼育も楽しめますが、穴掘りがとても上手なので柵の取付け方に注意し脱走には用心して下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| ベビーサイズより育てられたロシアです。 お客様委託のホルスフィールドリクガメ・メスの入荷です。 大抵のリクガメは甲羅がこんもりとしているのに対し、ロシアは扁平でメロンパンの様な独特の体つきをしています。 野性下では砂に潜った姿が観察されているので、恐らく地面に潜る為にこういった形状の甲羅になったのだと思われます。 リクガメの仲間では珍しく耐寒性もあり、室内であれば無加温で楽々越冬できますし、寒冷地以外では年中屋外飼育も可能です。 甲羅の成長が歪な為、 今回は特価にてお出しします。餌もよく食べてよく歩き回っており健康には問題なさそうなので、 初めてリクガメを飼われる方にもお勧めです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 鼈甲仕上げの極上ホルス! 小さな頃から丹念に育て上げられた2匹です、 ホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 初心者にオススメと言われるカメ、ミズガメならニオイガメの仲間がよく挙げられますが、 リクガメであればチチュウカイリクガメの仲間が特にピックアップされているでしょうか。 本属にはギリシャやホルス、ヘルマンなど可愛らしい人気者が勢揃いで、 大きくなり過ぎず日本の気候にも馴染みやすいことからペットとして飼育するのに適していると言えるかもしれません。 本種は近年、Testudo属から独立し本種のみで新属を形成するとも言われ、 確かに改めて観察してみると所々ユニークな特徴が見つかります。 扁平な甲羅や頑丈で太い前肢などは穴を掘るのに適応しているとされ、 飼育下でも庭に放しておくとよく穴を掘ります。 そんなことも関係してかワイルドの大型個体は甲羅表面のすっかり磨耗したものばかりですが、 今回やってきたのはどちらもまさかの飴色調というこのカメでは有り得ることの無かった美個体。 カラーリングもオレンジ系とレモン系の2色で好みの個体をお選び頂けます。 感心なのは色艶ばかりではなく、 時折見られる嘴の伸び過ぎた様子は欠片もありませんし、 爪もしっかりとケアされていたようで長過ぎず綺麗に揃っています。 甲板一枚一枚には多少の歪みはあるものの、 それでも全体のフォルムはワイルド顔負けの理想型ですから文句をつける所がありません。 前飼育者の愛情が形となって現れた素晴らしいホルスです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| イエロー&ホワイトのツータイプ! 生まれたばかりと同じ姿の真ん丸メロンパン、 ホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 いわゆるビギナー種の御三家であるギリシャ、ヘルマン、ホルスのひとつで定番の見慣れた印象が強いですが、 単に地中海のグループとして括ってしまうのは勿体ない、意外と変わったリクガメかもしれません。 パッと見た顔付きや甲羅の雰囲気は前述の2種に近い所もありますが、 よく観察してみると四肢の肉付きはそれらよりも幾分発達していて、 全体の形状も潰れ気味のちょっぴりぶさいくな格好をしています。 このスタイルは何を意味しているかと言えば、 つまりはこのカメがよく穴を掘りとにかく地面に潜りたいがための機能美、としても捉えることができると思います。 実際に育ちきったワイルド個体を見かける機会があれば甲羅の表面に着目してみて下さい、 継ぎ目さえも怪しいほどに激しく擦れた様子がお分かり頂けるでしょう。 しかし昔は流通していた大型個体も現在ではCITESの関係もあってか殆ど姿を消してしまい、 ほぼ全てがベビーサイズばかりになってしまいました。 今回はそんなベビーからしっかり飼い込まれた2匹のメスで、 奇遇なことに黄色味が強く出たタイプと、 それとは全く正反対の黄色味がすっかり消え失せ白っぽくなったタイプのお目見えです。 どちらも甲羅の凹凸はかなり抑えられ、本種ではしばしば見られる嘴と爪が極端に伸び過ぎた様子もなく、 このサイズまで丁寧に育てられたことが伝わってきます。 リクガメは小さな頃から飼い始めたいというケースが圧倒的に多いですが、 この辺りの種類に限ってはいきなり越冬にチャレンジできるというメリットもありますので、 それぞれの飼育スタイルで末永くお楽しみ下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| たしかに昔はこんなイメージのカメでしたが改めて見るとすごい迫力です。 欲張りな厚みがまるで別種のような長期飼い込み個体、 ホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 まず一言目には小型種、という謳い文句で販売されていることの多いこのカメも、 しっかり成長してしまえば実寸以上のボリュームを感じさせてくれるということがこの個体を見れば分かるでしょう。 まだ輸入され始めた初期の頃はワイルドの育ちきったサイズでやってくることがありましたが、 最近ではもっぱらピカピカのベビーサイズが中心になってきていますから、 これクラスの個体を知らなかった、見たことのなかった人にとっては衝撃的だと思います。 いわゆるビギナー種でも侮ることなかれ、 過剰に発酵して膨らみ過ぎたパンのようなはち切れんばかりの甲羅、 穴掘り上手が幸いした重厚で攻撃的な前肢、 そしてどちら様ですかと問いたくなるゴツい頭部は魅力を伝えるのに十分過ぎるでしょう。 多甲板はありませんが残念ながら甲ズレのような感じで甲板の配置にズレがあり、 それの影響か左後肢上面の甲羅がめくれ上がっています。 しかしながら片手で掴めばハンドボールを思い起こさせるこのフォルムはそうお目にかかれないと思います。 大きなサイズだからと言って繁殖目的に限らずとも目一杯楽しませてくれるお勧めの個体です。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 黒色と黄色のコントラストや各甲板の伸び率のバランスが極めて秀逸な教科書に載せたい一匹! パンはパンでも大きなチョコチップメロンパンより更に贅沢な厚みが嬉しい、 ホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 誰が呼んだか初心者向けの飼い易いリクガメとしてあまりにも有名な、 しかしながらカメ自体の紹介がそれだけで終わってしまいかねない危険すら孕んでいる、 確かにそう言われるだけあって頑強な体質が武器のいわゆるロシアリクガメ。 周囲から丈夫で飼育も容易と評価され続けた挙句、 実はリクガメの中でも風変わりな特徴を持つことについてあまり触れられないのが残念で、 例えばヨツユビリクガメの和名が示す四肢の爪が四本ずつしか無いことでさえ、 本当はかなり変わった形質だと言う事実も広く知られていないでしょう。 当店のホームページでは便宜上Testudoに分類してきましたが、 最近の研究によるとホルスのみで新属Agrionemysに独立させる向きが強いそうで、 よく見ると頭骨の形状から前肢の発達具合、 そして何より全体のフォルムからしてこれまで近縁とされていたチチュウカイリクガメの一派とは違う、 何処か異質な雰囲気を感じさせて止まないのです。 たまたま安価に大量の個体数が販売されていたため、 正直マニアックな視点で観察される機会のあまり設けられなかった種類ではありますが、 大型の飼い込み個体で優良なものを探そうと思うとなかなか巡り合えないのも、 ビギナーズトータスの殻を破り切れない要因なのかもしれません。 今回やって来たのは綺麗に伸びた背甲の造形が全体の厚みをより一層際立てる、 典型的、いやそれ以上に順風満帆な暮らしぶりが窺える絶妙な仕上がりの見事なアダルトサイズ。 椎甲板の一列がやたらと小さくまとまってしまったり、肋甲板の膨らみが足りなかったり、 四肢の筋肉が落ちてしっかりと立てなかったり、 嘴や爪が伸び過ぎていたりとしっかり育て上げるのは意外に難しいのですが、 この個体は全身を隈なく調べても欠点らしい欠点が殆ど見当たらない、 一見普通に思えてこの普通こそが本来あるべき野生の姿だと改めて感心させられる、 それに変な話、繁殖のことなど全く考えていなくとも観賞価値の高さで十分に存在感のある、 なかなかお目にかかれないグレードの高い逸品です。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (アダルト・♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| テリの強いなめらかな甲羅がセクシー! 即戦力になりそうな有難いサイズです、 ホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 いまリクガメの仲間で一番ホットなのがチチュウカイリクガメの仲間ですが、 その代表格とも言えるギリシャやヘルマンに比べてやや異なった雰囲気を醸しているのがこのホルス。 近年の分類では本種のみ独立した属に分けるという説も出始めたらしく、 今まで心の底でかすかな疑問に感じていたことが解決しそうです。 扁平な甲羅と、 後肢に比べて発達した強靭な前肢は穴掘り活動のために特化した特徴で、 野生下で穴を掘りまくっているせいか大型個体の甲羅は殆どが擦れており、 改めてピカピカの甲羅を目にすると不思議な感じがします。 時折見かけるアフガンタイプでなければ屋外越冬も可能で丈夫な種ですが、 最もCB化が進んでいるヘルマンと比較すると流通量の多いわりに国内繁殖の点では少し寂しい気も。 リクガメは全種がCITES入りしており将来的な流通はどう変化するか分かりませんので、 もしこのメスが役に立てるのであれば是非ともブリーディングメンバーに加えて頂きたい、 独身のままでは勿体無い良く育った貴重なメスです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (ホワイト・♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| あらゆる角度から見ても過去最高級の美しさを誇る総合得点の極めて高い至極の逸品! 目をやるべきはその白さのみならず、 フォルムから筋肉の付き具合まで全てにおいてハイレベルな、 ホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 恐らくこの先何十年も変わること無くビギナー向けの一般種と呼ばれ続けるのであろう、 その殻を未だ破れないことについては些かの不満も募る中東エリアを代表するリクガメのひとつ。 しばしば乾燥系に括られるのは決して誤りではありませんが、 何も好き好んでそういった過酷な環境を選択している訳では無く、 そこに生まれてしまった運命を受け入れ仕方なく耐え忍んでいるのだと言う、 彼らの苦悩まで理解することができればもっと距離を縮めて付き合うことができると思います。 つまり強健すぎるが故に、 言い方は悪いですがあまり大事にされていなくとも何となく出来上がってしまうのが本種の恐ろしいところで、 何故か庭先で十年以上も暮らしているなんてエピソードが聞かれるのもこのロシアリクガメならでは。 そんな特異な環境に適応するための面白い形質はマニアックになればなるほど興味深く映り、 改めてコレクション的な付加価値さえも見出すことができるほどですが、 誰に見せても恥ずかしくない成長過程を遂げた個体が少な過ぎるために、 多くの人々は真の魅力に気付いていないのかもしれません。 全体的にスクエアな顔立ちは他のチチュウカイリクガメと微妙に異なり、 あんぱんやメロンパンと称される扁平な甲羅はシャベルのように発達した前肢と共に砂地へ身を潜めるための進化で、 見慣れた姿ながら目的意識の高さが窺える造形美に自然の逞しさを味わうことができるのです。 今回やって来たのはパーフェクトと言う言葉を用いるのに何の躊躇いも無い、 遠目で見ても体中から色気が滲み出ているのが感じられる長期飼い込み個体。 ふっくらとナチュラルに盛り上がったシルエット、 しっとりと肌艶良く表面に飴色の光沢が表れた甲羅、 美白と言う表現がとてもお似合いな全体に淡いカラーリング、 そして十分な運動量の証と言えるパンパンに発達した筋肉質な四肢など、 どう考えても大切にされていなかったはずが無い素晴らしさが盛り沢山。 大きいからと種親用にだなんて用途を決め付けることに強い抵抗を覚える、 理想的な成長過程を絵に描いたような最良の掘り出し物です。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (Pr) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| リアルメロンパン! 以前からまるいまるいとは聞いていましたがここまで円いとは正直驚きです、 飼い込みのホルスフィールドリクガメ・ペアが入荷しました。 チチュウカイリクガメの仲間でも一際異彩を放つこのリクガメ。 いまいち呼び名が安定しない感じもしますが、ロシアリクガメやヨツユビリクガメとも呼ばれています。 残念なことにロシアには分布していないそうなので、 最近では学名読みでホルス、和名ではヨツユビと呼ばれることが多いかもしれません。 近縁のギリシャやヘルマンには前肢の爪が5本あることや、 甲羅もいくらか扁平な形状になっているなど違いがいくつかあり、 最近では本種のみで新属を構成するという意見もあるようです。 甲長と甲幅の差が1cmにも満たずほぼ円形で、チョコチップを散りばめて焼き色を付けたような黒斑もあり、 足を出して動き出すまでは本当にメロンパンがそこにあるような気さえしてきます。 CB個体がやや少ないというのもありヘルマンなどに比べると少し扱いにくいイメージもあるかもしれませんが、 この2匹は飼い込まれていたお陰かお腹を持ち上げて実に軽やかなウォーキングを見せています。 将来的には年中屋外飼育というのも良いと思います、じっくり育てて繁殖も目指して下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (フルアダルト・Pr) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 顔面から放たれる壮大な迫力に成熟度が滲み出た繁殖実績もある超即戦力アダルトペア! かつては一般種と呼ばれていましたが着実に流通量を減らしており早急な国内CB化が望まれる、 ホルスフィールドリクガメ・ペアが入荷しました。 アンパンやメロンパンなど喜んで良いのか悪いのか分からない愛称でお馴染みの、 そしてなおかつホルスやロシア、 ヨツユビと様々なネーミングで呼ばれているビギナー向けのリクガメとして有名な昔ながらの人気者。 とは言えその扁平なシルエットは好みの分かれるところであり、 パンケーキほどではありませんが決してこんもりとはしていない点や、 顔立ちがかなり年寄り臭いこともあって可愛いかどうかさえ人にもよる、 しかしながらリクガメ全体を見渡してもかなり面白いキャラクターであることは間違いありません。 多くの場合長所として挙げられるのは最大サイズのコンパクトさと、 類稀なる頑強な体質により通年屋外飼育が可能なそのスペックであり、 変な意味ではありませんが気楽に付き合えるペットトータスの選択肢として、 業界内では長きに渡りその実力を如何無く発揮して来ました。 昔はいつでもどこでも手に入る当たり前の存在だったものが、 このようなご時世ですからじわじわと見かける機会も減りつつあって、 当たり前のものを当たり前のままにしておく難しさを感じると共に、 何処かで誰かが細々とでもブリーディングを営んで下されば喜ばしいと思う次第です。 今回やって来たのはあくまでも趣味で淡々と育てられていたらしい、 それにしても長い間きちんと良好なコンディションを維持しながら、 念願の繁殖にも過去に一度成功していると言う嬉しいオプション付きのペア。 オスは甲高なフォルムに前肢もパンパンに鍛え抜かれた様子で、 頭部全体がガッチリと仕上がっていて鼻先などは持ち上がりそうな勢いがあり、 なりふり構わず交尾を仕掛けまくるガッツ溢れる仕草が容易に想像できます。 対するメスは決して大柄ではありませんがこれでもしっかりと産卵しており、 何よりも実際にベビーが誕生した有精卵を産んだ事実には大いに付加価値が感じられるでしょう。 オスはメスと空間を共にしただけで喜び勇んでヘッドボビングを繰り返すほど仕上がっており、 これからの暖かい季節は是非とも野外でのびのびと暮らして欲しいと思いますし、 今後ますますの活躍が期待できそうな将来有望のペアです。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (Pr) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
|
アダルトホルスの大行進!
小型種にもかかわらず地響きがこだますほど迫力の眺めです、
ワイルド長期飼い込みのホルスフィールドリクガメ・ペアが入荷しました。
ヘルマン、ギリシャ、ホルスと名を連ねればリクガメ入門種の御三家ができあがりますが、
今日に限ってはそんなことを言っている場合ではありません。
昔からアンパンやメロンパンなどと美味しそうな愛称で親しまれる庶民派は、
近年リクガメ全般の個体数が減少していることから流通に制限がかかり以前の身近な印象から一転、
すっかり影を潜めてしまいました。
毎年どこかでベビーが繁殖され出回っているのは確かですが、
それでも懐かしい記憶とのズレが生じてしまうことは避けられません。
今や長年お世話になったチチュウカイリクガメ属から独立する動きすら見られる本種、
それはつぶれた甲羅や野太い四肢といった独自の個性が認められた証とも言えるでしょう。
この特徴にはとにかく穴を掘りたいというメッセージが込められており、
そのため野生個体と繁殖個体では最終的なイメージに差異が生じてしまいます。
つまり、1cmでも1mでも長く穴を掘った個体とそうでない個体では、甲羅表面や長い爪の適度な磨耗、
更に追求すれば前肢の肉付きにまでその一匹が辿ってきた経緯が露になるのです。
CBとして販売されているものを野外で放っておく人はあまりいないと思いますので、
懐古主義のようになってしまいますが河原の石のようにツルツルの甲羅を持つホルスにロマンを抱いてしまうのも無理はないでしょう。
今回やって来たのは通年屋外で飼育が続けられていた2ペア。
当店に到着したのは昨年末、越冬を中断しての放出だったためしばらく様子を見ていましたが、
すっかり目が覚めている様子で目立ったトラブルはありませんでした。
気になる点と言えばオスの発情、
狭い水槽内での常時同居がシビアに感じられるほど積極的で子孫繁栄への意欲がひしひしと伝わってきます。
小さな体に筋骨隆々な様が味わえるリクガメも珍しいです、
クーリングの済んだ即戦力の状態でお待ちしております。
オスA・ オスB メスA・ メスB | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (アダルト・Pr) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| こんなとんでもないサイズのホルスを見た事があるでしょうか。バカでかい大きさのロシアリクガメ・ペアの入荷です。 コロコロと可愛いベビーサイズはリクガメ入門種として出回るものの、その後の成長した大型個体というのは意外と見かけないものです。 今回は特にメスがド迫力の大きさで、甲羅の質感などまるで石膏細工の様な滑らかさです。 2ペア来ましたがとりあえず白っぽいオスと メス、 黒っぽいオスと メスでペアを組んでみました。 もう少し暖かくなったら庭に放して年中屋外飼育にしてしまうと楽しいでしょう。 メスの産卵数にとても期待が持てるペアなので是非繁殖にチャレンジして下さい。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (Pr・♀) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
|
夏の陽気にはしゃぐ3匹のロシア!
どれも長期飼い込みの快調な個体ばかりです、ホルスフィールドリクガメが入荷しました。
近頃ではヨツユビリクガメの呼び名が主流となりつつあるでしょうか。
以前はロシアリクガメの名が使われていましたが、実はこのカメ一切ロシアには分布していないそうです。
主に中東エリアに棲息しチチュウカイリクガメ属の仲間に分類されますが、
新たな研究結果によると本種のみで新属を形成するという説も。
何より他の仲間に比べてとにかく穴を掘るのが大好きなようで、
シャベルのように強く逞しい前肢や平らな甲羅を見ると、野生での暮らしぶりが頭に思い浮かびます。
昔は流通量が多くどこでも見かけるリクガメでしたが、
最近では輸入される機会が減ってきたばかりではなく、小型で屋外越冬も可能なほど丈夫であり、
何よりも可愛らしい風貌などその魅力が再認識され人気が高まってきているようです。
本日ご紹介するのは1ペアとメスがもう1匹。
オスはキュンキュンと甘ったるい声で鳴きまくりメスを追いかけ回す肉食系で、
メスもある程度育ったサイズで受容的なので今後に期待が高まります。
もう1匹のメスは状態など全く問題ないのですが、
残念なことにマリリン・モンローよろしく背甲の後縁部がめくれ上がっています。
体格や体重などはむしろペアのメスより優秀なぐらいなのですが、一応B品扱いにて。
3匹まとめての場合は更にお値打ち価格をご案内しますのでお問い合わせお待ちしております。
ペア: 背甲・ 腹甲・ 尾 メス: 背甲・ 腹甲・ 尾 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (フルアダルト・Pr) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| もはや躍動感の塊でしかないエネルギッシュにも程があるフルサイズの二匹による最強のコンビ! 屋内だろうが屋外だろうがお構いなしに健康で暮らしてくれる繁殖まで果敢に挑みたい超即戦力、 ホルスフィールドリクガメ・ペアが入荷しました。 ペットとしてのカメには意外にも多くの選択肢、即ち種類の数や幅が物凄く沢山用意されており、 そのどれを選ぶかによって付き合い方が変わってくるというのはもちろんありますが、 その一方で全く同じ種類を選んだ人たちが全く同じモチベーションでカメと向き合っているのかと言うと、 実はそこに内在する物理的、精神的な距離感には多様な人間模様が見て取れます。 昔ながらの考え方で例えるのならばイヌを庭で飼うのか、 それとも人と同じ居住空間で飼うのかというシチュエーションに似ているでしょうか。 つまり屋外にいた場合は扉を開けてこちらから出迎えなければ目に付くことはありませんし、 反対に屋内にいた場合はもはや人間の家族に近しいイメージと言っても過言ではありませんから、 どちらが良いだとかそういった意味合いではなく、 同じ生き物を飼っていたとしても異なる役割を果たす可能性があると言うことです。 最近ではリクガメをひとりの家族として迎え入れられるケースが増えていますが、 それは今日の飼育方法や各種器材、 餌やサプリメントが充実した状態でこそ実現するものであって、 かつて自然の恵みを受けることが成功への秘訣だと考えられていた時代には、 本種のような春夏秋冬を野外で耐え得るものが好んで選ばれていたのを懐かしく思います。 放っておくと言うと悪く聞こえるかもしれませんが、 リクガメ自身が独立して生活することのできる環境をただ演出するだけという最低限の行為が、 ひょっとすると愛好家にとって極致とも言える美学のひとつなのかもしれません。 今回やって来たのは見るからに即行で繁殖にチャレンジできそうな、 サイズ的にも年齢的にも全てがベストタイミングな本当に即戦力と言える成熟を迎えたペア。 オスはオスらしく凛々しい顔立ちとツルンと綺麗なシルエットが好印象で、 メスはその豊満な体型も然ることながら、 カスタードクリームのように濃厚な甲羅のイエローが目に焼き付いて離れない美個体と、 それぞれがそれぞれの持ち味を以って我々にその魅力を訴えかけてきます。 今から準備すれば今年の冬から屋外越冬に間に合いそうな、最近あまり見かけない素敵な大型個体です。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (アフガニスタン産・ベビー) Testudo horsfieldii |





|
|
||||||||
| 実に久しぶり、5~6年振りぐらいでしょうか。アフガニスタン産のアフガンホルスの入荷です。 いつも見るホルスはカザフスタン産の各甲板に黒斑が入るタイプが多いですが、 アフガンは背甲に殆ど黒い部分が見られずクリーム色の綺麗なカラーリングになります。 またMAXサイズも一番大きくなり甲羅の厚みもトップクラスです (過去入荷個体参照)。 今回はファーミングの繁殖個体なのか、 実に可愛らしいサイズでピカピカなベビー達です。 初期状態も非常に良くこんな小さな体でも食欲旺盛な所がたくましいです。 探してもいない時には本当にいない、これを逃すと次に来るのはいつの事やらという種なので地中海リクガメに拘りをお持ちの方は”買い”です。 | ||||||||||
|
アフガンホルスフィールドリクガメ (ベビー) Testudo h. horsfieldii |





|
|
||||||||
| まだ幼いからと言う心配をよそにメキメキと状態を上げフードにまで餌付いたパワフルベビー! 流石にワイルドだとは思いますがまるでCBのように艶やかな質感が飼育欲をそそる、 アフガンホルスフィールドリクガメが入荷しました。 ホルスフィールド、時にロシアリクガメとも呼ばれる昔ながらのビギナーズトータスは、 今日の日本では改めてその名を挙げるまでも無いほど普及が進んでいますが、 実はいくらかの亜種を抱えそれぞれに形質差があることをご存知の方は少ないかもしれません。 私たちが最もよく見かけるのはカザフスタン亜種、 正式な和名にするとカザフスタンホルスフィールドリクガメと長ったらしくなってしまうため、 通常は省略されて呼ばれることが多く日頃意識する機会も与えられません。 その他の亜種については過去にもあまり流通した記録が無いようなのですが、 こと基亜種については数年に一度の単発的な輸入が確かに成されていたようで、 長いキャリアを持つ人ほど懐かしがる傾向にあります。 最も分かり易い特徴は各甲板の黒斑が消失しほぼ柄無しになる点で、 たったこれだけのことでも並のホルスとはまるで違った雰囲気になり、 実は最大サイズも一回り以上大きく完成された個体を目の当たりにすれば相当驚かされることでしょう。 何が凄いのかと言えば長さだけでは無く厚みも増してかなりの重量感になり、 顔立ちまで厳めしい表情へと仕上がるのですから育て甲斐が満載。 ある意味稀少種と言う見方もできないことはありませんが、 そうでなくともペットトータスの選択肢として長く親しまれるべき優れた性能の持ち主だと思います。 今回やって来たのは昨今あまり見かけられなくなったベビーサイズのアフガンホルス。 この手のリクガメを幼体で拝む機会は珍しくないように思えて、 ヘルマンやアカアシガメなどのようにコンスタントな繁殖が行われている訳ではないため、 そう言ったピカピカのベビーが何気なく店頭に並ぶような種類であれば別ですが、 こんなにフレッシュなオーラが発せられた状態で飼い始めることができるチャンスはなかなかありません。 葉野菜から野草、Mazuriリクガメフードまでメニューを問わずもりもりと平らげ、 店頭にて暫く育てている内にみるみる体重を増加させています。 マニアックだからと勝手に敷居を上げてしまうのはあまりに勿体無い、 一匹に拘って大切に付き合っていきたい方にもお勧めの珍種です。 | ||||||||||
|
アフガンホルスフィールドリクガメ (S) Testudo h. horsfieldii |





|
|
||||||||
| アフガンらしい独特の味がじわじわと見え始めてきた安心サイズ! 違いを楽しむ人の、アフガニスタンホルスフィールドリクガメが入荷しました。 私たちが普段よく目にしている、 ロシアやホルスと呼ばれているあのリクガメの正式名称はカザフスタンホルスフィールド、 実はいくつか分けられている亜種のひとつだったのです。 ギリシャやヘルマンと違い亜種関係についてはあまり言及される機会のない種類ですがそれもそのはず、 まともに見かけるのはカザフばかりなので自動的にそれを指してしまうことになります。 亜種がいるのなら当然基亜種もいることになり、 まさにその基亜種こそが今回ご紹介するこのアフガンホルスです。 一昔前に野生個体が流通していたこともあり非常に珍しいという訳でもありませんが、 存在自体があまりメジャーではないため知る人ぞ知るマニア好みのリクガメという絶妙なポジションを獲得。 その後、現地からの輸入は一切途絶えたと言っても過言ではありませんが、 最近では細々としかし確実に国内繁殖が続けられ、 こうしてなんとかコンスタントに姿を見かけることができるという大変有難い現状が維持されています。 普通のホルスとの大きな違いはパッと見た所では全体の色彩のように思えますが、 何よりも特徴的なのは圧倒的に恵まれた体格の良さ。 いわゆる地中海の仲間に共通する小型種という概念は全く通用しません、 カザフではアンパンだのメロンパンだの言われていた偏平な甲羅は、 アフガンの場合は成長に連れて醗酵が進み膨らみ過ぎたような厚みを備え、 それに伴い四肢の太さや顔全体の大きさなどもホルスの基準を楽々上回り、 もはや亜種関係とは思えない全く別物の姿へと完成していきます。 小さな頃に比較すればまだ共通点を見つけることは容易ですが、 完全に成熟してしまうとホルスの殻を破って新しい何かへと生まれ変わり、 見慣れていなければ種の判別すら危ぶまれる状態に。 今時では珍しく大きく育った様子があまり写真などの資料で公開されていないため、 成長後の姿は育て上げた人だけが実感できる特権のようなものです。 この極めて順調に成長を続けている2匹を仕上げ、 今まで未開拓だった新境地を体験して下さい。 | ||||||||||
|
アフガンホルスフィールドリクガメ (S・M) Testudo h. horsfieldii |





|
|
||||||||
| いざ来る時はまとまって来ますが中でも甲羅に張りがあり動きが機敏な選りすぐりをゲット! 毎度久々なことには変わりありませんがそろそろ胸騒ぎのする段階へと突入しつつある珍種、 アフガンホルスフィールドリクガメが入荷しました。 ロシア、ヨツユビ、ホルスフィールド、今も昔も相変わらず様々な名称で呼ばれ続けている、 リクガメ飼育の第一歩を踏み出すためのお供として長年重宝されてきたビギナー向けの代表種。 本来であれば相当に気を遣わなければならないイメージが先行するはずのリクガメにおいて、 元来備わった頑丈過ぎる体質によりその常識をことごとく覆して来た革命児は、 今でこそ他種の台頭に押されつつも未だポピュラーな存在として親しまれています。 とここまでは普段よく見かける並のホルスについてのお話、 本日ご紹介するのはメロンパンに例えるのならばチョコチップの付いていない方、 知る人ぞ知る基亜種アフガンホルスなのです。 無印のホルスはあえて表記される事例も少ないのですが亜種カザフスタンであることが殆どで、 分類上はあくまでも亜種関係に留まっているものの、 両者の違いは決してニシとヒガシのヘルマンのようなささやかなものではなく、 強いて言うのならインドとビルマのホシガメのような、 もはや別種として扱われるべきだと主張したくなる魅力が詰まっています。 最も顕著な相違点は何を隠そう最終的な大きさにあり、 せいぜい大人の拳ひとつかふたつ分にしかならない普通のホルスに比べて、 こちらアフガンは時に30センチに迫ろうかと言う巨漢を武器としており、 成熟した時の姿と言えば頭は大きく四肢も太くまるで別物と言った形相に仕上がります。 こればかりは実際に育てた方しか味わうことのできない特権なのですが、 ただの色違いだと決め付けてしまうのが大きな過ちであったことを、 完熟を迎えたその時に痛感して頂ければ幸いです。 今回やって来たのは待ちに待ってようやく久しぶりのお目見えとなった、 このまま姿を消してしまうには実に惜しい銘種のひとつに数えられるアフガンホルスの安心サイズ。 最近ではギリシャやヘルマン、それにマルギナータまで比較的安定した供給が成されているため、 この辺りでもう少し刺激を味わいたいと言う方にはぴったりの、 ちょっとマニアックな地中海としては面白い選択肢になると思います。 大きな個体は早くも特徴的な厚みのある甲羅が形成されつつあり、 非常に格好良いスタイリングが出来上がっています。 既にトリートメントも順調でMazuriリクガメフードにも餌付き始めており、 この気候を生かして万全な状態でお迎えしましょう。 | ||||||||||
|
アフガンホルスフィールドリクガメ (M) Testudo h. horsfieldii |





|
|
||||||||
| その一見ベーシックな名前に決して惑わされてはいけない今後の流通も危うい隠れた稀少種! 並のホルスとは全く別のカメとして捉えて頂きたい長さも厚みもワンランク上の存在感、 アフガンホルスフィールドリクガメが入荷しました。 ロシア、ヨツユビ、ホルスフィールド、やたらと和名に揺らぎのあるリクガメ界随一の入門種は、 我が国でも非常に古くから親しまれているビギナー向けのキャラクターですが、 その中には少しばかりのバリエーションがあることをご存知でしょうか。 真面目に亜種分けをすれば数種類を認知することができるものの、 実際に国内へ輸入されているのは亜種カザフスタンが割合のほぼ全てを占めており、 基亜種に当たるアフガンホルスは個人的には別種として独立させても良いのではないかと感じているほど、 並のホルスのことを思えばかなり特異な形質を持つ魅力的な種類です。 ご覧の通り甲羅全体が淡い明色に覆われると共に殆どの場合チョコチップのような暗色斑も消失し、 頭部は大きく幅広く発達し前肢の太さも体の大きさに合わせてより強調されたような、 一言で表すのならばよりダイナミックなシルエットが持ち味で、 完全に成熟したフルアダルトの姿を拝むことが難しいのは本当に口惜しいのですが、 一度それを目の当たりにすればその類稀な迫力に圧倒されること間違い無し。 普通に育てられたホルスをふたつ重ねたような天高く盛り上がる甲羅は格好良いことこの上なく、 顔立ちや四肢の逞しさからも巨人の風格が漂う素晴らしいリクガメに仕上がります。 この流れで察して頂きたいのですがコンスタントに養殖されているはずも無く、 何しろ分布域が思いっ切り訳ありなエリアですから散発的にしか出回らないため、 次のチャンスが全くお約束できない切なさの募る貴重な存在なのです。 今回やって来たのはちょうど手の平に収まるぐらいの安心サイズに育った飼い込み個体で、 野生の状態から飼育下に移された瞬間の違和感が甲羅の表面に全く表れていない、 絶妙な技の光る生育具合に大満足の一匹。 当店でも早速Mazuriリクガメフードに餌付き食べる量も半端では無く、 運動量から排泄量に至るまで日々の暮らしには何の不安もありません。 こればかりは何とも言い切れないのですが昔から品薄感の強い種でしたから、 この先いつでも手に入るリクガメだとお約束することは不可能なので、 手の届くところにいる内にきちんと確保しておいて下さい。 | ||||||||||
|
アフガンホルスフィールドリクガメ (♀) Testudo h. horsfieldii |





|
|
||||||||
| 遠い昔の遺産となりつつある現状を何とか食い止めなければならないもうひとつのホルスフィールド! 普段見慣れた彼らとは一味も二味も違った透き通る飴色の甲羅を持つことになるアイツです、 アフガンホルスフィールドリクガメ・メスが入荷しました。 ロシア、ヨツユビ、ホルスフィールド、 何とも語呂の良い言葉の並びはそのどれもが同じ種類のリクガメを呼んだものですが、 ビギナー向けのポピュラー種として大変に歴史のあるカメですから、 少しでも学んだ経験をお持ちの方ならばいずれかの呼称は聞き覚えがあることでしょう。 しかしながらあまりにも目にする機会が多いためかマニアックな雰囲気はさほど持ち合わせておらず、 そもそも本種にいくらかの亜種が存在することはあまり知られていないかもしれません。 気になって調べてみると一応は四亜種ほどに分けられるようなのですが、 ホビー的な観点では現実的に見分けることのできる基亜種とカザフスタンぐらいの認識だけでもよほど十分でしょう。 そう、かつて何かの拍子に時折見かけた茶褐色のボディに妙な体格の良さを持つあのタイプ、 それがこのアフガニスタンヨツユビリクガメなのです。 今回やって来たのはギリギリ流通していたはずの幼体すらも姿を消しつつあるこのご時世に現れた、 相方を探すのにはちょうど良い性別確定の手の平サイズ。 一体何処に消えてしまったのでしょう、 メロンパンのチョコチップだけをむしり取って食べてしまったようなあの輝かしいベビーたちは。 今となっては手に入れようと願ってもそんなチャンスすら巡って来ない立派な稀少種を、 何とか繁殖にまで漕ぎ着けて頂きたい一心でここへ掲載することにしました。 正直、甲羅の仕上がり過程としては上出来とは言い難いものの、 部分的に軟化した箇所などもちろん無く適切なペースで成長を続けていますので、 今後ケアの仕方を間違えなければ立派なメス親へと育っていくことでしょう。 店頭では同系統の他個体と同居させていますが、メスであるお陰か排他的な行動を見せたことは無く、 色々な種類のリクガメを飼育してみたいという方にとってもチャンスです。 いくらリクエストを頂戴しても次の機会は未定です、お見逃し無く。 | ||||||||||
|
ホルスフィールドリクガメ (アフガニスタン産・♀) Testudo horsfieldii |




|
|
||||||||
| まとまって入ったのは7~8年程前になるでしょうか。ホルスの中でも黒い斑が少なくクリーム色の背甲には驚かされました。 しかし今ではほとんど見られずすっかり貴重種になりました。アフガンホルスはなぜか大きくなる個体が多いようですが、 この個体は特に大きいです。最初見たとき、思わずケヅメかと思ったくらいです。今回お客様長期飼い込み個体で餌食いもよく、 500mlのペットボトルと肩を並べる大きさです。よく見るサイズでは扁平なカメという印象を受ける事が多い本種ですが、 さすがにこの大きさでは厚みも違います。 四肢は太く表面の鱗が発達しており、のしのしとケージ内を歩く姿は非常に迫力があります。 餌も飼い込みだけあって、葉野菜を中心にMazuriリクガメフードなどよく食べています。 嘴の伸びた部分がありますが、噛み合わせの異常はありません。いいオスをお持ちの方は是非どうぞ。 | ||||||||||
|
フチゾリリクガメ (サルデーニャ島産) Testudo marginata |





|
|
||||||||
| かつて学名ではサルダと呼ばれた第三のマルギナータとして一部では熱烈な需要を誇る稀少個体群! たとえ学術的に認められていなくとも産地が明確であるという事実が一周回って立派な付加価値となる、 サルデーニャ島産のフチゾリリクガメが入荷しました。 チチュウカイリクガメの仲間と言えばロシア、ギリシャ、 ヘルマンと都合良く御三家のようにして並べられていたのも今となっては懐かしく感じられますが、 その奥に四番目のチチュウカイとして恭しく鎮座していたのが、 今日では随分と馴染み深いキャラクターに変貌したこのマルギナータでした。 今でこそ私は普通のリクガメですと言わんばかりの表情を浮かべながらトコトコ歩いているかのヘルマンも、 十年以上も前にはビギナー向けと評されながら実は立派なプチレア種であり、 というのも昔から野生個体の保全に厳格であったヨーロッパ諸国では、 ワイルドの捕獲や輸出が非常に難しかったため、 まだまだ軌道に乗り切れていなかった繁殖個体が少しずつ流通し始めたばかりでしたから、 更に上位にいた本種などはもはや現物を拝むだけでも一苦労という崇高な存在だったのです。 今でこそヘルマンとマルギナータは外観こそ異なれど中身は同じだと、 そう断言しても差し支えないと考える人が圧倒的多数を占めていると思いますが、 昔は実際の飼育例に乏し過ぎて半ば都市伝説に近いエピソードがまことしやかに囁かれ、 よく覚えているのは寒さにはよく耐えるがその分暑さに弱く日本の猛暑は厳しいのではとか、 爽やかな風が流れる土地柄のため同じく梅雨の時季には衰弱してしまうのではとか、 結局そんな事実はなく知らず知らずのうちに全て忘れ去られてしまった程度でしたが、 そうやって誰もが簡単には飼育できないと噂することでカメ自体に凄みを与えるような、 容易くないというアピールが何故か高級感を演出するという不思議な文化があったような気がします。 最近では定番のヘルマンとは違ったもうひとつの選択肢として人気が再燃し、 新たなファン層を獲得するまでに至っているのです。 今回やって来たのは現地では離島への移入個体群とされるサルデーニャ島を由来とする血統の、 いわゆるサルディニアンマルギナータと呼ばれるタイプのベビー。 その風情としてはペロポネソスに近いものがあるでしょうか、 流通自体はかなり稀で目にする機会は圧倒的に少なく、 並のマルギに比べ最大サイズが小さく収まることや、 甲羅の前後が短くやや甲高気味に仕上がるのではなどと言われています。 お陰様で体も心も絶好調、 筋書き通りMazuriリクガメフードにもしっかりと餌付き、 初めての方でも安心して育てられるよう仕立ててあります。限定一匹のみ! | ||||||||||
|
フチゾリリクガメ (サルディニア島産・ベビー) Testudo marginata |





|
|
||||||||
| 先日のブログでも紹介しましたちょっと珍しいヨーロピアンです。 なんだか上品なイメージの強い隠れた人気種です、 マルギナータことフチゾリリクガメ・サルディニア島産が入荷しました。 ホルス・ギリシャ・ヘルマンと3種揃ってビギナーから玄人まで広く愛される私たちにとって大変身近なリクガメですが、 このグループにマルギも含まれていることを忘れてはいけません。 どうしても流通量の関係で目にする機会が少ないのですが、 気品のある顔立ちや 何と言っても強烈なインパクトを有するスカート状の甲羅はマニアでなくとも憧れてしまいます。 あまり知られていませんが本種も棲息地域により微妙な個体差があるようで、 この島の個体群はおおむね小型なのが特徴のようです。 どうやってか古い時代に本土より渡って来たのでしょうか、 少なからず独特の進化を遂げていることに変わりはなくとてもロマンに溢れていると思います。 今回入荷したロカリティ付き地中海リクガメ3種の中で一番活発に動いて餌もよく食べていたので本日UPしてみました。 ちょっとクセのある印象もありますが紫外線やスポットなど基本的な所を充実させてあげれば健康に大きくなってくれる事でしょう。 | ||||||||||
|
マルギナータリクガメ (ハイポメラニスティック?) Testudo marginata |




|
|
||||||||
| ケヅメリクガメと見間違う様な白さを持つ、ベビーサイズのマルギナータが入荷しました。 しかも貴重で嬉しい国内CBです。フラッシュをたかずに柔らかな光の下での撮影ですが、 やはり美しい白さです。餌も葉野菜をよく食べており、普段からケージ内をポコポコと歩き回ります。 腹甲の真ん中の縦に走る線の部分が若干膨らんでいますが、今から育てれば十分直る範囲です。 | ||||||||||
|
マルギナータリクガメ (国内CB S) Testudo marginata |




|
|
||||||||
| 委託主様のご意向により、価格を下げて再々度ご紹介です。これが最終価格です。 2006年国内CBマルギナータです。艶やかな容姿には理由があり、人工飼料は一切使わずに 野草のみで育てられたという、こだわりの個体です。自然の恩恵を一身に受けて、 すくすくと成長しています。性別は不明としましたが、現時点ではかなりオスっぽいです。 今後の成長でフチが反ってくるのを想像すると、今からわくわくします。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (EUCBベビー) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 肌色を通り越してクリーミーに仕立てられた透明度の高い体色が美しい二匹をセレクト! 幼体らしからぬ全体的にむちむちとした肉付きの良い体型が状態の良さを物語ります、 オオフチゾリリクガメが入荷しました。 古くからマルギナータの愛称で親しまれるチチュウカイリクガメの最終兵器は、 ここ数年でコンスタントなブリードが実現されたことにより敷居が低くなったものの、 未だにギリシャやヘルマンなどの一般種と横並びになることは考え難く、 不思議とある一定の品位を保ち続けているように感じます。 野生での分布が欧州に限られている本種は如何せん流通量に乏しくどちらかと言えばレアもの扱いで、 しかしながら日本でも国内CBが誕生するなど飼育から繁殖までの流れに余計な難しさは無いため、 以前よりビギナー向けにも広く浸透することが望まれていました。 属内最大種ともあり実際に飼い切ることのできる層は限られてしまうのでしょうが、 反対にある程度のボリュームや存在感を強く求める方や、 初めから通年に渡る屋外飼育を想定している方にとってはこの上ない逸材と言え、 元々選択の幅が狭いリクガメ社会において多大な影響を及ぼすことは間違いありません。 元来可愛らしさが売りのひとつとして考えられていたグループにいながら、 細長いスタイルが他とは一線を画すマルギは格好良さをも存分に追及しており、 熱烈な男性ファンを育ててきたことについては異彩を放っていると言えるでしょう。 今回やって来たのは昨年まで見かける機会がグッと増えたかと思いきや、 今年に入ってあまり姿を見なくなってしまったマルギナータの可愛過ぎるベビー。 しかも本種はベビーと言っても何故か6、7センチぐらいで販売されていることが多いのですが、 この二匹は思わず手を伸ばしたくなるベストサイズで、 複数匹いる中から際立って黒斑が少なく白味の強いものだけを選び抜きました。 小さいからと言って華奢な雰囲気は微塵も無く、 まだ柔らかい甲羅ながら指で押しても強く跳ね返るハリの強さと、 外界を恐れぬ好奇心旺盛な明るい性格でケージ内を激しく走り回る、 別段探していた訳では無かった方にさえも猛烈にお勧めしたい良品です。 時折見かける放出個体の育ち具合にいまいち満足できなかった方には、 綺麗に育てるための術を知り得る限り伝授したいと思いますので、お早めにお問い合わせ下さい。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (ベビー) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 一口サイズのお饅頭ぐらいの大きさながら足の速さと餌食いの良さがピカイチの最強ベビー軍団! 昔に比べて少し定番チックになったお陰でお気に入りが選べるようになった最も格好良いチチュウカイ、 オオフチゾリリクガメが入荷しました。 正しい和名に直してしまうと途端に堅苦しい雰囲気を帯びてしまいますが、 彼らの愛称は皆さんご存知のマルギナータ。 ラテン語の響きをそのまま和訳すれば縁があるというような意味になり、 甲羅の外縁部、特にリアフェンダーの部分が顕著に伸びることで知られています。 その特徴はまるでカブトムシみたいですが雌雄間において大きな差が見られ、 オスの方が二倍も三倍も長く伸びることになっており、 メスは見栄えがしないから残念なのかといえばそうでもなくて、 本種はベビーから育成すると大半がオスになることはもはや有名なエピソードとなっていますから、 何とも上手いことにどちらに転んでも美味しい仕組みが出来上がっています。 サイズ感としてはコンパクトであることが売りの本属にしては珍しく、 チチュウカイリクガメ最大の体躯を誇る彼らは二十センチをオーバーするスペックの持ち主で、 時に室内でぬくぬく育てる場合には重荷になる可能性もありながら、 反対に屋外をメインに据えた場合にはそのダイナミックな存在感がそのまま武器になり、 圧倒的なパワーで庭先を闊歩する姿を眺めるようなシーンにおいては、 ギリシャやヘルマンでは決して描くことの叶わなかった雄大な光景が広がるのです。 原産は東欧のどちらかと言えば寒さが厳しいエリアですから、 日本国内のさほど温暖な地域でなくとも通年屋外飼育が楽しめるのが強みで、 ビギナー向けの枠に含まれていないマニアックなキャラクター性もまた愛好家を喜ばせる要因となっています。 今回やって来たのは現地で養殖されたものと思われる手頃なサイズのベビー軍団より、 色柄にバリエーションを出しつつ初期状態にとことん拘ってセレクトした四匹。 パッと見似たようなデザインですがよく観察すると色彩の明暗や、 甲羅や頭部への模様の入り方にしれっと個体差が見受けられ、 将来像を思い浮かべながらお選び頂けるように取り揃えてみました。 狙い通り動きのキレが凄まじい上に餌に対する執着心も半端なく、 早くもMazuriリクガメフードオンリーで楽々育てられるように仕込まれています。 ここ最近ではコンスタントに見かけられるように感じられますが、 少し気を抜くと途端に姿を消してしまう恐れもあるため、複数から選べるこの機会に是非。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (ベビー) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| ただシンプルにマルギのベビーを探していた方へ手放しでお勧めしたいちょっと育った安心サイズ! 成長後にも美しい姿を保つのにはほんの少しコツが要りますがそれはお渡しの際のお楽しみに、 オオフチゾリリクガメが入荷しました。 殆ど目にしませんが一応ペロポネソスなる亜種が有効になっている都合上、 和名の表記はオオフチゾリとしましたが、現実的には単にフチゾリと呼んでしまうか、 学名をカタカナに直したマルギナータの方が圧倒的に通りが良い、 チチュウカイリクガメの最終兵器にも似たポジションで待ち構える珍種。 名前の由来は成長に連れて背中の後ろがビュンビュン伸びることで、 それがまるでスカートを穿いたような風変わりなシルエットに仕立てられるため、 ギリシャやヘルマンでは味わえなかった感動が込められていると思います。 その伸びが甲長にも影響するため余計にそう感じられるという説もありますが、 実際にグループ内では大型になる部類のため好みの分かれるところで、 いわゆる小型で飼い易いリクガメの枠からは残念ながら外れてしまうのかもしれません。 しかしながら寒さの厳しい東欧エリアに分布していることも手伝って、 そこに備わる耐寒性は群を抜いて高いとも考えられており、 野外で観察しても決して見失うことのないボリュームも含め、 お外のお供としては非常に優秀なスペックを発揮してくれます。 同じくヨーロッパ出身のヘルマンとは異なり、 計画的にブリードされている訳ではないため流通量はグンと減りますが、 その性能を知る人にとっては堪らないものがある隠れた人気種なのです。 今回やって来たのは極小のベビーサイズで輸入されてから数か月の間、 国内のとある有識者の下でストックされ順調な成長ぶりを見せているこんな一匹。 スモールサイズと言うにはまだまだ早いような気がしますが、 これをベビーとばっさり断言しては育てた方に対して失礼だと言いたくなるほど、 甲羅の硬さから広範囲に渡って歩き回る豊富な運動量、 そして葉野菜からMazuriリクガメフードまで選り好みなく爆食する餌食いの活発さまで、 あらゆる角度から見ても体中が安定感に包み込まれているようです。 椎甲板を矮小化させずに理想的な仕上がりを目指したい方に、 ちょっとしたポイントを押さえて誰もが羨む大型個体へと仕上げる方法をお教えします。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (CB・S) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| まるで焼きたてのパンのようにふっくらとそして艶やかに成長した初めての方にも安心のスモールサイズ! 右を見ても左を見てもヘルマンばかりに視界が遮られる中でこちらにも注目して頂きたいお隣の近縁種、 オオフチゾリリクガメが入荷しました。 今日の我が国では正式な和名として採用されているフチゾリリクガメという呼称、 それに対してむしろ学名由来のマルギナータリクガメの方が親しみ易いという意見も聞かれますが、 一方ではとあるピザやカクテルの名前と間違われがちというちょっとした小ネタも。 ちなみにその誤答はギリシャ語で真珠を意味する名称らしいのですが、 正解のマルギナータとは英語のマージンに相当する縁があるという意味を持ち、 成熟した個体の特にオスには顕著に現れる背甲後縁部が伸長する現象を指しています。 今やすっかり有名人となってしまったあのヘルマンとは兄弟のような間柄で、 分布域も重なるほどのご近所さんですから形態的にもかなり近しいものがあり、 育て方や付き合い方などはほぼ変わりないため同じくビギナー向けだと言えるでしょう。 ヘルマンとの差別化をしっかりと図りたい皆さんにとって重要なのは、 本種の方が最大サイズにして数センチほど大きく当然ながら体格もがっしりとしていて、 そのお陰で冬の寒さに対してもより高い耐性を持つのではという説もありますが、 それはさて置いてケージを飛び出し野外で歩き回るその勇姿にはかなりの迫力が味わえると評判です。 いつも私はその仕上がりをちょうどボックスティッシュに例えるのですが、 つまり立方体よりは直方体に近いシルエットで可愛らしさよりも格好良さの方が際立ち、 遠目で見た時に伝わってくる存在感の強さもヘルマンとは一味違う偉大さがあります。 何度も申し上げるようで恐縮ですが中身の性能はかのヘルマンと何ら変わりないため、 ヘルマンの素晴らしさを既にご存知の方はもちろん、 新たにリクガメの世界へ足を踏み入れようとお考えの方にもご紹介したい銘種のひとつです。 今回やって来たのは最近やたらと極小サイズのベビーを見かける機会が多かっただけに、 何だか久しぶりな感じのする甲羅全体もすっかりと硬くなり始めた安心サイズのマルギナータ。 こちらから解説するまでもなく明暗がはっきりと分かれた個性的な二匹で、 こればかりは完全に好みの問題ですが選べるということが重要であると念を押しておきます。 今はひとつのケージ内で仲良く同居生活を送っていますが、 どちらにも大きな差はなくMazuriリクガメフードオンリーで育てられるよう仕立ててあり、 入店して早速新しい成長線も伸び始めたどなたでも扱える優等生揃いです。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (S) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 小さなサイズでもどことなく気品が感じられるチチュウカイリクガメのプリンス! 今年に入って随分と入手しやすくなりました、オオフチゾリリクガメの入荷です。 小型で可愛らしい雰囲気が持ち味の本属において最大級の大きさを誇るマルギナータ。 名前の由来はアダルトサイズに見られる末広がりな甲羅のことで特にオスで顕著であり、 スカートを穿いた男性というのはスコットランドの民族衣装を思い起こさせます。 ギリシャやヘルマンが庶民的な雰囲気であるとすれば マルギはどちらかと言うと高貴な身分の風体を持ち、 これまでの流通量や価格帯からもそのようなイメージを保ち続けてきました。 中東には分布せず欧州にのみ棲息するためか見かける個体数は圧倒的に少なかったのですが、 今年は何故かまとまった数が入ったようで急激に手に入りやすくなっています。 今回やってきたのは成長線が二、三まわりほど出始めた安心サイズの個体で、 ブルジョアな雰囲気とともにどこかひ弱な印象も付きまとっていますが、 足取りと餌食いを見る限りこちらも大げさに身構える必要は無さそう。 体型は他の同属種に比べると早くも細長くなっており、 やはり同じ仲間の中でも一際存在感を放つキャラクター性に溢れたリクガメです。 単純にお求め安くなったことには寂しさも感じますが、 今まで憧れていた方にとっては最大のチャンスでしょう、お勧めの一匹です。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (EUCB・S) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 拳大になるまで生まれ故郷で育まれた自然なフォルムがますます魅力を惹き立てる安心サイズ! 他のチチュウカイとは一味異なるスマートな格好良さが滲み出てきたお年頃、 オオフチゾリリクガメが入荷しました。 フチゾリの名は今でこそすっかり浸透しているように思われるものの、 一昔前は専らマルギナータの愛称で親しまれていた本種は、 完全にレア種扱いだった過去も忘れ去られたかのように今では比較的目にする機会が増え、 ギリシャやヘルマンらに食い込むようにしてビギナー層にも喜んで選ばれ始めています。 チチュウカイリクガメの仲間が隆盛を極めた理由のひとつに、 大きくなり過ぎず風貌も可愛らしいと言う特徴が挙げられますが、 このマルギについてはそのような固定概念をぶち壊すかのように、 やや大柄の体躯にクールな表情が光る異端児とも呼べるようなポジションに居座ろうとしているのでしょうか。 ケージ内ではやや窮屈に感じるかもしれない立派な体格は屋外へ放牧されたその時にこそ真価を発揮し、 これらの仲間ではなかなか味わえなかったダイナミックな存在感に魅了される、 実に育て甲斐のあるリクガメであることがフルアダルトを目前にすることで思い知らされるのです。 今回やって来たのは都合良く手に入りそうでそうはいかないマルギナータのスモールサイズで、 一押しポイントとしては現地で育てられただけあり大変良好な成長過程を辿っていること。 世の中のマルギ好きを悩ませる重要事項、 それは何故か同グループの他種に比べて綺麗に育てることが難しいとされる点で、 各甲板が気を付けていてもボコついたり甲板の比率が均等に伸びないことも多く、 せっかく手塩にかけても大きくなるに連れて理想像から段々と逸れていくと言った話がしばしば聞かれます。 ですからこの二匹を見て最初にああ普通だなと感じたのですが、 その普通だと思える状態まで持って行くのが如何に難しいかをこの場で説明しておきたいのです。 特に注目したいのが椎甲板の伸び方で、 どうしてもこの縦一列が小さくなってしまう事例が後を絶たないのですが、 少なくとも現時点では絶品と言わざるを得ません。 原産はギリシャなど日本と緯度の近い地域なのでかなり寒い地域でも屋外越冬をこなすことのできる、 庭ガメとしての高いポテンシャルも秘めた有能な強健種です。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♂) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 持ち前の華麗さに磨きをかけた素敵な仕上がりを見せるミドルサイズ! 卵色にこんがりと焼けたカラーリングが一層上品です、 オオフチゾリリクガメ・オスが入荷しました。 ペットに最適なリクガメとしてすっかりその地位を築き上げたチチュウカイリクガメの仲間。 一時の過熱的なブームは落ち着き、 それぞれの種が持つ特徴をしっかり把握した上で飼育対象として選ばれるようになってきたように感じます。 ヘルマン、ギリシャ、ホルスフィールド、もう何度その名前を呼ばれたのかも分からないほど馴染み深い御三家ですが、 どういう訳かここにマルギナータという六文字はなかなか入って来ないのが現実です。 同じくヨーロッパに分布する種類であるはずが、 少々マニアックなポジションに収まってしまっているのは何故でしょうか。 前述の三種の中で、あとのふたつは野生個体の流通に恵まれていたこともあり見かける機会が多いのですが、 実はヨーロッパにのみ棲息するヘルマンは繁殖が軌道に乗るまで、 現在のように庶民的な感じは殆どなくやや高級な部類に入っていました。 そして本種はそのヘルマンを更に凌ぐレア度を誇り、 名前だけは知られていても実際に飼っている人に出会うのが珍しいぐらいでした。 あまり目にすることがないだけにその生態については色々な謂われがあり、高温に弱いらしい、多湿に弱いらしい、 神経質らしい、など中には噂の域を出ないものがあったのも事実で、 これらのことがマルギを謎のベールに包みこんでしまっていたのかもしれません。 今回やって来たのは手の平を卒業間近の安心サイズで、そろそろ大人の雰囲気も香り始める頃。 ツルンとまとまった全体のフォルムは申し分なく、 併せて色合いにもどこか格調高いムードを纏っています。 見た目のインスピレーションによる所が強いので明解な理由は分かりませんが、 明色部にはっきりと黄色が出ていることとその面積の広さがそう見せるのでしょう。 他種とは異なる切れ長の締まった表情を持つだけに、 元々持つエレガントな気質をよく引き出せていると思います。 飼育者の話を聞くと特別注意することはなく他のチチュウカイと同じ感覚で、 むしろ体格に恵まれている分より頑丈そうな印象さえ受けました。 もちろん耐寒性にも優れており地域によっては屋外越冬も十分可能です。 この先きちんと手をかけてやれば甲羅の後ろには立派な花が咲くことでしょう、 素養の高い個体を元に是非挑戦してみて下さい。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♂) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 野生で捕まえたようなシルエットに飼育下ならではの艶や光沢が見事にマッチした極上安心サイズ! 全体像を引き締める黒寄りの配色が凛々しい佇まいを演出しています、 オオフチゾリリクガメ・オスが入荷しました。 チチュウカイリクガメの仲間では最も大きくなるとされるかつての高級種も、 現在では主に欧州方面からの繁殖個体がコンスタントに供給されるようになり、 それまでは実物を拝むだけでも一苦労という時代もありましたから、 大変身近な存在となった現状が如何に恵まれているかと言うことがしみじみと伝わって来ます。 物は言い様ですがギリシャやホルスフィールドは非常に広大な分布域を持つのに対し、 本種やヘルマンはヨーロッパの限られたエリアにしか棲息していないため、 何処となく高貴な風情を纏っているかのように感じられるかもしれません。 しかしこれは何も表面上の話だけではなく、 広く繁栄し過ぎたためにどのような環境で暮らしているのかが分からなくなるよりも、 ある程度の国や地域が判明すれば現地の気候も自ずと見えてきますから、 飼育する上では随分と見通しが立ちやり易くなる部分も多いのではないでしょうか。 特に野外での冬眠にチャレンジする場合にはこの辺りがとても重要になり、 実際に国内ではヘルマンに続き通年屋外飼育が楽しまれるケースが年々増加しています。 そうなって来ると気になるのは最大サイズ、 部屋の中で眺めているのと外に放り出すのとではカメの体感甲長に大きな差異が生まれ、 遠くから見ると意外と小さく感じられ満足度が薄れてしまうと言う声もチラホラ。 そこでグッとスカートの伸びた巨大マルギが庭を闊歩する姿を想像してみましょう、 あまりの見栄えの良さに惚れ直してしまうこと請け合いです。 今回やって来たのは成長具合が実に好ましい、 まるでお手本のような教科書に載せたくなる飼い込み個体。 この頃巷ではヘルマンやマルギの椎甲板の成長にどうしても難が出てしまう、 そんな話題がしばしば持ち上がるようになりました。 どうやらある一定のラインを超えると肋甲板や縁甲板ばかりがグイグイ伸びてしまい、 何故だか天辺の一列のみが置いてきぼりになりがちで、 全体のバランスが乱れてしまい気になる人にとっては少々不格好なスタイルになってしまうのです。 しかしこの個体については嬉しいことに今の所そのような気配は全く見られず、 むしろボコ付きなども一切無いため何処に出しても恥ずかしくない美貌すら放っていると言えるでしょう。 黒味の強いカラーリングが適度に野蛮なオーラを醸し出している美麗個体、 来季から早速の冬眠も夢ではないグッドサイズです。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♂) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 成長のエネルギーがフレアスカートに集中し始めいよいよ見頃を迎えたヤングアダルト! 焼き目を付けたような甲羅の色艶が香ばしい今シーズンから屋外越冬も可能な飼い込み個体です、 オオフチゾリリクガメ・オスが入荷しました。 本人にそんなつもりは更々ないのだとは思いますが、 飼育対象として非常にポピュラーなチチュウカイリクガメの中でも何故か通好みの、 知る人ぞ知ると言わんばかりのキャラクターが定着している通称マルギナータ。 この世界で多くの人に愛されるための秘訣は大きく三点、 丈夫なことに始まり扱い易い大きさであること、 そして何と言っても敷居を上げないためのリーズナブルな価格帯でしょう。 この条件にいち早く飛び込んだのがロシアとギリシャ、 いずれも野生個体の流通量が豊富であったことから安価なリクガメとして注目され、 元来強健でありかつサイズも手頃ときていますから、 ビギナー向けの定番種として現在もなお重要な役割を果たしています。 それに続いたのがご存知ヘルマン、 こちらは現地で厳しく保護されている都合上ワイルドを入手することができず、 繁殖が軌道に乗るまでの間少し出遅れてしまいましたが、 かつて高価だったことを思えば今では随分と庶民的になりました。 問題はこのマルギ、図鑑には必ずと言って良いほど登場し名前だけであれば認知度もそれなりのはずが、 他種に比べ棲息地が限られていることが災いしペットとして流通する機会にあまり恵まれず、 超高額という訳でもないのに珍しさばかりが付き纏い、 結局はあまり人目に触れることもないままお高く留まってしまっている感が否めません。 最近では前述のヘルマン同様に繁殖された幼体の流通量が次第に増え、 具体的にはここ二、三年で大分浸透してきていますから、 妙なレッテルに縛られることなくその魅力が素直に受け入れられていくことを願うばかりです。 今回やって来たのはようやく性別が確定し、 その証として甲羅のリア部分がぐいぐいと伸び始めた育ち盛りのオス。 ギリシャでもヘルマンでも絶対数の関係からメスの方が珍重される傾向にありますが、 マルギの場合は種が持つアイデンティティの殆どがオスに詰まっていますので、 せっかく育てるのならばオスの方が良いに決まっています。 当店でも過去に20センチオーバーの巨体を扱ったことがありますが、 まるで別の付属品を装着したような仰天のフォルムにただただ息を呑むばかりで、 他のリクガメには絶対に真似することのできない格好良さに包まれていました。 この個体は色合いも上品でボディバランスも秀逸ですからきっと素敵な男児に仕上がると思います、 持ち味のひとつである表情に映るエレガントな趣きを堪能して下さい。 | ||||||||||
|
フチゾリリクガメ (♂) Testudo marginata |





|
|
||||||||
| 人気のオス!見事にフチがソリ始めています、 お客様委託のマルギナータことフチゾリリクガメ・オスの入荷です。 最近ではその飼い易さから人気の高い地中海リクガメの仲間において 一風変わった上品な印象のある本種は、 現地で個体数が減っており保護も進んでいる事から属内では流通量の少ないレア種。その学名や和名が指す様に、 成長に連れて縁甲板後部がスカートを履いた様な形状にどんどん伸びていき、 この特徴はオスで顕著に現れます。現在でも他のリクガメと比べると伸びていますが、まだまだこんなものではありません。 また大型になる事でも知られており大きな個体では30cmを優に超える事もあるそうです。 高温と低温に弱く神経質で飼育が難しい、という話もありますがこの飼い込みサイズではそんな事は全く当てはまらず、 基本通りの飼育法でピンピンしています。甲羅がフレアー状に伸びる格好良いオスをお探しの方、 ここからはフレアーが伸長していくのを思う存分楽しめるいいとこ取りの個体です。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♂) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 止めどなく伸びようとするフレアスカートと面長でガングロな顔立ちが格好良過ぎる大型サイズ! 少し天辺が寄ってしまいましたがそれにしてもがっつり育ったマルギの出物は稀、 オオフチゾリリクガメ・オスが入荷しました。 チチュウカイリクガメ、 現在では新属が認められるなど分類に変更が出ているため若干ややこしくなりましたが、 同グループにおいて最も風変わりで異彩を放っているのがこのマルギナータでしょう。 学名をカタカナ読みしたその愛称は英語に直すとmargined、つまり縁取られたという意味を表しており、 同名の他種では体の縁に描かれた模様を示していることも多いのですが、 本種の場合はそこが伸びてしまうという非常に大胆な特徴で人気を集めています。 リクガメは全般に色柄が異なっていてもシルエットは似ていることが殆どですから、 パンケーキなどと同様に形でインパクトを与えてくれる例外的な存在と言え、 好みの違いはあるものの他では代わりの利かない独自性が評価されています。 その昔まだ流通量の少なかった頃は神経質で飼育し辛いという意見もありましたが、 現在では状態の良い繁殖個体が大変を占めているお陰か、 それほど難しさを感じる場面に出くわすこともほぼ無くなりました。 本来は小型な点が売りのチチュウカイですがその中で最も大きくなるとあって、 ギリシャやヘルマンに飽き足らず新たな刺激を求める矛先としても注目を浴びています。 今回やって来たのはようやく20センチ台に突入した珍しく大きな長期飼い込み個体で、 表情も随分とスマートになりようやくマルギらしいオーラを醸し出す段階を迎えました。 既に相当長くなってきている甲羅の後ろは未だ余力を感じさせ、 これが完成へと近付いていく様を間近で見届けることができるのは本当に幸せだと思います。 耐寒性の高さはご存知の通りで、 しかしながらどちらかと言えば寒冷地とされるエリアでの屋外越冬もチラホラ確認されており、 我々の想像を超えたタフさを持ち合わせているようですから、 そのボリュームも相まってお庭で歩かせるメンバーとしても適任であると言えるでしょう。 他のチチュウカイとは見た目も雰囲気も少々異なるマルギ、 飼い方にもちょっと押さえて頂きたいツボがありますのでお引き渡しと同時にお伝え致します。 最近では手の平サイズの幼体が大分見かけられるようになりましたが、 アダルトサイズの掘り出し物は決して多いとは言えません。 この個体は甲板の癒着があるため、見栄えを細かく気にされない方にはお買い得な超特価にて! | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♂) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| これぞまさしく男前! スマート長身のイケメンマルギです、 とても大きく成長したフチゾリリクガメ・オスが入荷しました。 愛称はマルギナータリクガメ、学名をカナ読みした名前で昔からそう呼ばれ続けています。 チチュウカイリクガメの仲間では少々マイナーというか、 ギリシャやホルスと違いヨーロッパにしか棲息せずしかも分布が限られるため、 ひょっとするとレア種のような扱いさえ受けていた印象があるかもしれません。 顔付きや風貌もどことなく上品な香りが漂っていて、 稀少性と高級感が見事にマッチングしたちょっとセレブなリクガメと呼んでも差し支えないでしょう。 オオフチゾリと言われるだけあって大型化するらしいのですが、 実際に国内で見かける個体はなんとかオスと判別できるような途中サイズのものばかり。 しかし今回、写真から飛び出てきたようなちょっと凄い一匹が姿を現しました。 チチュウカイだと思ってなめていると完全にやられます。 頭の大きさや四肢の逞しさ、 そして何よりボリューミー極まりない甲羅の造形からは今までのマルギ像を完全にぶち壊す破壊力をびんびん感じます。 そして見た目通りのパワフルさ、 地面に置いた瞬間が彼のグリーンシグナルらしくあっという間に走り去る躍動感は半端ではありません。 最後に付け加えておきたいのは、 この素晴らしいフォルムを作り出しているのは何よりもボコつきの少なさであり、 こればかりは前飼育者がかけた愛情の賜物であり敬意を表す次第です。 ここ最近で価格が落ち着きましたが、アダルトサイズのありがたみと迫力は何も変わりありません。 数少ない貴重な出物です。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♀) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 毎度見かける度に大騒ぎしてしまう百匹に一匹、いやそれ以上に珍しいかもしれない貴重なメス! とにかく繁殖なんて目指そうものなら確実に悩みの種になるため真っ先に手に入れておきたい、 オオフチゾリリクガメ・メスが入荷しました。 ヘルマン、ギリシャ、ホルスフィールド、 この流れるようなフレーズを耳にした時に訪れる爽快な気分の裏で、 何処か釈然としないもやもやとした気分に苛まれるこの感覚は一体何なのでしょうか。 ビギナー向けの御三家であることには何の違和感もありませんし、 昔から名実共に高い人気を誇って来たことも認められるべきではあるのですが、 ここにマルギナータの名前を挙げてもらえないことが何とも悔しくて堪りません。 最近では分類に若干の変更もあり厳密には同じ括りではないのかもしれませんが、 ここに掲げられた四種は立派なチチュウカイリクガメの仲間だと思いますし、 有効な選択肢として同列に並べられていてもおかしくは無いはずです。 それが不思議とマルギだけに設けられた謎のハードルによって、 あたかも育てるのが難しいと言う先入観さえ植え付けられてしまっているようにも感じられ、 或いはひとりだけ最大甲長がグンと大きくなってしまうことも影響しているのか、 いずれにしても自然と避けられている感が否めないのです。 しかしながら最近ではその高い耐寒性に注目が集まっていて、 通年屋外飼育の場合はその立派な体格が却ってメリットになる可能性が高く、 例えば大きくなればなるほど単純に蓄えられる体力が増大しますし、 庭先を歩かせた時の視覚的なインパクトもより良くなる訳ですから、 ここにマルギナータ復権の鍵があると言っても過言ではありません。 今回やって来たのは見かけられる機会が絶望的に少ないせいで、 本種の繁殖がもはや諦められているとさえ感じる待望のメス確定個体。 フチゾリの程度だけで考えればオスの方が立派に成長するため、 ピンで観察するのには適していると言われていますが、 やはり相方が欲しくなるのも人情で全国に指名手配が出されているほど、 とにかく何処へ行ってもまず見かけられないと言うのが現状です。 甲羅のフォルムはご覧の通りですが健康状態に何ら問題は無く、 見かけだけで判断されても悔しいので暫し店内でたらふく餌を与え続け、 とびっきりの新しい成長線を伸ばしてみました。 まだまだ成長の見込めるサイズですからふっくらと仕上げ直してやって下さい。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (♀) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| 全国津々浦々何処を探し回ってもまず巡り合えない絶望的に数が少なく入手困難なメスマルギ! 有り余るパワーで周囲に当たり散らすゴリゴリのオスをお持ちの方はぜひこの機会に、 オオフチゾリリクガメ・メスが入荷しました。 ヘルマン、ギリシャ、ホルスフィールド、俗にチチュウカイリクガメ三兄弟と呼ばれる、 と言うよりはこの場でそう勝手に呼んでいる妙に語呂の良い彼らは、 巷では丈夫で飼い易い初心者向けのリクガメの代表格として認知された、 世界中にその名を知らしめる超有名な入門種。実際に飼育が容易か否かはさておいて、 現実的に流通量も豊富なことから多くの人々の目に触れ易く、 リクガメと言う生き物をペットとして広めた功労者であることは間違いありません。 ここにご紹介するマルギナータは前述の三種とおおよそ同一の括りに含まれるものの、 現地では早くから保護の対象となるなど商流に乗ることがあまり無かったためか、 今でこそある程度見かけられるようになったものの、 以前はどちらかと言えばマニア向けの稀少種的な扱いを受けることの方が多かったようです。 それでも相変わらず手に入らないのが本種のメス、 如何せん性別が判断し難いことも手伝ってかメスと確定した出物があまりにも少なく、 ブリーダーを志そうにも明るい未来が描けないため計画段階で頓挫してしまうことも多々。 愛好家に言わせればヨーロッパ原産であることが功を奏し、 同じチチュウカイの中でもかなり耐寒性に優れている点や、 それなりの体格が野外でも見栄え良く楽しめる点など、 マルギでしか味わえない魅力が盛り沢山なのですが、 結局のところ通好みのマイナーなポジションから脱却し切れず現在に至り、 従来からのファンは更なる大衆化を待ち望んではいるものの、 他種の台頭もありなかなか実力を発揮し切れずにいるのが何とも歯痒い状況です。 今回やって来たのはもうしばらく鍛え上げれば繁殖にチャレンジできそうな、 いよいよ20センチをオーバーしたサブアダルトの稀少なメス。 悲しいことに何故だか甲羅がややフラットな仕上がりとなりつつありますが、 とにかくオスをお持ちの方は相方を手配しなければ話が前に進みませんので、 数年に一度とさえ言われるこのチャンスを是非ものにして頂きたいと思います。 Mazuriリクガメフードから葉野菜まで選り好みしない至って健康な飼い込み個体です。 | ||||||||||
|
オオフチゾリリクガメ (特大サイズ・♀) Testudo m. marginata |





|
|
||||||||
| ただでさえメスが少ない上に20センチオーバーの巨体が嬉し過ぎるガツ盛りでかマルギ! 種親不足から繁殖例の僅かな本種も国内CB化の軌道に乗せてしまいましょう、 オオフチゾリリクガメ・メスが入荷しました。 慣れない内はどうにも舌を噛みそうになるこのフチゾリリクガメ、 そこはさらっと流暢にマルギナータと呼んで差し上げたい所なのですが、 最近ではどちらの名称も随分浸透して来たようで首を傾げられることも殆ど無くなりました。 チチュウカイリクガメの最大種という実にクールなプロフィールを持ちながら、 ここ日本での人気は決して鰻上りと言えるような雰囲気ではなく、 好きな人は好きと言ったポジションを長きに渡り守り続けています。 無理に例える必要はないのですが、小さいのかと思いきや意外と大きくなるという点では、 アメリカハコガメにおけるガルフコーストのような存在と言えるのかもしれません。 地中海系イコール小型種、 そんな前提があるお陰で評判はどちらかと言えば今ひとつになってしまいがちですが、 そのように安直な見解ではマルギの魅力を引き出してやることは到底できません。 他の種類では想像も付かない恵まれた体格は格好良いことこの上なく、 一歩一歩の足踏みに確かな力強さを味わい、何気なく太陽光を浴びる姿にさえ勇ましさを覚えます。 またそういったスタイル的な長所も然ることながら、 屋外飼育に絶対条件とされる十分な体力は身体が大きければ大きいほど有利になりますし、 やはりただただ大きいというだけで放牧した時の迫力も段違いですから、 通年野外飼育の友としてはぴったりの適役だと思います。 今回やって来たのは全国のマニアが血眼になって求め彷徨っていると噂される、 探してもまず見つからないことになっている本当に稀少なメス個体。 しかしこれが何となくメスではなかろうかと思われる言わば中途半端なサイズでの放出であれば辛うじて現実味を帯びていたものの、 あろうことかもう来シーズンにはぶりぶり産卵までしてしまいそうな超即戦力なのですから二度驚き。 同じくメスが少ないとされるヘルマンは絶対的なタマ数の多さにまだ助けられていますが、 マルギナータの場合は根本的に出回る量が少ないため非常にたちが悪いのです。 成長具合の関係でやや甲が扁平なのが玉に瑕ですが、 このフォルムに多い妙な柔らかさは微塵も無く健康面での影響は見受けられません。 もちろん直ぐにブリーディングさせてしまって差し支えありませんが、 薄っすらと新しい成長線の伸びが伺えるため化け物目指してこのまま育て上げるのも面白いかも。 これこそまさにいくら頼まれても探し出しようのない一点ものと呼ぶに相応しい逸品、 甲羅の後ろが伸び過ぎて困っている独身マルギを持て余している方へ捧ぐ未来への新たな一歩です。 | ||||||||||
|
ペロポネソスフチゾリリクガメ (♂) Testudo m. weissingeri |





|
|
||||||||
| 小型亜種らしくこのサイズでも小さくまとまっていて雰囲気あり! 一度聞いたら忘れられない、もしくはうまく聞き取れないかもしれない変わった名前です、 ペロポネソスフチゾリリクガメ・オスが入荷しました。 いきなり舌を噛んでしまったり巻き舌になってしまいそうなこのネーミングはギリシャの南西に浮ぶペロポネソス半島から。 半島という言葉に対しては突き出るというような表現が適切でしょうが、 この島に限っては殆どが本土から分断されているため、 陸続きになっている場所はほんの僅かで地図を遠目から見ると本当に浮んでいるように見えてしまいます。 普段流通している基亜種とは陸続きの分布であるらしいのですが、 大陸と小島に別れて棲息することで形態に違いが出るというのはよくある話。 あちらがわざわざオオフチゾリと呼ばれることからも分かるように、 本亜種は同じマルギナータでも大型化するようなことはなく、 具体的な数字としては文献を参照したところによると10cmほども差が出るのだそう。 亜種として分けられてまだ歴史が浅く個体群としての流通も極めて少なかったため、 国内での長期飼育例も決して多くはありませんが飼育種を選ぶ際の大きな判断材料になることは間違いないでしょう。 今回やってきたのはペロポネソスとして輸入されたベビーが国内で飼い込まれ成長した個体。 あえて手に持った写真を多く使い実寸を分かりやすくしていますが、 カメ単体で撮影すると既になかなかの迫力を備えていることが分かります。 ご存知の通り亜種として明解に区別する点に欠けるという説もありながら、 よく見るベビーではなくある程度まで育った個体を観察してみればその雰囲気は伝わるのではないかと思います。 何がそうさせるのか他のチチュウカイリクガメに比べて抜群の上品さを誇るマルギ、 大きくなることを望む人もいれば当然大きくなり過ぎては困るという人もいますので、 サイズという課題をクリアして種の魅力を味わえるというのは嬉しい限りです。 相変わらず性別の判断がし辛いリクガメですが、 今回は少しプッシュしたらすぐにヘミペニスを出してくれたので折り紙付きということで。 ミニチュア版マルギナータという感じで非常に興味深い珍種です。 オスの大切なアイデンティティであるリア周りの伸長もまさにここからがお楽しみの時間です。 | ||||||||||
Copyright (C) Since 2009 Herptile Lovers. All Rights Reserved.